“歌”を通して見ず知らずの人々にエンパシーを働かす揺らぎの音楽
バンドを続けることは至極面倒臭い。学生なら、ほぼ無限と言ってもいいほどの時間があるし、無鉄砲な熱意を音楽だけに注ぐことができる。社会に出たのならば、あらゆる面で時間に制約が生まれ、体力も仕事に奪われる。それに金だってかかるし、所帯を持ったなら不可能に近い。更に、良くも悪くも人間関係の面倒臭さが付き纏うし、きょうび一人で音楽を作る方が圧倒的にリーズナブルだ。もし、運良く人気を得て、音楽だけで生計を立てることができるのなら、そいつらは世界で最も幸せな者だと言えるだろう。ただ、経済的な成功が本当の成功ではない。
今回、私が取材をした揺らぎというバンドは、学生時代から活動を続け、今年で結成10周年を迎える。J-Shoogazeという括りの中では、彼らは若手の代表格で、国内外から根強い支持を得ている特別な存在だ。ギターのKantaro Kometani/Kntr氏とは共通の友人がおり、以前からオンラインで親交があったため、今回インタヴューをするに至った。私がジャーナリストと言える仕事を始めて、空間を共有したインタヴューは今回が初だったのだが、彼らがその相手だったのは間違いなく幸運だったと言える。
個人的な話だが、ここ5、6年、ロック或いはバンドというものから心が離れていた。そういう時流でもあったが、年齢的な思考の過渡期であったため、そういったナラティヴに対してシニカルな気分もあったのだろう。だが、今このタイミングで揺らぎのライヴを観れたこと、そして彼らに出会えたことは、大きな救いになった。完全に同世代で、非京阪神出身の関西人で、ティーンの頃に同じようなインディー・ロックを聴いて過ごしたという、共通言語を持った人々との会話はただ単純に楽しかった。また、殆ど同じ年月を社会に奉仕してきた生活者としての側面があるが、共通する悲喜交々があれば、普通じゃ経験し得ない特別な傷もある。ただ、彼らはそれを音楽で表現することができるし、家族よりも家族だと言えるバンドメイトと慈しみ合うことができる。羨ましいと同時に、誇らしくも感じた。
彼らはシューゲイザーを軸に、ポストロックという枠組みの中のトレンドと同期しながら、“歌”を通して見ず知らずの人々にエンパシーを働かせることができる。だから彼らは特別で、世界中からの支持が止まないのだと思う。もし、彼らの音楽に触れたことがないなら、すぐに聴いてほしい。もし、彼らのライヴを見に行ったことがないなら、後ほど掲載するライヴ情報から行けるところに行ってほしい。もし、彼らのことが既に好きだったのなら、これからのインタヴューを読んでもっと好きになってほしい。
(インタヴュー・文/hiwatt)
Interview with Miraco(Vo、G、Piano)、Kantaro Kometani/Kntr(G、Synth)、Uji(B、Cho)、Yusei(Dr、Samplar)
【揺らぎが開拓するライヴ・サウンド】──ライヴが終わった昨日(2025年3月9日 大阪《ANIMA》)の今日でお集まりいただきありがとうございます。オープンな質問というより、僕が感じたライヴや作品への感想をベースに、より深いところを聞けたらと思いますので、何卒よろしくお願いします。とりあえず、熱も冷めないうちに昨日のライヴの感想からいきたいんですが、まず音がめっちゃ良かったなというところで。
All:ありがとうございます。
──Xでもポストしたんですけど、揺らぎって轟音のイメージがあったので、帰る頃には耳がキンキンするのを覚悟してたんです。けど、音はデカくてしっかりと圧もあって分厚いのに、全く耳疲れせずにずっと心地良かったんです。それに、それぞれの楽器の分離が良いんですが、なおかつアンサンブルは抜群で、それはシューゲイザーとされる音楽をやっているバンドとしては特異というか、差別化を図れるポイントだと思ったのが、サウンド面での一番大きな印象です。そういった音作りの面で意識されたところとかありますか?
Kentaro Kometani/Kntr(以下、K):これはUjiが答えるべきやな(笑)。
Miraco(以下、M):やな(笑)。
Uji(以下、U):はっきり言って、それを言ってもらえる日が来るようにやってた節があって。その投稿を見て遂にそこを認めてくれる人が現れたと思って! これはお世辞とかではなく本音で。
──受け取れていて良かったです……!
U:サポート・メンバーから揺らぎに入って3作目になるんですけど、揺らぎは“シューゲイザー・バンド”ってずっと言われてる中で、どう差別化するかを個人的に考えていて。元々そんなにシューゲイザー界隈のものは詳しくなくって、音数の少ない音楽を好んでいたんですけど、楽器ごとの帯域を棲み分けたら、もっと音として出せる圧も増えるし。ただマスター・ヴォリュームを上げて圧を上げるんじゃなく、音圧を出すことを目指して、3年くらいかけてここまで来た意識はありますね。なので、感想を見てて一番湧いてました。これやでー!やっとやー! 気づいてもらえる日が来るとは! って感じで。
All:(笑)
──後から入った、違う哲学を持ったメンバーだからこその客観性が、シナジーを生んだわけですね。その音数の少ない音楽のルーツはどこから来てるんですか?
U:ペトロールズからの影響が大きいです。そういう、いかに削り落としてミニマルにやるかみたいな音楽が好きで、そんなのばっかり聴いてたんですよ。(揺らぎの)楽器の数が少ないのもあるけど、いかにそれぞれの音をぶつからないように出すかっていうところは個人的な音楽嗜好から来てて。ジャンルも違う、メンバーも、編成も違う切り口で、いかに落とし込めるかっていうのは、個人的な音楽の趣味から来てる節はあります。
──昨日のライヴは、PAさんにもサウンドの面でなにか注文されたんですか?
M:そもそも、昨日のライヴのPAをやってくれたのが、最新作の録音とミックスをやってくれた方で、理解度が圧倒的に深いです。
Miraco
──なるほど! その方は今回のツアーの全てのライヴに帯同されたんですか?
M:いえ、東京公演は元々ライヴだけをずっとやってくださってたPAさんがやってくれて、名古屋と大阪はその方と一緒に回りました。その方も忙しいので、お願いするかは行く地方とかによって決めたりしています。それに、昨日は2日目っていうこともあって、かなり仕上がってたんじゃないかなと思います。
──昨日の大阪のライブヴは、ホームタウンでのツアー・ファイナルということでしたが、バンド側の感想としてはいかがでしたか?
M:あんなにパンパンの《ANIMA》は初めてでやっぱり嬉しかったですね。
Yusei(以下Y):大阪でのライヴの中だと、かなり反応が良かった気がするよね。
M:そうやね、今までのライヴとお客さんの反応が違った。今回は帯域の棲み分けにこだわった中で、私はヴォーカリストとして、メンバーが帯域的なところで道を道を開けてくれているので、ひたすらに走らないといけないという気持ちで(笑)。
Y:今回は歌をフィーチュアしたライヴを意識したので、お客さんの反応が良かったというのはそこもあるかもしれないですね。
──確かに、揺らぎのサウンドの性質上、Miracoさんの繊細な声質はライヴだと負けちゃうんじゃないかと思ってたんですけど、全くそんなことはなく、事実として歌がしっかりと伝わっていました。お客さんが本当に良いですよね。熱心にバンドをサポートしているファンの方もいれば、現場でライヴを嗜むことが生き甲斐なんだろうなって方もいたり、フラットな音楽ファンもいたり、海外の方も多く、ジェンダーも偏りがなく、その場を作るのはなかなかできることではないと思います。
M:昨日、私がめっちゃ感じたのは、お客さんの表情がすごい良かったですね。顔つきというか、本当に皆さん柔らかい表情をしてくださっていて。
K:昨日、「Jason」というアコースティックな曲をMiracoが一人でやったんです。Miracoが下手で、僕は上手で見てたんですけど、Miracoにスポットライトが当たって、その真ん前で女性のお客さんが見つめていて、その方の表情がすごい素敵で。これまで揺らぎがイメージされていた、轟音を聴かせてるからとかだけじゃなくて、ソングライティングに力を入れた曲を揺らぎのお客さんに聴かせて、そういう反応してくれるっていうのがすごい嬉しかったです。もし自分が客側で、好きなフォーク・シンガーのライヴを見てると、多分そういう感じだったんだろうなと思うんです。それを最終日に見れて感慨深かったです。ええこと言うたよな?
U:ここまで(涙が)来てたのになぁ〜(笑)。そういう視線で見てられるのに慣れてないというか、自分はそこまでの存在じゃないっていう意識が昔からあったんですけど、ちゃんとお客さんとバンドの間に物語を作れてるんだなっていうのを、お客さんに改めて教えてもらったというか。
──10周年ということもありますが、その間に築き上げてきたものがあったんですね。
M:本当にエネルギーをもらいました。
【“In Your Languages”というキーワードから考える揺らぎのアイデンティティ】
──『In Your Languages』と近いタイミングにリリースされた、venturingの『Ghostholding』と相対化することで、私の中で揺らぎのアイデンティティが浮かび上がってきたんです。共にシューゲイザーや、スロウコア、スラッカーロックなどの要素があるんですが、venturingには根源的なところにエモの要素があって、そこに“アメリカっぽさ”を感じたんです。方や、揺らぎにも確実に“日本っぽさ”があるんですが、Miracoさんの歌がそれを担保する大きな要因だと思うんです。
M:おじいちゃんが詩吟の先生をやっていて、私自身も子供の頃にちょっとだけ習っていたんですけど、そういう環境だったから演歌なんかも当たり前にあって。それから、石川ひとみさんとか、今井美樹さん、(中森)明菜さんなんかの80年代の女性歌手が好きで聴いてましたね。父がブルースやハードロックが好きで、ギターもやってるんですけど、その影響で近藤房之助さんは特に大好きですね。あとは……Char! それから永井“ホトケ”隆さん!「鉛色の空からブルーズが落ちてきた」って曲がめっちゃかっこいいです!
──想像以上に濃い日本音楽の原体験ですね……!
M:それから、音楽としては多分そんなに好きじゃないんですけど、子供の頃からサーカスみたいなエンターテイメントとしてキッスが好きで、ライヴには3回も行きました。あと、『ローゼンメイデン』ってアニメがキッカケで、ALI PROJECTが好きになったんですけど、個人的に彼らはジャパンプログレの系譜にいると思ってて。『In Your Languages』はプログレをかなり勉強した作品なんですけど、忘れてたけど実はアリプロからも影響があるなって。
──なるほど。グラマラスでゴシックな、“歌舞いた“ものが趣向の根源にあるんですね。
M:そうですね! JUDY AND MARYも大好きですし、川瀬智子さんのプロジェクトでもTommy heavenly6が好きでした。ゴス系な自分になりたいとは思ってなかったんですけど、みんなと違う自分になりたいっていう欲求があって、買ってた雑誌も『Zipper』だったりします。だから昨日のライヴでも顔にキラキラを付けてもらったのかも(笑)。あ、それからAJICOの存在は超デカいです!
──そこでヴィジュアル系には行かず、尚且つアイコン的な存在が女性だというのは、非常にMiracoさんの人物像として納得がいくところですね。
M:作曲家では菅野よう子さんにめちゃくちゃ影響を受けました。アニメの『マクロスF』で最初に知って、小中学生の頃はかなり聴いてましたね。初めて買ったCDはYUIの「My Generation」でした! アンジェラ・アキさんはライヴにも行くぐらい好きでした。「黄昏」って曲が好きで、意外と歌詞がセンセーショナルで、日本語の譜割りが凄いんですよね。なにより、歌手になりたいと思うきっかけは手嶌葵さんでしたねー。それこそ、菅野よう子さんとコラボした「Because」って曲が凄く好きなんです。日本の音楽からの影響って、こうやって改めて考えたことなかったです。色々思い出せて嬉しいです。
──Kntrさんの作るメロディって、所謂“泣きのメロディ”みたいな、多くの日本人が本能的に惹かれる叙情的なコード進行が得意な印象で、それも“日本っぽさ”の一因だと思うんですが、そのメロディ・センスはどこから来ているのでしょうか?
K:うん、そうですね……メロディとしてメッセージ性が強いと思うんです、特に叙情的なものって。
──そうですね。私は揺らぎの最新作が映画っぽい、もしくは映画のサントラのようだと感じたんです。映画における音楽って、そのシーンや人物の心象を説明するために機能する側面がありますが、それに通じるところがあります。
K:そうですそうです、まさに。もちろん、今まで聴いてきた音楽が、自分のメロディ・センスにも影響していると思うんですけど、それ以外で考えると映画だったり、映像作品も大きいですね。日々生きている中で、あっ、今この場面ではあの曲が流れてるな、みたいな感覚が昔からあって。映画における音楽監修みたいなセンスは、今回のアルバムにはめっちゃ活きてるのかもしれないです。
Kantaro Kometani/Kntr
──《Earfeeder》というメディアが、“J-Shoegaze”という括りで日本のシューゲイズを紹介したのが音楽クラスターで話題になってて、そこで揺らぎのファーストEP『nightlife』が紹介されていたのですが、認知されてますか?
《Earfeeder》のインスタグラムの該当投稿https://www.instagram.com/p/C-iSOL_uDh4/?igsh=MWE4NHZsMm8yYXRuNw==
Y:あー見ました!
──Spotifyのランキングを見ても未だに人気で、最近、CDが再販されましたし、少しではありますが日本語詞の入った唯一の作品ですよね。
M:そうですね! 一番聴かれているのは「night is young」という曲なんですけど、日本のシューゲイザーがアニメと親和性があるのも理由の一つだと思います。
──それこそ、『nightlife』のアートワークがイラストなのもキャッチーですよね。英語以外で歌われる音楽が受け入れられやすくなって久しいですし、アニメ文化のおかげで日本語はアドバンテージがあると思います。最近で言うと、Lampや青葉市子、千葉雄貴などが広く評価を得られた良い例ですよね。まさに『In Your Languages』という今作のタイトルから考えさせられたんですが、揺らぎはこれまでほぼ全て英語詞で音楽を作ってきましたが、日本語で歌うことを考えたことはありますか?
M:そうですね。おっしゃったように、初期作品では日本語詞もあったんですけど、今になって挑戦したい気持ちはすごくありますね。やっぱり日本語話者なので、日本語で遊ぼうじゃないですけど(笑)。日本語で作るとなると、意味を持っていないわけじゃないんですけど、散文詩というか、これまでも言葉を散りばめる傾向にあると思います。
──逆になぜ英語詞で作り続けるのでしょうか?
K:まず、英語詞の音楽の方が量として圧倒的に聴いていたっていうのはあって、音楽に乗せるならその方が自分にとって自然というか。日本語は第一言語だし、理解がしやすすぎて、言葉の意味をダイレクトに伝えるってことは、ある意味では押し付けになってしまうと思うんですよね。 あとは書くのも、逆にリスナーとして受け取るのも、難易度として英語詞より日本語詞の方が高い気がしていて、それはちょっとまだクリアできていないです。主にその2つの理由ですね。
──これはMiracoさんの英語の発音が悪いと言いたいわけではないんですが、言語だけでなく、日本人の所謂“カタカナ英語”っていうものも、ある種の言語として、海外の方から個性として受け入れられ始めた印象があるのですが、いかがですか?
M:そう! 昨日まさに台湾のお客さんから頂いたファンレターにそういう風なことが書かれていて! あんまり考えたことはなかったけど、例えばエレファント・ジムとかが日本語で歌ってくれてたりしますけど、それを聴いた時に受ける印象と同じなのかもしれないですね。そう思ったら、今回の『In Your Languages』っていうタイトルって、私が英語で歌ってることにも当てはまるし、なんかいいタイトルやなって改めて思いますね。だから勝手に自信がついたというか、その国の人にならないと分からないところではありますけど、響きの違いも楽しんでもらえてるなら、それも嬉しいですね。
──そうした時に『In Your Languages』というタイトルにはどのような意図があるのでしょうか?
K:今回の作品は、ある種のメンバーのエピソードトークみたいな歌詞も多いんです。ただそれは、日本人の私だから思うっていうことでもなく、世界のどこかの誰かも感じている、普遍的なことを言っているんじゃないかとも思うんです。コミュニケーションにおいて言葉は欠かせないですし、かけがえのないものです。それに、自分以外の誰かとで成り立っている歌詞も多いと思うんですね。これまでの自分たちなら、“In My Language”にしかねなかったと思うんですけど、自分たち以外のための曲、アルバムでもあるので、“In Your Languages”にしました。
M:私は人と喋るのは割と得意な方だと思うんですけど、でも喋ることって自分を良くも悪くも取り繕ってたり、自分を守ってたりする部分もあって、自分の頭とか心で感じた気持ちで言語化しても、違うものに変換されてたり、半分ぐらいが壊れてる気がするんですね。両親がお店をやっていたこともあって、小さい頃にあんまり家族と一緒にいる時間がなかったんで、家で1人でハミングをしていたんです。だから、私の中の第一言語って、日本語でもなくハミングなんです。ライブでも、伝わってるかどうかは別にして、自分の感情とか気持ちの出力は、メロディなら100%出し切れたって気がするんですね。言語を喋って伝えるという場合もあると思うし、歌って伝えることもできる。言葉を発せられない人もいますが、文章だったり、体や目で伝えることもできると思うんで、みんなが異なる方法で自分の思いを出力できればいいなって思います。
【揺らぎのビートに宿るシガー・ロスからの影響】──揺らぎのリズム隊を聴いて思い出すのがシガー・ロスなんですが……。
U:僕は全然通ってきてなくて、サポートで入る時に参考となる音楽の膨大なプレイリストを渡されて、その中にも入ってたんですけど、ちょっとトラウマ過ぎて……。
M:100曲くらい入ってたんちゃうかな?(笑)
──そうなんですね!(笑) Ujiさんのルーツにドリーム・シアターがあると聞いて、シガー・ロスのルーツに北欧メタルがあるんで、そこで通じたのかもしれないです。
U:あーなるほど! ただ、僕以外の3人は大好きですね。
──そうですよね。Kntrさんのギターのリバーブだったり、Miracoさんのファルセット、あとYuseiさんのドラムの手数、ヴァリエーションみたいなところには、間違いなく感じます。
Y:僕はシガー・ロスのドラムに影響を受けたというより、“シガー・ロス”をドラムで体現したいと思うほどに、バンドから影響を受けています。一番好きなアルバムは『Kveikur』です。
──私もその作品は2、3番目に好きなんですが、かなり過小評価ですよね……。あの作品は多彩なシンバルが象徴的で、ドラムが主人公だと言えます。シガー・ロスのどういうところを魅力に感じますか?
Y:言葉では表現できぬような浮遊感を、音で表現できてるなと思ってて、シガー・ロスを聞くとやっぱり広大な景色とか自然を思い描くんです。20代前半の頃の僕はそれにすごく憧れて、それをどうドラムで表現できるかっていうのを探ってましたね。ただ、ドラマー(オーリー・ディラソン)からの影響は受けてないというか、シガー・ロスを聴き始めた頃は、全然ドラムを意識したことがなかったんです。だから、あんまりそこは関係ないかなと思ってます。
──影響を受けた具体的なドラマーの方はいますか?
Y:柏倉隆史さん(toe)とか、河村“カースケ”智康さんですかね。toeが好きで、toeを知った時期に日本のマスロックというか変拍子バンドをよく聴いていましたね。the cabsが大好きです。
──なるほど。最新作の「Our」で聴ける変拍子には、その辺りからの影響があったのですか?
Y:あー、そこもあるかもしれないですけど、制作時にみんなでプログレを聴いてたんで、自然と変拍子を入れてみようとなりましたね。やるっしょって感じで(笑)。
──揺らぎのディスコグラフィを全て聴き返した時に、2作前ぐらいからドラマーが変わったのかと確認したほど、Yuseiさんのドラムに変化を感じて、今作で更に成熟したように聴こえたのですが、何か新たな試みがあったのでしょうか?
Y:スティックは今まで1番太くて重い物を使ってたんです。重たい音を出したい、デカい音を出したいっていう理由で使ってたんですけど、それ以外は全然使ったことなくて。ただ、今回のレコーディングで、ジャズ・ドラマーが使うような細いスティックとか、中間ぐらいのスティックを使い分けてみたんですけど、やっぱりプレイスタイルに幅ができたと思います。今まで使ってた物だと、細かいフレーズが叩けない、 叩けてても繊細な音が出せない、ダイナミックスがないって感じていて。今回のアルバムでいうと、「Whenever, Whatever」はスネアのゴーストノートを意識的に加えた曲で、細いスティックじゃないと、さりげなく入れることはできなかったかなと思います。
Yusei
──Ujiさんの帯域の棲み分けの話であったり、Miracoさんのボーカルのために道を空けてもらったという話がありましたが、ドラムでその辺りに工夫されたところはありましたか?
Y:ドラムのフレーズを工夫して、ボーカルに道を空けたって感じがありますね。音域的にはシンバルの音とか、ドラムセットの音とか、曲ごとに雰囲気の合うやつを選んでったって感じです。「For Your Eyes Only」は、今回のアルバムの中だと一番シューゲイザー的な曲で、今までやったらボーカルを気にせずにどちゃくそに叩いてたんですけど、そうではないなって思って。今回はボーカルを目立たせるために、迫力もありながら、安定したドラムを叩こうよ思ってましたね。
──昨日のライブでは、前作から3曲を演奏されてましたが、今回のアルバムを経て叩き方の意識って変わりましたか?
Y:あー変わったかもしれないですね。「Here I Stand」は、前作のレコーディング時から中間のスティックを使っていて、それによってシンバルの雑さというのはちょっと減ったかと思います。あと「Falling」は、ハイハットで刻む部分があるんですけど、そこを繊細に演奏するのにスティック変えたことはデカかったとは思いますね。
【揺らぎにタイトネスをもたらすUjiのベース】──Ujiさんの黒子的なベースと、「This Room Is Comfortable」で聴けるような魅せるベース、どちらもバンドの幹になっていました。そのリファレンスであったり、影響を受けたベーシストを教えて下さい。
U:元々はサポートメンバーやったんで、黒子に徹してたとこはあったんです。最初の方は、ベースラインを持っていくときは割とフレーズが多めのものを持っていって、バンドに削っていってもらうパターンの作り方が多かったんですけど、今回は正式なメンバーとして色々と全く違う畑のレファレンスを持ってきて、何か合う形がないかなと模索しました。今、現代のベーシストで一番聴いているのは、ジョー・ダートとサム・ウィルクスが2大巨頭ですね。サム・ウィルクスの方は、この前、京都《Metro》でサム・ゲンデルとやったライブにも行って、ひっくり返るぐらい良かったですけど。
──僕も同じ場所に居ました! 良かったですよねー! ちなみに彼らの最新作のライナーを書いてます(笑)。
U:マジですか! その前にはKNOWERでのライブも見に行きました。僕は音楽を広くディグれる人じゃなくって、一回その人たちを知ると、アホみたいに同じ曲とアルバムを聴き続けて、そのアーティストを昇華するのにむちゃくちゃ時間かけることが多いんですよ。あとは、カーク・フランクリンっていうゴスペル・シンガーのバックでベースを弾いてる、マット・ラムジーですね。この3人は、ここ数年で自分のベースの軸として聴いてて、基本的にみんなめちゃくちゃタイトなんですよね。ああいうのを、揺らぎのような全然ジャンルが違うところに放り込むわけですけど、でも今回はより歌を前に出したので、その要素は落とさずに活かすことができたとは思ってますね。
──確かに、サム・ウィルクスのタイトだけど丸みがあるようなプレイはかなり似たものを感じます。
U:いやー、ありがたいです!
M:よかったね〜。
Uji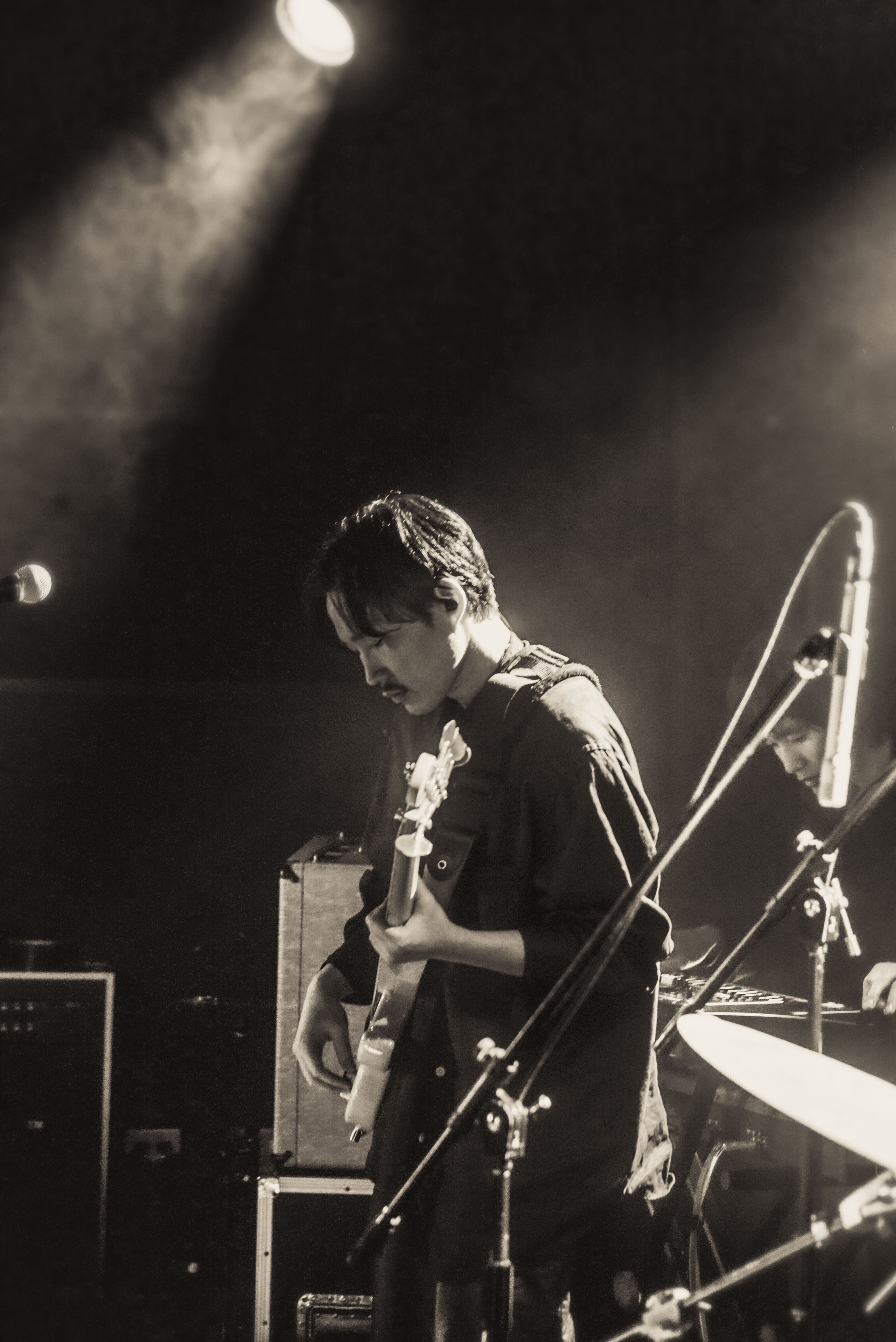
K:あとあれ忘れてるやん? スクエアプッシャー。
──意外ですね!(笑)
U:Kntrとは、ひたすらその辺の音楽を見たり聴いたりする時間が多いですね。制作期間も一生、スクエアプッシャーを聴いてました。
──確かに、Ujiさんのベース・ソロ曲「Sá Meditation」なんかは、「Iambic 9 Poetry」に似てますよね。あの曲のディチューンがかかるところは、Whammyかなにかを使ったんですか?
U:そうです。レコーディング時にKntrがPitchforkというオクターバーを買ったんですけど、自分が弾きながら、彼にランダムなタイミングで踏んで貰って録りました。そしてまさに、「Iambic 9 Poetry」のエフェクト感を参考にしていて、何回もライブ動画を見ましたね。あとは、開放弦をルートにしてフレーズ展開させるのもスクエアプッシャーから着想を得てる節がありますね。ちなみに、あの曲は僕が作ったんですけど、「Smile Meditation」っていうヴルフペックの好きな曲と、僕が応援しているウルバーハンプトンというフットボールクラブのゴールキーパーで、ポルトガル代表のジョゼ・サーという、好きなものを掛け合わせたタイトルにしました。
──なるほどー! 2、3年前のサーはハンパなかったですよね! 間違いなく、あの時期のサーは世界一止めるキーパーでした。あの安定感はまさにメディテイティヴだと言えます。
【変化(進化)した揺らぎのサウンド】──揺らぎにとって鍵盤を導入したのは画期的というか、革命レベルの変化だったんじゃないですか?
K:Ujiが先導となって音の棲み分けをどうするか考えた上で、新たなチャレンジとしてシンセを入れてライヴをしてみようと。これまではシンセを入れたセットで、機材をプロセットでやったことは、レコーディングではあっても、ライヴではなかったですね。
──シンセと言っても、ローズピアノやオルガンだったり、あとはメロトロンとか、オーセンティックなビンテージ系の物が多くて、それも揺らぎっぽいなと思ったんですが、そのチョイスに理由はありますか?
K:私がデモにローズやメロトロンみたいな音を入れていたんですけど、レコーディングの時にローズの実機が借りれそうってなったんで、ローズは実機を使いました。その他のメロトロンやオルガンとかの音は、もう鍵盤の人に任せて、レコーディング時や、その前の話し合いで一緒に作っていきました。
──レコーディングとライヴも同じ鍵盤奏者の方ですか?
M:そうですね。全部、青海さんにお願いしました。鍵盤のアレンジとかもお願いしてて、フィーチャリングみたいな感じです。
──どういう出会いだったんですか?
M:私の友人が働いてる家具屋さんで出会った人が、DUCK HOUSEというバンドでヴォーカル/ラッパーをやってて、そのバンドのキーボードが青海さんなんです。たまたまDUCK HOUSEのライヴを見に行って、めっちゃかっこいいってなって、かんちゃん(Kntr)にライヴ動画を見せたら、この人に弾いてもらおうとなって。
K:ちょうど鍵盤奏者を探してて、その後にライヴを見に来てくれて、面接というか顔合わせをして、譲れるところと譲れないところの話し合いをしたら、我々のスタイルに合ってたんです。結果的には、我々の思う範疇のものもあれば、こういうのもあったかっていうアイデアもあって、そこら辺のバランス感はうまく取れたし、青海くんに頼んでよかったなと思います。
M:最初に会った時に、スケジュール管理を手帳でしてるのを見て信頼できるなって(笑)。
──前作の話になっちゃうんですけど、『Here I Stand』の4曲目「You’re Ok (Hold Me)」から急にリバーブが急に消えて、これまでの揺らぎのサウンドから一変しますが、ここから今までに繋がるものがありますよね。
M:シンプルなソングライティング曲を増やしだしたきっかけの曲なんですよ。
U:でも、今それを言われてはっとした感があります。前のアルバムの中で、今作にフィーリングが近いのがそのあたりですね。
M:8曲目の「Because」とかもそうですね。
──リバーブを消してみようっていうきっかけはあったんですか?
K:前のアルバムのデモ作ってた時に、《Run For Cover Records》とか、そこら辺のレーベルを聴き漁ってたんですよ。ほんまに最初のアレックス・Gとか。なんというか、“最初インディー”みたいな。
All::最初インディー(笑)。
K:最初の方のミッドウエスト・エモとか、そういうモードだったんです。
【Kntrのギタリストとしての回帰と“空ける美学”】──まさに聞こうと思ってたんですけど、Kntrさんのギターも変わったなと思って。アレックス・GやMk.gee、元Inc.のエイジド兄弟だったりビッグ・シーフとか、そこら辺のギタリストとかは追ってらっしゃるんですかね?
K:Mk.geeはめちゃめちゃ聴いてて、家にテープレコーダーがあるんですけど、ラインで通してプリアンプにして家で遊んだりしてるぐらい好きなんです。多分そんなことしてるんちゃうかなと思って。全然、揺らぎに生きてないですけど(笑)。
──確実に彼以降、トレンドが変わりましたよね!
K:本当に。ギタリストがちゃんと評価されるってしばらくなかったんですよね。今回、ソングライティング主体の中でも、ちゃんとギターソロを弾いてる自負があるんですよ。っていうのは、もしかすると、Mk.geeがちゃんとギタリストとして出てきてきたから、そのモードになったんじゃないかなって。
──ライヴの転換BGMをKntrさんが選曲されてますが、ニール・ヤングが何曲か入っててなるほどと思ったんですが、どういうところに影響を受けましたか?
K:ニール・ヤングはアルバムで言うと『Harvest』が好きで、クレイジー・ホースとのアルバムだと『Zuma』が好きで、その2つを特に聴いてたんですよ。『Harvest』の方は、本当に学びの宝庫というか、プロダクション的なところも、ソングライティングとか抜き挿しのバランス感が、私的には教科書のようなアルバムです。ずっと聴かれてるのに古臭くないっていうのが力強すぎて……凄いです。
──今作はスローコアの要素があって、以前やり取りをした時にも、今回はスローコアを勉強したとおっしゃってましたが、それはジョン・フルシャンテの初期ソロ作とかから受け取ったんですかね?
K:ジョン・フルシアンテは本当に亡霊のような存在なんですよね。
M:昨日も自分のギターがジョンすぎて恥ずかしいって言ってたよね(笑)。
K:好きなギタリストは、ジョン・フルシアンテとロリー・ギャラガー、あとスティーヴィー・レイボーンが最も好きなトップ3で、特にその中でもジョン・フルシアンテさんが……。
M:ジョン・フルシアンテ“さんが”(笑)。
──さん付けしちゃうぐらいなんですね(笑)。
K:骨の髄まで染みていますね……ジョンのファーストとかフォーキーなんですけど、それをジャンルとして捉えたことがないというか。あれ本当に何て言うんかな、アシッド・フォーク的な感じもあるし、実験的でもあるし。改めてジョンのファーストを聴いて、さっきのニール・ヤングにも繋がる話なんですけど、やっぱり匙加減ですよね。僕やったら絶対行っちゃうところを、我慢して8秒くらい空けるところとか、特にインスト曲が顕著で、改めて影響を感じますね。曲作りをしてる途中にもたまに聴いてました。
M:カンちゃんが作ってくる曲と、 私たちに言ってくるリファレンスの曲をどっちも聴いてるんで、“空ける美学”的なものはひしひしと感じています(笑)。
K:空ける美学って、ジョンらへんのあの当時はよくあったじゃないですか。あと、ジェイムス・ブレイクさん。ジャンルが違うけど、 空ける美学みたいなのから学ぶことが一番多いです。スローコアみたいにテンポを落としてジャーンって飛ばすとか、 そういう変化は自分でも感じます。
──揺らぎの面白いとこって、シューゲイザーもそうですし、マスロックやスローコアだったり、“ポストロック”に包括されるフィールドで遊んでるとこで、だから“揺らぎ像”みたいなものから逸脱せず、ファンからの信頼が厚いんじゃないかって思うんですけど、意識はしてるんですからね?
K:揺らぎがプレーンな状態で一番やりやすいものを、敢えてジャンルで言うとポストロックみたいなのがそうですね。ナチュラルにやれるし、ある程度そのジャンルに対して貯蓄があるから。
──そうですよね。揺らぎをシューゲイザーだけでシュリンクするのはちょっと違和感があったんです。
M:カンちゃんは空けの美学の出身なんですけど、私は対照的に菅野よう子さんとハードロックがルーツで、歌は詰め込み歌い上げしか知らなくて。けど自分の声はそっちじゃなくって。そんな中で自分の声に合った手段や道筋を見つけてくれたのがシューゲイザーでした。ただ、これをやりたいっていうよりは、あくまでフィルターの一つだったっていう感じです。
──あとそう、Kntrさんのすごいなって思うとこが、結構バシバシとトレンドにはまるなーっていう、なんか寄せに行ってるんじゃなくて、たまたま当たったみたいなのがめっちゃ多いですよね。
M:めっちゃ多い!
K:たまたま続いてる(笑)。
──前作はオーセンティックなインディー・ロック然としたものが流行ったタイミングでしたし、欧州のIDMとかアングラシーンでトリップホップがリバイバルしてる中で、「Oppressed」が来て、めっちゃハマってんなーと思ったり。それこそスローコアがシューゲイズ界隈できてるタイミングで、揺らぎも来たなーと思ってたんですけど、予知できたりとかするんですか?
M:予知能力あるん?
U:聞かしてくれよ。
Y:「Oppressed」もたまたまやったもんな?
K:なんか不思議ですよね。なんでかは正直わかんないんですけど、直感が当たってきたというか。前は外国のトレンドとかをネットでディグり続けてて、アイルランドの地元紙みたいなの見てた時期があるんですけど、コロナ禍くらいからもう追うのやめようと思って。その代わりに、あったかい音楽が聴きたくなって、自分が好きな昔のブルースとか90年代のオルタナやヒップホップもそうですし、電子音楽なんかを聴くようになったんですけど、その頃から当たるようになりました。今、トレンドなものをやってる人たちも自分と同じように、自分の意思で今聴きたいものを聴いてるんじゃないかって思いますね。
──なるほど、トレンドを追うより温故知新してたら、自ずと今のムードに合っちゃうみたいなことありますよね。「Oppressed」はポーティスヘッドがリファレンスと思いきや、キング・クリムゾンの「Starless」がリファレンスなんですよね?
K:そうです。60、70年くらいのプログレを聴きまくって作った結果なんです。けど、今トリップホップやってる人もトリップホップを目指して作ってるんじゃなくて、昔の別の音楽、それこそ僕と同じプログレとかを聴いてる可能性はめちゃめちゃあるなと思いました。
【映画について訊いてみた】──さっきKntrさんに訊いたんですが、今回のアルバムってシネマティックなムードがあるんですが、みなさんが最近見てよかった映画とか、好きな映画について語ってください。
M:私は今、『サウンド・オブ・メタル』占領されてますね。自分の状況も相まって結構トラウマチックなんですけど、でも映画としてめちゃくちゃいいですよね。元々、聴こえ方に左右差があって、ドレミは一緒に聞こえるんですけど、『サウンド・オブ・メタル』を見てからは、余計に耳が聞こえなくなるんじゃないかっていう……。普通、耳の聞こえない人が出てくる映画って、冒頭で聞こえないシーンが10分くらいあって、あとはもう視聴者目線のものが多いですけど、健常者が聞こえてるものと、彼の耳で聞こえてるものが、コロコロ転換するじゃないですか。実在の2ピースバンドを基にしてるみたいですけど、サントラもゆっくり聴きたいなと思って、今ちょっと追ってるところです。
U:ちょっと恥ずかしいんですけど、映画に関してはほぼ終わりの人間なんですよ。アニメは、もう本当に片っ端から見ちゃうんで、アニメサントラで好きなのはいっぱいあります。めっちゃベタなんですけど、『攻殻機動隊』を最近全部見直して。この前、デリック・メイが日本で再現イベントやってて、気になってて行けなかったんですけど、その新和性は意識してやってます。
K:デリック・メイが好きなん?俗に言う三大テクノだと。僕はガルニエ派なんですけど(笑)。
U:なんかでも、テクノとかジャンルをちゃんと意識して聴くクセがついてなかったので、テクノをちゃんと聞こうと思って、Kntrにいろいろ聞きながらそれだけを聴いてた時期がちょうどここ半年くらいで、でもやっぱりデリック・メイでした。
Y:僕は恥ずかしながら『エヴァンゲリオン』とか今さら見てて……。
──いやでも『エヴァンゲリオン』はリンクする歌詞もあったり、揺らぎ性を担保してると思いますよ!
Y:揺らぎには活きてるかは分からないですけど、明らかに絶望的なシーンやのに、子供が歌ってる「翼をください」とか、クラシックが流れたりとか、乖離してるのが面白いですよね。
M:私はカルト映画もすごい好きなんです。ベタなので言ったら『ミッドサマー』とかその辺とかの感じで。それでカンちゃんに勧められて、ピーター・グリーナウェイ監督の『数に溺れて』のリマスター版を映画館で観たんですけど、最高の映像と音楽体験で。私は建築家としても仕事をしているんですけど、観ていて凄い建築が好きなのが伝わってきます。前作の『建築家の腹』はそれこそ建築好きが詰まった作品で、大学の授業で観ていたんですけど、同じ監督とは知らなくって。綺麗やけど恐ろしい、幽玄な新しいクラシックのサントラも素晴らしいです。けど、ああいう映画は家じゃ集中して見れないですよね(笑)。
──まだ観れてないんですけど、今やってる『ブルータリスト』とか建築家の映画ですし、ハマりそうですよね!
M:ねー!面白いって聞きますけど時間がねぇ……。一緒に観に行きましょー(笑)。
──いいですねー! 音楽も、我らがヤック/ケイジャン・ダンス・パーティのダニエル・ブルームバーグがやってて、オスカーも獲りましたしね!
K:へー!ヤックなんて我々の青春ですよね(笑)。
──そしたらKntrさんも映画についてお話しください。
K:映画はすごく好きで、予告とかを見て最新作も観に行きますし、リバイバル上映も調べて映画館に観に行ったりするんですけど、『ピアノ・レッスン』の4Kリマスターがめちゃめちゃ良くて、サントラも良かったですが、逆にサントラから入るパターンも結構ありますよね。さっきMiracoも紹介した、『数に溺れて』の音楽使いがすごくて、それこそさっきのYuseiさんのエヴァの話に近いと思うけど、なんかすんげえエグいシーンやのに、恐ろしく綺麗なピアノの軽快な音楽が流れて、それが長回しのワンカットでずっと続くんです。だから、まずサントラだけ聴いてから観に行って、あの曲はどういう場面で流れるんだろうっていう楽しみ方を最近はしています。
──それ面白そうですね!
K:最近、それで一番大きかったのは、ベルトルッチの『1900年』です。300分超で、若い時のロバート・デ・ニーロが出てて、音楽がエンニオ・モリコーネなんですけど、坂本龍一がピアノでカバーしてたりして、先に音楽を知ってて。けど、モリコーネ特集でもないかぎりリバイバル上映もないんで、わざわざ高いDVDをメルカリで買って、家で一人で見たんですけど、これはねぇ……これこそ映画体験って感じで……幼少期から年を取るまで、1900年から1950年くらいまでの同じ時代を生きた、出身の違う男2人の成長譚で、そのうちに戦争になるんですけど、そこでモリコーネがどう使われるかっていうのが面白かったですね。
【リミックス・アルバムへの期待とそこから見えてくるもの】──揺らぎと言えば、リミックスEP/アルバムがやっぱり楽しみの一つでもあるんですけが、けっこうなビッグネームにもコンタクトを取ってるんですよね?
K:そう、ボーズ・オブ・カナダからちょっと返信が来かけたっていう(笑)。既読が付いて入力中にもなったんですけど、結局来なかった……。
Y:なんかしてて忘れたんやろな(笑)。
K:まあ、揺らぎはバンドですけど、バンド音楽以外に聴いてる音楽っていうのは各々にあって、僕個人的に言えば電子音楽が好きで。元々、中学に入ったぐらいからSoundcloudで音楽を聴き初めて、阿部寛のホームページみたいなローファイなサイトで、《Stones Throw》周辺とかの現地のライブレポートを見漁ってたぐらい、特にLAビート・シーンが好きで。そういう来歴はリミックスを頼む人選に影響してると思います。前にリミックスをしてもらったライアン・ヘムズワースとか。
──そしたらお一人ずつ理想のリミキサーを聞かせてください。
U:僕はジム・E・スタックです。
──あぁ……絶妙にワンチャンあり得そうですね……。
U:今はケイシー・ヒルに完全に着いてるみたいな感じで、あの人の新しいソロを待ってるんですけど、しばらく出てこないんで、しょうがないから出てるアルバムばっかり聴いてるんです……。
M:私はフォー・テットか……。
──ヘッドライナー級ですね!(笑)
K:なんなら1回メール送ってますよ(笑)。
M:あとはねー、これはリミックスになるのかちょっとわかんないけど、最近すごい真っ白な光輝くトイレでスティーヴ・ライヒを聴くっていう体験をして、音姫みたいなリミックスを作ってほしいなっていうのを思いました。トイレしながら聴くのもすごいシュールやし……。
──それじゃあアンビエントというか環境音楽になるまでリビルドというか……。
M:そうですね。分解して極限まで削ぎ落としてもらって、揺らぎを踏襲せずに、もはや素材にされた自分たちを聴いてみたいです。
Y:僕はやっぱりヨンシーにやって欲しいですね! ソロ・アルバムも結構聴くんですけど、シガー・ロスとはちょっと違うけど、ヨンシーの思想が混ざってて、ドラムもパッドだけじゃないですか。あれも好きなんですよね。
──ヨンシー繋がりでアレックス・サマーズかA.G.クックもアリですね!
M:A.G.クックもやって欲しいですね〜。
──宇多田ヒカルから藤井風まで来てるんで、揺らぎも無くはないんじゃないですか?
U:だいぶ距離ありますよ?(笑)
M:なんか逆に良さそうな方っていませんか?
──それこそKntrさんとも話してたんですけど、タラ・クラーキン・トリオっていうバンドにやって欲しいですね。
K:ほんまに今年聴いてるアーティストでトップ3入ってますよ(笑)。
──マジですか!めっちゃ嬉しい! 実際ライヴを見に行ってメール・インタビューもしたんですけど、ブリストルを拠点にしている、唯一と言っていいブリストル・サウンドの継承者で、それこそ「Oppressed」をリミックスして欲しいなと。あとDIIVが、去年のアルバムのリミックスを何曲か出してて、昨日マウント・キンビーのリミックスが出て……。
U、M:マウント・キンビーもいいなぁ〜。
K:あといるやんか、好きなやつがさ……フルーム!
Y:あー! フルームにポッケからCD出してほしい(笑)。
K:《Triple J》のカバー企画にフルームが出てて、ポケットからCDを出して、CDJに入れて曲を流す動画があるんですけど、Yuseiさんと見ながらキャッキャ笑ってるんです。
K:フルームはめちゃめちゃ好きで、特に『Hi This Is Flume』から、こいつはすごい度胸があるって思ってから、より好きになって。そういうトップ・プロデューサーみたいな人にもやって欲しいし、HAAiとかにもやって欲しいですね。本当にいろんな人にメールを送ってるんですよ、いっぱい。フルームにもメール送りましたね。
U:送るのはタダなんでね(笑)。
K:バンドで候補をリストアップして、私が片っ端から“このアルバムが一番好きです”っていうのを送っています(笑)。
──でも、そういうのから更なるステップアップの足掛かりになったりしますし、絶対リミックス企画は続けた方が良いですよね。
【揺らぎの行方】──それでは最後にこれからのバンドの展望を語っていただければと思います。
K:今回のアルバムは、今までとは違ったバンドバンドしてる感じで、ウケるかなと思ってツアーをして、結果的には冒頭の「Jason」でのエピソードみたいなのがめちゃめちゃ多くあって、この方向性っていうか、このソングライティングに重きを置いた音楽が持ってる、人に届けるパワー、歌のパワーみたいなものは今回はよく学びました。上手くいくかは分からないけど、得たものを絶対活かせるだろうという自負はあります。作った時より、ツアーとかライブを重ねるごとに得るものが多かったですね。
Y:僕は今回のアルバムから変拍子をやったんですけど、もっと入れていきたいですね。これからまた曲を作っていくと思うんですけど、変拍子があることで、曲の中にちょっとした違和感があったりとか、音楽的にもっと遊べてもいいのかなって。ヴォーカルをフィーチャーするのは、これからもずっとやりたいと思うんですけど、音楽的にもっと遊んで、みんなの技術が向上できたらいいなと思いますね。
M:年代はカンちゃんが影響を受けたものと違うんですけど、フォークから影響を受けた人が多くて、最近の人だとレイフ・ヴォルベックとか、アリス・フィービー・ルーとか……たまたま入ったレコード屋さんでジョージ・ハリスンのレコードを見つけて、聴いてみたりしている中で、今回のアルバムですごい歌の力っていうのを出したと思うんですけど、まだまだいけるって思うんですよね。あったかみと言ったら安直ですけど、もっと表現面とか技術を学べると思うし、ささやくだけではない私、バンドのヴォーカルができる自覚と誇りを持てるように頑張りたいなと思います。
──とはいえギターの演奏も素晴らしかったです。
M:でもやっぱり、ギターで作曲するっていうのは、私のギターへの理解度が低いから、曲に反映しきれないっていうのがあって、もうちょっとやりたいんですよね。「Jason」を一人でやってみて、すごい緊張するけどやってみたらけっこう楽しいなって、それは良い発見でしたね。
──ソロで弾き語りをすることで、なにか新たなインプットがあるかもしれないですよね。
K:やっぱ各々でソロ・プロジェクトをしやなあかんね。
U:こんだけ趣味志向がバラバラでやってるバンドなんて珍しいんちゃうかな。今回はヴォーカルを前に出すっていうこのコンセプトで作って、ツアー中も試行錯誤しながらやってたんですけど、僕の中では昨日の大阪公演で一番まとまったなって思ったんです。それこそ、シンセが入った編成も、PAさんともリハでラリーを続けながら、どれだけ音だけを落とすとか上げるかをやり続けて、やってる側としても面白くて、こうやって外側からも評価して頂いて。ヴォーカルを前に出すのはシンプルなんですけど、楽器陣がそこ踏まえた上の音作りとか、音の構成とかを、揺らぎは今回で最もそこに新たな試みをしていて、各々のやり方で音作りの段階からやってたところは、プレイヤーとしていいものが蓄積されたなって思いがあるんですよ。Kntrが言ったように、ソングライティングの方をメインでやるのか、それとも全く別の形をこっから模索していくのかは、今の段階では分かんないんですけど、確実にこれが今後ひとつの武器になって活きてくるのは間違いないと、ツアーを通して思いました。
<了>

Text By hiwatt
Photo By Asahi Yamashita

揺らぎ
『In Your Languages』
RELEASE DATE : 2025.01.24
LABEL : FLAKE SOUNDS
購入はこちら
Tower Records /
HMV /
Amazon / Apple Music
<ライヴ情報>
《SYNCHRONICITY 2025》
2025年4月12日(土)、13(日)
TICKET
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2454517
問い合わせ
https://synchronicity.tv/festival/about/
《ANORAK! SA&TI&HTI TOUR 2025》
2025年5月23日(金)
場所: Live&Louge Vio
ゲスト: 揺らぎ
OPEN / START 18:00 / 19:00
ADV ¥3,500+1D
TICKET
https://eplus.jp/sf/detail/4143380001-P0030008P021001?P1=0817
関連記事
【FEATURE】
揺らぎ
シューゲイザーという「空間」を感じて
https://turntokyo.com/features/here-there-and-shoegazer-yuragi/
