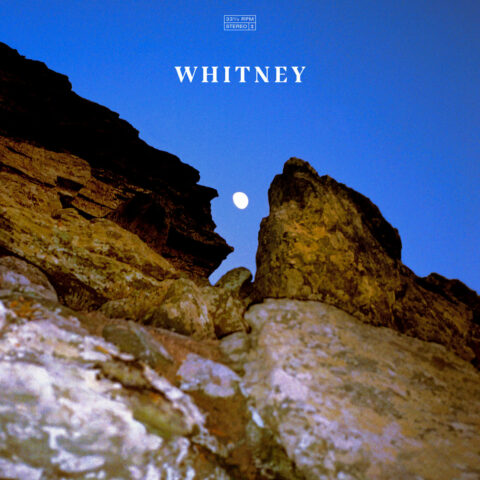率直なフェイバリットにとどまらない研鑽の成果
コロナ禍直前の2020年はじめに録音したというカヴァー・アルバム。ホイットニーの直接的なルーツである70年代カントリーやフォークに加え、ティーンエイジャーのころから愛聴してきたというブライアン・イーノ&デヴィッド・バーン「Strange Overtones」、きわめて情報の少ない70年代フランスのライブラリー・ミュージック作家ジャック・アレル「Something Happen」など、一見するとレコード棚からそのまま持ってきたかのような、音楽ギークたる彼ららしい選曲である。
彼らは以前からライヴで頻繁にカヴァーを披露してきたバンドで、かねてよりカヴァー・アルバムを期待していたリスナーも少なくないだろう。しかし注目すべきは、十八番であるはずのNRBQ「Magnet」やニール・ヤング「On the Way Home」が選曲から漏れ、代わりに、ホイットニーと同時期にデビューしたケレラの「Bank Head」、90年代R&Bユニットの代表格・SWVの「Rain」という直球のR&Bナンバーが収められている点だ。特に先行シングルにも収録されていた「Rain」は今作の白眉で、原曲のメロウさを引きずらないヴォーカルと整理された素朴なアンサンブルによって、フォーク・ロックの質感を備えたネオ・ソウルとでも言うべき絶妙な調和が成り立っている。
今作はどの曲も編成・アレンジともに全く奇をてらっていないが、このように、控えめながらもそれぞれの楽曲に即したモード・チェンジが確実になされているのが特徴だ。ベース・ラインが躍動的になり全体に抑揚がつけられた「Something Happen」は、サイケデリックな原曲とは異なりライヴでのアグレッシヴなプレイを期待させるし、「Rainbows & Ridges」ではガラリと変えたキーと最小限の編成によって、原曲とは違う角度からメロディの美しさを際立たせている。彼らのトレードマークであるテープ・ライクな音処理が今作では影を潜めているのも、より緻密なレベルでアプローチの差異を出そうとした結果だろう。
ジュリアン・エールリッヒ(Dr / Vo)は今作のリリースについて「はじめは、単に曲とバンド・メンバーをとても愛していてカヴァー・アルバムを作りたかっただけなんだけど、結果的にバンドとしてどう進化していくかという探求になったんだ」とコメントしている。今作における楽曲解釈と構成の工夫の取り組みは、今後はっきりとした形で彼らのモードにあらわれてくるはずだ。そして発端にフェイバリットがある以上、彼らはそもそもカントリーだろうがR&Bだろうが、ひとしくリスペクトを抱いてディグを繰り返してきたのだろう。ミュージック・ラヴァーとしてのそんな気質と自身のスタイルを突き合わせ、より洗練された共通解を出したことによって、彼らはいよいよ、ポップ・バンドとして時勢にとらわれないしなやかさを身に着けつつある。(吉田紗柚季)
関連記事
【REVIEW】
Whitney『Forever Turned Around』
http://turntokyo.com/reviews/whitney/