アメリカの良心、その苦悩と歓喜のプロセス
ウィルコ全アルバム・ディスク・ガイド
ウィルコのニュー・アルバム『Ode To Joy』がリリースされた。前作『Schmilco』から約3年ぶりのオリジナル・アルバム…というのは大した問題ではないが、『Schmilco』とその前の『Star Wars』が僅か1年のタイムラグでスピーディーに発表されていたこと、さらに『Star Wars』が当初フリー・ダウンロードで公開されていたことなどと比して考えると、3年という実際の年月以上の時間経過を実感する。その間、バンドの内部で何が起こったのか? これについては先ごろ実現したバンドの要のギタリストであるネルス・クラインのインタビューを近々お届けできると思うので、そこで当事者に語ってもらうことにするが、ともあれ、3年以上にも感じられるタイムラグが、実際にここまで作品の内容にも影響を与えたとは!と驚愕してしまうほどに、『Ode To Joy』は素晴らしいアルバムになっている。
『Yankee Hotel Foxtrot』(2002年)との共振を指摘する海外メディアも多いが——もちろん音作りには17年前のあの作品以降のキャリアの積み重ねによる柔軟性や包容力が備わっているものの——確かにターニング・ポイントにもなったバンドのあの代表作の持っていた、ギリギリのところでさらに淵まで追い込んでみたようなニヒリズムと危機感がゆるやかに伝わってくる作品になっているのは間違いない。ゆるやかに贖罪まで表現したようなこのニヒリズムと危機感がどこからきているのか。その回答は、ネルス・クラインのインタビューに譲るが、その公開前に、まずはバンドのこれまでのキャリアをオリジナル・アルバムで振り返ってみたい。今回、岡田拓郎、三船雅也、西田修大というウィルコの影響を受けたミュージシャンたちにも執筆参加してもらったので、バンド誕生時はもちろん、ブレイク以降の彼らを知っているようで知らない方にもぜひ楽しんで読んでみてほしいと思う。本音を言うと、ここ数作、少し気持ちが離れていたが、ウィルコがアメリカにいることを当たり前だと思ってはいけない、新作『Ode To Joy』を聴きながら今は改めてそう感じている。(岡村詩野)
『A.M.』
1995年 / Reprise

オルタナ・カントリー・バンドとして人気を集めながら、ヴォーカルのジェイ・ファーラーの脱退によって解散したアンクル・トゥペロ。その背景には、ファーラーとジェフ・トウィーディーの対立があったらしいが、解散後、ジェフはファーラー以外のメンバーでウィルコを結成する。アンクル・トゥペロの名前を継がなかったのは、新バンド、サン・ヴォルトを結成に動いたファーラーへの対抗心もあったのかもしれない。
そして、リリースされたファースト・アルバム『A.M.』は、全曲をジェフが作曲。「パンク世代のカントリー・ロック」というオルタナ・カントリーのイメージをわかりやすく展開して、本作だけの参加になったブライアン・ヘンネマン(ボトルロケッツ)の泥臭いギターも存在感を発揮している。そんななか、サン・ヴォルトがグランジ的なシリアスさでオルタナ・カントリーを深めていったのに対して、ジェフはギター・ポップ的なフレンドリーさで惜しげもなくキャッチーなメロディーを繰り出していく。ルーツ・ミュージックに根差した幅広い音楽性を持ち、みずみずしくてポップなソングライティングは、彼らが愛するグラム・パーソンズやビッグ・スターに通じるものがある。
本作のデラックス・エディションが2017年にリリースされた際、ベースのジョン・スタラットはアルバムを聴くと「当時の純粋さと信念とが入り混じった奇妙な感覚が甦る」とコメント。カントリー、ブルース、ロック、R&Bなど、自分たちが影響を受けた音楽への愛情をストレートに表現した本作は、そのナイーヴさゆえに、いつ聴いても、何度聴いても、エモーショナルで甘酸っぱいアルバムだ。(村尾泰郎)
『Being There』
1996年 / Reprise
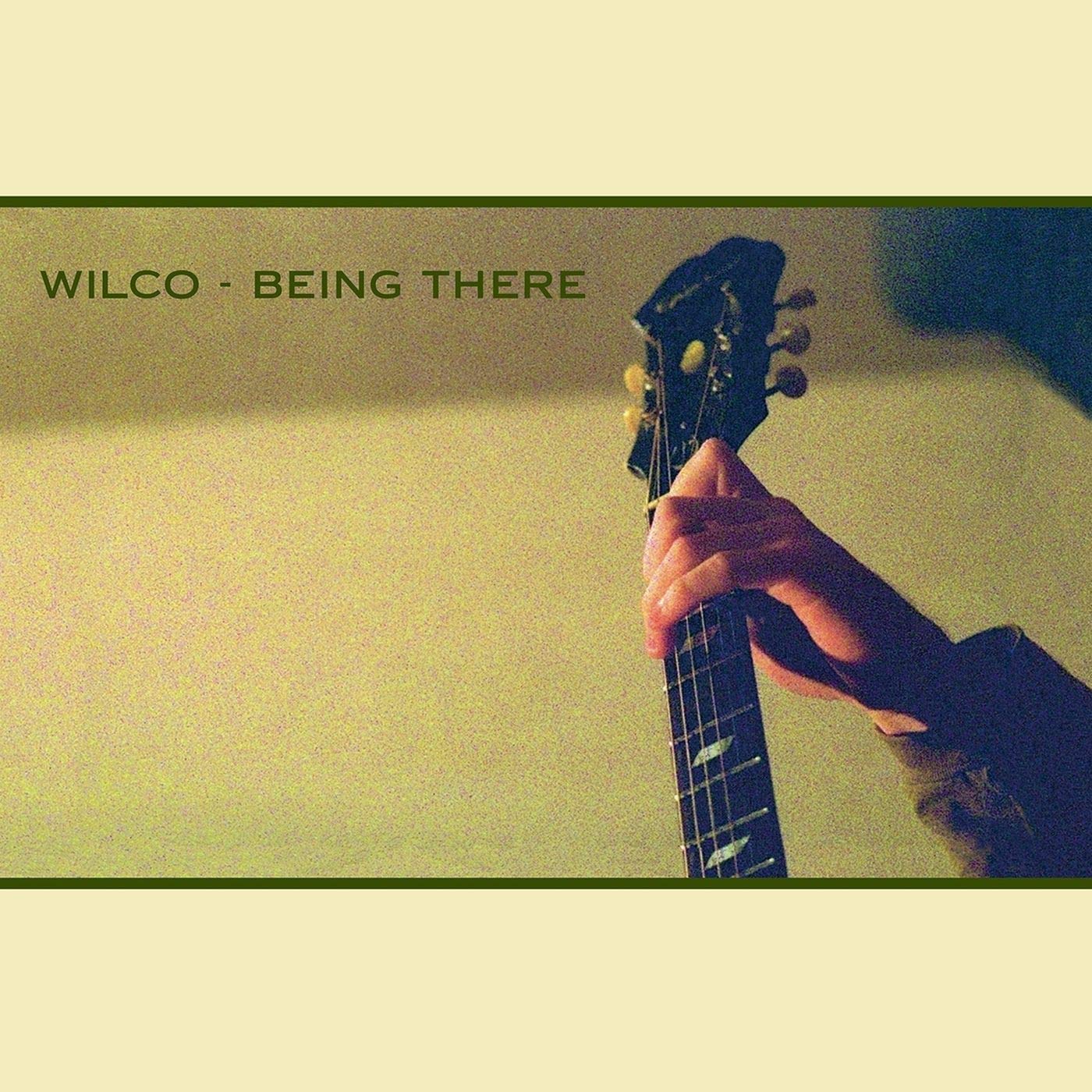
恥ずかしながら、筆者がウィルコに本心で魅せられるようになったのは『Yankee Hotel Foxtrot』以降のことだ。アンクル・テュペロ時代はもとより、ファースト・アルバム『A.M.』でさえもピンとこなかった、というのが当時の本音で、というのも、その頃は《Drag City》から作品を出していたスモッグやボニー“プリンス”ビリーといったアシッド・フォーク色あるアーティスト、あるいはトータスやアイソトープ217といったジャズやハードコアパンクをベースとした《Thrill Jockey》勢の方にオルタナティヴな魅力を感じていたから。当然ながら、ウィルコのこのセカンド・アルバムがリリースされた時も、2枚組というヴォリュームだったこともあり、当時人気を集めていたジャム・バンド系との親和性の方を強く感じていた。実際、筆者は本作を同じ年に発表されたフィッシュの『Billy Breathes』と並べて聴いていた覚えもある。尤も、その時に感じていた親和性は今も間違っていたとは思っていない。
だが、ご承知のように、その後ジム・オルークがウィルコをバックアップするようになった。参ったな、と思った。ジムはガスター・デル・ソルを経てソロとして活動を展開していた、《Drag City》の看板的存在の一人。もちろん、筆者にとってもこの時代最も重要なアーティストだ。のちに、そのジムに聞いたところ、途中参加となるドラムのグレン・コッツェと親しかったことからウィルコに関わるようになったが、そもそもジェフ・トゥイーディーとはそれ以前から顔見知りだったという。だが、「ジェフはソングライターとして素晴らしいが、それを生かすサウンド・プロダクションが必要ではないかと思っていた」とジムから聞くに及び、この作品を当時評価できなかった後悔(恥)の思いが少し報われた気がした。なるほど、あまりにアーシーな音作りと録音が、《Drag City》周辺の作品に馴染んでいた耳には平面的に感じたのかもしれない、と。リマスタリングされたデラックス・エディションを聴くと、そうした物足りなさももはや解消されてしまっているのだが…。
しかしながら、ディスク1(10曲)、ディスク2(9曲)…いずれも楽曲、演奏と歌、アレンジ自体は本当に素晴らしい。カントリーをグルーヴあるブラック・ミュージックとして解釈するような演奏、ブルーズをメロディアスな子守唄のように表現するヴォーカル、あるいは南部の音を北部のタッチで鳴らしてみる勇気とダイナミズム……。ジャンルに対する既成概念をすべて混交させるようなチャレンジが、一聴するとベタなアメリカン・ロックとして収束されてしまうような楽曲の中で丁寧に仕組まれている。それはローリング・ストーンズがジミー・ミラーと組んでアメリカ南部で録音していた時代の作品にも匹敵する混合具合と言ってもいい。ハイライトはビリー・プレストンが参加していた時代のストーンズを思い出す「Red-Eyed And Blues」。アレサ・フランクリンやチャカ・カーンなど多数のセッションを経験してきたベテランのゲイリー・グラントがトランペットで参加している「Monday」もいい。
今でもウィルコの個人的最高傑作は『Yankee Hotel Foxtrot』に代わりはないが、懺悔を込めて、筆者は今やジャケットのアートワークも素晴らしいこのアルバムをその対抗馬として位置付けている。ジム・オルークのいうような“のびしろ”を持っていたその可能性も含めて。(岡村詩野)
『Mermaid Avenue』with Billy Bragg
1998年 / Elektra

ボブ・ディランの自伝によれば、ここで歌われている歌詞は本来であれば彼の手に渡るはずのものだった。彼の師ウディ・ガスリーその人(当時彼は入院中だった)に伝えられた通り、ブルックリンの南端、コニーアイランドの湿地帯の先──“マーメイド・アヴェニュー”にある彼の家を訪れたはいいものの、幼い息子アーロは、父の未発表詞の存在を知らず、結局ディランは、それを手にすることはなかった。それから約40年後、その未発表詞に曲をつけることになったのはディラン…ではなく、イギリス人シンガーで社会活動家のビリー・ブラッグ、そして彼が共作の声をかけたウィルコだったのだ。ガスリーに影響を受け、アメリカン・ルーツ・ミュージックに傾倒するブラッグ。彼が本作を「もし今ガスリーが生きていたなら…」という作品と構想したのならば、当時まだ若手とも呼べる存在ながらも、カントリー~フォークをロック・バンドとしてアウトプットすることに野心的だった彼らを共作者に指名したことにも頷ける。その証拠に、ブラッグがヴォーカルを取る楽曲は、動きの少ないメロディとごく僅かなヴァースの繰り返しで構成されているものが多い。つまりはガスリーがその歌詞を残した時代、1930年代~60年代のフォーク・ソングの形式を比較的忠実に再現したものと思えるのだが、ジェフ・トゥイーディーがヴォーカルを取る楽曲は対照的に、展開の多い現代的なポップスの構成とバンドの力強さを大いに生かしたダイナミックなアレンジに仕上げられている。言ってみれば、ガスリーという存在をウィルコというバンドに大胆にも取り込んでしまったかのように、だ。それらが『A.M.』なんかに収録されていても、さほど違和感はないだろう。歴史に忠実なブラッグと、歴史を包摂しアップデートするウィルコ。そのコントラストは結局、最後には二者のコンフリクトを生んでしまったわけだが、それこそがまさに、ウィルコの“オルタナ・カントリー”たる所以を色濃く示しているように思えてならない。(井草七海)
『Summerteeth』
1999年 / Reprise

現在では轟音ノイズと共に演奏されるのがおなじみとなったマーダー・ソング「Via Chicago」、高揚感あふれるエクスペリメンタル・ロック「A Shot in the Arm」とライヴ定番曲も数多く収録したビーチ・ボーイズやビートルズの成分多めの3作目。どこの記事だったか、ジェフ・トゥイーディは本作発売後に「ペイヴメントみたいなバンドとして語って欲しいんだ」とコメントしていた記憶がある。カントリー・ロックのリバイバルというだけでなく、より広くオルタナティヴ・ロックの流れの中で評価されたいという発言も90年代末らしいな、と今では思うのだけど、その野心から作品はウィルコ史上最もポップになってしまった。脱オルタナ・カントリーから始まり、曲の大半を今は亡きギタリストのジェイ・ベネットと共作、スタジオ作業にウェイトを移して、より広い意味でのアメリカン・ミュージックの再構築を目指して試行錯誤が始まる。方法論の変化によって、この作品は瑞々しさと翳りを合わせ持つウィルコのポップ・サイドを決定づける仕上がりに。ジェフの書く曲は、『A.M.』から現在までどう解体しても揺らがない芯の強さを持つけれど、制作面での模索は長いキャリアの中でもちょっと浮いてるぐらいのアンバランスなカラフルさをもたらしている。1999年、まだ同時多発テロの起きていないアメリカ、そう思うとモラトリアムの白昼夢のような雰囲気さえ漂う。バンドの成長と野心が混ざり合い、スタイルが確立されていないからこそエバーグリーンな輝きを放つウィルコの青春アルバム。(冨永啓仁)
『Mermaid Avenue Vol.Ⅱ』with Billy Bragg
2000年 / Elektra

あくまでこの『Mermaid Avenue』シリーズの軸になっているのはビリー・ブラッグの方である、という事実を前提として話を展開するのと、ウィルコがビリーをたきつけて盛り上げたという妄想(仮想)を前提に論旨を進めるのとでは、おそらくこの“ウディ・ガスリー巡礼の音の旅”…わけてもこの2作目は聴こえ方がたぶん大きく違ってくる。曲自体はビリー主体で作られたものとウィルコ主体で作られたものとが約半々で、本作の第一弾とあまり変わらない。だが、徐々にフェイドインしてくる1曲目「Airline To Heaven」(ジェフ・トゥイーディーとジェイ・ベネットの共作)のパッション溢れるブルージーでバスキング風の演奏が、本作をウィルコ主体のように“聴こえさせる”。主導だったのはビリーだろうが、あるいはスタジオに勢いを持ち込んだのはウィルコだったのではないか、と思うほどに。
本作の2年後に『England, Half English』を発表してフジロックにも出演したビリー・ブラッグに取材した際、「僕はどっちかといえば言葉の人だから、ウィルコの連中のサポートは絶対に必要だった」とこのシリーズについて話してくれた。多少の謙遜もあるのだろうが、実際にガスリーの言葉に瑞々しい跳躍力をもたらしているのがウィルコの演奏なのは言うまでもなく、結果として半世紀以上も前のアメリカの文化財産であるガスリーの作品を現代人の耳に届くよう引っ張り上げ、モダンなアメリカン・ルーツ・ロックにすることで、遠く離れた時代と21世紀が見えていた時代とを繋げることに成功させたのはウィルコのまだ青さも残した若々しさだ。そこに、アメリカ文化に敬意を持ちつつも英国人らしいコックニーを手離さないビリーの歌がクロスしてくることの意味の大きさ…。両者の邂逅は、それこそストーンズやクラプトンが米南部に憧れたり、ディランがフォークからエレキギターに持ち替えてみたりしてきた歴史的にダイナミックな地域や文化の攪拌を思い起こさせる。
元々は、ウディ・ガスリーの未発表の歌詞に音楽をつけたいとウディの娘、ノラ・ガスリーがビリー・ブラッグに相談。そのビリーがウィルコを誘って制作したのが1998年に最初にリリースされた第一弾である。本作はその続編にあたるもので、グラミー賞「Best Contemporary Folk Album」にもノミネートされるなど高く評価された第一弾と合わせて100万枚以上をセールスした。2012年には2作品に加え、さらなる未発表セッション17曲を収録した第三弾やDVDなどを加えた『Mermaid Avenue: The Complete Sessions』がリリースされている。さすがにもうこれ以上ないだろう、と思いつつ、またガスリーの何かの節目に掘り起こされそうな気がしないでもない。なにしろ、このシリーズの第一弾のリリースからも、もう20年以上が経過しているのだから。(岡村詩野)
『Yankee Hotel Foxtrot』
2002年 / Nonesuch

その音楽的実験要素から商業的自殺とまで煽られた、『Kid A』をレディオヘッドがリリースした翌年、ニューヨークに飛行機が突っ込んだ2001年、ジェフ・トゥイーディーはトム・ヨークの哲学とはまた違ったロジックでノイズと音響、新しいサウンド・テクスチャーで自分の殻を破ろうとした。多くの“オルタナ・カントリー”の1バンドだった彼らが、盟友であるジム・オルークをアディショナル・エンジニア、ミキサーとして初めて迎え、様々な実験、ストリングス、怪しく繰り返される支離滅裂な言語、非公式な諜報ラジオである乱数放送から収集したサンプルを駆使し、音の彫刻とも言えるフォーク・カントリー・アルバムの大傑作を作りあげた。しかし彼らの場合はレディオヘッドのように順調にいかず、作り上げた作品は所属レーベルからリリースを断られてしまう事態になってしまう(危うく本当の自殺になりかけたというわけだ)。そこで彼らは今では当たり前となった、ウェブサイトでの音源のフリー公開に踏み切る。その結果、無事、エクスプローラー・シリーズで高名な(その後フリート・フォクシーズのアルバムもリリースすることになる)《Nonesuch》から翌年リリースされ、世界的な評価を得、今のメンバーでの最強のライヴ・バンドとしての地位を確立するのだ。ウィルコ史における大きなターニング・ポイント。真のオルタナティブ・カントリーの姿がここにある。そして最強のライヴ・バンドとなったウィルコが今のメンバーで『Yankee Hotel Foxtrot』を作ったらどうなるか? その答えが新作『Ode To Joy』にたくさん散りばめられている。(三船雅也)
『A Ghost Is Born』
2004年 / Nonesuch
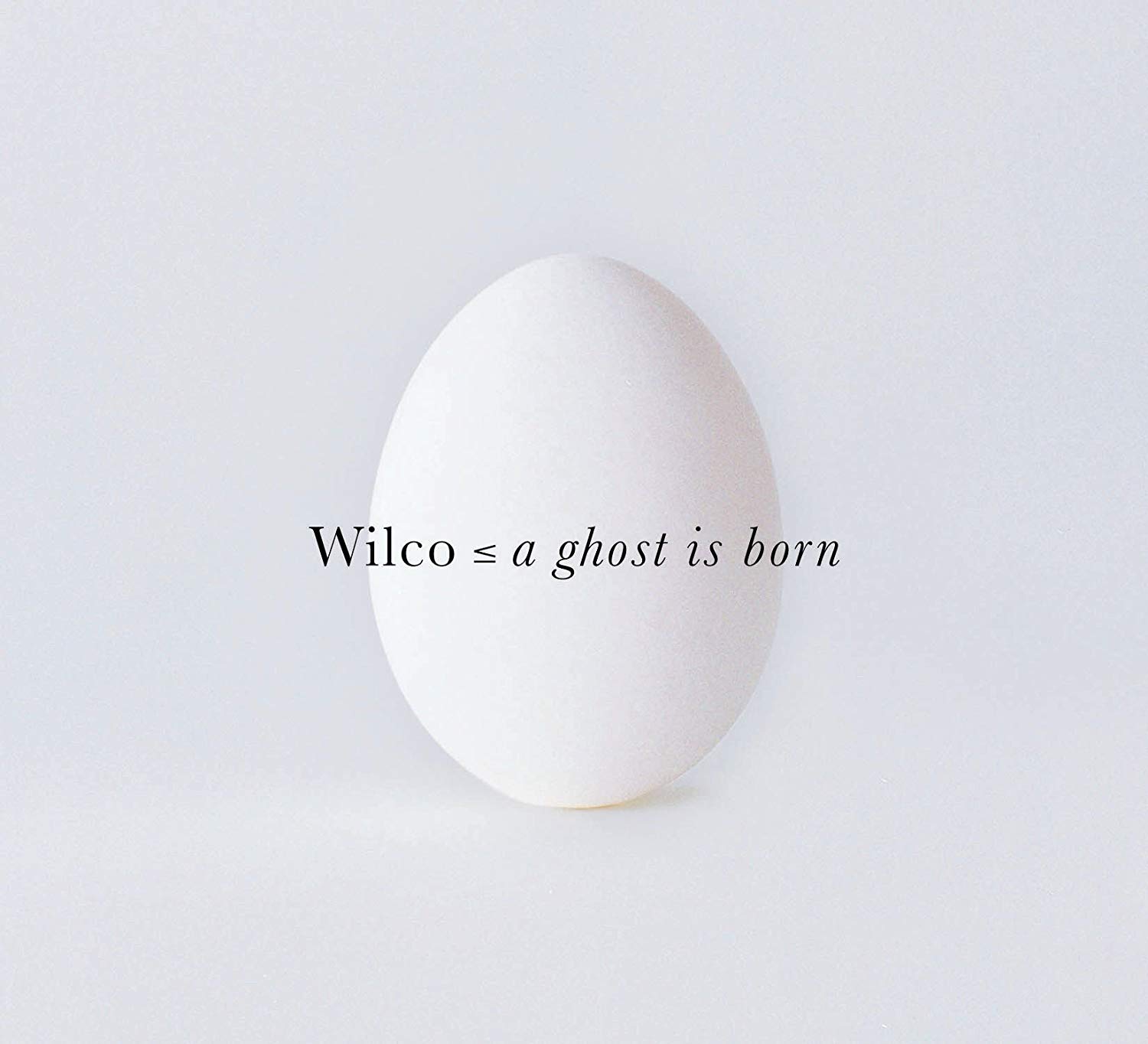
前作『Yankee Hotel Foxtrot』がアメリカン・ロックの脱構築であるならば、本作を一聴したときの静けさはアメリカン・ロックの抽象化を思わせる。本編1曲目を飾る「At Least That’s What You Said」の耳をそばだてなければディテールが浮かび上がらない程に小さな音で奏でられるイントロは、今日的なフラットなラウドネスに慣された私たちの耳に音楽そのものを聴取させる事へ改めて向き合わせる。こうしたナチュラルなダイナミクスのレンジの広さは本作に通底した要素となっている。
「Hummingbird」「I’m a Wheel」といったポップ・チューンから、「Spiders」「Less Than You Think」といったエクスペリメンタルなトラックまで、幅広い楽曲を並べた本作は、リリース当初“まとまりのないアルバム”とpitchforkで酷評されたが、その後の彼らの成熟の後にこうして振り返ると、もっともフレッシュな形でのウィルコらしさが詰まった最高傑作といえないだろうか。共同プロデューサーはジム・オルーク。(岡田拓郎)
『Kicking Television: Live In Chicago』
2005年 / Nonesuch

バンドにとって夢のような瞬間は、きっとすごく複雑な形で成り立っている。継続的な活動、新鮮な初期衝動…必要そうなものはたくさんあるけれど、単にこれがあればいいというものはなさそうだ。全てが絶妙に噛み合った時、奇跡のようなものが一瞬顔を覗かせるんだろう。『Kicking Television』はそんな貴重な瞬間を切り取った最高のライブアルバムだ。現体制のウィルコにとって要といえるネルス・クラインやパット・サンソンが加入して間もなく行われたこのライブには、いまに比べれば荒削りな場面もある。でもだからこそそれぞれが持ち味をいかに発揮するか奮闘し、偶発的に噛み合ったフレーズが曲を加速させ、ライブならではのスリリングな瞬間が数え切れないほど生まれている。
開始早々、最高潮のテンションで聴かせる「Misunderstood」はこの曲のベストテイクなんじゃないかとすら思えるし、「Handshake Drugs」のフォーキーさとフリーキーさの共存はまさに理想! 「Via Chicago」ではホームを持ちそこで根強く活動を続けるバンドの力強さにハッとして、「Muzzle of Bees」のかっこよすぎるギターソロは何度コピーしたかわからない。
挙げていけばきりがないほど、自分のバンドへの憧れが詰め込まれた一枚、憧れを形作ってくれた一枚だと感じる。いまの時代にライブを続けていく意味を考える上でも、必ず指標として聴き続けていくだろう大好きなアルバムだ。(西田修大)
『Sky Blue Sky』
2007年 / Nonesuch
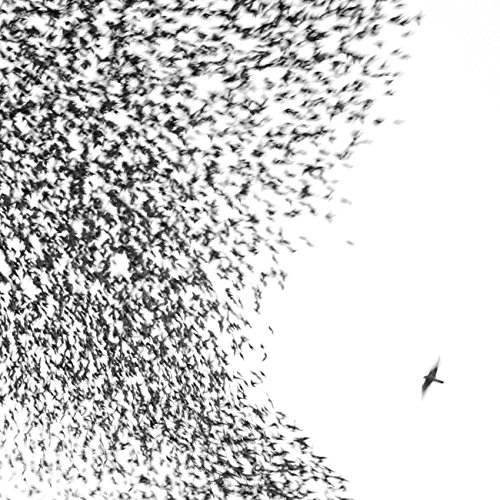
ネルス・クラインとパット・サンソンを加えたウィルコ最終形態、最強編成による記念すべき1枚目の作品。本作でも引き続きジム・オルークが参加しているが、クレジットはストリングス・アレンジのみで、6人のロック・バンドとしての道を選んだ意思を感じさせる。アルバム全編でやはり耳を引くのは、コンテンポラリー・ジャズのインテリジェンスと、ハードコア/ノイズのラディカルさを兼ね備えたネルスの存在がやはり大きい。中でも「Impossible Germany」後半の長尺ギター・ソロはアンビバレント性を中和させず同時に操る事の出来るネルスのバランス感覚に何度聴いても驚嘆させられる。常に新しいギター奏法の発明が進化を押し進めてきたロックの歴史を辿れば、本作はロックをまた新しい次元に押し進めたといっても過言ではないだろう(“ロックの歴史”における“パパ・ロック性”はさておき…)。とはいえ、前2作と比較すると、エクスペリメンタルさは影を潜め、「Either Way」や「Hate It Here」といったメロウなポップ・チューン名曲も多い事から、ウィルコのアルバムの中でも、もっとも耳心地が良く、ストレートなポップ・アルバムとして聴ける作品ではないだろうか。(岡田拓郎)
『Wilco (The Album) 』
2009年 / Nonesuch

『6歳のボクが、大人になるまで。』でイーサン・ホークが幼い息子に「この詞を聞け」と『Sky Blue Sky』の「Hate It Here」をかけるシーンがある(そう、ウィルコは最良の「ダッド・ロック・バンド」でもある)。とはいえ、日本語話者にとってジェフ・トゥイーディーのリリックのおもしろさは、なかなか理解しづらい。というわけで、この機会に彼の詞を読んでみよう。「ウィルコはきみを愛する」と突然自己言及する、冗談めかした「Wilco (the Song)」。「片翼では飛べない/あなたもわたしも/さようならと手を振ることしかできない」と「One Wing」は痛切だ。ファイストとデュエットした「You and I」は一聴、ボブ・ディラン風の穏やかなフォーク・ロックだが、「あなたとわたし/他人どうしみたい/どれだけ近づいても/会ったことのない人どうしのよう」「あなたのすべてを/知りたくもないし/知る必要もない」という両義的なラブ・ソング。「You Never Know」は、「どの世代も『これが世界の終わりだ』なんて考えたんだ」とシニカル。そして、「Country Dissapeared」の一節――「夜寒があなたをシャンデリアのように揺らすとき/雪のひとひらが大気を通り抜け/競売人の青い吐息に溶けて消えた」は、このアルバムでもっとも感動的なラインだろう。音楽的な志向性は、どちらかといえばオーセンティック。けれども、ネルス・クラインの存在感はやはり大きく、ジョージ・ハリスンやザ・バーズへのストレートな敬愛をのぞかせながら、自由闊達なプレイをする(かわいらしいクラウトロックの「Bull Black Nova」の後半は彼の独壇場だ)。グレン・コッチェの奇妙なパーカッションや、魔術師のようにさまざまな鍵盤を操るパット・サンソンの演奏も聞き逃してはならない。『Sky Blue Sky』と『The Whole Love』という二つの傑作の狭間にあるアルバムといえど、この親しみやすさやメロディの輝きに潜む実験とトゥイーディーの詩情にもう一度注目してほしいと思う。(天野龍太郎)
『The Whole Love』
2011年 / dBpm

「ウィルコらしさが詰まっている」、そんな曖昧なワードからは静かにはみ出していく。一見シンプルな曲の奥底で細やかに重なり鳴っているのは、過去作で見せてきた振り幅の大きさをそのまま反映したような様々なスタイルの音楽だ。ビートルズ、ノイズ、ソウル、クラウト・ロックなどなど、今まで参照してきた要素を6人が丁寧にたどり直している。幅の広さから考えると「ウィルコらしさ」なんて彼ら自身もとても定義できない。でもバンドはあえて曖昧さを残して「ウィルコ」の音楽全体を客観的に参照することで、新たに自分たちのルーツ・ミュージックを捉え直した。それは原点回帰とも集大成とも違うとても知的な作業で、アメリカのロックを背負って90年代から00年代を生き延びた自信を持つ彼らでなければ選べないやり方だ。特にアルバム全体の印象を決定づけているのはラストの長尺バラッド「One Sunday Morning」に至るフォーキーな後半3曲の流れ。霞んだような音像の中で、穏やかで繊細な演奏と共にジェフ・トゥイーディが朴訥と歌い綴るだけなのに、気づくと最後は地平線の見えるアメリカの原野に連れ出されたような感じで、「なんかスケール大きくなってないか」と驚かされた。ぐるりとひとまわり目が終わったウィルコの旅は、それでもまだまだ続いていく。(冨永啓仁)
『Star Wars』
2015年 / dBpm / ANTI-

オープニングを飾る「EKG」の不協和音のフレーズ、「Random Name Generator」のファズの歪み、そういったザラつき、まるでパンクのように荒々しく聴こえるサウンドがウィルコの中でも際立つアルバムが本作だ。ただし、この荒々しさは解放という言葉に置き換えることができるかもしれない。オルタナ・カントリー、ダッド・ロック、そういった言葉に定義されてきた彼らが、改めて自身を振り返りながら、それまでには無かったサウンドを表出させたからだ。本作がリリースされた2015年、彼らは楽器専門サイト《Reverb》で自身のページをオープンし数々のレコーディングで使用した機材の販売を開始。過去のサウンドを構築した機材について積極的にオープンにしたこと、本作が期間限定でフリーダウンロード・リリースされたことは、本作の解放ともリンクするように思えた。「Random Name Generator」のタイトルから分かる匿名性や「The Joke Explained」の歌詞で自らの存在について振り返る様子が描かれていることは、それまでにカテゴライズされたサウンドとは異なる方向性で、彼らが解放的に本作のサウンドに取り組んだことが反映されている。まるでソニック・ユースのようなパンクを彷彿とさせるサウンドは、ウィルコの“もう一つの”ルーツを感じるところでもある。(加藤孔紀)
『Schmilco』
2016年 / dBpm

僕たちは世界じゃない――「We Are The World」から30年あまり、その反語をジェフ・トゥイーディーが歌ったのは、“アメリカ”なるものが根底から揺らぐことになる選挙の数か月前だった。その曲、「We Aren’t The World (Safety Girl)」は軽快なカントリー・ポップだ。シャープなエレキによるロック・サウンドで攻めた『Star Wars』から一転、控えめなフォーク・ソングが並ぶこのアルバムの冒頭では「ずっと嫌いだった、ああいう普通のアメリカの子どもたちは」と吐露される。ここで言う“普通のアメリカ”は、どこかで“MAKE AMERICA GREAT AGAIN”と言うときの”アメリカ”と重なっているだろう。“アメリカ”の伝統をたしかに引き継ぎながらも、伝統保守主義者に称揚される“アメリカ”を憎むこと――ここではオルタナティヴとして生きること、生きてきたことの困難と誇りが奥行きのある音響のフォーク・サウンドで差し出されており、そうした主題はのちのトゥイーディーのソロ作にも受け継がれていく。内省的で、とてもアンニュイなアルバムだ……“オルタナティヴ・カントリー”であることは、そもそも“アメリカ”に対する愛憎で引き裂かれることだからだ。だが、だからこそウィルコは普通には生きられないアメリカの子どもたちを解放してきたし、アメリカの外で生きる僕たちにも“オルタナティヴ”であることの勇気を示してくれた。彼らの静かな、しかしたしかな覚悟がここからは聴こえてくる。(木津毅)
『Ode To Joy』
2019年 / dBpm

『シュミルコ』以来、3年振り11作目のニュー・アルバムは、ここ数作と同じ自身のレーベル《dBpm》からのリリース(日本では今作はワーナー・ミュージック)。昨年から今年にかけてリリースされたジェフ・トゥイーディーのソロ2作と、ニュー・アルバムより先行公開された2曲(「Love Is Everywhere (Beware)」「Everyone Hides」)からある程度の方向性は予想されたが、全体的にフォーキーで歌とメロディに軸を置いた温もりのあるサウンドになっている。インプロ的な要素はやや後退し、一聴するとウィルコの作品のなかでは比較的地味な印象を持つかもしれないが、繰り返し聴くうちに、音のスペースを立体的に使ったサウンド・デザインと、ギター、ドラム、ピアノ、ハンドベルなど、それぞれの楽器1音1音の粒が満天の星空のように輝いていて、あっという間に引き込まれる。特にグレン・コッツェのドラムは、音数を極端に抑制しながらも、曲全体を包み込む大樹のような役割を担っていて、次第にウィルコの伝統と革新の音楽性が、いよいよここでひとつの完成形を見たという確信を持つようになった。
アルバム・タイトル『Ode To Joy』=“歓喜の歌”とあるように、全編を通して、愛を通じた至福の歌がひとつのテーマとなっている。ただ、ジェフ自身が”愛が憎しみに勝っていると、自信を持って言えるほど自分はポジティブではない“と語るとおり、愛という、誰もが正しいと思わなくてはいけない、あるいはそうあるべきという、ある種聖域化された理想に対し疑問を投げかけることさえ許されない雰囲気や、暴力的な正義の押付けに、立ち止まってみようと警鐘を鳴らしているようだ。それは、まさに2002年に『Yankee Hotel Foxtrot』(YHF)がリリースされた時のアメリカの雰囲気に酷似している。そういった意味では、本作は、その『YHF』と対をなす作品といえないだろうか。
人は時に愚かだし、いつも理想と現実の間を、らせん階段のようにいったり来たりしている。だからこそ”You Have to Lose(War on War)”であらねばならないと『YHF』では歌っていた。本作では、”僕らは変われない(Bright Leaves)“、”誰も否定しない。心の奥に誰もが隠し事を抱えている(Everyone Hines)”といった人間が根源的に抱えるカルマのようなものを肯定しながらも、それでも懸命に現実に立ち向かい、もがこうとするウィルコの今の姿がある。そして彼らが本作に込めた思いとは、先人たちのルーツを引き継ぎ、こうして伝えたいことをメロディに乗せて歌うという、フォーク・ミュージック本来の力なのではないだろうか。(キドウシンペイ)
■Wilco Official Site
https://wilcoworld.net/
■ワーナー・ミュージック・ジャパン内アーティストページ
https://wmg.jp/wilco/
関連記事
【REVIEW】
Various Artists『All of God’s Money / A Tribute To Wilco’s Yankee Hotel Foxtrot』〜20年近く経っても変わらない“You have to lose”の重要性
http://turntokyo.com/reviews/all-of-gods-money-a-tribute-to-wilcos-yankee-hotel-foxtrot/
Text By Shuta NishidaRyutaro AmanoYoshihito TominagaYasuo MuraoMasaya MifuneTakuro OkadaTsuyoshi KizuShino OkamuraNami IgusaKoki KatoSinpei Kido
