幸福と解放の使者、全能性サイケデリック・スターの歩み
〜ケミカル・ブラザーズ アルバム・ガイド〜
ケミカル・ブラザーズによる4年ぶりの新作『For That Beautiful Feeling』リリースから1ヶ月以上が経った。1989年にマンチェスター大学で出会い、ダスト・ブラザーズ名義で活動を始めた彼ら。前作『No Geography』の時点で結成30周年を迎え、すっかり大ベテランの域に達している。今回のアルバムはそんな円熟味も確かにあるものの、サウンドに衰えは見られないし、エッジも効きまくっている。そもそも90年代に数おおく登場した、ダンスフロアとメインストリーム・ポップを行き来する存在の中でも、いまだコンスタントに優れた新作を出し続けているその存在の希少さを思えば、彼らのクリエイティヴィティやタフネスが伺えるだろう。
とはいえケムズほどのキャリアとなると、そのリスナー層も毎度の新作ごとに幅が狭まっている可能性は否めない。また、彼らの音楽的ルーツや作品ごとのサウンドの変化についても、いまから全てを聴いて確かめていくことに難しさを感じているリスナーも多いかもしれない。そこでケミカル・ブラザーズのオリジナル・アルバム、計10枚を短評とともに総ざらい。来年2月には《東京ガーデンシアター》にて、5年ぶりの来日公演も行われる。いま、彼らが映し出してきた終わらぬ愛の夏を振り返ろう。
(ディスク・ガイド原稿/岡村詩野、尾野泰幸、Casanova.S、坂本哲哉、佐藤遥、高久大輝、髙橋翔哉、田中亮太、吉澤奈々)
『Exit Planet Dust』
1995年 / Universal Music
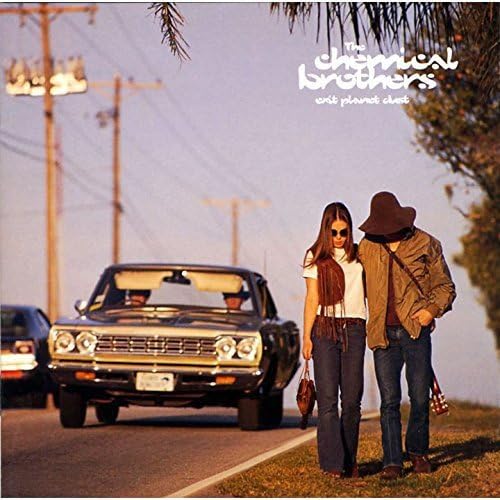
まずはここから。ケミカル・ブラザーズの音楽はそもそも、ヒップホップとアシッド・ハウスとサイケデリアの融合から始まった。つまり、セカンド・サマー・オブ・ラブ、マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン、ビースティ・ボーイズ……などなど、90年代前半という時代の空気をたっぷり吸い込んで生まれたスタイルだ。サンプルをガシガシ継ぎ接ぎしたヒップホップ的なビート、レイヴ的なサイレンが聴かれる「Song To The Siren」。バキバキのアシッド・ハウス「Chemical Beats」に超サイケデリックなトリップ・ホップ「One Too Many Mornings」と、のちの手札の雛形になるアイディアを惜しみなく出し揃えているのがこのファーストだ。一見バラバラにも見えるこれらのアイディアを貫き通しているのは、同年の電気グルーヴ『ORANGE』や映画『トレインスポッティング』にも通ずる、怒りと刹那の反照たるレイヴ音楽からの影響だろうか。どっしりしたブレイクビーツにロック的で骨太なベース、けたたましい上モノが渾然一体となって、90年代前半のシューゲイザー〜トリップ・ホップ的な音楽シーンの陰鬱なムードを「おらおらおらおら!」と一点喝破した強烈にアッパーな49分間。前年のオアシス1stのひたすらな全能感と比較してもいいかもしれない。そのオアシスのノエル・ギャラガーらを招き「メディア化」していく次作に比べて、これはまだ芽の段階。まだ何物でもない、“ビッグ・ビート”なるタームすら生まれる以前のストロング・ミュージック。これも夏の事件だった。(髙橋翔哉)
『Dig Your Own Hole』
1997年 / Universal Music

発表当時、彼らのリスナーにレイヴァーやクラバーがどれだけいたのかはわからないが、少なくともトム・ローランズとエド・シモンズの2人は一夜の可能性に賭けていたのだろう。前作で成功を収めたケミカル・ブラザーズがロックとダンス・ミュージックを繋いでいたのは事実として、彼らはそれで満足してはいなかった。
『Dig Your Own Hole』にノエル・ギャラガーが参加していたり、クール・ハークが(サンプリングで)登場したりするのは象徴的だが、さらにケムズは、ときにロックを置き去りにし、ときにエレクトロニック・プロダクションの鎖を外す。「Don’t Stop The Rock」を完全にダンスフロア向けのフォーオンザフロアに仕上げ、「Elektrobank」にセッション・ドラマーのサイモン・フィリップスを起用したことはそのわかりやすい例だろう。そうしていくつもの境界線を跨ぐことで、本作は「ロックは首が振れて、テクノは踊れる」といった安易なフレーミングを拒み、すべてを巻き込むように激しく、美しく、溌剌と進んでいく。ギャングスタ・ラップのパイオニア的存在、スクーリー・Dの「Gucci Again」をサンプルしたヒット曲「Block Rockin’ Beats」から、朝方のダンスフロアに射しこむ光のようなベス・オートン参加の「Where Do I Begin」、そして9分越えのサイケデリックなアンセムにして最後のトラック「The Private Psychedelic Reel」まで、様々なジャンルを横断する野心に溢れた一作。(高久大輝)
『Surrender』
1999年 / Universal Music

前2作に比べると、やや散漫な印象の作品ではある。デュオのB-BOYイムズを映していたブレイキンな感覚は少し後退。ロック・マスター・スコットをモロ使いした「Hey Boy Hey Girl」などでエレクトロ魂を提示する一方、バーナード・サムナーとボビー・ギレスピーを招いてハシエンダ・マナーのヴォーカル・ハウスに挑んだ「Out Of Control」など4つ打ち曲の存在感も強い。そしてノエル・ギャラガーは前作に引き続き登板し、ソング・オリエンテッドなサイケ・ロック「Let Forever Be」を朗々と歌っている。手を広げすぎた感のあるサウンドがチージーに響く瞬間はあるものの、ダンス・カルチャーがミレニアムの狂騒へと向かっていた時代において、ビッグ・アクトとしての立ち位置を引き受けたことを示した一枚とは言えるだろう。だが、それをふまえて、このジャケットだ。ほかの全員がまったりしているなか、1人の男だけが立ち、天に腕を掲げ、溢れ出てくるエクスタシーを身体全体で表そうとしている。このケイト・ギブによるイラストは、76年にロンドンで開催された《Olympia Music Festival》での一幕を撮影したリチャード・ヤングの写真をベースにしたもの。それは、ケムズの音楽が大観衆を一斉に盛り上げつつ、同時に受け手1人1人の内部にサイケな感覚を喚起するものであることを表していよう。名曲「The Sunshine Underground」は、いまも僕にこう語りかけてくる。かつてないほど音と光をリアルに感じられ、世界のすべてを把握できているように思える瞬間――それは誰にも侵すことのできない、君1人だけの神聖な体験であると。(田中亮太)
『Come with Us』
2002年 / Universal Music

何といっても重要曲は「It Began In Afrika」だろう。トライバルなこの曲のバックグラウンドには、1988年にノーマン・クックがThe Urban All Stars.名義で発表したカットアップ作品「It Began In Africa」があり、さらにその元ネタは1974年にジム・イングラムが発表したスポークン・ワード・アルバム『Drumbeat』のタイトル曲の冒頭部分──“それはアフリカで始まった”というセリフだ。イングラムは1967年のデトロイト暴動で白人警官に逮捕された黒人の一人。ノーマン・クックはそうした歴史的背景を知った上でこの曲をサンプリングしたのだろうが、ケミカル・ブラザーズに至ってはここで“Afrika-ka-ka…”と語尾をループさせて波及効果を狙っている。そこにはアフリカの歴史への理解と敬意、繰り返される人種差別暴動に対する抗議のメッセージを孕んでいるように思えてならない。当初この曲のタイトルが「Electronic Battle Weapon 5」だったことからも一定の抗戦的な姿勢を持った曲だとわかる。ミシェル・ゴンドリー監督によるテクニカルで洒落たMVが話題になった「Star Guitar」もクールだし、人気の頂点にきていたタイミングとあってさすがにどの曲もいい。ファーストでも歌っていたベス・オートン、ザ・ヴァーヴを解散させたリチャード・アシュクロフトがヴォーカルで参加しているのも注目だが、それでも本作はこの1曲でトムとエドが十分信頼に足るユニットであることを伝えている。(岡村詩野)
『Push the Button』
2005年 / Universal Music

本作の革新的な試みにヒップホップへの接近、中東・ワールド・ミュージックの要素を取り入れたことがある。Q-Tipがゲスト参加した「Galvanize」のモロッコ楽器によるストリングスは、スタジオで埃をかぶっていたワールド・ミュージックのCDからインスピレーションを受けたそう。ラー・ディガ「Party & Bullshit」をサンプリングしたスパニッシュ・ギターとパーカッションの弾む「Shake Break Bounce」からも積極的なクロス・オーヴァーの姿勢が伺える。一方で、リード・シンガーを前面に出した作品でもある。メロディが前に出たぶんビッグ・ビートは頑強さを増し、ブレイク・ビーツの粗さも削られた。余白が増えたことで、過激なビートやグルーヴはより渦巻いているようだ。例えば、Anna Lynne-Williamsの気怠げな歌声と裏打ちのリズムが生み出す「Hold Tight London」のうねりはアシッド・ハウスの残響を感じさせる。ブロック・パーティーのケリー・オケレケが参加した「Believe」のストレートなリリックに合わせる四つ打ち。「Marvo Ging」はザ・ストーン・ローゼスを彷彿とさせる逆回転を使用するなど、幻想的な展開を見せる。もしかしたら本作の本質はローランズとシモンズがクラブでDJをしていた頃やマンチェスターの音楽シーンに対する愛情にあるのかもしれない。彼らの柔軟性に富んだアルバムの一つ。(吉澤奈々)
『We Are the Night』
2007年 / Universal Music

夜空へ宇宙へ、どこまでも突き抜けて飛翔し、視界は次々に開けていく。そんなこのアルバムを聴いて、正反対とも言えるだろう、約半年後にリリースされるブリアル『Untrue』のことを考えずにはいられなかった。アシッド・ハウスというレイヴ・カルチャーの一端をロックやヒップホップと融合させてきた彼ら。パーティードラッグがないだけに、もたらされるのは破壊的な享楽ではなく、どちらかと言えば健康的な興奮。リトル・バーリーのギター、バーリー・カドガン、プライマル・スクリームのキーボーディスト、マーティン・ダフィーを迎え幅の広がった器楽編成や、クラクソンズを始め前作に引き続き多彩なゲストを招聘していることは、ポップ・アーティストであることを引き受けた作品のようにも思える。彼らのアルバムの中でも飛び抜けてハイな本作の多幸感と陶酔感は、たとえば「Battle Scars」でのウィリー・メイソンの藍色の歌声を輝かせる星の瞬きのようなピアノ、「The Pills Won’t Help You Now」の寝転がり回転する星座を眺めているような気分を呼び起こすシンセなどダフィーによるところもあるだろうし、レイヴ・カルチャーのかすかな残像なのかもしれない。本作は彼らの2000年代最後のアルバムで、ブリアル以降、レイヴの亡霊が漂う2010年代へと時代は進む。(佐藤遥)
『Further』
2010年 / Universal Music

ベスト盤『Brotherhood』(2008年)を発表後、自分たちの美学とダンス・フロアを見つめるようにライヴ・セットを意識して制作された本作。ゲスト・ヴォーカルの参加はなく収録曲すべてに映像が作られており、デビュー時からライヴ・ビジュアルを担当するアダム・スミス、マーカス・ライアルとの強力なコラボレーション作品と言えるだろう。アルバム全体を通して、センチメンタルな物語のように波のあるサイケデリアが拡大している。フィルターの音色をうっすら変化させながら構築していく「Escape Velocity」をはじめ、ノスタルジックなシンセ・リフを反復させる「Another World」など、終始心地よい揺動を作り出す。中でも、イントロから美しく軋んだシンセ・リードで始まる「Swoon」。ブレイクで突如響き出すブレイク・ビーツの開放的な高鳴り、緻密なベースラインとダンス・ミュージックへの没入を促すようだ。ほかにも、<恋に落ちることだけは忘れないで/他には何もない>というロマンティックなフックも印象的。本作の柔らかくファズの効いた音色、浮遊するグルーヴはドリーム・ポップ〜シューゲイズに通じるものがある。とはいえ過激にビートを鳴らすM5「Horse Power」などケミカルらしいダンス・チューンもありバランスの良い作品。また、名前が大きくなり過ぎてややマンネリが囁かれていた評価をも吹き飛ばす快作だ。(吉澤奈々)
『Born in the Echoes』
2015年 / Universal Music
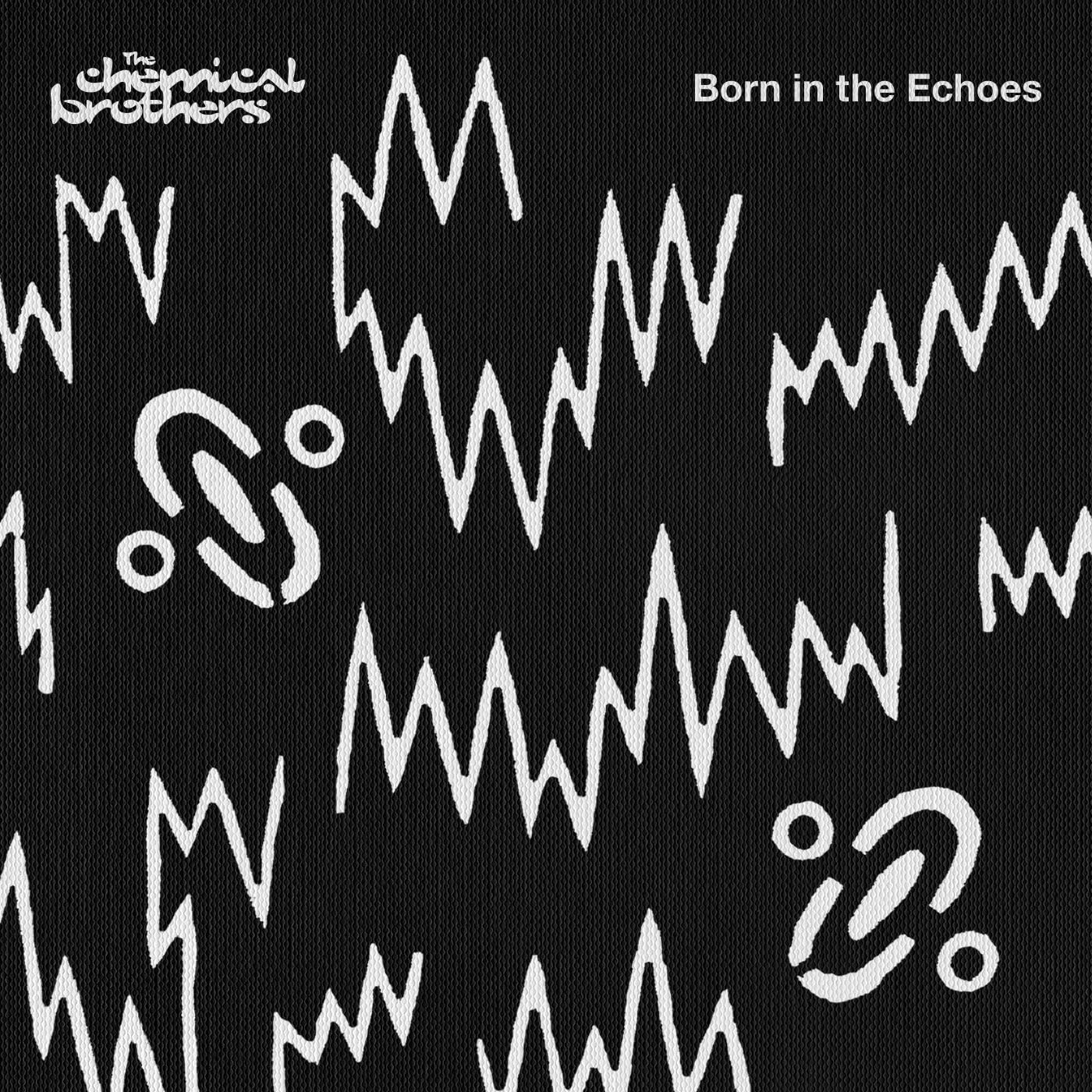
インディー・ロックに軸足を強くおいた僕のようなリスナーにとって、ケミカル・ブラザーズを最初に聞くきっかけになるのは、本作『Born In The Echoes』にセイント・ヴィンセントやケイト・ル・ボン、あるいはベックが参加しているというような側面があるのが大きいのではないだろうか? 『Born In The Echoes』の10年前、2005年の『Push The Button』ではブロック・パーティーのケリー・オケレケが、さらにその8年前、97年のセカンド・アルバム『Dig Your Own Hole』にはもちろんノエル・ギャラガーの存在がある。2023年の今、ざっくりとしたこの10年ごとのタームを振り返るとケミカル・ブラザーズが自分たちの音楽に混ぜるべきだと判断した要素がいかに優れていたのかわかるだろう。ただ単にその時代の流行りに乗ったわけではない確かな審美眼がそこにはあり、異なったフィールドの大きな部分とそれよりも小さな部分をあわせ一つの世界に色を交えて変えていくのだ。今、こうやって『Born In The Echoes』を聞いていてもさりげないフレーズにギターバンドの息吹を感じ、そうして胸が高鳴っていくのを感じる。タイトル・トラックから「Radiate」、そしてベックが参加した「Wide Open」へと続くサイケデリアの流れに身を委ねれば、このままどこまでもいけるとそんな錯覚を抱いてしまうくらい強烈な多幸感に満ちている。(Casanova.S)
『No Geography』
2019年 / Universal Music

トム・ローランズとエド・シモンズの2人は今、レイヴ・ミュージックを鳴らすことをどのように捉えているのであろう。不安定な現実を生き抜くために必要な逃避なのか。あるいは、社会変革への渇望を投影するものなのか。わたしは後者であると思う。というか、彼らのサウンドの特徴である、制御されたカオスと歪んだサイケデリアを自在に行き来するトリップ感に、レイヴ・ミュージックの躍動感のあるリズムを大胆に放り込んだこの『No Geography』を改めて聴いていると、そう思わずにはいられないのだ。例えば、アシッド・ハウスとディスコ・パンクを巧妙に接続させた「Eve Of Destruction」(ゆるふわギャングのNENEによる「ぶっ壊したい 何もかも」という叫びも印象的)やローランドTB-303の破壊的なスケルチ・サウンドが唸りをあげる「MAH」は分断化が加速する世界への怒りを表現しているようだし、『Dig Your Own Hole』の頃を思い起こさせるブレイクビーツにきらびやかなシンセが溶け合うタイトル曲や、ノルウェー出身のシンガー・ソングライター、オーロラの厚みのあるヴォーカルと昂揚感を煽るシンセが複雑に絡む「The Universe Sent Me」は、我々が繋がることを強く肯定してくれる。そう、彼らが自身のルーツであるレイヴ・カルチャーに立ち返ったのは、そこに現実と向き合う力が潜んでいることを伝えるためだったのである。(坂本哲哉)
『For That Beautiful Feeling』
2023年 / Universal Music

『Come With Us』を思い出させるアルバムと言えようか。つまり、ケムズ流の中音域ドカドカのロック的サウンドではなく音数を絞った仕上がり、ドラッギーだがとりわけポップ。キャリア初期に顕著だった、暴力的なキック&スネアや図太いベースラインはここにはない。しかし、2000年代の迂回──サイケデリアや、大文字のポップ/スタジアム・ロックの代替物としてのダンス・ミュージック──を経た近年のケムズは、かつてとは異なる形で自身の音楽を定義づけている。つまり、少ない音数でサウンドの際立ちを強調することで、ただダンスにのみ奉仕していく……。曲間をなくし、前のめりに次の曲へ雪崩れ込んでいくアルバム構成は前作『No Geography』から引き続いている。そんな中でもドープで多幸感あふれるハウス・チューン「Live Again」や、ボトムの効いたビッグ・ビートにディスコ的なカッティング・ギターが乗る「Fountains」など、際立った曲もある。しかし最高潮にハッピーな瞬間が連続的に繋がれていく展開は朝方のフロアを思わせるように、明確なピークもテーゼも提出されることもないがひたすら快調な47分間。LPだとB面にあたる8曲目「Skipping Like A Stone」以降の、アヴァランチーズやかつてのチック・チック・チックばりのドロドロで極彩色なサイケデリアも確かに捨てがたい。しかしもっと素晴らしいのはA面だ。ミニマルに引き締まったビート、大きく取られた余白に突き刺されるヴォイス・サンプル。これで踊らずして何で踊ろう。(髙橋翔哉)
Text By Haruka SatoShoya TakahashiNana YoshizawaCasanova.SRyota TanakaShino OkamuraDaiki TakakuTetsuya SakamotoYasuyuki Ono

【来日ツアー情報】
「For that beautiful feeling tour 2024 LIVE IN TOKYO」
2月2日(金)東京 ガーデンシアター
2月3日(土)東京 ガーデンシアター SOLD OUT
詳細は以下から
https://smash-jpn.com/chemicalbrothers2024/
