ベックは音楽の歴史そのものだ! 『メロウ・ゴールド』から新作『カラーズ』まで――ベックのオリジナル・アルバム・ガイドで来日予習!
グレッグ・カースティンがプロデュースを手掛けたニュー・アルバム『カラーズ』は、ベックがアメリカの音楽の歴史の中で最も重要な……いや、世界規模であらゆる国の新旧大衆音楽の位置付けを見直し、それをアップデイトすることができる音楽家であることを改めて証明した大傑作だ。というよりも、ベック自身が再定義されたポップ・ミュージックの歴史そのものと言っていいかもしれない。極端に言えば、この人の全ての作品を聴けば、大衆音楽の歴史が一望でき、規定し直された新たな解釈も堪能できる……縦軸も横軸も、あるいは斜めに伸びていくいたずらな動線も、点も線も面も、それらを恣意的に組み立てた立体も、全てベックという男のクリエイティヴィティに複合されていくことに気づくはずだ。そこにあるのは彼自身が自身の活動の中で証左としてきた紛れもない事実と、それでもそこに繰り返し疑問を投げかけるクリティカルな目線である、ということに。
そこで、来日公演を間近に控えたそんなベックのオリジナル・アルバム・ディスコグラフィーをTURN執筆陣総結集で作成してみた。新作『カラーズ』は3人によるクロス・レビューでお届けする。ぜひ今一度、彼こそが歴史であるとするかのような足跡を味わってほしい。
Beck Original Album Disc Guide
『Mellow Gold』(1994年)

ベックはとてもアメリカ的な作家だ。だが、それはトランプが言うような“アメリカ”ではない。様々な地域たちから集まった移民たちの手によって作られた、複雑で多層的な文化圏。それを体現する意味でのアメリカだ。『メロウ・ゴールド』は、『オディレイ』以降、ポップス・サイドとシンガソングライター・サイドにデフォルメ的に分かれていく彼のディスコグラフィーの、言わば前史とも言える作品で、アンダーグラウンドな音楽シーンの寵児だった頃の面影を強く残している。そんな中で、いま聴いて最も興味深い曲の一つが、彼のビートニク志向における大先輩、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド風のアレンジが施された最終曲「Blackhole / Analog Odyssey」。しばしば、そのブルース趣味ばかりが強調される初期ベックだが、この曲のメロディは、むしろアイルランド的。どことなく、レッドベリーの歌唱で知られ、アパラチア~アイルランド民謡にルーツを持つと言われる「Where Did You Sleep Last Night?(In the Pines)」を思わせもする。そう、レッドベリーの時代から、アメリカ音楽のルートは、アフリカにヨーロッパに強く絡み合っている。『メロウ・ゴールド』=“芳醇な黄金”というタイトルはジャンクな作風と掛けた皮肉の利いた言葉遊びのつもりだったのかも知れないが、アメリカ音楽の深遠を(図らずも)体現していたという意味で、今では全く真っ当なタイトルに聞こえるのだ。(坂内優太)
Lead Belly – Where Did You Sleep Last Night? (1944) (TRUE STEREO)
『One Foot In The Grave』(1994年)

思い余って戦前ブルーズをやっちゃいました的な1曲目「He’s A Mighty Good Leader」。これはカントリー・ブルーズマンのスキップ・ジェイムスの曲を元にしたもので、本作には他にもカーター・ファミリーやフレッド・マクダウェルで知られる曲を改題したものも含まれている。もちろんオリジナル曲が中心だが、ギター奏法も声の出し方もまだ独自の境地には至っておらずなんとも青い。だが、全ての曲においてブルーズ、カントリー、アパラチアン・フォークなどを採取してみせたハリー・スミスの仕事を実践しようとするような真摯な眼差しに包まれていて、ベックのどのアルバムでも必ず本作が隣に置かれることを前提としたような、常に本作こそがベック自身のリファレンスとなるようにと作られていることには年々驚かされる。つまり、ベックは自分自身で、『Anthology Of American Folk』に相当する参照点を最初の段階で作っていた。そして、自身の活動がいかなるスタイルへと発展しようとも、あるいは先へ先へと枝葉が伸びていったとしても、常にこのアルバムが大きな意味を持つであろうことを想定していたのではないかと思う。本作を起点にした新たなる歴史の再定義を最初から視野に入れた活動をしていたということを、このアルバムの存在が折に触れて証明していっているのだ。
いまさら説明するまでもないが、ジャケットの左側に映る男はキャルヴィン・ジョンソン。他にもそのK~サブ・ポップ周辺のアーティストが多数参加していることからUSインディー好きには今も愛される1枚ではある。けれど、そんなことより重要なファクターがこのアルバムには与えられていることを、私たちは今一度知るべきだろう。(岡村詩野)
Skip James – He’s a Mighty Good Leader
『Odelay』(1996年)
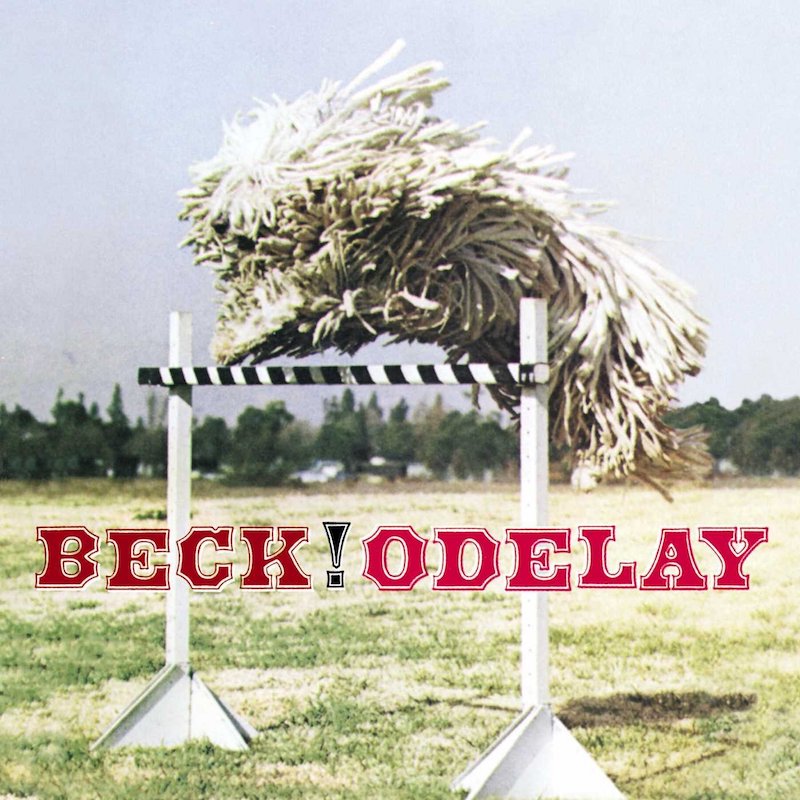
この90年代を代表する作品が、コラージュ・アートであることは勿論、ヒップホップが意識されていることを改めて言う必要はないだろうが、その核心は、サンプルやフレーズの“反復の悦び”にあるのではないだろうか。特にベックが少年時代を過ごした80年代のLAのダウンタウンでは、ティーンがこぞってラップをしリフを作って遊んでいた、という体験は彼の身体に染み付いているはず。だから、本作ではリズム・トラックはもとより、ギターのフレーズもメロディが強烈に残るヴァースも、その多くが1曲のうちにしつこく反復される。
『オディレイ』のリリースとほぼ時を同じくしてピークに達したギャングスタ・ラップは、その過激さを競い合っていた。ベックは、既存曲のブレイクを繰り返し繋げることで生まれたヒップホップの原点である反復の快楽を、身体性の高いタフなビートが得意なランDMCやビースティー・ボーイズをモデルに、本作に呼び戻したものと言える。ただ本作は、例えば「Hot Wax」の冒頭のようにブルーズ、あるいはカントリー調のフレーズが多く用いられロック作品として成立していることも重要だ。もう進化しないと言われたロックに、延々とフレーズが反復し楽曲がなかなか“先へ進まない”心地よさ、という発想の転換を持ち込んだことが、本作の大きな功績だ。(井草七海)
RUN-DMC – My Adidas
『Mutations』(1998年)

「アメリカ人は過去と競争して、より輝いている新型ヴァージョンを作る。文化が記憶される時間は恐ろしく短い。でも、ぼくの曲はこの土地を彷徨いながら……何かしらルーツや本質的なものとつながろうとしているんだ」。
ローファイ、フォークといった、自身のルーツが色濃く投射されている本作に関し、ベックはこのように語った。トラディショナルにも思えるフォーク・サウンドが鳴り響く本作は、しかし、単なるルーツ・ミュージック然とした作品であるだけではない。本作で顔を出したベックのエモーショナルな歌声にも表れる、カウンター・マインド的側面が、本作の大きな特徴となっているのだ。
それを端的に示すのが、本作に収められた、ボサノヴァ・ライクな「Tropicalia」であろう。本曲には、その名が示すように60年代後半にカエターノ・ヴェローゾらが起こした芸術運動《トロピカリア》に対する、ベックのシンパシーが垣間見える。同作品のコンセプトはブラジル音楽の伝統性の継承、並びにロックをはじめとする多種多様な音楽との融合からなるユニバーサルな音楽を通じ、軍事政権独裁下におけるブラジルの保守的価値観や既成の規律に対する抵抗を試みることであった。
そのような、作品的背景と冒頭のベックの言葉を鑑みれば、「Tropicalia」で植民地支配や貧困という絶望と、そこから這い出すための一筋の光を陽気なリズムに乗せて、気丈に歌い上げるベックのまなざしは、60年代のブラジルへ向けられているのみならず、ルーツに対する希薄な意識に包まれた90年代後半当時のアメリカをも貫いている。
そのように、ルーツへの深い敬意と、カウンターというコンセプトを含む本作を、当時『ミューテイションズ』(突然変異)と名付けた、いや名付けざるを得なかったベックの意思は、2017年を生きる私たちにも向けられているのだ。(尾野泰幸)
Gal Costa – Baby / Inclusão: Diana
『Midnite Vultures』(1999年)

確かに本作はベック史上最もまがまがしく、そして最も踊ることのできるアルバムだ。ソウルやR&B、ファンクを根底にし、ヒップホップやエレクトロ、テクノをコラージュさせながら、まるで自らがダンス・ミュージックの歴史を継承していくと宣言するがの如く、猥雑なパーティー・ミュージックを展開していく。だが、それと同時に彼が表明したかったのは、優れたダンス・ミュージックには優れた歌があるということではないだろうか。例えば『オディレイ』が自らの声をサウンドの一部としてある種の楽器のように扱っていたのに対して、続く『ミューテーションズ』が歌そのものを大切にする構成になっているが、本作は『ミューテーションズ』で歌と真摯に向かい合ったからこそ出来上がったのである。だからこそ彼は本作でプリンスを模倣し、咀嚼し、再構築しようとした。それが最も顕著に表れているのが、クライマックスを飾る「Debra」である。ここでのゆったりとしたファンク・ビートとそれを彩るホーン、そしてそのビートに乗る彼のファルセット・ヴォイスは肉感的で卑猥さすら感じさせる。このスマートでスウィートでセクシーな曲があったからこそ、このアルバムはただのばかばかしいパーティー・ミュージックでは終わらなかったのだ。(坂本哲哉)
Prince – Scandalous
『She Change』(2002年)

“アフター・グランジの時代”のアイコンという重責を引き受けることで少しずつ引き裂かれていったベックがその役割を降り、一度深く深く自分の中へ潜ることで遂に光を見出したアルバム、それがこの『シー・チェンジ』だ。
一聴してシンプルでフォーキーな耳障りに“ルーツ回帰”と思うのは誤りだ。凛としたギターの弦の鳴り、流麗でエモーショナルなストリングス、全てが驚異的なまでに研ぎ澄まされたコズミックなサウンド・テクスチャーは、伝統的なシンガーソングライターとしてのベックと編集能力に長けたイノベーターとしてのベックが初めて、そして遂に完璧に同居した初のアルバムでもある。
楽曲の礎となるのは彼のアイデンティティの一つでもある戦前のフォーク/ブルーズというよりはむしろ、カントリーにロックとソウルを融合した”コズミック・アメリカン・ミュージック”(あるいはカントリー・ロック)の創始者、グラム・パーソンズのソングライティング。そこにナイジェル・ゴッドリッチの手により施されたモダンかつ極めて精緻な装飾が楽曲の魅力を存分に引き立てている。ぜひ3曲目「Guess I’m Doing Fine」から6曲目「End Of The Day」までの極上の流れに身を任せ、その魅力を堪能してみることを薦めたい。
そしてベックの独特で魅力的なダミ声で歌われるモチーフは“過去と現在”、そして“喪失と忘却”について。自分の内面を噛み締めて産み落とした言葉の欠片はあなたの心に突き刺さるに違いない。ベックが描いた痛みを伴った心象風景を一番的確に表す言葉は件のグラム・パーソンズがすぐに退学することになるハーバード大学に入学した頃に妹に宛てた手紙にあるこの一節かもしれない。”人生が混乱し、逃げ場を失った人から学ぼう”。
ベックの諸作の中でも最もタイムレスな紛うことなき最高傑作。(定金啓吾)
Gram Parsons & The Flying Burrito Brothers – Wild Horses
『Guero』(2005年)

“グエロ”とは何か?それは、スペイン語で白人男児を指すスラングである。LAのヒスパニック地区にて、マイノリティの白人として育った、ベック自らの出自を指す言葉を題名とした本作で、何よりも目を向けなくてはならないのは、自らの人種的ルーツと向き合い、自らを通り抜けていった音楽を、再出発として鳴らす彼の姿に他ならない。
本作で、ベックはブルース、ロック・テイストの「Go It Alone」や「Black Tambourine」で虚ろに抑揚を落とし歌い上げる。さらに、ラップと、ビートが土台となる「Qué Onda Guero」「Hell Yes」といった曲群での気だるげなベックのラップには、白人として、ラップをするという必然的な諦念と決意がある。このように、一人の白人がブルースも、ソウルも、フォークも、ロックもすべてを飲みこみ、大きな表現的一歩を踏み出したという意味から言えば、本作はアル・クーパーとマイク・ブルームフィールドが果たした、あの『フィルモアの奇蹟』とも比類する作品であるといえようか。
自らと違う人種を、あえて自らは“よそ者”であると振り切り、それに擬態すること。それは、ミンストレル・ショウからロックンロール、そしてヒップホップまでを貫く、(アメリカの)ポピュラー音楽の歴史を形成してきた大きなモーメントでもある。フォークという自らのルーツを土台をしながらも、ブルース、ロック、ヒップホップ、ブラジル音楽などが混淆した本作の音を、“よそ者”として鳴らすことに向き合ったベックが生み出した本作は、やはり、《(アメリカの)ポピュラー音楽》の巨大な一側面を体現しているかのようだ。(尾野泰幸)
The Easy Rider Generation In Concert: The live Adventures of Mike Bloomfield & Al Kooper
『The Information』(2006年)
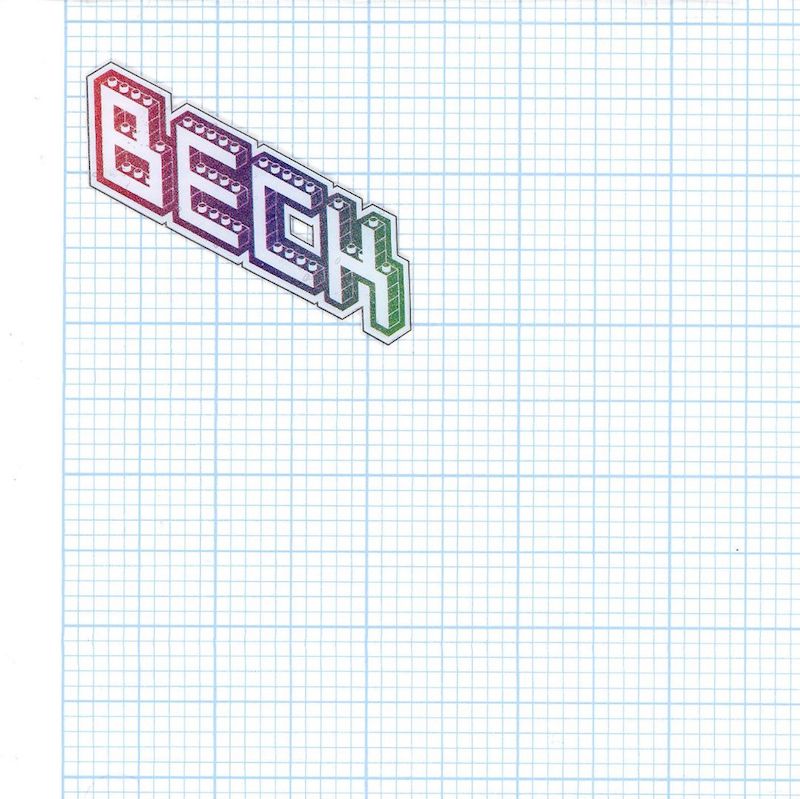
おそらく、LCDサウンドシステムあたりに触発されたのだろう。ベックのキャリア史上、最もニュー・ウェーブ色の強いアルバム。ナイジェル・ゴドリッチの手掛けたクリアな音質も、そのファンク・ビートの無機質な印象を強調している。多くの曲で、サビに分厚いコーラスが施されており、そのデフォルメされたアフリカンな響きは、ブライアン・イーノが手掛けたトーキング・ヘッズの『リメイン・イン・ライト』を思い出したりもする。その極め付けとも言えるのが、14曲目の「Movie Theme」で、こちらは同じくイーノが手掛けたデヴィッド・ボウイ作品、特に『ロウ』あたりのサウンドを思わせる(曲調は「Space Oddity」風だけど)。これらの先達がベック&ナイジェルにとって少年時代のヒーローであったことは想像に難くないが、そんな意識も作用したのか、『ザ・インフォメーション』はベックの作品群の中でも、ひときわ入り組んだアンサンブルが耳を引く。それは、現代のハイファイなロック・プロダクションにおける一つの極点を示しているとも言えるだろう。16曲という曲数の多さはiTunes時代を、全曲MV付きというアイデアはYouTube時代を見据え、必ずしもまとまりの良いアルバムではないが、今なおユニークな価値を放ち続けるエクストリームな一枚だ。(坂内優太)
David Bowie – Space Oddity
『Modern Guilt』(2008年)
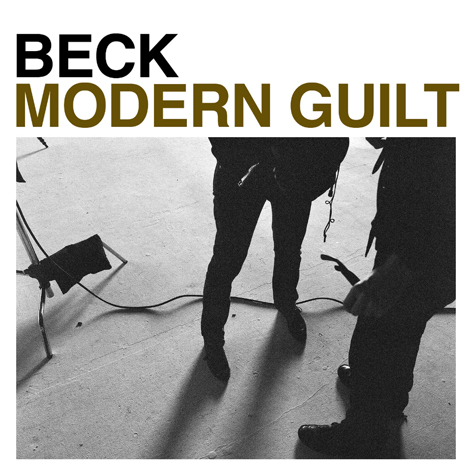
長髪にハット、さらにナンバーナインで身を包んだ当時のファッションは『All Things Must Pass』(1970年)時代のジョージ・ハリスンのようだが、後に「Wah-Wah」をカヴァーしていることからも、当時のベックはかつてなくビートリーな気分だったに違いない。
というわけで、全10曲30分台というキャリア史上最もコンパクトなアルバムが本作だ。それは引き算の美学というよりも、いかに最短距離でロックの純度を封じ込めるか? という自らへの挑戦。共同プロデューサーのデンジャー・マウスは、ビートルズの白盤とジェイ・Zの黒盤をPPAPして物議を醸した策士であり、その折衷感覚はフォークからファンク、ブルース、果てはヒップホップを横断してきたベックの頭の中と似ているのかも。
『モダン・ギルト』の通奏低音は60年代後半のサイケデリアだが、ドリルンベースを思わせる「Replica」を筆頭にビート・プログラミングの妙も光る。しかし、曲の基盤はあくまでもアコギだ。蜃気楼のような歌声は町から村へと旅する吟遊詩人みたいだし、南部を舞台にした「Orphans」はもはやデルタ・ブルースに聴こえる。あえてビートルズの曲を1つだけ挙げるならば、やはりジョージ作詞・作曲のコレでしょう。(上野功平)
The Beatles – While My Guitar Gently Weeps
『Morning Phase』(2014年)

脊髄の治療により6年のブランクが空いたものの、その間に彼はプロデュース業に専念しつつ、名盤丸ごとカヴァー企画《レコード・クラブ》を発足するなど、音楽家としての在り方を見つめ直す局面にあった。そこで道標となったのが、黒き巨星デヴィッド・ボウイである。
『シー・チェンジ』の姉妹編と噂された本作だが、もはや失恋の痛手を負った青年の姿はない。93年のカセット『Golden Feelings』以来となる完全セルフ・プロデュースということからも、手触りとしては米フォーク・ミュージックのルーツ、ひいてはベック自身のルーツを掘り下げるポジティヴなムードが漂う。その関係性からは、『ヒーローズ』(1977年)を換骨奪胎したジャケットと共に、鮮烈なカムバックを遂げたボウイの『ザ・ネクスト・デイ』(2013年)を連想するファンも少なくないだろう。
事実、ベックはボウイの「Sound and Vision」を150名以上のミュージシャンと共に再構築し、昨年のグラミー賞では元ニルヴァーナ組と一緒に“世界を売った男”をカヴァーしてもいる。そんな彼が、新作に『カラーズ』なんてタイトルを付けたのも、ボウイの遺作『ブラックスター』(2016年)に対するオマージュなのかな? と僕は妄想してしまうのだ。(上野功平)
David Bowie – Sound and vision (live by request)
Beck – Colors
LATEST ALBUM
『Colors』(2017年)

ベックはそのキャリアの中で(ポップ・ミュージック市場の前線で)“闘うこと”とそこから“降りること”を意識的に切り替えてきたアーティストだ。“闘うこと”を別の言葉で置き換えてみよう。それは“最も挑戦的で、最もイノベイティブで、同時に最も売れること、そして音楽で多くの人をユナイトさせること”だ。そしてベックは本作『カラーズ』でこれを成し遂げる予感を抱かせてくれる。この期待感から思い起こすのは、そう、やはりビートルズだろう。
『カラーズ』の中身に耳を傾けてみよう。ディスコのヴァイヴもある「Seventh Heaven」からサイケデリック・ロックな「Dear Life」、トラップの意匠を借りた「Wow」、ビッグなコーラスを持つ「Dreams」と音楽的なベクトルは実に豊かで、ある意味バラバラ。唯一共通しているのは、1曲目から最終曲まで徹底して素晴らしくキャッチーなメロディとカラフルで明るいヴァイヴを持つこと。プリンスからザ・カーズ、そしてザ・キンクスまで過去のポップ史の偉人たちの影響を聴き取れるのも楽しいが、先に挙げたビートルズとの比較で言うならば発売から50年が経つ今も色褪せることない金字塔『サージェント・ペパーズ』を挙げるのが妥当だろう。
レノン&マッカートニーのソングライターコンビの才能が爆発し、と同時に徹底したスタジオ・レコーディングの叡智と果てなき挑戦が結実した作品だ。ベックは今作でかつてのバンド・メイトであり、今やアデルからテイラー、シーアまで手がける超売れっ子プロデューサーのグレッグ・カースティンとのコンビでレノン&マッカートニーに比肩したと言いたくなるほどの珠玉の出来栄えだ。
それにしてもシングルにもなっている「Up All Night」の小気味良いギター・カッティングから産まれる高揚感は、’13年に世界を席巻し一大現象を生み出したファレル・ウィリアムスの「Happy」も思い起こさせてくれる。ひたすらに分裂が進む世界において、キャリアにして4半世紀近いベテランがこんなにもカラフルで瑞々しいポップ・アルバムで人々をひとつにする姿を、僕は見たい。(定金啓吾)
The Beatles – Lucy in the Sky with Diamonds
ファンキーなベースとバック・ビートを強調したリズム・セクションが鼓膜を打ち、アップテンポな楽曲が怒涛の如く駆け抜ける超ド級のポップ・アルバム。そしてダンス・アルバムだ。本作のベックは「踊る」ことに真っ向勝負を挑んでいる。シックのナイル・ロジャースらを招いたダフト・パンク『ランダム・アクセス・メモリーズ』(2013年)をも彷彿とする70~80年代にかけてのダンス・ミュージック風のそのビートに、つい動いてしまう身体が何よりもそのことを物語るだろう! とは言え本作はブラック・ミュージック風という訳ではない。スムースで複雑なコード・ワークには落とし込まず、ザ・ビートルズ、ザ・キンクスからブラーやオアシスといった人懐っこい英国ポップのようでもある、直球に紡いだコードとメロディはシンガロングにぴったり。だからこそ、アデルやリアム・ギャラガーも手掛けたグレッグ・カースティンとの共作なのだろう。本作のベックは“歌う”ことにもフルスイングだ。
ダンス・ミュージックやド王道メロディのポップスのように、時に大衆的とも揶揄されがちなタイプのフィールドの楽曲も積極的に肯定し、数多の音色を繰って万華鏡のようにアップデートしてみせるのがベック流。ローファイなキャリア初期とはサウンドとしては真逆の本作だが、そんな彼の本質は当時からやはり不変だ。(井草七海)
Daft Punk – Get Lucky (Full Video)
もしデヴィッド・バーンがこのベックの新作を聴いていたら、とりわけ、「No Distraction」を耳にしていたら、きっと猛烈に嫉妬するに違いない。バーンがブライアン・イーノと組んで夢想していたのは、こんな「No Distraction」みたいな曲を書きたいということではなかったのだろうか。軽やかでやや重心の低い、アフロビートからの影響を窺わせるホワイト・ファンクのビートと鋭利なギター・カッティングが刻むリズムに乗せて、ベックが伸びやかなヴォーカルを披露しながら曲は展開していくーーと緻密なサウンド・プロダクションではありながらもそこまで変哲のない曲のように思えるが、サビに突入したときに現れるメロディとヴォーカルの鮮やかな交錯によって、この曲はポップ・ソングとしての強度を持つのだ。この曲が示すように新作『カラーズ』でベックはヴォーカルを生かしつつも、モダンな音響感覚を背景とするプロダクションを得意とするグレッグ・カースティンと組み、ソングライティングとプロダクションを共存させながら、我々の心を掴み、ワクワクさせるような10曲のポップ・ソングを書いた。この野心溢れる10曲は、プロダクションばかりが重要視される今の風潮に対する、ベックなりのアンサーなのかもしれない。(坂本哲哉)
David Byrne – Once In A Lifetime [Live From Austin, TX]
Text By Shino OkamuraYuta SakauchiNami IgusaTetsuya SakamotoYasuyuki OnoKeigo SadakaneKohei Ueno
Hostess Club Presents…Beck
2017/10/23(月)東京・日本武道館
WITH VERY SPECIAL GUEST CORNELIUS
Open 17:30 / Start 18:20
※ゲストアクト決定につき、開演時間を18:20に変更させていただきます。出演予定時間は以下の通りとなります。予めご了承ください。
CORNELIUS 18:20~19:00
BECK 19:30~
Ticket:
アリーナスタンディング¥12,000(税込)
スタンドS席¥12,000(税込)
スタンドA席¥9,000(税込)SOLD OUT
2017/10/24(火)東京・新木場Studio Coast
Open 18:30 / Start 19:30
Ticket:
¥12,000(オールスタンディング・税込・1ドリンク別途)SOLD OUT
http://ynos.tv/hostessclub/schedule/2017-1023-1024.html
