創造的再生がもたらすパラダイム・シフト
〜Sault ディスク・ガイド〜
突然の登場からまだ3年程度。しかし作品は既に6枚を重ねた。当初は匿名性強いユニットという印象だったが、今や、クレオ・ソル(も準メンバーだが)、リトル・シムズ、マイケル・キワヌカらをプロデュースするインフローことディーン・ジョサイア・カヴァーが中心になって動かしていることも公になっている。ファンク、ソウル、ラテン・グルーヴ、ジャズ、ポスト・パンクなどの要素を複合したこのUKコレクティヴは、しかしながら、2019年にシングル「Don’t Waste My Time」と「We Are the Sun」という示唆的なタイトルの曲でデビューして以来、手法としての優れたミクスチャー・スタイルに終始するのではなく、人類最大の発見・発明の一つである“音楽”の立脚点を捉えるような作業を通底させてきた。もちろん、例えばミニー・リパートンが在籍したロータリー・コネクション、アリス・コルトレーン、ニューヨリカン・ソウル、ダニー・ハサウェイ、テリー・ライリー……といった様々な先達への圧倒的な知識、歴史的な流れや結びつきを理解していればこそ、だろう。ニューヨリカン・ソウルはロータリー・コネクション「I Am The Black Gold Of The Sun」を90年代にカヴァーしているが、インフローの頭の中にはこうした時代とエリアの越境によって起こる価値観の再定義が多く刻み込まれているはずだ。
コロナ禍に改めて露呈した体系的人種差別を2作に渡ってテーマとしたり、99日でネット上から引きあげることを明言して新作をリリースするなど、創造性と同列で放たれる不気味なトライが旋風を常に巻き起こしてきた。そして、起こる意図しない巨大なパラダイム・シフト……。ニュー・アルバム『Air』でさらにその先へと扉を開けたそんなSaultの作品を振り返ってみる。(編集部)
『5』
2019年 / Forever Living Originals

このアルバムを初めて聴いたとき、なんだか狐につままれたような感覚になったことを今でも覚えている。ロータリー・コネクションのようなサイケデリック・ソウル、ESGのような無邪気なディープ・ファンク、あるいはJ・ディラを思い起こさせる艶かしいヒップホップ・ビートやエリカ・バドゥを彷彿させる生々しいヴォーカル・ワーク、さらにはディスコ/ハウスのようなダンスを意識したサウンド・プロダクション──これほどまでに様々なサウンドを混在させているのに、なぜこんなにシンプルに聴こえるのだろうとなかなか納得することができなかったのだ。だが、そのシンプルなサウンドを折に触れて何度か聴きかえすうちに、不意に気づいたことがある。それはこのミステリアスなコレクティヴは、ベーシック・チャンネルがテクノで行ったことを、ソウル・ミュージックで行おうとしているのではないかということ。ベーシック・チャンネルはデトロイト・テクノ、レゲエ/ダブ、ミニマル・ミュージック、ノイズを整然と混淆させ、極限まで音を削ぎ落としたミニマル・ダブでテクノの風景を塗り替えたが、Saultのソリッドで端然としたソウル・サウンドはこのベーシック・チャンネルの美学を今に甦らせ、ソウルの新たな地平を切り開こうとしているように思えてくるのだ。本作の所々に散りばめられたレゲエ的なサウンド・デザインの背景には、リー・ペリーだけでなく、ベーシック・チャンネルもある、というのは筆者の深読みだろうか。(坂本哲哉)
『7』
2019年 / Forever Living Originals

5月のデビュー作『5』から僅か4ヶ月後の9月にリリースされた本作はそのスピード感からするに『5』のアウトテイク集という見方もできるだろう。『5』との明確な違いははっきり言ってインスト曲が収録されていないことくらいで、それ以外の要素はほとんど前作の延長線上にあると言っていい。ただ発表するタイミングがタイトルになっているとすれば、予想よりもこだわり過ぎたために遅れたリリースとなったのかもしれない。それくらい完成度の高い作品である。
ファンキーなループにソウルフルでときおり歪みリフレインするヴォーカル、生演奏とエレクトリックなサンプリング・ミュージックの間をジグザグと動き回るそのサウンドはSaultのシグネチャーと呼べそうだ。だが、ダンサブルで享楽的でスピリチュアルで、にも関わらず親しみ深いという掴み所のなさはそれを安易に許さない。裏を返せばその音はSaultの音であり、同時にSaultの音ではないということではなかろうか。「彼らは今、あなたを脅威とみなしている」「あなたが孤独になるのを見たくない/もう十分でしょう/あなたはとても美しい」。そんな風に歌う「Threats」のアウトロ、鍵を開ける音のようなサンプルについ背後を確認するが、そこには当然誰もいない。翌年の『Untitled』2作を聴いてからならばよりその意味が理解できるはずだ。当時のSaultの匿名性も相まって、世界中で意識せずとも聴こえるブラック・ミュージックがどこから来たものなのかを改めて考えたくなる快作である。Saultは扉を開く。あなたはどうする? (高久大輝)
『Untitled (Black Is) 』
2020年 / Forever Living Originals
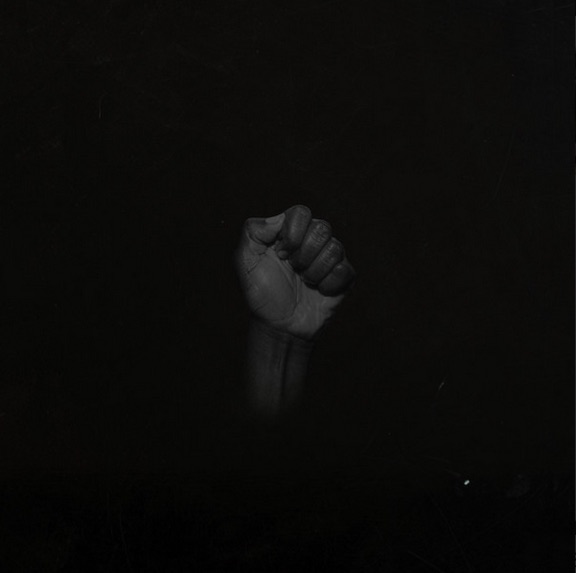
冒頭から「革命がやってきた/まだ銃を下ろさないのか」と子どもの声のようなサンプルが重なってリフレインする。アートワークは黒を基調とし、握りしめた拳が浮かび上がっている。本作がジョージ・フロイドの不当な死によってアメリカで再発火したブラック・ライヴス・マターに呼応していることは疑う余地がないだろう。つまりこれは警察による不当な暴力、システミックな人種差別に対する強力なプロテスト・アルバムである。
まるで生のバンド演奏かのような生々しく軽快な音とローファイで親密なサウンドを絶妙な匙加減でブレンドするSaultのスタイルは変わらないままに、これまで以上にアフリカンなリズムを盛り込んで届けられる、ファンク、ソウル、ジャズ、ヒップホップ(比重は少な目)、R&B。Saultがここで表現しているのは、一言で言えばブラック・ミュージックの歴史、となるのかもしれないが、もう少し正確に言えば、ブラック・ミュージックの豊かさである。あるいは、こう言い換えた方が良いかもしれない。黒人への差別がこれまでうんざりするほど繰り返されているにも関わらず、それに屈することなく鳴り響いてきた音楽の連なりをレプリゼントするものである、と。リリース時は現在よりミステリアスな要素の多かったSaultだが、本作でそのルーツやアイデンティティがはっきりした印象だ。怒りはいつも、その熱源にある大切なものを知らせている。(高久大輝)
『Untitled (Rise) 』
2020年 / Forever Living Originals

ブラック・パンサーのチャントでスタートして、ヘヴィーでタイトなグルーヴを軸にした『Untitled (Black Is)』の3ヶ月後に、突き上げた拳の代わりに祈る手が写し出された『Untitled(Rise)』はリリースされた。ここでは、80年代のディスコから、ソウル・II・ソウルやマッシヴ・アタックなどのUKソウル〜ブレイクビーツも参照され、Saultの出自が伺えるようなサウンドだった。とはいえ、決してレトロで融和的な音楽を奏でているわけではなく、どんな状況にあってもダンス・ミュージックの快楽を忘れないという決意表明であり、それこそがUKのダンス・カルチャーの伝統だと言わんばかりの姿勢は、「I Just Want to Dance」という曲によく表れている。
リリース当時はミステリアスな音楽集団だったが、いまではプロデューサーのインフローことディーン・ジョサイア・カヴァーを中心に、シンガーソングライターのクレオ・ソルらが関係したプロジェクトだったと知られている。本作はリリースからまだ2年も経っていないのだが、随分と前のリリースに感じた。誤解のないように申し添えておくと、Saultの音楽が古くなったと言いたいのではない。誰が作っているのかを問わない匿名性の高い音楽として特別な魅力を放ち、説得力を持った表現が、いまは作り手の顔が見えて、この音楽がブラック・ミュージックの優れたリプレゼンテーションとして聴こえているからだと思う。(原雅明)
『NINE』
2021年 / Forever Living Originals
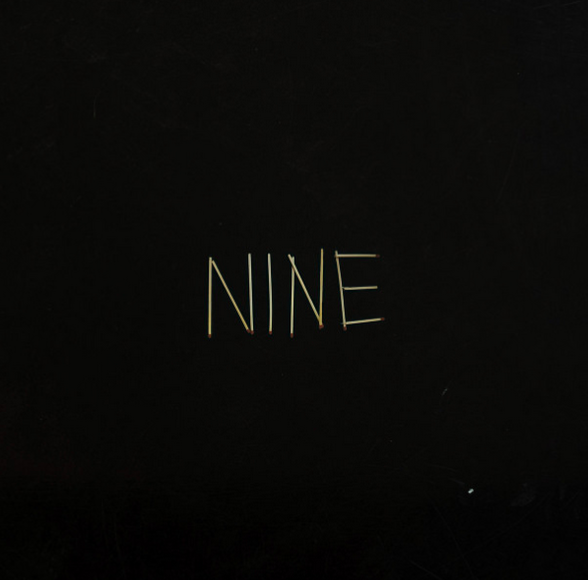
もしも本作に、ほかのSaultの作品とくらべて強い異物感を感じるのなら、それは『NINE』の圧倒的な音の近さと少なさのためかもしれない。手拍子や息継ぎ、金属線に空気の振動やら、すべての音や声が目の前で乱暴に鳴らされているかのようで、スムースな心地よさとはまったく別モノ。LPのA面(6曲目「Bitter Streets」まで)は特にそれが顕著であり、たとえば「Trap Life」の裂けるようなモーグの音色は、サイレン音のように鼓膜と心臓をビリビリとふるわせる。この生命を肌で感じるような質感は、インフローがプロダクションに意図して残したラフさによるものだろう。彼が手がけたリトル・シムズの『GREY Area』と『Sometimes I Might Be Introvert』とのあいだに、じつに5枚ものリリースをねじ込むスピード感が、音と声を生々しいままにパッケージしているのだ。わらべ唄のようなメロディー、「Haha」の旋律をはずれて分散する子どもの声、緊急通報の番号を唱える歌、サイレン音の声真似。これらの声や歌は、ロウなサウンドと相まって、強烈な「生」のイメージを聴き手に伝える。99日後にいっさいの入手経路が絶たれるという発表方法は、多すぎる情報によって切実な声すら記憶からなくなってしまう時代への挑戦だ。あなたがもし幸運にもBandcampでLPを入手していたなら、ふたたびその音を、声を文字どおり「再生」させてほしい。(髙橋翔哉)
注:現在はCD、レコードで購入可
『AIR』
2022年 / Forever Living Originals

ポイントになるのは主に2曲だ。一つはケニア周辺のルオ族の伝統的な音楽の影響を反映させた「Luos Higher」。ケニアといえばオバマ元米大統領のルーツとして知られるが、ルオ族の音楽はオルトゥという民族楽器のきめ細かな音色が特徴で、本作では最終曲となる「Luos Higher」の全編に渡って聞こえる音色はまさにそれに近い。だが、オーケストラや合唱が時折覆いかぶさることで次第に壮大なオペラの印象から奇妙なチャントとして聞ける曲となっていることに気づく。もう一つはクラウス・ノミのようなオペラ歌唱が後半にはゴスペルへとシフトしていく過程を描いたような「Time Is Precious」。本作で歌詞があるのはこの曲だけだが、熱情的なコーラスによってかなり逞しい生命力が刻まれている。いずれもクラシック音楽の転換点とアフリカン・フォークロアを含めたブラック・ミュージックの源泉とが交錯してパラダイム・シフトが起こったような曲と言えるが、まさにこれこそがロージー・ダンヴァーズによるストリング・アレンジ(演奏はワイアード・ストリングス)がまるでストラヴィンスキーからエンニオ・モリコーネまでを貫いたような本作の大きなテーマではないか。前2作で #BlackLivesMatter の時代の怒りと祈りを形にしたSaultは、ここで西洋クラシック的マナーと黒人音楽との根を一つにしようと……いや、もともと種の起源は一つだったという大きな視点を提唱しているような気がしてならない。マイケル・キワヌカ、リトル・シムズらは不在。リズムもほぼない。室内的でミニマル。だが、音を奏でる歓びがここにはある。音楽が音楽であることの立証点がここにあるのみなのだ。(岡村詩野)
Text By Shoya TakahashiMasaaki HaraShino OkamuraDaiki TakakuTetsuya Sakamoto
