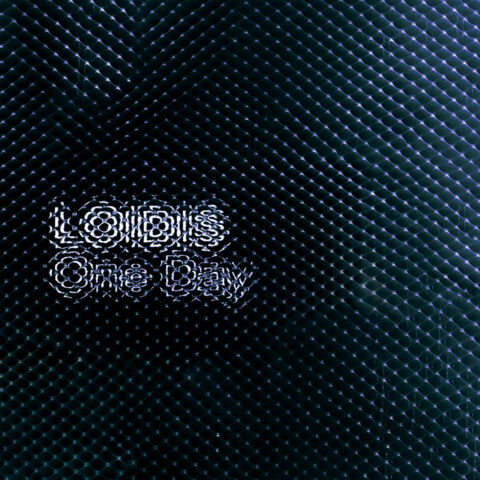洗練の果てで踊るLoidis~複数名義がもたらす豊潤なミニマリズム~
2010年代前半のエレクトロニック・ミュージックについて思いを馳せた時、つい頭をよぎってしまう、今となっては使われなくなったワードがある。アウトサイダー・ハウスだ。それは《Hessle Audio》の主宰であり、DJであったBen UFOが《Rinse FM》のショーで使った造語だった。西海岸のプロデューサーであるAustin Cesear「Shut In」を紹介した際にこのワードを使用したそうだ。Basic Channelの影響を感じさせるこの曲が収録されているアルバム『Cruise Forever』は2012年にリリースされているので、その頃の発言だろう。当時、アメリカで現れ始めていたエクスペリメンタルなハウス・ミュージックの作り手に対して使用されたこのワードの射程はなかなか広かったし、それなりの説得力があったと、今振り返ってみて思う。
当時は、初期ハウスや、ムーディーマンやセオ・パリッシュといったデトロイト・テクノ勢、前述したBasic Channel、《Chain Reaction》周辺等の影響下にありながら、新たなハウス・ミュージックの方向性を模索した音楽家たちに惹きつけられたエレクトロニック・ミュージック・ラヴァーたちがいた。2010年前後に、ゲットー・ハウスから発展したジューク~フットワークが盛り上がりを見せ始めたことを考えると、2010年代前半は奇妙な進化を遂げたハウス・ミュージックが同時多発的に発見された時期なのかもしれない。アウトサイダー・ハウスはロウ・ハウスというワードと並べて語られることが多かったことを考えると、そのザラついた、インダストリアルといってもいいような質感が当時のハウス・ミュージックの中で、ひとつのトレンドだった。カリスマであるロン・モレリ(Ron Morelli)が率いるレーベル《L.I.E.S.》や、USインディーの有名レーベル《Not Not Fun》の姉妹レーベル《100% Silk》、前述したAustin Cesear『Cruise Forever』をリリースした《Public Information》や、先鋭的な才能がこぞって集まったロンドンの《Opal Tapes》、《Mo’Wax》でメイン・ヴィジュアル・ディレクターを務めたWill Bankhead主宰の《The Trilogy Tapes》をはじめ、数々のレーベルから先鋭的な音楽家が出現し、ハウス~テクノにおける決して小さくはない地殻変動を形作っていた。アウトサイダー・ハウスの勃興におけるロウな質感~インダストリアルの拡散というトピックで話を広げると、アンディ・ストットやアクトレス(Actress)、デムダイク・ステア(Demdike Stare)といった才能が2010年前後にアクセルを踏み始めたのもその時代に求められていたテクスチャーだったのではないか、と妄想してしまう。アウトサイダー・ハウス~ロウ・ハウスは、2010年代中盤頃からローファイ・ハウスと呼ばれるようになり、なんとなくその実験性や勢いが曖昧なモノになって霧散していった印象だが*¹、当時出現した才能たちの中には、今も輝かしい才能を発揮している音楽家もいる。本稿の主人公であるブライアン・リーズもその一人だ。
ブライアン・リーズ、という名前を聴くだけではクエスチョンを浮かべるかもしれないが、Huerco S.という名前を目にすると、あの人ね!となる方もいるのではないだろうか。Huerco S.は、アウトサイダー・ハウスの盟友であるアンソニー・ネイプルズ*²のレーベル《Proibito》からリリースされたディープ・ハウスでその存在感を知らしめていき、デビュー・アルバム『Colonial Patterns』(2013年)をOPNことダニエル・ロパティンのレーベル《Software》からリリース。ディープ・ハウスからダブ~インダストリアルなサウンドでザラついたアンビエントを携えた異形のエレクトロニック・ミュージックを築き上げ、その異彩っぷりを世界中に知らしめた。ただ、そんな『Colonial Patterns』での達成も、Huerco S.にとっては単なる始まりに過ぎなかった。またしても《Proibito》からリリースされた2作目『For Those Of You Who Have Never (And Also Those Who Have)』(2016年)は、前作で達成されたダブ/インダストリアルなアンビエント・サウンドの液状化/ガス化がさらに突き進められ、透明性すら手にし、2010年代のアンビエント・ミュージックにおけるひとつの達成と言える傑作となった。ここにかつてハウス・プロデューサーとして名を馳せた彼の顔はほとんど見いだせない。そしてアンソニー・ネイプルズが主宰に名を連ねるレーベル《Incienso》からリリースされた3作目『Plonk』(2022年)で、彼はまたしても世界を驚かせた。『For Those Of You Who Have Never (And Also Those Who Have)』で、あれほど完成度の高いアンビエント・ミュージックに到達していながら、Huerco S.はそれをほぼ捨て去り、今度はIDMやジューク/フットワーク、現行のヒップホップ(トラップ)を参照しながらそのリズムにフォーカスを当てて抽出し、彼の独自の感性によってブラッシュアップした、極限のリズム・ミュージックが展開された。これらのアルバムすべてが賞賛され、時代を推し進める稀代のエレクトロニック・ミュージシャンであるHuerco S.は、ブライアン・リーズが持つ最も有名な名義となった。しかし、これは彼の音楽性のひとつの側面に過ぎないというのもまた事実である。
Huerco S. Boiler Room NYC DJ Set
ブライアン・リーズという当代随一のエレクトロニック・ミュージシャンが持つ、Huerco S.以外の主だった名義をいくつか紹介しよう。まずはRoyal Crown of Sweden。初期の活動で《Proibito》からハウス・レコードをリリースした際の名義であり、ダンサブルなクラブ・トラックをリリースし、ブライアン・リーズの知名度を上げる一助となった。『R.E.G.A.L.I.E.R.』(2013年)では、ロウでダビーな音響感を身にまとったダンス・ミュージックが確立されており、ハウス・プロデューサーとしての彼の実力が十二分に発揮されている。次にPendant。ブライアン・リーズ自身のレーベルである《West Mineral Ltd.》からリリースした『Make Me Know You Sweet (OUEST099)』(2018年)は『For Those Of You Who Have Never (And Also Those Who Have)』と双子のような関係にあると、個人的には思っている。母体となるヴォキャブラリーは同じだが、後者はどこか透明感のあるアンビエント・ダブだったが、前者はダークなメランコリアが全編を覆っており、それは『To All Sides They Will Stretch Out Their Hands (OUEST091)』(2021年)でさらに突き詰められることになる。ある意味では、Huerco S.よりもエクスペリメンタルに突き抜けた名義であると言ってもいいかもしれない。最後にPDP III。ジョン・ハッセルやマトモスともコラボする音響作家=Britton Powell、《Modern Love》からのリリース等で今やエクスペリメンタル・シーンの中でも抜きんでた存在となってきたチェリスト、ルーシー・レイルトンらとのコラボ名義。『Pilled Up on a Couple of Doves』(2021年)は、 3人の才能が衝突することで絶妙なバランスで混じり合った、傑出したアンビエント/ドローン作品となっており、個人的にはブライアン・リーズの関連作品の中でもフェイバリットな1枚だ。他にもBell Le RoyやMio Mioといった名義もあり、ある種匿名的な側面を持った音楽活動をしているのがブライアン・リーズという人物だ。本稿で紹介するLoidisもその名義の中のひとつだ。
Loidis名義では『A Parade, In The Place I Sit, The Floating World (& All Its Pleasures)』(2018年)と新作『One Day』をリリースしている。この名義でブライアン・リーズは、一言でいえば、ディープ・ハウス~ミニマル・ハウス~ダブ・テクノを軸にしたフロア・ライクなサウンドを追及している。現在稼働中の名義の中で、おそらく最もダンサブルな音がここで聴ける。アウトサイダー・ハウスの影響源として挙げた初期ハウス~デトロイト・テクノ勢~《Chain Reaction》周辺が、美しく整理された端正なミニマルなダンス・ミュージックに昇華されているのだ。『A Parade, In The Place I Sit, The Floating World (& All Its Pleasures)』リリース時に、彼は本作を「マイクロハウス」と呼んでいたが、彼のオリジナリティでもあるロウでダビーなテクスチャーを香らせた、その精緻なミニマリズムを骨子としたイーヴン・キックがもたらす快楽性は、本作の時点ですでに唯一無二だ。ユーフォリックなシンセパッドやきらめく電子音のアンビエンスがもたらすフィーリングは、Pendant名義ともHuerco S.名義とも異なる多幸感をもたらし、ひとりの音楽家が、これだけ異なる感情を音楽化してアウトプットできるものなのかと驚かされたものだ。
そんなLoidisによる6年ぶりの新作となる『One Day』は、ブライアン・リーズのダンス・ミュージック路線を愛する人々にとっては待望の作品となっただろうし、その期待を越えるような傑作に仕上がっている。イーヴン・キックと小刻みに響くハイハットとヘヴィなシンセ・ベースが作り出すグルーヴ、揺れ動く電子音が魅惑的な「Tell Me」を聴けば、本作が『A Parade, In The Place I Sit, The Floating World (& All Its Pleasures)』よりもさらにダンス・ミュージックとしての精度が上がっており、ブライアン・リーズが他名義も含めて培ってきた音楽的ヴォキャブラリーをスマート&エレガントにパッケージした作品であることを予感してしまう。均等にリズムをキープするハイハット、ほのかにファンキーなベース、一定間隔で響くスネア、そしてじんわりと広がりサウンドを覆いつくしていくシンセパッドが印象に残る「Wait & See」の細部まで行き届いたサウンド・デザインは圧倒的だ。水中で跳ねるようなくぐもったビートはまさしくブライアン・リーズ節だと思わされる「Tequa」も見事。10分に及ぶ「Lover’s Lineaments」では、徹底した反復とそこにわずかに生じてくる音色/音響の差異がこれほどの快楽を聴き手にもたらすのか、と改めてテクノ・ミニマリズムのグルーヴィーな迫力に圧倒され、スパイス程度に使用されるグリッチの音色もじつに粋だ。「Sugar Snot」のディレイするシンセに絶妙なタイミングでライドしてくるキックの下を、メロディックに這いまわるディスコ・ハウス的なベースラインの反復に身を任せながら体を揺らしていると、あっという間に9分近くの時間が過ぎてしまう。本作は7~9分程度の長尺トラックがメインに収録されているが、緻密な音響操作と楽曲のテンションのコントロールにとって、長いはずの時間があっという間に過ぎ去ってしまう喜びがここにはある。「Dollarama」で明滅するように響く地鳴りのようなベースと、ダンスフロアのハイライトを静かに彩るようなユーフォリックなシンセの音色が形成する対極的な音響の在り方に痺れるし、ダビーなベースとシャッフルするスネアのコンビネーションが絶妙な「All Of Em」もその完成度にひれ伏したくなるばかりだ。ラストの「Why Do」も他の曲と同様にシンプルだ。軽やかなブレイクビーツ、ヘヴィなベース、ダビーなシンセ。これらの要素をブライアン・リーズが巧みに組み合わせることで唯一無二のダンス・ミュージックができあがっている。
シンプルであること、ミニマルであることは、単純で情報量が少ないということではなく、膨大な情報量をそぎ落とし、適切なものだけを抽出して整列させたものだということをブライアン・リーズはLoidisを通じて教えてくれる。決して派手ではないが、機能主義に陥ることもないこのダンス・ミュージックの、そのスマート&エレガントな態度には荘厳さすら感じる。そのサウンドの背景には、ブライアン・リーズの他名義の影がチラついており、ひとつの名義が他の名義と共鳴し合っているということを知ることが、その音楽的な深みを味合わせてくれるきっかけになる。かつてアウトサイダー・ハウスの隆盛を形成するひとりとして数えられていたレフトフィールドなプロデューサーであるブライアン・リーズのあまりにも鋭い先進性が、ここでは端正なサウンドに凝縮され、その研ぎ澄まされた洗練がもたらす静かな輝きが、どこかのダンスフロアや誰かのベッドルームを照らすのはなんと美しいことだろうか。(八木皓平)
*¹ ロス・フロム・フレンズをはじめ、ローファイ・ハウスの括りのもとで有名になったプロデューサーの中にも優秀な音楽家がいるので、筆者はローファイ・ハウスに否定的なスタンスを取っているわけではない。また、俳優ウィノナ・ライダーのヴォイス・サンプルを音源に活用し、サムネイルに彼女の画像を使用したDJ Boringの「Winona」に代表されるように、ローファイ・ハウスはSoundCloudやYouTube をはじめとしたSNSで広がりをみせたジャンルで、その点はローファイ・ヒップホップを想起させられる。
DJ Boring – Winona
*² アンソニー・ネイプルズは、本稿ではブライアン・リーズの盟友として描写されているが、他にもDJパイソン(DJ Python)やBeta Librae、ダウンステアズ・J(downstairs J)といった才能の紹介もしており、目利きとして極めて優秀な人物だ。それだけではなくアンソニー・ネイプルズ本人もじつに素晴らしい音楽家であり、彼もブライアン・リーズと同様にハウス・プロデューサーとして知名度を上げたが、『Chameleon』(2021年)~『orbs』(2023年)あたりでは、ドラムやギターの音色を取り入れながら、ポストロック的要素を含んだオリジナリティあふれるアンビエント・テクノを展開しており、現代のテクノ・シーンの最前線で活躍している。
『orbs』、 Anthony Naples @TheLotRadio 04-11-2023
関連記事
【The Notable Artist of 2022】
Huerco S.
──アンビエント・ミュージックの向こう側へ駆けていく
https://turntokyo.com/features/the-notable-artist-of-2022-huerco-s/