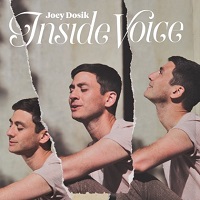1つの扉やチャンスが閉じられてしまっても他の扉が開かれる
ジョーイ・ドーシックが語るLAシーンの無限の可能性
ジョーイ・ドーシックという人といると誰もがわくわくする。取材の前々日に《ブルックリンパーラー新宿》で行われたソロ・ライブ、取材後に観た《ブルーノート東京》でのバンドセットも、2016年に代官山《晴れたら空に豆まいて》で行われたソロ公演の際も、一貫して彼の演奏から放たれるエネルギーは力強い。実際に会って取材をしてみると彼には自分や他者、そして過去、現在、未来とあらゆる物事について可能性を信じる眼差しがあった。
アルバム『Inside Voice』ではビル・ウィザースの「Stories」を、《ブルックリンパーラー》の際にはアル・グリーンの「Let’s Stay Together」を、そして《ブルーノート》ではマーヴィン・ゲイのメドレーを披露した彼からは、オーセンティックなソウルへのリスペクトを感じる。彼自身は、過去や歴史が自身の可能性を広げてくれる1つの大切な要素だと考えているようだ。その証拠に、どのソウルのナンバーも原曲とは異なるアレンジを用いながら、そこには現代を生きるジョーイ・ドーシック自身の意図が含まれている。
先日行われたブルーノート東京の公演では、ジョーイ・ドーシックはじめ、ヴルフペックのベーシストであるジョー・ダート、ドラムのジュアリアン・アレンやギターのジェイムス・コーネリソンのそれぞれが度々アドリブやソロまわしを披露していたことが印象的だった。お互いへの信頼感やバンドで音を重ねることの楽しみや、彼らが日頃から幾度となくセッションを行う仲間だということが伝わってくるステージだった。楽器を持ち、互いに演奏することを愛しているそんな仲間だ。ジョーイ・ドーシックはそういった友人のミュージシャンたちとのコラボレーションの可能性も信じている。
「また来るね!」はモッキーの来日公演に帯同したときから彼が使っているお気に入りの日本語だ。今回のライブ終了後も使っていたが、どうやら今回の来日では、もう1つお気に入りの日本語が増えたようだ。アザラシがプリントされたTシャツに笑顔が眩しいLAの俊英、ジョーイ・ドーシック、チャーミングでありながら音楽さらには人生に向き合う彼の姿を垣間見たインタビューとなった。(加藤孔紀)
Interview with Joey Dosik
――《ブルックリンパーラー》でのソロ・ライヴの際にもアル・グリーンの「Let’s Stay Together」を歌っていたように、あなたは多くの他アーティストの楽曲のカヴァーをしています。一方で、ヴルフペックと度々共演を行っている中で「Running Away」や「Grandma Song」など、あなたの曲がカヴァーされることもあります。あなたにとって自身の曲がカヴァーされるというのはどういう体験ですか?
Joey Dosik(以下、J):とても価値がある体験だと思うんだ。まず、ヴルフペックは尊敬する仕事仲間でもあり、親友でもある。そして、カヴァーされるということは、原曲とは別な解釈が生まれることを意味している。ヴルフペックの『Mr Finish Line』(2017年)で、アントン・スタンリーが「Grandam Song」をカヴァーしてくれているんだけど、彼のおばあちゃんはユダヤ系で、彼は彼自身のおばあちゃんについて歌っている。自分とは違う解釈で、自分を飛び越えて曲に新しい視点が加えられることはそれだけで意味があるし、そうやって音楽は広がっていくと思うんだ。
――では、あなたがカヴァーする立場としてはどうでしょうか? アルバムの中でビル・ウィザースの「Stories」をカヴァーしています。あなたにとってビル・ウィザースというソウル・シンガーはどういう存在でしょうか? ビル・ウィザースにも「Grandma Hands」という曲がありますよね。
J:ビル・ウィザースは僕にとってのヒーローであり、重要なソングライターだ。歌い始めたとき、自分と彼の声の音域が近いことに気付いて、それ以来、彼の歌からは多くのことを学んだよ。先生のような存在だとも思ってる。おばあちゃんについての曲は、彼の曲を意識したというわけではないけれど、僕にとっても彼にとっても大事な存在で、たくさんの人に歌われるほど大きな存在なんだと思うんだ。
――ビル・ウィザースの「Stories」はピアノの伴奏から始まりますが、あなたはクラップのみで歌い始めていますよね。そこにゴスペルの影響を感じるのですが、なぜこのようなアレンジになったのでしょうか?
J:ゴスペルを感じたっていうのは面白いね。僕は、ビル・ウィザースの曲が大好きなんだ。『Inside Voice』ではピアノを使った曲が多いし、ビル・ウィーザースの原曲もピアノを使っているから、原曲と違いを出したかったし、アルバムの他の曲とも違いを出したくて、このアレンジにしたんだ。そして、いまの僕のライブでは「Stories」を(クラップはせず)アカペラで歌い始めている。これもライブで演奏する他の曲のアレンジとの違いを意識してのものなんだ。
――なるほど。そういったことが意図されて演奏されているから、アルバムを通してあなたの「Stories」を聴くとわくわくさせられるんですね。
J:(日本語で)あざーす!
――ありがとうございます(笑)。そもそも、あなたは初めて組んだバンドが、高校時代のジャズ・バンドだと聞きました。サックスも演奏するあなたが、ピアノを弾いて歌うスタイルになった経緯を教えてください。
J:大学へはサックスの勉強のために行って、そこでジャズに夢中になった。20歳前後くらいのときだったかな、自分の残りの人生ついて考え始めたんだ。そのときに原始的な体験、幼少期を振り返ったら、僕にとって最初の楽器は歌でありピアノだったことを思い出した。そんなことを考えていたら、自分が良い曲をつくって歌えるか、そしてアルバムを作れるか、挑戦してみたいという気持ちになったんだ。挑戦しないで後悔したくなかったし、いまも試行錯誤の途中だよ。
――あるインタビューで、以前に膝を怪我したとき音楽以外の物事の価値に気付いたと話していましたよね。その気付きは、先ほど話してくれたピアノを弾いて歌い、曲を作ることに挑戦してみたかった、後悔したくなかったという気持ちとも関係するものですか?
J:その質問、面白いね。ひどい怪我をしてしまったとき、これからどうなるんだろうという焦燥感にかられてしまった。サックスを演奏していたときも、これからミュージシャンとして満足のいく人生を歩めるか不安を感じていたんだ。だから、怪我をして気付いたことと、音楽家として別なスタイルに挑戦したいと思った気付きは似ていると思う。僕はバスケットボールが大好きなんだけど、そのプレイ中に膝を怪我してしまって。膝を痛めてはしまったけれど、その体験によってバスケットボールの曲を書くことになった。手術を終えて回復して初めて書いた曲が「Game Winner」で、怪我をしたことも僕にとっては大切な物語だったんだ。大変な出来事が起きてしまったけれど、大切な曲を書くことができたし、曲を書くことで救われた気持ちにもなった。人生の中で一つの扉やチャンスが閉じられてしまうことはあるけれど、他の新しい扉が開かれることがあると思うんだ。
"僕の曲の中には、サウンドは過去を、歌詞は現代を意識したものもある。過去と現在、その二つをバランスよく取り入れたいと思っているよ"
――新しい扉という意味では、『Inside Voice』でモッキーやミゲル・アトウッド・ファーガソンと一緒に制作したことで、サウンドがよりバンド主体のオーケストラへと変化したようにも感じました。
J:EP『Game Winner』の前に、モッキーとはたくさんの音楽をつくっていたんだ。そしてモッキーと作業している間に膝を怪我してしまって、その怪我が『Game Winner』をつくるきっかけにもなったわけなんだけど、そのときはモッキーとコラボレーションした音楽は一旦置いておいたんだ。『Game Winner』は自分の内側に向いたパーソナル作品で、療養しながらベッドルームで作り上げたものだったのに対して『Inside Voice』は、モッキーとスタジオに入って様々なことを整理しながらつくったアルバムだった。モッキーは僕にとって音楽の兄のような存在で、彼がLAに越してくる前からファンだったし、日本に初めて来たきっかけも彼のツアーだった。ミゲルは僕が17歳の頃からの付き合いで親友なんだ。
――モッキーがLAにやって来て音楽を共にするようになったことは、あなたにとってどんな体験でしたか? ニア・アンドリュースやペガサス・ウォーニングも彼とセッションするミュージシャンですが、そこには彼を中心とする音楽のコミュニティがあったのでしょうか?
J:僕らは友人同士で、モッキーの家によく出入りしていたんだ。それはすごく自然に行われていたことだったと思う。セッションをしたり、食事をしたり。お互いにソングライティングをすることも自然に行われていたし、あの体験は素晴らしいものだったよ。ニアは、先日アルバム『No Place Is Safe』をリリースしたばかりだけど、あのアルバムも素晴らしかったよね。
――LAは歴史的にみても多くのミュージシャンが集まり様々な音楽が生まれてくる魅力的な町ですが、あなた自身はLAをどのような場所だと感じていますか?
J:僕はLAという場所で育ったから、多くの素晴らしいミュージシャンを見てきた。例えばカマシ・ワシントン。彼は頻繁にライブやギグに出演していたし、無料のライブにも飛び込みで演奏していたりもした。彼はいま、世界的に有名だけど、その才能やスタイル、やっていることは前から変わっていなくて、ただ世界の認知が変わったんだと思う。世界は彼の存在を知るべきだったから、それは素晴らしいことだよね。サンダーキャットにも同じことが言えるよね。LAは特別な音楽が生まれる場所で、常に新しい音楽、シーン、コミュニティが登場し続けている。5年先にもどんどん新しい才能が出てくる、というか元々そこにあるものに周りの人や世界が気付き始めて注目していく。そういうことが起きている街だと思う。

――新しい音楽が生まれる地、LAであなた自身は、70年代のソウルにリスペクトのある音楽を届けていると思うのですが、その音楽の歴史を継承するということには自覚的なのでしょうか?
J:時代を越えた音楽をつくるということが僕の軸になっている。今という時代は過去の様々な時代を含んで成り立っているし、今やっている音楽も未来に伝わっていくと思っているんだ。
――新しいことと歴史を継承しようとすること、どちらへの意識が強いでしょうか?
J:過去のミュージシャンから影響を受けながら、またそれをどのように現代で聴かせることができるか考えながら音楽をつくっているんだ。僕の曲の中には、サウンドは過去を、歌詞は現代を意識したものもある。過去と現在、その二つをバランスよく取り入れたいと思っているよ。
■Big Nothing内アーティスト情報
http://bignothing.blog88.fc2.com/blog-entry-9043.html
■Joey Dosik Official Site
https://joeydosik.com/
関連記事
【FEATURE】
ジョーイ・ドーシック、オーセンティックな歌を通じてひたむきにソウルの伝統を継承する男
http://ai132qgt0r.previewdomain.jp/wp/features/joey-dosik/
Text By Koki Kato
Photo By Yusuke Sasamura