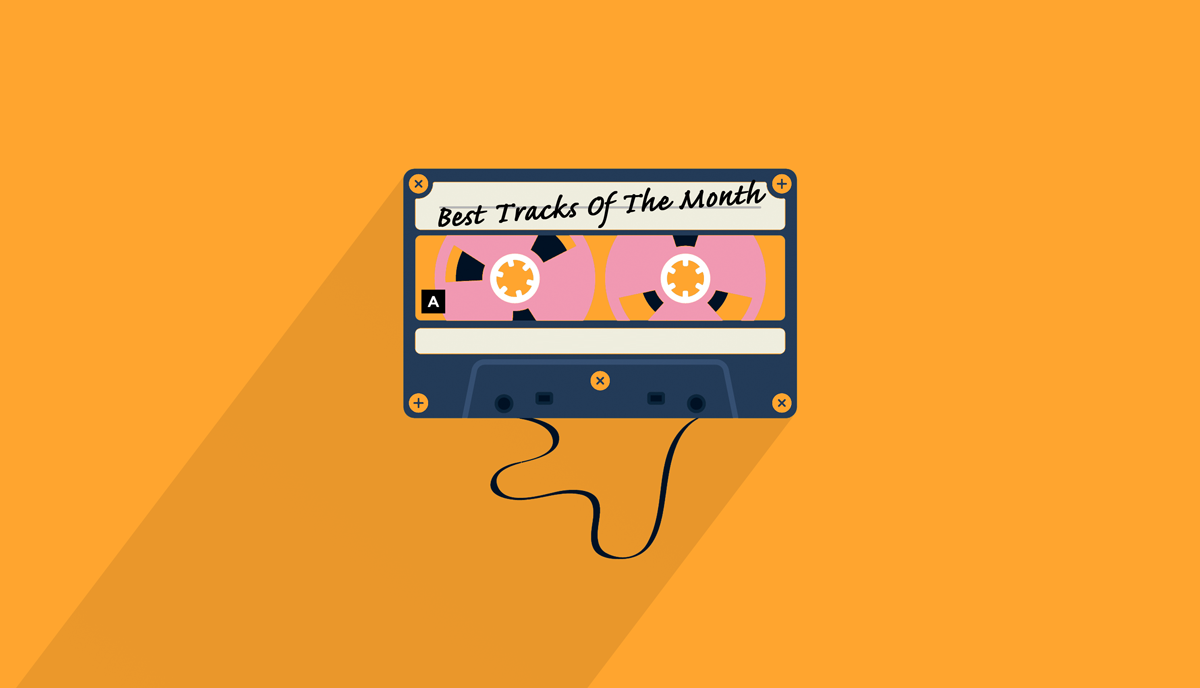BEST 12 TRACKS OF THE MONTH – February, 2022
Editor’s Choices
まずはTURN編集部が合議でピックアップした楽曲をお届け!
Caroline Polachek – 「Billions」
A.G.Cookとの活動でも知られるプロデューサーのDanny L Harleは、これまでもキャロライン・ポラチェックの楽曲で手腕を振るってきた人で、本楽曲も2人による共作。Harleが制作したビートを聴いてポラチェックは、サイケデリックなイメージを思い浮かべて制作に取り掛かったという。そんなサイケな面を特に強調しているのはパーカッションで、これはおそらくタブラだろうか。重厚なビートやシンセの中から、パチパチと飛び跳ねるように聴こえてくるこの音は、明滅する光のようでいて、そのフレーズの反復で陶酔を導く鍵になっている。ポラチェックとトリニティ合唱団の歌声の組み合わせも心地いい。(加藤孔紀)
Montaigne, David Byrne – 「Always Be You」
『American Utopia』の上演再開に続き、オノ・ヨーコ・トリビュート盤への参加、サントラへの曲提供、ドラマへの出演など多忙な状態が続くデヴィッド・バーンが、今度はオーストラリアのポップ・アーティスト、モンテーニュとデュエット。彼女からのオファーで実現したという二人だが相性は抜群だ。カラフルなハイパーポップ調のアレンジと、リンガラやソンをも彷彿とさせるビートがミックスされたダンス・ポップで、バーンが歌うパートでは後期トーキング・ヘッズを思い出させるほど。歌詞に出てくるダニエル・キットソンとはオーストラリアでも人気の英のコメディアン/作家。限られた言葉の繰り返しでグルーヴを生み、洒脱なユーモアを伝える手法は古典的だがシンプルに楽しい。(岡村詩野)
David Friend & Jerome Begin – 「These Patterns」
スティーヴ・ライヒとも共演したピアニスト、デヴィッド・フレンドによるアタック感の強いピアノが、コンポーザーのジェローム・ビギンの手腕による高解像度な編集で流動性を獲得していく。幾層にも重ねられたリフから、絹のようになめらかな響きが立ちのぼる瞬間を聴き逃してはならない。トーン・クラスター的な音響は多重振り子のように、混沌から幾何学的調和を導き出す。あなたの耳はその充実感と、やがて訪れる収束への渇望とに引き裂かれる。ポスト・クラシカル系レーベル《New Amsterdam》から共作『Post-』がリリース予定。“ – ”の後の無限&無常&無碍の空白、その可能性が、この先行曲にも宿っている。(髙橋翔哉)
Pictoria Vark – 「Wyoming」
自身の友人でもあるスクワレル・フラワーのツアー・バンドでベーシストを務め、アイオワを拠点として活動する韓国ルーツのシンガー・ソングライターによる一曲。尖り、渦巻き、歪むギターを主軸に、曲中でその厚みをコントロールしながら大胆かつ繊細に構築されたオルタナティヴ・ロック・サウンドに瞠目。そのうえで主張を忘れない凛としたヴォーカル・スタイルからは自身もフェイヴァリット・バンドにあげるフランシス・クインラン擁するホップ・アロングのような“エモ”の文脈を読み取ることもできる。本曲が収録されたデビュー・フル・アルバムは4月にリリース。ミツキ、ササミによるアルバム・リリースに続き、アジア・ルーツのフィメイル・シンガーソングライターによる好作リリースが本年も止まらなそうだ。(尾野泰幸)
Vince Staples – 「MAGIC feat. Mustard」
ヴィンス・ステイプルズの新作『Ramona Park Broke My Heart』からの先行曲であり、LAを代表するプロデューサーの1人であるマスタードとの共作曲。ヴィンスが昨年リリースしたセルフタイトル・アルバムと新作がほぼ同時進行的に制作されたというのもあってか、浮遊感のあるビートのシンプルさやレイドバックした心地よいフロウ、そして「ママはパパに会って、俺はゲットーに入れられた/38口径を渡されて、俺は特別だと言われたんだ」とハードな経験をさらけ出すライムには繋がった印象を受ける。ちなみにレコーディング・エンジニアには彼の作品にはお馴染みとなったケニー・ビーツがクレジット。(高久大輝)
Writer’s Choices
続いてTURNライター陣がそれぞれの専門分野から聴き逃し厳禁の楽曲をピックアップ!
Arlo Parks -「Softly」
デビュー・アルバム『Collapsed In Sunbeams』が非常に高く評価されただけに、その二番煎じは失望を招くことは聡明な彼女のことだからよく理解していたはずだ。かと言って、音楽性を大きく変えてしまうのも同様に期待を損ねてしまう。このグルーヴ感を前面に押し出した新曲は、前作を覆っていたメランコリックなムードを残しつつも、リズミカルでビートによって新たなステージへ向かったことを意識させる。一方で、歌詞は恋が終わろうとしているひりひりとした瞬間をリアルに描写しており、その焦燥感の中ににじみ出す諦観もサウンドが表現しているようだ。3月頭からはクレイロと共に北米ツアーを敢行。そこでの経験や成長も次の新曲に注がれることだろう。(油納将志)
Christian Lee Hutson -「Age Difference」
フィービー・ブリジャーズとブライト・アイズのコナー・オバーストをプロデュースに迎えた、4月リリースの新作『Quitters』からの先行カット。慌ただしく過ぎ去る日々の中で悲惨なニュースに無力感を覚え、気がついたら後悔ばかりが積み重なって……。断片的なヴィジョンを散りばめたようなハットソンの歌声にはそんなどうにもできない物悲しさを重ねてしまう。しかしおおらかな時間の流れを感じさせる演奏に、悲惨なスロー・バラッドとは違う不思議な安らぎを感じないだろうか。柔らかく爪弾くエレキギターと伸びやかに哀愁を描くトランペットに乗せて歌う「でも僕にはたくさんの時間が残っている」という言葉は、優しくも力強く響く。(阿部仁知)
The Crane – 「拉麵公子 Ramen Boy」
「拉麺公子Ramen Boy」というとぼけたタイトル、不条理にもほどがあるシュールなPV、一杯のラーメンから立ち上る湯気を前に辛い失恋を忘れようともがく心情風景が至って真面目に描かれる歌詞……この不思議な微笑ましさが胸を打つ。約2年前からそのハイレベルな曲作りで既に台湾インディーで注目を集めていたザ・クレーンの待望の初EP「鶴園」のリード曲。重ためのビートの上をゆらゆら漂うシンセサイザーのドリーミーなサウンド、淡々としたスムースなヴォーカルは彼が得意とするところで、今回も存分にその才能を堪能できる。ちなみに拉麺公子は台北に実在するザ・クレーンが好きな日本風ラーメン店だそう。(Yo Kurokawa)
Rex Orange County -「AMAZING」
3/11にリリースされるメジャー2作目『WHO CARES?』から2曲目となる先行トラック。2017年発表のシングル「Loving Is Easy」でコラボレーションしたベニー・シングスとよほど意気投合したようで、今回はアルバム全体を共作することになったそうだ。ベン・シドラン、マイケル・フランクスを思い出させる甘美なストリングスやピアノを主体としたメロディやアレンジは、レックスとベニーが共有するセンスによって編み出されたものであり、そこに互いのヒップホップを始めとする音楽的な背景も加わる。(油納将志)
曽我部恵一 -「Beginners」
ロシアによるウクライナ侵攻の翌日、YouTubeにアップされた曽我部恵一の新曲。どこかいびつで空白の多いビートは、歴史の教科書の中の出来事だったはずの侵略戦争というものを目の当たりにした我々の混乱と無力感を反映しているようにも聴こえる。しかし「歩いていけば88日と13時間」「戦争よりもセックス」という歌詞からは、彼の地で起きている信じ難い事態をなんとか自らの日常に引き寄せようという試みが感じられる。この暗い恐怖の中、軍人でも政治家でもない私たちが忘れてはならないことは、彼らもまた我々と同じ本能を持ち、赤い血が流れる人間であるということである。そして音楽には常にそれを思い起こさせる力がある。(ドリーミー刑事)
Wet + Dijon – 「Larabar – Remembering Something Heavy in the Car Going Wherever Remix」
“サッド・ガールのためのアンセム”とも形容される、破局と復縁を執拗に繰り返す人間関係のループをテーマにしたメランコリックなバラードを、間もなくスタートするボン・イヴェールの全米ツアーにオープニング・アクトとして抜擢されているディジョンがリワーク。オートチューンを施されたリード・ヴォーカリスト、ケリー・ズトラウのささやくような歌声にR&Bマナーとして男性からのアンサーを重ねるだけでなく、気の置けない恋人たちのこわれもののような結びつきをカオティックにうごめくフリー・フォームな音響で表現し、原曲の切なさを倍増させている。グラウンド・ホッグデーをテーマにした映画『恋はデジャ・ブ』(1993)も思い出しながら、2月にふさわしいコラボレーションだと感じた。(駒井憲嗣)
Yves Jarvis – 「Prism Through Which I Perceives」
モントリオールを拠点とするJean-Sebastian Audetのプロジェクト、イヴ・ジャーヴィスの新曲はちょうど1分。啓示を喚起するような定型詩と、その間に挿入されるトライバルなギター。これが3回繰り返された後に「手遅れでありませんように!」と告げて詩は終わる。その後ろに流れるリズムやギターのバッキング・パターンも、特定のジャンルに回収される瀬戸際でそれを拒むように遷移し、よりプリミティヴなものとして詩の神秘性を前景化させる。ジャンル横断的というより、超自然的な力が音楽を媒介にして説くような内容で、畏怖の念すら覚える。そして、それを1分間のポップスとして表現したJarvisの手腕にも。(風間一慶)
【BEST TRACKS OF THE MONTH】
過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)
Text By Hitoshi AbeYo KurokawaKenji KomaiShoya TakahashiIkkei KazamaDreamy DekaShino OkamuraMasashi YunoDaiki TakakuKoki KatoYasuyuki Ono