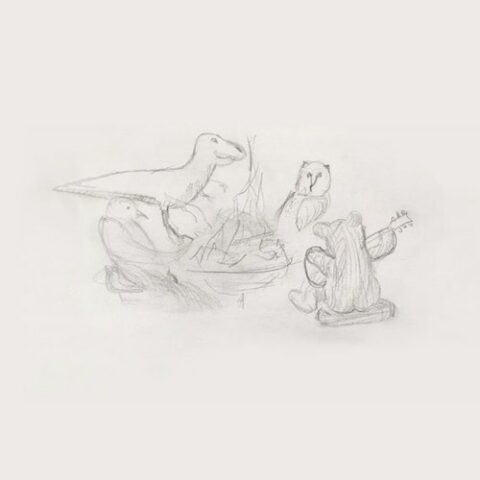執着と恍惚の物語
「Little Things」。すごい曲が届いたものだ。ギターだけでどのくらいのトラック数を使っているのか正確にはわからない。わからないし、実際にはそこまで極端に多く使っているわけではないかもしれない。ただ、ギターという楽器でここまで層の厚い音を作り上げ、しかも一定のリズムをキープするのではなく、常にビートを変化させていく。そのプロセスが陶酔してしまうほどに美しく、癪に触るほど粋な曲だ。一聴すると、意識的にバタつかせたように高音で跳ねるドラムがビートの遷移を引っ張っているようだが、この曲にパースペクティブな刺激をもたらしているのは、間違いなくいくつものリフが重なっては広がり、また寄り添っては離れていく織物のようなギターのレイヤーだ。
ヘッドフォンで片方ずつ聴くとその違いはさらに明確で、Rは極めて淡々と4ビートで柔らかく刻まれるアコギがベースになっているが、Lにはイントロの最初10秒付近で登場する、最初は心地いいエレクトリック・ギターが徐々に曲を侵食していくのがわかる。すると、今度は中盤、RからLを凌ぐノイジーなソロが挿入されてきて、左右のギター・リフが大きな畝りを形成していくという具合。終盤はそれらがまるで警鐘音を轟かせるようにラウドに変異しながら混沌としつつも没我の色調を残していく。そして、気がつけば、とても細かくビートが切り替わっては次へとバトンが受け渡されていることに翻弄されるだろう。これはもうヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「Heroin」さながらの恍惚と言っていい。このバンドがニューヨークを拠点とするバンドである事実を改めて実感する。
この曲に奇妙なビート感をもたらすもう一つのポイントはエイドリアン・レンカーによるヴォーカルの乗せ方だろう。全てのフレーズでエイドリアンの歌は譜割を気にせず、演奏から少し遅れたり、少し前のめりになったりと、追いかけたり追いかけさせたりしながら、複数のギターによる層の厚みを翻弄させる。しっかりとリズムに合わせることを嫌うように、前に後ろにとさりげなく振り回す。だから、ビートに合わせて歌を聴いていると、裏に入ったり表に出てきたりと結構バラバラだ。ほとんどポエトリー・リーディングにも似た、言葉を置きにいくような表現も見られ、それによってリズムには奇妙な起伏が生まれる。ギターのレイヤーによって度々変化していくグルーヴを歌によってさらにズラしてしまっている。エイドリアンの愛らしい歌声につい心地よさを感じ取ってしまいがちだが、彼女のこの曲での役割は、心地よさどころか、居心地の悪さ、異物感を醸し出すことにあると言えるかもしれない。
そして、その異物感とやらは“Living in the city(New York City) is a crowded place”などというクダリがあまりに象徴的なリリックに託された、無秩序な都会に生きる者の、周囲の雑踏の中に我を見失った甘い執着ではないかと思うのだ。この「Little Things」とは、確かにギターなどの弦楽器の層の厚みと衝突が、ニューヨークの地中に今もねっとりと巣食う巨大な亡霊たる存在、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「Heroin」を連想させる曲ではある。それはハーモニックだったりノイジーだったりするギターだけではなく、“私は少し取り憑かれている”“あなたについて好きなほんの些細なことに”という強烈なフレーズが不規則に顔を出す歌詞からも、かのニューヨークのゴーストの幻影を感じ取ることができるだろう。「Heroin」を収録したアルバム『Velvet Underground & Nico』において、かつてニコが“あなたの鏡になりたい/だって見なくてもあなたのことがわかっているから”(「I’ll Be Your Mirror」)とその甘美なオブセッションを歌ったように。
面白いのは、この曲をドラムのジェームズ・クリヴチュニアのプロデュースで録音したのはカリフォルニアのトパンガ・キャニオンだということだ。トパンガは風光明媚なLAの西側にある町であり、エリア。ビッグ・シーフがこの自然豊かな場所での録音を好んだ理由はわからない。だが、ニューヨークで「ほんの些細なこと」に取り憑かれてしまったこの曲の主人公が、その「あなた」を追い求めどこにいるのか彷徨う様子を表現するにあたり、気候も生活慣習も何もかもが正反対の、ある種、桃源郷のような美しさを持ったトパンガという場所を選ぶ思惑は少し理解できる気がする。そのせいか、エイドリアンの歌声はまるでLAで制作をしていた頃のフリートウッド・マックのスティーヴィー・ニックスのようだ。ちなみに、もう1曲の新曲「Sparrow」(こちらはニューヨークのキャッツキル録音)は非常にオーセンティックなフォーク・ロックで、その仕上がりにおいてはどう考えても「Little Things」の方に軍配があがるが、失楽園の寓話が聖書風に語られたリリックには「Little Things」との連続性も感じられる。
2連作となったリリースを経てビッグ・シーフの風向きを大きく変えたのは、明らかにエイドリアン・レンカーの昨年のソロ作だ。フォークやクラシックだけではなく、ドローン、アンビエント・ミュージックまで、ギター・サウンドの持ちうる様々な可能性を内包した、でも的を一箇所に絞らせないまま聴き手をそっと高揚させるエクスタティックなあのアルバムが、この「Little Things」への橋渡しのような役割を果たしていたとさえ思えてしまう。ビッグ・シーフという名の執着と恍惚の物語は、きっと我々が想像している以上に壮大で長い。(岡村詩野)
万華鏡のようなサウンドとリズム・セクションが生み出す“不確実性”の歌
新曲に至る情報は以前からあった。エイドリアン・レンカーはビッグ・シーフが同時代的なインディー・バンドとして最も創造的であり、感情的であり、繊細であるという評価を決定づけた『U.F.O.F』(2019年)と『Two Hands』(2019年)二連作のあと、2020年に発表された自身のソロ作品に関連したインタビューで最近はトパンガ・キャニオンにてバンドが音楽制作を続けているという話をしていたし、ビッグ・シーフのオフィシャル・インスタグラムでも彼らが集い、音楽制作をしていることを示唆するようないくつかの写真を見ることもできた。しかし、グラミー・ノミネートへも結実した過去二作で提示したエイドリアンによる感情の触れ幅を的確に表現する類まれな才気を迸らせるボーカルと、それを支える無駄を削ぎ落としシンプルに設計されたサウンドを持つミディアム・テンポな楽曲群から想像するに(「Not」のような唸るギターをフィーチャーした楽曲は例外的にあったとしても)、この度サプライズで耳へと届いたバンドの新曲「Little Things」が、一作目『Masterpiece』(2016年)や二作目『Capacity』(2018年)で展開していたオーセンティックなフォーク・ロックへと歩み寄りつつ、楽器一つ一つがエモーショナルに重層する万華鏡のようなバンド・サウンドをこれ以上ないバランスで練り上げた楽曲であったことに唸った。その美しく、儚く轟くバンド・アンサンブルにビッグ・シーフがワールド・ワイドなインディー・ロック・バンドの頂へと向かう道を急角度で駆け上がっていた2018年、《Pitchfork Music Festival》で演奏した「Shark Smile」におけるバック・ミークとエイドリアンのヒリつき、痺れるギターの掛け合いを想起もした。
この新曲「Little Things」は、バンドにてドラムを担う、ジェームズ・クリヴチュニアがプロデュース。2020年にはレコーディングを進めており、カリフォルニアのトパンガ・キャニオンにある《Five Star Studio》にて録音された。エンジニアにはウォー・オン・ドラッグス『A Deeper Understanding』(2017年)、ケイシー・マスグレイヴス『Golden Hour』(2018年)、ブリタニー・ハワード『Jaime』(2019年)といった2010年代後半におけるインディー・ミュージックの重要作品にてエンジニアリングやミックスを担い、ベック『Hyperspace』(2020年)にてグラミー賞「最優秀アルバム技術賞(ベスト・エンジニア賞)~クラシック以外」を獲得したショーン・エヴァレットを迎えている。
クリアなアコースティック・ギターのストロークと絞り出すように体の芯を突き刺すエレクトリック・ギターの複層するサウンドが、ハンドクラップを織り交ぜた一見複雑だが心地良く体に届くリズム・セクションによって導かれる。そのような本曲に、ジム・オルーク『Eureka』(1999年)のフォーク・ミュージックを基調としつつ綿密かつ繊細なスタジオ・ワークにより構築された多幸感に満ちた(実験)音楽の洪水や、『Being There』(1996年)、『Summerteeth』(1999年)、『Yankee Hotel Foxtrot』(2001年)周辺の初期ウィルコにおけるルーツ・ミュージックをオルタナティブに解釈したハードかつ抒情的なサウンド・メイキングの姿を接続することもできる。ときに優しく、ときに気丈に歌い上げられていく本曲は最後、エイドリアンのかなぎり声とともに、ノイジーなギターを主軸としたインストゥルメンタル・パートへと遷移しながら締めくくられる。“「Little Things」はまさに文字通りの意味で不確実な感覚を土台とした物語なのです”と本曲の目まぐるしく変化するリズムに言及しつつ《4AD》オフィシャルは本曲について語るが、その“不確実性”という主題を、人間関係の複雑な変容とその中で生を継続していくことに関する思索を巡る本曲のリリックにも見て取ることは間違いではないだろう。楽曲の最後、ギターの残響と入れ替わるように前景するクリスタルなウィンド・チャイムの音は、“不確実性”の先にバンドが眩く光る“何か”を見ていることを示唆してもいる。バンドはこの9月からUSツアーに旅立ち、2022年にはヨーロッパでも巡業する。彼らが住むアメリカの地から遠く離れたこの日本でも行われるはずだったバンドの公演が、近い未来に開催されることをいつまでも待っている。(尾野泰幸)
関連記事
【REVIEW】
Big Thief『Capacity』
http://turntokyo.com/reviews/capacity/
【FEATURE】
エイドリアン・レンカーが示す二元性と揺らぎ〜ビッグ・シーフの紅一点の最新ソロ作を聴き解く
http://turntokyo.com/features/adrianne-lenker/
【INTERVIEW】
現在のNYを支えるビッグ・シーフが放つ《4AD》移籍第一弾作『U.F.O.F』
これは「見知らぬ友人」への投瓶通信か? 信頼と友愛のロック・ミュージックか?
http://turntokyo.com/features/interviews-big-thief/
テキサス、カントリーという自身のルーツと伝統/共同体への貢献
ビッグ・シーフのギタリスト、バック・ミークが語る制約が生み出したセカンド・ソロ・アルバム
http://turntokyo.com/features/buck-meek-interview/