THE 25 BEST ALBUMS OF 2020
2020年ベスト・アルバム
パンデミックが世界中を襲った一年。感染防止のため隔離環境を過ごした人も、その環境を支えるために外で動いた人も、平時以上の過酷な環境を生きた人も、誰しもが現在進行形で見えないリスクが迫るこの時代を生きる意味を反芻し、自らに問うた。そのなか、ミュージシャンも、産業従事者も、リスナーも、音楽に何らかのかたちで関わる人々は日々変わりゆく状況に翻弄されつつ、なんとか音楽を鳴らし、届け、聴こうとした。例えばそれは配信ライヴの拡大、《Bandcamp Fridays》やクラウドファンディングなどの配信/販売プラットフォームを通じた支援の動きとして顕在化したといえる。ここに《TURN》はそのような2020年を代表する25枚を示す。その中にはコロナ禍で制作された作品もあれば、そうでない作品もある。しかし、それらは総体としてこの「特別な年」とそこに描かれた音楽地図をなぞり返すための25枚であること。それだけは確かだ。(尾野泰幸)

25
Hello Forever
Whatever It Is
Rough Trade / Beatink
一見するとかなり浮世離れしたバンドに映るかもしれない。ヒッピー風情のルックスもさることながら、LA郊外でメンバーが一つの家で暮らすとか、気のあった仲間ならどんどん招き入れるようなオープンな姿勢とか……まるで60年代ラヴ&ピース時代からタイムスリップしてきたようなところは確かにある。実際、厚みあるハーモニーやコラージュ的なアレンジも、キャッチーなメロディもその時代のポップスさながら。だが、ビーチ・ボーイズからエレファント6周辺あたりに連なる“室内楽的捻くれポップの系譜”という以上の可能性は、むしろ現代のR&Bやヒップホップを視野に入れた緻密でグルーヴ感ある音作りにある。そういう意味でもオートチューンを用いたソウルフルな「Rise」のような曲が次作以降の評価のポイントとなりそうだし、最初は自主制作だったこのデビュー作のリリースに踏み切った《Rough Trade》もそうした時代の越境性を評価したのかもしれない。(岡村詩野)

24
Various Artists
tiny pop – the tiny side of life
P-Vine
昨年に《ele-king》へ掲載されたコラム、上野で開催された《tiny pop fes》、さらにブックオフを主戦場としたディグ集団《lightmellowbu》やネットレーベル《Local Visions》の活動ともリンクし、ここ数年で徐々に可視化されていた《Bandcamp》や《Soundcloud》に散らばった「しょぼいポップス」=「インターネットを漂う“DIY歌謡曲”」たち。それを“tiny pop”と称し集積させたミュージシャン、hikaru yamadaによる集大成的コンピレーション。インターネットという(幻想)共同体/プラットフォームの奥底にただよう危うさときらめきを併存させた楽曲たちに圧倒される。その新たなポップスはあまりにもゆるやかな“tiny pop”というカテゴリーの鍵括弧の内外を自由に出入りし、今もどこかで増殖し続けているだろう。そのような蠢きの文脈化に、本作の凄みがある。(尾野泰幸)

23
Headie One
Edna
Relentless
アメリカとイギリスで同時にラップ・ミュージックのサブ・ジャンル=ドリルが流行り、世界を席巻した1年だった。対抗意識を燃やすこの2カ国で、同時に1ジャンルが盛り上がることは珍しい。そんな中で、北ロンドン出身のヘディー・ワン(Headie One)は、ファースト・アルバム『Edna』でストレートなラップと掛詞を多用したリリック、そして幅広いサウンドで格上の余裕を見せつけた。ストームジーとAJトレーシーを迎えたリードトラック「Ain’t It Different」では、掛詞を多用しながら、リリカルな実力を発揮。フューチャーとコラボした「Hear No Evil」では、メロディックなトラックの上で憂げな声で力強く、また優しく歌い上げ、どこか哀愁が漂うのが魅力的だ。ときどきクスっとするダイレクトな表現が飛び出たり、MVではガーナの叔父さん風のダンスを披露したり、と肩肘を張りすぎない姿も新鮮で、ラッパーとしての成熟を感じられる1作だ。(米澤慎太郎)

22
John Carroll Kirby
My Garden
Stones Throw
過去にはノラ・ジョーンズやフランク・オーシャン、今年はアヴァランチーズの新作に参加など、実に多くのアーティストへ貢献してきたLA拠点のキーボーディスト。これまでのソロ作では、2010年代に再評価が進んだアンビエントやニューエイジに呼応するようなサウンドで、曲名には地名を用いたりしながら音で情景をスケッチしたような作品を発表してきた。今作では、前作までと同様の質感は残しつつも、特にピアノのフレーズの反復や演奏で作品を印象的に彩っている。ソランジュの直近2作に参加したことを思い出させるフレーズの反復。ジャズ・ベーシストの鈴木良雄が84年に発表した『モーニング・ピクチャー』など日本の環境音楽からの影響を語りながら、学生の頃に学んだというジャズ・ピアノのアプローチも表出させた。演奏者としてのアイデンティティを生楽器の演奏でもって、いかにアンビエントなサウンドに編み込むか、その積極的な姿勢と実践が2010年代以降へのアップデートを予感させた。(加藤孔紀)

21
Becca Mancari
The Greatest Part
Captured Tracks / Inpertment
従来の生活環境が一変し、精神と身体のバランス維持に心を割いた2020年。《NPR》が端的に指摘したように、ひとびとは様々なやり方で自室での“チル”を試み、音楽もそれに寄り添った。ナッシュヴィル拠点のSSW、ベッカ・マンカリによる本作はまさにそのようなムードと共にあった。浮遊感のあるギター・サウンドの素晴らしい鳴りに驚嘆する「Like This」と「Pretend」。透明感のあるアコースティック・ギターと虚空に向かって叫ぶようなエレキ・ギターの絡み合いが美しい「Knew」。全編を通じたシルキーなエフェクト・ヴォーカル。それらが構築するたゆたうインディー・ポップ・サウンドが伝えるリラクシングな風合と、同性愛者という自身のセクシュアリティをテーマとする内省的感覚の混交。それは、本年に四角い部屋のなかで繰り返された思考/身体の弛緩と緊張という経験へ結びつき、本作を“2020年の”作品とした。(尾野泰幸)

20
Logic
No Pressure
Def Jam
デビュー・アルバム『Under Pressure』から6年、プレッシャーから解放されることを選択したロジックの、7作目(本人談)にして最終作。キャリアを通じてこだわりを見せてきたアルバムを通してのストーリー展開と、密で巧みなフロウは今作においても健在。ラッパーとして、夫として、父親として、30歳として、一人の黒人男性として、過去作で張られた伏線を回収するような表現も見られ、フィナーレを飾るにふさわしい仕上がり。ソーシャル・メディアや有名税のもたらす悪影響から逃れるべく引退を決意したと語るロジックだが、No I.D.のトラックに乗り澱みなく吐き出される言葉は60分に及ぶセラピーのよう。最終トラックは、白人警官から殴打され盲目となった黒人の退役軍人=Issac Woodard Jr.について語られた『Orson Welles Commentaries』のエピソードに割いている。(奧田翔)

19
Jessie Ware
What’s Your Pleasure?
PMR / Virgin EMI
近作では評価が鈍っていたジェシー・ウェアの4枚目は、徹頭徹尾“ディスコ”な、起死回生のコンセプト作。だが、懐古趣味ではない。ゴージャスなストリングスで飾り立てながらも、トラックは無機質に、ヴォーカルはクールに。聴き進めるほどに熱さと冷たさの間を焦らされるアレンジは、実にモダンだ。停滞したキャリアを打破し「音楽は楽しいものだ」という想いを自身に取り戻すべく、ひと時のアヴァンチュールに耽るかようなロマンティックな雰囲気も演出。と同時に今作は、エイズが猛威をふるい多くの人が愛する人を亡くした、80年代のニューヨークのクラブでよくかけられたというファーン・キニーの「Love Me Tonight」(1981年)を元ネタとしていることも重要だ。つまり、“普遍/不変的な愛の音楽”としてのディスコを題材にチョイスしつつ、それを生んだクィア・ブラック・コミュニティの人々の差別との戦いにも敬意を捧げられた、シリアスな愛に関する作品なのである。決して軽く見過ごせまい。(井草七海)

18
田中ヤコブ
おさきにどうぞ
Newfolk / Mastard Records
作詞作曲歌唱演奏の全てをこなす宅録マエストロとしての才能を全方位に知らしめた『お湯の中のナイフ』から2年。大学時代の仲間とのバンド、家主も絶賛される中で届けられたこのアルバムが年間ベストに名を連ねることは、ファンにとっては予め決まっていた宿命のようなもの。しかしそうした外野の勝手かつ過大な期待をよそに、今作においても相変わらず彼は部屋の中で孤独にどんづまり、世間と折り合えない諦念を万人に開かれたポップ・ソングとして届けずにはいられないというアンビバレンスの真っ只中にいるように見える。そしてその姿がステイホームを強いられる中でも他者とのつながりを求めていた2020年の私たち自身と重なることにより、作品に切実なリアリティーと、救いにも似た力をもたらしたように思う。『おさきにどうぞ』というタイトル通り、前衛を競わず、普遍を突き詰めた音楽が図らずも時代を象徴する一枚となった、愛すべき皮肉。(ドリーミー刑事)

17
Waxahachee
Saint Cloud
Merge / Big Nothing
前作『Out in the Storm』でのオルタナティヴ・ロック・テイストから一変、EP『Great Thunder』のフォーキー・サウンドを引き継ぎ、ブラッド・クック(ボン・イヴェール他)を制作陣へと迎えた一作。アートワークに写されたピックアップ・トラックと彼女自身のルーツたるアラバマのライセンス・プレートに象徴される、ルシンダ・ウィリアムスを影響源としたアメリカーナ・サウンドが設計された。時に引きの美学も感じるカラっとしたサウンドの通りの良さに導かれつつ、「Fire」や「Lilacs」で顕著に響き渡る、喉から絞り出すようなエモーティブなヴォーカルが本作の最大の魅力。昨年にはほぼ制作が進行していたというが、自身の経験も踏まえアルコールと薬物依存からの回復と自己の再帰的構築をテーマとした本作は、2020年という内省の時代にアクチュアルに届いた。(尾野泰幸)

16
冥丁
古風
Kitchen Label / Inpertment
“LOST JAPANESE MOOD”をテーマに掲げた三部作の結びとなる本作は、前々作『怪談』、前作『小町』と同様に全体を包み込むようなヒスノイズによって聴く者を日本のどこかに存在した、今や失われてしまった(だがぼんやりとイメージできる)景色へと誘う。とりわけ本作ではヒップホップ的なサンプルが多く使用され、その騒々しさすら感じさせるサウンドから「貞奴」や「女房」、「花魁」など女性の姿(ジャケットを見てもわかりやすい)が鮮明に浮かび上がる点が特徴といっていいだろう。重要なのは、その美しさは“古き良き日本”などと安易に呼ばれるべきものなのか、判別するのが難しいということ。そうして本作は“失われてしまった”ことを逆説的に証明しながら、そこには確かに命を燃やした人々がいたというひとつの真実を音の中に立ち上げていく。喪失の中にこそ、希望が隠されているのではないか? そんな問いかけを宿した、実に批評的なアンビエント・アルバム。(高久大輝)

15
Sam Gendel
Satin Doll
Nonesuch
LA拠点のこの人の神出鬼没な活動は実に刺激的だ。今年はフル・アルバムを2枚(本作と『DRM』)をリリースしているし、サム・アミドンやブレイク・ミルズら他アーティスト作品への参加も多数。のみならず、ソロ=fresh breadとしてBandcampに次々と楽曲やその断片をアップしたり、頻繁にインスタ・ライヴをやったり。ジャズ、現代音楽、エレクトロ、ヒッピホップ、アンビエントなどを横断しつつ、肉体的な演奏とラップトップ・ワークとを巧みに、かつユニークに織り交ぜて仕上げるスキルと知性もある。チャールズ・ミンガスやデューク・エリントンなどのカヴァーも含むこの《Nonesuch》第一弾作は、ライ・クーダーもツアー・メンバーに抜擢するほどの腕前を持つサックス奏者という評価に終始しないそんな彼の、本名へ改名後の集大成的1枚。海外メディアはほぼスルーしているが、現代アメリカきっての鬼才であることは断言できる。(岡村詩野)

14
Le Makeup
微熱
Pure Voyage / EM Records
Le Makeup=井入啓介は、オンライン・アンダーグラウンドとUKベースのエッジ、そのムードをめいっぱい吸い込んだプロデューサーとして登場した。その後関西のコミュニティを味方につけながら、彼は次第にルーツであるロックのエレメント——ギター、そしてヴォーカル――を前景化させていった。この『微熱』は、昨年《Ashida Park》から発表した『Aisou』、そしてプロデューサーとして携わったDoveの『Irrational』に続く、待ち望まれていたファースト・アルバムだ。冒頭、「Beginnings」からして、フランク・オーシャンの「Biking」などを思い起こさせる。だが、そう思うよりも前に歌とフロウが、言葉がまっすぐに飛び込んでくる。“この音は肌で この言葉は僕の血だ”。日々の記憶と思考が落とし込まれた生々しいリリックはエレクトロニックなプロダクションの中から屹立し、何にも似ない孤独な肌ざわりを持ちえている。Le Makeupの『微熱』は血が通った極めてパーソナルな表現であり、憂いとエレクトロニック・ミュージックとの緊張感あふれるせめぎあいから生まれた、どこかかなしげな、しかしとてもエモーショナルなレコードである。(天野龍太郎)

13
Sufjan Stevens
The Ascension
Asthmatic Kitty / Big Nothing
新たなディケイドへの期待も虚しく、何もかもが飽和点を迎えてしまった2020年。スフィアン・スティーヴンスの眼差しからも情愛や思慕のあたたかみは薄れ、祖国アメリカ、そしてこの世界への絶望と諦念が悲しいほどにはっきりと見てとれる。ドラムマシンとシンセサイザーを基調に統制された肉感的なデジタル・ビートに、インストゥルメントの鳴りやメロディの抑揚を抑えた禁欲的なサウンドスケープ。どこか冷たく不穏な空気を纏いつつも天界のように甘美に響くその様に、この不安こそが快楽のような、混迷と安息が同居しているような、そんな倒錯を覚えてしまう。だがこれは現実逃避などではなく、「一度死んで再生しないといけない」と語るスフィアン。行き詰まった時代に解体と再構築の楔を打ち込まんとするその表現は、2020年のムードをあまりに鮮やかに描き出してしまった。僕らはもう後戻りできない。そして時代はまたここから流動する。(阿部仁知)

12
Yves Tumor
Heaven to a Tortured Mind
Warp / Beatink
イヴ・トゥモアはクィアネスがエクスペリメンタルを拡張した2010年代の、その先鋒のひとりだった。アルカ、ロティック、アースイーター……音の実験が性の自由を広げていくなかで、ノイズやIDMとソウルをキマイラ的に結びつけていたイヴ・トゥモアは、そして、本作で堂々たるグラム・ロックへとたどり着く。グラマラスに生きること……それこそが、いまもっとも抑圧されていることだからだ。いまやファッショナブルからほど遠いとされる70年代英国ハード・ロックのギター・ソロを引っ張り出し、それに合わせて本人が愛を絶唱する。異形の愛を。かつてグラム・ロックが掬ったのも、そのようなものだったろう。自分がこの世からはみ出していると感じる子どもたちのファンタジーを解放し、その先にある官能を祝福すること。ブラスが高らかに鳴る「Gospel for a New Century」はありったけのロマンを握りしめ、新世紀のロック・アンセムとなった。(木津毅)

11
環ROY
Anyways
B.J.L. X AWDR/LR2
ラップ/トラック全編セルフ・プロデュースとなる本作では環ROYが磨き上げてきた半径数メートルの壮大な世界観が凝縮されている。「Protect You」で見せる精緻な情景、心理描写が『Anyways』の幕開けであり全てだ。日常を戦争と呼び、大切な人(あるいは場所か物か事か)を守るための確固たる決意表明。アブストラクトでエクスペリメンタルな楽曲の数々は肌寒い街を歩きながら聴くにふさわしい。環ROYの地に足つきすぎている言葉と声がその足取りを無重力のように軽くさせてくれるだろう。《TURN》が行ったインタビューに依れば2019年末にはアルバムが完成していたということだが、当たり前が当たり前でなくなった今、目の前のありふれた景色を目に焼き付けながら彼の紡ぐ音楽に五感全てを委ねたい。歩くことすら、これは戦争。『Anyways』というタイトル通りなりふりかまわず大切なモノを守り、生き抜いていこうではないか。(望月智久)

10
Adrianne Lenker
SONGS
4AD / Beatink
コロナの影響からビッグ・シーフのツアーが延期されたことで、ぽっかりと空いてしまった時間と、元々多作な彼女の溢れ出る創作意欲·才能が良質な形で実を結んだ傑作。“アコースティック・ギターの中にいるようなレコード”を目指したという本作は、アナログ機材を田舎のキャビンに持ち込み、自然な音をそのまま取り入れながらバイノーラルでレコーディング。その結果もあり、スタジオワークでみっちりと作り込んだような“量としての時間”はないが、さらに長い観念的な時間軸の世界へと引きこむ不思議な幸福感をもたらす作品となった。フレットの擦れる音、アコースティック・ギターとともに静寂の中で囁く雨音や風音、鳥のさえずり、虫の羽音は、まるで時の移ろいの音そのものだ。音響面からはアンビエントや、フォーク、トラッドの要素、あるいはバート・ヤンシュやジョン・フェイヒィの影響を思わせるミニマルなギター・サウンドなど、彼女のミュージシャンとしての幅広さを多面的に楽しめる1枚だが、根幹に流れるのは、強迫的な“時”の圧力から開放されて、静かに悠々と身を任せようと語る、豊かなヒーリング・ミュージックである。(キドウシンペイ)

9
岡田拓郎
Morning Sun
only in dreams
3年ぶり2作目のソロ・アルバム。前月に出ているduennとの共作『都市計画』と並行で制作を進めていたらしく、ギタリストとしての仕事も含めると恐ろしい活躍ぶりだ。スケールの広い音場、けむを巻くように遠ざかるヴォーカルといった、前作『ノスタルジア』までの彼に共通していたスタイルから舵を切り、“歌もの“としてより距離が近く、はっきりとした手ざわりのある作品となっている。増村和彦と谷口雄によるミニマルながらもダイナミズムのあるプレイに、打ち込みめいたソリッドな録音。それらを絶妙に配置した立体的なサウンドに、あてどない哀しみをそばで耳打ちしてくるような岡田のヴォーカルが乗っていく。そこにあるのは、言葉にならないまま霧散する思念のかけらを逃さず拾い、それらすべてを継ぎ合わせようとする鋭さと誠実さだ。言葉の外側にこぼれ落ちていく思いに光を当てる——ポップ・ミュージックが持つそんな役割がここに凝縮されている。(吉田紗柚季)

8
Phoebe Bridgers
Punisher
Dead Oceans / Big Nothing
複数のサイドプロジェクトを経てのリリースとなった、3年ぶりのセカンド・アルバムは、それらの活動で親交を温めたアーティストも集結、結果としてLAを中心にUSインディーのキーマンを揃えた作品に。ブレイク・ミルズを招いた「Halloween」等での静謐さとスケール感のバランスの深化、「Kyoto」でのアップリフティング路線へのシフトなど、音楽的挑戦が随所に見られるが、その主導権が豪華参加アーティストではなく、あくまで彼女自身にあることを感じさせられるのが今作のポイントだ。自身のレーベルの立ち上げという今年のトピックも、その証拠。前作収録の「Motion Sickness」では、強迫的なパートナーとの決別を歌ったが、今作での彼女は周囲に振り回され乗り物酔い(=Motion Sickness)していた過去を払拭し、自分の手でハンドルを握ってドライブしていく。仄暗い内側の世界に浸るのはここで終わり──<The end is here>と歌い、絶叫しながら、新たな“はじまり”へ向かう意志を感じさせる1枚。(井草七海)

7
Bob Dylan
Rough and Rowdy Ways
Columbia / Sony Music Japan
通算39枚目にしておそらくキャリア上もっとも優れたアルバムのひとつ。齢79歳にしてこのような前人未到の音楽世界を作り上げるボブ・ディランという人は、改めて本当にすごい。先行シングルとしてリリースされた17分にも及ぶ「最も卑劣な殺人(Murder Most Foul)」を中心として、様々な歴史的出来事や固有名詞を多数織り込むリリックは、まるでそれ自体が彼自身の個人史とアメリカ現代文化史を内包するかのようなめくるめくもの。歴史と記憶、文化と社会、コミュニケーションと孤独、音楽と私。聴くもののあらゆる思考を詩的に起動させながら、芳醇な饒舌で慰撫する。今世紀に入ってから目立ってきたクセのある歌唱も、むしろ枯淡の境地に達した感あり。スタンダード・カヴァー集を経たゆえか、機知に富んだ和音構成も味わい深いし、もちろん、演奏面の充実も素晴らしい。レギュラー・バンドに加え、ブレイク・ミルズやフィオナ・アップルという“今年の顔”が参加しているのにも注目。(柴崎祐二)

6
Moses Sumney
græ
Jagjaguwar / Big Nothing
清冽な歌声は天の使いのようでいて、他方、地に這いつくばり、おのれのマスキュリニティにもがき苦しむ一人の男を描いた「Virile」。そこに筆者が見たのは、聖と俗。“白と黒の中間色”たる今作は、そのように、おのれの中に宿るいくつものアイデンティティに引き裂かれんとする、生々しい彼自身の姿そのものだ。ガーナ出身のアメリカ人という二重性を自覚しつつ、カントリーにも、ソウルやゴスペルにも影響を受けた彼は、その多元的なルーツを今作では、これまで以上に隠し立てしない。そして立ち現れたのは、フォーキーな弾き語りがさらけ出すフラジャイルさ、アンビエントなサウンド処理が引き出す神秘性さ、野性味溢れる爆発力……。定まらない、いや、あえて定めようとしない音楽性を収め切るのに、2枚組という長さは必然だったのだ。その複雑さがにわかに理解され得ないことを知るがゆえか、繰り返される<isolation>という言葉。孤独を抱え茫洋と漂う自らを、“グレー”な状態のまま打ちたてようと試みた意欲に敬意を表したい。(井草七海)

5
Taylor Swift
folklore
Republic / Universal Music Japan
数年先まで決まっていた多忙なスケジュールは、コロナウイルスによって停止を余儀なくされた。そんな状況から本作の制作は始まった。旧知のジャック・アントノフと、兼ねてより愛聴していたザ・ナショナルのアーロン・デスナーをプロデューサー兼コンポーザーに、そしてボン・イヴェールも迎えて制作することを彼女自身が希望して依頼、リモート・ワークで完成させた。この作品は、アリーナの大観衆を沸かせるようなこれまでのサウンドとは異なる。自宅にいる間に観賞したという様々な映画から着想したイメージを用いて、まるで一冊の短編集のように紡がれた16篇の歌詞は、全編に敷かれたアコースティック主体の静謐で奥行きのあるプロダクションと、語りかけるような歌声によって、その繊細な描写を瑞々しく表現している。予定外の創作に向き合う時間が生まれたことで、観賞し、詩を書き、曲を作り、歌い、普遍的な作品を作ろうとするSSWとしてのプリミティヴな探究は加速、その可能性を一気に広げた作品となった。(加藤孔紀)

4
Charli XCX
how i’m feeling now
Atlantic / Asylum
TWICEのようにキャッチーな楽曲群が、聴くほどにツイストしていく。チャーリーXCXは、ジャンルとしてのポップ・ミュージックの形式を使いながら、それ「らしくない」ムードやニュアンスを醸造し続けている。そのために、やはり奇才と呼ぶほかない才人、A. G.クックの参加は欠かせないのだろう。アートワークにも反映されているように、ロックダウン期間中、自室に籠り、SNSを通じてファンと交流する中で制作された本作は、XCX主宰のポップ実験室の最新成果と呼ぶべき充実した作品に仕上がった。ただ、ポップ・ミュージックを(良い意味で)弄び、その綻びを広げて楽しんでいるとき、作家の頭の中に更新性や完成度といったお題目は、おそらくは存在していない。ツイストした(してしまった)人々とつながるためだけに生まれた音楽。そのピュアな欲望の触感こそが、本作の強度を支えている。率直なタイトルが、詩的な印象を残す作品だ。(坂内優太)

3
Fleet Foxes
Shore
Anti-
バンドからはロビン・ペックノールドのみが参加し、コロナ禍で彼自身の自己隔離中に制作された。ウイルス感染の拡大を懸念する状況が続く一方、BLMをはじめとする差別や格差などの問題が一気に表面化し、世の中を覆っていた今年。ロビンは「音楽は最も必要ないものであり、最も必要なもの」と感じていたのだという。多くの人が不安や無力感を感じていることを認識しながら、音楽の存在意義を問うていた彼が今作で響かせたサウンドは救いのようでもあった。前作に続き、今作でも自然をテーマにしながら、遠くこだまする歌声が広大な景色を連想させ、サンプリングされた鳥のさえずりはポリリズミックに反復するピアノのフレーズと交わって神秘的な側面を強調する。淀みのない歌声の多重録音とコーラス、管楽器のハーモニーは、まるでアンビエント・ミュージックのように癒しの効果を運んできた。当たり前に存在している自然への気付きはやがて音楽に昇華され、その意義が最も求められた年に真価を証明してみせた。(加藤孔紀)

2
Perfume Genius
Set My Heart On Fire Immediately
Matador / Beatink
“僕の人生の半分は終わった”、“ゆっくりと僕はそれを置き去りにする”という本作の幕開けは、過去との決別も、新たな旅立ちも意味しない。これは、可能性についての歌である。前作『No Shape』と同様にブレイク・ミルズの手がける大胆かつ繊細なプロダクションによって素肌を直接撫でるように鼓膜を揺らす音。そしてアメリカ音楽の歴史に接続し、自らのクィアネスを以って再構築していくかのようなソングライティングはサム・ゲンデルらによる多彩なアレンジも相まって、これまでで最もポップな花を咲かせている。何より持ち前の甘く美しいメロディに乗せて届けられる言葉は、セクシャル・マイノリティだけでなく全ての人々を包み込むように、痛みと快楽についてクエッショニングしていく。全ては結果だが、同時にプロセスでしかない。欲望を探求すること。それは次の瞬間に全く別の自分へと変化する可能性である。我々が音楽を聴く理由のひとつがここに詰まっているのではないかとさえ思わせる、パフューム・ジーニアス史上、最高傑作。(高久大輝)

1
Blake Mills
Mutable Set
Verve / Caroline International
ボブ・ディラン、パフューム・ジーニアス、フィービー・ブリジャーズ、サム・ゲンデル……2020年を代表する彼らの新作に共通して参加する人間交差点のような存在である。LAシーンの成熟を象徴する支柱的重要人物と言ってもいい。だが、ロブ・ムースやサム・ゲンデルらも参加したこのソロ作では、アラバマ・シェイクスなどの現場で培ったプロデューサーとしての批評的目線を維持しつつ、ジャズ、フォーク、クラシックなど様々なスタイルに長けたギタリストとしての新たな奏法、音色創出にも着手。さらにアメリカーナの歴史に向き合う学究肌でありながら、イノヴェイティヴな録音術にも踏み込み、それでいて歌ものとして丁寧に聴かせる包容力も野心的に見せつけた。中でも素朴なフォークを基調にアンビエンスを絡ませ展開させた「May Later」が出色。海外メディアの年間ベストが黙殺するとはまこと信じられない、伝統と革新を纏いながらプログレスさせるまさに“可変的”大傑作だ。(岡村詩野)
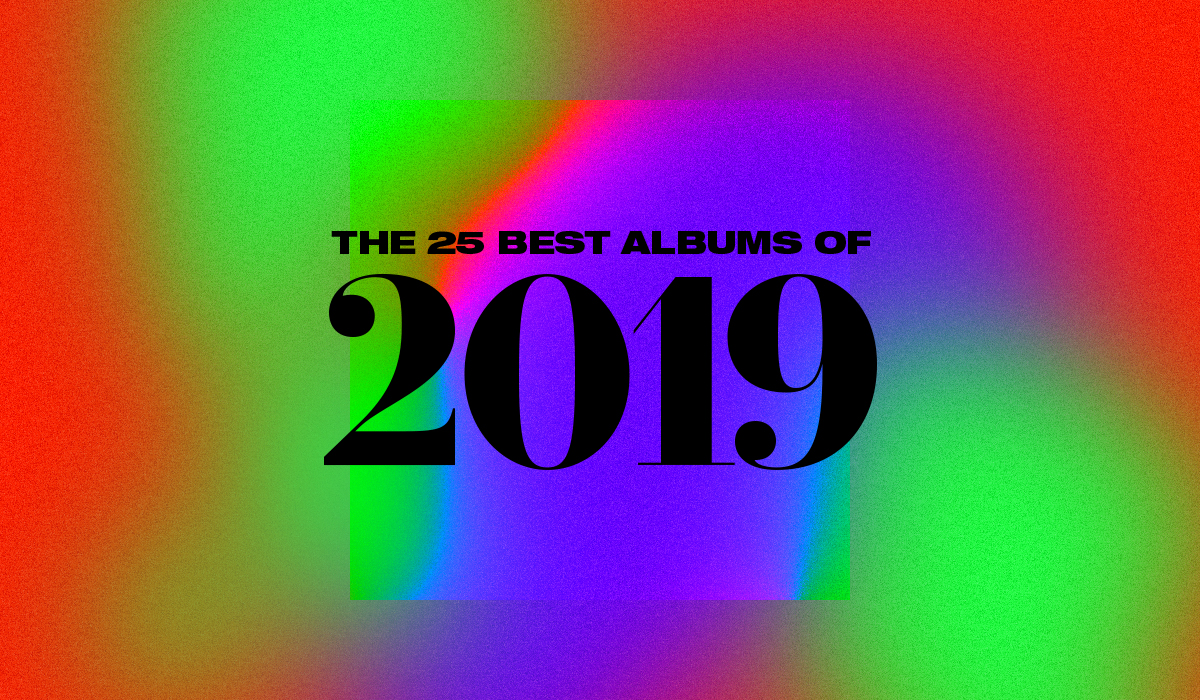
THE 25 BEST ALBUMS OF 2019

THE 25 BEST ALBUMS OF 2018
Text By Shintaro YonezawaSho OkudaHitoshi AbeRyutaro AmanoTomohisa MochizukiSayuki YoshidaDreamy DekaTsuyoshi KizuShino OkamuraYuji ShibasakiYuta SakauchiNami IgusaDaiki TakakuKoki KatoYasuyuki OnoSinpei Kido
