あの頃、追いかけた野望と栄光
〜オアシス アルバム・ガイド〜
昨年、英国サッカーのクラブ・チーム、マンチェスター・シティーがチャンピオンズ・リーグで優勝したことによってオアシス再結成の期待がにわかに高まった。「マンCが優勝したらオアシス復活の可能性があるか?」というファンからの問いに対し、「準備はできている」とリアム・ギャラガーが回答。今のところその兆しは見られないが、ファンの間で大きな話題を集めたことは記憶に新しい。気がつけば、デビュー・アルバムから今年で実に30年、ノエル・ギャラガーの脱退を機に解散となった2009年からも15年になる。
90年代以降、ロックンロールのカタルシス、あるいは危うさを常に孕ませた重要バンドであったばかりか、スターとしての輝きを放ち、多くのヒット曲を持つメロディ・メイカーとしての才気を伝えてきたオアシス。英マンチェスター出身のノエル&リアム・ギャラガー兄弟が再び手を組むことがあるかどうかは誰もわからないが、ともあれ、彼らの作品に触れるとロック・バンドの醍醐味を今なお実感させられることは間違いない。
そこで改めてオアシスのオリジナル・アルバムを中心とする重要作をまとめたディスク・ガイド記事をお届けする。同じ94年にファースト・アルバムをリリースしたアウトキャストのディスク・ガイド記事と合わせてお楽しみください。(編集部)
(ディスク・ガイド原稿/岡村詩野、尾野泰幸、高久大輝、髙橋翔哉、吉澤奈々 トップ写真/Jill Furmanovsky)
『Definitely Maybe』
1994年 / Creation

「“Definitely(間違いない!)”と言い切った後に、“Maybe(たぶんね)”と付け加える。それが俺たちマンチェスターの仲間内で今流行ってる言い方なんだ」。そう話してくれたのは、まだデビュー曲「Supersonic」1曲しかリリースされていなかった94年春にロンドンで取材に応じてくれたリアムだ。その数日前にノーウィッチの小さな古い教会跡地で観たライヴも、「Shakermaker」や「Live Forever」……つまりこのファースト・アルバムに収録されている曲を既に多く披露していたものの、フロアにはハッピー・マンデーズのベズそっくりの踊りで盛り上がるファンもいたりして、ビートルズの再来というよりも超絶メロディックないい曲を演奏する強力なマンチェスターのバンド登場、という印象だった。実際、本作のプロデュース(一部)は直近のニュー・オーダーやエレクトロニックなどを手掛けていたオーウェン・モリスだし、録音の音質こそ粗いがノエルのギターは少しジョン・スクワイアを思わせる瞬間もある。ノエルがインスパイラル・カーペッツのローディーだったという事実を抜きにしても、マンチェスター人脈をお手本にしたことがわかる音作りなのは間違いない。そうした仁義のようなものを尊びつつも、その先達の誰よりもポップな曲と破天荒なまでの華やかさで彼らは時代のトップランナーへと走り出す。1曲として要らない曲がない完璧なこの初作で。1曲目の歌詞そのままの、堂々たるローカル下剋上のロックンロール・スター宣言だ。(岡村詩野)
『(What’s The Story) Morning Glory?』
1995年 / Creation

誇張しているわけではない。おそらくリアルタイムでは聴いていなかった世代もたくさんいたはずだ。だがバンドがオアシスの曲をプレイするたびに、周りにいた全員が声を張り上げて歌っていた。《SUMMER SONIC 2023》(幕張)の2日目、リアム・ギャラガーのステージである。セットリストの12曲の内、6曲がソロ、あとの6曲がオアシスの曲で、さらにその内3曲は本作からの選曲だった。「Morning Glory」「Wonderwall」「Champagne Supernova」。「Don’t Look Back in Anger」も含め、これらの曲以外もアンセムだらけのアルバムだ。ちなみに《SUMMER SONIC 2023》を俯瞰してみれば、リアムはメイン・ステージのトリ前、ブラーが別日のメインステージのトリ、という状況で、いわゆる「バトル・オブ・ブリットポップ」と呼ばれたある種の代理戦争の成れの果て?を映しているようにも見えなくはないが、そんなものはもはや関係がなかった。いや、もちろん当時を体験している方にはまた違った見え方をしていたと思うが、間違いなく輝いていたのはリアムより、バンドより、オーディエンス一人ひとりだった。どの時代もポップ・ミュージックはリスナーの人生と共にある。あの日、あの時間は、そんな真実を照らしていたはずだ。世界で約2200万枚売れたのは伊達ではない、オアシスの最も“歌える”アルバム。(高久大輝)
『Be Here Now』
1997年 / Creation

歴史的傑作『(What’s the Story) Morning Glory?』(1995年)での世界的大成功とネプワースでの伝説的ライヴを経て、ブリットポップという時代が分水嶺を迎えようとするなかでリリースされた3作目。
アコースティック・ギターをメインに作曲が進められた前作までとは一転、エレクトリック・ギターを軸に作曲された本作は、ヘヴィーでノイジーなギターをフィーチュアし、ストリングスやピアノを挿入しつつメロディアスに仕上げられた良くも悪くも“オアシス”流の模範的ロック・バラード楽曲が中心。一曲が6、7分にも及ぶ長大な「Stand By Me」、「The Gilr In the Dirty Shirt」、「All Around the World」といった楽曲も多い。バンドの成功とともに肥大化した商業主義と、制作現場内外で繰り返し使用されたというドラッグによって弛緩したメリハリのない楽曲群に対して向けられたセルアウト批判は、前作・前々作が偉大過ぎるゆえの反動でもあっただろうし、本作以降、過去の幻想をファンもバンドも追い求めたが、ついにそれは2023年の現在まで実現してはいない。
それでもなお、本作を魅力的なロック・アルバムたらしめているのは「I Hope, I Think, I Know」、「It`s Gettin` Better」といった楽曲のエモーショナルでぶっきらぼうなリアムのヴォーカルと、大胆不敵なオルタナティヴ・ギターが醸す大文字のパワー・ポップの屈託のなさ。そこで鳴り響く胸の奥に刺さり、二度と外れることがないような愚直なポップネスこそ、いま本作からロック・ミュージックが読み取るべきものだと思う。(尾野泰幸)
『The Masterplan』
1998年 / Creation

ブラー『Blur』(1997年)、レディオヘッド『OK Computer』(1997年)とブリットポップの瓦解を象徴するリリースと同年に、一方で僕らはここにいるよ(Be Here Now)とブリットポップとの心中を決め込んだオアシスがその翌年に放ったB面集。多くの楽曲はファースト『Definitely Maybe』とセカンド『(What’s The Story) Morning Glory』と同時期に書かれ、なるほど各楽曲のクオリティには、B面という先入観を抜きにして目を見張るものがある。そして当時のオアシスを象徴するシューゲイザー的なギターのウォール・オブ・サウンドはどこまでも酩酊的で全能感あふれるもの。「Acquiesce」や「Listen Up」を聴き直してほしい。嗚呼、こりゃもうだめだ! 多くのファンやメンバー自身が、進歩する足を止めてでも変わらずにいたがった気持ちが分かりすぎる。さて、このオアシス流『Past Masters』である本作とスタジオ・アルバムとの違いを指摘するとすれば、スタジアム・ロック的なシンガロングできるコーラスが意外にも少ないことだろうか。すなわち音圧の強弱と歌い上げるヴォーカルによって楽曲に展開をつけるEDM的なソングライティングを、意図してなのか避けた楽曲がB面に集められたということ。A面曲の引き立て役にとどまらず、単体で確固たる強度をもった楽曲を生み出していたノエル・ギャラガーには驚かされる。しかしその後オアシスがしばらく苦しいキャリアを送ることになるのは、ノエルたちがファンダム以上に、その優れたソングライティングへの信仰を手放せなかったことに理由がある気がする。(髙橋翔哉)
『Standing on the Shoulder of Giants』
2000年 / Big Brother

オリジナル・メンバー2人の脱退、《Creation》の閉鎖という出来事を経て、本作でバンドは自らもその中心に担ぎ上げられ、過去のものとなったブリットポップの幻想を振り払うかのようにサイケデリック・ロックへと接近した。
アルバムのハイライトはノエルがドラッグを絶とうとした際の経験を描いた「Gas Panic!」。幾重にも重ねられたギター、縦横無尽に跳ね回るシンセイサイザー、 ハーモニカ、フルートが混在して生み出されるサイケデリアはまさに本作を象徴するかのよう。オープニング・トラック「Fuckin’ In The Bushes」でのドラム・ループの重用、シタールやメロトロンが響く「Go Let It Out」、シンセサイザー・リフが印象的な「Put Yet Money Where Yet Mouth Is」など各所に仕込まれた小技も過去の作品にはみられないもの。
前作までの大仰なスタジアム・ロック的意匠を相対的に後退させ、サウンド・プロダクションの実験と更新に挑戦したといえば聞こえはよいが、本作がバンドの混乱と混迷の打開策として効果的に機能したとは今日に至っても言い難い。自らの身の回りを取り囲むゴシップについて歌った「Roll It Over」でメランコリックなメロディーと泣き叫ぶようなギターを背景に歌われる「Does it make it all right?/It doesn’t make it all right(これでうまくいくのだろうか/これでうまくいくことはないだろう)」というリリックが今となっては胸に迫る。
(尾野泰幸)
『Familiar To Millions』
2000年 / Big Brother
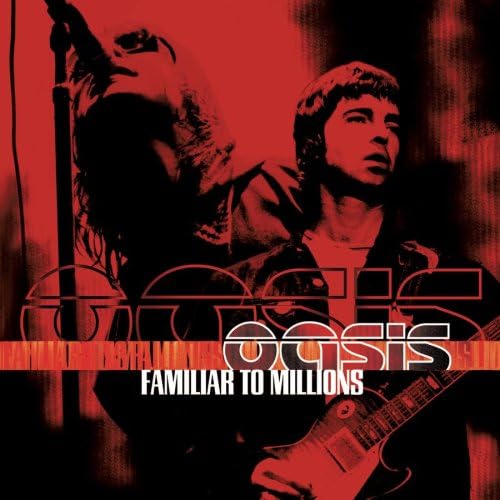
オアシスの来日公演で思い出深いのは94年9月の渋谷クラブ・クアトロと09年の幕張メッセ、つまり最初と最後だ。マンチェスターの垢抜けない若者然とした94年と、堂々たる風格でショウを見事に演じた09年……比べるのも野暮なほどあらゆる事象が変化していたが、囚人のごとく手を後ろに組んで歌うリアムと、その横で黙々とギターを鳴らすノエルは不思議なほど何も変わっていないように思えた。結局ギャラガー兄弟は“ポップなフックのある曲をギミックなしに強かに聴かせる”ことへの執着で結ばれている。00年7月の英《Wembley Stadium》公演を収録した本作は、兄弟の仲はガタガタでリアムのコンディションも日によって酷いものだった時期のもの(「Wonderwall」の歌は同年の横浜公演のものに差し替えられている)。だが、そんなことどうでもいいと思えるほど、会場のエネルギッシュな盛り上がりに感動する。確かにライドのアンディ・ベルとヘヴィー・ステレオのゲム・アーチャーという新加入した《Creation》人脈の二人がうまく整合しているとは言い難い。リアムのヴォーカルもいくらなんでも荒っぽ過ぎるだろう。でもそれがどうした。これがロックだ。ロックの歴史の中に今自分たちがいて継承しているという自負と、ニール・ヤング「Hey Hey, My My」、ビートルズ「Helter Skelter」のカヴァーのみならず、「Cigarettes & Alcohol」の終盤でレッド・ツェッペリン「Whole Lotta Love」のフレーズを引用するような彼らの真摯で無邪気な姿勢を誰も否定などできない。(岡村詩野)
『Heathen Chemistry』
2002年 / Big Brother

リズム・ギターにヘヴィー・ステレオのゲム・アーチャー、ベースにライドのアンディ・ベルを新たに迎え、ドラムのアラン・ホワイトは最後の参加となる5作目。こうしたリズム隊の変化によるものだろうか。4作目で顕著だったグルーヴや雑然とした推進力はほとんど感じられない。むしろ、サウンドは簡素になり構成もシンプルになった。メンバー4人が作曲を行なった本作はその状態を映すように瑞々しく、かつブリティッシュ・ロックを継承している。なかでも、リアムによる楽曲は明確に思えた。わずか2コードと繊細なピアノによる「Songbird」、繰り返されるフレーズからジョン・レノンの「Working Class Hero」を強く想起させる「Born on a Different Cloud」と対照的な曲調になっている。更には、重い雰囲気を引き摺ったままギター・リフの入り混じる「Better then」へと流れる様は、次作への前触れのようでもある。そういった点で言えば、ゲムが手掛けた「Hung in a Bad Place」も6作目への布石となっていたのだろう。とはいえ、オアシスのアティチュードは健在。バラード・アンセム「Stop Crying Your Heart Out」からノエルの一段と力強いヴォーカルが響く「Little by Little」まで、それぞれの成長がめざましい。こうしたバンドの前進を落ち着いたと捉えるか、充実したかで言うのならばもちろん後者だろう。(吉澤奈々)
『Don’t Believe the Truth』
2005年 / Big Brother

まさかの大復活と言っていいだろう。『Be Here Now』以降か、モダンで多彩な音色を試してみたり、ノエル以外のメンバーも作曲に参加してみたり。その上でどこか伸び悩んでいたオアシス。それを打開したのは原点回帰とも言うべき、ザ・ローリング・ストーンズやザ・ビートルズを恥ずかしげもなく模倣したソングライティングだった(本作のドラムはリンゴ・スターの息子、ザック・スターキーが叩いている)。オルガンやカウベルなど60年代後半のロックを思わせる「The Importance of Being Idle」のプロダクションはさながら後期ビートルズだし、リアムが作曲した「The Meaning Of Soul」や「Guess God Thinks I’m Abel」もストーンズ全開でなかなか愛嬌がある。「Mucky Fingers」や「Lyla」の無骨とも言えるシンプルなアレンジは、ビートとラップだけで構成された音楽を日常的に耳にする現代においても通用するのではないか(本作を聴いていると、ノエルがトラップ時代のプロダクションに目配せした2017年のソロ作『Who Built The Moon?』を思い出す)。ここにはもう、グラム・ロックの力を借りた歪んだギターも、アシッド・ハウスの洗礼を受けたマンチェスターのドラッギーな景色も見当たらない。それでもオアシスは、ビッグであることが最大のレゾンデートルとなってしまうロックスターの呪いを振り払った。手垢のついたメソッドや目新しいプロダクションによってではなく、自分たちのルーツとなった音楽に立ち返ることによって。(髙橋翔哉)
『Dig Out Your Soul』
2008年 / Big Brother
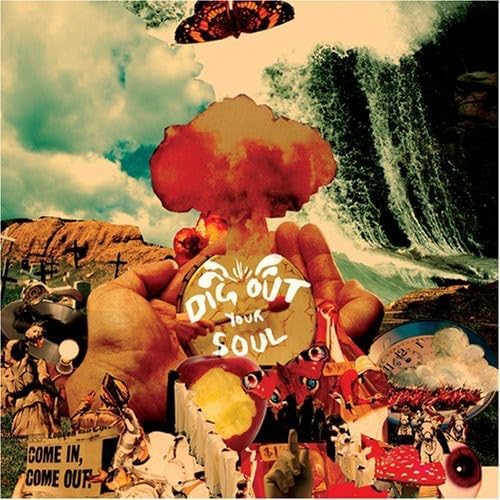
『Dig Out Your Soul』の言う魂はなんだ? ロックンロール? 答えはノエルが冒頭の「Bag It Up」について語った<反芸術的な声明>にあると思っている。アート・スクールに通わない、公営団地出身に生まれた自分たちを誇りに思うこと。つまり、ここから生まれたオアシスとしての歩みを十分に肯定していると感じるのは、私だけだろうか。7作目となる本作から聴こえてくるグルーヴにはそんな彼らの背負う野心、気迫を感じずにはいられない。特に、アルバム前半の「The Shock of the Lightning」までオアシス特有のメロディアスで解放的な楽曲が続いていく。ノエルによる楽曲は、ベースとギターに比重を強く置いた90年代のロックを彷彿とさせつつ、同時に敬愛するU2を想わせるスケールがある。一方で、リアムのヴォーカルはバランスの取れた表現が伺える。バック・コーラスを取り入れた「The Turning」では感情を抑えた歌い回しから、ラフな盛り上がりまで前面に出過ぎていない。かと思えば、自身の作曲した「I’m Outta Time」はしっとりと情緒的なファルセットを聴かせるなど、堂々たるフロントマンの姿がある。 <自分たちの道を行け>そう聴こえてくるようなアルバム・タイトルを冠したのが、オアシスの最後のスタジオ・アルバムとなった。現時点では。頭では分かってはいても、そう付け加えたくなるバンドはそうそう見当たらない。(吉澤奈々)
Text By Shoya TakahashiNana YoshizawaShino OkamuraDaiki TakakuYasuyuki Ono
