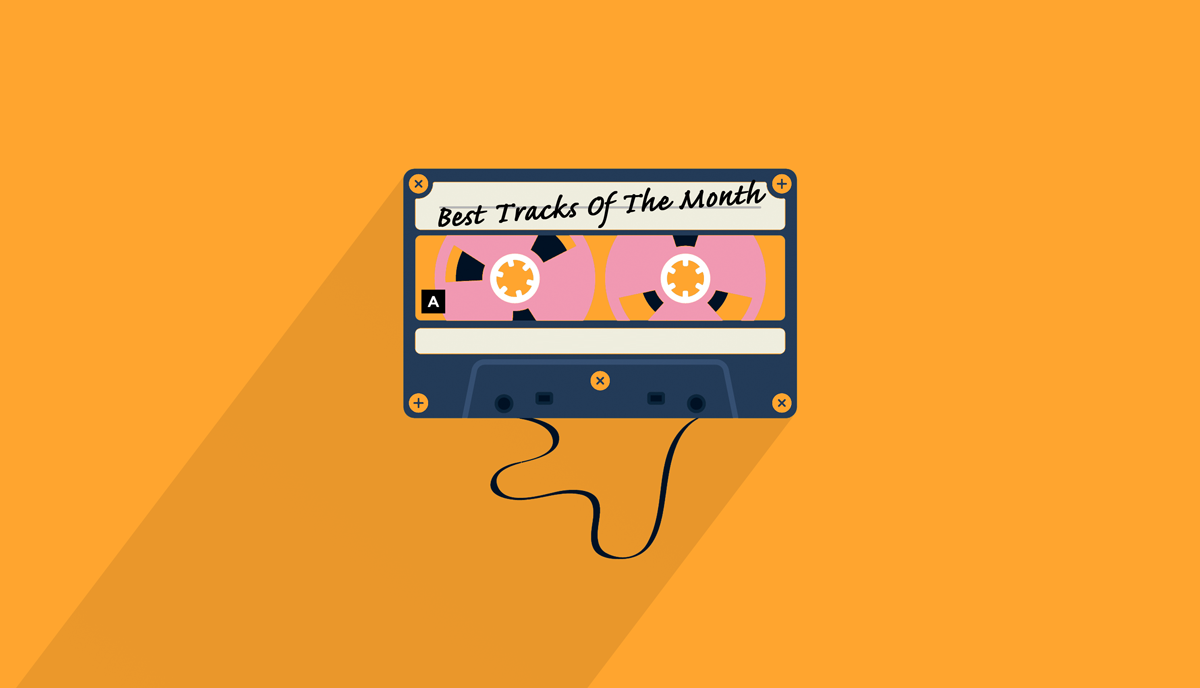BEST 14 TRACKS OF THE MONTH – March, 2023
Editor’s Choices
まずはTURN編集部が合議でピックアップした楽曲をお届け!
Beach Fossils -「Don’t Fade Away」
家族の闘病、親になること、成長に伴い増えていくノスタルジーは懐古主義ではないだろう? ブルックリンのインディーロック・シーンで沈着に活動を続けるBeach Fossilsが《Bayonet Records》より6月2日にリリースする『Bunny』からのシングル曲。『What a Pleasure』(2011年)を想起させるイントロのアルペジオや抑揚を抑えたリヴァーブの柔らかさにいつもの彼ららしさを感じるが、リリックはこれまでにないほど痛みを曝け出し時間の経過を連想させる。旧友に会いたい、不安、愛、憧れについて歌う姿は誰もが経験しうるノスタルジーをまっすぐに受容するようだ。(吉澤奈々)
Cindy -「The Price Is Right」
サンフランシスコを拠点とするインディー・バンド、シンディが4月にリリースする4作目『Why Not Now?』からの先行楽曲。シンセサイザーとギターにフィーチュアしてミニマルに構築されたバンド・サウンドと、それを柔らかに包み込むカリーナ・ギルの穏やかなヴォーカルが醸すアンビエンスがバンドの特徴と魅力を端的に伝える。類似する複数のシーンのカットアップの繰り返しによって構成されたミュージック・ビデオにおける白昼夢的表現も印象的。来る新作はサンフランシスコで活動するインディー・ポップの仲間たちを招聘した作品になっており、同地のドリーム・ポップ・コミュニティの充実を伝える一作となることにも期待。(尾野泰幸)
Joanna Sternberg -「I’ve Got Me」
2019年のデビュー作『Then I Try Some More』が日本でも静かな話題になった異形のフォーク・シンガー。いよいよ約4年ぶりのニュー・アルバムが6/23にリリース(しかも《Fat Possum》から!)となるが、この先行曲の悲哀とユーモア溢れる破壊力に、やっぱりこの人は天才だ!と快哉を叫ぶほど興奮してしまった。戦前フォークのような朴訥としたアコースティック・ギターの弾き語りだが、自分に優しくなれない自己嫌悪の塊になっている思いを「自虐の箱」と名づけ、“Take the box self-deprecation / Lock it and put it on rhe shelf”と綴るいたいけな愛らしさにズギュン。それを泣き笑いのような歌で表現する姿はもう世界遺産級だ。(岡村詩野)
Lunv Loyal – 「高所恐怖症 (feat. SEEDA) 」
現時点で、国内ラップ・ソングのベスト。Lunv Loyal作品ではお馴染みのBERABOWによるドリルビート、そしてそこに乗る2人のリリックにフロウ、どれをとっても素晴らしいのだが、制作方法も面白い。SEEDAのYouTubeチャンネル@NEETSEEDAに投稿されたショート動画によると、まずSEEDAの思いをLunv Loyalに伝え、それをLunv Loyalが受け取ってフロウとラインを構成、それをSEEDAが歌い直したそう。Lunv Loyalのプロデューサー的な手腕、さらにはSEEDAが常にフレッシュであり続ける理由も垣間見える1曲だ。(高久大輝)
Potter Payper – 「Corner Boy」
ドラマ・シリーズ『Top Boy』にTiggs Da Authorとの「Gangsteritus」が起用されUKチャートのトップ40に滑り込んだことをひとつの起点に、今ひときわ注目を浴びる存在となったPotter Payperによる今年3枚目のシングル。ディジー・ラスカルのデビュー作にしてグライムの金字塔『Boy in Da Corner』(2003年)を踏襲したタイトルを掲げ、過去を振り返って展開されるラップがヒリついたストリートの記憶を呼び起こしていく。浮かび上がる街角の情景。「目には目を、それが失ったものを悼む方法なのさ」。Potter Payperが癒えることのない傷跡に触れるとき、ヒップホップが資本主義の抱えた哀しみの旋律を奏で始める。(高久大輝)
霊臨 – 「CITY BOY」
どういうわけかいろいろなもの、特にお金をかければ手に入れられるものに、達成すべき目標とか、到達してないとヤバいボーダーとかを見いだしてしまうのは、高まりすぎた自意識からくる防衛とポジショニングなんだろう。そういう見覚えのある or 身に覚えのある仕草を、おそるべき解像度で抽出し、称揚するふりをして揶揄して、微笑みかけるふりで中指を立ててきた霊臨。この楽曲の既出のヴァージョンはもっと脱力していた気もする。だがこのリテイク版の溌剌ヴァイブスが感じさせる瞳のきらめき、あるいは無尽蔵の自信と他者への冷めた眼差しまで想像できてしまえばもう笑うしかない。まずはどうか身体と記憶で感じたり照れたりしながら聴いてください。(髙橋翔哉)
Rachika Nayar -「hawthorn」
きらめきの音色はギター。短いループの合間を大きな旋律が縫っていくような単音の連なりが、シンセサイザーの甘美な蜜に満たされることで、なめらかかつ三次元的な肌ざわりを獲得するまでの2分間。2021年の『fragments』は、エレクトロニック~アンビエント作家としてしられるRachika Nayarの、ギター主体の方法論とアイディアの立ち上がりをほのめかすための“断片集”。本楽曲は未発表曲を加えたリイシュー盤からの先行曲であり、Nayarのアメリカン・フットボールほかミッドウェスト・エモからの影響をつまびらかにするものでもある。どうかヘッドフォンで、あなたの頭上にとけだすエーテルを香らせてほしい。(髙橋翔哉)
Writer’s Choices
続いてTURNライター陣がそれぞれの専門分野から聴き逃し厳禁の楽曲をピックアップ!
bar italia – 「Nurse!」
近年盛り上がりを見せるUKシーンとはまた別ラインから登場したロンドンのバンドbar italia。これまでDean Bluntのレーベル《World Music》からリリースしてきた彼らが、ここにきてなんと名門Matadorとサイン。そして公開されたニューシングル「Nurse!」であるが、移籍第一弾には似つかわしくないほどに醒めている。スカスカなリズムにソリッドなギター、Joy DivisionのデモのようでありながらどこかThe Pastelsにも聞こえるのは気のせいだろうか。いよいよベールを脱ぎ始めたバンドからの、挨拶代わりには十分な反逆のポップ・ミュージック。(小倉健一)
Domenico Lancellotti – 「Diga」
様々な音楽家たちとの協働によってリオの地下と地上を接続してきたマエストロ、ドメニコ・ランセロッチ。馴染みあるボッサのリズムにモジュラーシンセやシンセベースといったエレクトロニカ由来の要素を掛け合わせたサウンドを得意とする彼だが、ヒカルド・ヂアス・ゴメスとのコラボによる最新作『SRAMBA』(4月28日リリース)からは、そのストイックな実験がいよいよ特異点に達したことを伺わせる芳香が存分に漂っている。先行曲「Diga」では、無機質なグリッチとコンガとサブベースとパンデイロが全く並列に置かれ、異形のカーニバルを展開している。そこに軟着陸するドメニコの弾き語りは朗らかで、だからこそ、怪奇なビートがより際立ってしまう。ウェルメイドでいてカオス、ボサノヴァによる前衛表現の極北がここにある。(風間一慶)
Hak Baker – 「Windrush Baby」
ハク・ベイカーは東ロンドンのアイル・オブ・ドッグス出身のフォーク・シンガー。アイル・オブ・ドッグスは今でこそ超高層ビルが立ち並ぶ金融街となったカナリー・ワーフに隣接し、めざましい再開発を遂げたエリアになるが、一方でロンドンでも最貧困地区も擁していた。カリブ海からの移民2世のグライムMCで、そうした貧富の差を目の当たりにしてきたハクが自らのアイデンティティを問いかけるべく、フォークのスタイルに移行したのが2018年頃のこと。以来、彼は自らの音楽をグライムとフォークの融合である“G-Folk”と定義し、家族やコミュニティ、カルチャーにまつわることを歌い続けている。6月9日にリリースされるデビュー・アルバム『Worlds End』からの先行トラックとなるこの「Windrush Baby」は、まさに彼のルーツをたどる楽曲であり、英国の歴史において移民がどう扱われてきたかを知らせる伝承歌でもある。待望のアルバムはスリーフォード・モッズの『UK GRIM』と並べたくなる作品になりそうだ。(油納将志)
Jackie Mendoza – 「Galaxia de Emociones」
21世紀のラテンアメリカ音楽を牽引する名門《ZZK Records》から発売されたJackie Mendozaの1stアルバム『Galaxia de Emociones』の表題曲。サンディエゴ在住のメキシコ系アメリカ人で、以前はNYを拠点にGingerlysなどのギターポップ・バンドで活動してきたが、ソロではウクレレなども用いて、ロザリアとアニマル・コレクティヴが出会ったような実験的なエレクトロニック・ポップを披露。この曲では空間的なシンセにサイケデリックな単音ギターが溶け込み、自身を鼓舞するようなビートとともに内面世界を告白する。彼女のこれまでの歩みの結実であると同時に、大きな羽ばたきだ。(前田理子)
マーライオン – 「春を待ちわびて – ermhoi Remix -」
昨年3月にリリースされたマー・ライオンの楽曲をBlack Boboi、millennium paradeのメンバーとして知られるermhoiがリミックス。片や朴訥としたフォーク・シンガー、片や先鋭的なエレクトロニック・サウンドを特長とするトラックメーカーという異色すぎる組合せ。聴く前はクエスチョンマークが浮かんだが、チップチューン的な音頭のリズムの上で、愛らしい声のロボットとマーライオンをデュエットさせるという斬新なアイデア、そしてそれを「良い歌」として違和感なく聴かせてしまうスキルに驚いた。結果的に浮かび上がってくるマーライオンの包容力のある歌声が、春の柔らかい陽射しによく似合う。(ドリーミー刑事)
Ryan Beatty – 「Ribbons」
LAに拠点をおくSSW、ライアン・ビーティーの4月末発売予定の最新作『Calico』からの先行楽曲。ブロックハンプトン「BLEACH」などをはじめ、現行ヒップホップ・シーンとのコラボでは、彼の参加が楽曲にメランコリックなアクセントとなっている。前作では失恋をテーマにし楽曲の順番も含めた物語として提示してきた。新作のオープニングを飾る本作の歌詞だけでは抽象的で全貌は見えてこないが、しっとりとしたピアノでの始まりから、ビートが入ってきて、ストリングスが盛り立てるという徐々に広がりを感じさせる構造は、これから語られる物語に期待感を抱かせる意味で、1曲目に相応しい楽曲だ。(杉山慧)
wannasleep – 「六十四(demo)」
2021年金音創作奬で最優秀新人賞を獲得……という枕詞も不要なほどファースト・アルバム『裸雀』で圧倒的な存在感を示したヒップホップ・アーティスト、wannasleepの待望の新曲デモ版。蛋堡やLEO王といった先人の系譜を受け継ぎながら、王羲之や魯迅といったリファレンスに象徴される美しい中国語の歌詞は健在だ。何か成し遂げたい焦燥と自己を立ち上げていく内面的混乱の中でwannasleepは「たとえ青い鳥を見つけたとしても/手に入れるには遠く及ばない」と繰り返す。自らの肉体の重み、命の重みを感じながら前に進むことを学ばなければならない……ひりつくような彼の人生に対する切迫感がジンジンと伝わってくる1曲。(Yo Kurokawa)
【BEST TRACKS OF THE MONTH】
過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)
Text By Yo KurokawaShoya TakahashiRiko MaedaNana YoshizawaIkkei KazamaKenichi OguraDreamy DekaShino OkamuraMasashi YunoKei SugiyamaDaiki TakakuYasuyuki Ono