「福祉的なマインドが超大事」
荒ぶる感情に寄り添って
ラッパー、Weird the artが綴る熱狂の先『AFTER MANIAC』
東京は品川をレップするヒップホップ・クルー、Flat Line Classicsのメンバーでありラッパー、Weird the artが昨年11月にソロとしてはファースト・アルバムとなる『AFTER MANIAC』をリリースした。
クルーの楽曲でも聴ける彼の詩情に溢れるリリックはより輝きを増して、Sartの手掛けるジャズやソウルの香りの漂うビートと絡み合い、まるでクラシック映画のようなムードを醸し出す。ギター・リフのサンプルが光る「Cool power」や2つのインスト曲「Exotic fuel」「Sweet dreams」も効果的に作用している。
このスモーキーでチルな、あるいは全体を通して非常にBPMの遅い作品は、どのようなマインドで作り上げられたのか。Weird the artに話を訊くと、意外にも“福祉的”というワードが飛び出してきた。その言葉の意味を、ぜひインタヴューの本編でたしかめてほしいと思う。もしかするとそれは、ヒップホップの可能性を押し拡げる、一つの希望と言い換えられるものかもしれない。
(インタヴュー・文/高久大輝 トップ写真/OSK 記事内写真/Kohki Kanai、AN)
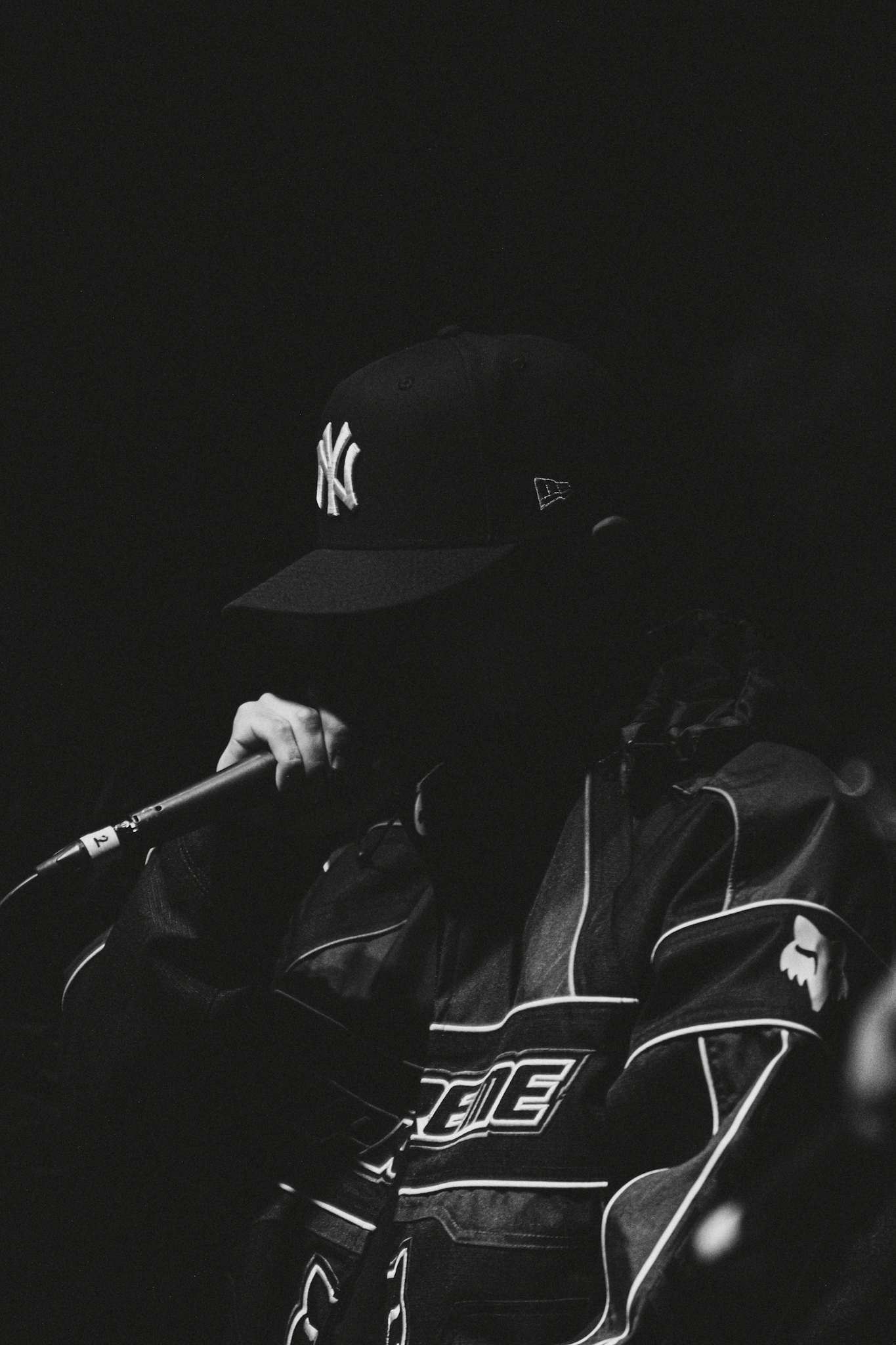
Interview with Weird the art
──昨年11月にリリースされた最新作『AFTER MANIAC』について、昨年5月に公開された宮崎敬太さんによるインタヴューでは「壁にぶち当たっている」と話していましたよね。
Weird the art(以下、W):宮崎さんのインタヴューを受けたとき、アルバムは7割方出来ていたんですけど、今回の表題曲の「After Maniac」で壁にめちゃくちゃブチ当たって。そこから完成まで3ヶ月くらい掛かりましたね。
──当然制作そのものはもっと前から始まっていたということですよね。
W:もともと1曲だけ2、3年前に録っていた曲があって。ビートが面白いしソロ・アルバムに入れたいなと思っていて。3曲目の「Cool power」というポップな曲なんですけど、ラップだけ録音し直して入れているからビートは当時と変わってないですね。
20歳くらいからソロの作品は作っていて、そこからFlat Line Classicsのファースト・アルバム『THROW BACK LP』(2023年)の制作に注力して。サードEPの『Backstage』(2024年)も作って、今回はソロに戻ってという流れですね。
──『AFTER MANIAC』はFlat Line ClassicsのメンバーでもあるSartさんのビートで統一されています。
W:一番近くにいるし、彼のビートの精度も上がってきていると思ったんで、純粋に一緒にやりたいと思って「フル・プロデュースでやって」とお願いした感じです。しっかり決まったのは2年前くらいで、そこからビートのストックを送ってもらったりして。
──作品のイメージはそのときから固まっていたんですか?
W:ゴリゴリのブーンバップというより、ちょっとチルな感じに寄ろうというイメージはあって。ナウい感じというか(笑)。BIG FAFとのジョイントEP『Party Joint EP』(2022年)はタイトル通りパーティーでゴリゴリだったし、これまでの自分のソロ作品に関してもポップ寄りな作品だったり、ビートを引き立てるような作品のイメージがあったので、今回はちょっとチルなイメージで作りたかったんですよね。
──実際「Cool Power」以外はジャズやソウルを感じる、かなり統一感のある印象です。このくらい落ち着いたBPMで作品を作るのは挑戦の一つですよね。
W:苦戦しましたね。フロウの面でもそうなんですけど、どうしてもダラダラしているように聞こえてしまうところがあって、でも一方で結局そのくらいのBPMがやっぱりカッコいいとも思うんです。だからこそ、今作ではあえてそこを課題にしていますね。BPM90半ばくらいはラップを乗せやすいんですけど、80くらいだと遅いから当然難しくなる。『AFTER MANIAC』は基本的にBPMが80くらいなのでそこにどうアプローチするかがカギでした。
──流れを考えるとイントロの「Exotic fuel」と後半の「Sweet dreams」がインストなのも効いています。
W:イントロに関してはここから僕の世界に呼び込むようなイメージです。「これからちょっとトリップしていくよ」みたいな曲が欲しくて。没入感のある作品にしたかったんですよね。「Sweet dreams」は「ちょっと落ち着こうか」って曲で、気持ちをちょっと変えていこうってタイミングで挟んでます。
──映画的な流れがあると思いながら聴いていました。ビートもブーンバップが主体だけどそれだけじゃないですよね。何かインスピレーションになった作品などはあったりしますか?
W:UKだとLord Apexとか。あとUSにLord Skoってラッパーがいるんですけど、その辺りがみんなダウンタウンやベッドタウンで育ちながら、どちらかと言えばブーンバップな、だけどトラップもあるみたいなスタイルで。その影響はあったかもしれないです。彼らの使うビートもソフトさを感じるものが多かったりするんで、そういうところは自分のビート・チョイスにも出ていると思いますね。
──ちなみにリリックはある程度書き溜めたものを乗せているんですか?
W:ある程度書いて、ビートを流して、フリースタイルでやってみてという流れですね。どうしても入れたいフレーズがあればそれを軸にフロウを作ったりすることもあります。基本的にリリックは書き溜めているんですけど、今回は3、4曲は一回書いたものを全部書き直していますね。単純に聴いていて面白くなく感じてしまって。リリックの内容もそうだし、フロウもダラダラして聞こえるし、言葉も面白くなかった。
──それも先ほどおっしゃっていたBPMの話とも繋がりますね。Flat Line Classicsでのラップのリリックと比べると静的な印象だったのですが、クルーとソロで書き分けている感覚はありますか?
W:ありますね。クルーのときと比べて内面に意識的だったと思います。比喩表現のスタイルはあまり変わらないけど、Flat Line Classicsの場合はどちらかというとアクティヴというか、身体的なノリが強いけど、ソロの作品に関してはかなりマインドの方を向いていると思います。
ソロだとテーマ的にも自分の書きたいものを書けるし、普段1ヴァースにギュッとしているところをちょっと広く構えて、その曲のテーマに対してエゴを出せる。間違いなく、本当に書きたいものを書いた印象があります。
──たしかに、比喩表現の部分はクルーのときと変わらず冴えていますよね。“カランコエ”や“Sundial(日時計)”というワード・チョイスも面白いです。
W:ウチのクルーにHaruっていうDJがいるんですけど、背中にカランコエが彫られてるんです。花言葉を調べたら、「香水のように人に幸せを振りまく」といった内容だったので、ピッタリだなって。この曲(「Cool power」)では基本的にクルーのことを歌っているんで。
“Sundial”は地元の公園に日時計があることから来ていて。その公園で日中や朝早く起きたときによく散歩して、ベンチに座って歌詞を書いたりするんです。遊んでいる子どもたちがいたり、犬の散歩をしているマダムがいたり、これから仕事に行くんだろうなって人がいたり、いろんな人が行き交っているから、そこで歌詞を書いていると想像しちゃうんですよね。みんなどこに向かっているんだろうって。例えば子どもだったら「彼らは大人になったらどうなるんだろう?」「Bボーイになってるといいな」とか。その人がどんな生き方をしていくのか、その情景が日時計と重なって。
──お洒落な表現です。冒頭でも話したインタヴューで『心の免疫力 「先の見えない不安」に立ち向かう』(加藤諦三、PHP新書)という本の影響が本作には大きいと話していましたが、その部分についてもう少し詳しく教えていただけますか?
W:人の不安をテーマにしている、エッセイではないんですけど、事例を元に「この人にはこういう不安があって……」みたいな本で。不安って絶対に抱えるものでもあるけれど、本当にあるかないか、可能性でしかない物事らしいんです。どうなるかわからないのに勝手に悲観してしまうというか。それでパラノっちゃったりしてしまう。
つきまとう不安をそのままつきまとわせていくのか、それを振り払って自分のやりたいことや考えているイメージに近づかせるのか。やっぱり不安をあえてつきまとわせるとなると人ってネガティヴの方が強かったりするんですよ。人はその前に準備とか備えをするための予備能力が強くなるから。逆に不安を振り払ってとりあえずやってみる、トライ&エラー的な思考の人って回数をこなせばいつか成功する。その両価性を自分は持ちたいなとアルバムの全体像では考えたりしましたね。
当たり前だけど、結果は終わった後じゃないとわからないので、『AFTER MANIAC』というタイトルにはその後の展開というニュアンスもあるんです。“maniac”っていう言葉には、“おかしな”とか、ちょっと“アガっている”という意味もあるんで、その後の世界っていう感じ。何があるかわからない状況の先を書いている感覚です。
──不安を完全に振り払うワケではないと。
W:そうですね。どちらにせよやれるって気持ちで。
あと街の情景的な面でも影響を受けています。トー横キッズが注目されていたタイミングで書いていた曲もあったから、OD(オーバードーズ)自慢が目についてしまって。「いやいや、環境もわかるけど、クリエイティヴな時代だしもっと他にやれることあるでしょ」って。OD自慢とかちょっと“maniac”な状態に入るより、ちょっと落ち着いて、もっと他に目を向けようよっていうピースなメッセージも入っていたりします。
──そういう意味では「State of mind」の客演も納得というか。
W:LibeRty Doggsのbabe bonitoも、9treeのDAIも波長が合うというか、僕が知っている中でもとびきりピースな2人で。実際にちゃんと話していても、「やっぱりそうだよね」と思うことが多くて。
──どういったところで?
W:一つは福祉的なマインドが超大事だよねってことです。自分もそうだけど、誰かのために何かをやることによって、自分の自己肯定感のようなものも含め上がってくるじゃないですか。「よし、人にこうしてあげた」「こういうことができた!」って。自分も含め、他の人にしっかりフォーカスして手助けをしてあげたい2人なんですよ。
この曲は3人でいっしょに録りました。「State of mind」というタイトルもナズやジェイ・Zを踏襲してというより、何で平和的なメッセージを伝えるかといったら、それは音楽であり、俺らの生き方だよねって話になって決めていて。
──それってまず自分を上げて、その姿を見せて周りを上げるような、いわゆるヒップホップ的なアプローチとは違いますよね。
W:そうですね。でも僕は、どちらかと言えば病んでいる人に「わかるな」と思って欲しいところがあるんです。もちろんラップとしてカッコいいものも出せたら、たぶん誰でも刺さるから、自分の好きなビート、メロディー、ラップのスタイルでどこまでやれるか今はずっとやっている感じですね。
──そういった福祉的なことをリリックにしていく上で意識していることはありますか?
W:それをリリックにしていいのかというモラル的な面があると思っていて。そこを考えなかったらバンバン書けるんですけど、これを聴いて誰かが良い思いをしないと感じることは書きたくないんです。難しいです。本当は書きたいけど、聴いている人が納得するか、そんなことねえよと思われるか、そのリスクがあるのならわざわざ書かなくてもいいなって。その線引きはあります。モラル的にグレーだったら書きたくない。
だから直接的には書いていないことにも自然と気づいてくれたらいいなと思っていますね。意外と聴いてくれている感覚です。若い子に限るんですけど、数的には。圧倒的にリスナーは増えたなって。
──“福祉”というのはもしかしたら今の時代のキーワードかもしれませんね。
W:自分が東京で生きてきたことも関係しているかもしれません。忙しい中だと自分しか見れなくなるけど、落ち着いて考えてみたら自分だけじゃなく他の人もそうで。だからこそ誰かを手助けしたらそれはそれで回るんじゃないかっていう。
──つまり自分も助けられている感覚があると。
W:それこそエンジニアとか、ビートもジャケ(『AFTER MANIAC』のCDのデザインはFlat Line ClassicsのDJ、Ryo Ishikawaが担当)も周りの友達がいて成り立ったなと思うんで。だいぶみんな良くしてくれて、ありがたいです。
『AFTER MANIAC』ジャケット
──今回「State of mind」に参加した2人はクルーやユニットに所属していますが、LibeRty Doggsや9tree以外で動きが気になっているクルーなどはありますか?
W:TiGht Plumpは最近Olive Oilさんとも関わったり、面白い動きをしてますね。あとSound’s Deliはやっぱり気になります。いっしょにやってきたし、次どうくるのかなって。
福岡だったらSOUL NEWS PAPERZというレーベル/コレクティヴ。そこには圧倒的にヤバいDJが揃っているし、東京にない音だなって思うんですよね。それが好きで遊びに行ったりもします。ジャンルレスで、なおかつオーセンティックさも感じますね。大阪だったらTha Jointzだと思います。しっかりスタイルを築いているコレクティヴで。カッコいいです。
その中で、クルーとして僕たちは東京らしさを出したいんです。僕らは全員東京出身なんで。東京の良さはやっぱり、シティ・ボーイって言われるからにはシティ・ボーイらしい振る舞いだったり、スタンス、スタイルにあると思うんです。それを音楽にも出したい。やっぱり東京は刺激の強い街だから、その圧倒的な情報量をどう整理するかだと思うんです。人も多くて情報も多い分、それをセンス良く切り取るというか。カッコよさというより、オシャレさですかね。その東京らしさは出したいです。
──ちょっと脱線してしまいましたが、客演の話だと本作にはFlat Line Classicsを除けばme2さんも参加しています。
W:me2とは前からいっしょにやりたかったんです。制作が滞っていたんでちょっと遅れてしまったけどお願いしたら「ぜひ」と言ってくれて。「Yen jewel」はだいぶムーディーですよね。承認欲求をテーマにしていて、じゃあそれをどう満たすのかということを考えて書いたリリックというか。自分はどうやって満たしているのか、これからあなたたちはどうやって満たしていくのか、自問自答しつつ、問いかけています。
──そういったリリックには年齢を重ねたことも影響していますか?
W:やっぱりありますね。前の方がもう少しガキ臭かったというか。ノリもフリーキーで、軽くラップしていた部分もあったけど、今回の作品では自分に合ったスタイルが固まってきた感覚があります。
──今後もそのスタイルで続けていく予定ですか?
W:たぶん変わります(笑)。『AFTER MANIAC』はチルな作品だけど、次はしっかりヒップホップをやろうかなって。もっとハードになると思います。がっつりブーンバップになるんじゃないかな。
──ということは次の作品にも着手しているんですね。
W:はい、ビートは今回より速いかな。現時点で書いているのは、情景的な面もあるけど、自分のことが多いかもしれないです。自分がこの場所にいてどういう心境なのかを歌っている曲が今はできていますね。『AFTER MANIAC』はチルでスモーキーな作品になっていると思うけど、次回は次回で面白い色を出していこうと思っているので期待していて欲しいですね。
Photo by Kohki Kanai
──ちなみにソロのライヴで意識していることはありますか?
W:パフォーマンスに関してはもっと頑張れるところもあるなって。スタイルがあると思うんです。例えばステージでアクティヴに動いていてラップするスタイルとか、落ち着いてラップするスタイルとか。好き嫌いというより合う合わないの話だと、僕の場合は後者のクールな感じの方が合っている気がしていて。自分はヴァイブスが上がりすぎちゃうと変に声が上擦ったり、やりにくくなったりもするし、やっていて違うなと思っちゃうので、どちらかというと淡々とラップしている方が合っている気がします。でも難しいです。やっぱり楽しいんで。
──クラブも、ライヴも楽しんでいるということですね。タイトル曲の「After maniac」の「夜を楽しみ朝にもがく」というラインにはまさにその光景が浮かんできます。
W:クラブにいるとやっぱりめちゃくちゃ遊んじゃうじゃないですか。だけどある程度の理性を保ちつつ、次の日に仕事とか予定があるのを考えて、しっかり遊ぶけど、次の日も起きて動き出す。そっちの方が身体的にも絶対に良いから(笑)。そういう意味でも「After maniac」です。どれだけ遊んでも、しっかり働いていた方がカッコいいよねっていうのは言いたかったことでもあります。だから朝にもがいてます(笑)。
──わかります(笑)。
W:単純に好きなんですよね。DJも聴きにいくし、そこで刺激を得て歌詞ができたりするんです。僕は家にこもって書くより動きながら書いている方が調子が良かったりするんで。クラブの帰り道も、それこそDJを聴いているときもリリックを書いていたりしますね。
──遊びもインスピレーションになっていると。では最後にラッパーとしての目標を教えてください。
W:コンスタントに作品を出して、安定型というか、一番は続けていくことです。その上でどんな規模の会場でライヴしてもしっかりかますことですね。
<了>
Photo by AN
Text By Daiki Takaku

関連記事
【INTERVIEW】
「場所を作り続ける」
Flat Line Classicsが乾杯を続ける理由
ファースト・アルバム『THROW BACK LP』大反省会
https://turntokyo.com/features/flat-line-classics-throw-back-lp-interview/
