【未来は懐かしい】特別編
柴崎祐二・選 2025年リイシュー・ベスト10
新しいものはつい最近時代遅れになったものから離れようとして、古めかしくて根源-時間的な要素を更新するのだ。新しいものの出現に伴うユートピアのイメージは常にこぞって根源-過去へと手を伸ばすのだ。どの時代も自分の眼前で何らかの形象をまとった次に続く時代を夢見るが、その夢においては、その形象は根源史の諸要素と結びついて現れる。
──W・ベンヤミン
今年のはじめに米音楽情報サイト《Music Business Worldwide》が報じたところによると、2024年の一年間にストリーミング・サービス上で新規リリースされた楽曲の数は、一日あたりの平均で99,000曲にも登ったという(“How much music is released every year?”)。これを365日分として計算すると、一年間におよそ36,135,000曲もの膨大なトラックが世に放たれた勘定になる。
それに対し、《Discogs》の検索機能を使った調査(“How much music is released every year?” https://nikkimiller.space/2025/02/09/how-much-music-is-released-every-year/)では、米国内でのアルバム・リリースに限れば、1970年代には各年あたり約2,000作品強の発売数で推移していたと推計されている。もちろんこの数値は、《Discogs》上に作品情報が存在するアルバム数に基づくものであるため、そこから漏れたレコードについては加算の対象外となっている上、逆に、記録メディア別の重複を除外しきれていない可能性があると調査者自身が述べているという点からも、議論のための簡略的な目安に過ぎないことに留意すべきだが、それでも、この目安を採用した場合、ざっくりと1アルバムに平均10曲が収録されていると仮定して、米国内のみで1年につきおよそ2万曲余りが新規リリースされていたという推計が導き出される。
つまり、現在のストリーミング・サービス上では、1970年代のアメリカにおいて任意の1年間のうちにリリースされた(と推計される)全ての楽曲の約5年分にあたる量が、たった一日のうちに新規登録されているという計算になる。先述の《Music Business Worldwide》の記事では、こうした極端なリリース数の激増についての議論は2025年を通じてますます加速するであろうと予測されているので、集計結果の発表を待つまでもなく、今年も同様の傾向を示していたことは間違いのないところだろう。
このような爆発的な状況の背景には、各種配信プラットフォームへのデータ登録手続きが急速に簡便化したこの間の動きも密接に関係しているだろうし、それに伴う既存レーベルの特権性の劇的な相対化、更には、AIを利用した「音楽制作」の劇的な進化(それを「蔓延」とみる論者も多いだろうが)など、様々な要因が存在すると考えられる。その一方で、上述記事で指摘されているように、現在Spotify上に登楼されている全アーティストの約86%は月間リスナー数が10人未満であるということ、および、現在利用可能なトラックの総計約2億トラックの4分の1、つまり5000万曲ほどは、再生回数がゼロであると推察されている。すなわち、ストリーミング・サービス上に存在するあらゆる曲がおしなべて「聴かれている」とはいい難い状況にあるわけだが、それでも、かつてに比べてほとんど天文学的といっていいほどに、世の中に「新曲」が溢れ返っていると言っていいだろう。このような状況は、音楽制作とその発信工程の爆発的な「民主化」がある種の必然としてもたらしたものであり、同時にそれは、人類史上に類のない新たな文化的生態系が現れつつあることを告げている。
このような環境において、私達の音楽生活はどのように変化していくのか。最も導きやすい推論は、選択肢の増大が選択の困難を導く事態──いわゆる「選択のパラドックス」が引き起こされるのではないか、というものだろう。実際に、そうした議論は、多くの人々の直感に結びつく形で既に数多く提出されてきた。その一方で、バイラル型ヒットの構造に顕著なように、あるアーティストなり楽曲がたまさか注目を浴び、巨大な文化的アイコン/ミームへと成長していくという現象も、その潜在的可能性の増加を背景に、より一層加速していく可能性もあるだろう。
更に、このような急速なインフレーション状況は、多くの楽曲が既存のマーケティング理論や、それに基づいたジャンル概念のラベリング圧力を捨象した上で存在することになるという意味において、(つやちゃん氏が秀逸な論考「2020年代の文化領域におけるPost-Genre Aestheticという波について」で論じてみせたように)、脱ジャンル(概念)志向と美学ラベルの前面化を加速させる要因の一つにもなる/なっているだろう。
私自身は、ポピュラー音楽評論の圏域から物事を考えてきた立場から、このような状況に対して、(つやちゃん氏がいみじくも述べている通り)批評言語の更新と適材化を図るべきであるという言説に対し深く頷く一方で、ひょっとすると、歴史的なパースペクティヴ──それが、いわゆる「教養」なるものとほとんど同義であるかもしれないと嘯くのも悪くないと思っている──を我が物にすることの重要性が、以前も増して、かつ、逆説的に上昇していくのではないかと考えているのである。
今、過去の音楽を聴くという行為は、望むと望まざるとに拘らず、歴史に触れるという行為と切り分けられない。それを言ったら、昔からそうだったはずなのだが、かつてにも増して今はもっとそうなのではないか。つまり、過去の音楽──特に、その存在がごく一部の人々にのみ認知されていたものや、広く認知されていたとはいえその「聴き方」が特定かつカノン的な文脈にばかり回収されてきたもの──を聴き「直す」行為というのは、現在のアノミー的なポピュラー音楽地図の中において、自らの現在地と自らの由縁を知るためのまたとない導きとなるのではないか、という考えが、「新曲」の氾濫の上昇曲線と同じような軌跡を辿りながら、自分の中で大きく膨らんでいく一方なのである。
更に言えば、知られざる過去を知るという行為、知っていたつもりの過去を知るという行為は、上述のように自らの現在地を見定めることにも繋がっていくが、同時に、「有り得た現在」、より敷衍するならば、「有り得る未来」への道筋を引き直す思考にも誘う。可能性の凝集点であるはずの現在、しかもその凝集点のパターンがかつてないほどの規模で短略的に可視化され、切り刻まれた断片的なコンテンツと化して私達の実存を溶かし続ける今にあって、そこから一旦身を引き剥がして時間軸の左方へと移動し、その地平から、「可能性が可能性として可能性を秘めていた」景色を想像し、写生し直すこと。
過去の音楽――に限らない文化全般──とは、この想像、この写生のためのまたとない画具なのである。私達は、その画具を用いて、様々な思考の可能性へと導く判じ絵を描くことができる。私は今日も、今という時間の中で、今を味わい、未来を想像するために、今新たに世に放たれたばかりの音楽とともに、過去の音楽を聴いている。
以下は、2025年にリリースされたリイシュー/発掘作品の中から、重要かつ好内容と思われるものを10枚選び、ランキング形式で評したものだ(連載のレギュラー回で扱ったものは除外した)。今年も本連載を読んでいただき、ありがとうございました。来年も宜しくお願いします。
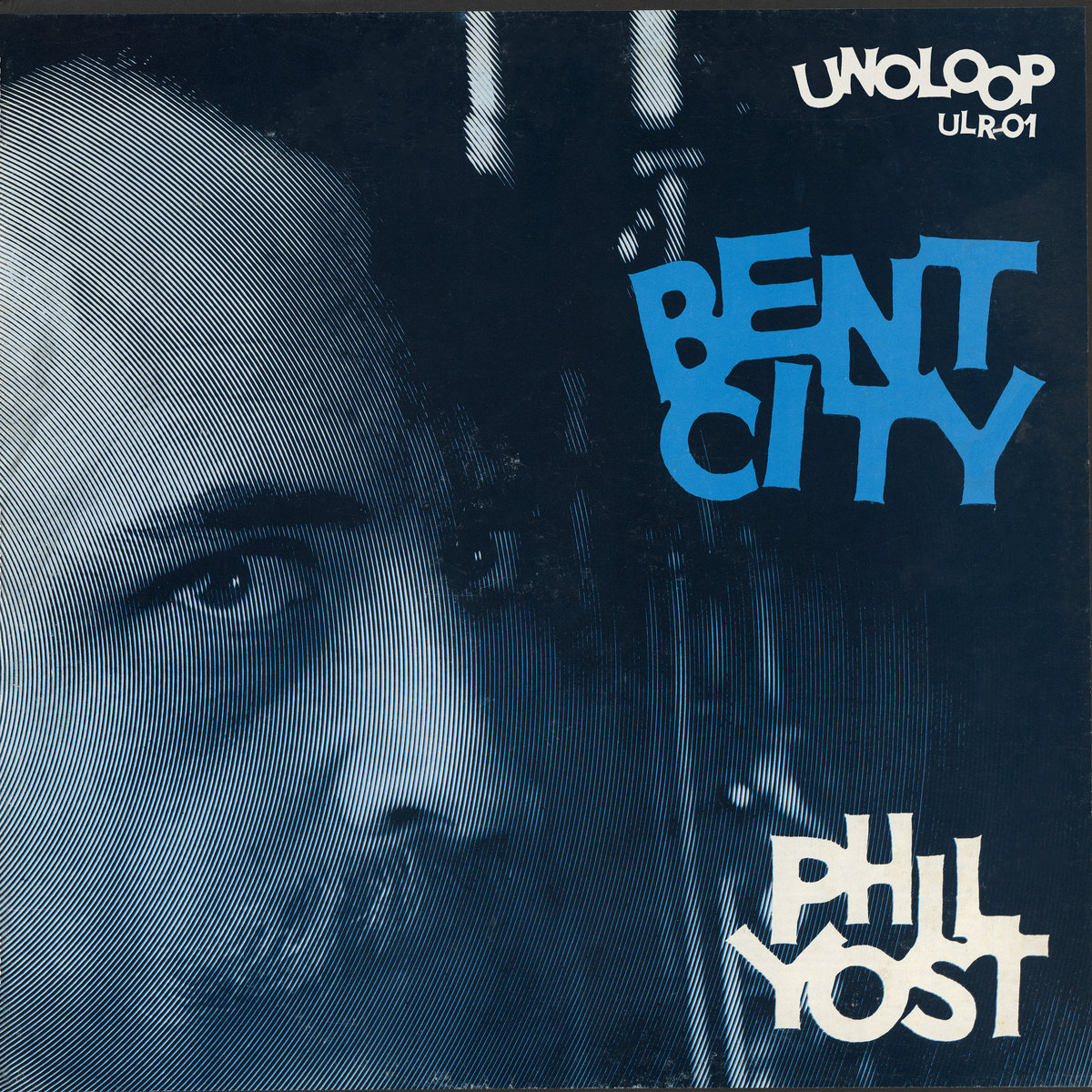
10
Phil Yost
Bent City
Uno Loop
ジョン・フェイヒーとエド・デンソンの二人によって設立された《Takoma》レコードは、一般的には、フェイヒー自身の作品やロビー・バショー、レオ・コッケらの作品のイメージが先行していることから、いわゆる「アメリカン・プリミティヴ・ギター」の起源の一つとなったレーベルとして認識されているだろう。もちろんその認識は間違いではないのだが、一方で、そうした文脈には収まりきらない個性豊かで実験精神に富んだアーティスト、および作品を、積極的に紹介したレーベルでもあった。その中には、ジャズ・サックス奏者のロビン・ケニヤッタや、現代音楽系のベース奏者バートラム・トゥレツキー、電子音楽作家のジョセフ・バードらがいたし、後に《Windam Hill》レーベルの看板アーティストとなるピアニストのジョージ・ウィンストンや、バーニー・クラウス、元ランチャーズの喜多嶋修など、ニューエイジ畑で活躍する面々も含んでいた。
フィル・ヨストは、そんな《Takoma》の中でも特に先鋭的かつ先駆的な表現を行ったマルチ楽器奏者であり、このアルバムは彼のデビュー作にあたるものだ(オリジナル発売は1967年)。サックスやフルート、ギター、ベース、マラカスなど全ての楽器を自ら演奏し、それらの多重録音を経て完成された本作は、語義通りの意味でジャンルレスであり、同時に1967年という時代背景を色濃く反映したサイケデリックな内容となっている。前衛ジャズと(プレ)ニューエイジ、実験音楽の交差するところに生まれた、真に時代超越的な音楽といえる。
購入はこちら
Bandcamp

9
Doctor Rhythm
I Feel It Rising
Hungry Records
ドクター・リズムは、南アフリカのジャズフュージョン系グループ=スピリット・リジョイスのギタリスト、ロビー・ジャンセンを中心とする別プロジェクト。1981年にリリースされた本作は、同グループが唯一発表したオリジナル・アルバムだ。スピリット・ジョイスは、2020年代に入ってから2枚のアルバムがLP再発されるなど、ここにきて一躍注目度の高まりつつある存在だが、その熱を受けてか、本盤までもが再発されてしまうのだから、嬉しい驚きとはこのことだ。既にヨーロッパのDJの間で人気を博していた「Hook It Up」や「I Feel So Strong Now」といった曲に代表されるように、ディスコ〜ブギーの視点からみて極めてクオリティの高い曲が並んでおり、いかにもフロア受けのしそうなサウンドが詰まっているが、一方で、こうした流麗なサウンドを指して、単に「西洋化」の圧力を指摘してみるだけでは取りこぼしてしまう同時代的なリアリティがあったはずで、改めて、そういうものにこそ常に敏感でありたいと思うのだった。
購入はこちら
diskunion

8
Repetition Repetition
Fit for Consequences: Original Recordings, 1984–1987
Freedom To Spend
リピティション・リピティションは、ルーベン・ガルシアとスティーヴ・カートンからなるLAのミニマル・ミュージック・ユニットである。1980年代にいくつかのカセットテープ作品を残し、あのハロルド・バッドの関心を惹いたこともあったというが、その存在が広く知られたことはついぞ無かった。本作に収められた楽曲は、それらのカセット音源から精選されたもので、無名であった事実が驚かれるほど素晴らしい内容だ。テリー・ライリー由来のサイケデリックなミニマリズムと、ザ・ドゥルッティ・コラムを思わせるような清涼感と薄明性が入り混じったサウンドは、こういってよければ意外なほどに「ポップ」なもので、必ずしも現代音楽の語法のみに自足しているわけではない点も含め、ある種のポストパンク的な美意識も感じさせてくれる。ロスアンゼルスらしいニューエイジ風味も実にいい塩梅だ。本作は、これまでにアーネスト・フッドやリマリンバなどの優れたリイシュー/発掘作を送り出してきた米《RVNG Intl.》傘下の《Freedom To Spend》の面目躍如というべき傑作コンピレーションであり、米ミニマル・ミュージックの裾野の広さ、肥沃さを証明する一枚である。
購入はこちら
diskunion

7
大月みやこ
大月みやこの日本民謡 ラテン・フィーリング
Fourth Wave Record Factory
私が音楽業界に入ったのは、2006年、老舗ドメスティック・メジャー・レーベルである《キング・レコード》に新卒採用で職を得たことに端を発しているのだが、入社後正式に配属先が決まるまで、各部署の現場を研修して回る期間があった。その時の経験で最も強く印象に残っているのが、同社の演歌部門の看板歌手である大月みやこ(と呼び捨てにするのは評論文の一環とはいえいまだに憚れるので、以下「大月先生」と書く)の現場を見学したときのことだ。他を圧するその歌唱の説得力、超絶的と言っていいほどの巧さ、艶めきは、洋楽のポピュラー音楽ばかりを聴いてきた自分にとって、ひとつのショックだったといっていい。これが演歌道を極めたプロの凄みなのか、と。
本作『大月みやこの日本民謡 ラテン・フィーリング』は、そんな大月先生が1973年に吹き込んだアルバムで、表題にある通り、テラン・リズムに乗って有名民謡曲を歌ってみせた異色作だ。ラテン・パーカッションの巨匠・瀬上養之助のグループをはじめ、宮沢昭(フルート)、江口啓介(ピアノ)、原田長政(ベース)、中牟礼貞則(ギター)、池野成秋(オルガン)というジャズ系の手練達によるバッキングは、いわゆるイージー・リスニング調のラテン・ジャズ系オケとはひと味もふた味も違うもの。かといって、レア・グルーヴ的な審美眼でのみ味わうのもまた違う。むしろこれは、外来文化志向とローカリズムの拮抗が1973年という時代状況の中で顕現した、自覚的なルーツ探求(拡張)の優れた具体例であったと理解したい。そういう解釈を促すのも、大月先生のたっぷりとした、同時にプロフェッショナルならではの緊張感を孕んだ歌唱の素晴らしさあってこそ、だ。
購入はこちら
diskunion

6
Evinha
Cartao Postal
Vampisoul
ブラジルの兄妹ヴォーカル・グループ「トリオ・エスペランサ」のメンバーとして知られる歌手エヴィーナ。彼女が1970年代に吹き込んだソロ・アルバム群には、かねてよりMPBファンから厚い支持を集めてきたものが少なくなかったが、中でも、内容への評価・ウォント数ともにトップクラスで、特に再発が望まれていたのが1971年発表の本作だったといえるだろう。マルコス・ヴァーリ&セルジオ・ヴァーリの「Que Bandeira」や、ロー・ボルジェス、ベト・ゲヂス、フェルナンド・ブラントの「Feira Moderna」など、選曲の素晴らしさもさることながら、ごくごく丁寧に練り込まれたオケのサウンド、そして、歌唱の素晴らしさといったらない。これは文句無しの名盤だろう。時代的に、ソフト・ロック的な柔和さと、それ以降のMPB繚乱の中間に位置するような音で、爛熟と先進性の両方が絶妙なバランスで溶け合っている。なんと豊かな音楽なのでしょうか。個人的に、(もちろん具体的な音楽傾向は異なるにせよ)先に紹介した大月先生のアルバムと、そう遠くない芳醇さを秘めた歌声、サウンドに感じるのだが、どんなものだろう。全30分以下という尺の短さも、風格です。
購入はこちら
Bandcamp

5
Evelyne / Masao
Testpattern
Dark Entries
今年手掛けさせてもらった仕事の中で、特に光栄の至りだったのが、日本のテクノポップの至宝、テストパターンの唯一のオリジナル・アルバム『アプレ・ミディ』の再発盤へ、拙解説文を寄稿させてもらったことだ。《YEN》レーベル指折りのコアな人気を誇る、そして個人的にも大好きな同作のライナーノーツとあって、執筆にあたり当時の資料集めやらなにやらに励んだのだが、その過程の中で、同作リリース後に、テストパターンの首謀者である故・比留間雅夫が、フランス系アメリカ人モデル/ヴォーカリストであるエヴリン・ベニューと共に短期間活動していたことも知ることとなった(1984年、《YEN》のプロデューサーである細野晴臣とともに二人がテレビ東京『TOKIOロックTV』にも出演しパフォーマンスを行っている映像がネット上で視聴することができる)。それは、この時期にも新たな音源制作を行い、リリースを予定していたということを推察させる情報だったが、よしんば音源のありかが判明したとしても、既に比留間氏が逝去された今、それが世に出ることはなかなか困難であろうと思われたのだった。……が、それからたった数カ月間の間に、その比留間とエヴリン・ベニューのデュオによる未発表音源が(《ALFA》ではなく、米サンフランシスコの先鋭的レーベル《Dark Entries》から発掘リリースされてしまったのだから、大いに驚いた。しかも、目の覚めるような高音質、全76分の大ボリュームで。その内容も、勝手に想像していたよりもはるかに高クオリティで、しかも、(テストパターンの作品と同じく)テクノポップの時代のその後を予見・実践するような先進性に溢れている。素晴らしい。この音源の存在を詳らかにし、世に出した関係者の皆さんに敬意を表します。
購入はこちら
Bandcamp

4
Sister Irene O’connor
Fire of God’s Love
Freedom To Spend
これも前述した《Freedom To Spend》発だ。オリジナル盤は、オーストラリアの修道女であるシスター・アイリーン・オコナーが、1973年に豪《Philips》からリリースしたアルバムで、各曲名からも分かる通り、信仰心を題材としたオリジナルの聖歌が集められている。楽曲も、聖歌風のもの、イギリスのトラディショナル・フォークを想起させるものなどが多いが、注目すべきはそのオケだ。こうした作品によく聞かれるピアノやギターなどのアコースティック楽器による伴奏に留まらず、電気オルガン等の各種キーボードやリズムボックスまでもが駆使され、しかも、その演奏に極端なイコライジングを伴った空間的な音響処理がなされているのである。これは、平たく言ってかなり風変わりだ。いわゆる「モンド・ミュージック」の範疇に入るものと理解できるが、一方でこの音楽を今そのようなまなざしの元にでのみ珍重するのは、なにか本質をとりこぼすことになりそうな気もする。むしろ、現在の一部のDTM作家たちが、やむにやまれず表現欲をブリコラージュ的に具象化しようとし、結果的に「創作」という行為の深遠に触れる成果を(ときに人知れず)ものにしている現象と近しい何かがあるのではないか。そう考えてみるほうが、この音楽の美しさに肉薄しうる気がする。極めてプリミティブな電子音と、単に「特徴的」というだけでは心もとないほどの特異な音像にも、物理的な表象を超えて奉じるべき何か──シスター・アイリーン・オコナーにとってはそれは当然「神」であるわけだが──への、切実な想いが充満している。テクノロジーは、それを原始的に――つまりブリコラージュ的に扱うときにこそ、崇高な何かへと密着する。そこに聖/俗の違いはきっとない。
購入はこちら
Bandcamp
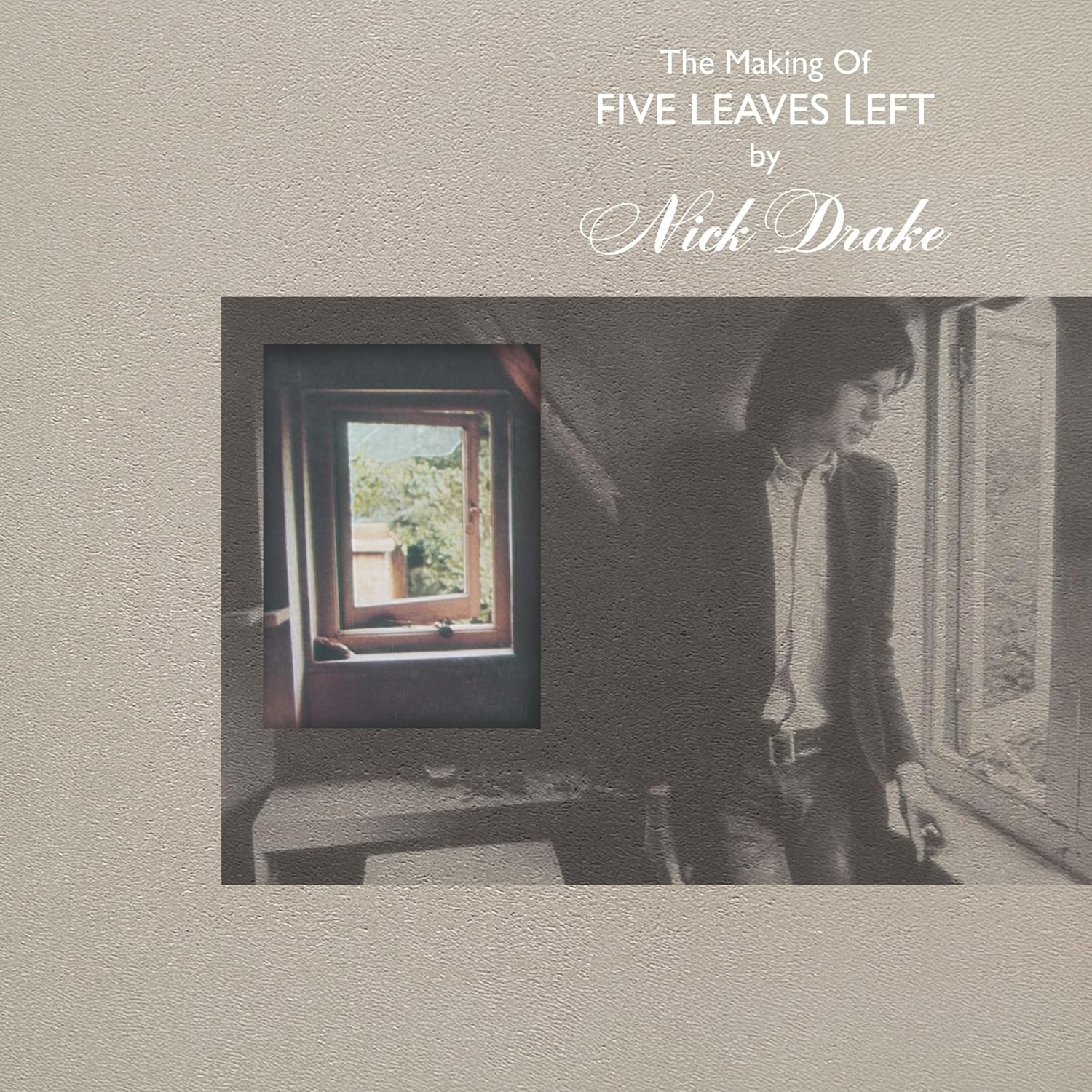
3
Nick Drake
The Making Of Five Leaves Left
Island
ニック・ドレイクという人物、彼の遺した作品の数々は、私という一人の人間とってあまりにも特別な存在であり続けている。同じ思いを抱えている人は、世界中に沢山いるだろう。要するに彼というシンガー・ソングライター、そして彼の遺した音楽は、沢山の「一人」によって慈しみをもって大切に愛されてきたという意味において極めてパーソナルな存在でありながら、同時に、そうした個人同士をある儚げな美の感触の元に繋ぎ合わせる力を秘めているという意味において、大変に「ポピュラー」なものでもある。
『Five Leaves Left』は、1969年にリリースされたニック・ドレイクのファースト・アルバムだ。英国フォークの伝統を継ぎながらも、卓越した作曲能力と斬新なハーモニー・センス、天賦の美しさを持った歌声で同ジャンルを大きく前進せしめ、更には発売後長い時間が経ってから、オルタナティヴ・フォーク世代に大々的に「再発見」された作品だ。本セットは、そんな名盤の制作過程を、貴重極まりないデモ音源やアウトテイクの数々によって明らかにするファン歓喜の4枚組ボックスである。
本セットがリリースされるまでの経緯を知る中で、私が特に胸を打たれたのが、当初ニック・ドレイクの遺産を管理する団体が、『Five Leaves Left』というアルバムの純粋さを阻害することのないよう、拡大盤の発売を避けていた、という事実だった。結果的に、本セットにも収録されている(生前のドレイクと深い親交を結んだ)ビヴァリー・マーティン所蔵の未発表テープや、キース・カレッジに眠っていた音源に対して、ニック・ドレイク財団がその意義を認めたことで、こうして秀逸なボックス・セットとして世に出ることになったのだ。このエピソードからは、他でもないニック・ドレイク財団が、多くの人にとって『Five Leaves Left』という作品が特別な存在であることを理解していたことが知れるのであった。そして、紛れもない事実として、このセットは、『Five Leaves Left』が纏うアウラを霧消させてしまうことがないのは当然として、それをより深遠なものにならしめているのである。
購入はこちら
diskunion

2
X-Cetra
Summer 2000
Numero
X-Cetraは、2000年代初頭に米カリフォルニア州のサンタローザにて結成されたキッズ・アイドル・グループであり……と書いても、当時のコマーシャル・ポップをリアルタイムに見聞きしてきた大方のリスナーが彼女たちの存在をその頃から認識していた可能性は限りなくゼロに近いだろう。11歳のジェシカ・ホール、エイデン・マイエリ、ジャネット・ウォッシュバーンの3人、それに若干9歳のメアリー・ウォッシュバーンからなるX-Cetraは、元々スパイス・ガールズ、フィオナ・アップル、デスティニーズ・チャイルドらのポップ・スターに影響を受けて始動(などといういかめしい語彙はあまり似合わないが)され、当初は自作のビデオを拵えたり、歌とダンスに興じたりしていた。そのうちに彼女たちは、ジャネットとメアリーの母親でもあるミュージシャンのロビン・オブライエンにオリジナル楽曲を録音したいと申し出、ロビンの知人でベルリンの音楽家であるアチム・トイがトラックを提供することで、『Stardust』なる自主製作CD-Rが作られるに至った。それは今から25年前、2000年のことだった。
名門《Numero》がコンパイルした本作『Summer 2000』は、同CD-R収録音源を元に組まれたコンピレーションアルバムである。ネット上で、「Y2K版シャッグス」なる形容が複数見つかることからも分かる通り、その内容はローティーンの直接的な表現欲求が刻まれたいかにも非プロフェッショナルなものなのだが、あのシャッグスとは異なりオケを制作したのはプロの音楽家なので、当然ながらダンス・ポップの定型から完全に逸脱するようなところは(あまり)なく、むしろ、ダンス・ポップの勘所を彼女たちなりに押さえたものになっていると感じる。……などと説明的な評を重ねてみても一向にここに収められている音楽の魅力と核心には迫り得ないような気がするので、あえて断言させてもらうが、ここには、Y2Kリバイバルなる(しばらく前からしぶとく続く、既に背景的美学となって久しい)現象の、最もデリケートな部分を突く何かが詰まっている、と思わされるのだ。
まるで、ローファイな音質の家庭用カラオケに合わせて気の置けない友人たちと思い思いに歌っているようなヴォーカル・パフォーマンスをはじめ、妙にミニマルで先鋭的なトラック(これは、サウンドプロデューサーを務めたアチムが、ノイエ・ドイチェ・ヴェレの系譜に連なる人物であることによるのかもしれない)や、まるで、様々な複製メディアのリレー──具体的には、あの時代によくあった友達同士のソフトの貸し借りの繰り返し──を経てノイズ成分を増してしまったかのような特異な音像を含め、ミレニアル世代のノスタルジアを直接的に刺激する何かが、高濃度でパッケージ──そう、まさに物理メディアの「パッケージ」性を想起させるのだ――されているのである。
しかし、この音源集の本領は、そうした「実際に体験されたノスタルジア」の喚起力のみにあるのではなく、むしろ、Y2Kリバイバルにおける大半のコンテンツがそうであるように、未体験世代の想像的なノスタルジアを遡及的に表象するような機能を持っている点にあると思われる。こうした機能は、かつてヴェイパーウェイヴが、その美学的な参照元にリアルタイムで接した経験を持たない後進世代に対して果たした働きとも近似的であり、ひょっとすると、(私のように)実際に「Y2K」を体験しているものよりも、体験をしていない人々に対しての方が、ノスタルジアの感覚を鮮烈に想起させるのではないか、などと考えてみたくなる。そんな風に考えてみると、確かにここに収められた各トラックは、極めて「Post-Genre Aesthetic」的であり、現代のポップ表象文化の正統的な祖先であるようにも思われるのである。
購入はこちら
Bandcamp

1
Bruce Springsteen
Nebraska ’82: Expanded Edition
Columbia / Sony Music Japan
今年一年を振り返ると、ブルース・スプリングスティーンの曲ばかり聴いていた気がする。なぜか。度々評論を頼まれるのに加え、そうでなくともことあるごとに自分から進んで書こうとするので、実際上の理由から聴き続ける必要があったというのもある。だがそれ以上に、ブルース・スプリングスティーンを聴くことで、私はなんとか、この「分断」の常態化が進む世界の中で正気を保とうとしてきたのかもしれない、と思う(そうした日々が導き出した思考の変遷については、この連載でも披瀝したことがある)。
彼の多くの傑作の中でも、1982年にリリースされた異色の弾き語りアルバム『Nebraska』は、彼が彼であることを、ひいては、この私が私であることについての思考を深めるにあたって──つまり、この世界の中でパーソナルな音楽とは一体どんなものであり得るのか、そして、そういう音楽を愛する自分とはいかなる存在であるのかという避けがたい問いを考えるにあたって(こんな風に思考の跳躍を可能にしてしまうのが、彼の音楽の凄さの一つだ)、大変重要な役割を果たしてくれた。もっと言えば、『Nebraska』は、個人的、社会的な意味の両面で、現代において歴史と対峙することの意味を考えるにあたっても大きなヒントを与えてくれた。ウェブ・メディア《NiEW》の連載で映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』を論じた回は、まさにそうした自問へのありうべき一つの回答として書かれたものだ。
本作『Nebraska ’82: Expanded Edition』は、その映画の公開と同タイミングで登場した同作の拡大盤である。オリジナル・アルバムの最新リマスター音源に加え、ブルースが自身のベッドルームで録音したデモ・テープをそのままレコード化しようと決断する前にEストリート・バンドの面々を交えて試験的に録音したバンド入りのテイク、オリジナル本編から漏れた未発表デモ、今年春に行われた同作の全曲再現ライヴ音源、およびその映像版が収められた大ボリュームのセットだ。
長年のファンにとって最も興味をそそられるのは、バンド入りの音源を収録したディスク2だろう。オリジナルの4トラック・テープレコーダーで録られた弾き語り音源に慣れ親しんできた身としては、それぞれの曲がバンドの演奏を纏う様子は、あたかも、モノクロの映画がにわかに色彩を得たかのような鮮烈な印象を抱かせるものだった。なるほど聴き応えのある音源だし、前作『The River』と次作『Born In The USA』の間を埋める存在として、歴史的にも大層貴重な音源といえるだろう。
しかし、その一方で、ブルース自身がこの音源をボツにしてしまったことが物語っている通り、確かにそこには「何か」が決定的に欠けてしまっている。それが一体なんであったのかは、ディスク4のオリジナル音源を聴き、先述の映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』を観ればおのずと知れるだろう。私は、上述の映画評で、その何かとはずばり(G・フロイトのいう)「不気味なもの」であったと論じた。そして、そうやって論じる行為の中で、私自身がこれまでの人生において「不気味なもの」の影に慄きながらも、同時に逃れがたく魅了され、それを追い求めてきたことを知ったのだった。「不気味なもの」──つまり、ロックンロールを駆動させ、この自分を明日へと拐かす亡霊のようなものは、いつでも過去から、根源の方からやってくるのである。
購入はこちら
diskunion
(以上、文/柴崎祐二)
Text By Yuji Shibasaki
柴崎祐二 リイシュー連載【未来は懐かしい】
過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)

