綾をなすダンス・ミュージックの探求へ
〜フォー・テット アルバム・ガイド〜
フォー・テットことキエラン・ヘブデンの活動は実に多岐に渡る。フォー・テット名義の作品のみならず、DJ、リミキサー、プロデューサーとして多くのアーティストとコラボレーションを重ねてきた。今年の《Coachella》では急遽出演キャンセルとなったフランク・オーシャンの代わりに、スクリレックス、Fred again..とのトリオ編成によるライヴを大観衆の前で魅せたことも記憶に新しい。
英ロンドン・パトニー出身のヘブデンは15歳の時に、ポストロック・バンド、Fridgeでレーベル契約を結ぶ。その後は奔放というかストイックというべきか、⣎⡇ꉺლ༽இ•̛)ྀ◞ ༎ຶ ༽ৣৢ؞ৢ؞ؖ ꉺლ名義、△▃△▓名義、00110100 01010100名義、KH(ケイ・エイチ)、パーカッションズ、と別名義をサウンド・スタイルにあわせて着実に作品を編み出してきた。
有名なのは、批評家たちが”フォークトロニカ”とフォー・テットの音楽(『Pause』)を言い表したことだ。生楽器の持つ温かさに電子音を結合させるフォークトロニカ。これはヘブデンが長い事DJで培った経験から生まれた側面もあるだろう。巧みなマニピュレートを施したコラージュは一聴してフォー・テットだとわかる。フリー・ジャズ、ヒップホップ、ハウス・ミュージック……さまざまな文脈の音楽に影響を受けてきた彼の作品はカオティックで優美だ。
そんなフォー・テット名義のファースト・シングル「Thirtysixtwentyfive」の1998年のリリースから、今年でちょうど25周年を迎える。さらにはFridge『Happiness』(2001年)の記念盤が今年リイシューされ話題を集めた。そこで彼の活動を俯瞰するべくフォー・テットのアルバム・ガイドをお送りする。ここではスタジオ・アルバムに加えてEP『Ringer』を取り上げているが、別名義を含めフォー・テットの作品は他にも驚くほど多くある。この記事があくなきダンス・ミュージックの探究へ触れるきっかけとなれば幸いだ。(編集部)
(ディスク・ガイド原稿/天井潤之介、天野龍太郎、岡村詩野、尾野泰幸、木津毅、坂本哲哉、佐藤遥、高久大輝、髙橋翔哉、吉澤奈々)
※文中でのKieran Hebden片仮名表記に「キーラン」「キエラン」とバラつきがありますが、筆者の表記をそのままにしてあります。
『Dialogue』
1999年 / Output

トータス、ガスター・デル・ソルらに拮抗しうる演奏のセンスとスキルを持つイギリスのバンドの一つがFridge、つまりキーラン・ヘブデンがメンバーだった3人組。当時はそんな印象があった。Fridge自体はかなりポストロック寄りで、ヘブデンによる4T Recordings名義でのEP『Double Density』(1997年)もタイトル曲はクラウトロック調。ところが、その後フォー・テットとして届けられた1曲36分ものシングル「Thirtysixtwentyfive」(1998年)、「Misnomer」(1999年)などを経てファースト・アルバムへと続く流れは、いったんファットに肉をつけたのちに徐々に削ぎ落としていくプロセスを見ているようで実に刺激的だった。そして、他のポストロック系とも、エレクトロニカ勢とも一線を画したのがそのファースト……つまり本作だ。サンプリング、ループを生かしたミニマルな曲もあるが、圧巻なのは前述の「Misnomer」や「3.3 Degrees from the Pole」、そして生ドラムとアコースティック・ベースを軽やかに操りながら、サックス、ヴィブラフォン、タブラ、シタールなども取り入れて速度をあげながら鋭く切り込んでいくラストの「The Butterfly Effect」だろう。これらを聴くと、今日の新世代ジャズとシンクロ……それどころかかなり早くからヘブデンの目標にジャズの解体があったことに気付かされる。初期からフォークトロニカとして紹介されることも多かったが、少なくとも本作はジャズトロニカといった仕上がりだと思う。(岡村詩野)
『Pause』
2001年 / Domino

後年ヘブデンはフォー・テット名義の初期作品について批判的なコメントを発していて、とくにこの2枚目は評価が低い。そこには、生演奏のエレクトロニック・ミュージックで即興演奏をするという“本懐”を次作以降で形にしたことからくる反動という側面もあるのだが、何より「フォークトロニカ」とタグ付けされ消費されたことへの失望が大きかったようだ。もっとも、生楽器のオーガニックな音色とエレクトロニクスの実験が融合したその牧歌的でアトモスフェリックなサウンドは今聴いても抗いがたく魅力的で、当時ボーズ・オブ・カナダやアイサンなどの諸作と共に商品棚に並べられた事実はしかし本作の価値を貶めるものではけっしてない。そして、ヒップホップのビートやドラムンベース、子供たちの詠唱のサンプル、フラメンコのメロディ、アフリカやバリのリズム楽器……と目まぐるしいヴァリエーションをまとめ上げる手際の良さは、DJカルチャーを通過したターンテーブリストであるヘブデンの抜きんでた個性でもあるだろう。「Parks」が誘うダウンテンポなアンビエンスと「No More Mosquitoes」のヘヴィで耳愉しいコラージュは、勾配豊かな本作の両端を示している。一方、文字通りフォークと電子音響の領域を横断するように視野が開かれたその音作りは、フリッジ時代の盟友アーデムやマイス・パレードのアダム・ピアースがそうだったように、たとえばサンバーンド・ハンド・オブ・ザ・マンとのコラボなどを通じてフリー・フォークの文脈においてもクローズアップされることになる。(天井潤之介)
『Rounds』
2003年 / Domino

初期フォー・テットを代表する作品との呼び声も高い本作は、たしかに非常にバランスが良く、まるでここにはすべて──大まかに言えばエレクトロニカ、ヒップホップ、ジャズ、フォーク、ノイズ、アンビエント──があるようにさえ感じる。とは言ってもダンスの要素は薄い。というかダンスできなくもないが、フロアが見えてこない。本作はほとんどサンプルで構成されためまぐるしいサウンドである一方で、フォー・テットを象徴する暖かく美しい音色が損なわれることはなく、その音は極めてパーソナルなフィーリングを全体に与えているのだ(本作が“フォークトロニカ”という言葉に収まらない音楽性であるにも関わらずそう呼ばれる所以はこのあたりにあるだろう)。実験的な要素が顔を出す瞬間も数えきれないが、それらはあくまでドキュメンタリーフィルムによくある織込み済みのアクシデントのようなもので、感情の高まりを演出する装置としてそこにある。“想像上の”だとか“架空の”だとか言いたくなるような、デフォルメされたドリーミーな音の空間。もちろん、この良く出来たサウンド・コラージュの箱庭に長居するのも悪くないのだが、「Slow Jam」のカタルシスあるクロージングまで聴き終えて、もし出来すぎだと感じたなら、あるいは「Spirit Fingers」のようなトラックに心奪われてしまったなら、キエラン・ヘブデンの作品群をさらに深掘りしてみるべきだろう。個人的には、まずはこれを聴いてみて欲しいと言いたくなる、試金石的な一作だ。(高久大輝)
『Everything Ecstatic』
2005年 / Domino

ヘブデンの愛するフリー・ジャズ要素を膨張させ、フォークトロニカからの脱却を図るように思えた本作。『Pause』や『Rounds』ではアコースティック・ギターやダウンテンポを用いた、メロウな揺れと軽さがあった。一方、『Everything Ecstatic』は複雑なリズム・パターンに傾斜を深めている。90年代ビッグ・ビートを思わせる「a joy」から始まり、素朴なパーカッションが巨大化していく「Sun Drums and Soil」。そのアヴァンギャルドなドラムの演奏は翌年からコラボレーションを重ねる、ジャズ・ドラマーのスティーヴ・リードの影響がすでに伺えるようだ。実際にKieran Hebden & Steve Reid『The Exchange Session Vol.1』での即興演奏は、ヘブデンの直感的なサンプラーとリードの研ぎ澄まされたドラミングが、かっちりと合わさっていた。このリズムへの執着は、のちの『Ringer』で変容を遂げることになるのだが。とはいえ、陽気にベルやシンセのコードを重ねる「Smile around the face」はフリー・フォークとの接近を感じられるし、「High Fives」はヒップホップとエレクトロニカの対峙など、ヘブデンが得意とする多彩な音使いが見られる。カラフルなアートワークが示すように、多くの音色を四方へ散りばめた本作はある意味、これまでの歩みを総括するアルバムと言えるだろう。(吉澤奈々)
『Ringer』EP
2008年 / Domino

光り輝く旋律と生楽器由来のサンプルの温かい音色、瑞々しい電子音がほぼ完璧なバランスで融合した『Rounds』を経て、キエラン・ヘブデンはフリー・ジャズにボアダムスを衝突させたような『Everything Ecstatic』を発表し、混沌とした音世界へ突き進む。 そこにあったビートの強調は彼のダンスへの憧憬のように思えたが、決してダンスを誘発するサウンドではなかった。そんなどこかまわりくどいカオティックなサウンドから、一気にミニマル・テクノへと舵を切ったのが本作である。様々なループをレイヤードしながら展開するタイトル曲は、マニュエル・ゲッチング『E2-E4』にカール・クレイグの初期作品を繋げたようなグルーヴィーなトラックだし、続く「Ribbons」では透明感のあるメロディとイーヴン・キックを織り重ね、我々を恍惚へ導く。さらに「Swimmer」では発振器のようなシンセ音、生楽器のサンプル、反復ビートの組み合わせで白昼夢へと誘い、アフロビートを効果的に用いた「Wing Body Wing」でダンスの沼へ引きずり込む。そう、本作は紛れもなく、ヘブデンのダンスへの欲望が初めて具現化された作品だ。本作がなければブリアルとの「Moth / Wolf Cub」(2009年)は生まれなかったと思うし、もっと言えば『There Is Love in You』だって生まれなかったかもしれない。結果論かもしれないが、わたしはそう強く思う。(坂本哲哉)
『There Is Love in You』
2010年 / Domino

フォー・テットことキーラン・ヘブデンというのはとても不思議なひとである。インターネットの世界では別名義の⣎⡇ꉺლ༽இ•̛)ྀ◞ ༎ຶ ༽ৣৢ؞ৢ؞ؖ ꉺლや00110100 01010100の作品に親しんでいるリスナーも多いだろう。フリッジで活動した前史、無数のリミックス・ワークス、最近のスクリレックスとフレッド・アゲインとの協働など、全体像を掴むだけでも一苦労なアーティストだ。そんなフォー・テットの重要作をいくつか挙げろと言われたら、この『There Is Love in You』は間違いなく筆頭に上がるアルバムであるはず。初期の『Pause』や『Rounds』に代表される、いわゆるフォークトロニカ的作風をより洗練させ、シンプル化、ミニマル化を推し進め、ミーム化したあのポストを思いださせるような現在の作家性に通じるアーティストリーを確立させた傑作だと言える。前作にあたるEP『Ringer』は長尺曲を4つ収めており、サウンドは思いっきりテクノ。しかし本作は4分の4のキックを強調し、ヒップホップ的な風合いを抑える代わりにダンス・ミュージック的な趣を強めながらも静謐さと涼やかさを保持し、陳腐な表現をするとダンスフロアとベッドルームの併存、幻想的なヴィジョンと冷めた視点の共存、という矛盾を最大の強みにしている。クラックル・ノイズ、アコースティックな器楽音やゴーストリーなヴォーカルのサンプル、アフリカンなリズムへのさりげない志向性……。クローザーの「She Just Likes to Fight」はフォー・テットらしい温かみと感傷、メランコリーに満ちた美しいピースだ。ちなみに2010年といえば、ジェイムズ・ブレイクがEP『CMYK』をリリースした年。フォー・テットは2009年に学友ベリアルと初の共作EP『Moth / Wolf Cub』をリリースしており、シーンなるものからは常に浮いた存在ではあるが、ポスト・ダブステップの潮流にも敏感に反応していたのではないだろうかと想像する。(天野龍太郎)
『Pink』
2012年 / Text
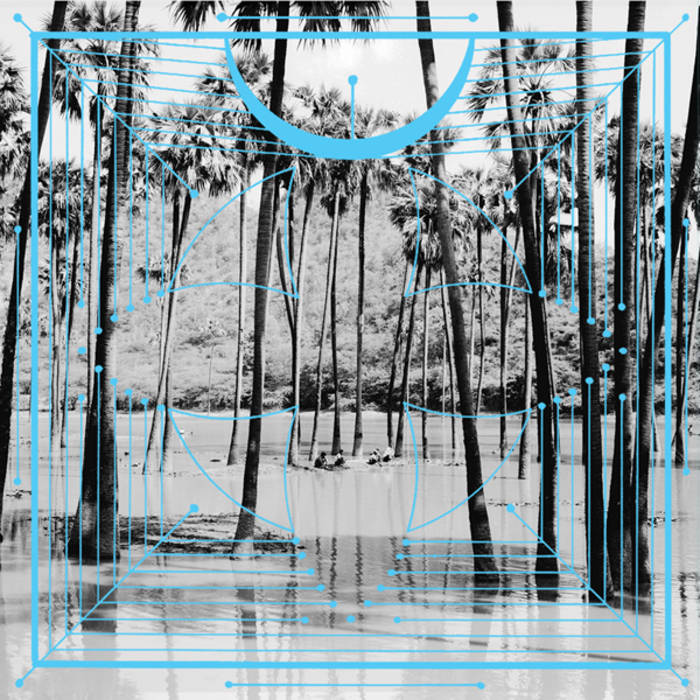
『There Is Love in You』発表後、キエラン・ヘブデンによるダンス・ミュージックの探究はますます加速していく。《fabric》からのミックスCD『FabricLive 59』(2011年)では、UKガラージを中心とするビートの連続体にクラブ内で採集した環境音を混入するという野心的なミックスを披露。さらに自身のレーベル=《Text》からは、ダンスフロア直撃の12インチを連発。本作はその12インチからの6曲に2曲の未発表曲を追加したものである。いわば編集盤という体裁ではあるが、その実は、彼が『There Is Love in You』の称賛に胡坐をかくことなく、自身のサウンドを拡張し続けていることをまざまざと証明した作品だ。身体がリズムを捉えたと思った瞬間、リズムが身体から逃げていく──そんなある種の至福の時間をメロディックなベース・テクノで表現した「Locked」やアクフェンを彷彿させるカットアップ・ハウスをよりメロウなものとして響かせた「Pyramid」、あるいは官能的なジャズ・ハウスの「Pinnacles」(個人的には彼のベスト・トラックの一つだと思う)。これらを聴くだけでも、当時ヘブデンが異常なスピードでサウンドを深化させていたことが理解できるだろう。こんなダンスへの情熱溢れる本作の翌年に、ジャングル/レイヴ・ミュージックの持つ儚さに着目した『Beautiful Rewind』を発表しているのも興味深い。(坂本哲哉)
『Beautiful Rewind 』
2013年 / Text
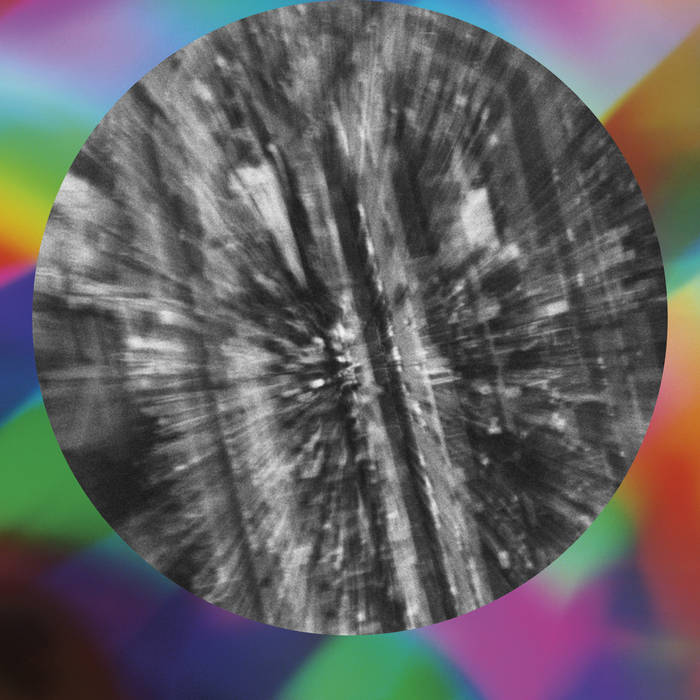
オリジナル・アルバムとしては前作にあたる『There Is Love in You』は、キエラン・ヘブデンが得意とする綺麗な音色やメロディを保持したままダンスフロアへとぐっと接近した作品だった。それからブリアルとトム・ヨークとのコラボレーション12インチ「Ego/Mirror」(2011年)があり、シングル・コンピレーション『Pink』があり、この『Beautiful Rewind』ではさらに意識的にクラブ・ミュージックの内側に分け入っている。先行シングル「Kool FM」がオリジナル・レイヴ時代のおもにジャングルやドラムンベースを流していた海賊ラジオの名前を取っていることからもわかるように、ワイルドで猥雑なエネルギーが迸るフロアを目指しているのだ。それは、どこか潔癖なイメージのあったフォー・テットのエレクトロニック・ミュージックの外側を探求する試みであったかもしれない。チャイムの音とヴォイス・サンプルとビートがガチャガチャした「Gong」で始め、同時代のベース・ミュージックやグライムとシンクロしつつ、あまり統一感なくトラックを並べているのは初期レイヴのような雑食性をコンセプトにしているように感じられる。もちろんフォー・テットらしい美しくドリーミーなメロディはあるが、それはよりダンスフロアの現場に近いところで(あるいはまさにそこで)鳴らされている。かつてヘブデンのエレクトロニカやポストロックは肥大化したダンス・ミュージックに対するオルタナティヴだったが、その先でふたつの道は繊細かつ大胆に合流した。(木津毅)
『Morning / Evening』
2015年 / Text
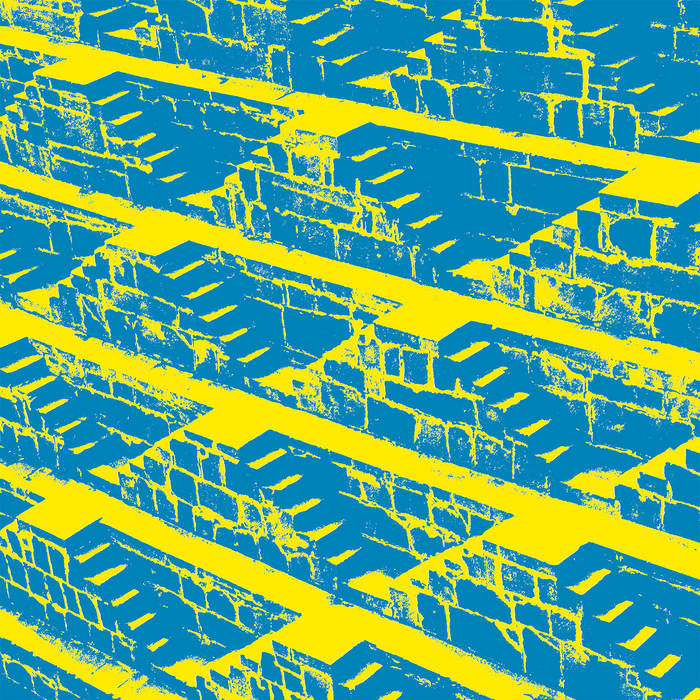
「Morning Side」と「Evening Side」と銘打たれた20分程度の楽曲2つにて構成された8枚目。「Morining Side」は楽曲を先導する四つ打ちのビートとインドの著名なプレイバック・シンガーであるラタ・マンゲシュカルの幻想的で透き通るような歌声のサンプリングが印象的。5分過ぎからは徐々にキーボードの音数を増やしながらアンビエント感を強めたと思えば、そのあとには複雑なパターンのドラム・マシンが張り巡らされる。15分前後にヴォーカル・サンプリングがフェイド・アウトしたあとは、シンセサイザーが主体の明度の高いドローン・パートとなり楽曲が締めくくられていく。一方、「Evening Side」は「Morning Side」と比べてよりミニマルかつインダストリアルな音像が特徴だ。ミニマルなエレクトロニカで構成された導入部分から、何者かに祈りを捧げるような歌声と多種のシンセサイザーが瞑想的に響き渡る中盤を経て、後半はプリミティヴなハウス・ミュージックが展開し、アルバムは幕を閉じる。
アルバム・タイトルの通り、朝と夜のサウンド・スケープをフォー・テットの身体を介して解釈した実験的なコンセプト・アルバムとして本作を解釈することも可能だが、上述したマンゲシュカルのヴォーカル・サンプリングや、「Evening Side」の最後に登場するハウス・サウンドからは、彼の人種的/音楽的ルーツに対する思考の痕跡を感じる。(尾野泰幸)
『New Energy』
2017年 / Text
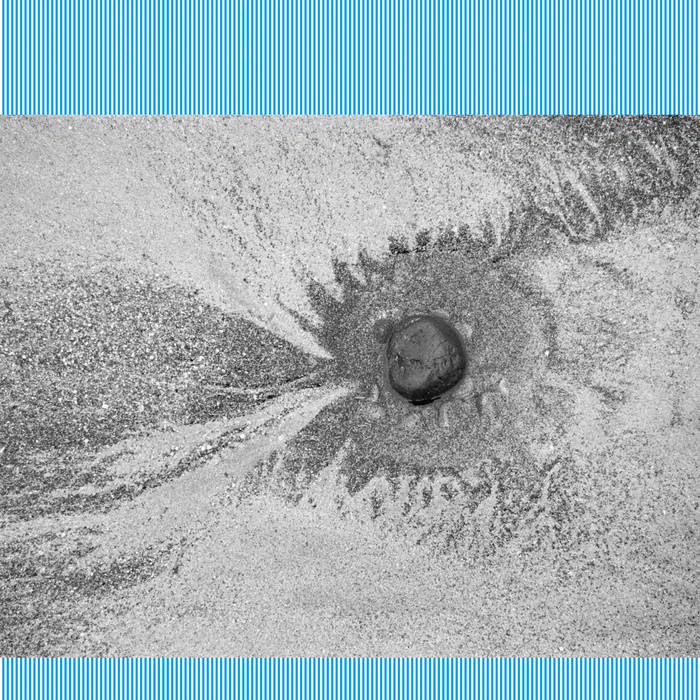
『There Is Love In You』でのダンスフロアへの接近以降というもの、シングルやアルバムごとにさまざまテイストを変えながらも、シーンでの地位を確固たるものとした2010年代のフォー・テット。その中でも2017年は、複数の変名プロジェクトでのリリースを開始し、さらに活動の形や存在感を不定&不測のものにしていったという意味で、ヘブデンにとって節目の年だったのではないか。それを補強するようにこの『New Energy』は、彼のこれまでのキャリアを振り返るような作品として評価されている。すなわち、『Rounds』のあたたかな生楽器の響きにダウンテンポ的なゆるやかなビートと、『There Is Love In You』以降のUKハウス的な洗練された繊細なテクスチャのめぐり合わせ。そこから浮かび上がるのはヘブデンのリフ・メイカーとしての才であり、そのミニマルな美しさには、思わず日常の煩雑さや時間の早さやらを忘れてうっとりとしてしまう。「Lush」のハンドパンによる印象的なリフが聴こえた瞬間、身体と精神が再び一定のリズムを刻み始めるのを感じる。「Daughter」のヴォイス・サンプルがループすると、自分の中にもまだ振動する声と体温があったことを思いだし静かに歓喜する。このビートやベースやループはダンスフロア向けというよりは、帰る場所なき自室での唯一の逃げ場になりうるような音楽である。鬱々と塞ぎこんだ重い吐息に対して、蓋をこじ開けるでもなくただうすく優しく包みこんでくれるアルバムだ。(髙橋翔哉)
『Sixteen Oceans』
2020年 / Text

パンデミックの発生という時分に届いたのは、カリブー『Suddenly』の多様なジャンルをつなぎ漂うやさしさ、そして、このアルバムの同じ場所に留まり包み込むやさしさだった。本アルバムにはこれまでの作品と共通する特徴が多くある。たとえば、ダンス・ミュージックへの傾倒があらわになった『There Is Love in You』からよく使われているローファイで乾いたキックによるミニマルなビート。活動初期から頻繁に使われているハープシコードやハープ、ベルのような音に、「Baby」のカットアップされ詰まるようなヴォーカル。「Teenage Birdsong」のフリー・ジャズの影響が顕著だった頃をかすめるブラス。前作からよりメロウになったメロディ。これらが、いままでに増して豊かになったリヴァーブやディレイによって反射し増幅し、あたたかな木漏れ日のように辺りを満たす。そこに、これもまた彼の楽曲でよく聴かれる鳥のさえずりや水の流れる音のフィールド・レコーディングと、それらをより近く鮮明で人工的にした音とがたびたびコラージュされる。まるで本作を聴いているときにだけ現れる、共生のバランスが取れた繊細で美しい生態系を訪れているようでもある。やわらかい光に包まれたその中で、このアルバムは平和を祈るマントラを遠くに聴きながら、まどろんで目を閉じるようにそっと終わる。ロマンチックな安穏の余韻を残して。(佐藤遥)
『Parallel』
2020年 / Text
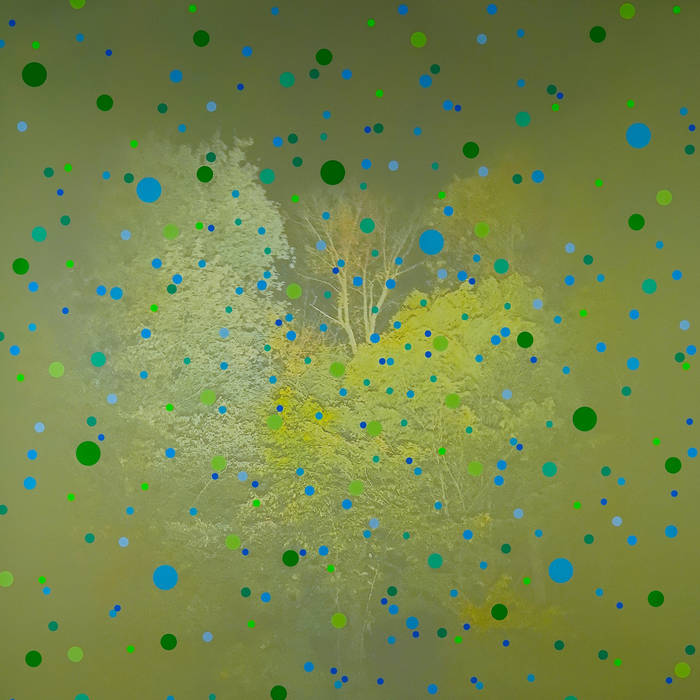
よりミニマルに、混沌とした広がりを魅せる『Parrallel』。簡素な番号のついたトラックは音数を抑え、シンセのアルペジエーターから厳かに響きだす。続く「Parallel 2」のハイハットとピアノの入れ替わりはヘブデンが影響を受けたハウス・ミュージックへの愛だろうか。長年続けているDJについて、「中毒性がある」と語ったように次第にビートは加速していく。静寂なエレクトロニカの「Parallel 7」は音色は違えど、『Pause』に漂うメランコリックさがあるように、フォークトロニカと呼ばれたフォー・テットの音楽は着実に探究を繰り返し、フロアへ向けたダンス・ミュージックへと遂げていた。この2020年は多作を極めた年でもある。トム・ヨーク、ブリアルとコラボレーションしたEP『Her Revolution / His Rope』をはじめ、本作と同時発表された、00110100 01010100名義での『871』。翌年はビートメイカー、マッドリブとのアルバム『Sound Ancestors』を控える。なかでも、『871』は『Dialogue』以前の1995年から1997年にかけて制作された作品。アンビエント〜ノイズ〜フォーク〜ブレイクビーツまでをも内包する実験性の強いアルバムだ。ヘブデンの当初の着想を詰め込んだ『871』は、本作『Parrallel』(並列/平行)の言葉が指すように、フォー・テットの音楽性を示唆している。(吉澤奈々)
Text By Ryutaro AmanoJunnosuke AmaiHaruka SatoShoya TakahashiNana YoshizawaTsuyoshi KizuShino OkamuraDaiki TakakuTetsuya SakamotoYasuyuki Ono
関連記事
【REVIEW】
Four Tet 『Planet』
ベッドルームとダンスフロアの往還から生まれた、ほのかに官能的なディープ・ミニマル・ハウス
http://turntokyo.com/reviews/fourtet-planet/
【REVIEW】
Four Tet 『Sixteen Oceans』
ダンスフロア向けの肉体的な音楽から離れる準備
http://turntokyo.com/reviews/fourtet-sixteenoceans/
