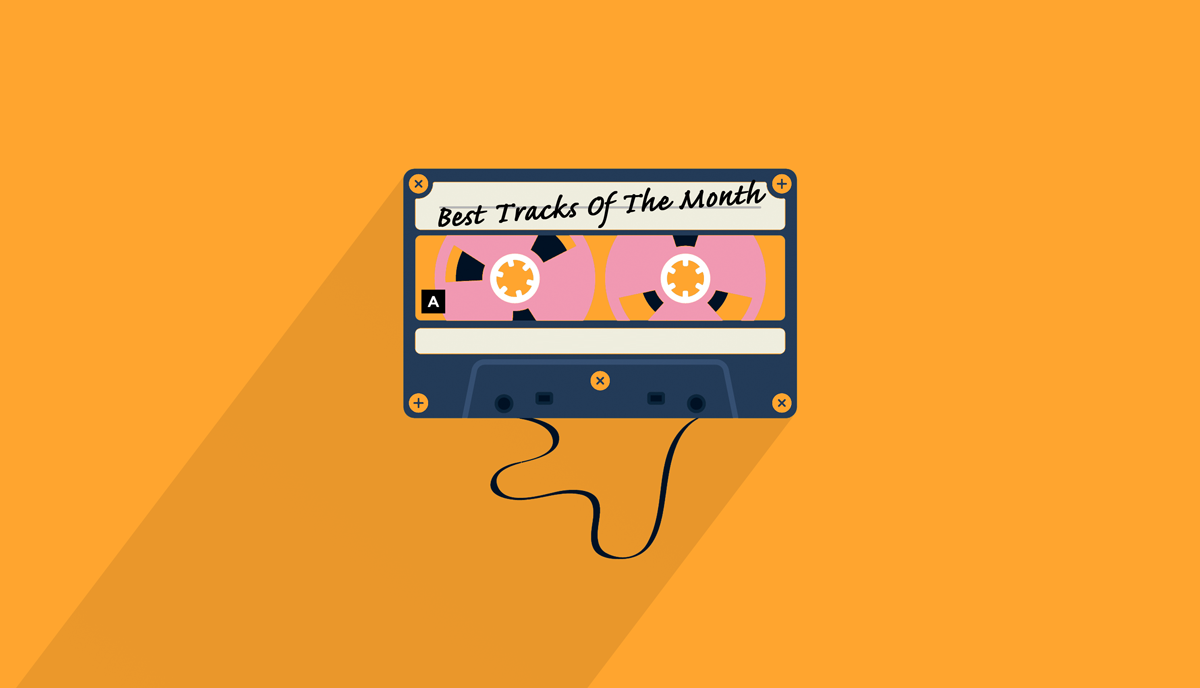BEST 18 TRACKS OF THE MONTH – November, 2021
Editor’s Choices
まずはTURN編集部が合議でピックアップした楽曲をお届け!
Earl Sweatshirt – 「2010」
デビュー・ミックステープ『Earl』を発表した年をタイトルに据え、アール・スウェットシャツが新曲をリリース。アールのツアーDJであり、彼のレーベルと契約した初のアーティストでもあるBlack Noi$eによるトラックは水面に広がる波紋のようにややサイケデリックで心地よく、ラップと絡み合ってその言葉を引き立てている。抽象的で詩情に溢れた表現はもちろん健在で、『Some Rap Songs』(2018年)や『FEET OF CLAY』(2019年)で見せてきた不可解な(それでも十二分に魅力的な)リリックと比べると明快といっていいだろう。稀代のリリシストが再び外の世界へと踏み出し始めた。(高久大輝)
Jenny Hval – 「Jupiter」
これは素晴らしい! 今年はロスト・ガールズとしてアルバムをリリースしたノルウェーのジェニー・ヴァルが《4AD》と契約。来年には届くだろうニュー・アルバムに向けた先行曲だが、こんなにエレガントで洗練された歌モノを聴かせるとは……と驚くばかりだ。そのメロディの美しさ、彼女の歌の凛々しさに惚れ惚れするが、約8分もの長尺の後半はこれまでのジェニーのキャリアを裏切らないアブストラクトなエレクトロが優美に展開されていく。MVでは“Close your eyes now. Listen. There is nothing left to see.”というメッセージが現れてからのノイズと化していく最終盤と、殆ど聞きとれない彼女の呟きにも注目したい。(岡村詩野)
Naima Bock – 「30 Degrees」
元ゴート・ガールのベーシストのソロ曲だが、あのポスト・パンクな音楽の面影はあまり無い。アコースティック・ギターとおそらくはダルシマーによるフレーズ、その後方から高揚感のあるクラップとカバサやカウベルのような異国情緒を感じるパーカッションが聞こえるなど、様々な楽器が鳴らされている。SSWとして《Sub Pop》からデビューとなったNaima Bockのこの曲には、折衷の感覚がそこかしこに潜んでいて面白い。幼少期にサンパウロに住み、7歳の時にサウス・ロンドンに移住したという彼女の、ブリティッシュク・フォークのようでブラジル音楽的でもある、複数の国のルーツを感じさせる自己紹介がわりの曲だと思える。(加藤孔紀)
snow ellet, Quarter-Life Crisis – 「Cannonball」
シカゴを拠点とするインディー・ロック・アクト、スノウ・エレットによる最新楽曲。弾けるファズ・ギターと快活なエレットのボーカルが駆け抜けていく2000年代ポップ・エモ、ポップ・パンク的な大味さが魅力の本曲は昨年フランシス・クィンランやクロード、ハンド・ハビッツらを迎えたEPをリリースしているマルチ・プロデューサーのライアン・ヘムズワースによるプロジェクト“Quarter-Life Crisis”とのタッグの下で制作されている。本年3月にリリースされているエレットのデビューEP『suburban indie rock star』よりも厚みを増したこのエモ・チューンに、早くも次作への期待を高めてしまう。(尾野泰幸)
Sun June – 「Easy」
昨今インディー・フォークのホットスポットとなっている、テキサス・オースティン。今年はバック・ミーク、ケイティ・カービーと優れたSSW作品をドロップした地元レーベル《Keeled Scales》から前作をリリースしている5人組、Sun Juneもその流れを汲むバンドだ。レトロ・ポップとフォークをベースに、堅実なリズム隊、柔らかくきらめくギター・サウンド……とアレンジ自体はごくシンプルながら、それゆえにフロントマンのまどろむようなヴォーカルが際立つ、引き算具合が秀逸だ。キリッとしたピアノの音色で要所を引き締め、いなたくなりすぎない音像のバランス感も確信犯的。こうした肩の力の抜けた良質なポップスこそ、案外貴重なのでは。(井草七海)
Writer’s Choices
続いてTURNライター陣がそれぞれの専門分野から聴き逃し厳禁の楽曲をピックアップ!
Blackhaine – 「And Salford Falls Apart」
マンチェスターの電子/実験音楽シーンが面白くなってきている──これは今年リリースされたスペース・アフリカの『Honest Labour』を聴いたときにぼんやりと感じたことだが、同作にも参加したBlackhaineのこの新EPを聴いて、その思いは強くなるばかりだ。凍つくようなアンビエントにヘヴィなベースと冷徹なラップが交錯する冒頭曲も素晴らしいが、特筆すべきはタイトル曲だろう。サンO)))、メルツバウ、そしてデス・グリップスが火花を散らしているような重厚なノイズの上で、彼はブレグジット後の英国での生活に対する怒りを激しく叫ぶ。今年、これほど鋭利に時代への反抗を表現した電子音楽はあっただろうか。(坂本哲哉)
Blu DeTiger – 「Blondes」
兄のRex DeTigerと楽曲制作を行っているBlu DeTigerの最新作。彼女の魅力はディスコティックなグルーヴを醸し出すベースだが、本作もその魅力を遺憾なく発揮している。この曲には、この兄妹に加えJennna Andrews(BTSなどの楽曲制作)やTeddy Geiger(マルーン5などの楽曲制作)、2000年代ディスコ・リバイバルのアイコンだったアフィが参加している。彼女たちの活動はこの20年ディスコ・ポップの文脈でも大きな影響を与えてきたことを考えると、本作の人選やサウンドは、ディスコを一時の流行ではなく、形式として定着させてきた彼女たちへのリスペクトが込められているのではないだろうか。(杉山慧)
Bonobo -「Otomo (feat. O’Flynn)」
なんてドラマチックなんだろう。来年リリースの新作『Fragments』からの先行カットは深夜のクラブにしかない情感を思い起こさせ、僕は思わず涙が出てしまう。大胆にサンプリングされたブルガリアの合唱団の歌声が、オフリンの持ち込んだダイナミックなリズムセクションに彩られる様は、まさにフロアで踊りふける人々の感情が憑依しているかのよう。身体を揺らすウーファーの重低音、感覚が混濁する夢うつつな音像、ひたむきに自分の鼓動に没頭する群衆、あの陶酔感。僕らはまたあの美しい光景を描いていけるんだ。フロアで鳴るために生まれたようなこの楽曲が、数多のミュージックラバーにそんな希望をもたらすことは想像に難くない。(阿部 仁知)
Johanna Samuels & Ohtis – 「Via Chicago」
LAを拠点に活動するシンガーソングライターとイリノイのカントリー・ロック・バンドが共演、ウィルコの名曲をカヴァーした。「昨日また君を殺す夢を見た/それでオレは全然OKだった」と始まる、ライヴではカオティックな音の嵐が吹き荒れる彼らの重要曲だが、語り部の声が変わることで物語の主人公や背景に新しい色の照明が当てられて、装い新たに目の前に歌が立ち上がってきて新鮮。男女混声、レイドバックした演奏で奏でられる本楽曲を聴いて僕が想起したのはピーター、ポール&マリーがカヴァーするディラン楽曲だった。ジェフ・トウィーディーの深遠で捻じくれた詩作で語られる望郷の想いが世代をまたいでメロディアスなラブソングとしてロマンティックに響く。(山田稔明)
Joyul -「Marginalia」
深いリバーブに包まれた静謐な歌と、スロウコアの影がみえるギターのアルペジオ。奥からは鳥のさえずりや水の滴り、雑踏の音が聴こえてくる。その美しい融合に身を委ねていると、やがて旋律とアンビエンスのバランスが逆転していることに気づくーー。韓国・ソウルを拠点とするJoyulは、ファースト・アルバム『Earwitness』で、歌や演奏だけでなく様々な環境音を共存させることで、ただならぬ「気配」を作り出しているように思う。本楽曲ではとりわけ顕著だ。自己と他者、動物と人間、この世とあの世の境界線が溶け合う感覚に、同じくアジアでタイの映画監督アピチャッポン・ウィーラセータクンの作品を重ねたのは私だけだろうか。(前田理子)
Saint Jude – 「Alright, All Tied」
刮目すべきコレクティブ《Slow Dance Records》の屋台骨を支えるサウス・ロンドンのプロデューサーは、クラブからベッドルームを経由したインディロックへのアプローチを継続する-ちょうどキング・クルールがDJ JD Sports名義でダンストラックを発表するのと対照的に。ダブステップを出自としながら、『In Rainbow』期のレディオヘッドを想起させるギターと深みのある歌声をくぐもったプロダクションのなか漂わせる。これまでより抽象度を高めたリリックが浮遊感を増幅させるとともに、彼独特の琴線に触れるメロディのセンスとプロダクションの“汚し”の感覚がとにかく冴えていて、永遠にループし続けたいほど心地よい。(駒井憲嗣)
Sea Girls – 「Hometown」
シー・ガールズは2015年にロンドンで結成された4人組バンド。2017年より音源をセルフ・リリースしてきたが、2019年に《Polydor》と契約し、20年にはデビュー・アルバム『Open Up Your Head』をリリースした。キラキラとしたシンセ・サウンドをアクセントにした、ザ・キラーズに通じるキャッチーなロックが魅力で、フォールズのフロント・アクトに起用されたのもよくわかる。この「Hometown」は2022年1月14日にリリースされるセカンド・アルバム『Homesick』からの先行トラックで、エモーショナルな展開を含めて、王道のUKロックが復調しつつあることを実感させる。2022年はシー・ガールズのような存在と、現在日本でも注目されているポスト・パンク~エクスペリメンタル・バンドたちが両輪となって、UKの音楽界を活気づけそうだ。(油納将志)
Terrace Martin – 「Work It Out (feat. Cordae) 」
DJクイックの「Pitch In OnA Party」が、ハウス・パーティーでなく、ラスベガスのホテルのロビーかバーで生演奏されているとしたら、こんな感じ? テラス・マーティンお得意の、上品な中にもギャングスタ・ラップらしさを感じさせるシンセサイザー+ヴォコーダー使いの一曲。コーデーはさすがの地力を感じさせるスムーズなフロウで、久しぶりの再会を果たした元カノに一夜の関係を求める。テラスのリリックはそれに比して幾分真面目そうだけど、このトラックの遊び具合から察するに、あまりまともなことを考えていなさそう。まぁでも、いいんじゃない? それで。待望のアルバム『DRONES』収録。(奧田翔)
TNGHT – 「TUMS」
2年ぶりの新曲はLAで開催のパーティーに先立ってリリースされた。パーティー再開への期待から生まれた楽曲というコメントに合点がいく、奇妙な笑い声やスライド・ホイッスルがマッチしたユーフォリックなエレクトロニック・ミュージック。発散と収束を繰り返すシンセと抜き差しされるベースが高揚感を生み出し、希望に溢れた瞬間の訪れを予感させる。またこのシンセはいままでになくエモーショナルで音圧が高く、ベースもラウドで強烈だ。TNGHTは偶発性や楽しさ重視の感覚的なプロジェクトではあるが、こういった特徴からは、ダンス・ミュージックとしてのトラップを形作った彼らなりのRageサウンドと受け取ることもできる。(佐藤遥)
Wu-Lu – 「Broken Homes」
現代UKジャズとブラック・ミディを繋ぐ「怪人」が、《Warp》との契約と同時に発表したアルバム先行曲。地元スタジオ「The Room」をクウェイク・ベースと運営する人脈の繋がりもありジャズの文脈で名前が挙がることも多い彼だが、特に近作はソニック・ユース等、オルタナティブ・ロックのファンにも響く魅力がある。この新曲でも南ロンドンの「壊れた家庭」、それを生み出す社会を「Shit」と吐き捨てつつ、ダビーで重いドラム&ベースと共にノイズ・ギターの多層的な質感を追求。レディオヘッド「The National Anthem」へ20年越しのオマージュのようにも聴こえるダーク・サイケデリック・チューン。(佐藤優太)
陳以恆 Yi Heng Chen – 「In Touch」
2019年のEP「但係我愛袂驚惶」以降、Robot Swing や王彙筑の楽曲へのゲスト参加が続いていた陳以恆。待望のシングルは國立歴史博物館(台湾・台北市)で昨秋開催された特別展《In Touch》のテーマソングというちょっと意外な形で発表され、ついにリリースとなった。ソウルやAORをベースにしたメロウなセンスは健在で、更に初めてラップを取り入れたことで台湾語シンガーとして新たな魅力を垣間見せた。ポロリポロリとつま弾かれる甘いギター、絶妙なズレを生む挑発的なドラム、それに複雑に絡み合っていく骨太なベースが混然一体となって、本作に通底する印象的なビートを構成し、不思議な高揚感を漂わせる一曲になっている。(Yo Kurokawa)
思い出野郎Aチーム – 「日々のパレード 」
コロナ前の空気をようやく取り戻しつつある社会と呼応し、土の香りがするサザン・ソウルのリズムの上で微かな希望が歌われる思い出野郎Aチームの新曲。歌詞の中に出てくる「セカンドライン」とは、ニューオリンズの葬送において、遺族の後に続いてパレードに参加する人々を指す。私たちが感じている明るい兆しは、無数の深い悲しみの上に成り立っていることを忘れないという思いが伝わってくる。そしてこの重いメッセージをケレン味なく、どこまでもポジティブに発信できるのは、コロナ禍が発生した直後からクラウドファンディングを通じて全国のライヴ・ハウスやレコード店をサポートするために奔走した彼らだからこそ。(ドリーミー刑事)
100 gecs – 「mememe」
8-bitノイズを散りばめた「mememe」を聴いて連想したのは、YouTubeで発見した100 gecsとCrystal Castelsをマッシュアップした二次創作音源。100 gecs自身もまた、ジャンルや意匠をコラージュしてミーム(meme)を作り楽しむ主体だったはずが、いつしか自身(me)もミームとして消費されているという皮肉。知名度を上げハイパーポップの旗手という役を担う一方で変わらないMVの質感には安心するが、Laura Lesの声はもう加工されていないし、ギターとドラム(風)の音色は生々しさを増している。甘い糖衣を取り払った声と音は、膨らんだ消費と期待から二人を解放しうるか。(髙橋翔哉)
【BEST TRACKS OF THE MONTH】
過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)
Text By Sho OkudaHitoshi AbeYo KurokawaHaruka SatoToshiaki YamadaKenji KomaiShoya TakahashiYuta SatoRiko MaedaDreamy DekaShino OkamuraMasashi YunoKei SugiyamaNami IgusaDaiki TakakuKoki KatoTetsuya SakamotoYasuyuki Ono