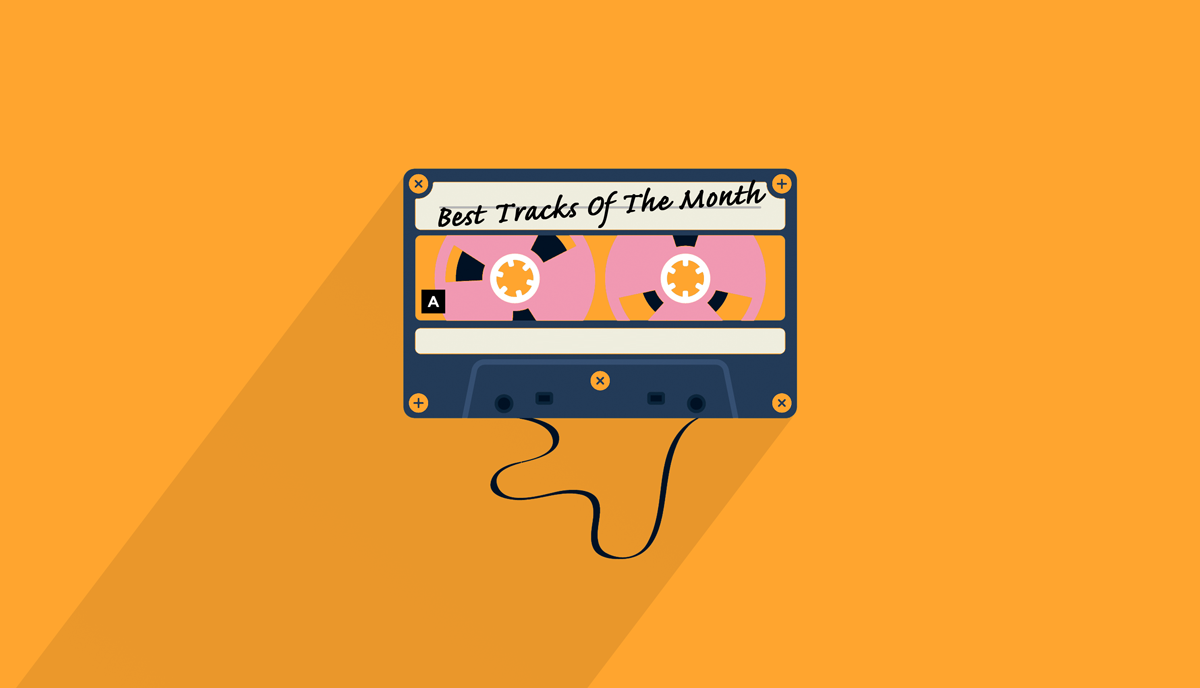BEST 14 TRACKS OF THE MONTH – November, 2022
Editor’s Choices
まずはTURN編集部が合議でピックアップした楽曲をお届け!
Hatchie – 「Nosedive」
インダストリアルな質感を含んだノイジーなビートに、オーストラリア出身のSSW、Hatchieの以前の作風を期待していた筆者は驚かされた。しかし、以前からマッドチェスター的なダンス・ビートを取り入れていた彼女にとって、80年前後のEBMや90年前後のgreboといったイングランド北部〜ヨーロッパのダンス・フィールの参照は案外自然な成り行きなのかも。彼女のようなドリーム・ポップ系アクトにおける80年代参照は以前から良くも悪くもな軽薄さがあった。しかしゴス・クラブに着想を得て、怒りや自己破壊をモチーフにしたというこの楽曲の、サウンド面でも前のめりな姿勢は、彼女の次のステージへの前進とシーンの今後の可能性の拡大を感じさせる。(髙橋翔哉)
Joe Rainey – 「Once The Reaper」
レッドレイク・オジブエ族(ミネソタ州北部に住む先住民族)の血を引くミネソタ出身のジョー・レイニー。ボン・イヴェール主催のウィスコンシンのフェスに出演した経緯もあり今年5月に《37d03d》から初のアルバム『Niineta』をリリースしたが、この曲を含むEPが今度は米ダーラムのレーベル《Psychic Hotline》から到着。アメリカ・インディアンの踊りの集会・祭りであるパウワウで5歳の頃から歌ってきただけに、チャントのような叫びにも似た歌が、激しく打ち鳴らされるパーカッション、キック・ドラムなどと一体となって轟く。Sun O)))あたりとの共振も感じさせる次世代のドゥーム・ヴォーカル・ミュージック。プロデューサーは今回もアンドリュー・ブロダー(Fog)。(岡村詩野)
Night Shop – 「Harness」
ケヴィン・モービーのバンドにおいて、ドラマーを担い、本年ソロ・アルバム『Forever Night』をリリースしたジャスティン・サリヴァンのソロ・プロジェクト、ナイトショップによるダブルA面シングルの一曲。恍惚としたディレイ・ギターとシンセサイザー、ピアノが楽曲全体のリラックスしたムードを形成しているが、タイトなドラムが楽曲中、継続して響くことで楽曲全体も引き締まった印象に。楽曲のテーマは世界におけるダイナミズムを時に受け入れ、時に従い、溺れ、祝福することであるというが、リリースに際し本シングルを「井戸から抜け出すための縄梯子のようなもの」と評したナイト・ショップのある種の世界に対する希望の感覚も本楽曲には内包されている。(尾野泰幸)
rRoxymore – 「Water Stains」
流動的なビート、断片的に立ち現れるメロディ。内省的かつ剥き身で、自由自在な美しい音のタペストリー。それはリスナーに、ダンスフロアに、新しい時間の感覚を与えるだろう。パリで音楽を学び、90年代半ばにDJをスタート、クィアパーティーの集団、Room 4 Resistanceに参加しつつ10年ほどベルリンでキャリアを築き、現在はベルリンからメキシコシティへの移住の最中だというrRoxymoreが、ノルウェーの実験的レーベル《Smalltown Supersound》からリリースした『Perpetual Now』。そのラストに収録された15分に及ぶ音の旅は、伸縮する“今”への誘いである。(高久大輝)
S.C.A.B. – 「Tuesday」
尖るギターのアルペジオを用いて、ノスタルジーからポストパンクまで行き来するのはブルックリンを拠点に活動するS.C.A.B.だ。《Grind Select》より発売されたセルフタイトル・アルバムから「Tuesday」。ヴォーカル&ギターのショーン・カマルゴが、アメリカのTV番組『Seinfeld』に登場するニューマンの台詞からインスピレーションを得たそう。「価値のあるものをあてもなく探していることを歌った曲」と話している。金属的なギターの響きと無機質に刻まれるビートから生じるリズムの揺れは、荒々しくもメロディアスだ。加えて、蜃気楼のような歪んだうねりの中を、一週間をやりこなす歌詞が浮き立つことで妙な現実性を感じる。(吉澤奈々)
Writer’s Choices
続いてTURNライター陣がそれぞれの専門分野から聴き逃し厳禁の楽曲をピックアップ!
Benito 80 & Juçara Marçal – 「Retalhos De Cetim」
70年代から今に至るまで、いくつものサンバ・クラシックを生み出してきたベニート・ヂ・パウラ。そんな彼の80歳を祝うプロジェクト「Benito 80」が立ち上げられ、息子であるホドリゴ・ヴェローゾのプロダクションによるコラボ・アルバム『Novo Samba Sempre Novo』がリリースされた。ベニートの名曲をサンバの名手たちが歌い直していく過程が、そこには瑞々しく刻み込まれている。特に唸らされたのはラストナンバー、ジュサーラ・マルサルによるものだ。サンバの前衛を切り開き続ける彼女と年輪を重ねたクラシックの邂逅、そのフットワークの軽やかさと鍛えられた足腰の強靭さが醸す、どこかあべこべで享楽的なクルーヴが堪らなく心地良い。(風間一慶)
hemlocke springs – 「Girlfriend」
ノース・キャロライナを拠点に活動する23歳、Isimeme Uduによるプロジェクトhemlocke springsのセカンド・シングル。前作はグライムス「Oblivion」っぽさを感じる楽曲だったが、本作は、宅録感を残しながらもブラック・キッズなど00年代後半の80年代リバイバルにおけるダンス・ポップの要素が強くなっている。サビである「あんたの彼女になりたいって誰が言った?」からは、思い上がんなよという怒りと呆れの感情が沸々と滲み出ており聴いていて痛快だ。80年代ダンス・ポップなサウンドは、こうした出来事を笑い飛ばす雰囲気が出ており、歌詞とサウンドの必然性という意味でも完成度の高い楽曲だ。(杉山慧)
H. Hawkline – 「Milk For Flowers」
来春に5枚目のアルバムがリリースされるウェールズのH. Hawkline。『In The Pink Of Condition』(2015年)から3作連続でケイト・ル・ボンがプロデュースを手掛けており、共同制作者としての彼女への絶大な信頼が伺える。その先行曲は、軽やかなピアノが先導するトッド・ラングレンさながらの魔法がかったサイケ・ポップ。シュールかつ理性的につづられるリリックは健在だが、一方で「君が恋しい、とても」とストレートに感情をあらわにする新しさも。「ひねくれ」という形容詩を冠したくなる音楽を鳴らしていた彼が「自分の血、骨、魂をさらけ出した」というアルバムは、きっと新境地に達しているはず。(前田理子)
Ingredient – 「Wolf」
イアン・ダニエル・キーオとルカ・コプロウスキーが結成したユニットのデビュー作より。〈colossal faith(大いなる信念)〉という言葉で始まるこの曲をオープナーに、アルバムの制作自体がコロナ禍の期間にメンタル・ヘルスの不調を覚えたキーオの治癒のためのプロセスだったという。柔らかなハーモニーと風通しの良いプロダクションを持つバレアリック経由のオブスキュアなシンセ・ポップは、交流がある同郷トロントのジョゼフ・シャバソンやザ・ゼンメン&ジョン・ムーズ、あるいはウェスターマンといったアーティストの間に漂っている。あるいは、YMOやジャパニーズ・ポップスへの屈折したトリビュートと言ってもいいかもしれない。(駒井憲嗣)
烏流Kuroshio – 「困佇彼个冬天的早頓」
烏流とは、台湾東部の暖流“黒潮”を意味する台湾語。まるでその激しい濁流の中にフュージョン、ファンク、R&Bといったジャンルを丸吞みしていくように“烏流”流のソウル・ミュージックを志向する6人組バンドだ。メンバーのベース陳健安、ドラム林子祈は問題總部としても活動していて、本作のミキシングに名を連ねる問題總部のリーダー吳昱陞からもこのビートの堅牢さには合点がいく。バンドの中心である簡小豪が綴る難解で抽象的な歌詞は本作のミステリアスかつダークな雰囲気を盛り上げ、シンセサイザーの李宛諭との男女ツイン・ヴォーカルから、メイン・ヴォーカルとラップに分かれ絶妙な掛け合いを見せる中盤以降の展開も心憎い。(Yo Kurokawa)
mei ehara – 「ゲームオーバー」
フェイ・ウェブスターやCornelius、HALFBYなどへの客演でヴォーカリストとしての存在感が際立っていたmei ehara、2年半ぶりの新曲。私は先日名古屋で行われたカクバリズムの20周年記念ライブで一足先に聴いたが、前作『Ampersands』(2020年)と同じ気鋭のバンドメンバーが鳴らす、地中深くで揺れるネオ・ソウルのリズムと、アシッド・フォーク的とも歌謡曲的とも言える憂いのある歌声が絡みついて立ち上った有機的な世界に、サウンド・プロデューサーとしての唯一無二の才を感じた。さらに音源では高橋一のトランペットが加わり、おかしみにも似た不穏とでも言うべき、アンビバレントな余韻が広がっている。(ドリーミー刑事)
Overmono – 「Walk Thru Water feat. St. Panther」
ジャケットの景観そのもののようにおおらかで雄大。LA拠点のシンガー・ソングライター、St. Pantherの「Greatness」をOvermonoがサンプリングした一曲。なめらかに揺れる水面のようなシンセパッドは、詞に込められた望む生活への思いをおだやかな祈りに昇華させた。フィルターがかかった音は水中を連想させ、不鮮明さはなつかしさを呼び起こす。『Cash Romantic』は古いテープをきっかけに制作されダンスフロアの外にも開かれていたが、そこに続く楽曲と捉えていいだろう。鼓動のようなキックや反射する光のような電子音が加わるとその風景はより鮮明に。深呼吸をすればひんやりとして澄んでいる空気で満たされそうだ。(佐藤遥)
Steam Down – 「Overcome」
スティーム・ダウンは、ロンドン南東部のデトフォードにあるバー《Buster Mantis》で毎週水曜日に行われていたイヴェントと同名のミュージック・コレクティヴで、地域のコミュニティとミュージシャンを繋ぐ目的で発足した。筆者はコロナ前に《Buster Mantis》で彼らのパフォーマンスを目の当たりにしたが、フリー・ジャズの放埓さとパンクのエネルギーが合体したようなアフロ・ファンク・ジャズに対して、ただただ圧倒されるばかりだった。この1年ぶりの新曲もグライムのビートを取り入れながらも、彼らのルーツであるアフリカを通して掲げるアフロ・フューチャリズムを前面に押し出したパワフルな演奏が渦巻いている。(油納将志)
台風クラブ – 「野良よ!」
前作「下宿屋ゆうれい」からはや2年。今年の残暑はまだ終わっていないぜ!と言わんばかりに飛び込んできた日本語ロックの西日。今回は90年代メロコアを、メタルやバブルガム・ポップまでも貪欲に咀嚼したところまで完全再現したパンクチューン。モッシュピットで転がるスケーター・ファッションの幽霊たちの姿が目に浮かんでくるかのよう。そしてアクセル全開、バンド史上最速のスピードで石塚淳の予測不能なコードワークとメロディという急カーブに突っ込み、駆け抜けていくスリルはもはや神業の域。その一方、内に秘めた思いを成就できず、ただ人生に追い抜かれていく様を描いた歌詞とのコントラストはより容赦なく、私たちの影を伸ばす。(ドリーミー刑事)
【BEST TRACKS OF THE MONTH】
過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)
Text By Yo KurokawaHaruka SatoKenji KomaiShoya TakahashiRiko MaedaNana YoshizawaIkkei KazamaDreamy DekaShino OkamuraMasashi YunoKei SugiyamaDaiki TakakuYasuyuki Ono