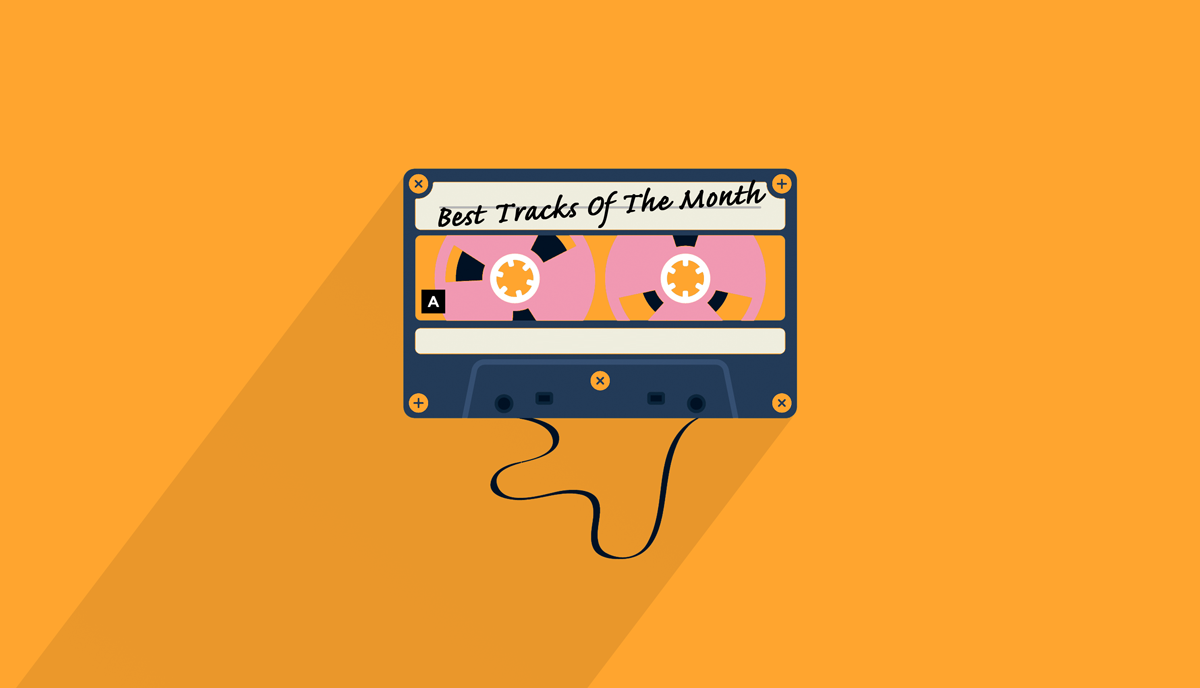BEST 14 TRACKS OF THE MONTH – March, 2022
Editor’s Choices
まずはTURN編集部が合議でピックアップした楽曲をお届け!
Good Looks – 「Bummer Year」
テキサス州オースティンを拠点とするバンド、グッド・ルックスが4月にリリースするニュー・アルバムからのリード・トラック。空間をふんだんに利用した奥行きのあるエレクトリック・ギターの音色と落ち着いたメロディー・ライン、ボーカルであるタイラー・ジョーダンの湿り気のある歌声を耳にすれば、このバンドの音楽に対してウォー・オン・ドラッグスが引き合いに出されるのも納得。本曲は昨年にビッグ・シーフのギタリストであるバック・ミークや、ケイティー・カービーといったフォーク/カントリー・ミュージシャンによる良作を送り出し話題となった《Keeled Scales》からのリリースとなっている。(尾野泰幸)
NEI – 「DOORS」
唯一無二のスタイルで注目を集める名古屋市南区出身の気鋭ラッパー、NEIによる約1年4ヶ月振りの新曲。水の流れる音だろうか、それとも焚き火の音だろうか? 後ろで鳴るアンビエンスに、孤独を浮かび上がらせるように広々と響くシンセ。同郷のプロデューサー、Voxxの手掛けるビートに重なる、僅かにメランコリーを纏ったNEIの声。身の丈以上のことを求めすぎず、でも近くにある大切なものと日々無数に生まれてくる希望は見失わずに。言葉は決して多くないが、ついつい浮き足立ってしまう春に、彼のリリックはゆっくりと沁みてくる。ミックスは『NEYOND』(2020年)も手掛けたThe Anticipation Illicit Tsuboi、マスタリングはColin Leonard。(高久大輝)
君島大空 – 「Lalala Means I Love You」
フィラデルフィア・ソウルのグループ、ザ・デルフォニックスが1968年に発表した曲のカヴァー。これまでプリンス、スウィング・アウト・シアター、アルトン・エリスなど多くの音楽家によってカヴァーされ、オリジナルのグルーヴとは異なる角度でリズムやビートをアレンジした曲が多かったように思う。ただ、君島のバージョンにベースは不在で、中盤以降にドラムのミニマルな演奏があるのみ。その代わりか、ギターのバッキングにグルーヴを作り出すこともほとんど一手に引き受けさせながら、奥行きのあるサウンドを構築している。低音弦を中心に鳴らすトレモロがかかったエレキ・ギターのゆらゆらと「揺れる」音は、J・ディラがアンビエントと出会ったかのような予想しなかった響きを運んできた。(加藤孔紀)
Sam Gendel & Antonia Cytrynowicz – 「Wondering Waiting」
6月にサム・ウィルクスと来日するサム・ゲンデル。相変わらず多作で神出鬼没だが、中でもこれは過去一ポップな作品と言えるだろう。サムのガールフレンドで、サムのヴィジュアルを数多く手がけるマルセラ・チトリノヴィッチの年の離れた妹、アントニアとの完全即興で作られた曲。サムの自宅で、作る予定もないまま、サムの演奏に合わせ、当時まだ11歳だったアントニアがその場でメロディをつけて歌ったのだそう。あまりに素晴らしかったので、すぐさまボイスメモで簡単に録音、その後、一つのアルバムとするフレームの中で独創的なオーケストレーションを与えて作り上げたとのことで、そのあたりはどんな環境でも自分の色彩に引き込むサムの手腕のなせる技だろう。これを含めた10曲入りのアルバム『Live A Little』(5/13発売)が激烈に楽しみ。(岡村詩野)
Yung Bae – 「L.O.V.E. (feat. EARTHGANG, Jon Batiste & Sherwyn)」
もとはFuture funkのプロデューサーとして登場したヤング・ベーによる、ジャスティス「D.A.N.C.E.」にオマージュを捧げたなんともご機嫌なシンセ・ファンク。もっとも、「D.A.N.C.E.」がそもそもジャクソン5へのオマージュであるように、参照に参照を重ねることで歴史観が薄まっていくメカニズムはfuture funkに類似している。ゲストには、昨年古典ジャズからソウルまでを内包した傑作『WE ARE』を上梓したジョン・バティステや、EARTHGANGらが参加。グルーヴやフロウに奥行きを与えているが、それでもどこか不思議な冷たさや軽さを感じる、プラスティックな魅力のサマーソング。(髙橋翔哉)
Writer’s Choices
続いてTURNライター陣がそれぞれの専門分野から聴き逃し厳禁の楽曲をピックアップ!
Bright Eyes「St. Ides Heaven (Companion Version)」
スタジオ・アルバム全9作品のリイシューに伴い、収録曲の再録と当時影響を受けた楽曲のカバーを収録した『A Companion』シリーズを5月にリリースするブライト・アイズ。そう聞くとノスタルジーのようにも感じられるが、決してそれだけではないことがエリオット・スミスのカバーとなる本楽曲の演奏からありありと感じられる。荒々しいバンドサウンドや吐き捨てるような歌唱はインディーの焦燥感に満ち溢れていて、エリオットの描いた生々しい情景が克明に蘇るかのよう。アコースティック主体の原曲とまるでスタイルは違うが、むしろ「これしかない」という気持ちにさせてくれるから不思議なものだ。彼の遺したものはここにはっきりと息づいている。(阿部仁知)
Jordan Rakei – 「Defection」
昨年の傑作『What We Call Life』でシンセとストリングスの幽玄なる海にダイブしたジョーダン・ラカイが、今作『Bruises』では丹念に削ぎ落とされた肉体を伴って浮上してきた。無論、その肉体には傷痕(=Bruises)が残っており、その傷跡を愛でるプロセスとして歌がそこにある。冒頭曲「Defection」での、彼のルーツであるレゲエのマナーに則った跳ねるベースとパーカッション、そして驚くほど素直なピアノの旋律。どれもが、ラカイの憂いを湛えた伸びやかな歌声の器として調和している。影響源の多さが言及されがちな彼だが、今作は研磨された肉体による身体が醸す、スリリングでしなやかな体験が楽しめる。(風間一慶)
Mavis Staples & Levon Helm「You Got To Move」
リヴォン・ヘルム生前の2011年、2人にとっての最後のセッショ ンから先行公開されたナンバーは、ゴスペルのトラディショナルソング”You got to move”(アルバムは5月リリース)。メイヴィスとリヴォンといえば、やはり映画ラストワルツでの共演だが、その後も、そしてリヴォン亡き後も、2人の友情が大切に育まれてきた事が伝わる素晴らしい共演だ。スライドギターを使ったブルージーなスタイルではなく、アップテンポなリズムでリフレインする”You got to move”という言葉からは、受け入れるべき「死」を連想したものの、生と死、肉体と魂の際を、軽やかに跨いでいきたいと願う彼女の今を生きる声が聴こえる。 (キドウシンペイ)沼澤成毅「結晶」
かつてはヒップホップ・バンドTha Bullsxxtのキーボーディスト、現在はODOLAの一員である沼澤成毅のソロ名義でのデビュー作。さとうもか、思い出野郎Aチームなど、数えきれないほどのアーティストを支えてきた彼にふさわしく、厚海義朗(GUIRO)、鳥居真道(トリプルファイヤー)、mei eharaという豪華メンバーが参加。ブラジル、ジャズ、ジャパニーズポップス等の良質な遺産と最新の音像を折衷したサウンドは佐藤博の名盤『Awakning』を想起させ、流麗かつ大胆な鍵盤の演奏にはセッションミュージシャンとしてシティポップ黎明期を支えていた頃の坂本龍一の面影も。彼の描く風景をもっと見てみたくなる。(ドリーミー刑事)ROBOT SWING, LEO37ほか – 「TM5」
台湾のヒップホップ・アーティストLEO37が2016年から主催するライヴ・パーティー《That’s MY SHHH》。ブラック・ミュージック、DJ、ダンス、アートがクロスオーバーするこのイベントは才能溢れる台北のアーティストが集まる強力な磁場として機能している。コロナ禍以降オンラインで活動を続け、今年遂にライヴ会場にカムバックするのにあわせてリリースされたテーマ・ソングが「TM5」だ。台湾インディー新進気鋭の面子がリレー形式で次々と現れるオールスター感に胸が躍る。謝明諺の気の利いたサックス、原住民パイワン語シンガーとして有名なAbao阿爆のヴォーカル・ワークなどヒップホップ・ファンならずとも見どころの多い1曲。(Yo Kurokawa)
Sen Morimoto – 「Deep Down ft. AAAMYYY(tamanaramen Remix)」
セカンド・アルバム『Sen Morimoto』収録曲のリミックス・ヴァージョンが毎月1曲ずつ公開されているが、3月はtamanaramenが再構築した「Deep Down ft. AAAMYYY」がリリース。原曲のスウィートなムードと清涼感を180度反転させた仕上がりで、まるでパラレルワールドへ来てしまったような感覚に陥る。本人が「3ジャンルを浮遊しているよう」とコメントする通り、ダーク・ウェイヴを基調としながらも実に多様なビートが散りばめられており、2分32秒という尺が信じられないほど濃密。ヴォーカルをシンセ・パッドのように活用した、tamanaramenならではのアトモスフェリックな音遣いも光る。(前田理子)
Σtella – 「Charmed」
ステラはアテネ出身の女性シンガー/サウンド・プロデューサーで、2020年発表の3rdアルバム『The Break』はカナダのArbutus Recordsからのリリースだったが、サブ・ポップに移籍。このシングルは今年後半に予定されているアルバムのリード・トラックであり、リズ・アーメッドが所属するヒップホップ・クルー、スウェット・ショップ・ボーイズの一員でもあるレディンホによってプロデュースされた。一聴して思い浮かぶのがクルアンビン。彼らほどサイケデリックな雰囲気はないものの、ステラの持ち味であるメランコリックな音作りとヴィンテージ感のあるアプローチが絶妙に溶け合っていて、来るべきアルバムへの期待も高められる。(油納将志)
Tone – 「In and Out」
ミカ・レヴィ、コビー・セイが在籍するサウス・ロンドンのコレクティブ《CURL》の一員であり、エレクトロニック・ユニットFaraiでの活動でも知られるプロデューサーがソロ・アルバムをリリース。レゲエ、ダブ、ポスト・パンクそしてシューゲイザーの要素を、8トラックのテープマシーン、タスカム38によりそっけないほどシンプルにプロダクションに閉じ込めた。なかでもメンタルヘルスの問題と闘う友人のために書かれたこの曲は、アフロ・カリブとウェールズの血を引き、娘の誕生を期に自らを見つめ直したかったという彼の素朴なヴォーカル・スタイルにより、木漏れ日のような温もりとメランコリーを色濃く映す。(駒井憲嗣)
Olivia Escuyos – 「Hit My Line」
高校時代にビヨンセやジェネイ・アイコをカヴァーしたYouTube動画で名を上げ、コロナ以前はアトランタやLAを拠点に活動していた、メルボルン出身のシンガーソングライター=Olivia EscuyosのEP『Fantasy Girl』から。作品全体として、本人もファンだと公言する《OVO Sound》っぽいクールなサウンドに官能的なリリックの組合せが印象的だが、その方向性を示すかのようなオープナーがこの「Hit My Line」。どことなくGhost Town DJ’s「My Boo」というかシアラ「Body Party」っぽいと思ったら、後者はカヴァー済み。よろしければそちらもどうぞ。(奧田翔)
【BEST TRACKS OF THE MONTH】
過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)
Text By Sho OkudaHitoshi AbeYo KurokawaKenji KomaiShoya TakahashiRiko MaedaIkkei KazamaDreamy DekaShino OkamuraMasashi YunoDaiki TakakuKoki KatoYasuyuki OnoSinpei Kido