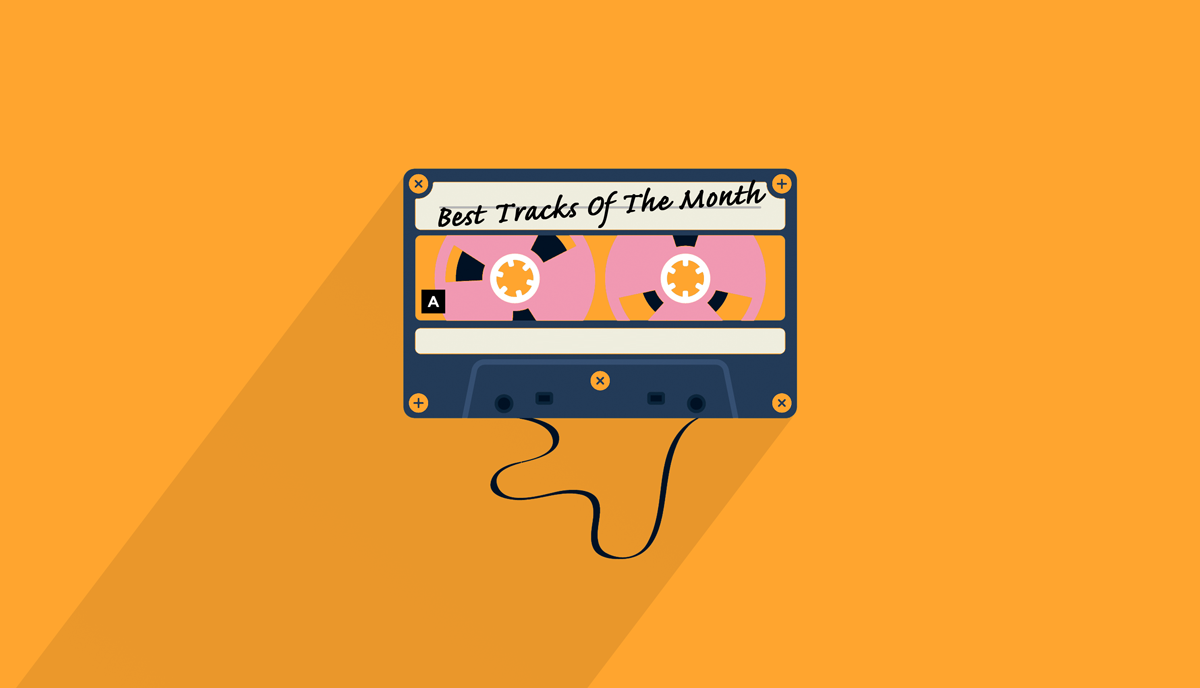BEST 13 TRACKS OF THE MONTH – April, 2022
Editor’s Choices
まずはTURN編集部が合議でピックアップした楽曲をお届け!
Katie Bejsiuk – 「Onion Grass」
《Double Double Whammy》から作品をリリースしていたインディー・ポップ・プロジェクト、フリー・ケイク・フォー・クリーチャーを主導していたケイティー・ベネットが同プロジェクト停止後、その名をウクライナ移民一世である両親の姓、“ベジユック”と変え6月に発表するソロ・アルバムからのリード・トラック。ボーカルにサウンド・バランスを傾けて強調したプロダクションが特徴的だが、ギターを主体としたアンビエント感のあるバック・トラックと混ざりあうことで楽曲全体としては落ち着いた印象に。ケイティーはそのしなやかな歌声で、無垢で想像力豊かな幼年期からジェンダー構造などに拘束された青年期への移行する中で生じる友情の変化について歌いあげていく。(尾野泰幸)
Lunv Loyal – 「Outside Ft. ゆるふわギャング」
秋田出身のラッパー、Lunv Loyalのセカンド・アルバム『SHIBUKI』から。これまでも客演等で絡みのあったゆるふわギャングを招いた1曲は、BERABOWとViryKnotによるギターリフが駆けるビート、Lunv Loyalのリズミカルで滑らかなフロウ、Ryugo Ishidaの衒いのないライム、NENEのスムースなフックが渾然一体、心地よい陶酔感と爽やかさを生んでいる。また、リリックのテーマはタイトル通り、外、ここではつまり、夜の街だ。コロナ禍以降、たくさんの遊び場が変わってしまったとしても、あるいはどれだけネット上でできることが増えても、人々が交差して始まる物語があり、受け継がれる物語がある。(高久大輝)
Şatellites – 「Olurmu Dersin (feat. Vicki Ashkenazi)」
イスラエルのサイケデリックファンク・バンドによる、トルコ人歌手・Kamuran Akkorの’71年楽曲のカヴァー。伝統的なトルコ音楽にリスペクトを示す彼らは、演奏に弦楽器のサズやパーカッションを取り入れている。しかし、ベースはファンク的だしドラムはバックビートを強調しており、原曲と比べてぐっと粘っこくグルーヴィーなものに。トルコ語詞のサイケデリアどうしの比較で、ロンドンのキット・セバスチャンがどこか箱庭ポップ的なコンパクトさも魅力であったのに比べると、Şatellitesのリヴァーブのかかったサズの音色はずっと壮大で、トルコ語のリリックの響きとトルコ音楽特有の音階に神秘的な魅力を加えている。(髙橋翔哉)
Zenizen – 「Aja」
ZenizenとはNYはブルックリン在住のSSW/プロデューサーのOpal Hoytによるソロ・プロジェクト(日本の“Zen(禅)”と居留民/帰化外国人を意味する“Denizen”を独自に組み合わせた造語)。エレクトロ、ソウル、アフロなどの交差させたユニークな曲で、ローズ、シンセ、サンプラーなどを用いつつヴェイパーウェイヴ的な感覚でライトい仕上げられてある。けれど、この曲を含む7/27発売のアルバムにはアラスカでの養子縁組からDC、ジャマイカ、バーモント、NYを転々とした幼少期の辛い体験を反映。エリカ・バドゥ、ディアンジェロ、ハイエイタス・カイヨーテ周辺のサポート・ミュージシャンも参加しているそうだ。(岡村詩野)
Writer’s Choices
続いてTURNライター陣がそれぞれの専門分野から聴き逃し厳禁の楽曲をピックアップ!
Been Stellar – 「Kids 1995」
Lime Garden、Folly Groupなど要注目アクトを輩出するUKの《SO YOUNG RECORDS》が新たに契約したNY出身のバンド。正確には2021年11月に続く再リリースとなるこの曲で彼らは、ラリー・クラーク監督/ハーモニー・コリン脚本の映画『KIDS/キッズ』を引用しながら若さの終わりを描く。伝統芸能のような90’sリバイバルには興味がないけれど、全く新しい地平からかき鳴らされる彼らの野性味たっぷりのバンドサウンドと漂うメランコリーには、抗しがたい魅力そしてスタジアム級のポテンシャルを感じる。プロデュース&録音を担当したAron Kobayashi Ritch(LAのバンドMommaのメンバー) の名前も覚えておいてほしい。(駒井憲嗣)
BIA – 「LONDON ft. J. Cole」
ニッキー・ミナージュもリミックスに参加した「WHOLE LOTTA MONEY」のヒットなどで知られる、マサチューセッツ州メドフォード出身のラッパー=BIAがJ. コールと共演。この曲の制作秘話はコールが自らのInstagramの投稿で明かしており、初めて聴いたその瞬間からいたく気に入った様子。「ロンドン」というタイトルに因んでか、BIAのフックでは“shop”や“mall”といった単語がブリティッシュ・アクセントで発音されている。コールのヴァースに出てくる“trainers”も「スニーカー」を意味するイギリス英語だ。力の抜けたBIAのフレックスが曇り空に似つかわしいかっこよさ。(奧田翔)
Lynks – 「Perfect Human Specimen」
奇抜な覆面とそのシュールな佇まいは、一度みれば忘れないだろう。LynksことElliot Brettの覆面ソロ・プロジェクトの最新曲「Perfect Human Specimen」は、彼のそうしたスタイルを用いた風刺的な一曲ではないだろうか。シンセを用いた悪ふざけのようでありながら整理された良質のダンスミュージックである本作は、ニュー・レイヴの中でも特にレイト・オブ・ザ・ピアを思わせる。そうした楽曲で彼は”完璧な人間”をテーマにすることで、その歪さを浮き彫りにする。そして彼の覆面に対して抱く違和感は、顔というメディアに対し社会がどんな役割を抱いているのかを我々に意識させる。(杉山慧)
MoonD’shake – 「Purple bridge」
MoonD’shakeはギター黃國晏、ボーカル許家菱を中心に問題總部のギター黃子恩が加わった2019年結成のインディーポップバンド。台湾音楽ポータルサイト吹音樂やKKBOX潮流新聲でも2022年最注目アーティストに挙がるアップカミングなバンドだ。初EPを2020年にリリースした次が2021年末のシングル「Sunrise」とマイペースな活動だが、今年に入り活発にデモを公開している。特に本作「Purple bridge」はボーカル家菱のコケティッシュな魅力はそのままにこれまでのダンサブルなビートに代わってよりメロウでドリーミーなエレクトロサウンドが採られ、バンドの進化を感じさせる1曲となっている。(Yo Kurokawa)
Real Lies – 「DiCaprio」
2014年発表の「North Circular」で注目されるも、その後はデビュー・アルバム『Real Life』を挟んで散発的なリリースが続いていたロンドンのエレクトロニック・デュオが、ようやく第2作を完成。本トラックはその新作『Lad Ash』からの最新カットで、クロージング・ナンバーでもある。バレアリック~レイヴ時代のダンス・ビートを参照したポスト・ダブステップとも言うべき彼らのサウンドはロンドンの深夜~明け方の光景と常にシンクロしているようで、このトラックはまさに夜明けを迎える瞬間を描いたような厳かな雰囲気をたたえている。アルバムに起承転結があると捉えるならば、刹那的な一夜の光景を映し出していると言っていい。(油納将志)
ryo hadano – 「too young to die(love)」
浜松在住のSSW/ギタリスト・ryo hadanoが名古屋のインディーレーベルGalaxy trainからリリースした新曲は、いくつもの神秘的な矛盾を抱えている。ベッドルームの隅で囁くように歌われる歌は、極めて内省的であると同時に世界が儚く崩れ落ちる瞬間を目撃するようなスケール感があり、スフィアン・スティーブンスを彷彿とさせる消失寸前の美しさを捉えたメロディには井上陽水へのオマージュが唐突に挿入される。そして繊細に織り込まれたギターとサウンド・コラージュによって構成された音像は、音が重なるほどに透明度を増していくようである。身を投げ出しなくなるほどの美しさと底知れない不敵さを体感してほしい。(ドリーミー刑事)
Sault – 「Time Is Precious」
先月、突如発表されたソーの『Air』は、すごいアルバムだ。彼ら(この覆面ユニットの首謀者はリトル・シムズらを手掛けるインフローだと言われている)の魅力だったネオソウル譲りのビートは皆無で、代わりフルオーケストラとクワイアが全編に響き渡る。既にフィリップ・グラスのミニマリズムやコルトレーン夫妻のスピリチュアル・ジャズと比較するレビューも散見される。その中でもこの曲は従来の彼ららしいソウルフルなヴォーカルがフィーチャーされ、チャーミングでとっつき易い(歌はクレオ・ソル?)。〈人生は常に喜びを与え得る/時間を賢く使って、それらを逃さないで〉。アルバム全体にも通じる直感的で力強いメッセージだ。(佐藤優太)
Supershy – 「Happy Music」
Supershyはトム・ミッシュのオルター・エゴで、ダンス・ミュージックにフォーカスした新プロジェクト。新しいサウンドを探求する目的もあるとのこと。いつの間にかソウルフルなヴォーカルをなぞるように「Singin’ Happy Music」と口ずさみ、心地よいグルーヴに身体が揺れている。街に繰り出した緑のスマイリーに目を惹かれ一緒に踊っている人々は、画面の前の私たちだ。ディスコからハウスへ移り行くダンス・ミュージックの歴史、現行のUKソウルや、じわじわ再びの盛り上がりを見せるフレンチ・ハウスに考えを巡らせるけれど、彼は制作の楽しさを重視したそうだし、ひとまず、エネルギー溢れるこの曲に身を任せよう。(佐藤遥)
Triathalon – 「Spin」
Triathalonのサウンドは非常に記名性が高く、それゆえにどんなジャンルも飲み込んでしまう。「Spin」は、そんなTriathalonが正面からアブストラクトな演奏に舵を切った「意欲作」だ。しかし、「意欲作」と呼ぶにはあまりに心地良すぎる。元から瑞々しいサイケデリックな音が得意だった彼らだが、Navy BlueやInjury Reserveのミックスなどを手がけるZerohのマスタリングによって、サウンド全体の酩酊度が底上げされている。Dean Bluntにも通じる、暗闇で鳴らされる漆黒のアシッドフォーク。ボトムを強調したアレンジも含め、現代のシーンへの目配せも怠っていないところも彼ららしい。(風間一慶)
【BEST TRACKS OF THE MONTH】
過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)
Text By Sho OkudaYo KurokawaHaruka SatoKenji KomaiShoya TakahashiYuta SatoIkkei KazamaDreamy DekaShino OkamuraMasashi YunoKei SugiyamaDaiki TakakuYasuyuki Ono