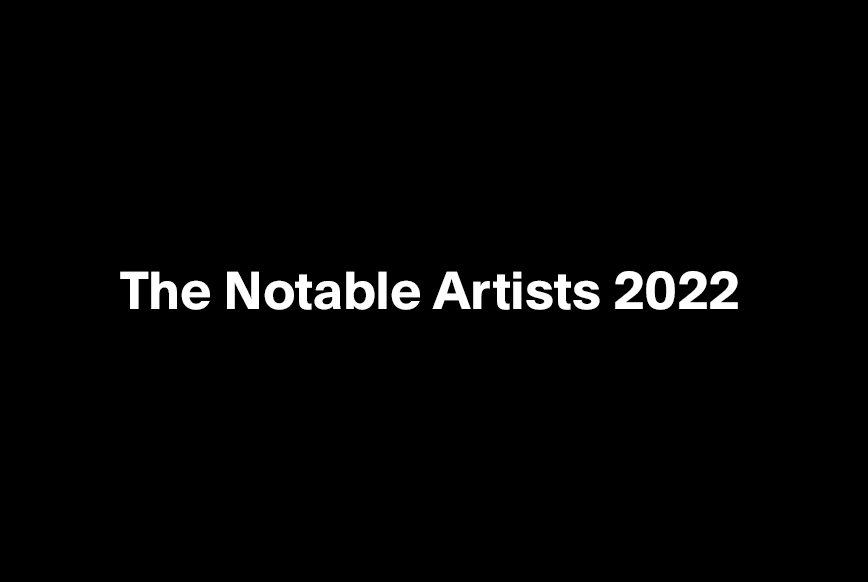《The Notable Artist of 2022》
#5
Honeyglaze
サウス・ロンドンから現れたスリーピースが奏でる曖昧で不完全な美しさ
聴いた瞬間すぐに口ずさみ、その後も一日メロディが頭を離れないほどポップなんだけれど、鎮静剤のようなアンビエンスを感じる。グルーヴをコントロールしながら、どこか熱狂からは離れた醒めた感覚を覚える。新人登竜門としての地位を確立したレーベル《Speedy Wunderground》と契約を果たし、4月29日にファースト・アルバムをリリースするサウス・ロンドンのスリーピース、Honeyglazeの音は、バンドの生々しい響きをもって夢想的な世界と音楽がゆさぶる本能的な心の動きを描く。
きっかけは、ボーカル/ギターのAnouska Sokolowが、ゴート・ガールら実験精神を持つアクトを多数輩出するブリクストンのヴェニュー《The Windmill》でのソロライブの3日前にバンドで演奏したいと思い立ち、ベースのTim CurtisとドラムのYuri Shibuichiに声をかけたことだった。その後3人は、2021年の《Green Man Festival》出演などでまたたく間に注目を集めることになる。すでにウェット・レッグやソーリー(「Shadows」のMVはアーシャ・ローレンスが監督している)といった同郷のバンドとの交流を築き、サウス・ロンドンのロック/ジャズ・シーンのコミュニティから生まれたことを公言しているが、Honeyglazeにはいわゆるサウス・ロンドンから飛び出したバンド、という形容ではどうにも捉えきれない、不思議な魅力がある。
チャールズ・ブコウスキーの詩から構想を得た「Burglar」、「何一つ自然に身につくものはない/それでも私は果てしなく努力する/だって私は誰かじゃないんだから」と心情を吐露する「Creative Jelousy」、明るさと暗さの間を漂う「Shadows」。これまで発表された3曲どれもブロードキャストを思わせるヒプノティックで甘いメロディのセンスが発揮されており、自身も60年代のソウルと90年代のドリームポップから触発されていることを明らかにしてはいるものの、巧妙にひとつにカテゴライズされることを避けているようにも感じられる。そうしたスタンスを象徴するものとして、彼らがSNSやステージ上でクリエイティブな発信のひとつとして用いているHaiku(いわゆる5/7/5の俳句ではなく英語の三行詩)がある。ネット上の彼らのライヴ・パフォーマンスを観ていると、それが決して奇をてらった演出ではなく、Haikuの構造を利用したある種の居心地の悪さや期待感の提供となっていて、いい意味での掴みどころのなさを強調しているのだ。
Honeyglazeはコーティングされたポップではなく、もっとラフで、偶然性を活かし、より流動的な存在として、リスナーを心地よくはぐらかす。〈ダン・キャリー印〉として知られる方法論―アルバムの楽曲をふたつに分け、ヴォーカルを除いたパートをバンドが完璧に演奏できるまでリハーサルを行い、アナログテープに録音したうえでデジタルに変換し制作する―は、『So Young Magazine』のインタビューでバンドが語っている「感情は精神的なものと思われがちだが、音楽を通して肉体的なものになる」という態度と合致したのだろう。日々の不安をしなやかなグルーヴ、芳醇なディレイ、ノスタルジックでウォームなキーボードの響きに変え表現しようとしている。
なお、ドラムのYuri Shibuichiは2021年10月に公開された熊坂 出監督の映画『プリテンダーズ』に音楽担当としてロンドンから参加し、夢と意識の間を漂うようなサウンドスケープを持つ楽曲を提供している。その映画の物語の主人公―ファンタジーを通して現実を変え、自己を取り戻したいと願うふたりの17歳の少女―になぞらえるなら、Honeyglazeもまた、不遜なほど枠にとらわれない探究心を持ち、内なる闇を見つめたまま、人懐っこさと不安さがないまぜになった、不完全な美しさを奏でる。(駒井憲嗣)
Text By Kenji KomaiThe Notable Artist of 2022
【The Notable Artist of 2022】
画像をクリックすると一覧ページに飛べます