THE 30 BEST ALBUMS OF 2025
2025年ベスト・アルバム
今年の上半期が過ぎた時点で、ポップ・ミュージックの世界における2025年は、悲観的にいえば主役不在の年になるだろうと予想されていた。昨年にさかのぼれば、ドレイクとのビーフを経てメジャーのラップ・シーン全体を減衰させたケンドリック・ラマー、2010年代では分裂していたいくつかの文脈を『BRAT』というパッケージに統合し社会現象へと押し上げたチャーリーxcx、そしてストリーミング・サーヴィス以降のライヴ興行の可能性を拡張したかにみえたテイラー・スウィフトの「The Eras Tour」は2024年末まで続いていた。あらゆる点で2024年は、真の意味で“2010年代のフィナーレ”を迎えた年として振り返られる。つまり2024年は、翌年に持ち越されるべきムーヴメントを欠いた稀有な年であったともいえよう。
そして2025年。バッド・バニーが年始めにプエルトリカン・ミュージックの要素を前面に出した最新作『DeBÍ TiRAR MáS FOToS』をリリースし、その後のライヴの多くをプエルトリコ国内に絞って行うようになったこと。そして2025年下半期になると、ロザリアもまた、自らのルーツのひとつであるクラシック音楽に大きく接近した最新作『LUX』を発表したこと。さらにチャーリーxcxが映画『嵐が丘』の音楽として、クラシック音楽〜ダークウェーヴ的なサウンドのシングルをリリースしていること。こうした動きに象徴されるように、ポップ音楽シーンをめぐる空気が、いま確かに変化している。
ここまでメガ・ポップ・スターに絞って話を進めてしまったが、ここで私たち《TURN》が主にカメラで捉えようとし続けている、よりインディー/アンダーグラウンドなシーンに視点を移そう。ここまで述べてきたようにメインストリームにおける、音楽的な意味においても“イケイケな”演者の不在は、それ以外の個々のローカルなシーンにとっての成長機会を意味する。かつて2020年にパンデミックを契機としてポップ・シーンの北米中心時代が終わりを迎え、プエルトリコや西アフリカやアジアから新たなスターが台頭してきたように、あるいはサウス・ロンドンのインディー・ロック・シーンが盛り上がりを見せたように。次なる時代の到来が可視化されゆく兆しでもある。
たとえばそれは、A.G.クックやダニー・L・ハールをプロデューサーに迎えどこかY2Kの質感を湛えたパリのオーケールーや、サウス・ロンドンのポストパンク系インディー・ロックの影響を受けながら、アレンジメントの力で自身のカラーを手に入れたブルックリンのギースが、どちらも存在感を放っていたことに指摘できるだろうか。2026年以降のシーンを予測することは本記事の趣旨ではないとして、結論めいた言及は回避させてもらいます。少なくとも2025年が真の意味で“2020年代の始まり”であることは、希望をもって述べておこう。それは、2010年代型のリスニングの形を定義したApple Musicのローンチが2015年であることや、パンデミックによって強制的にモード・シフトを迫られた2020年代初頭のシーンが、いま振り返ると2010年代後半のムーヴメントの残響に依拠していたことにも似ている。
しかし今年は、ここまで述べてきたような状況を指差して、聴くべき音楽がわからなかった、面白い音楽がなかったと嘆く声を何度か聞いた。うんざりすることにアディクトするなかれ。次なる時代の胎動を渇望し耳を澄ませ続ければいい。私たちのリスニングのあとに、2020年代は続いていくのだから。前置きが長くなりましたが、今年も2025年のベスト・アルバムを30枚セレクトしました。ここで選ばれた作品やそれに対するテキストたちが、未来のリスニングのための何かしらのヒントや出会いのきっかけになりますように。(編集部)

30
kurayamisaka
kurayamisaka yori ai wo komete
tomoran / bandwagon / chikamatsu
kurayamisakaの音楽は寂しい。彼らの主題は常に何かの終わりである。喪失、別離、夏──夏へのオブセッションは、それが常に終わるがゆえに生じている。バンドの中心人物である清水正太郎は制作中に両親と死別したことを明かしたが、ツアーの最終公演のMCでは“自分たちが死んだあとに本作が誰かに見つけてもらえればそれでいい”といったことを語った。そこにあるのは未来を望み願うことより、わずかに諦念を滲ませた、終わりを見据えた透徹した感覚だ。オルタナティヴ・ロック史に連なろうという意志や憧憬や尊敬が込められたサウンドにも、“歴史の終わり”を前提にした寂しさがある。「寂しいね」。そう歌う内藤さちの声は、その感情すら客観視しているかのようである。内藤が「はあっ」と息を吸いこむアイコニックなブレスがマイクを通して伝えば、5人は寂寞感を轟音として鳴らす。彼らがカヴァーした和田アキ子の「さあ冒険だ」は実に前向きな曲にもかかわらず、奇妙な寂寥感がある。「ワクワクする/この気持ち/なんだろう/さあ冒険だ」。未来に踏みだす詞の裏に幼年期の終わりが潜んでいる。その感覚こそkurayamisakaのロックを象徴するものにほかならない。kurayamisakaはメッセージをアルバムという瓶に詰め、海に投げこんだ。物語が終わったあと、いつか誰かがそれを受けとってくれればそれでいい。(天野龍太郎)

29
Ethel Cain
Perverts
Amigo Records
これはまるで、非在の記憶と祈りのドキュメントじゃないか。深夜の無人駅に響く静かな心音。2022年のアルバム三部作の第1弾『Preacher’s Daughter』の裏側でこぼれ落ちた“声にならなかった声”のアーカイヴだ。当初は逸脱者(perverts)を主題としたコンセプト作として構想されたが、いまや“記憶の断面だけが残響する”非完結の構えそのものが核をなしている。これは、非在の誰かへ向けた呼びかけのような語り。カタルシスを内包するギターのレイヤー、滲み出るモノローグ、歪んだリバーヴに沈むスポークン・ヴォイス。それらは楽曲というより、変質し続ける記憶の濃度を焼き付けるかのようだ。ここでは主張や闘争ではなく、不可逆な何かの前に輪郭を失いかけた、名もなき“わたし”が立ち尽くす姿勢そのものが祈りとして響いている。ポストクラシカル的なギターは構造を崩し、再生し、滲ませる──“終末的ドリーム・ポップ”としての〈非在の美学〉の最新版と言える。歌声は常に“遠く”を見ている。喪失や暴力、倒錯や償いのイメージは、ステンドグラス越しの光のように淡く屈折する。本作の“触れられなさ”は、筆者が共同主宰する音楽レーベル《Siren for Charlotte》の「遠泳音楽」(Angelic Post-Shoegaze)における距離の倫理とも共鳴し、声と音を“非在の記憶”として漂わせる。祈りとしてのポップ、死者に寄り添うドリーム・ポップ、自己崩壊の果てに差し出される他者への眼差し。本作は、そのすべてを音楽と文学の境界で、儀式のように反復する。“声を失った者たち”のための、新たな始まりとして。(門脇綱生)

28
Alex G
Headlights
RCA Records
「愛のためにやることもある/金のためにやることもある」(「Beam Me Up」)。《RCA Records》へのメジャー移籍や劇伴など、それなりに上手くやっているはずだが、前作『God Save the Animals』(2022年)以降、授かった子供をジープの後部座席に乗せてハンドルを握る側へと人生はシフトしたのだろう。ナイーヴさを含みつつ、フォークやロックにやや重心が寄ったソングライティングには落ち着いた印象もある。ギターやピアノを軸としながら時折登場するチープな質感のシンセ。クールになりすぎないヴォーカル。終盤の表題曲「Headlights」で前触れなく差し込むクラクションのような轟きが作品全体にまで届かんばかりに聞こえた瞬間、不思議と気分が晴れた気がするが、ふと我に返ると道路はただ続いている。折り合いをつけつつ、ただ諦めたわけでもなくて。地に足のついた内省との絶妙な距離感は、アレックス・Gの10作目として顕現した。ささやかなマジックはたしかにここに。(寺尾錬)
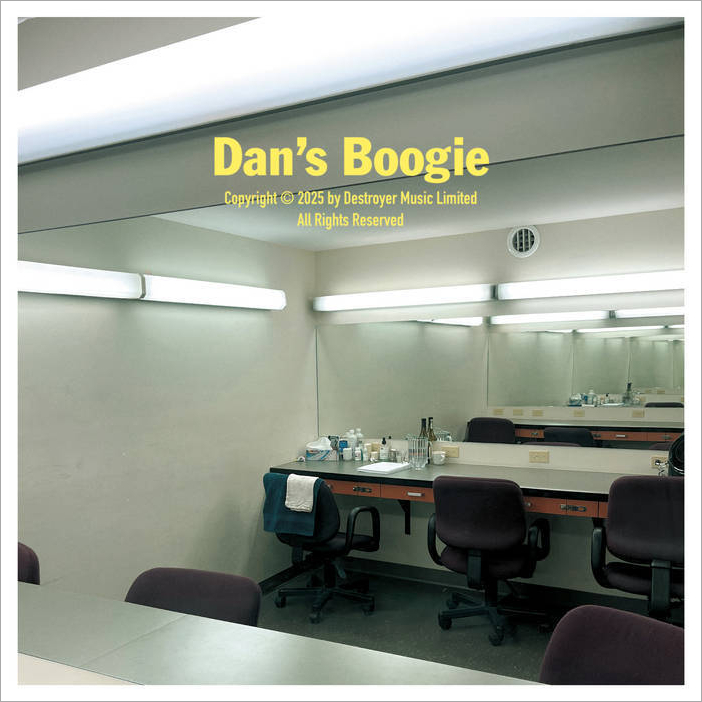
27
Destroyer
Dan’s Boogie
Merge / Big Nothing
ニコ・ケースをはじめ個性豊かな面々が在籍するカナダのロック・バンド、ニュー・ポルノグラファーズのメンバーとしても活動していたシンガー・ソングライター、ダン・ベイハー。彼が率いるバンド、デストロイヤーがバンド結成30年の節目にリリースしたのが本作。プロデュースを担当したのは、バンド・メンバーであり、ダンがニュー・ポルノグラファーズで活動していた頃からの盟友、ジョン・コリンズだ。エレクトロニックなビートで新境地に踏み出した前作から、従来のバンド・サウンドを際立たせた曲に変化。立体的な音作りは独特で、ダイナミックで力強いドラムが響き渡るなか、きらびやかなシンセが降り注ぎ、ギターやピアノが流星のように飛びかう。まるで音のプラネタリウムのようにスペイシーな音響空間を、自由に飛び回るダンの歌声。その甘くロマンティックな歌声は、“吟遊詩人”なんて古めかしい言葉がよく似合う。個人的に嬉しいのは、かつてのバンド・メンバーであり、近年、多方面で活躍するジョゼフ・シャバソンがサックスで参加していること。ダンの歌声に負けない、とろけるようなサックスの音色を聞かせて30周年を祝福しているようでもあり。オルタナティヴだけど普遍的。そんなデストロイヤーの魅力が凝縮されたアルバムだ。(村尾泰郎)

26
bar italia
Some Like It Hot
Matador / Beatink
ロンドンのアート・バンド、《Matador》期のサード・アルバム。かつてバー・イタリアは謎だった。どこの誰がやっているのかもわからない謎のベールとノイズに包まれた実験的なバンド。それが今やこんなに直接的にロック・バンドの魅力を伝えてくるようになるだなんて。90年代のグランジ/オルタナ・バンドのような大仰なリフ、ほんの少しだけ物足りない欠けたものがあるという不完全な青春のメロディ、乾いたギターのメランコリックなフレーズ、そして3人による最高の歌い継ぎ。シンプルなギター・バンドから始まりキャリアを重ね難解で複雑になるというのが一般的なこの世界でバー・イタリアは逆の道を辿るのだ。ブランド化・権威化された場所に留まらないこのアルバムはストレートだからこそズレている。ともすれば陳腐にも思える像の重ね方に美学を感じずにはいられない。バー・イタリアは常に価値観への問いを投げかけるのだ。即座に答えを求められるありかなしかの地平においてその普通の意味を問う。(Casanova.S)

25
Blood Orange
Essex Honey
RCA / Domino
タイトルにあるエセックスはロンドン郊外の街で、ブラッド・オレンジことデヴ・ハインズにとっては故郷である。幼少期の記憶、母との離別、そして哀惜という感情に向き合うパーソナルな内容となっているものの、ロード、キャロライン・ポラチェク、ダニエル・シーザー、ムスタファ、ティルザ、シャーロット・ドス・サントス、そしてベン・ワットなど、多彩なゲストの参加もあって風通しは良く、甘美な瞬間もたびたび訪れる。とりわけプリファブ・スプラウト的な情緒が生じる場面には息を呑んだ。『Steve McQueen』は13歳頃の愛聴盤だったそうだ。「Westerberg」とはザ・リプレイスメンツのポール・ウェスターバーグにほかならず、彼らの「Alex Chilton」のコーラスが引用されている。重層的な本歌取りだ。ほかにもエリオット・スミスの「Everything Means Nothing To Me」の引用も耳に残る。全14曲47分弱。短歌集のような味わい。(鳥居真道)

24
TORSO
Faces
Ozato Records
サックス、フルート、チェロが描く緩やかな放物線が本作の肝だ。ポストパンク的な質感を時折ほのかに感じつつも、どこかリラックスした雰囲気がそこには宿っている。ミニマリスティックなフレーズのリフレインが基盤となる楽曲が多いが、ミニマル・ミュージック的な“システムの音楽”というよりも、ゆっくりと呼吸をするような、生きることそのものが優しく響いているような音楽。楽器から湧き出る音をきめ細やかにキャプチャーした録音を、名手・内田直之がミキシングを手掛けることによって丸く磨き上げられた音は、シンプルな素材に宿る旨味を的確に抽出している。だが、本作には時に厳しさが宿る。スタッカート気味のチェロに遊びのある電子音が絡み、柔らかなボーカルが包み込む「BLINKING」の後に、ドローンを基盤となったサウンドに乗るぶっきらぼうに爪弾かれるチェロが印象的な、どこか殺伐とした「HEAT」が流れたとき、背筋が寒くなる想いがした。その瞬間は「CONTACT」における“もしもし”のリフレインにも現れる。本作には深く、色濃く、そして複雑な感情が刻み込まれている。(八木皓平)
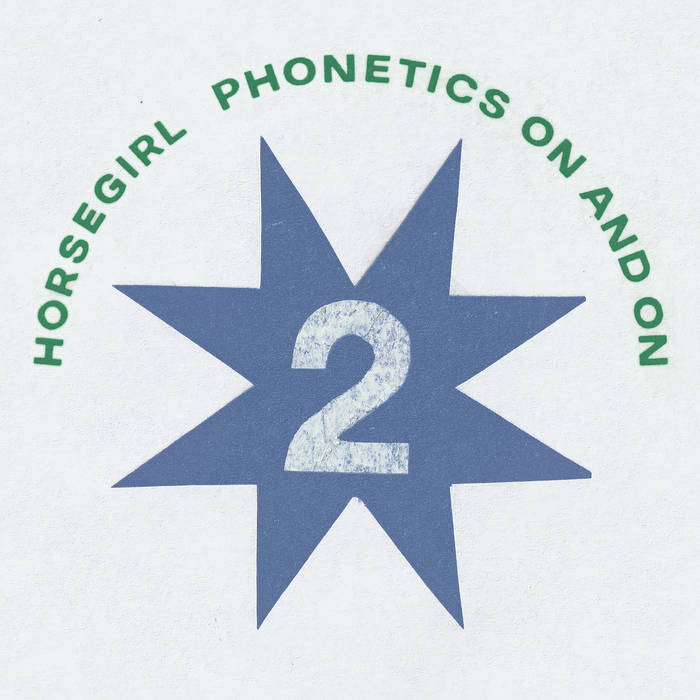
23
Horsegirl
Phonetics On and On
Matador / Beatink
これはネットで見かけて同意した視点なのだが、2025年は、というよりここ5年ほどだろうか、以前よりフェンダー・ジャガーを使うプレイヤーをよく目にする。Mk.geeも、羊文学も、そしてこのホースガールのペネロペも。確かにジャガーの歪んだローやミッドのパワーや粘り、他方、クリーントーンでの繊細な表現力は、言外にある“質感”を描くのに適しているように思うし、それはまさに先に挙げたミュージシャンに共通する空気感でもあるかもしれない。彼女たちもデビュー作こそノイジーではあったが、本作ではスカスカなクリーントーンを骨組みに効果音的なギターや、妙なミュート感のドラム、ドローン音などで“感情の余韻”を生むことに注力している──まるで手作りのZINEを作るような手つきで。定型を逸脱しながら先入観を持たずに楽器に取り組む様は、DNAやアート・リンゼイのノーウェイヴやノイズの精神とも近い。反復とズレの狭間に脈動するグルーヴと、音の響きそのものを探求する彼女たちの姿勢は、“オルタナティヴの更新”などという大仰な言葉以上に意義深いと思う。(井草七海)

22
DARKSIDE
Nothing
Matador / Beatink
デビュー作で『Psychic』と銘打っているように、このバンドはサイケとされるモチーフを一貫して持っているが、電子音楽によるサイケの脱構築を試みた気概は理解できるものの、抽象性に終始した緩慢な1stは、非常に退屈であった。メディーヴァルな作風でサイケにアプローチしたセカンド『Spiral』も、ほぼ同様の感想だ。私はこのバンドにとって良いリスナーではなかったが、本作からのリードシングル「S.N.C」で、その見方は変わった。デイブ・ハリントンのコーラスがかかったドンシャリなスラップベースから始まるこの曲は、ファンカデリックからファンクネスを抜き出し、アシッド・ハウスの狂酔を注入したような曲だ。完全にやられた。続く「Are You Tired?」では、サザン・ロックにあるヒッピーマインドからアプローチしており、そのムードは作品全体に充満している。ニコラス・ジャーの音響センスの円熟からか、バンドがサウンドにおける柔軟性を得たのも大きな成果だ。00年代以降のネオ・サイケデリアの血脈においても類を見ない秀作と言っていいだろう。(hiwatt)

21
claire rousay
a little death
Thrill Jockey / HEADZ
2020年の『a heavenly touch』と2021年の『a softer focus』に続く3部作の最終作とされる本作は、ヴォーカルやメロディを押し出した前作『sentiment』を経て、元のエクスペリメンタル/アンビエント路線へと回帰した作品と呼べるだろう。とはいえ、クレア・ラウジーの音楽は一貫している。フィールド・レコーディングされた音を背景に、浮かび、沈み、曖昧に流れていく電子音や生楽器の音色……ラウジーはときに自らのヴォーカルも操りながら、それらを巧みに配置することで、リスナーの過去/記憶を呼び起こすと同時に、それらがすでに手の届かないものであることを、その哀しみを伝えてきた人だった。そして、ラウジーは本作でとりわけ音がお互いに融解していくプロセスにフォーカスしている。つまり、『a little death』にあるのは哀しみだけではない。哀しみを積み重ねて続く人生、その苦しさと美しさである。(高久大輝)

20
Sudan Archives
THE BPM
Stones Throw
ポスト『brat』のシーンにおいて最も洗練された音がロード『Virgin』だったとしたら、最も混乱した音は『THE BPM』だ。スーダン・アーカイヴスは本作で、長年連れ添ったパートナーと別れた苦悩を、混沌としたやけっぱちのサウンドに乗せて表現している。採用されたのは、“ガジェット・ガール””という新たなペルソナ。冒頭の「DEAD」から、ジャージー・クラブの疾走するスピード感に乗せて、自らの存在を疑うかのように自問自答を繰り返す。ケレラ『Raven』(2023年)を思い出すようなR&Bとエレクトロニックの流動的な共演は、しかし、アンビエントな揺らぎなんて要らないと言わんばかりに、ヴァイオリンによって華麗に切り裂かれる。その奇妙な作家性が見事に結実している曲が、「SHE’S GOT PAIN」だ。失恋の哀しみがR&B的な情緒の形で歌われるのも束の間、「bite/right/babe」の押韻とともに弦の音が炸裂する。これを作らないと次へと進めなかったのであろう、彼女の実存が飛び散りながら舞う怪作。(つやちゃん)

19
Everything Is Recorded
Temporary
XL Recordings / Beatink
“もしフォーク・ミュージックが80年代にレゲエと同じように『デジタル化』していたら?”。《XL Recordings》を主宰するリチャード・ラッセルによる協働プロジェクトの三枚目のアルバムは、ノア・サイラス、ビル・キャラハン、サンファ、カマシ・ワシントン、ジャー・ウォブル、ジャック・ペニャーテ、そしてあのスティーライ・スパンのマディ・プライヤーなど、多様という言葉では表せないほどの異才達が参加しながらも、右の問いの通り、フォークの音楽形式がいかにして現代のテクノロジーと逢着しうるかという命題への実践的な回答となっている。“フォークのデジタライズ”は、たしかに今年の音楽シーンを貫く一つの基底音だったことは間違いのないところだろうが、この作品ほどそれを自覚的に行った例は稀に思う。元来フォークがブリコラージュ的音楽表現だったことを思えば、現代においてこの問いが発されるのは必然だったともいえる。そして、“私”と“公”が様々な技術を介して大規模に撹拌される今、つねにすでにそうした二項対立を超えてあったフォークがこのような形で彫琢されるに至ったのもまた、ある種の必然であったのだろう。(柴崎祐二)

18
Wednesday
Bleeds
Dead Oceans / Big Nothing
カーリー・ハーツマンの歌とギターは彼女自身の感情を吐き出すためのものだが、それが結果的にオルタナティヴ・ロックなるものに生々しさを取り戻すこととなった。一大ブレイクスルーとなった前作『Rat Saw God』の時点で“カントリー・ゲイズ”などという言葉でウェンズデイの音はまとめられないものだったが、バンド・サウンドをビルドアップした本作に至り、彼らにとってカントリーと南部ゴシックのストーリーテリングからの影響がいかに重要だったかを痛感する。アメリカ南部に生きる見落とされた人びとの物語を掬いあげることに使命を感じている、というのはハーツマンの弁だが、彼らの歌はそれを観察的なアプローチではなく、いったん内部に取りこんでから痛みとともに放出する。血を流すように。ヘヴィなギター・アンサンブルと軽快なカントリーのタッチが平然と共存しているのは、アメリカの片田舎で生きる者たちの日常や人生の多層性を体得しているからだ。自分たちの情動は、アメリカの音楽の内側に息づいているのだと。(木津毅)

17
Algernon Cadwallader
Trying Not to Have a Thought
Saddle Creek / DISKUNION
10年代後半以降のインディー・ロック/フォークにおける重要な要素の一つであった多層的かつ多面的な“エモ”という表現形態を、ミッドウエスト・エモ文脈において継承し再興させた第四波エモの旗手による14年ぶりとなるサード・フル・アルバム。彼らの特徴であるトゥインクルなギター・フレーズを抱えた情感的なメロディーのうえを、軽快に跳ね、衝動的に駆けるヴォーカルはいまも鮮やかに輝く。前作から経過した長い年月は、ルーツであるアメリカを、フィラデルフィアを、そして足元にある自らの生活を真摯に見つめ、書き留めたリリックにかたちを変え、思考の深みを作品に与えていく。昨年、シンディ・リーを年間ベスト・アルバムとしてセレクトし、自らの原点でもあるインディー・ロック回帰の流れをみせる《Pitchfork》がいち早く本作の取材記事を立ち上げ、批評メディアにおけるほぼ唯一となるレヴューを“BEST NEW MUSIC”として掲載したことも必然だった。(尾野泰幸)

16
kanekoayano
石の糸
1994
この人の言葉を一文字でも聞き漏らした時点で、この人について一切話してはいけない。高校3年生の春に『祝祭』を初めて聴いた時から、なぜかそう思い込んでいた。“歌詞は日記”というスタンスについて、彼女ほど徹底している人物を、私は知らない。そして唐突なファルセットの流入から人称代名詞の揺らぎに至るまで、彼女ほど全身で生活の不安定な脆さを声に出している人物を、私は知らない。もしや、この人が100歌ったうちの1について話すことは、残った99の日記を焼却していることと同義なのでは? そう妄信していたのだが、“メンバーの自発性を引き出したかった”と語り、バンド名義としてアルファベットを用いて、半ばサプライズで放たれた本作を再生し、スタジオに連れて来た猫がオルガンに乗っかって鳴らしたという「noise」のトーン・クラスターが流れた瞬間、憑き物が降りたように楽しく聴けてしまった。この人の曲にいるのは、この人だけじゃない。当たり前だ。そして、この人は“あなた”のことがわからないのに、“あなた”について話している。その勇気さえあれば、どれだけの壁を壊せるだろう。祈りに還元される直前の歓びと苛立ちに宿るパワー、血のように巡る。思えば、彼女は3年前のシングルで「わたしたちへ」と、青筋の浮いた手を差し伸べていた。いつも気づくのが遅い。(風間一慶)

15
MIKE
Showbiz!
10K
サンプリングないしそれらしき渋いビートの上で、26歳がこれだけ自然にラップしているさまも驚きだが、それでいて、現代の若者のアテンション・スパンに合わせたかのように、ほとんどの曲が1ヴァースで完結しているのも驚きだ。その短い曲たちの中でストーリーを展開すべく、そしてインパクトを残すべく、MIKEはウィットに富んだラインを淡々と吐き続ける。悪習を断ち切ることができないという告白とともに、クォーターライフ・クライシスの残渣とでも言おうか、どこに答えが見つかるでもない、答えられることのない問いや嘆きが並べられる。惨めといえば惨めなのだが、その声が80年代のソウルをサンプルしたビートに乗せられるとき、そこに否定しがたい求心力が生まれることもまた事実なのだ。なお、イントロが20トラック目に配されているのは半ば偶然の産物のようだが、それにより何度も聴きたくなる仕掛けになっている点も心憎い。(奧田翔)

14
FKA twigs
Eusexua
Atlantic
AIに縋り、IPコンテンツに支配された世界で、絶対的な結果や存在、明確な価値を人々は追い求めるが、FKAツイッグスはそこから探り出せない領域を本作で見つけようとする。前回のミックステープ『CAPRISONGS』(2022年)でグローバルなヒップホップ、R&B、ダンス・ミュージックの刺激的な折衷の現在地点を見せつけた後、アルカとのコラボレートを想起させるようなプロダクションのもとで再び先鋭性を示す本作は、甘美で鋭利な音世界を創造するFKAツイッグスの到達点の一つだろう。しかも彼女の思想は、テクノロジーに溺れることではなく、生身の身体を取り戻し、その実存の在処を紛らわせるところにある。例えば100 gecsのディラン・ブレイディが参加した苛烈なビートが襲う「Striptease」から、粒だって聴こえるような電子音に歌唱が覆われる「24hr dog」、そしてついに歌唱が主導を握る「Wanderlust」の反転。その物語には、優れた結果に到達しすぐに果ててしまうような様とは、別の永久的な快楽が備わっている。(市川タツキ)

13
Lucrecia Dalt
A Danger to Ourselves
RVNG Intl./ PLANCHA
抵抗という名の官能がドロリと渦巻く。怪奇幻想小説のような不気味さの中に。これを、国のトップが排外主義を加速させるアメリカで制作したことの意味を考えるに、リアルな愛とエロスこそがレヴェル・ミュージックたりえるということを彼女は訴えようとしたのではないか、とも思う。現在はアメリカはニュー・メキシコに暮らすコロンビア出身の44歳。かつてベルリンに暮らしていたこともあった彼女は、これまでもノマド、もしくは異分子としての強さと寂しさを常に携えながら活動してきた。しかし、本作で今までのSF的ナラティヴではなくパーソナルな恋愛、経験を柱にすることで反逆にさらなるエナジーを与えたと言っていい。本作の1曲目で“あの歌声”を聴かせているだけではなく、自らのスタジオ《Samadhi Sound》を提供し共同で制作に挑んだデヴィッド・シルヴィアンも、本作に参加しているフアナ・モリーナもまた、アメリカでは本来余所者だ。諦めずに蠢き、胎動することで地盤はきっと崩れていく。(岡村詩野)

12
Nick León
A Tropical Entropy
Tra Tra Trax
再生すると夕日の下で海が穏やかに揺れ、巨大なビルが眩しく輝き、静かに胸が高鳴る。エリカ・デ・カシエールとの「Bikini」を青写真に制作された、マイアミを拠点とするニック・レオンのニュー・アルバム。彼はDJパイソン、Anthony Naplesや、Jonny From Spaceら地元のアクトとともにマイアミを再び注目される都市にしてきた。生活者と旅行者が、移民たちのいくつものルーツが、移住した超富裕層を含む幅広い所得層が、気候変動から受ける様々な影響が、その地理ゆえの利害が輻輳するマイアミで、デンボウやチャンガ・トゥキといったラテン・アメリカのダンス・ミュージックを存分に取り込んだこの仄暗いポップ・ミュージックは、イメージによって立ち上がる都市と身体で経験する都市との関係を結び直す。その足取りは終末に向かって加速する高揚感を、ここにいて他者と他の生物と生きていく美しさを信じるための鼓動に変え、私たちはそこに未来をみる。(佐藤遥)

11
Djrum
Under Tangled Silence
Houndstooth
幼少期からクラシックピアノ、そしてジャズの演奏に親しみながらも、DJ/プロデューサーとしてポスト・ダブステップの領域から頭角を表したDjrumことFelix Manuelによる新作は、制作期間が2017年から2023年までの足かけ7年に及んだことが示すように、総決算的な厚みを持った一作だ。2018年の『Portrait With Firewood』以来試みられてきた生楽器(特に自身のネイティブな楽器であるピアノ)とエレクトロニック・サウンドの合流はさらに巧みなものとなり、また2019年の「Tournesol」などで突き詰められたジャングル・ブレイクビーツの執拗なカットアップも、アルバム後半で集中的に披露されることで劇的なハイライトを形成する。キャリアを総ざらいするかのような“巨編”的佇まいを持つ一方で、アナログ2枚組におけるA〜D面の振り分けに応じて音楽性や雰囲気、音の密度が調整された、ある種オムニバス的なフォルムを持ち合わせている。自身の抱える多面性や複雑性とそれを整理して提示する几帳面さが結合したその様相は、正にセラピーとしての自己分析と再構築により示された“超越”の証だ。(よろすず)

10
caroline
caroline 2
Rough Trade / Beatink
ロンドン出身の8人組によるセカンド・アルバムは、フォークと実験音楽、一見かけ離れた音楽要素を融合させる。「Total euphoria」では、異なる響きを持つトロンボーンとヴァイオリン、電子ノイズを組み合わせた。最も大きな狂騒の「Two riders down」では、境界がぼやけるまでレイヤーを重ねる。前作よりヴォーカルが増えてはいるものの、オートチューンを施したりコーラスは断片的だったりと政治的なメッセージを含めないこともあり抽象的だ。この今作における曖昧さは、2025年の音楽構造の傾向にも通じるようだ。ビートの動きは目立たなく、アンビエンスな響きにより背景を満たしている。“美しいと感じる響き”を一致させる今作はファンタジーの世界へ逃避するようだ。ただ、ジャスパーが語るように即興的な響きを言語レベルまで認識しようと試みる内に、過去の懐かしさに接続することがある。彼らがしきりに言う“共通言語”とは未来のノスタルジーを指していると思えてならない。(吉澤奈々)

9
Nourished By Time
The Passionate Ones
XL Recordings / Beatink
Nourished By Timeことマーカス・エリオット・ブラウンが直面した挫折や孤独、世界に対する呪詛、そこからの再生について描いた前作『Erotic Probiotic 2』から2年。かつてのマーカス同様、人生に夢や情熱を持つあらゆる職業の人々の姿が本作の根底にあったという”情熱的な人”と冠された本作では、愛への渇望や繋がり、現代社会の困難といったモチーフが並び、個からより社会に暮らす市井の人々の暮らしや繋がりへとその視野を広げている。R&Bやチルウェイヴ、シンセポップなどを横断したプロダクションに乗っかるバリトン・ヴォイスからは、トランプ2.0に象徴されるアメリカの社会問題やパレスチナのジェノサイドといった世界の混迷を反映するように愁いや諦念が漂っているが、同時に本作の節々に散りばめられたエモーションからは、そんな時代に暮らす市井の人々を鼓舞し、少しでもより良い社会を作っていくための連帯を促すような熱も帯びている。そんなマーカスの情熱に応えることができるのかは我々次第だろう。(tt)
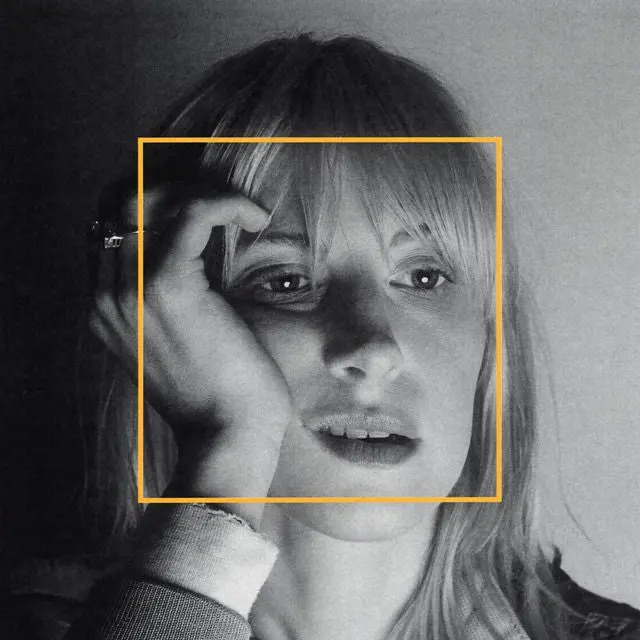
8
Hailey Williams
Ego Death At A Bachelorette Party
Post Atlantic
ジュリアン・ベイカー、ベッカ・マンカリ、ボーイジーニアス……。ヘイリー・ウィリアムスがパラモアとしてではく、自らのソロ・ワークで共演/共作してきた面々の名を見れば、ヘイリーが10年代以降のインディー・ミュージックにおいて次々と重要な作品を生み出した数多のフィメイル・シンガー・ソングライターたちにとって特別な存在であったことが伺いしれる。これまでのソロ二作で展開された、それらの作家たちと共振するようなセルフケア、エンパワメントといった主題をもった歌詞の情感、メランコリックで内省的な旋律、ミニマルかつソリッドに凝縮された音像は本作でも健在。過剰に制御されていたという《Atlantic》との契約を断ち切ったことも背景に、「I Won`t Quit On You」や「Parachute」、「Showbiz」のような大仰なシンセ・ポップにのせて沈思から激情まで動き回る歌声は従来の作品以上に軽やかで、一人の人間の揺れ動く感情と思考の過程をそのままなぞるかのよう。本作の収録楽曲が当初、まるで《Myspace》時代を想起するようなホームページでリリースされた事実が物語る、DIY精神と挑戦心が生み出したヘイリーの最も自由でリアリスティックなアルバムだ。(尾野泰幸)

7
aya
hexed!
Hyperdub
私はこのアルバムを聴くたびに混乱する。本作は、アヤ・シンクレアが薬物や酒への依存の最中、それが手に負えなくなっているような感覚のもとで、クィアであることの自覚と宗教との格闘という自身のトラウマと向き合いながら制作したという。そこでアヤはガバやテクノ、グライムのリズム、ドゥーム・メタルやスクリーモの意匠といった自身の音楽的経験から得た語彙と、ポップ・ソングの慣習的な楽曲構造を衝突させた。そんな中で生まれたのは、リズムが機能不全に陥り、音色が歪んだ楽曲たち。アヤの声はそこに幽霊のように侵入し、メタルコアのような歌声で叫びながら、悪夢とわずかな快楽を置いて去っていく。我々はそのグロテスクと崇高の狭間で宙ぶらりんの状態のまま取り残される。アヤのそのサウンドは、すでにあるとされる普遍性/正常性に与する意思があるものではないと思うが、それでも冷静ではいられない。だが、その混沌に浸ることが、何らかのトラウマを乗り越えるための一つの処方箋になるのではないかとも私は思っている。きっと折に触れて聴きかえすことになるだろう。(坂本哲哉)
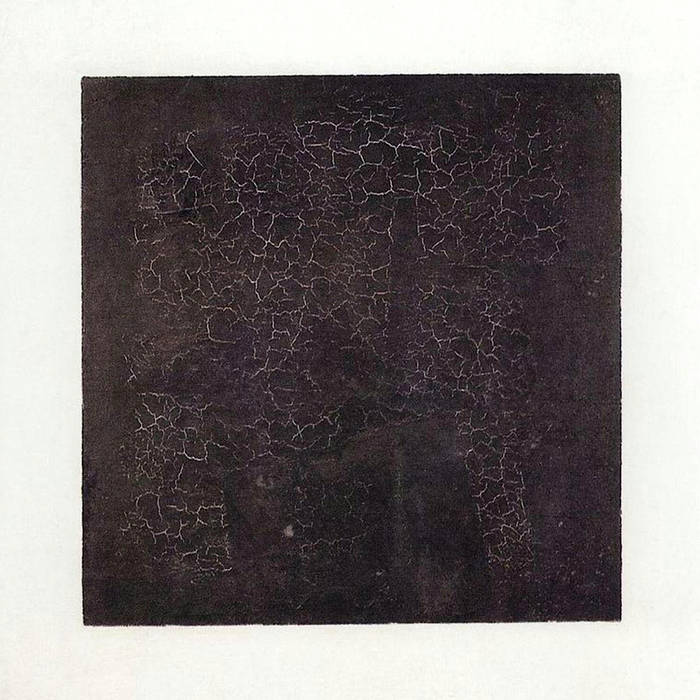
6
想像力の血
物語を終わりにしよう
想像力の血
流麗なメロディ、巧みなコードワーク、そして驚きに満ちたアレンジメント。想像力の血=佐藤優介の楽曲を構成するフラグメントは、彼がヴァン・ダイク・パークスとYMOを遠戚にもち、ムーンライダーズの息子であることを雄弁に示している。だが、それらが一つの総体として立ち上がったときに生まれる歪さには、そもそもそんな血統書に意味があるのかと突き放すような暴力性すら漂う。くぐもったヴォーカル、起承転結を無視した進行、過剰なノイズ、深読みを拒むタイトルとリリック──圧倒的な構築美と拮抗するかのように並べられた既成概念の否定と、定型への愛憎こそが本作の核心。その姿はまるで、生成AIが量産する陳腐なナラティヴによって白痴化されつつある現代に対し、一人のポップス職人が示すラッダイト的抵抗のようにも映る。その反抗が異形でありながらもまぎれもないポップ・ミュージックのかたちをまとう矛盾に、私は揺るぎない希望を見出すのだ。(ドリーミー刑事)

5
YHWH Nailgun
45 Pounds
AD 93
16分の刻みを3の倍数単位で切り分けることで酩酊感を生み出すドラムス。アーミングとワウペダルを多用し弦楽器離れした音色へと変質しているギター。モジュラーシンセの無調の音響、そして喉を引き裂くように叫ぶヴォーカル。このフィラデルフィア出身の4人組ヤハウェ・ネイルガンの音楽は、総じて聴き手を拒むように複雑かつ粗野な要素でソングを構成しているように見える。だが実際にはどこか親しみやすさを覚えるのは、ロート・タムの甲高い打音が楽曲に骨組みを付加しているからにほかならない。一方で「Pain Fountain」や「Iron Feet」における、金属臭のするペンキで塗りつぶしたようなウォール・オブ・ノイズは、現在ならざるものを立ち上がらせる不気味さがあり、楳図かずおが『14歳』でべったりとした赤の塗りによってグロテスクな遠未来を予測したのにも似る。「ハゲタカが俺の髪をつかんで持ち上げる/赤ん坊みたいに彼らの翼を見つめる/俺は白い雲の上にいる/俺はロシアの飛行機だ」(「Tear Pusher」)。歌詞の多くは抽象に閉じており露悪は控えめ。しかしキャリア初期にノーリッシュド・バイ・タイムやChanel Beadsと共演し、「2010年代後半のくだらねえインディー・ロックの時代から疎外されていた」と語るこのバンドの攻撃的なアティチュードは音楽そのものが何より雄弁に語っている。(髙橋翔哉)

4
Darian Donovan Thomas
A Room With Many Doors: Day
New Amsterdam Records
ただただ魅惑的なアルバムだ。11月下旬にワークショップから発展させたコラボによる次の新作を発表し、クィアネスの美しさや苦悩をさらなる境地へと繋いでいったこのブルックリン拠点のマルチ・インストゥルメンタリストは、筆者にはアメリカーナのちょっとイビツな重要継承者であり、チェンバー・ポップの現代最高レヴェルのミュージシャンである。あくまでキラキラとした音質とハイブリッドで精緻な音作りを武器に、ポップ・アマルガムとしてのオープンで野心的な矜持で、アメリカン・フォークロアをポップの領域にまで最大限に近づけることに成功したという意味で、ここにも参加しているサム・アミドンやキトバ、あるいはアノーニやスフィアン・スティーヴンスらの同志と言っていい。一方で、そうした先達が実は喉から手が出るほど欲しいであろうカラフルな邪気のなさ、無垢で鮮やかな明るさが、ある種のオプティミズムを求めている現代を象徴してもいる。昨年のアルバム『〜:Night』の前日譚にあたる本作は、過去に学び、未来で崩壊させる、もう一つの「想像力の血」だ。(岡村詩野)

3
Oklou
choke enough
True Panther
聴く人が聴けば、本作は“中途半端な作品”と断じられるかもしれない。実際、本作から聴こえる加工された声や、参加しているA.G.クックやダニー・L・ハールといった参加プロデューサー(メインは長年タッグを組むCasey MQ)の名前から想像するのはハイパーポップ的な音だが、期待する過剰さには届かず、ダンス・ミュージック的要素やアンビエント的要素、ポップ・ミュージック的なダイナミズムもゼロではないが突き抜けることはない。だが、そんな中途半端さを認識しつつも、一方で無視できない魅力も本作は携えている。例えば、まるで自分が書いたのかと錯覚するような世界の核心をつく歌詞、妖精の世界に迷い込んだような夢見心地のサウンド……それらはちぐはぐで、まるで実社会と想像力の交感と断絶を描いているようですらある。2025年も、私たちはクソったれな現実に対処しながらも、そこで夢に手を伸ばし続けた。『choke enough』は、その煮え切らない音でもって、私たちの限界と可能性を2025年に最もリアルな形で切り取っている。(高久大輝)

2
Geese
Getting Killed
Partisan
昨年はMk.geeが新しい音の加工とギター奏法でギター・ミュージックの概念を引き上げた。今年ブルックリン出身の4人組バンドは商業性を捨て、「人々は本物のクソを求めている」と言いカオスを律した。静かなグルーヴに不協和音のギターが飛び交う「Trinidad」、ウクライナ合唱団のサンプル素材で始まるタイトル曲「Getting Killed」。「100 Horses」のピアノと着実なタムによるリズムセクションは、ボアダムスの「Seadrum」を感じさせる。こうした音の渦にものまれないキャメロン・ウィンターの歌声だが、彼の声が力強いのはトム・ウェイツ、ヴァン・モリソンらを思わせるミドル・ヴォイスだからじゃない。ウィンターの書く歌詞は、未来に対する不安、戦争と社会批判、貧困などクソ真面目だ。これは老若男女問わない人間の叫びだ。それに彼のソロ作のように宗教的な側面もある。影響源は浮かぶけれど、一つ一つの構築が独創的で誰にも似ていない。ゆえに2025年の最重要ロック・アルバム。(吉澤奈々)

1
Dijon
Baby
R&R / Warner
2010年代以降における、2000年代を経由したプリンスの再参照はこれまでも、たとえばラ・プリーストやカルヴィン・ハリスやジャム・シティなど、主にR&B/ソウルの外縁の文脈で実践されてきた。すなわち、いまディジョンが『Baby』で成し遂げたこととは、プリンスの模倣者の現在地を、由緒正しき“ミュージック・フォー・セックス”たるサイケデリックR&Bの分野に揺り戻したことではないだろうか(彼が未来の正史に属する作家ではなく、すぐれた模倣者であることも強調しておく)。冒頭の2曲「Baby!」「Another Baby!」は、楽曲の構成を崩してまで、情けないほどのパッションと語りにソングを委ね、センチメンタルな性愛のストーリーを綴っていく。最近ではディジョンのパフォーマーとしての弱さが指摘されていたが、彼はこのレコードではベッドルームの密事の告白に徹しており、ステージ上の観客との対話に彼のスタイルが適していないのは自明である。また、『Baby』はプロダクションのレコードである。ギターや鍵盤のポキポキとした質感や、音割れするようなヴォーカルが、グリッチ・ノイズの代わりにアルバム全編に銀色の魔法をまぶしている。近年のYeを思い出させるサンプリング多用は、曲中にちぐはぐな継ぎ目を頻出させている。「Another Baby!」や「HIGHER!」におけるDJクイックやブラック・フラッグのサンプリングは、性愛という名のアシッドによってピッチアップされており、甲高くミックスされたスネアと同調して昂揚を表出する。
「もう一度いける、じゃあ続けよう!」(「Another Baby!」)。
『Baby』は父の物語であるという以上に、夫婦の物語である。子供がいる家庭において、親子という関係性に引っ張られずにパートナーとの関係性を描くことは難しいとされてきた。本作は子どもが生まれてからの性愛を描くことを、剥き出しのリリックと粗っぽいプロダクションによる力技で成功させている。ディジョンがほぼ共作として参加したジャスティン・ビーバー『SWAG』『SWAG II』もまた、ビーバーが子供の誕生を経験しての作品だった。33歳を迎えたディジョンは人生における現在のステージを肯定することを志向する。この数年は各メディアによる年間ベスト・チャートの大半の作品が、女性とLGBTQ+作家たちによる作品だった。それに対して、男性のセルフケアや男性性の肯定としても解釈できる作品性や、それがひび割れたストレンジな音像とともに、盟友Mk.geeとの連帯やトップアクトであるジャスティン・ビーバーへの拡張としてポップ音楽の世界全体に共有されたことはひじょうに2025年的といえよう。(髙橋翔哉)

THE 30 BEST ALBUMS OF 2024

THE 30 BEST ALBUMS OF 2023
.jpg)
THE 30 BEST ALBUMS OF 2022

THE 25 BEST ALBUMS OF 2021

THE 25 BEST ALBUMS OF 2020
Text By Sho OkudaRyutaro AmanoHaruka SatoShoya TakahashiNana YoshizawaTatsuki IchikawaIkkei KazamaMasamichi ToriihiwattttRen TeraoyoroszCasanova.STsuyachanTsunaki KadowakiYasuo MuraoDreamy DekaTsuyoshi KizuShino OkamuraYuji ShibasakiNami IgusaDaiki TakakuTetsuya SakamotoYasuyuki Ono
