THE 30 BEST ALBUMS OF 2024
2024年ベスト・アルバム
選盤、順位は編集部5名の合議によって決定。そして、編集部でどの筆者の方にどの作品を書いてもらうかを決める。TURNの年間ベストがスタートした時からこのやり方は変わっていない。けれど、今年はとりわけ選定するのが難しかった。2024年も優れた作品は多々あった。頭抜けていると思う作品もおそらくこの記事を読んでくれている読者の方なら各自思い浮かぶことだろう。だが、相対的に、どの作品を1位にしてもおかしくない、というと綺麗事のように聞こえるかもしれないが、ここに選んだ30作品の一つ一つが発信していることに、改めてもっと対等に丁寧に目を向けるべきではないか。そんな思いから選ばせていただいた。先進国の多くが政権交代に揺れ、政局不安定な状態が続き、どの国でも自国に対して不信感を募らせる者が激増している。侵略もジェノサイドも止まらない。けれど、音楽や文化は無力だと嘆くのではなく、影響力を持つリーダーに託すのでもなく、世界中に点在する小さな力こそが動かしていくだろうことを、ここに選んだ2024年の30枚で感じ取ってもらえたらと思う。2024年もTURNの記事を読んでくれてありがとうございました。2025年もよろしくお願いします。(編集部)

30
Tyler, The Creator
CHROMAKOPIA
Columbia
時は誰にも平等に流れている。10年以上前、オッド・フューチャーのリーダーとして彗星のごとくシーンに現れ、MVでゴキブリを喰らい、確かな実力をもって有数の人気アーティストとなったタイラー・ザ・クリエイターにも。頭髪や体型の変化から加齢を感じずにはいられないなか、周囲の人間たちは着実に次のライフ・ステージへと進んでいるが、自身はその準備ができているとは思えない。加えて、常に誰かに監視されているかのように感じるパラノイアにも襲われる。本作においてそうした──おそらく誰もが中年へと差し掛かる際に直面する──事実と向き合うことは、タイラーが最も必要としていた作業だったのであろう。悩みを解決する物語は、いつもリニアに進むとはかぎらない。むしろ、大抵の場合はひとところに留まっているように感じるものだ。だから、本作をタイム・スタンプにすべく、新鋭アーティストをゲストとして迎えることも彼、いや、「あのニ○兼あのビッ○」にとって必然だったのだろう。(奧田翔)

29
Ezra Collective
Dance, No One’s Watching
Partisan
マーキュリー・プライズ受賞後に飛び回った世界の各都市でのライヴからインスピレーションを受けながら、各地で断片的に作られたという本作は、「ダンス」をアティチュードの核として掲げているエズラ・コレクティヴというバンドが、ダンス・ミュージックを媒介に様々な国のオーディエンスとシェアした空間をパッケージした幸福な旅の記録のような作品だ。フェミ・コレオソのジャジーなドラムを皮切りにダビーな演奏がフロアの喧騒に溶け込むイントロダクション。インタールードを要所に配置しつつ、アフロビートやハイライフを取り入れたアップテンポなダンス・トラックと、リラックスした雰囲気のラウンジ・ジャズやハウス・ミュージック影響下の心のインナースペースに入り込むようなダウンテンポのディープなトラックがシームレスに繋がる構成は、本作がバラバラのルーツを持つメンバーたちによる、あらゆるジャンルがクロスオーヴァーする優れたダンス・ミュージック集であることを証明すると同時に、バンドが世界各国のオーディエンスとシェアしたであろう、様々な感情が交差するダンスフロアの1夜の空気感をも見事に表現している。(tt)
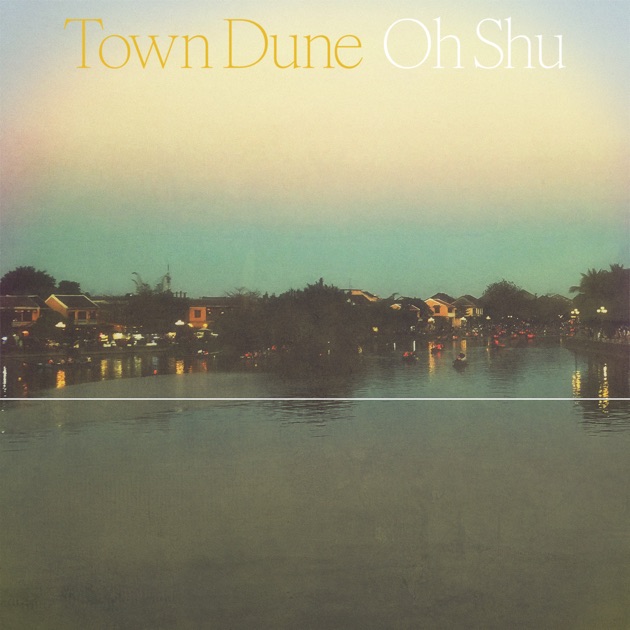
28
王舟
Town Dune
Self-released
デモの質感をそのまま残した前作『Pulchra Ondo』のリリースが2020年。パンデミック当時の地に足がつかない感覚をどこか捉えた一枚だった(「Disco A」は特にリピートした)。近年劇伴などのプロジェクトが続いた合間に生まれたことが想像できる、短い曲が集められた本作の構成は前作の延長にあたるような趣で、自然と比較してしまう。今、どんな気分がそこに映りこむのか。R&Bやエキゾ、ディスコなどが熱を持ちすぎずに配置され、サンプリングや環境音は空気を攪拌し、「Machibito」で戻ってきた彼の歌声にやたら落ち着いたり。でも、ところどころ優しく儚いトーンはジャケットの半端な夕暮れを思わせてうっすらと寂しい。時代は結局戻ることなく、そのまま変わっていった。不安は形を変えつつ、最悪と言い切るのもまだ早いような。2024年の煮えきらなさは、むしろ断片的な11曲の中にこそ、今回も定点観測された気がした。(寺尾錬)

27
Ghost Dubs
Damaged
Pressure
Michael Fiedlerによるソロ・プロジェクト=Ghost Dubsの初アルバムは、The BugことKevin Martinのレーベル《Pressure》からリリースされ、PoleことStefan Betkeによってマスタリングされているという事実が端的に示すように、《ベーシック・チャンネル(Basic Channel)》から《Chain Reactio》、そして《~scape》などへと続く、ベルリンのクラブ・シーンに根付くダブの新たな1ページとなる作品だ。『DUB論』の再発、『DUB入門』の刊行、そして『キング・タビー──ダブの創始者、そしてレゲエの中心にいた男』の翻訳と、その歴史を追いながらダブへ着目を促す動向が度々起こったこの1年ほどにあって、本作のジャマイカ~UK~ベルリンへと渡る射程の長い眼差しと磨き上げられたソリッドな重さが結合した濃厚なダブ・サウンドは、その魅力の現在形を思い知るに十分な威力を誇っている。(よろすず)

26
Fcukers
Baggy$$
Technicolour
このレコードをパーティー好きの日和見主義なアクトの産物、インディー・スリーズのムーヴメントのひとつとして、ナイトライフを満喫する人に独占させてしまうにはもったいない。The ShacksとSpud Cannonの元メンバー3人がビートとダブステップを作りたくて結成したという逸話や、ナンセンスだけれど不思議と心に刺さるリリックから、ある種のフラストレーションの発露としての熱量が重視されていると聴かれるかもしれない。しかし90’sハウスを彷彿とさせる表面上の“軽さ”やDIY的な手さばきの痕跡はあるけれど、夢見心地の「Mothers」では《Brainfeeder》のSalami Rose Joe Louisを引用していたり、プロダクションにおける審美眼は驚くほど深く広い。映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』で無軌道で野心家の若手カメラマンこそが歴史に残る1枚を撮れたように、実に冴えたアイディアをもって、2024年のシリアスさと楽観さがないまぜになったムードがパッケージされている。(駒井憲嗣)

25
Ka
The Thief Next To Jesus
Iro Works
「これは俺たちがみな経験し、共有する苦闘/奴らがお前を痛めつける武器になんてならぬよう」(「Bread Wine Body Blood」)。ニューヨークを中心に連綿と続くアンダーグラウンドラップに特有のラフで煤けたループにのせて、カーはヒップホップシーンやアフリカンアメリカンの友人たちへ呟くような声で警告する。そこにあるのは諦念、苦悶、自他への嫌悪、そして未来へのこんがらがった意志だ。が、カーは『イエスの隣の泥棒』というアルバムを遺して52歳の若さでこの世を去った(なお彼は、ステージの外では消防士としてブルックリンを守っていたという)。最期の作品に相応しい、と感じていることに私自身が混乱しているが、ともあれ黒人とキリスト教、そして救済を巡るこのレコードがカーの到達点の一つであるのは間違いない。イエスとともに磔にされたが悔い改めることで救済されたディスマス(=イエスの隣の泥棒)は、カー自身であるのと同時に今のアメリカ社会を生きる黒人たちのことでもある。「Borrowed Time」でオルガンのロングトーンを背景に「服従する前に自らの死を目論む」「その時が俺にも来たら、それが天に与えられた時間であってほしい」と吐き出したカーが見つめていたのは絶望だったのか、希望だったのか。私たちにできるのは遺された音楽に耳を傾けて何かを感じること、そこから考えることだけだ。(天野龍太郎)

24
Bolis Pupul
Letter To Yu
DEEWEE / Because Music
Charlotte Adigéryとの共作も伏線にすぎないと思えるほどの、なんとプレイフルなシンセポップであること。Bolis Pupulの新作『Letter To Yu』の魅力は、単にYMOを経由したジャパン『Tin Drum』風味なビット/オリエンタル・ポップな音色/音階遣いに留まらない。あるいは、ゲサフェルステイン(Gesaffelstein)とPupulがリバイバルを画策している「new beat」というジャンル(DAFやナイン・インチ・ネイルズに代表される80年代のポップなインダストリアル)の滋味にも留まらない。本作のもっとも際立った快楽性をひとつ提示するとすれば、それはビートのジャスト感である。予感されるツボを突く、正確に小節を4分割したこのビートは、時に小っ恥ずかしささえ覚えるほどに聴き手の足元や腰回りにぴったり貼りついてシェイクする。特に「Doctar Says」の馬鹿馬鹿しさと言ったらないよ、スクエアで過剰なビートはdrift phonkの夢の続きを見せてくれるかのようで。(髙橋翔哉)

23
Wool & The Pants
Not Fun In The Summertime
Self-released
「今年の夏は暑かった」という愚にもつかない感想を、毎年のように呟いている気がする。このくらいの気温だと、屋外で活動を行うこと自体が現実的ではなく、エアコンを効かせた自室の方がむしろ夏の主戦場になるわけで、Wool & The Pantsの新作が届けられたのはそんな2024年の残暑も終わりに差し掛かった頃だった。タイトルの元ネタであるスライの原曲が「Hot Fun in the Summertime」であったことを踏まえると、この“H”から“N”へのスライドは生活の間隙から導き出された精一杯の洒落であるようにも思えて笑える。大絶賛で迎えられた前作同様、ヴォーカルの德茂が全て一人で作り上げた自己/自室完結型の冷感ファンク。ぶっきらぼうなローと浮動する声はそのままに、「熱帯夜」のストレートなダブや「I’ve Got Soul Pt.2」の前のめりなシャッフルビートなど、各セクションの音像がクリアになったことによりビートの打感が強調され、ナイトクラブをはじめ様々な環境で気持ちよく鳴らせる作品だ。ごめん嘘だ、自分の部屋が一番良い。(風間一慶)
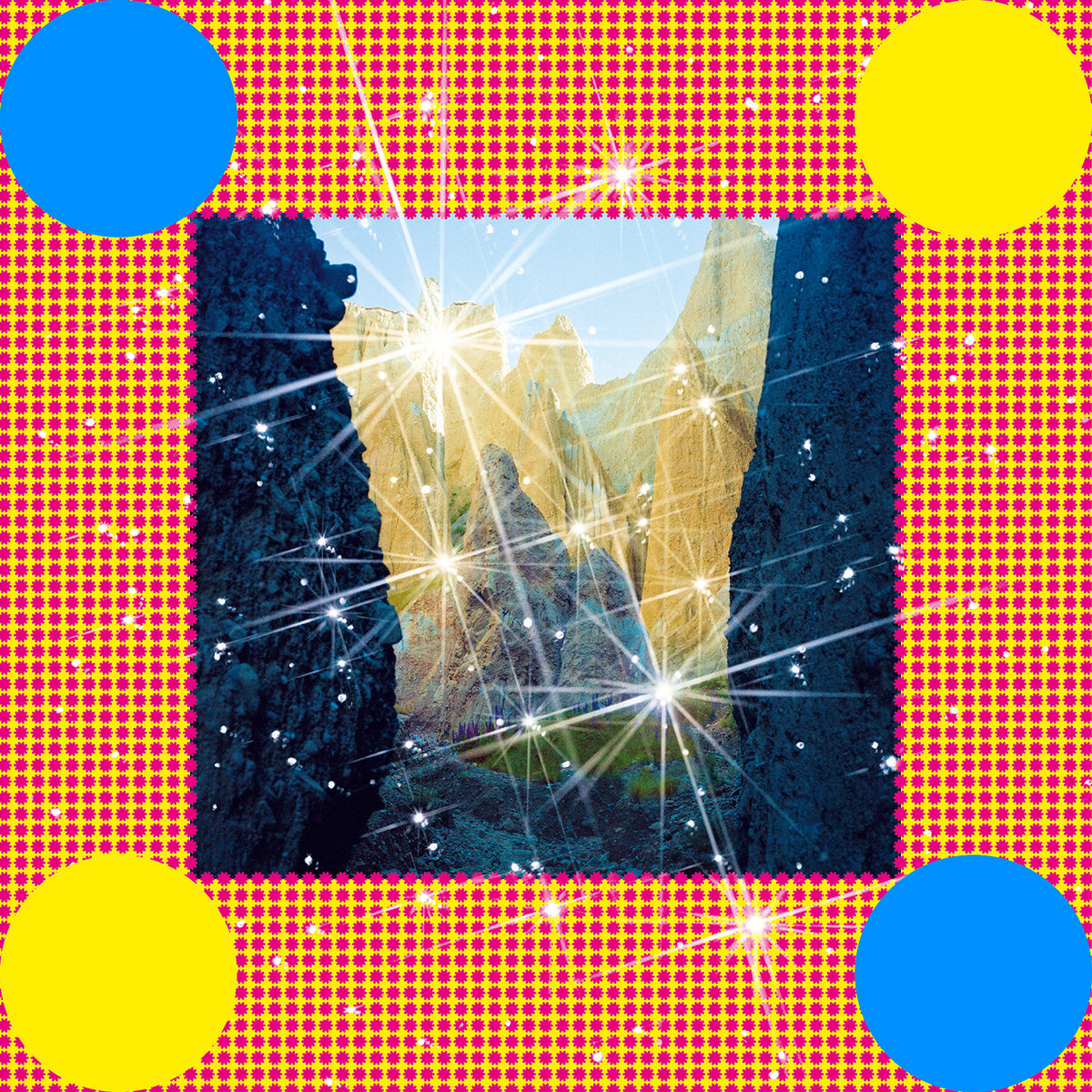
22
Caribou
Honey
City Slung
本作の「Volume」にM/A/R/R/Sの「Pump Up the Volume」がサンプリングされているので、久しぶりに原曲を聴いてみたらそのプリミティヴなダンスへの欲求に胸が高鳴った。そう、たしかにわたしたちは、長らくこの感覚を忘れていたかもしれない。ポスト・パンデミックで高まるダンスへの欲望に応えるように、ダン・スナイスはクラブ・ミュージック寄りの名義であるダフニとの境界をみずから溶かすようにして、カリブーとしてもっともストレートなダンス・アルバムを作りあげた。ここには彼らしいエレクトロニカの細やかさやベッドルームから夢を見る感覚もあるが、それらはダンスフロアで実際に音の粒を浴びてこそ完成する。ケリー・リー・オーウェンスやジェイミーXXらの新作とともに、ダンスフロアの多幸感を再誕させんとする一枚。自身の声を変調させた甘いヴォーカルとともに、スナイスは夜中3時にベッドルームではない場所で見られる夢もあるのだと誘惑する。(木津毅)

21
Various Artists
TRAИƧA
Red Hot Organization
30年以上の歴史を持つ、平等なケアへのアクセスを通じて公衆衛生と多様性の促進を目指す非営利団体《Red Hot Organization》の最新コンピレーション・アルバム。本作は性的多様性とトランスの権利へと意識を向けるというコンセプトのもと制作され、自らトランスジェンダー、ノンバイナリーを表明しているミュージシャンを含めた80名以上のアーティストたちが、ときにコラボレーションも行いながら参加している。ビヴァリー・グレン・コープランドが自身が86年にリリースしていた楽曲「Ever New」をサム・スミスと共に伸びやかに歌い、ジェフ・トゥイーディー(ウィルコ)とクレア・ラウジーはウィリアム・ブレイクの詩に曲をつけアンビエント・フォークとして蘇えらせる。時代、人種、性的指向、国境を認識したうえでそれらを越えた表現の探求が本作を貫いている。アルバム・タイトルはカエターノ・ヴェローゾがイギリス亡命中に録音した『Transa』(1971年)の引用であり、境界線を生き、寄る辺のなさを感じながらも表現を続けるという生の在り方を象徴している。(尾野泰幸)

20
Fievel Is Glauque
Rong Weicknes
Fat Possum
トロピカリズモやジャズ・ロックの遺伝子的アーティストは現代にも数々いるが、ブルックリンとブリュッセルを拠点とするこの男女ポップ・デュオは、音に求める徹底した心地よさやグルーヴと、そうは言ってもその心地よさは様々な試行錯誤の末に誕生するということを軽妙に表現しているユニットだ。この2作目のスタジオ録音作に関わっているのは実に26名。もともとはブルーズ系で知られるミシシッピの《Fat Possum》からのリリースということもあり、確かに録音のクオリティは上がっているし、予期せぬ方向に転がっていく転調、アレンジの妙味も前作以上に鮮やかだが、テクニカルな側面を強調せず、あくまでハンドメイド感があるのがいい。インドア・スタイルのポップ・ミュージックに改めて注目される流れを2025年以降に呼び込めるかに期待。ところでメンバーのザック・フィリップスは2017年にマヘル・シャラル・ハシュ・バズとのツアーで来日もしていて、次の機会には四国のお遍路をしたいそうだ。(岡村詩野)

19
HYPER GAL
After Image
Skin Graft
豊田道倫 & His Band!の角矢胡桃と美術家、石田小榛からなる大阪のデュオのサード・アルバム。アートワークの悪魔的なモチーフと腐食したスカム/ノイズコア・サウンドが前景化していた前作からの 「飛躍」を象徴するのか否か、本作のジャケ写では、直立する錆びた車輪がユーフォリアの象徴たる天使の両翼を受肉した。フェミニスト・パンクの先人譲りの、美意識の透徹された痙攣するインディー・パンクの美学と、オプティミズムが結晶した75年のデュッセルドルフを想起させるミニマリスト志向のプロトパンク・グルーヴ、関西ゼロ世代直系の、妥協も媚びもない初期衝動に突き動かされる狂騒的アート/ノイズ・ロック、それらの三位一体からなる、ラディカルでありつつ、ポップに突き抜けた音楽性。この焦げ付いた音の残像と調和する、どこか平熱のまま切迫した現実を見つめ、噛み締めるように反復される歌詞は、やがて訪れる「飛翔」の瞬間に熱く焦がれている。(門脇綱生)

18
Two Shell
Two Shell
Young
《Livity Sound》からデビューし、2022年にEP『home』で注目を集めハイパーポップに合流し、続くEP2作で彼らのサイバー・ワールド、《shell.tech》を紹介し、孤独や自信といった活動の核にある精神に触れ、「Talk To Me」でよりポピュラーな領域に踏み入れた。そこにはいつもベース・ミュージックへの愛と、ざらついたデジタルの感触、メタリックな閃きに照らされたメランコリーがあった。本作にもそれらはある。しかし、ムードはこれまで以上に身軽に切り替わり、ビートはより身体的でエクストリームでポップにメタモルフォーゼを遂げている。このセルフタイトル・アルバムは、Two Shellの新たな鏡像であり、新たな自我と言えよう。どこか祝祭的なムードが漂う中、インターネットの裂け目からサウンド・システムのロボットと共に“Everybody Worldwide”と呼びかけている。(佐藤遥)

17
Waxahatchee
Tigers Blood
Anti
オルタナティヴ・ロックからカントリー路線に舵を切った『Saint Cloud』(2020年)から4年。前作の主題であったアルコール依存からの回復を経たワクサハッチーことケイティ・クラッチフィールドにとって、今作は平穏な心で音楽を作るという意味で挑戦作だった。彼女が試みたのは、同じアメリカ南部出身で一回り下の世代の新星ギタリスト、MJ・レンダーマンと共にアメリカーナ作家としての青写真を発展させること。まろやかなバンジョーの音色に彩られたデュエット曲「Right Back to It」ではグラム・パーソンズとエミルー・ハリスが引き合いに出される程お手本のようなカントリー・ロックを披露。他方「Ice Cold」「Bored」はインディー・ロック的アプローチで刺々しい感情を見つめ受け入れるようなリリックが交差する。過去を受容し辿り着いた成熟こそが、どっしりとした安定感のある屈指の現代アメリカーナ作品を生み出した。(前田理子)

16
Klein
marked
Parkwuud Entertainment
クラシック、アンビエント、デスメタル、ヒップホップ、その他諸々が交錯し、ノイズと静寂に塗れたサウンドと共に、サウス・ロンドンのKleinは鼻歌のように軽妙な歌声を、切り刻まれたヴォーカル・サンプルを、ときに不明瞭な形で響かせる。さて、あなたは「nightwatch」のノイズの隙間から聞こえる「What’s the meaning?(意味とは?)」というフレーズを、どのように受け取るだろうか。「Blow the Whistle」のMV(本年最も美しい映像の一つだ)に映し出される、閑散とした夜の工業地帯と黒人の若者たちのダンスを見て、何を思うだろうか。悲観的な見方をすれば、それはコンテクストと情報、あるいは偏見と差別の嵐の中でひしゃげてしまった自由の在り方? 楽観的に見れば、私たちにまだ自由を声高に叫ぶ余白が残されていることの証明? 『marked』を前にした私たちは、答えを迫られる。今、この手に握り締められた自由がどんな形をしているのか、話をしようじゃないか。(高久大輝)

15
COVAN
nayba
D.R.C.
喧嘩に夢中か? ラップ・ゲームに夢中か? それとも高級車やブランド物のバッグに目が奪われるか? 何か忘れていないだろうか。《D.R.C.》所属のラッパー、COVANは、待望のファースト・ソロ・アルバムで、忘却の人々にビンタする。すなわちこれは、漢 a.k.a.GAMI『導 〜みちしるべ〜』の路上の暗さ、ECD『FINAL JUNKY』の非情な世界の断末魔、THA BLUE HERB『Sell Our Soul』のバイオレンスとダンスの混沌に心を掴まれた人々のためのレコードだ。つまり過去の日本語ラップの名作たちと肩を並べるように、諦念に満ちた殺伐とした世界で踊るのを促すだけではなく、生きているその呼吸、動作、目的そのものが踊ることなのだと諭してくれるような作品である。かつての日本歌謡が携えていた色気を思い出すような、全編に漂う夜の香りや、実存的な逡巡がリリックに刻まれていることも、作品の生々しさを浮かび上がらせるだろう。illな世界の中で、COVANは踊り続けることの価値を問い、数字のない世界を夢見ながら、ドラムは鳴り続ける。(市川タツキ)

14
Empress Of
For Your Consideration
Giant Music
ホンジュラス出身の両親を持ち、ブルックリンを拠点にするシンガー・ソングライター、Empress Ofの4枚目。この作品は、彼女の失恋が制作のきっかけだが、その恋を振り返るのではなく、愛を題材に自分の意志を自分の言葉として語ることを柱にしているのではないか。ストリップクラブで着想を得た「Femenine」は、彼女のために料理、掃除、ストリップ、ダンスをしてくれる男性が欲しいと歌う。これは、逆説的に男女間の差別を描いている。本作は全体を通して、身体の自己決定権を表現したフレーズ“My Body, My Choice”というテーマがあるように思う。しかし、アメリカ大統領選挙においてトランプの当選が決まった時、上記の言葉を言い換えた“your body, my choice”という女性の人権をはく奪する言葉がSNSに溢れた。こういう時代だからこそ、自分の言葉で歌う彼女の存在がより大事になってくるのではないだろうか。(杉山慧)

13
Nala Sinephro
Endlessness
Warp
シークエンス/アルペジエイトされたシンセ、循環呼吸奏法で鳴らされるブラス、シネフロが奏でるハープのリフ……これらは、本作のタイトルである『Endlessness(終わりなきこと)』と、楽曲のタイトルである「Continuum(連続体)」というコンセプトを表現するマテリアルとして用いられているが、聴いている内に、気付けばそれらは途切れている。「永遠なんてものはない」とはよく言ったものだが、それは「永遠」をテーマにしたこの作品にも当てはまる。演奏のリフレインは気付けば途切れているし、気付けば曲も終わっている。メタ的な見方をすれば、アルバムというフォーマットにあるこの作品も、45分で終わる。だが、3曲前のあのリフがまた戻ってきたりと、終わったものもいつかはリバイバルする時がくる。連続体の連続が永遠となる。この傑作もまた、今この瞬間も続いている。そして、形を変えたとしても、永遠に残り続けるだろう。(hiwatt)

12
O.
WeirdOs
Speedy Wunderground
O.、ロンドンの注目レーベル《Speedy Wunderground》と契約するサックスとドラムの二人組という変わった編成・名前のこのユニットはなんとも奇妙で素晴らしいデビュー・アルバムを作り上げた。あらゆる種類のエフェクターを通過してグルグルと頭の中を駆け巡るグルーヴに、予想だにしない方向から飛んでくるサウンド・エフェクト、そして次々に繰り出されるフレーズでこれでもかと心をかき乱す。スクイッドの諸作のようなダン・キャリー・プロデュースの実験的な側面が強く出たこのインストアルバムは、あるいは空間を作り出す体験の音楽なのかもしれない。まるでスクリーンに映るレトロなビデオゲームのSF世界に迷い込んでしまったかのような趣で、スリリングな音の連なりにせき立てられ彷徨うように時間が過ぎていく。そうして惑い、また最初からこの38分の輪の中に戻っていきたくなるのだ。力強く心を刺激する奇妙な体験、『WeirdOs』のタイトルに偽りなし。(Casanova.S)

11
トリプルファイヤー
EXTRA
Space Shower Music
海の向こうでトランプが返り咲き、尹錫悦がクーデターを企て、国内ではユーチューバーが選挙を牛耳り闇バイトが跋扈した2024年。ポスト・トゥルースが良識を凌駕した分岐点として記憶されるであろう本年を象徴する作品は、映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』と『EXTRA』だと言い切りたい。陰謀論に耽溺しながらここではないどこかでのサクセスを夢想し、不毛なバイトに勤勉さを発揮する男。吉田靖直が自らのキャラクターと重ねて自嘲的に描いてきた、いわゆる弱者男性の呪詛はいまやマジョリティとして、アングラ経済から政治まで駆動させる巨大な塊になり、世界は吉田に飲み込まれた。あのモリッシーですら万引き犯同盟を作れなかったというのに。その屈折した絶望が、稀代のグルーヴ求道者・鳥居真道がコンダクトするアフロ・ビートと結びつき、トリプルファイヤーは EP-4、じゃがたら、坂本慎太郎と受け継がれてきた不条理ファンクの新たな番人となった。(ドリーミー刑事)

10
Various Artists
funk.BR – São Paulo
NTS
2010年代、サンパウロのアンダーグラウンドでは、2000年代後半から続く自己顕示欲的なファンキが下火になり、欧米のEDMを吸収したファンキ・マンデランなどが台頭。そのサウンドはミニマルなビートを基調とし、爆発的なドロップとサブ・ベースの重低音を最大の特徴とする。そして、その延長線上にありつつ、鼓膜を粉砕するようなトレブリーなサウンドで、ドラッグがキマったときのような幻覚を与えるのがファンキ・ブルクザリア。本作に登場するMCやプロデューサーは、それらの美学を軸に、暴力的なディストーション・シンセやチープな8ビット・サウンド、アシッド・ハウスの催眠性、ジャズ的なシンコペーション、拍を無効化するようなラップを交え、鮮やかにファンキ・サウンドを攪拌する。現在のサンパウロのストリートのラディカルな活動報告であり、バイレ・ファンキ、ひいてはダンス・ミュージックにはまだ開拓されていない沃野があることを示す強烈な一枚。(坂本哲哉)

9
Arooj Aftab
Night Reign
Verve
コンテンポラリー・ジャズの人がさまざまなジャンルを器用に採り入れるという音楽性と、アルージ・アフタブのそれは異なっている。最初に聴いた『Siren Islands』はアナログ・シンセとエレクリック・ギターによる繊細なアンビエントで、グラミーにノミネートされた前作『Vulture Prince』は大半の曲がウルドゥー語(パキスタンの国語)で歌われていた。今作もヴィジェイ・アイヤーやギャン・ライリーから、エルヴィス・コステロやチョコレート・ジーニアスまで参加しているが、賑やかな要素は一切ない。それでも惹きつけるものが充分にあるのは、匂いや香りと同じニュアンスが尊重された音楽だからだろう。一線級のジャズ・ミュージシャンを自分の世界観の中で使いこなしているという意味ではダニエル・ラノワやジョー・ヘンリーにも近い。サウジアラビアで生まれてパキスタンで育った彼女のような存在が真っ当に評価されるアメリカ音楽の懐深さも感じている。(原雅明)

8
Mk.gee
Two Star & the Dream Police
R&R Digital
エリック・クラプトンにギタープレイを賞賛され、ジョン・メイヤーから若き日のプリンスに例えられた、マイケル・ゴードンことMk.gee。彼のサウンドはロック、80年代ポップス、90年代R&Bなどの折衷性に長けている。それはプリンスが築いたミネアポリス・サウンドに通じるだろう。だが、マギーの魅力は再現力の高さだけでない。謎めいた表現を好むプロデュース力にある。本作は、精神科医・心理学者であるユングの自己発見の元型からインスピレーションを受け、ある英雄の旅を題材に制作された。「Rylee&I」のワンフレーズの繰り返しも「I Want」のバラード調も「Candy」のキャッチーなメロディですら、サウンド処理によって新しく聴こえる。荒々しいビートを効果音として挿入したり、自らのギター・サウンドの輪郭をぼかしたり、SF的な音作りをしている。断片的な音色の集まりをスムースに繋いでいく、本作の構築性に脱帽。(吉澤奈々)

7
Cassandra Jenkins
My Light, My Destroyer
Dead Oceans
「Clams Casino」でのトム・ペティのようなフォーク・ロックで綴るロードムービーから、目線は一気に宇宙へと飛躍、プロデュースに迎えたアンドリュー・ラピンによるスペーシーながらも有機的なサウンドに、カサンドラ自身のアルト・ヴォイスと軽やかなギターが人の喋り声や虫の声とも溶け合いながら、温かな人肌感をも伴った環境音楽としても響く。遠く理解を超えた存在としての、天体への好奇心や畏怖、それらと並列される、人間のありふれた光景。そこには、死と喪失をもまるで吹き去っていく風のように概観していた前作と同様、人間とそのあらゆる営みもまた自然現象の一部であるとでも言うような、おおらかで大局的な目線を感じ取ることができるだろう。右と左、宗教の違い……理解が及ばない相手の生き様もまた確かに存在する営みであるのに私たちはそれらを視界から遠ざけることで分断を加速させている。だが彼女はそうではない。大地と宇宙との狭間で、地上のあらゆる営みを、鳥の目で見、虫の目で愛するのだ。(井草七海)

6
MJ Lenderman
Manning Fireworks
Anti
まず、声がいい。レンダーマンの音楽は、頼りなさげでいながらも確信に満ちたこの声の存在があればこそ、韜晦と自嘲に満ちた「メタ」の無限後退のレースから自らを引き剥がし、そしてまた、聴くものにそうしたレースのピットにつくことを諦めさせる。端的に言って、色香があるのだ。弱さについての歌は、その弱さを歌う表現に自足した時点で、とたんに「肌理」を失う。むしろ大事なのは、弱さや敗北を歌うという事実それ自体よりも、なめらかで美しい、つまり色香に満ちた「肌理」がそこで達成されているか否かなのだ。だからこそ物語は動き出すし、その物語はまた、単なる「うまくできたお話」以上の何かとして、私達の心を否応なく捉える。カントリー・ロックとオルタナティヴ・ロックの幸福な出会いから数十年を経て、今またそれらの手法を丁寧に練り上げることで、このような神話的な強度をもって現代人の生・性が歌い上げられ得るという事実。それもすべて、彼の音楽にあるセンシュアルな「肌理」のせいである。(柴崎祐二)

5
Clairo
Charm
Clairo
作品に課したサウンド・コンセプトを実現するため、ロスタム・バトマングリ、ジャック・アントノフといったプロデューサーをアルバムごと、周到に選択しつつ、ベッドルーム・ポップ~アンビエント・フォークを展開してきたクレイロが本作で手を組んだのは、本年にノラ・ジョーンズのプロデュースでも話題となったソウル畑のリオン・マイケルズ。キャリアを通じてクレイロが取り組んできた親密でハート・ウォーミングなソング・ライティングは、マイケルズの協力のもと、より厚みを増し、洗練されたアーバン・コンテンポラリーな質感のソウル・フレイヴァーをまぶしたサウンドと、軽やかで肉感のあるグルーヴをまとって更新された。クレイロ自身のピュアな音楽的趣味から生まれた歌を、自らの(音楽的)アイデンティティを保持しながら意図的にメインストリーム・ポップの流脈へと接合させた本作は、グラミー・ノミネートの事実が物語るように、現在における“インディー”の模範的回答ともいえる。(尾野泰幸)

4
Mustafa
Dunya
Jagjaguwar
“死”は救済か、忌むべきものか。もしくは世界は終わるべきか、続くべきか。ブラック・ムスリムの詩人/シンガー・ソングライターであるムスタファは、そのルーツを反映させるように、ウードやマセンコといった楽器をフォーク・サウンドに織り込み、英語の中にイスラム語を混ぜ合わせながら、そういった問いの間を揺れ動く。故郷=暴力に塗れたトロントのリージェント・パークへの愛憎もその狭間で色濃く浮かび上がってくる。だからそう、イスラム語で“この世”を意味する言葉を冠した本作は、極めて穏やかな音像ではあるが、常にどこかヒリヒリとした緊張感を纏って耳に届くのだろう。もちろん現実と同様に、本作に答えは用意されていない。ただ、祈りがある。いや、より正確に言えば、苦悩がときおり祈りへと転じる瞬間がある。ほんの幾ばくか、死を目の前にした誰かを立ち止まらせるかもしれない、そんな美しく、あたたかな瞬間が。(高久大輝)

3
Charli xcx
BRAT
Atlantic
正直なところ、やれfunk brasileiro、やれdrift phonk、やれhyper云々といった過剰さやら過激さはもうとうに飽きの対象だし、チャーリーxcxに関しても『how i’m feeling now』でその領域の最高到達点を打ち立てた以上、同じ方向性でのアップデートにはあまり期待していなかった。しかし、『BRAT』はサウンドの固有性──ポップネスの内壁に隠されたエクストリームなクラブ・ミュージック趣味、特にハウスやエレクトロクラッシュ方面の強化──はもちろん指摘されるべきだが、かと言って単にサウンドのみによって評価されてもいけない。3段階に分けたリリース形態や、いくつかの政治的なコンセプト化によるマーケティング、さらにポップスターからアンダーグラウンドのビートメイカーまで幅広いコラボレーション…による総合プロダクション。特にコラボレートについては、2010年代を通じてメインストリームとアンダーグラウンド、その他あらゆる両極端の属性に引き裂かれ続けていた永遠の二番手=チャーリーの不遇がついに報われた感動的な結実として捉えられたい。とはいえ「ブラットって何?」から履修するよりまずは当然、聴覚と脳天で感じてほしい。(髙橋翔哉)

2
Kim Gordon
The Collective
Matador
皮膚で捉える音だ。ノイズも短い振動であれば、そうした動物的な勘が働く音なのかもしれない。けれど、ノイズを引き延ばす持続音にしたり揺らぎを加えると、心地いい陶酔を生み出す。かねてより、ノイズとアンビエントに共通点を感じていたのは、こうした陶酔による鎮痛作用なのだろう。キム・ゴードンのソロ2作目『The Collective』はノイズとビートを直感的に採集した、ゴードンの記録集だ。冒頭「BYE-BYE」のシグナル音や押しつぶされたシンセベースは奇妙な夜道を想起させ、続く「The Candy House」から中盤「Trophies」までグリッチまみれのトラップが鳴り響く。「Psychedeic Orgasm」から終盤にかけて、澄んだ音域とギターノイズが感傷的なまでに増えてくる。とりわけ「Tree House」と「The Belivers」のパーカッシブな響きは多彩な音色に塗れていて芸術的。本作を意欲作と呼ばずして何という?(吉澤奈々)

1
claire rousay
sentiment
Thrill Jockey
複合性が一切ないポピュラー音楽などないと言っても過言ではないが、今やLAを拠点とするこのクレア・ラウジーの作品は彼女の人となりやキャリアがそのまま自然と折り重なった、ある種のドキュメントと捉えることができる。性的マイノリティであることを自覚し、葛藤するようになった10代、様々なバンドでドラマーとして活動してきた最初期、エモ・コアに出会い、さらには電子音楽やアンビエントに出会い曲作りを研磨してきた20代、そして、実験音楽、コラージュ音楽の手法を取り入れつつも、カントリーやアメリカーナの持つ寂寞にも心を寄せる近年……彼女の音楽の断面はそのまま彼女自身の体験の蓄積だ。あるいは、完成度の高さ、セールス面からいくと他のビッグネームに劣るかもしれないが、ある種古典的なシンガー・ソングライターの在り方を継承し、自分を曝け出すことを厭わない強さを時間かけて表現するひたむきな彼女は、自分のように世界中の“小さな存在”を見過ごすな、と主張しているかのようでもある。そもそも、イビツな個の発信力で地道に歩みを進めてきた彼女を、複合的な音楽レーベル《Thrill Jockey》が今フックアップしたこともまた大きなトピックだった。(岡村詩野)

THE 25 BEST ALBUMS OF 2023
.jpg)
THE 30 BEST ALBUMS OF 2022

THE 25 BEST ALBUMS OF 2021

THE 25 BEST ALBUMS OF 2020
Text By Sho OkudaRyutaro AmanoHaruka SatoKenji KomaiShoya TakahashiMasaaki HaraRiko MaedaNana YoshizawaTatsuki IchikawaIkkei KazamahiwattttRen TeraoyoroszCasanova.STsunaki KadowakiDreamy DekaTsuyoshi KizuShino OkamuraYuji ShibasakiKei SugiyamaNami IgusaDaiki TakakuTetsuya SakamotoYasuyuki Ono
