THE 30 BEST ALBUMS OF 2022
2022年ベスト・アルバム
ローカリズムが“都市部(中央)ではないどこか”を創生・再生するのではない。ローカリズムがグローバリズムと相克の関係にあるわけでもない。むろん、ポップスという主流に対峙する武器としてインディー音楽やマイノリティたちの表現があるわけでもなく、だがしかし、そうした二項対立に逃げ込む安易さが主流としてのポップスやR&B、ヒップホップとインディー・ロックやオルタナティヴとされてきたロックとをさらに乖離させている。全ての音楽がそれぞれに“局所的なホーム”にいる、とすることはできないものか? 強引なグローバリズムの普及が提示する“求められる能力”とやら。「誰もが豊かでありますように」が姿を変えた「お前より俺が優れている」。マニュアル化されたその優生思想が引き起こす重いヒエラルキーに、大衆……に限ったことではないかもしれないが、音楽という表現がまず立ちはだかっていてほしい。手段ではなく、方法論でもなく、自分という個をアインデンティファイした末の強烈なハレーションとして。音楽、音は空気の振動が形になったもの。世界中で激しい振動だらけだった2022年から相変わらず見通しの読めない2023年へ、まもなくバトンが渡されていく。
今年も『TURN』を読んでいただきありがとうございました。今年は年間ベストとして例年の25枚より多い30作品を選出しています。ぜひゆっくりと読んでみてください。(編集部)

30
Bartees Strange
Farm to Table
4AD / Beatink
インディー・ロック、ラップ、R&B、エレクトロニカ、フォークといった特定ジャンルに内閉しない、ジャンル越境的なサウンドと自らの人種的アイデンティティにまつわる違和感を鋭敏に表現したリリックがバーティーズ・ストレンジの音楽的特徴であり、それがストレンジの音楽における批評的成功を下支えしてきた。名門《4AD》移籍後初のフル・アルバムとなる本作でもその構築性は踏襲されているが、対象を“ジャンル越境的”と言及したとたん、当該カテゴリーにその音楽を囲い込んでしまうという矛盾をストレンジは見逃さない。「満たされる方法を知ることは最も難しい/飽くなき消費を止められない/あいも変わらず腹が減ったが、絶対に満たされない、絶対に満たされない」(「Cosign」)というリリックはまさにその矛盾への言及とも見て取れる。自らの音楽を生かしも殺しもする“カテゴリー”と常に戯れ、対峙し続けること。それは創造的で政治的な決断としてストレンジの音楽を形成している。(尾野泰幸)

29
Ecko Bazz
Mmaso
Hakuna Kulala
インダストリアル、グライム、トラップ…等々、様々なスタイルと隣接する、超エッジーでヘヴィなサウンドが展開されるのがこのウガンダのラッパーによる本作だ。リリース元は《Hakuna Kulala》。親レーベルの《Nyege Nyege Tapes》と共に、アフリカを拠点に世界と繋がる重要レーベルの一つだ。本作にはレーベルオーナーであるケニアのSlikbackを始め、ブライトンで活動する日本人のScotch Rolexなど世界中から多彩な面々が参加。2022年は絶好調だった2つのレーベルを象徴するような作品となっている。しかし、本作の素晴らしさはビートだけではなくEcko Bazzのラップあってこそ。貧困や暴力など社会的なテーマを扱ったラップは、言いたいことがあるからこそ力がこもり、言葉数も増え早口にしなければビートに収まらない。その切実さが音楽としての強度に繋がり、本作を2022年屈指の作品にしている。(アボかど)

28
大石晴子
脈光
大石晴子
サックスとシンセサイザーの音色が織りなすレイヤー、空間的で揺らぎのあるリズムとそこにたゆたう湿り気のあるボーカル。本作が到達した高みを、サム・ゲンデルを中心とした最新のLAジャズ、ネオ・ソウル、そして大貫妙子をルーツとする良質なジャパニーズ・ポップスの稀有な結節点として語り切ることも十分に可能だろう。しかしこの折衷的な世界に、更なる深淵とそれに相反する親密さを同時にもたらしているのは、大石の歌声が孕む人間の体温と質実な生活の匂いである。”蕾のままで食べるのは悪いねと 菜の花をつつく”といった生と死がさりげなく共存する歌詞、鼻歌とマントラのあわいを思わせる「echo」の生々しさに震えた。沼澤成毅(SAMOEDO)、宮坂遼太郎(折坂悠太、South Penguin他)をはじめ多くの新鋭ミュージシャンの非凡さを堪能できる作品としても意義深い。デビュー作『賛美』から三年の雌伏を経た、鮮やかな跳躍。(ドリーミー刑事)

27
NewJeans
NewJeans 1st EP ‘New Jeans’
ADOR
発売当初から勢い落ちることなく大ヒットし続けている本作。まず、これまでもf(x)やRed Velvetなどの作品コンセプトを手掛けたミン・ヒジンによる、徹底したY2K感性のデザインやヴィジュアルもK-POPという総合芸術において、特筆すべき完成度の高さだろう。ただ、毎日のように本作を聴いた筆者が最も惹かれた瞬間は、収録曲をとあるクラブでハウスやテクノのセットに交じって聴いた時だった。最近のK-POPヒットにありがちなマキシマリズムには頼らず、歌唱や演出にも過剰さを全く感じない。メンバーたちの声は、自然に滑らかなビートに溶け込み、心地よく聴き手を踊らせる。楽曲プロデュースを行ったのが、以前は梨泰院を始めとしたクラブ・シーンでも活動、今年は長年のポンチャックについての研究をアルバム『PPONG』で発表した250、先鋭的なヒップホップ・デュオ、XXXのパク・ジンス(FRNK)というソウルの2人のアンダーグラウンド・ミュージシャンである点は重要だ。(山本大地)

26
Father John Misty
Chloë and the Next 20th Century
Sub Pop / Big Nothing
ジョシュ・ティルマンがファーザー・ジョン・ミスティ名義での活動を始めて今年で10年。今作は通算5枚目のアルバムで、楽曲及び編曲のウェルメイドさは過去最高と言えそうだ。オーケストラルなサウンドはもともと彼の得意とするところだが、今回はロック以前のポピュラー音楽へのアプローチがより顕著に見られ、ストリングス・カルテット、ブラス、木管楽器からなるオーケストレーションをバックに、ティルマンは前世紀半ばのポピュラー歌手のような堂々たる佇まいと歌唱によって曲中の登場人物たちの姿や声を浮かび上がらせていく。橋本治は著書『二十世紀』で20世紀がいかに19世紀的であったかということを述べているが、21世紀についてもまったく同様のことを感じざるを得なかった2022年に発表された今作には、シミュレーションや憧憬ではなく、「次の」新たな20世紀を現出させようというティルマンの意思が強く込められているように思える。(橋口史人)

25
BROCKHAMPTON
TM
Question Everything / RCA
古今東西のボーイバンドが経験する、活動の末期に引き起こされる目を覆いたくなるようなトラブルの数々を、ブロックハンプトンは実に用意周到に回避した。ライブを開催し、マーチも用意して、彼らは公明正大に無期限の活動休止期間に入る。兼ねてから告知されていたラストアルバム『The Family』のリリース翌日に発表された『TM』では、リーダーのケヴィン・アブストラクトがほぼワンマイクでライミングを重ねていった前者とは異なり、バンドの面々が幕切れを引き受けながらもブロックハンプトンという船から降りずにビートを乗りこなす姿が描写されている。アグレッシブなハイハットがトラップの進化と共に帆を進めてきた彼らの歴史そのものへの批評ともなりうる「FMG」や、らしさ全開のマイクリレーを繰り広げる「NEW SHOES」など、聞き終えてもなお前のめりにフィニッシュを迎えた清々しさがただ残るばかりだ。(風間一慶)

24
岡田拓郎
Betsu No Jilkan
Newhere Music / Spaceshower
このアルバムは聴く人によって解釈のポイントが異なるだろう。ビル・フリゼールからブレイク・ミルズまでを貫いたギター史の最先端に位置するアルバムとも言えるし、ジャズの方法論を解体することに刺激をもたらすアルバムとも言える。ヴォーカルの少なさが歌の概念を捉え直すイマジネイティヴなアルバムでもあるし、心地よさありきではない能動的なアンビエント音楽のその次を示唆したアルバムでもあるだろう。加えて、作品が出来上がったら終わりではなく、岡田はその後も様々なライヴの場で楽曲を変化させている。このアルバムの中で一体何が起こっているのか? 見えない。でも見える。多くを語らない。でも語る。ブラックボックスであることの豊かさとは……? 気がついたら多くの人が今年のベストに選出している。当然だと思う。(岡村詩野)

23
Bad Boy Chiller Crew
Disrespectful
Relentless
「親ガチャ」なんて言葉が飛び交ったのは比較的最近のような気がするが、決まりきった未来に打ち拉がれる若者は古往今来、至る所にいるだろう。馬鹿げた動画と共にイギリスの郊外、ブラッドフォードから現れたこのラップ・トリオもまた同様、深いニヒリズムに基づいて行動していることは言うまでもない。重要なのは、そのキャリアのスタートではなく、スターダムを駆け上がろうというタイミングでこのミックステープがリリースされたこと。そして相変わらずほとんどくだらないリリックと、ベースラインを中心にブレーキの壊れたようなバカ騒ぎのためのダンスビートに満ちた作品であったということ。「俺たちはただ自分たちの人生をソーシャルメディアに載せてしまった愚か者なんだ」。2021年、《NME》の取材に応えた際にも自覚が滲んでいた通り、彼らのブレーキは壊れたのではなく、彼らが自らの意思で壊したものである。人生の主役は自分自身だと言い切るために、中指とガンフィンガーを掲げろ。BBCCは今年最も挑発的かつユーモラスな方法で、絶望する同胞たちの魂を癒してみせた。(高久大輝)

22
Julia Jacklin
PRE PLEASURE
Polyvinyl / Big Nothing
地元オーストラリアを離れ、カナダのモントリオールでレコーディングされた3rdアルバム。自身の写真に手を触れるジャケットにも象徴されているように、少し引いた目線で自らの営みを冷静に見つめ直すような、抑制の効いたプロダクションが印象的だ。優雅なストリングス・アレンジを手がけるオーウェン・パレットをはじめ、アーケイド・ファイアやザ・ウェザー・ステーションに関わる面々による柔らかなテクスチャーも決して主張的ではないが、滑らかにフォークとオルタナを接合するサウンドやしっとりとした歌唱によく馴染んでいて、かねてから魅力だった彼女のソングライティングや作家性がより際立っているようだ。この2年間、演奏することよりもただ聴くことに専念し、音楽と再びつながろうとしたと語るジュリア・ジャックリン。インディーのザラっとした憂いの質感はそのままに、より普遍的なポップミュージックへと広がっていく意欲作といえるだろう。(阿部仁知)

21
HAAi
Baby, We’re Ascending
Mute
オーストラリア出身で現在はロンドンを拠点にするHAAiのデビュー作は、今年最もダンスと内省を軽やかに遊動した作品の一つであり、そして、最も充実したコラボレーション・ワークが展開された作品の一つでもある。獰猛なテクノを媒介に、ダンスフロアは社会的に疎外された人たちのためのサンクチュアリであることを伝える「Human Sound」。クラブという場所は多様な人たちの喜怒哀楽が交錯する場所であることを、ホット・チップのAlexis Taylorと共に描いた、メランコリックなドリーム・ポップ「Biggest Mood Ever」。そして、親友のJon Hopkinsと作り上げた、恍惚に向かって速度を上げていくレイヴのエネルギーを抽出したようなタイトル・トラック。テクノだけではなく、アフリカや中東の音楽も背景にしながらこれまで一人で寡黙に音楽を作り続けてきた彼女は、信頼のおける仲間たちと共に、その外の領域への跳躍を成功させたのだ。(坂本哲哉)

20
霊臨 (TAMARIN)
NEO NORMAL
三次元遊戯
元々YouTuberとして活動を開始したヒップホップ・クルー“三次元遊戯”の霊臨。彼が吐く日常的だが強い言葉たちは、“ノーマル”とされるものを並べ立てることで違和感を炙り出す。そして、心は貧しく文化も貧しい、でも飽食でいられる東京の街と若者の姿を活写する。「カニエのインスタ載るとかあのアートめっちゃ最新じゃーん/森美で売ってるグッズ絶対プレるってそれ!」(「アートかっこいいじゃん」)。ハイブランドとアートの蓄積された歴史と文脈を、無自覚にグロテスクに踏みにじりながらも、こんなにも日常はつつがなく進んでいく。皮肉と一人称による毒っ気たっぷりな『NEO NORMAL』は、アイロニーによる笑いこそが、時に殺気にも近い凄みを持つことを証明した。その後リリースされた、病み(闇)とスピ(すぴ♡)と三人称によるドライな『Log in! (deluxe)』とは対照的なアルバムである。(髙橋翔哉)

19
Salamanda
ashbalkum
Human Pitch / PLANCHA
人間界から程遠く、森にひっそりと住んでいた妖精サラマンダーがわたしたちの夢に現れた。ソウルを拠点とするレフトフィールド・アンビエント・ミュージックのデュオ、3枚目のアルバム。シグニチャーとも言えるマリンバによく似た音や、深い霧のようなコーラス、儀式や祈りを彷彿とさせる打楽器はそのままに、レゲトンやデンボウなど多様なリズムに支えられミニマルな展開が先鋭化、そしてそれらをいままでになく繊細で奥行きのあるサウンド・プロダクションがやわらかい布のように包み込む。現実での経験が実は夢だったことを表す韓国語の発音が冠された本作は、蛇のように、はたまた液体のように、ミステリアスに形を変え、トリスタン・アープらの《Human Pitch》からエレクトロニック・ミュージックの先端に顔を出し、たとえばリ・イレイやアップサミーと目を合わせ、ベッドルームもフロアも、夢も現実も越えたところへ聴く者を導く。(佐藤遥)

18
Weyes Blood
And In the Darkness, Hearts Aglow
SUBPOP
ジョナサン・ラドーと再びタッグ、やや室内楽的になった今作からは、“取り戻せない過去”が聴こえる。クサいほど甘いメロディとリフレインの多用は、“古き良き時代”のアメリカン・ポップス風。そして『ペット・サウンズ』を思わせるコーラスに、ローレル・キャニオンの美しいセピア色のフォーク。つまり、アメリカが戦後の豊かさの中で未来を信じ、まだ挫折を知らないあの頃の音──。陶酔のうちに自分の姿がわからなくなったナルキッソス、ジェームズ・ディーンの事故死、終焉した恋愛などを取り上げるリリックが暗示するのは、気付かぬうちに斜陽の帝国となっていた今のアメリカの姿だろう。だから、漂う懐かしさは翻ってディストピアSF的でもあり、その意味でOPNの起用はあまりに適任。とはいえ歌声には、嘆息とともにその愚かさを受容するような温かさも。我々はいつだって、過去へと押し戻されそうになりながら必死で前へ進むしかない、とでも言うかのような、三部作のうち“今”がテーマの二作目。(井草七海)

17
Lucrecia Dalt
!AY!
RVNG Intl. / PLANCHA
1人の人間の内側にある様々な記憶と感情、体験や思考が入り乱れたその混沌をどのように表現するか。特に本作でのルクレシア・ダルトには、そういう試みがある。電子楽器を中心に生楽器や時に金属の打音なども用いながら実験的な表現をするベルリン拠点の音楽家が、出身地のコロンビアで幼少期に聴いていた中南米の音楽、ボレロやメレンゲ、サルサを取り入れた。しかし、必ずしも照りつける太陽を感じないのは、極力抑えられたアップライト・ベースのビートやフリー・ジャズのトランペット奏者Lina Allemanoによる演奏の作用だろう。また、ダルト自身が演じたプレタを主人公とする全4編のMVを観ると、まるでアンジェイ・ズラウスキーの『シルバー・グローブ』を思わせる哲学的なSF神話すら広がっている。結び付くはずのなかった数多の個人的な興味を、作品としてまとめ上げることがいかに刺激的か。まだ見ぬサウンドは、自身の足元にこそ潜んでいる。そんな自己探求の可能性を示す作品だ。(加藤孔紀)

16
Florist
Florist
Double Double Whammy
虫の羽音や鳥の声、雨音といった自然音が背景で鳴り、擦れ合う弦の音までも録音した体温を感じるアコースティック・ギターがしなやかに爪弾かれ、ハートウォーミングなシンセサイザーやホーンが穏やかに響く。ヴォーカルのエミリー・スプレイグはアトモスフェリックな歌声で家族や周囲との関係性の変化や、親しき人の死をいかにして受容していくかという精神的なレジリエンスについて歌う。そのような本作に生々しく多彩なアコースティック・ギターをフィーチュアしたエイドリアン・レンカー『songs and instrumentals』(2020年)や敬愛する音楽家の自死を契機とし、喪失の受容と再起の過程をテーマとしたカサンドラ・ジェンキンス『An Overview on Phenomenal Nature』(2021年)の姿を重ね合わせてしまう。近年における上述の二作品に代表されるような所謂〈アンビエント・フォーク〉を総括するようなパーソナルでコンシャスな佳作。(尾野泰幸)

15
Huerco S.
Plonk
Incienso
“中間”を感じさせるものに惹かれる1年だった。最適化されないこと。極端さと極端さのあわいにただようこと。曖昧で脆弱なムードを捉えること。名作『For Those Of You Who Have Never (And Also Those Who Have)』(16年)、ダーク・アンビエントの新たな潮流をつくったPendant名義の諸作を経てHuerco S.(Brian Leeds)が発表した『Plonk』は、その代名詞となったアンビエントから離れ、リズムに回帰したことでリスナーを驚かせた。しかし、たとえば1曲目の「Plonk 1」において、そのポリリズムが肉感的に躍動するよりも不定期に休止を挟み、背後にある不穏なアンビエンスへと融解していることに注目したい。実際のところ『Plonk』はアンビエントでもダンス・ミュージックでもない地点で(どこか居心地悪そうに)浮遊しているのだ。その混淆的な響きはBrian自身の運営する《West Mineral》や、関係の深い《Incienso》、《3XL》といったレーベルからのリリース、そしてDJ Pythonの《worldwide unlimited》からの諸作とも共鳴し、22年という年の不穏で複雑なムードを捉えていたように思う。(吸い雲)

14
ゆるふわギャング
GAMA
YRFW_LTD
ここ数年、トランシーなEP『GOA』のリリースやレイヴへの参加など、独自の道を開拓してきたゆるふわギャング。本作はその集大成と呼べるかもしれない。スピリチュアルな「Too High」や、リスナーとの対話性が高いエモーショナルな「Golden Night」「Tomodachi」など、アルバムを通して多面的。加えて「E-CAN-Z」や「Moeru」などではジャージー・クラブを取り入れ、ダンス・ミュージック・シーンとも親しい彼らならではのノリ方をリスナーに提案。コロナ禍への反動もあってか、ヒップホップ的側面を持つアーティストとレイヴ・シーンが交わり、音楽的にもアンビエントやダンス・ミュージックを取り入れる動きが活発だった2022年、ゆるふわギャングは直感的かつ誠実に積み上げた結果として、同時代性と高い説得力を獲得した作品を生み出してみせたのだ。彼らは本作を引っ提げ、レイヴを含むツアーを敢行。『GAMA』の熱気溢れる世界観を生モノとしても昇華した。(MINORI)

13
Beth Orton
Weather Alive
Partisan / Big Nothing
ロンドンのサックス奏者のアラバスタ・デプルーム、ニューヨークで活動するコンポーザーのシャーザッド・イズマイリー、Polar Bear / The Invisibleのメンバーでもあるトム・ハーバートなど、ジャズ・シーンに欠かせないプレイヤーを招いて制作された7枚目のスタジオ・アルバム。美しい静寂と品格をあわせ持つ本作は、ドラムにThe Smileのトム・スキナーを迎えた存在も大きかった。音数を抑えながら、独自の音色やパターンを引き出し、面々と演奏の調和を保つ。もはや、ジャズ・セッションの経験と感覚による職人技と言えるだろう。注意深く消え入るピアノ、そして彼女の幽玄なヴォーカルは、脆くもはっきりと陰影を帯びていた。トリップ・ホップの孤高のシンガーとして例えられることの多いベス・オートンだが、フォーク、ジャズと表現の架け橋を能動的に働きかけた作品だ。レーベルを多彩な面々の集まる《Partisan》に移籍して、初のセルフ・プロデュースを行ったのも頷ける。(吉澤奈々)

12
Lil Silva
Yesterday Is Heavy
Nowhere Music
UKベースとメインストリームを繋ぐプロデューサー/DJが12年をかけて辿り着いた初のフルアルバム。サンファやサーペンウィズフィートの生々しい歌声、オブスキュア・ソウルのサンプリングが生む高揚、そしてBADBADNOTGOODがはじき出すファンクネスまで、しなやかなブレンドの手さばきに魅了される。「To The Floor」なる曲タイトルは、2022年のダンスフロア回帰を象徴するフレーズといってさしつかえないだろう。明確な音のシグネチャーを持たない代わりに、かつて仮歌を入れていると必ず「誰が歌ってるんだ?」と聞かれたという自身の誠実さが伺える柔らかなヴォーカルが全編を包括している。ここ数年で多くのアーティストがコロナ禍の期間のメンタルヘルスを題材にするなか、本作も例外ではない。ジャケットに綴った文章で「昨日は重い」の後に「しかし明日は永遠だ」と付け加えているように、彼は実体験を経て、心の重荷を下ろそうと訴えている。(駒井憲嗣)

11
Stromae
Multitude
Mosaert / Universal
多文化の共生という「理想」は、当然ながらその背後に様々な軋轢も生み出してきた。一方で、グローバリゼーションの敷衍は、識者たちが危惧したような全面的均質化やローカルリティの完膚なき駆逐へは帰着しなかった。むしろ、現代はローカリティがかつてなかった複雑な姿容とともに復権した時代だともいえる。それはもちろん、ポピュラー音楽においてもそうだ。というより、ポピュラー音楽こそがそういったダイナミズムを最も鮮やかに、いち早く反映してきた存在だといえる。今作でストロマエが描き出した、軽味を帯びたツーリズム的なフォークロア志向と実存的な思索が混じり合った音楽(かつて母と旅した南米大陸と、父のルーツであるアフリカ大陸が地続きになるような音楽)は、グローバリゼーション後のローカリティの点在的なあり方が、リモート時代の想像力を得て果てしなく増殖していく、その最もドラスティックな例なのではないか。溌剌と憂愁。絶望と享楽。物理的な離散と再集合。「マルチチュード」と名付けられた本作は、単に「多数性」の活写に与しているのか、あるいはやはり、ネグリ=ハート的な意味での紐帯と、それによる闘争への期待も映しているのだろうか。(柴崎祐二)

10
Whatever The Weather
Whatever The Weather
Ghostly / PLANCHA
今年MVP級の活躍を果たしたロレイン・ジェイムスが、名義を変えて今作を発表したのには理由があるだろう。メイン・プロジェクトの曲には、アイデンティティについての批評が込められており、その喜怒哀楽は彼女の代名詞でもあるグリッチサウンドにも反映されている。それはある種、IDMという彼女の土俵の根底を批評するものでもある。Whatever the Weatherでは「どんな天気でも」というコンセプトが示すように、タイトルにはその曲のを表す温度が刻まれており、リスニング・ミュージックの様相を呈している。全天候型の重厚で煌びやかなアンビエントには彼女の音への拘りを感じさせ、メイン・プロジェクトとの違いを生んでいる。それはイングランドにおけるIDM延いてはブライアン・イーノから続くマナーに則った物とも言えるが、彼女はそれをシグネチャであるグリッチビートで破壊する。しかも、これまで以上の緩急で聴き手をより深い快楽へと導く。だから彼女は最高なのだ。(hiwatt)

9
Kendrick Lamar
Mr. Morale & The Big Steppers
pgLang / Top Dawg Entertainment / Aftermath / Interscope / Universal
コロナ禍やBLM運動の高まりの最中、稀代のリリシストがどこにいたのかという問いへの答えは、大方の予想以上に重苦しく、同時にカタルシスに満ちたかたちで示された。誰にでも、何と言われようがやらねばならない宿題がある。映画『マトリックス』でいえば、赤いピルを飲むような作業。ケンドリック・ラマーにとっては本作を制作し世に出すことが、まさにそんな作業だったのではなかろうか。タップダンスをやめて課題と正対することは簡単ではないが、彼はそうすることを選び、蓋をしてきた事実や感情と向き合った。婚約者のホイットニーやエックハルト・トールといった導き手の存在もあったが、何よりも重要なのは彼自身が一歩を踏み出したことだ。トラウマを克服せんと一歩を踏み出そうとする人々に、少なくとも勇気を与える作品ではなかったか。今作をもって古巣レーベルを卒業したケンドリックは、別の意味でもビッグ・ステップを踏んだのだ。(奧田翔)

8
ROSALÍA
MOTOMAMI
Columbia
スペインはカタルーニャ出身のロザリアが発表した『MOTOMAMI』は、過激と繊細を混合させたラテンポップスの進化形だ。ボレロ、レゲトン、フラメンコ、ポップスを自由自在に扱いながらも、彼女のヴォーカルは儚く、柔らかに包み込む。今作のロザリアは、誰も予想しないような、音楽の実験を楽しんでいるようだ。ドラムマシーンの上でバラードを儚く歌ってみたり(「HENTAI」)、レゲトンにジャズを融合したりと(「SAOKO」)、予想をつかせずに、おもちゃ箱のような驚きを与える。プロダクションにはファレル・ウィリアムス、ジェイムス・ブレイクが参加していたり、「LA FAMA」ではザ・ウィークケンドもスペイン語で客演していたりと、作品のスケールも大きい。同じラテンコミュニティの同胞=バッド・バニーが世界を圧巻し続ける中で、同様にロザリアがポップスの今年の顔となった事実は、実に自然な流れだろう。(島岡奈央)

7
billy woods
Aethiopes
Backwoodz Studioz
アーマンド・ハマーの活動でもお馴染み、NYのラッパー、ビリー・ウッズによるソロ作。そして重厚な力作である。Preservationによる予測不能で奇怪なサウンドに乗るウッズのラップで描かれるのは、人類が繰り返してきた戦争、侵略、人種差別をはじめとする闇の歴史。そこに現代のNYからの視点が入り、作品の時制、場所は入り乱れる。恐らくは、かなり綿密なリサーチと教養に基づいて作られたであろうこの作品が持つジャーナリスティックな視点もさることながら、それをフィクション的なある種のストーリーに乗せ、時には暗いユーモアすらも添えて綴っているところに、教科書的ではない、このアルバムの唯一無二の魅力がある。淡々としたドライなラップが全編を貫く中で、とりわけ、6曲目「NYNEX」のフックの強調や、8曲目「Heavy Water」から9曲目「Haarlem」への途切れない繋ぎなど、音としての展開も忘れ難い。(市川タツキ)

6
Big Thief
Dragon New Warm Mountain I Believe in You
4AD / Beatink
米国のフォーク/カントリーそしてロック音楽の歴史と繋がることと、それを現代のオルタナティヴな音として鳴らすこと。前者を担っているのがレンカーとミークであり、そして後者はリズム感覚に長けたベーシストであるオレアルチックそして全編プロデュースを手掛けたクリヴチェニアである、と本作は明確にした。それはフォーク・ミュージックの公共性を「ロック・バンド」で実践しているビッグ・シーフのひとつの完成であり、そこでこそレンカーは個人の空想や愛、誰かとの信頼やそれゆえの傷を歌い分かち合うことができる。2枚組のヴォリュームのなかでサウンドは多岐に渡り、歌と演奏はときに不安定な揺らぎを露にし、録音は生々しいタッチをそのまま残す。にもかかわらずこのアルバムにあるのは生きることの心許なさではなく、それを仲間と交感できることの喜びと確信であり、だからビッグ・シーフのワイルドで繊細なフォーク・ロック聴くわたしたちもまた、オルタナティヴな場所へ進もうとする人間を再び信じる気持ちを抱けるのである。(木津毅)
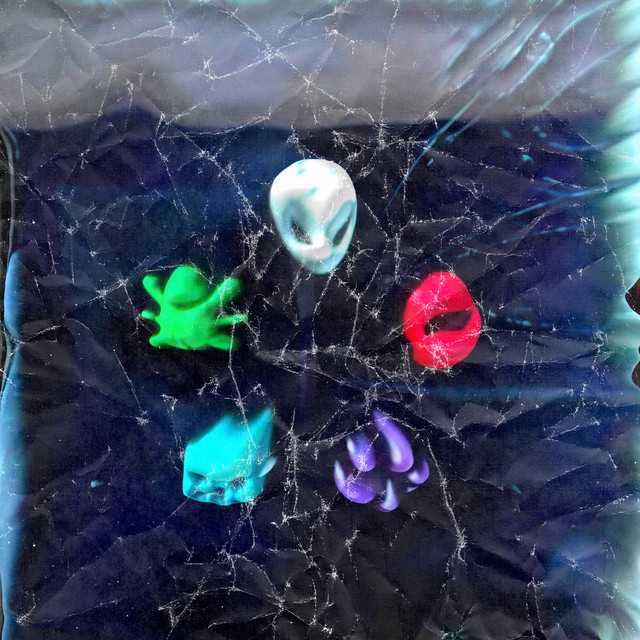
5
Two Shell
Icons EP
Mainframe Audio
加工されたキャッチーなヴォーカル・サンプルが強烈なインパクトを残す、1月リリースの高速ベース・ミュージック「home」は、未だ謎多きUKのデュオのユーモラスな側面を垣間見ているようで非常に興味深い1曲だった。そこから約半年後に発表された5曲入りのEPは、ジョイ・オービソンをはじめとするUKテクノやビッグ・ビート、ハイパーポップなどをミックス、UKのダンス・ミュージックによりフォーカスされたものになっている。本作に散りばめられた、それらのオマージュはノスタルジーを刺激するものになっているが、同時に随所に配置された、彼ら自身のシグネチャーでもあるサンプリング手法や超処理されたボーカルなどで発揮される持ち前のユーモアからは痛快な個性を感じ取ることができるだろう。UKダンス・ミュージックの過去と未来の歴史の連なりにTwo Shellが加わる、その始まりのような作品だ。(tt)

4
Björk
fossora
One Little Independent / Big Nothing
ビョークの肉声と地を蹴るビート、目新しさは少ないかもしれないが彼女の原点を模る音がある。サウンドを低音に着目したこと。たとえば、「Atopos」でのクラリネットによる高音の響きの少なさ、サスティンの短さはこもったような空間をつくり出し、そこには菌の繁殖に値する湿気の高さを感じさせた。アートワークには本作のコンセプトでもある“mushrooms”が写っている。こうして連想を膨らませることができるのは、視覚を通じても作品を披露する彼女の流儀があってのことだ。さらに、インドネシアで活動するGabber Modus OperandiのKasimynをフィーチャーした「Trolla – Gabba」。インダストリアル・ハードコアの荒く無機質なビートを、プリミティブな音色に変えてしまうのは、彼女のエモーショナルを込めた歌声に他ならない。常に新しいアーティストやビートを積極的に取り込み、ジェンダーや環境の問題に言及する姿勢。ビョークを突き動かす衝動を集結した意欲作だ。(吉澤奈々)

3
Wilma Vritra
Grotto
Bad Taste
暗い洞窟の中を、『きかんしゃトーマス』ばりのキュートな列車が進んでいく。くぐもったキックやハイハットに、「One Under」のリニアなクラリネットの響きが、そんな情景を再現する。Wilma Archurが生み出すストリングスが前面に出たビートはしばしば映画的と評されるように、聴き手にムードやイメージを強く喚起するもの。VRITRAの淡々とした語りのようなラップと相俟って、物語のサントラかラジオドラマを聴いているような感覚をおぼえる。低音を強調しないプロダクションやギターなどの生音を多用したサウンドは、マイクやウィキなどdrumlessとされる作り手との共通性も。だが、Wilma Vritraの構築性や楽器のメロディアスさに由来する不思議なポップネスは今までありそうでなかった。1、2分台の短いビートと、4、5分の「ソング」との配置には、彼らのポップとアルバムに対する明確な意図が覗いている。(髙橋翔哉)

2
Sudan Archives
Natural Brown Prom Queen
Stones Throw
音楽へのアクセス、あるいは音楽制作が容易になったこの時代、例えば自らの記号的なルーツを探求した作品が過去の権威的作品の不格好なトレースとなってしまったり、音楽的なジャンルの越境が意図せずとも表面的な搾取に止まってしまうケースは決して珍しくない。このような悲観的な状況把握そのものを軽やかに乗り越えた作品として、シンガーソングライターでマルチインストゥルメンタリストであるスーダン・アーカイブスによる2作目、『Natural Brown Prom Queen』は、わたしの2022年に強く記憶されている。黒人女性をときに縛り付けるR&Bという言葉から解き放たれたように自由なヴォーカル、音楽におけるセントリズムを打ち砕くようなヴァイオリンの響き、目くるめく展開に加え、曲間の数秒まで興奮剤と鎮静剤を仕込むほどのこだわりっぷり…….。要素を並べれば些か先鋭的に感じる部分があるかもしれないが、この矢継ぎ早に押し寄せる胸の高鳴りをポップと呼ばずに何と呼ぼうか。彼女が黒人女性としてのルーツを独自に掘り下げてたどり着いた全18曲は、あなただけが、わたしだけが秘めた可能性に触れるための、万人に開かれたプロムナードである。(高久大輝)

1
Charlotte Adigéry & Bolis Pupul
Topical Dancer
Bounty & Banana / Deewee / Calentito
ベルギーはフランス、ドイツ、オランダと国境を接する、EUの中枢機関を持つヨーロッパのヘソのような国だ。公用語も3種、地域圏も3つ、加えて移民が多いことでも知られており、外国籍の人口は全体の約12%。一方都市部では売春や劣悪な労働環境など改善の余地が残されているようだが、このシャーロットとボリスはまさにそんなベルギーはヘンクの移民の家系に育った。シャーロットはマルティニーク島の奴隷貿易でベルギーにやってきたナイジェリア系ユダヤ人、ボリスはマカオ出身の中国系。世界のフリンジだと思われてきたこうした複雑なルーツを持つ民族マイノリティたちが、ミソジニーや人種差別をテーマにした曲で快活にステップを踏み、躍動する。持たざる者たちと持つ者たちが逆転する世界線。かつてプリンスも夢見たであろう、世界のオセロがひっくり返る日がもうそこまで来ていることを実感する、未来への誓いのアフロ・ポップ・ファンク・ミュージックだ。(岡村詩野)

THE 25 BEST ALBUMS OF 2021

THE 25 BEST ALBUMS OF 2020
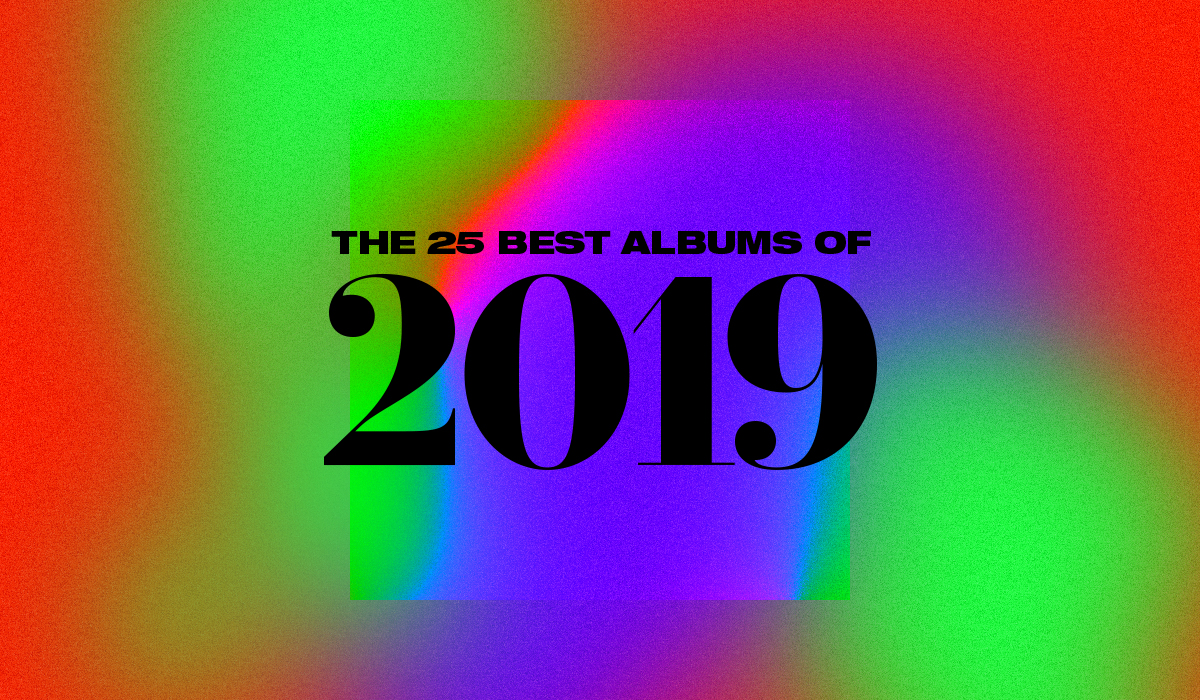
THE 25 BEST ALBUMS OF 2019

THE 25 BEST ALBUMS OF 2018
Text By Sho OkudaHitoshi AbeHaruka SatoKenji KomaiShoya TakahashiNana YoshizawaTatsuki IchikawaIkkei KazamaSuimokuFumito HashiguchiabocadoNao ShimaokahiwattttMINORIDreamy DekaTsuyoshi KizuShino OkamuraYuji ShibasakiDaichi YamamotoNami IgusaDaiki TakakuKoki KatoTetsuya SakamotoYasuyuki Ono
