欺瞞と愛に満ちた日々を進め
〜PJハーヴェイ アルバム・ガイド〜
その表現の領域はもはやミュージシャンたる枠組みを超えている。なのに、一方でどうしようもなく音楽家でしかない。同じように、オルタナティヴ・ロックの時代にセンセーショナルに登場したポーリー・ジーン・ハーヴェイは、約30年の時を経て、もはやロックという看板だけでは全く足りない作品を制作するようになっているが、不思議なことにエッジーでパンクという横顔は失われることがないままだ。コソボやアフガニスタンにおもむいて題材にしたり、イギリスが過去行ってきた暴挙ともいえる戦争に対して検証を促すかのように自国批判したりとテーマはより一層社会性を帯びるようになってきたが、では、肉体的トラウマ、女性性における内的葛藤などなど初期の作品において何かと取り沙汰されてきた、自傷的とも言える歌詞の切り口が一切消え去ったのかと問われれば必ずしもそうとは言い切れない。おそらく彼女の中ではそうして作品に落とし込んできたありとあらゆるジレンマ、怒り、焦燥、痛みなどが何も解決しないまま、30年が経過しているのではないかと想像する。
だから、ポーリーは進む。学びながら、振り返りながら、掘り下げながら、旅をしながら、ダンスをしながら……どこにも存在しえない解決の糸口を探すかのように、進む。その行動の一つ一つが、彼女を過去に囚われない、でも現実逃避もしない、未来に向けて生きる、でも安易なフューチャリストでもない、非常に冒険的で特異な存在にさせている。1969年10月生まれ。現在53歳。近年は過去作のデモ音源や未発表テイクなどを惜しみなく公開してきたが、今振り返ると、溜まっていた膿を出すような作業だったのかもしれない。約7年ぶりとなるニュー・アルバム『I Inside the Old Year Dying』のリリースを記念して、大胆でアグレッシヴなのにエレガントで気品もある言葉とメロディで欺瞞だらけの日々を突破するシンガー・ソングライター、ポーリー・ジーン・ハーヴェイ=PJハーヴェイの足跡をアルバムで辿ってみよう。(編集部)
(ディスク・ガイド原稿/天野龍太郎、井草七海、石田昌隆、岡村詩野、尾野泰幸、Casanova.S、木津毅、駒井憲嗣、高久大輝、髙橋翔哉、鳥居真道、吉澤奈々)
※文中でPolly Jean Harveyの片仮名表記に「ポーリー」「ポリー」とバラつきがありますが、筆者の表記をそのままにしてあります。
『Dry』
1992年 / Too Pure
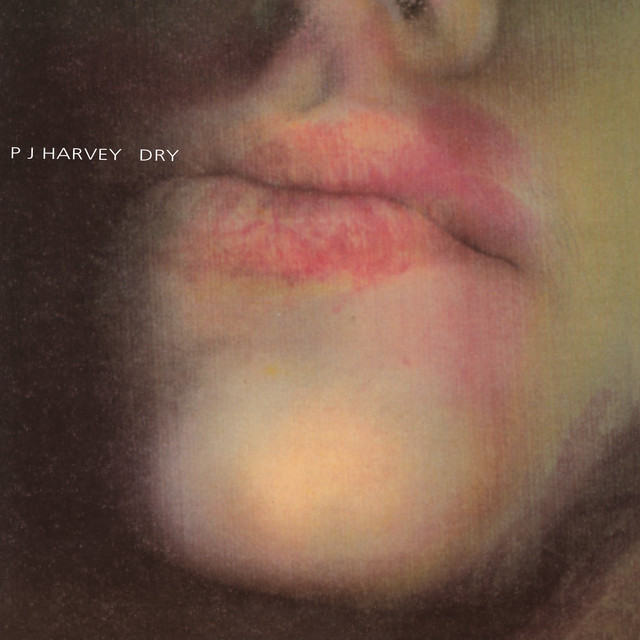
ブルージーでヘヴィなギターとフォーキーなサウンドを基調に、地の底から這い出てきたような湿り気と不穏さが同居した力強いヴォーカルがはじめに耳に残る。本作がカート・コバーンのフェイヴァリット・アルバムとして言及されたエピソードはあまりにも有名だが、同時代的なグランジ、オルタナ・サウンドとの接合というよりはむしろ、ビートを執拗に強調し、サウンド、リリックのフレーズ反復を多用した楽曲群から放たれるポストパンクの残り香を改めて聴くと強く感じる。
ドレスで着飾り男性の気を引こうとする女性の姿を“女性らしさ”が刻印されたドレスの着苦しさとともに歌った「Dress」、威圧的な男性との性的関係性を英国やアイルランドに点在する女性彫刻の名前を比喩として用いながら表現した「Sheela-Na-Gig」など、本作に収録された楽曲はセクシュアリティに由来する精神的/肉体的な痛みや、制約、欲望をモチーフとし、伝統的な“女性性”に縛られそうになる女性の姿やそれに対する批判、はぐらかしを表現している。しかし、それは全面的な否定や肯定に傾向したものではなく、むしろ固定化された“性”の在り方に対して揺れ動く人の姿を描いたもので、ポリー・ジーンの歌とリスナーの生を接続したのはそのような葛藤の表現であったのだと思う。 (尾野泰幸)
『Rid Of Me』
2003年 / Island

「フェミニズム・アルバム」と評される本作だが、当時彼女にその意図はなかったことは補足する必要があるだろう。確かに“社会的弱者”としての訴えは本作からあまり聴こえてこない。むしろ逆で、彼女は(男性を含む)すべてのリスナーに、自らの生と性の欲望への従属を、“心の渇き”そのものを具現化したかのようなスティーヴ・アルビニ・サウンドとともに、暴力的に要求するのである。
もちろん〈Lick my legs of desire〉のリフレインよろしく、「Snake」での進んで蛇を誘惑するイヴよろしく、性的主導権を握る描写を通じて、女性像を、与えられるのではなく主体的にもぎ取るものとして定義するのは今の文脈からすればまさにフェミニズム的だ。ただ一方で「Man-Sized」での“男性になろうとする”彼女や、男根主義を嘲笑する「50ft Queenie」、(あるいはボブ・ディランのカヴァーも)が強烈に発するのは、纏う役割としてのジェンダーの脆さを暴いた上で、男女の別やその窮屈さなどもはや凌駕し“何にでもなれる”PJハーヴェイという存在自体の生の自由さと、大胆不敵さだ。下世話ながら、気高い。それに比べて体裁で張り合うばかりの男たちのなんとつまらないことか、などとつい口をつきそうにもなるが。
ミニマルなアレンジとがっぷり四つのアンサンブル、何よりブルージーに声色を操る彼女の表現力にはサウンド以上に洗練の片鱗も。トリオ体制の終焉でもあり、バンドの中の彼女が“PJハーヴェイ”という人格に覚醒したターニングポイント的作品。(井草七海)
『To Bring You My Love』
1995年 / Island

PJハーヴェイという同名のトリオの解散後、つまりポリー・ハーヴェイのソロ・プロジェクトとしてのPJハーヴェイによる初作にして、U2やニュー・オーダーとの仕事でも知られるフラッド、盟友というべきジョン・パリッシュを共同プロデューサーに迎えてサウンド的にはこれまでより複雑になった、PJハーヴェイの出世作として名高いアルバムである。まず、魅力的なのはその緩急だ。荒く歪んだギターリフがフェードインするタイトル・トラック「To Bring You My Love」での陰鬱なオープニングから、大地を踏みならすようなドラムの響く「Meet Ze Monsta」へ。呻き声のような何かが散りばめられ、再び沈み込む「Working For The Man」から、歯切れのいいアコースティック・ギターの響く「C’mon Billy」へ……というような具合で、本作は大きくうねりながら、驚きと心地よさを運んでくる。そして、うねりの先に用意されているのは見事なクライマックスだ。ジリジリと燃えるスパニッシュ・ギターなどアレンジが光るラスト「The Dancer」にたどり着いたときに押し寄せてくる、えもいわれぬ高揚感。本作がキャプテン・ビーフハートの引用から始まることからも、この計算された、まるでリスナーを手のひらの上で踊らせるかのような構成は、きっとポリーの遊び心に依拠しているのだろう。ゴシックな世界観にどこか不敵な笑みの浮かぶ傑作だ。(高久大輝)
John Parish & Polly Jean Harvey『Dance Hall At Louse Point』
1996年 / Island
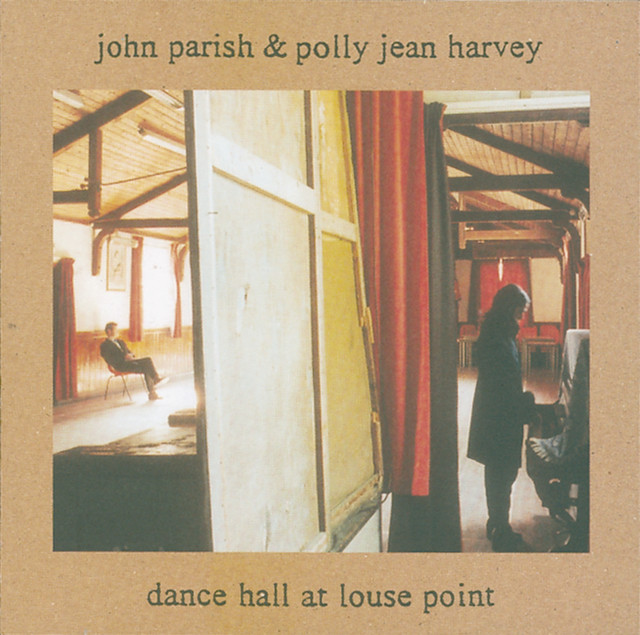
『To Bring You My Love』で高い評価を得たのち、PJハーヴェイが世に放ったのがジョン・パリッシュとのコラボ作『Dance Hall At Louse Point』だ。ハーヴェイにとってパリッシュは古い友人であり、かつてのバンドメイトという存在で、『To Bring You My Love』にはマルチプレイヤーおよび共同プロデューサーとして迎え入れられている。『Rid Of Me』がリリースされた後、パリッシュが音楽を担当した舞台を観劇したハーヴェイは、彼にこう尋ねた。「これと似た音楽を作ってくれない? そこに歌詞をつけても良い?」 これがきっかけとなり共同作業が始まったそうだ。
二人のイギリス人によって描かれたゴシック・アメリカーナといった趣のアルバムである。まずハーヴェイの歌唱、パリッシュおよびMick Harveyの演奏の生々しさが半端ではない。切れば血が出るようなサウンド・プロダクションだ。どすの利いた残響とでもいうべきか。その臨場感に気まずさを覚えるほどだ。ハーヴェイとパリッシュの連名によるこの勇猛果敢なプロジェクトを、ロス・ロボスにおけるLatin Playboysのようなものだと捉えてみると、その位置づけがクリアになるのではなかろうか。タイトルはウィレム・デ・クーニングの絵画「Rosy-Fingered Dawn at Louse Point」から取られたとの由。(鳥居真道)
『Is This Desire?』
1998年 / Island

1998年はハル・ハートリー監督の映画『ブック・オブ・ライフ』に出演と楽曲提供を行い、アーティストとして活動の幅を広げていた時期だが、今作ではJ・D・サリンジャー『バナナフィッシュにうってつけの日』、『愛らしき口もと目は緑』、フラナリー・オコナー『田舎の善人』、『河』、『生きのこるために』といった短編小説からインスピレーションを受け、様々なキャラクターを持つ女性の登場人物と彼女たちの物語に自己を投影。痛々しいほどに内省を強めてはいるものの、私小説的な視点から開放されたことによるものか、ある種の“吹っ切れ感”が全編に漲っている。
ポーティスヘッドを思わせる不穏なムードに引き込まれる「Electric Light」をはじめとして、トリッキー「Broken Homes」へのフィーチャリング参加を経て、ダークでエレクトロニックなプロダクションが支配するアルバムとして知られている一方で、ソングライティングの面でも、最大のヒットとなったシングル「A Perfect Day Elise」や近年のライヴのセットリストでも欠かせない「The River」など粒ぞろい。彼女が自宅で制作した4トラック・デモに吹き込んだヴォーカルが音源でもそのまま採用されており、その生々しさには抗いがたい魅力がある。世界的なトリップ・ホップ再評価の潮流はさておいて、自身の歌を獲得するために、キャリアの分岐点となった作品として重要度は増していると思う。(駒井憲嗣)
『Stories From The City, Stories From The Sea』
2000年 / Island

特に日本では顧みられる機会が少ないアルバムだがリリース当時、商業的にも批評的にも成功した紛れもない代表作、Y2K(9.11直前)のクラシックである。このアルバムがなかったとしたら、非礼を承知で言うと、彼女のキャリアは「90年代のオルタナティヴ・ディーヴァ」で終わってしまっていたかもしれない。ともあれ、PJハーヴィは新しいディケイドの始まりにこの『Stories from the City, Stories from the Sea』を置いた。ここでポリーが歌う“City”とはニューヨークのこと。ハル・ハートリー監督作『ブック・オブ・ライフ』(1998年)に出演するため同地に移り住んだ経験から曲が書かれている。プロダクションは前作までのダークなそれへの反動だといい、たしかにピアノやパーカッションなど、それまでになかった楽音に彩られている。多少はメロディ志向になっているものの、ただ、それらはポリーの陰鬱な世界に染め上げられている、と言うほかない。それよりも、やはり、深く伸びやかに響く声と無造作に掻き鳴らされるギターの生々しい音の方が、ずっと印象に残る。リスキーな方向転換ではある。ブルーズをルーツに男根主義的なロックの世界で女の(性的な)欲望を叫んだポリーは、ここで「これが愛だ」と喉から血が吹きだしそうな声で歌っているのだ。そう、このアルバムの主題は狂おしいほどロマンティックな愛である。「まるで現代のボニーとクライドみたいにまた逃走中」(「Good Fortune」)。しかし、それは男(そのアナロジーとしてのニューヨーク)への激しい憎悪も入り混じった、はちきれんばかりのクレイジーな愛でもある。「この世界は狂っている/私に銃をくれ」「あなたといる時、私は不死身/でも、この手にピストルが欲しい/ちがう土地へ行きたい」(「Big Exit」)。「人生がなぜこんなに複雑なのか理解できない/ここに座って、裸のあなたを見ている時は」(「This Is Love」)。なおレイディオヘッドのトム・ヨークが3曲で参加しているが、彼の参加は余計であると感じるので割愛した。それよりハイライトは「The Whores Hustle and the Hustlers Whore」だろう。「売女たちがハッスルし、ハスラーたちが売春する/多くの人々が愛に飢えている/この街は中心(core)まで裂けている」。これほど鋭い街の批評もない。(天野龍太郎)
『Uh Huh Her』
2004年 / Island

前作『Stories From The City, Stories From The Sea』が外の世界へ向けた眼差しだとすれば、本作は個の感情に入るようだ。Rob Ellisのドラムを除き、レコーディング、ミキシング、プロデュースなどすべてをポーリー自ら行った作品だが、内省的に塞ぎこむものではない。本能的に感じる抵抗や愛を歌う姿は『The Hope Six Demolition Project』で政治的な題材を取り上げる姿勢となんら変わらない気もするし、制作に向けてアーティストとして目指してきた位置がボブ・ディランやニール・ヤングだと答えていることも興味深い。すでにこの辺りからポリーの洞察は本質へと向かっていたのだろう。
ジャキジャキにリフを刻むシンプルな構成は、オルタナティヴに回帰した印象。8ヶ月に及んだツアーはギターをジョシュ・クリングホッファーが務めており、互いに剥き出しのピュアネスによってアート・ロックの緊迫性を高めていた。一方で、イノセントな魅力は歌詞に宿る。「Who The Fuck?」の<他の女とは違うんだ/私のカールはまっすぐにできない>、アルバム未収録のタイトル曲「Uh Huh Her」の<結婚しないで/あの娘と>など熱を帯びた本音が綴られている。特に「The Darker Days Of Me & Him」の<精神分析もない/悲しみもない><ピースを拾い集め/どうにかして続ける>という歌詞は繰り返される偏見への怒り、悲しみが滲んだ手紙のようだ。本作はポーリーのポートレイト作品でありながら、愛と問題をも投げかけている。(吉澤奈々)
『White Chalk』
2007年 / Island

2007年にリリースされた『White Chalk』は彼女のキャリアの中でも異色のアルバムなのではないかと思う。PJハーヴェイという名前を聞いて頭に思い浮かべるようなギターも突き刺すような声もここには存在しない。このアルバムから聞こえて来るのはピアノの音とファルセットを使いつぶやくように歌う彼女の声だ。それは長い間歌い継がれてきたトラディショナルなフォークミュージックのようにも聞こえ、部屋の暗がりで書き留められたノートの中の物語のようにも思える。作られた部屋の空気がそのまま残っているかのようにラフで、けれど親しみの持てるようなものではなく、ひんやりとしたホラーみたいな恐れがある。その空間は本当に魅力的で、抜け出すことが出来なくなるくらいにどうしよもなく引き込まれていってしまう。
そうしてぼんやり考える。まるでそうであるのが当然だというように、静かに深く時間が流れるこのアルバムの中のPJハーヴェイは個人を表現するというよりも彼女の内で発掘された物語を伝える語り手としての役割を担っているのではないかと。おおげさに言うと作品の中に彼女がいるような感覚で、その存在は音楽と共に漂いそうして次第に薄れて消える。それは誰が演じているのか気にすることのない映画のようなもので、彼女の表現が音楽と重なり空恐ろしくそして繊細で美しい空間を作り出していく。PJハーヴェイの暗く輝く魔法が最も素晴らしく封じ込められているのはひょっとしたらこのアルバムなのではないか? 聞く度に頭にそんな言葉が浮かんで来て、そうして心に確かな余韻を残していく。(Casanova.S)
PJ Harvey & John Parish『A Woman A Man Walked By』
2009年 / Island / Interscope

作詞と歌がPJハーヴェイ、作曲と演奏がジョン・パリッシュ、というアルバム。PJハーヴェイはそもそも19歳のとき、88年にジョン・パリッシュが率いるブリストルを拠点とするバンドに加わったことからキャリアが始まり、2017年の来日公演のときのバンドのひとりもジョン・パリッシュであった。音楽的に長い付き合いがあり、コラボ・アルバムは『Dance Hall At Louse Point』に続いてこれが2枚めだ。ジャケット写真は『Rid Of Me』を含めてPJハーヴェイのヴィジュアルの傑作を撮り続けてきたマリア・モクナッツによるもので、2枚のポートレイトの人物の大きさの不揃いぶり、ジョン・パリッシュの写真の無駄に空間を入れているかのようでかつ足下が切れているところ、PJハーヴェイの頭上の切り方など、見れば見るほど斬新で惹きつけられる。PJハーヴェイは、内なる心の叫びのようなものを歌っていた初期の3枚と、10年代になってからコソボ、アフガニスタンを旅して、社会の不条理に目を向け、決して明るくはない現実に囲まれて暮らしている肌触りのようなものを表現するようになるところが凄すぎるので本作はスルーされがちだが、改めて聴くとすでに長いキャリアを築いていた時期でありながら、90年代のグランジ/ローファイな肌触りを瑞々しい感覚のままキープしていて、ふたりのコラボで世界のポイントを発見していく姿が見えてじつに美しいと思う。(石田昌隆)
※Apple Musicでは配信なし
『Let England Shake』
2011年 / Vagrant / Island / Def Jam

イングランドが戦争で繰り返してきた暴力と殺戮。PJハーヴェイとして歴史と政治を強く主題としたはじめての作品だが、それは知的に構築されたコンセプトというよりも、やはりどうしようもなく彼女の内側からやって来たものである。「わたしはイングランドで生きて、死ぬ」――国土に対する愛着と、国家がおこなってきた暴虐に対する怒りとの間の葛藤とどう向き合うのか。そうした本作の複雑なテーマを生々しく扱えたのは、ポーリーがずっと自分の内面をえぐり出してきたからだ。そして、だからこそ本作で彼女は大戦にまつわる歴史や英国のトラッド・フォークを音楽に織り交ぜて豊かな外部性を獲得した。とくに大戦の生存者から話を聞いた経験はフォークの口承性を含ませることになり、どこかポリフォニックな語りをもたらしている。戦車が土を耕し、その土には愛国者たちや犠牲者たちの大量の血が染みこんでいる……死者たちの声をもここでポーリーは憑依させる。だが、ふくよかな管の鳴り、不意に優しいメロディをなぞるギター、躍動するリズム、そしてポーリーのいつになく透明な歌声は聴き手を沈みこませない。自分たちがその歴史の先に生きていることを意識させ、考えさせ、だけど踊らせ、心身ともに揺さぶりをかける。それは重いテーマを前にした彼女自身や聴き手を硬直させずに、動かすためだろう。歴史は繰り返す。ならば、いまわたしたちにできることは何なのか? 引き裂かれた愛とともに、自分自身を揺さぶり続けるための音楽だ。(木津毅)
『The Hope Six Demolition Project』
2016年 / Island

このアルバムは、前作『Let England Shake』のフォーク・ロック〜チェンバー・ポップ路線を引き継ぎつつ、シンガーソングライター寄りな作風から大所帯のバンドによる息遣いの多さや有機的な繋がりにスケールを広げたものといえよう。ただその多幸感や祝祭感あふれる音楽はライヴでこそ最大効力を発揮するものでもある。2017年の来日公演では、10人編成のバンドでありながら技巧を披露するプレイヤーはひとりもおらず、あくまで観客が音楽の主体であることを示していた。複数のホーンとギターとコーラスがユニゾンした和音と、2台の太鼓の鳴りはひと繋がりのソニックとなり空間を満たした。YouTubeで「The Wheel」のライヴ映像を観てほしい。今でもフルセットの映像を探して観ては、ハーヴェイの気迫とバンドの欣然たるヴァイブスに負けて泣く。アルバムの主題は、アフガニスタン、コソボ、ワシントンD.C.への取材旅行でツアーガイドから聞き知った事実や歴史的物語の伝承である。開発事業のために家を追われた数千の人びと、数年後には撤回される公約、子どもの大量失踪。権利と土地と金を食い荒らし、後片付けもせず去っていく。それらは貧しく最悪な現状を改善するための政策と結果らしい。そんな世界中の紛争や開発における「アメリカ」という国家の役柄を浮き彫りにするアルバムだ。話を聞くものと伝えるものという主体と客体の共在。ガラス張りのスタジオで録音されたという逸話での、見るものと観られるものという主体と客体の共在。だがやはり彼女たちの音楽の主体は聴き手なのだ。作品が糾弾する問題に視線を向けることに意識が向きがちだが、その一方でただ音楽に身を任せて身勝手に歌い踊ることも促してくれる。(髙橋翔哉)
※配信なし
『I Inside the Old Year Dying』
2023年 / Partisan / Island

昨2022年8月にポーリー・ジーン・ハーヴェイは2冊目の詩集『Orlam』を刊行している。ポーリーが生まれ故郷であるイギリスは南西部のドーセット地域の方言をマスターするため8年かけて書かれたもので、実際に今は殆ど使われていない方言を使用しているのが大きな特徴だ。9歳の少女──それはかつてのポーリー自身でもあるのだろうが──の目を通して、田舎の澱みない風景と、そこに潜んだ恐怖を描いているようで、方言がなかなか理解できない私でも、自身の体験と学びを通じて英国の伝統的なバラッドへの試み、アプローチをも感じ取ることができた。当初、ポーリーはこの作品を演劇化することを希望していたが、結局はジョン・パリッシュとフラッドというお馴染みの二人の力を借りて3週間ほどで本作を完成(アダム“セシル”バートレット、俳優のベン・ウィショーも参加しているそう)。したがって、本作の歌詞もところどころにドーセットの方言が混ざっている。例えば1曲目「Prayer at the Gate」にある“Speak your wordle to me”という一節、この“wordle”はドーセットの方言で“world”を意味するそうだが、その中に“word”という言葉もまた含まれていることに気づいた時、バラッドという、名もなきある一人の個人の物語が言葉伝いに世界へと広がっていく過程を実感する。万事がこんな感じで全ての曲においてドーセットの原風景が時代と場所を超えて“伝承されて”いくわけだが、それをただ長閑なフォークにするわけでもなく、ポーリー自身がフィールド・レコーディングで採取した音源を、それもプログラミングしてから鍵盤でその音を弾いてみるようなアナログな作業によって取り込みながら仕上げられているのが面白い。だからサウンド自体は奇妙にゴツゴツとしていたり靄に包まれているようだったり歪んでいたりするし、ポーリーの歌も幼女がオペラを歌っているように甲高かったり泣いているようだったりと、まるで幻想的で少々ホラーな舞台を観ているかのようだ。過去2作品のようなヒリヒリとしたメッセージは直接的には出ていないが、バラッドがそもそも政治や社会を写す鏡のようなものだったことを思うに、本作もかなり内包的にポリティカルと言えるのかもしれない。ポーリー、気がつけば誰の追随も許さない、とんでもなく進取の気性に富んだ表現者になっている。(岡村詩野)
Text By Masataka IshidaRyutaro AmanoKenji KomaiShoya TakahashiNana YoshizawaMasamichi ToriiCasanova.STsuyoshi KizuShino OkamuraNami IgusaDaiki TakakuYasuyuki Ono
関連記事
【FEATURE】
「ポーリーは最初からどのようなことをしたくて、それをどうやってやりたいのかが明確に分かっていた」
PJハーヴェイを初期から支えるプロデューサー
HEAD インタビュー
https://turntokyo.com/features/head-pjharvey-interview/
【FEATURE】
PJハーヴェイでお馴染みのジョン・パリッシュと再び組んだ
『Designer』は思考と幻想の間をフラットにするか。
ニュージーランド出身のオルダス・ハーディング、新作を語る
https://turntokyo.com/features/interviews-aldous-harding/
