「現代音楽」の先へ──《New Amsterdam Records》がつくる作曲家たちのエコシステム
インタビュアー:レーベルを立ち上げたきっかけは何ですか?
ジャッド・グリーンスタイン:それは簡単です。私たちのシーンには他にレーベルがなかったのです!
(mental_floss Blog » How to Start a Record Label, with New Amsterdam Records)
ジャッド・グリーンスタイン、サラ・カークランド・スナイダー、ウィリアム・ブリテルの3人は、クラシック〜現代音楽の教育を受けた人間たちの新たな挑戦をサポートできるようなレーベルを作ろうと思った。レーベルの名前は《New Amsterdam Records》。創立したのは2008年のことだった。このレーベル以前にも、例えばポスト・ミニマル・ミュージック以降の現代音楽シーンをリードするバング・オン・ア・カンの面々が設立した《Cantaloupe Music》にもジャンル混合の側面はあった。しかし《New Amsterdam Records》は、どちらかといえば20世紀的な現代音楽と近しい《Cantaloupe Music》よりも、最新のインディー・ロックやエレクトロニックミュージックにアプローチするようなレーベルであり、《Warp》、《4AD》、《Brainfeeder》、《Rough Trade》の横に並べたくなるような存在だ。
このレーベルの作品を一聴すれば、その越境性に驚かされることだろう。ジャズとクラシック〜現代音楽のもっともモダンな融合体であるダーシー・ジェームズ・アーグズ・シークレット・ソサエティ、現代音楽を突き抜けてアルカに肉薄するダニエル・ウォール、人間の声の可能性を追求するルームフル・オブ・ティース、そしてカニエ・ウェスト(現:Ye)をも魅了するボーカリスト/作曲家、キャロライン・ショウなど、際立った才能が目白押しだ。設立から17年を経た今も作品の質は年々向上し、停滞感は一切ない。《New Amsterdam Records》の存在感には、老舗レーベル《Nonesuch》も着目しており、2019年にパートナーシップ契約を結んで以来(共同声明はこちらNew Amsterdam − NewAm & Nonesuch)、“New Amsterdam / Nonesuch”としていくつかの作品をリリースしている。その中にはダーティー・プロジェクターズの新作『Song of the Earth』を含んでおり、どの作品も極めてクオリティが高い。
ただ、21世紀になってもクラシック〜現代音楽とポップ・ミュージックの間には独特の距離感が残っているようだ。以前、《New Amsterdam Records》の象徴のような存在だったyMusicの結成についてインタビューしたとき、メンバーのCJ・カメリエリが以下のように答えた。
「僕たちが“インディー・ロック”に関わりはじめた当時、先進的なバンドの中で、オーケストラの楽器をもっと使用していこうという強い動きがありました。それを通して僕たちが課題として発見したのは、ただオーケストラの楽器を演奏するだけではだめだということでした。オーケストラのミュージシャンは、バンドと歌を演奏することに慣れていなかったし、異なったジャンルを見下す傾向がありました。僕たちはそういったミュージシャンたちとは違い、インディー・ロックが大好きでしたから、もっと良い形で彼らのサポートをできた等と思い、yMusicを結成することになりました。」
(『ラティーナ』2017年3月号「インディー・クラシックとその周辺の注目のシーン」)
yMusic所属メンバーたちは、今やテイラー・スウィフトやロード、サブリナ・カーペンターといったメインストリーム・ポップから、ボン・イヴェールやアノーニ・アンド・ザ・ジョンソンズ諸作に客演しながら、チェンバー・ミュージックとポップ・ミュージックの関係をアップデートし続けことで、そのような状況を変えようと戦っている。
《New Amsterdam Records》は活動形態もユニークである。サラ・カークランド・スナイダーはレーベルのポリシーについて以下のように説明している。
「アーティストがマスターの録音を保持できるようにすること、アーティストと“契約”するのではなくプロジェクトごとに作業すること、アーティストにアルバムからの売上の100%を与えるビジネスモデルです。」
(Sarah Kirkland Snider’s Mass for the Endangered; Call to Action to Save Planet — CLASSICAL POST)
非営利団体として音楽レーベルを運営する目的は、優れた音楽を作ったアーティストたちがしかるべき権利を持ち、報酬を得ることだ。一言でいえば、音楽をめぐる健全なエコシステムの構築と言えるだろう。設立者の3人自身が大学院修了後に居場所を模索し辿り着いた答えであった。自分たちのような苦労を下の世代にさせないために、コミュニティを作ること。そういった志が、レーベルの特徴的な運営方針を決定した。
また、《New Amsterdam Records》は、初期キャリアの音楽クリエイター向けのマスタークラス/ワークショップ・プログラム「Composer’s Lab」も運営している。ラボを率いているのはウィリアム・ブリテルであり、内容はジャンル越境的な作曲方法の考察、共同リスニングセッション、参加者の作品のグループディスカッションがあるとのこと。21世紀の音楽産業システム、基本的なミキシング/制作技術、感情的・芸術的・財政的な持続可能性戦略についての詳細な議論が、Zoomを介して実施される(詳細はこちらNew Amsterdam Records – Composer’s Lab)。
レーベルが音楽家のための環境構築や、教育を実施し、設立者たちが持つ知見をシェアし、それらをシステムとして確立させることは並大抵な苦労でできることではない。今の時代、どの国も音楽に限らずカルチャーの存続は難しい中で、確かな何かを残すために知恵を絞るという、その振る舞いにはリスペクトを禁じ得ない。
作品紹介
NOW Ensemble『Awake』(2011年)

《New Amsterdam Records》のルーツにクラシック〜現代音楽があるからといって、その音楽性にどこか大仰で難解なイメージを持ってはいないだろうか。それなら本作の冒頭曲「Change」を聴いてみるといい。元々ヒップホップ・プロデューサーを目指していたというジャッド・グリーンスタインのペンによるこの楽曲では、フルート、クラリネット、エレキギター、コントラバス、ピアノという特殊な編成のアンサンブルだからこそ持ちうる、華やかでポップなインストゥルメンタル・サウンドを味わえる。特にソリッドなギターの音色からは、このレーベルがインディー・ロックと親和性があることがわかるだろう。これが21世紀のチェンバー・ミュージックなのだ、というプライドがそこにはある。
Roomful of Teeth『Render』(2015年)
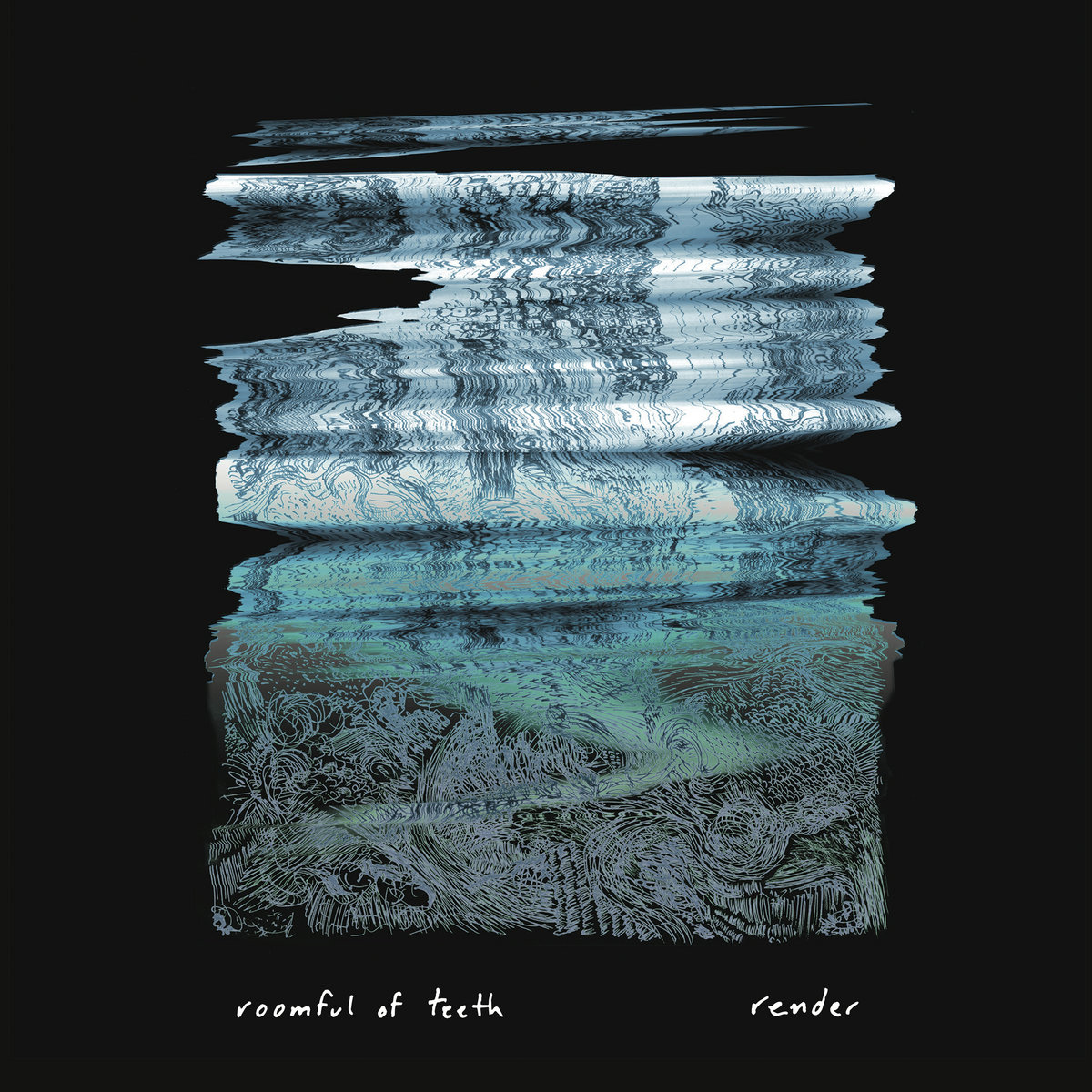
2009年にブラッド・ウェルズによって設立されたこのボーカルアンサンブルは、人間のボイス/ボーカル表現を拡張し続けており、メレディス・モンクやビョークといった先人たちが追求してきた領域を深く、広く掘り下げる。クラシック〜現代音楽といえばベルカント唱法、と思う人もいるかもしれないが、彼らはポップス的な唱法も積極的に取り入れるし、咳払いでさえも音楽化する。珠玉の名曲「High Done No Why To」からはブライアン・ウィルソン的なコーラスを聴くことができ、至高のボーカリゼーションが持つ圧倒的な迫力を味わってほしい。
Sarah Kirkland Snider『Unremembered』(2015年)

10代のころ、PJハーヴェイ、スリーター・キニー、リズ・フェアといったミュージシャンたちに憧れていたサラ・カークランド・スナイダーが、フォーク・ミュージックとクラシック〜現代音楽の間を行き来するような作品としてリリースしたのが本作だ。マイ・ブライテスト・ダイヤモンドとしても知られるシャラ・ノヴァやDMスティス、パドマ・ニューサムといった面々の声の力を借りながら、繊細かつダイナミックなアレンジメントを施したオーケストラ・サウンドは極めて魅力的で、自身を初期ドビュッシーとジョニ・ミッチェルの間のどこかに位置づけていたのも頷ける。
Darcy James Argue’s Secret Society『Real Enemies』(2016年)

ビッグバンドのカッティング・エッジだったダーシー・ジェームス・アーギューが2016年にリリースした本作は、アメリカ民主主義の陰謀について広範囲に渡る入念な調査によって書かれた同名の書籍から強い影響を受けて作られた。ジョン・F・ケネディやジョージ・H・W・ブッシュ(父)、フランク・チャーチ上院議員をはじめ、数多くのボイスサンプルが引用されているのは、その書籍のコンセプトを踏襲しているからだ。アルノルト・シェーンベルクの12音技法からシンセファンクまでバリエーション豊かな作曲によって彩られたサウンドは、20世紀のアメリカにフォーカスしており、極めてコンセプチュアルな世界観を形作っている。
Daniel Wohl『État』(2019年)

クセナキスやシュトックハウゼンをはじめ、20世紀の現代音楽はそもそもエレクトロニックミュージックのボキャブラリーを備えていたし、生楽器を用いながらもインダストリアルな音色を響かせていたから、ダニエル・ウォールのような才能が現れるための土壌があったといえる。とはいえ、それが初期のアルカと並べてもなんら遜色のないサウンドだったということは、やはり驚きに値する。しかもそこには細やかなセンチメンタリズムも散りばめられている。演奏にはyMusicの面々が参加し、プロデュースはサン・ラックスのライアン・ロットが担当している。間違いなく、このレーベル最高の成果物のひとつだ。
Caroline Shaw, Attacca Quartet『Orange』(2019年)

ルームフル・オブ・ティースのメンバーであるキャロライン・ショウは、ボーカリストであるだけでなく、ピューリッツァー音楽賞/グラミー賞を受賞している作曲家であり、カニエ・ウェスト(現:Ye)の諸作品にも起用される、間違いなく現在のクラシック〜現代音楽のフィールドで抜きんでた存在だ。そんな彼女が、ルネサンス音楽からミニマル・ミュージックまで幅広いレパートリーを持つ世界屈指のアンサンブル、アタッカ・クァルテットと組み、自身の溢れんばかりの創造力を存分に発揮した本作はグラミー賞を受賞。組曲「Plan & Elevation」で聴ける卓越した演奏は、ぜひ大音量で体感してほしい。
yMusic『Ecstatic Science』(2020年)

yMusicに所属するメンバーたちが現在のUS音楽シーンにどのような形で貢献しているかを知りたければ、例えばDiscogsでリサーチするのが手っ取り早い。ここまでダイレクトにポップ・ミュージックへ影響を与えているクラシック〜現在音楽出身のアクトは、2000年代以降だとオーウェン・パレットくらいではないだろうか。そんな彼らがこのレーベルからリリースした、今のところ最後のアルバムが本作である。確かな技術で紡ぎだす音色のリフレインをトリガーにすることで成立するサウンドは、ポスト・ミニマル・ミュージックにおけるひとつの模範解答だ。滑らかに放物線を描くように柔らかく響き渡る不協和音からは、前衛ではなく、ユーモアと自由があふれ出す。
Wild Up『Julius Eastman, Vol. 1: Femenine』(2021年)

近年、アーサー・ラッセルとも繋がりのあったブラッククィアの音楽家、ジュリアス・イーストマンの再評価が著しい。ロレイン・ジェイムスが作品でオマージュを捧げ、ブラッド・オレンジことデヴ・ハインズが楽曲を演奏しているなど、彼の影はそこかしこにちらついている。その再評価の波の中で、もっとも真正面に彼の楽曲に挑んでいるのが、このワイルド・アップだ。ミニマル・ミュージックの系譜にその名を連ねるジュリアス・イーストマンのサウンドは、どこかストレートで、時に荒々しい音色を伴った執拗な反復が特徴的だが、そのアグレッシブな楽曲群をワイルド・アップは完璧にモノにしており、その激しさと同居する美しさを見事に表現してみせた。
William Brittelle『Alive in the Electric Snow Dream』(2024年)
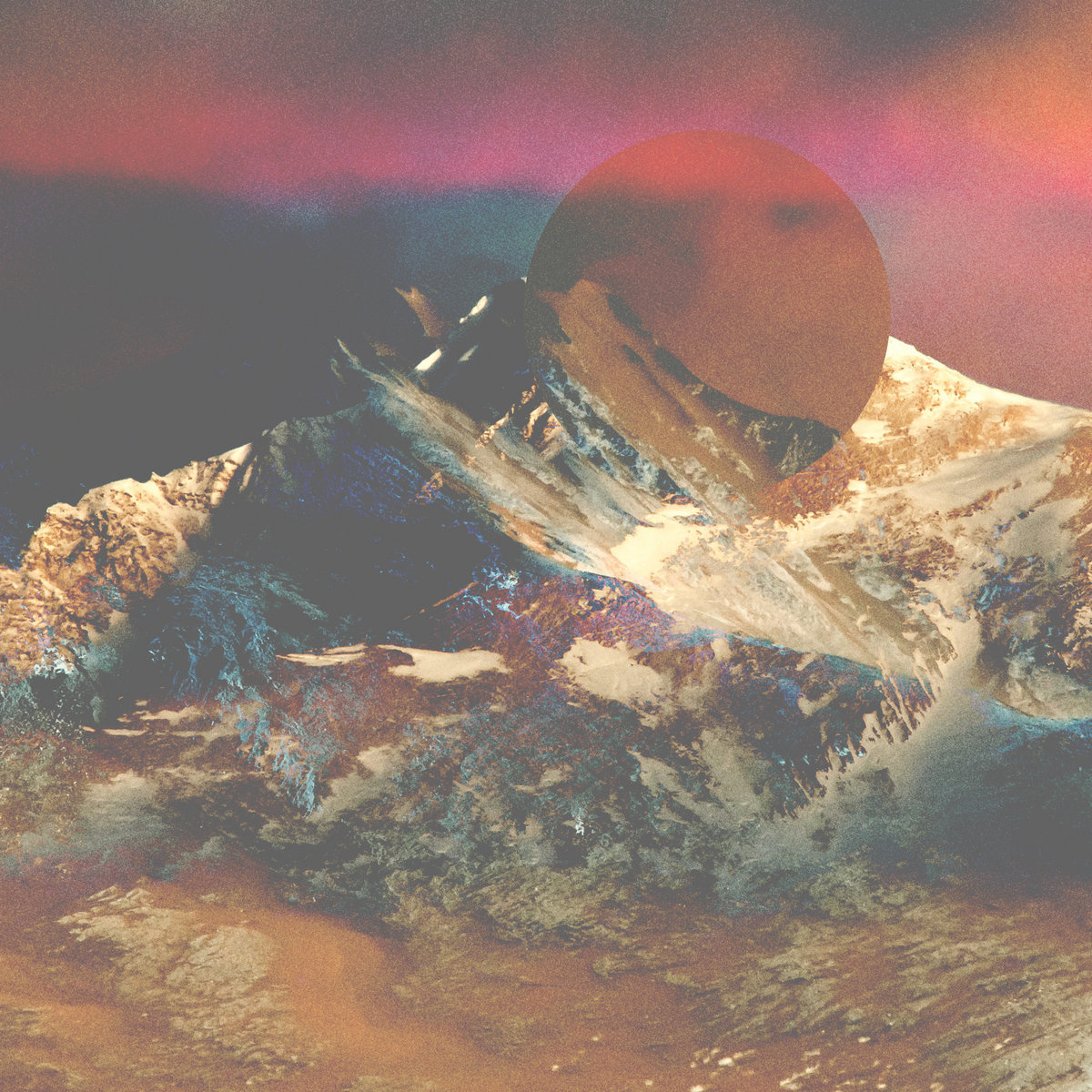
レーベル設立者のひとりであり、革新的な作品をリリースし続けているのがウィリアム・ブリテル。エレクトロニクスとアコースティックの区別なく、すべての音色が断片のままコラージュ的に配列され、切なく煌めきながら、殺伐とした風景を照らし出す。現代音楽的なボキャブラリーをベースとするサウンドの根幹を担うのはメトロポリス・アンサンブルで、自身はパーカッションやエレクトロニクスを担当、サックスには現代ジャズの寵児、イマニュエル・ウィルキンスを呼び寄せた。その混沌としたサウンドをまとめあげるのは、ボン・イヴェールやロウ、エス・キャリーを手がけてきたミキシングエンジニアのザック・ハンソン。クラシック〜現代音楽の現在と未来を照らす傑作。
Dirty Projectors, David Longstreth, stargaze『Song Of The Earth』(2025年)

《New Amsterdam Records》は2000年代に隆盛を誇ったインディー・ロックの刺激を大いに受けている。そのシーンのなかでもっとも著名なロックバンドがダーティー・プロジェクターズだった。だから、オーウェン・パレット、アイスエイジ、ジュリア・ホルター等と仕事をしてきたベルリンのアンサンブル、s t a r g a z eとのコラボ作をこのレーベルからリリースしたことの意味は大きい。クラシック〜現代音楽のメソッドが活きたメロディーラインを聴いて、デヴィッド・ロングストレスの才能の底知れなさに改めて驚かされる。本作は決して彼のサイドワークスなどではない。
(文・選盤/八木皓平)
Text By Kohei Yagi
関連記事
【INTERVIEW】
「作ったものが独自の生き物となる」──6年振りとなる新作『Something in the Room She Moves』について、ジュリア・ホルターに訊く
https://turntokyo.com/features/julia-holter/
【REVIEW】
Loraine James『Building Something Beautiful For Me』
https://turntokyo.com/reviews/building-something-beautiful-for-me-loraine-james/
