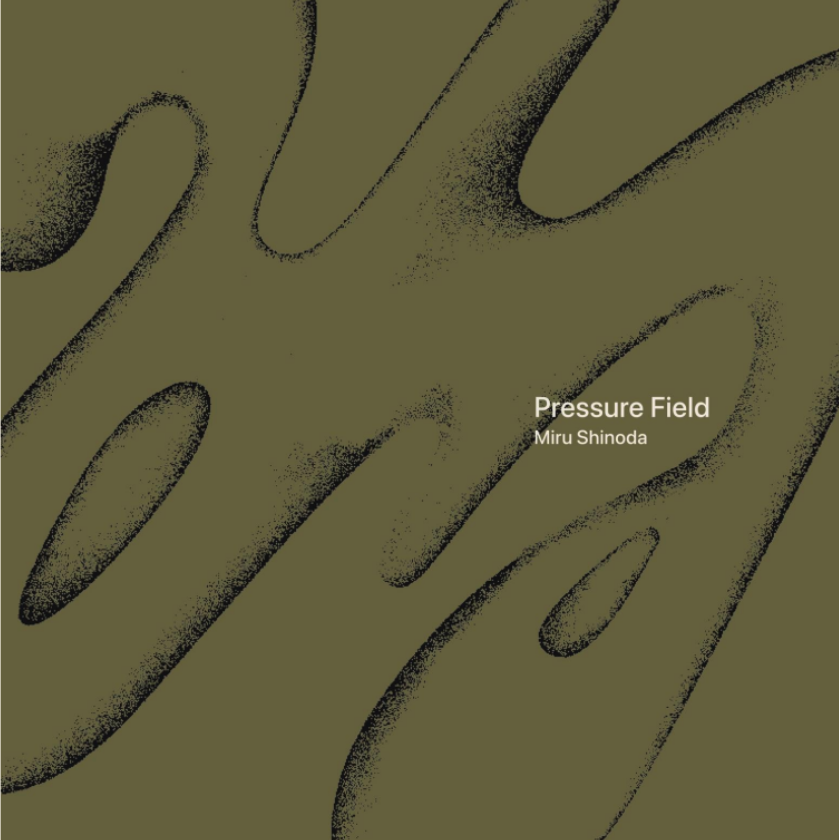サイン波が繋ぐ日本の電子音楽史と、音の快楽主義
篠田ミル 最新ソロ・アルバムを語る
大衆的な音楽だけが力を持つのだろうか。今回の取材を通して、私はその問いを深く考えた。例えば、地域に根付く伝統音楽は、祭礼やコミュニティの結束に大きな役割を果たすものであり、基本的に大衆に向けられたものではない。南方の離島で伝統音楽を継承する私の友人は、その魅力を発信しようとしても、島外の大衆に向けてはなかなか伝わらないと嘆いていた。しかし、このような音楽の価値を単一の基準でシュリンクすべきか? ニッチと揶揄される音楽であっても、世界のどこかの誰かに雷撃のような衝撃を与えうる。そんな中で、ジャーナリズムには、より一層の真なる熱意が求められる。
私が熱意を向けるのは、2000年代の国産エレクトロニカだ。欧米の電子音楽家からの再評価はここ5年で活発化し、メディアもその動きを盛り上げている。しかし日本国内では、当時のレジェンドである池田亮司や蓮沼執太らは現役で活躍している一方、活動を止めた者や惜しくも亡くなった者もいる。加えて、若手プレイヤーの台頭が少なかったことも、盛り上がりを制約した要因のひとつだ。そのような状況で、篠田ミルは『Pressure Field』を持って現れた。
1992年生まれの篠田ミルは、2015年にyahyelのメンバーとしてデビューして以来、バンドでの活動以外に、様々なプロデュース・ワークやコラボレーションでも実績を重ねながら、音楽家としてデビュー10周年の今年、初のソロ作品をリリース。彼がこよなく愛する電子音楽への愛が結実したものだが、特に1990年代以降のIDMや、2000年代のエレクトロニカに標榜したもので、海外のものはもちろん、特に先述した国産エレクトロニカへの憧憬を持ったものだ。ただ、単純なリスペクトと引用をしたわけではなく、彼のマニアックな視点から独自性を目指している。加えて、プロテスト運動にも熱心な関心を持ち、積極的な活動をしてきた篠田だが、国内外の情勢からローカルな社会問題に対する彼の思考や憤怒、悲哀、それらに対するシニカルな視点、市井の人としての実景、これらのテーマを電子音楽を通していかに表現したのか。『Pressure Field』が、このジャンルにおける新たなメルクマールとなる理由は、本稿に詰まっている。
(インタヴュー・文/hiwatt)
Interview with Miru Shinoda
ブリアルを通して紐解く『Pressure Field』
──まず、『Pressure Field』は既に何度も聴かせていただいて、とても素晴らしい大好きな作品です。
篠田ミル(以下、S):ありがとうございます。
──篠田さんが《TURN》に寄稿したブリアル論考が素晴らしい原稿で、本稿をお読みの方は、そちらも読んで頂きたいのですが、その論考が今作を聴く上でかなりヒントになりました。その中で、クラックルノイズ(レコードノイズに代表される微細なノイズ)について言及されていましたが、1曲目の「Big Site」では、全編を通してレコードノイズを聴くことができます。やはり、あれは彼の影響があるんですかね?
S:そうですね。影響もありますが、あれはギリギリまで入ってなくて、マスタリングをしてもらっている作業中のWax Alchemyさんにお願いをして、本当にその場で録って入れてもらいました。やっぱりクラックルノイズを入れると、レコードっていう音響メディアのクラックルノイズが持つ意味みたいなことに意識が行きますし、コンセプトには無かったので、ギリギリまで入れなかったんです。けど、あのクラックルノイズを入れることで、もうちょっと音響的なランダムネスを取り入れたいってなって。
──最後に入れたんですね! とはいえ、最初からノイズがある前提のような楽曲に思えて、ノイズがビートの一部に溶け込むような瞬間もあって、まさにそのランダムネスが完成度を高めていると思います。同曲の終盤に、ハサミみたいな音が聞こえるんですけど、そこからはブックスやマトモスみたいな、ミュージックコンクレートへの意識を感じたのですが、いかがでしょうか?
S:自分が今回の作品でやったのは、いわゆる狭義の電子音楽だという意識ではあるんですけど、ミュージックコンクレートも凄く好きです。次の作品というか、今作以降で取り組みたいなと思って、今まさに研究中です。
それこそ、《EYESCREAM》っていう雑誌の企画で、自分が今ハマっている盤を2枚紹介することがあったんですけど、そこで自分が挙げたのが、ブリアルが今年出した『Comafields / Imaginary Festival』と、あとリュック・フェラーリの『Presque Rien n°4』でした。今すごい自分の中でミュージックコンクレートがアツいんですけど、近年の長尺作品を作るようになったブリアルも、ミュージックコンクレートとして聴けるなって感じていて、その辺への意識はありますね。
──「Big Site」というタイトルは、どういう意図で命名されたんでしょうか?
S:この曲を作ったのは、《by this river》(篠田が松永拓馬らと共催したイベント)で、自分がライブをするってなった時に、一発目でアテンションを取れる曲を作ろうと思って、サイン波をポンと置くところから作り始めました。《by this river》って野外でやってるんですけど、サイン波って自然界にない音なので、野外にポンとサイン波を置くと、異物というか人工物が急に現れたみたいな感じになるな、というアイデアからこの曲は組み始めました。
今回の自分の作品全体に言えるんですけど、普通のバンドなんかの(生楽器を使った)録音作品って、何かしら実際に世界で鳴った音があって、それをマイクなりで録音して、録音芸術として組み立てていきますよね。けど、今回ってほぼ実際の世界で鳴ってる音を使っていないんです。例えば、PCの中のソフトシンセで作ってる音は、実際に世界で何かが振動した音ではないし、あるいはアナログシンセサイザーとかで作ってる音も、ライン録音でデジタル変換されてPCに取り込まれるので、実際には鳴ってないなと思って。そうなった時に、自分はステレオ空間の中でフィクションを作っているんだと、ぼんやりと考えていて。ステレオ空間の中にいろんな音を配置しながら、建造物を作っていくみたいなことをイメージしました。
もう一個、この曲は作中で一番カチカチに構造的だなって自分でも思うんですけど、構築されたこの世界が、自分の生まれてきた時空間と重なっている感じがして。というのも、自分は1992年生まれなんですけど、90年代に生まれた人間って、人生のほとんどの時間が、いわゆる“失われた30年”とかとリンクしていて。そんなことを思い浮かべながら、仕事の用事でゆりかもめ線に乗ったんですよね。そしたら、誰かが作ったエイフェックス・ツインのブートレグMVみたいなものを思い出して。
ゆりかもめ線の先頭車両からの景色を撮ったビデオなんですけど、あの景色がすごく電子音楽っぽいっていうのもあったし、ゆりかもめ線自体も、90年代のいわゆる臨海副都心開発計画の一部で、お台場とか東京テレポートもそうですけど、インターネット黎明期のマルチメディア都市みたいな感じでいろいろと建っていく中に、東京ビッグサイトっていう建築もあって。ビッグサイトと綴りは違うんですけど、そういうことが全部重なって、「Big Site」(巨大な場)っていう曲名に落ち着きました。でも、もうちょっと雑に言うと、がんじがらめになってしまった構造物としてのこの時代のこの世界、自分にとってのひとつのバビロンの象徴として、ビッグサイトという語感がしっくり来たということでもあります。
こういう曲名のつけ方にも、ブリアルから影響を受けていることが多いです。彼の初期作品によくある、「In McDonalds」や「South London Boroughs」とかいろいろあるんですけど、自分の生きて動いてる都市風景の中で、何か象徴的なものを見つけて、そこに曲名を付して、そこに彼なりの意味や何かを読み取っていくスタンスに影響を受けています。自分の場合、それがゆりかもめ線になったっていう感じです。
2000年代国産エレクトロニカにあった“記名性のあるサイン波”と、その継承
──タイトルの付け方で他にも興味深いものがあって、それは「Sine Waves In The Rain」なんですが 、電子音楽のアーティストって、シンセブランドや機種の名前だったり、シンセにまつわるものをメタ的にタイトルに入れがちですよね。そんな中で、「雨の中のサイン波」という、リリカルなタイトルがすごく素敵だなと思って。
S:この作品の制作を始めた時に、自然界にない音であるサイン波についてすごく考えてたんですね。いわゆるフーリエ変換、物理の中における波の理論で、要はフーリエの理論によると、あらゆる波っていうものは“サイン波”に分解できるんです。これを音響の世界に言い換えると、あらゆる音はどんなものでも波形なんですけど、そういう波を分解してったらサイン波から構築できるよね、みたいなことで。自分がその時に住んでいた部屋の横が、ルーフテラスみたいになっていて、雨の音とかがよく聞こえてたんですけど、コンクリートに反射する雨のランダムネスがいい感じだなと思って、この雨の感じを全部サイン波でやれたら凄くないか?みたいなことを、フーリエなんかのことを想いながら考えたんです。
あと、自分の中で、日本で生まれ育った電子音楽家として取り組むアティチュードについてずっと考えていたんです。僕はやっぱり2000年代のエレクトロニカの人たち、それは最近海外でもバズってるsoraや、竹村延和、レイハラカミも、自分にとって大きい存在なんですけど、あるいはそのちょっと前に流行っていた、80年代のいわゆる環境音楽周りの人たち、吉村弘とか、あの人たちの感性ってなんなんだろうなって。電子音楽って、別にどこの国の人でもできるし、誰が触ってもシンセはシンセというか、ある意味民族性がない楽器なのに、それらを使って組み立てていった時に出てくる、それぞれの生まれ育った場所とか、環境による違いを感じますよね。そうした時に、雨などを見て一句読みたくなる感覚は、もしかしたらジャパニーズ・バイブスなのかも、ぼんやりとそう思っていて。一方で、これ自体も「創られた伝統」的な構築された日本観であって、別に世界のいろんな地域の人たちも、雨を見たらそれぞれの形で一句読みたくなると思うんですけど、それを自分なりに表現するならどうするんだろうとを考えた時に、「Sine Waves In The Rain」というタイトルに落ち着きました。
──《サウンド&レコーディング》でのインタビューの写真だけしか見てないんですけど、KORGのARP 2600 Mが写っていましたね。これは積極的に使われたんですかね?
S:そうですね。ARP 2600 MもARP ODYSSEYもそれぞれ使ってます。で、ARP 2600 Mに関しては、アナログシンセサイザーには珍しく、サイン波があるんですよ。今回、大体の曲にサイン波が入ってると思うんですけど、サイン波オーディションみたいなのを自分の中でやってて、アレンジが進んでいく中で、Ableton Operatorか、それともSERUMなのか、他のソフトシンセなのかと色々聴き比べて、曲ごとにサイン波を決めていきました。ソフトシンセのサイン波はそれぞれに違う味があって、多分プログラミングの過程でそれぞれ味をつけてると思うんですけど。ARPのサイン波は面白くて、サイン波なのにアナライザーとかで見ると、サイン波って普通は倍音がないのに乗ってる感じがするっていうか。それが面白いし、変な色のついたサイン波が欲しい時に使っていて。あとチューニングがシビアでなかなかピタッと合わないんだけど、それも面白くて。
僕がなぜ、このサイン波を大事にしてるのかと言うと、倍音がない最小単位のものから音響を作り上げたかったっていう意識もあるんですけど、それとは別の観点もあって。それこそレイハラカミがずっと使ってたRolandのSC-88 Proのエレピの音だと思うんだけど、レイハラカミの中でいつもよく登場するあれがあるじゃないですか。あれって倍音構成的にはある種のサイン波だなと思っていて。
吉村弘に関しても、『MUSIC FOR NINE POST CARDS』とかめっちゃ好きで、あれはFender Rhodesだけで作ってるんですけど、Fender Rhodesも倍音構成的にはほぼほぼサイン波なんで、多分、彼らはサイン波と思って使ってないかもしれないんだけど、みんなそれぞれあるじゃないですか。だから自分なりのサイン波欲しいなと思って、色々探している中で、アナログシンセでサインが波あるのは珍しいなと思って、ARP 2600のサイン波をよく使ってます。
──サイン波(sine)とは綴りの違うサイン(sign)ですけど、シグネチャーみたいな意味合いが含まれているように感じてきました。ある種プロデューサータグ的と言いますか(笑)。
S:そうですね。マニアック過ぎますけどね(笑)。
──「Big Site」のサイン波もすごい特徴的ですよね。あれは何の音ですかね? 2、3種類あるように思いますが。
S:冒頭一発目に鳴るのはSERUMのサイン波で、ただ不協気味なコードで鳴らしてて、その濁りみたいなのが面白くて、それらが一個の塊として聞こえるようにうまいことやったんですけど。それと、ARPのサインもどっか入れた気がするな。サブベースとかは、AbletonのOperatorとかで作ることが最近は多くて、それで作ったと思います。結局、この曲のハイで鳴ってる、ピーっていうサイン波もあるし、ローの方のサブベースもサイン波で結構作ることが多いんで、なんかサイン波の旅は終わらないって感じですね。
継承者としての篠田ミルに訊く、00年代国産エレクトロニカ再評価の波
──かなりマニアックな話になってきて、理解されるのかちょっと心配になってきましたね(笑)。ただ、まさに私が一番聞きたかったことにも言及されていて、日本の1990年代末〜2000年代前半のエレクトロニカは、世界的な再評価を受けています。《NTS Radio》などのメディアをはじめ、海外の若手プレイヤーからも再訪される中で、日本ではそれが遅れていて、若手プレイヤーも多くはないです。この状況をどう観察されているでしょうか?
S:そうなんですよね。でも、僕はずっと一貫して好きだったので、今これが流行るんだみたいな気持になってたというか(笑)。ロレイン・ジェイムスとかも、来日した時にsoraとかレイハラカミのCD買って、instagramやXに上げてたりして。だから、これ流行ってる感じなんだみたいな驚きはあったんですけど。でも、シティポップや80年代の環境音楽と来たら、多分流れが来るんだろうという予感は言われてみればなんとなくあったというか。ただ、自分としてはトレンド云々ってよりは、自分が根っから好きなものの中の一つで、それを日本で発展させることを研究してたって感じなんですよね。偶然同期したというか。
──それこそロレイン・ジェイムスも、Xで『Pressure Field』について、お気に入りのアルバムだと言及されてましたね。
S:嬉しかったです。ロレイン・ジェイムスがさっき言ったようなポストを上げてたから、リリースする前にDMしたんです。良かったら聞いてみたいな感じで。そしたら何週間後ぐらいかに、「分かった聴いてみる!」と言ってくれて。その後、「『Sine Waves In The Rain』と『Power Plant – Fukushima 250117』がめっちゃ好きだった」って返してくれて、いくつか会話をしました。それがきっかけで、ホワットエバー・ザ・ウェザー(ロレイン・ジェイムスのサイドプロジェクト)の、《Circus Tokyo》での来日公演の前座をさせてもらえることになって、楽しみですし、嬉しいです。
──それきっかけでコラボとかになるとさらに熱いですね!
S:なんだろうな、IDMやエレクトロニカも本当に一番好きなジャンルだから、若手でやってる人をずっとチェックしてるんですけど、意外と世界的に見てもプレイヤーがそこまでいる感じがしないというか。そのジャンルの中で見れば一緒なんだけど、同じ問題関心というか、同じ興味、同じ深度でやってる人間って、なかなかいないなあと思ってて。例えば、ロレイン・ジェイムスがマウス・オン・ザ・キーズのイベントで去年に来日して、マウス・オン・ザ・キーズのショーの一部でロレインと一緒にやっている時間があって、その時にめっちゃサイン波だけで演奏とかしてて、やっぱこの人も同じことを考えてんだなと思いながら見てたんですけど。もちろん、世界中にすごい人たちがいるんだけど、このニッチな関心を共有できる仲間って、意外と母数が多くない気もしてて。だから、漠然と期待があってDMしたって感じなんですよね。仲良くなれそうかもみたいな。これで仲良くなれなかったらどうしよう(笑)。
──ただ、去年にOPNが来日した時に、 転換の時にsoraを流してたり、今度のアルバムでエレクトロニカ寄りのことをしていますし、ビッグネームもこの流れを支えていくんじゃないかと思います。そうした時に、篠田さんのレコードは、時流を先読みしたリリースなんじゃないかなっていう風にも感じます。
S:ラッキーですね。ただただ好きでオタクしてただけなんですけど。
──このジャンルは世界から尊敬を集めていて、これを途絶えさせるのはもったいないなと思っている中で、篠田さんが凄いのを出してくれたんですけど、継承する責任感と言いますか、義務感のようなものは感じたりしていますか?
S:継承しなきゃいけないっていう気持ちは全然ないんですけど……義務、責任……負えるのかな……(笑)。でもなんだろうな、上手く言えないんですけど、欧米でのトレンドに乗っかったり、あちらで過去のものが取り上げられることに一喜一憂するのではなくて、日本にはこんなやばいレーベルがいまあるらしいよ!こんなシーンの動きがあるらしいよ! ってなった方が楽しいなとは考えていて。そういう気持ちから松永拓馬と《ecp》を始めました。ハブがあったらそこで交流しやすいよなみたいな気持ちもありますね。でも、自分が負わずとも自然と出てくるとも思ってます。今ブームが来つつあるのかもしれないけど、好きな人って常に一定数いるんじゃないですかね。
──今、韓国にいらっしゃいますけど、それこそサラマンダみたいな人たちが出てきて、日本というより、アジア単位で盛り上がるんじゃないかとも思ったりもします。
S:それこそインドネシアとかもすごいじゃないですか。中国とかはちょっと落ち着いちゃったけど、ハウィー・リーとかもいるし。確かに、何か起きたら嬉しいなっていう気持ちはあるし、そのために《by this river》とか《ecp》をやってるんだなっていう気はしています。自分が交流するための口実というか(笑)。
オフグリッドなダンス・ミュージック
──2曲目の「Hottest Summer」ですが、強烈なシンセのカットオフから、それらが細胞分裂するかのようにどんどん派生していく感じが面白くて、シンセなのに有機物的に思えたんですが、どういうふうなアイディアから作られたのですか?
S:あれはAbletonの純正のウェーブテーブルで、LFOとかを動かして適当に遊んでたら、まずあの冒頭のナメクジっぽい動きが出てきて、そこから組んでいった感じですね。シンセだったり、ソフトウェアとかを触ってる時に生まれたものから出発することは多いです。
──この曲は一番フロアライクに感じるんですけど、特にハットの裏打ちなのがすごく好きで。ああいったクラブ寄りなビートパターンっていうのは、どういう意識やリファレンスがあって作られたものなんですか?
S:あれも、《by this river》用で作ったんです。自分が24時からの1時間を当てられてて、割とアンビエントな感じの人が多いラインナップだったから、さすがに盛り上げてって言われてて、そっかー、やるかみたいな感じで作ったんですけど(笑)。
ただ、ウェーブテーブルであの音ができたと同時に、マーク・フェルとかガボール・ラザールのことが自分の中でよぎったというか。彼らはMax/MSPで作ってると思うんですけど、彼らが作ってる複雑なモジュレーションの動きみたいなものが浮かび上がってきて。じゃあどう組み立てようかと考えた時に、マーク・フェルのハウスのプロジェクトであるSensate Focusとかも頭をよぎったんですけど…でも彼はちゃんとハウスとかUKガラージの中で育ってますもんね。けど、僕がダンス・ミュージックをやる時は、どこか他人事というか半人前というか半分ギャグでやってるみたいな気持ちがあって。DJもするけど、フロアを沸かすこと、踊らせることとか、そういうダンスミュージックの持つ身体性や歴史性に対しては、自分が真剣に向き合ってアプローチできていないから、自分がDJ だっていうのがおこがましいって思っているぐらいで。
だったらまず踊ってもらうために安直に裏打ちのハイハットは入れよう。ただ、IDMやエレクトロニカで育ってきた自分のエゴとして、踊れるか踊れないかのギリギリのところでぐちゃぐちゃに複雑にしたいという気持ちがあって。それでキックの打ち方を外したりしたんです。でも、今話しながら思い出していくと、ダンス・ミュージックのパーツとしてビートを打ってるっていうよりかは、パズルを配列するみたいな気持ちで組んでるというか。1曲目の「Big Site」もそうなんですけど、例えばステレオ空間の中で、サイン波をここに置いたらこういうふうに聴こえて、じゃあ次はこの辺が空いてるからここに置こうとか、ここのブロックが空いてるなとか、帯域やステレオ空間の定位とかも、そういう感覚で組んでます。これ言語化が難しいんですけど(笑)。
──おっしゃるように、基本的にビートモノに関してはオフグリッドに感じて、ブリアルの論考でも、彼が波形の編集ソフトで音楽を作ってると書かれていたように、彼の揺れ感とかすごい有機的でノレるなって思うんですけど。やはりオフグリッドに作ることは意識はされましたか?
S:オフグリッドに関しては、これは自分の中で一貫したロジックがあるんですけど、やっぱりオングリッドだと、グリッドの線に揃ったものが同時に鳴るじゃないですか。そうすると周波数の帯域的においしくないんですよね。“音の快楽主義”みたいなことは今回のテーマとしてあったので、一個一個の音をデカくリッチに聴かせたいけど、ある程度、音圧レベルも決まったステレオ空間の中でリッチに鳴らすには、同時に鳴っているものが少なくなけれは少ないほどいい。そう考えた時に、ほんのミリ秒でもずらした方が食い合わないし、音が抜けてきやすいっていう風に考えていて。もちろんグルーブも意識するんだけど、それより帯域的なリッチさ、気持ちよさのためにズラしたことが多かったです。
一方で、ACE COOLさんとか、ヒップホップのビートに関わる中でビートメイクの勉強をしたり、なんちゃってでテクノを作る機会も多かったので、他のプロデューサーの手法を研究した時に、やっぱりビートのグルーヴ感の調整に、みんなが命をかけて作家性やスタイルを見つけ出すじゃないですか。
──分かりやすいところだとJ・ディラですとか。
S:そう、それからテクノの人たちもシャッフルの設定をどうするかとか、キックやハイハットの音色やディケイをどうするとか、結構追い込むなと思って。ただ、僕は踊らせることより、同時に音が鳴る周波数のコントロールやバランスを考えて取り組みました。
グリッチというランダムネスな快楽性
──“音の快楽主義”っていうのがテーマだとおっしゃっていましたが、僕が一番快楽を感じる音はグリッチなんですよね。この作品でもグリッチが鳴りまくりで、もうたまらなかったんですけど。で、一口にグリッチと言っても、音が細かく連続するものをグリッチと言ったりとか、オウテカみたいなエラー音が由来のノイズのことをグリッチノイズと言ったり、定義が難しいと思うんです。そこで篠田さんからグリッチに関して解説していただきたいです。
S:僕の中でのグリッチの定義としては、少なくともPCソフトウェアじゃないと発生しない打ち込み方、ないしはデジタル技術のエラーによって発生する音のどっちかだと思っています。例えばBPM 999でキックを16分で打つみたいなことって、人間はもちろん、多分アナログな機械でもなかなかできないと思うんですけど、そういう時に発生する音響。これが1個目のグリッチのあり方。
もう1個はデジタルのエラー、それこそ90年代にオーバルとかが取り組んでいた、CDに傷をつけたりして、そういうデジタル由来のエラーや処理落ちとかをグリッチと言いますね。最近、インスタのリールとかで、PCにめっちゃ負荷かけまくってグリッチ録音しようぜっていうIDMの解説動画みたいなので回ってきますけど、そういうコンピューターチップでしかやれない、もしくはコンピューターチップ由来で起こるエラーによって発生する音響がグリッチなのかなと、僕は思ってます。
──そこで生まれる快楽性については、どういうふうに捉えていますか?
S:なぜ快楽的に感じるのかっていうのは、そうですね……でも、単純に“聴いたことのない音響”は、僕にとって快楽だと思っていて。90年代とか00年代ってとにかく開拓をしていて、みんながMacのPowerBookとかを使うようになって、それで何ができるか色々と実験したんだろうと思うんですけど、その中で生まれた新しい音響の形としてのグリッチなのかなと思います。自分もめっちゃ好きだけど、グリッチっていうものの大体は90〜00年代でやり尽くされていますし、個人的には今は死んでいるというか、ただ一種のフェチになったというか、自分が挙げた意味での本質的なグリッチの探求はあんまりないというか。PCのスペックが高くなって、なかなかエラーも起こせないし(笑)。
──この作品を作るにあたって、影響を受けたアーティストっていうのは、やはりその年代の音楽家なんでしょうか?
S:そうですね。レイハラカミ、エイフェックス・ツイン、スクエアプッシャー、マークフェル、アルバ・ノト、パン・ソニック……フェネスとティム・ヘッカーもめっちゃ好きで影響を受けてて、あとはもちろんブリアルもですね。
ダンスミュージックで表現するシニシズム
──3曲目の「Good Morning Mr. Kishida」は、ちょっとドラムンベースっぽいというか、BPMが速いからそう感じるかもしれないですけど、僕がこれまで聴いた中で、クリックでドラムンベースやってるのって、エアーヘッドの『Lightness』ぐらいしか思いつかなかったんですけど、これはどういうアイデアから作られた曲なんですか?
S:僕がクリックとかサイン波とか、点みたいな音を使うのって、自分でコントロールしてミニマルに絞った上で、快楽を設計したいからっていうのがあって。例えばマシュー・ハーバート以降、どんな音でもハイハットやスネアとかキックとして使えるようになったと思ってるんですね。何かを叩いた打突音とかなんでも。そうなった時に、じゃあ一番ミニマルなハイハットって?一番ミニマルなスネアって? と考えた時に、やっぱりクリック音に戻ってくるんです。っていうのも、さっきのビートをオフグリッドにする話とも繋がってくるんですけど、ステレオ空間と時間の中で占めるパーセンテージが小さいですよね。一瞬で終わるから。チッて(笑)。
そこでデュレーションもないし、その分の帯域も空くし、点を打ってスネアやハイハットとしての役割を果たすんだったら、もうそれで十分だなと思っていて。むしろ、その分の帯域を他のことに使ったりとか、あるいはその一点ですごい痛いところとか、すごい気持ちいいところで音が出せれば、それで十分だなと思っていて。クリックでビートを組み立てるっていうのは全体のテーマとしてあって。これはもちろん、00年代の《Raster-Noton》とかClicks&Cuts周りの人たちとかが取り組んでたことだとも思うんですけど、そこまで絞り切った上で、全体の音響を組み立てていきました。
──そのクリック音はどのように作ったのでしょうか?
S:「Good Morning Mr. Kishida」は、多分一番最初に作ったんですけど、とりあえず自分でクリック音のサンプル集みたいなのを作るところから始まりました。シンセで作った音もあるし、既存のサンプルをチョップして作った音とか。ただ、この曲に関してはどっちかって言うと、《Raster-Noton》みたいなClicks&Cuts的論理でビートとして組んだというよりは、《Warp》的な感性でビートに組みたいなみたいな気持ちがあって。エイフェックス・ツインとかスクエアプッシャー が持っている悪ガキ感にすごく影響を受けているんですけど、おちょくる感じというか、ちょっと露悪的というか。
なんでこの露悪的なものを作りたかったかっていうと、やっぱり安倍(晋三)さんが撃たれたことがきっかけなんです。問題のあった首相がちゃんと司法で裁かれずに、こういう形で倒れてしまったパターンって、いよいよファシズムに向かっていく時のきっかけになる予感がするなって、結構落ち込んじゃって。そんな中で、とりあえず気を逸らすためにガチャガチャしたビートのものを組みたい気持ちがあって。そんな時にすぐ岸田政権に変わったんですけど、岸田さんって広島出身で、首相になる前は非核三原則や、唯一の被爆国としての日本みたいなことをすごい大事にしていたはずだし、なんなら新しい資本主義みたいなことも言ってたけど、就任するなり全部コロッとなかったことにして進んでいて。そこで日本における類型的な一つの生のあり方を見たような気がしていて…それはもちろん、自分の中にもあると思うんですけど。染み着いてしまった馴致された生のあり方が嫌だなとか思いながら、でも一方で頑張ってアジャストして生きてくしかないこともわかるよなって気持ちもあって。で、“おはようございます、今日もがんばりましょう”ぐらいのこととして一旦捉えておくかって思って。
──そういうシニカルなバイブスを、音楽的なアイデアとして昇華させたということですね。
S:半分ストレス発散的な部分はありました。だからあの曲は最後にめちゃくちゃ転調するんですけど、J-POPってとにかくめっちゃ転調するよなって思いながら、僕もとりあえず転調しとこうみたいな感じで。本当にあれはちょっと露悪的な気持ちというか、破れかぶれな気持ちで作りましたね(笑)。
福島原発事故による三次/四次被害をドキュメンタリスティックに表現した「Power Plant – Fukushima 250117」
──ロレインも賞賛した「Power Plant – Fukushima 250117」ですが、タイトルにもあるように、福島で収音されたんですよね?
S:この曲名に入れてる日に、福島にリサーチで行ったんですけど、いわゆる帰宅困難区域になってる場所は、誰も帰ってこれない、居住はできない代わりに、めっちゃメガソーラーが建ってたんですよね。あるメガソーラーのエリアを通った時にすんげえノイズが鳴ってて、なんだこれと思って録ったんです。さっき「Big Site」の時に言ったこととも繋がるんですけど、ステレオ空間の中で実際に鳴ってない音を使って作っている裏で、僕の音楽への取り組み方って、シンセサイザーにしろPCにしろ、供給された電気を媒介にしないとできないものだなと思っていて。 電気っていうエッセンシャルなものについて、富田勲さんは「電気は雷由来だからアナログシンセサイザーは自然の音なんだ」みたいなことを言ったりとか、坂本龍一さんもそれを引き継いでいろいろ言ったりしてるんですけど、“電気”っていうことが、なんとなく自分の中でテーマとしてあったんです。
原発に比べたらソーラーはすごくいいエネルギーだと思っているし、ベターなチョイスだなと思ってるけど、とにかくそこのメガソーラーはすごいノイズを発していて、曲の一番最後とかで聴けると思うんですけど、ジーって音がそこに立ったら普通に聴こえるぐらいの音量で流れている。じゃあ、ここは原発ではなくなったけど、ここのサウンドスケープがこのジーって音がずっと鳴っている環境なんだと考えると、やばいなと思って。人間が聴いても不快な音だし、鳥や動物、人間が聴こえない周波数が聴こえる、聴覚の敏感な生き物にとって、多分ものすごく邪悪なサウンドスケープが鳴っているんだろうなと感じて。福島っていう地域が日本の中で近代以降、電力や石炭とかもそうですけど、エネルギー供給地として背負わされてきたものが色々とよぎって、これを録って何かに使いたいなと持ち帰りました。
──メガソーラーは物理的に自然を破壊する一方で、核のゴミ問題もありますが、原子力発電はその供給量も加味してエコなエネルギーだと言われます。安全な運用を探るべきか度々議論になりますが、どうお考えですか?
S:僕自身は原発にはもちろん反対だし、日本っていう土地が持つ、地震などの災害を考えるとまずありえないだろうと思っています。3.11のこともあったのに何してんだよみたいなことはあるし、原発がどこに立っているか、この国の中で原発を建てさせられたエリアが何を背負わされてきたか、やっぱりすごく気にかかるというか。どこか周囲の土地にそういうものを集約することによって、東京の電力は供給されてるけど、結局リスクを負っているのは、福島のような周囲の土地という構造自体も良くないし。でもメガソーラーに関して僕は一緒だなと思っていて、結局それが替わっても、今言われているような様々なリスクがあるじゃないですか。
エネルギーを発生させるものを、どこかに集合的に建てて背負わせるっていうこと自体が、多分限界が来ているんだろうなっていうことは考えていて。今の限界が露呈していく中で、巨大な送電網みたいなことを作らなくても、もうちょっとオフグリッドな電気供給の在り方とか、絶対いろんなオルタナティブがあるはずだと思っていて。二十世紀的な資本主義のシステムで考えたら、どっかにまとめて建てて、そこからエネルギー引いてきてみたいなのが、もしかしたら合理的とされていたのかもしれないけれど。なかなか変えるのは大変だと思ってるんですけど、でもそういうものから脱していかないと、このしんどさは変わらないよなってずっと思っていますね。これは、植民地主義の問題ともつながってくることだと思っているし、実は本当に大事なことだなとは思ってます。
──「Power Plant」を聴いた時、ものすごい圧迫感や不安感を感じました。ソングライティングや音作り、演出面で、そういった意図を込められたのでしょうか?
S:そうですね。フィールドレコーディングしたものを(DAWに)置いて、何かを作ろうと思った時に、圧迫感しか出てこなかったんです。自分はメガソーラーのエリアに行くまで、その感覚を知らなかったけど、あそこを通った時に感じた異様さ、不快さみたいなことを、自分が全く知らない土地に押し付けてるんだなと感じたし、それを踏まえた上で作りましたが、圧迫感しか出てきませんでした。
──ちなみに、あれは電磁波マイクで収音されたんですか?
S:普通のフィールドレコーディングのマイクで録れたんです。あれが恐ろしいのは、電磁波マイクに変換しなくても録れるぐらいのノイズが出ているんです。別に特殊な録音をしようとして福島に赴いてたわけではないので、本当に簡単なフィールドレコーディング用のレコーダーしか持ってなかったんですけど、それでもあれだけ録れちゃうぐらいの音が鳴っていて、結構びっくりしたというか。
──そんなにデカいノイズなんですね……ちなみになぜ電磁波マイクのことを訊いたかと言いますと、LOMっていうエキセントリックなマイクブランドがあるじゃないですか? Instagramで篠田さんもフォローしていたので、もしかしたら使ってるんじゃないかなと。
S:原摩利彦さんとの《THEY ARE HERE》の展示で、今は韓国にいるんですが、LOMのGeofónが大好きで持ってきてます。どっかで使ってやろうと思って、とりあえず持ってきたんですけど。というのも、自分の今の関心はフィールドレコーディングだったり、世界で今鳴ってる音を使うことにすごく興味が湧いてるんです。だから、“実際には鳴っていない音”に区切りつけるためにも、今回のレコードを出したみたいなところがあります。
快楽主義が繋げた道筋
──グリッチ的なものと、リニアなビートって、哲学的に相反すると思うんですよね。それらを組み合わせるのは難しいことではないかもしれないですけど、篠田さんは越境するその手腕が優れているなと感じました。創作する上で、越境、あるいは壁を壊すような意識があったのでしょうか?
S:本当に電子音楽が大好きで。ただ、電子音楽って何でもやれるじゃないですか。今どきの人って、ちょっと勉強したり、チュートリアルを見たら何でもできるし、プラグインがあれば誰でも何でもできる。じゃあ初めて自分の作品を作るってなった時に、自分の作家性ってどうやって作っていくんだろう? そう考えた時に、とりあえず自分が本当に好きなものに取り組んで、その組み合わせの中からやってみるしかないと思って。その先に、まずは守破離の守じゃないですけど、自分のオリジナリティとか、自分がこの世界に対して新しく付け加えられることが見つかるかもしれないと思ったんです。
ただ、やっぱり00年代で電子音楽はある程度の極地まで行ったと思っていて。エレクトロニカと言われるジャンルの人たちが電子音響の面でやり尽くした部分もあるし、ダンス・ミュージックの方でやり尽くしていった流れとして、《Warp》的なものがある。この両方のやり尽くしたところに行ってみたい。彼らが何を考えてたのか、何をしようとしてたのかを、自分も知りたいなと思って。両方の勉強をしたり、見よう見まねでやりました。でも、どうやって混ぜたんだろう? 上手く混ぜれたかは自分で判断できることじゃないんですけど、自分にはどちらの音楽もすごく“快楽的”なものに聴こえたから繋げられたのかもしれないです。
それこそ、IDMが出てきた時に、特に《Rephlex Records》が“Braindance”という用語を押し出したけど、脳で踊るというか、脳や耳に気持ちいいという感覚があって。あるいは、アルヴァ・ノトとか池田亮司のライブを浴びると、痛さもあるじゃないですか? 痛いけど気持ちいいという、二つの快楽があるというか。何年か前のフジロックでスクエアプッシャー見た時も、ホワイトステージの音がやばすぎて、気持ちいいのか気持ち悪いのか分からないけど……やっぱりトータルで気持ち悪かった気がするんですけど(笑)。エレクトロニカもダンス・ミュージックも、音響的な快楽っていう意味では、実は哲学的に重なっていると思っていて。そこにおいて繋がれたのかもって、今話しながら思いました。
──終曲の「Path」ですが、ユーフォリックと言いますか、アトモスフェリックなムードの曲で終わるので、希望を持てるような終わり方に思えました。それは構成として意識したことなのでしょうか?
S:これも《by this river》 のためのもので、特に目的なく作ったデモの中からピックアップして、無理矢理に磨いて、自分のセットを終わらせるために作ったんです。なんかサイン波ばっか言ってますけど、適当にサイン波で弾いてた時にあのメロディができて、それを起点にクリック音を使いながら、《Warp》的な感性で組み上げることを目指しました。今作では、自分の好きなものを組み合わせるというか、とりあえず終わらせて次に行こうみたいな目的があったので、好きなものを消化するために作っていた面もあったんです。
「Path」っていうタイトルに関しては、明るいイメージがあって、自分は大学院でメディア論をやってたんですけど、自分の師匠というか、指導教官だった人が吉見俊哉っていう人で、その吉見俊哉の師匠に見田宗介っていう学者がいて、彼の著書に『気流の鳴る音』(筆名は真木悠介)というのがあるんです。その中にカルロス・カスタネダっていう、80〜90年代に日本でも流行った文化人類学者が登場して、彼がドン・ファンっていうネイティヴ・アメリカンの魔術師みたいな人にフィールドワークで同行して、調査をしながら色々と教えてもらうんです。その中に“道”っていう概念が出てくるんですよね。
人生は道なんだけど、目的がどうとか、道の先に辿り着くものじゃなくて、道自体が美しければそれは良い道なんだよ、みたいなことを言っていて。その歩いている道自体を楽しめとか、いろんな意味に取れると思うんですけど、すごく感銘を受けて。暗いし、しんどいなとか思いながら、世の中や人生のことを考えてこの作品を作ったので、最後に明るい気持ちになっとくかって。希望を感じないと、くじけそうだなと思いながら、はい、生きてます。
実存しない音を経て、この世界で鳴っている音に向き合う
──最後に、このレコードがどういう風に伝わって欲しいのかお聞きしたいです。
S:マニアックな内容だと思うので、万人にこれを聴いてほしいって言えるようなものではないし、万人にウケるものだとも全然思ってないけど、自分と同じような音楽が好きな人にまず刺さるといいなと思っています。それこそロレインみたいに、作品を通してコミュニケーションを取る機会が増えるようになったら嬉しいなって思っています。自分名義での作品はこれまでになかったし、プロデュースワークとかの場合は、やっぱりできるだけ奉仕したいというか、自分のエゴみたいなものを第一に出す場じゃないなと思っていて。でもソロに関しては、とりあえず自分の好きなことをやって、好きな人とやりたいと思ってますね。
──先ほども言われたように、今後はミュージックコンクレートやフィールド・レコーディングのような、実存する音に挑戦していくのでしょうか?
S:そうですね。既にミュージックコンクレート的なことはかなりやってて、《beatfic experiment》っていう福島で小学生の時に被災した子が主宰している、被災地を繋ぐプロジェクトがあって。そこで作った音源はフィールド・レコーディングをメインに作ってたりとか。あと、原摩利彦さんとやっている《THEY ARE HERE》というプロジェクトでは、パレスチナの人たちから送ってもらったフィールド・レコーディング素材、と言ってもあちらの人が撮った動画とか、録音したボイスメモを送ってもらったもので楽曲を作っています。楽曲の売り上げを素材を提供してくれた人に送金するというプロジェクトです。
ただ、ガラッとミュージックコンクレートに振り切るというよりは、自分が今までサイン波やクリック音とかを素材として扱ってたのと同じ感じで、フィールド・レコーディングした素材を扱いたいなって思っていて。ただ、ベタ置きはしたくないんですよね。音楽に対して鳥の鳴き声をベタ置きみたいなのとか、あんまり面白い効果を生まない気がしていて。ただ、フィールド・レコーディングで録れた音って、音楽の小節や拍の概念がない、音楽の構造では捉えられないような実際の世界で流れている時間をもった音なので、それをどう取り扱うかはずっと考えてますね。
一方で、フィールド・レコーディングって変わらないようでいて、何十分も同じところで録音しながら聴いていると、やっぱすごい快楽的に感じることもあって。そういう時間の感覚を、どう自分の音源に取り入れるか、リュック・フェラーリみたいに、コラージュのセンスで魅せるやり方とかもあると思うんですけど、今は研究中ですね。
──お話を聞いていると、坂本龍一の『async』の哲学に通じるものを感じます。
S:そうですね、すごく影響を受けていると思います。自分は『Pressure Field』でやったようなカチカチなことは忘れずに、フィールド・レコーディングと同居させることを考えていて。それこそ、《THEY ARE HERE》のために書いた「Reminder」では、パレスチナの家族が、10月7日の前に海辺で遊んでいる様子を撮っていて、その15秒のクリップを送ってくれたんだけど、その15秒を1つのループとして捉えて、15秒でずっとループさせ続けたら、BPMはいくつで何小節分だっけ? みたいなことを計算して、それに対してここにサイン波を置いて、ここにエレピを置いて、というふうに組み上げていったんですけど。これはミニマル・ミュージックの、ループのズレで遊ぶみたいな、ズレから生まれるものを楽曲に取り込む技法を念頭に置きながらやったりしたんです。 自分なりに“実際の世界の音”を録音して、それを音楽作品にしていく時の自分なりの使い方みたいなのはすごく研究中で。でも、『Pressure Field』の感覚も失いたくないなと思っていて。そういう半人前という意味で、『Pressure Field』は自分にとってアルバムではなくEPで、とりあえず出さなきゃ前に進めないみたいな感じがあって。なので、これからファースト・アルバムを作るために頑張ります。
<了>
Text By hiwatt