BEST TRACKS OF THE MONTH特別編
-TURNスタッフ/ライター陣が2021年を振り返る-
当サイトの連載企画《BEST TRACKS OF THE MONTH》。今年も編集部とレギュラー執筆陣が2021年を振り返り、その中で自らの思考や行動と密接に関わっていた楽曲あるいは2021年のベスト・トラックを5曲程度選出し、それぞれの視点からコメント。コロナ禍2年目でみなが疲弊している中、それでも音楽は健気に鳴り続けています。命より大切なものなどない。その正論の上で、それでも個々の脳裏で鳴り続けてきた2021年の音を改めて振り返ってみました。(TURN編集部)
Editor’s Choices
まずはTURN編集部のピックアップとコメントからどうぞ!
井草七海
・arauchi yu「Whirlpool」
・Coco「Come Along」
・Rosie Lowe & Dival Timothy「Don」
・ROTH BART BARON「みず / うみ」
・Japanese Breakfast「Paprika」
環境が変わると人間簡単に求めるものが変わるのだなということに驚いた1年でした。コロナ禍を境に他人との新しい出会いは片手で数える程になってしまいまして、コロナ1年目に皆がこぞって試してみたオンラインでの飲み会のような類のモノも1周して飽きてしまったというのが正直なところ。人から受ける予期せぬ刺激を感じないままに1日を回していくことは初めは快適であったものの、2年目ともなるとさすがにちょっと干からびてしまいそうでした。
そんなわけで、唐突に、ライブ以外にも舞台表現を観ることに興味を抱いたコロナ禍2年目です。そもそも、その特有の大仰な発声や身振り手振りにこそこれまでなじめずにいた訳ですが、今やそれを受け取るのが心地いい。演劇のみならず、ダンスや舞踊もそう。舞台セットや小道具、衣装の力は大いに借りるけれど、基本はそれら作りものを本物に見立てた板の上で、人間の身体表現による躍動する生のパワーをもってそこに無いものをあたかも有るように観客に想像させる、という仕組みに面白さと潤いを感じる機会が多かったです。そういえば、2021年最もワクワクさせられた映画、デヴィッド・バーンの『アメリカン・ユートピア』。ライブという枠を超えた舞台表現として見ると、音楽のパワフルさに対するあのミニマルなセットや衣装という対比は、まさにそうした受け手の想像力を大いに掻き立てるものだったなとも改めて気づかされました。
さて、ここに選んだ楽曲は、今書いてきたことと直接関係はないのですが、歌やコーラス、楽器の音などの生命力や“生感”の美しさに惹かれたナンバーを無意識に選んでしまったようです。そしてどん底から幸福へと突き抜けていくミシェル・ザウナーの陽のパワーにも勇気付けられました。やはり2022年は、もっと人間の体温を感じられる年になってくれないと困りますね。(井草七海)
岡村詩野
・Sam Gendel, Sam Amidon「weak brain narrow mind」
・Moses Sumney, Sam Gendel「Can’t Believe It」
・Amelia Meath, Blake Mills, Sam Gendel「Neon Blue」
・Brijean 「Ocean (Sam Gendel Remix)」
・Laurie Anderson「Sweaters (Sam Gendel Remix)」
今年はサム・ゲンデル絡みの曲で5曲を選びました。昨今は邦人アーティストの作品にも力を貸すようになったけれど、身近になるどころか、この人の真意というのはますますわからなくなっている。こうしている間にもきっと新曲が次々と生まれているのだろうが、混沌たる量産ぶりでただ惑わせていることがもちろんその理由などではなく、みなと同じ環境で同じものを聴くことに警鐘を鳴らし、自らの意志で発見することを怠るその愚かさをニヒルに捉えているように思えてならない。真の大衆性とは消費社会の欺瞞と対峙するところにこそ宿る。サム・ゲンデルのますますわからなくなっている活動から私が受け取るのはそんな宝探しにも似た行動力だ。だから彼の活動を追いかけるのは本当に楽しい。知らない音楽を聴くことがこんなにも面白い、ということを近年強く私に教えてくれているのはこの男に他ならない。
2021年ほど孤独を実感した年もなかったし、迷いと惑いに苛まれた年もなかったが、2021年ほどそこに達観できた年もなかった。コロナ以前からとうに地球が危機的な状況になっていることを念頭に入れつつも、新たな音楽との出会いを追い求める5年目のTURNにぜひこれからもおつきあいください。2022年もどうかよろしくお願いします。(岡村詩野)
尾野泰幸
・Alien Boy「Don`t Know What I Am」
・Bartees Strange 「Weights」
・Flock of Dimes 「Two」
・Snow Ellet 「To Some I`m Genius」
・家主「飛行塔入口」
ギター・オリエンテッドで魅力的なロック・ミュージックをずっと探し続けていました。もはや誰もシリアスに聴取することはなくなってしまった(というかそもそもそういうものだった?)2000年代ギター・ロックやポップ・パンク、エモを国内外作品を問わずに片っ端から聴きなおし、サブスクリプション・サービスで取扱がないものはBOOK OFFや駿河屋、メルカリ、ヤフオク、Amazon、中古レコ屋などで値段も崩れるところまで崩れたCDたちを地道にピックアップ(≒救出)を繰り返しながら聴くのが習慣になっていました。国外で少し前からその兆しが見えてきていた2000年代ポップ・パンク、エモのリバイバルを横目で見つつ、そこからもこぼれ落ちている/いくであろう作品群に現時点では明確に言語化できていない底知れぬ魅力を感じていました。そのような音楽聴取環境が個人的に平常化するなかで、私を魅了した楽曲群がここで取り上げた5曲です。2022年はこれらの楽曲で鳴っているエレクトリック・ギターが耳に届いたとき、どの音楽より自身の体が痺れてしまう理由を一つでも多く言葉に、文章に残していくことができる一年にしたいなと、別モニターに映っている「もったいない本舗 楽天市場店」のTOPページを眺めながら思っています。(尾野泰幸)
加藤孔紀
・Leo Nocenteli「Your Song」
・Hand Habits「4th of July」
・Amelia Meath, Blake Mills「Neon Blue」
・Jennifer Hudson「I Never Loved A Man (The Way I Love You) 」
・Dan Reeder「Born a Worm」
インスタグラムを見ていたら《Light In The Attic》の投稿でモノクロ写真が流れてきて、そこには観衆とギタリスト。よく見るとギタリストの体とタバコの煙だけ『ハリー・ポッター』の魔法の写真みたいに動いてる。これは2021年のベスト・クリエイティヴだ!と思った瞬間でした。そのギタリストはミーターズでお馴染み、レオ・ノセンテリ。彼の未発表のソロSSW作が発掘され、時を超えて(まさに魔法みたいに)音源がリリースされることを象徴するその投稿に、レーベルの気概も感じて興奮でした。中でもエルトン・ジョンのカヴァー「Your Song」が印象的で、特にふた回し目のアコースティック・ギターソロと口笛とがハモる部分が良い。この人はファンク・ギター以外にも口笛とハモらせる発想とか、美しい長尺のソロとか魅力を持っていた人だったんだと再発見。やっぱりギターが好きという気持ちが年々増します。そんな2021年は、エレキではなくアコースティック・ギターに注目することが多く、ハンド・ハビッツやブレイク・ミルズなど今をときめくギタリストの作品の中でも「4th of July」や「Neon Blue」などアコギの響きを追求したような曲を面白く聴きました。ハンド・ハビッツのインスタのストーリーに投稿されるアコギの(変速チューニングか、独特なコード・ヴォイシングか)不思議な響きを伝える動画も刺激的で目が離せなかったです。話は変わり、アレサ・フランクリンの伝記映画『リスペクト』でのジェニファー・ハドソンの好演、楽器まで作ってしまう超DIYなSSWのDan Reederの曲も素敵でした。(加藤孔紀)
高久大輝
・butaji「RIGHT TIME」
・Fivio Foreign「Story Time」
・Loraine James「We’re Building Something New (feat. Iceboy Violet)」
・OMSB「JUSTIFY MYSELF」
・Vince Staples「THE SHINING」
2021年も相変わらずだらしなく、にもかかわらず頑固で方々に迷惑をかけていた自覚はあります。この場を借りて謝罪と感謝をさせてください。すみませんでした。いつもありがとうございます。ところで変わったことといえば、ネガティヴでいても全然悪くないじゃんというスタンスでここ何年間か過ごしてきたのを少し変えて、せめて会う人や関わる人にはできるだけ気持ち良く対応しようと思い……いや、書いていて「全然できてないじゃん」と思わず口に出しそうになりましたが、まあ気持ちが大事ってことで経過を見てください。もちろんネガティヴでいるのも全然悪くないといまだに思っていて、何というか、やっぱり少しでも笑えてた方が気分いいのかな、みたいなすごくぼんやりした理由で始めてみた次第で、自分でも経過観察中なので、まだ結果は出ていません。とはいえ、2021年の後半は人と会って話す機会も増え、自分のやりたいことを改めて認識できたような気もしてます。選んだのはそんな感覚を後押ししてくれた曲たちです。聴いてみてください。
今のところ長生きしたいという欲も湧いてこないので、先のことはあまり考えずとりあえずやってみようという、前を見てるのか後ろを見ているのかよくわからない気持ちです。2022年は時間と金とウィルスとヴァイブスの許す限り、遊びたい場所に遊びに行って、会いたい人に会いに行く、そんな年にできたらいいっす。
Writer’s Choices
続いてTURN・レギュラー・ライター陣(50音順)がそれぞれの専門分野から2022年のベスト・ソングを選出!
阿部 仁知
・折坂悠太「炎(feat. Sam Gendel)」
・サニーデイ・サービス「TOKYO SUNSET」
・Billie Eirish「Happier Than Ever」
・Moment Joon「Spotlight ‘1921」
ほとんど一律で自粛を余儀なくされた2020年と比べて、2021年は「選択」の年だった。飛び交う賛否の中開催された《FUJI ROCK FESTIVAL》。GEZANやサンボマスターがそれぞれの表現で僕らを鼓舞したことが強く印象に残っているが、折坂悠太の出演辞退の言葉もまた僕の胸を打った。
誰にとっても与えられた正解などない。自分が何をすべきで何をすべきでないか、自らの判断で選択する。ライブやフェスティバルの最中にこれほど自らの存在を意識した年はないが、これまでもずっとそうだったはずだし、コロナ禍のライブではそんな音楽との主体的な交わりを誰もが当事者として実感した。それは僕にとって意義のあることだったと思いたい。
フジロックの後には少し虚無感があって、曽我部恵一の「パラリンピックが終わって空っぽの九月」という言葉が僕に重なった。日々の生活のリアルタイムの情感を紡ぐ彼らの歌は今年も変わらずともにあったが、京都のボロフェスタでこの曲を歌い終わった後、「やったー!すごくよかった!」とはにかんだ彼の笑顔が忘れられない。海の向こうからは「本当に同じ世界か?」と感じるような熱狂が中継され、ビリー・アイリッシュが叫んだ最高潮のフレーズは“Just fuckin’ leave me alone”。やはり選びとるのは自分だ。
少しうわつきながら年末気分に浸っているが、先日東京の《LIQUIDROOM》で観たMoment Joonの「来年はいい年になると思ってる? ならねえよ」という言葉がリフレインしている。僕は彼くらい真摯に切実に生きられてるのか? なんてまた自問自答しながらも、僕の選択は続いていく。今年も来年も。
(阿部仁知)
奧田翔
・Baby Keem「16」
・J. Cole「m y . l i f e」
・Joyce Wrice「Losing」
・Tyler, The Creator「WUSYANAME」
徒歩にせよ車にせよ公共交通機関にせよ、移動しないと音楽を聴く時間が自然と減ってしまうという方は多いのではなかろうか。私もその一人だ。そんなわけで、というわけでもないのだが、2021年はよく散歩をした。個人の年間ベスト楽曲として上に挙げた4曲は、私の散歩時間を彩ってくれた曲たちと換言してもいい。
春先の散歩時によく聴いたのがジョイス・ライスの『Overgrown』だった。その収録楽曲の中でもシャルドネを思わせるような清涼感に満ちた「Losing」は、ちょうど異動があり環境の変化を経験した私に活力を与えてくれた。恋人に三行半を突きつける同曲は、恋愛に限らず、あらゆる決別を決断する人々への応援歌だと思う。
海外旅行に行けない2年目の夏に一服の清涼剤となってくれたのがタイラーの「WUSYANAME」だ。リリックにも出てくるカンヌの海沿いをドライブしながら聴ければ最高なのだが、鎌倉に向かう晴れた冬の日の電車内で聴いた「WUSYANAME」も悪くなかった。2021年の夏を代表する一曲としてこの曲を挙げるファンも多いと思うが、騙されたと思って冬にも聴いてみてほしい。
J.コールの「m y . l i f e」とベイビー・キームの「16」は、ともに深夜の散歩時に重宝した。ラップの技量を磨きディスプレイするというシンプルな結論にたどり着いたコールの声と言葉は、人生そのものについて考える機会がとみに増えた2021年の私に「お前は、どうするんだ?」と迫ってくるように感じた。その対極にあるような軽ささえ感じられる「16」を最もよく聴いたのは、その反動からかもしれない。(奥田翔)
坂本哲哉
・Guerrinha「Flautas Cosentino」
・Pessoas Que Eu Conheço「Peço Desculpas por Não Ter Ido a Sua Festa de Aniversario」
・Seixlack「Tele-Sexo」
・Kauan Marco「Simpsons」
・Sérgio「Hamburger」
普段からアンビエントを聴くことが多いのですが、2021年は例年以上にアンビエントに耳を傾けることが多かったように思います。Nala SinephroやFuubutsushi、Joseph Shabason、Bremer/McCoy、Bendik Giskeといったアンビエント・ジャズに夢中になったり、《Daisart》からリリースされたpicnicの新作やSfericから届いたTIBSLCの新作、あるいはUNKNOWN MEの初LPの美しさにうっとりしたり、Space AfrikaやKelman Duranの漆黒のサウンドスケープにゾクゾクしたり……。
とはいえ、日常的にアンビエントを聴く中でも、踊りたいという欲望が消えることはありませんでした。それは『Ulyssa Presents: 40% Foda / Maneiríssimo』というコンピがあったからです。このコンピはアメリカのインディアナ州ブルーミントンとメキシコのサン・ミゲル・デ・アジェンデを拠点にする《Ulyssa》がブラジルのアンダーグラウンド・ダンス・レーベル、《40% Foda / Maneiríssimo》に焦点を当てたもの。ハウスの無機質な反復ビートと、アンビエントやジャズ/フュージョンに少なからず存在する、グリッドに囚われないしなやかなリズムのあわいを野性的に縫っていく異物感に圧倒され、合間を見つけては繰り返し聴いていました。ということで今回は、反則を承知の上でこのコンピの冒頭5曲を選んでいます。個人的には2021年のベスト・コンピは間違いなくこの作品です。
2022年もきっとアンビエントを聴いていると思いますが、アンビエントに関係なく、上記のコンピのような異物感のある作品に出会えたら良いなと思っています。(坂本哲哉)
佐藤遥
・박혜진 Park Hye Jin「Let’s Sing Let’s Dance」
・Sofia Kourtesis「La Perla」
・PARKGOLF「火」
・諭吉佳作/men「ムーヴ」
・Qrion「Your Love」
家にこもる心地よさを覚えてしまい、結局2021年もほとんどの時間を家で過ごした気がする。2020年からの変化を探そうと日記を見返したところ、そのひとつは家でひとりで踊るようになったことみたいだ。きっかけは「Let’s Sing Let’s Dance」を聴いたことだった。ピアノが落ち着いた雰囲気を作り上げるこのハウス・トラックで、悲しいときには〈歌おう、踊ろう〉と呟くようにパクは歌っていた。元気なときにクラブでしか踊らず、TikTokユーザーでもない私は「悲しいときにその気持ちのままその場で踊ってもいいんだ」とこのとき気づいたのだった。
挙げたのはどれも悲しいときに聴きながら踊った楽曲である。クラブで踊るのは呼応の踊りだとすると、自分で曲を選び家でひとりで踊るのはひとりごとの踊りだ。自分以外誰もいない家の中で、大きく身体を動かせばそれなりに気が紛れる。そして、悲しい誰かがどこかで同じように踊っているかもしれないと思えば、どんな理由にせよ悲しいという感情を共有する踊りにもなり、幾分かの安堵を感じた。少なくとも〈目を閉じてあなたは私の手を握る / 見えずとも感じることができる〉と歌うパクは、MVのようになぜ悲しいのかと聞くこともなく一緒に踊ってくれる。
毎日はうっすらと悲しい。外に出ると「そうだった、こういう社会に生きているんだった」と思い出し、それを直視しなくても済む家に帰りたくなる。それでも踊って悲しみをどうにかしながら、2022年はもっと外に出て人と話し、いろんなものに触れ、知見を蓄えて、自分の手足を動かせる範囲が広がる歓びを感じながら音楽と真摯に向き合っていけたらと思う。(佐藤遥)
佐藤優太
・Tems「Crazy Tings」
・Amaarae & Kali Uchis「SAD GIRLZ LUV MONEY (feat. Moliy) [Remix] 」
・Dijon「Many Times」
・Oli XL「Go Oli Go!」
・宇多田ヒカル「One Last Kiss」
連載《ロンドン南東便り》にもある通り9月末に渡英。それからの約3ヶ月はとても濃密な時間で、音楽についての楽しみも尻上がり的に大きく広がった一年だった。ロンドンに来てやはり一番驚いたのは「アフロ・ビーツ」というジャンルの市井での存在感の大きさ。同ジャンルの今年の代表曲の一つ、Temsの「Crazy Tings」は、極めて変化の少ないトラックに対して豊かなメロディを引き出すシンガーの歌の上手さに感心しリリース時から好きだったが、クラブの大音量で聞いた時にテクノ・ミュージック的な硬質なベース・ラインの魅力に気がついて、ますます入り込んで聴くようになった。Amaaraeの曲は、このリミックスの発表を機に一年越しでTikTokで大ブレイク。11月に観たライヴでの現地のティーネイジャーたちの大合唱はいまも目と耳に焼き付いている。Dijonは、インディからR&Bやゴスペルまで射程に含む、折衷的な音楽性が魅力の作家で、僕は特にこの「Many Times」の血湧き肉躍るロックンロールを大いに楽しんだ(ライヴ映像のブチ切れた歌いぶりも注目)。Oli XLは《Warp》との契約を機に最近知ったアーティストだが、先鋭的なサウンドの裏にある「ソング」としてのチャーミングさに作家の底知れぬポテンシャルを感じる。そして最後は「One Last Kiss」。この曲の2番で入ってくるベース・ラインとサビのキック。その昂揚感を劇場の音響で確かめながら、子どもの頃から魅了されてきた「エヴァ」シリーズの最後を見届けられたことは幸運だった。この機に庵野秀明監督はじめ制作チームへの感謝を書き添えたい。ありがとうございました。(佐藤優太)
髙橋翔哉
・Clark「Lambent Rag」
・冬にわかれて「もうすぐ雨は」
・Library Tapes「Breeze」
・Common「Majesty (Where We Gonna Take It) ft. PJ」
・Kit Sebastian「Affet Beni」
またTwitterで発見された書き手が本を出したって? 大好きなバンドの新譜を5ヶ月も気づかず放置していた! あの映画って地元だと上映されないの? 年々、カルチャーへの興味の幅が広がるほど、リアルタイムの現象を追いきれないことに対するFOMO的不安に苛まれる。Twitterをアンインストールしてみても、積ん読された本の山、かさばる映画の半券の束、Spotifyのアルゴリズムによるレコメンド……。
2021年はそういったあらゆる情報への精神的疲弊だけでなく、私の個人史としても重苦しい時期だったように思う。目まぐるしい変化とそれに伴う試行錯誤に、ジェットコースターのように振り回されて過ぎ去った2020年に比べると、2021年こそがむしろ体感として「パンデミック以降」の暗く荒んだムードに支配された一年だった。音楽のテイストはより内省と逃避へ向いた。特に今回選んだ5つの楽曲には、「ここではないどこか」に連れ出してくれるフィーリングを感じている。なかでも、冬にわかれて「もうすぐ雨は」のやさしいオルガンの響きと丹念な演奏は、いまの気分に寄り添ってくれた。また、私が最近注目している、クラシックと他ジャンルとのクロスオーヴァーの楽曲も忍ばせている。
今回、年間ベスト・ソングを選びながら、いかに自分が日ごろ夢中になっているものについて言語化していないかを再認識した。人一倍強い表現欲を持つ一方、できれば前に出たくないという厄介なジレンマを抱えながら、2022年はもう少し、自分の熱狂と偏愛について何かしらの形で発信しようと思う。(髙橋翔哉)
ドリーミー刑事
・Cornelius「変わる消える(feat. mei ehara)」
・Gotch feat. 東郷清丸「Summer Dance」
・佐藤優介「UTOPIA」
・長谷川白紙「ユニ」
・スカート「海岸線再訪」
2021年、特に7月以降は、谷深く山高き時間だった。Corneliusがmei eharaをフィーチュアした楽曲は、John Carroll Kirbyによるリミックスも含めて、高すぎる期待をなお上回るものだったが、ある日突然配信が停止され、今はもう聴くことができない。芸術に対する根拠なき死刑判決。そして久しぶりに足を運んだフジロックを巡っては、誰よりも献身的に音楽シーンの裾野を発展させてきたGotchが理不尽な十字架にかけられた。しかし彼らに与えられた罰は本当に適切なものだったのだろうか。私はまったく納得がいかないが、レコード会社も音楽メディアもそれを検証しようとはしなかった。では一体誰がアーティストと音楽を守るのか。そもそもどうしてこの国ではヘイトスピーチは野放しにしながら芸術はいつも簡単に殺されてしまうのか。そんなことばかりを鬱々と考えていた夏だったが、そこから救ってくれたのもやはり音楽だった。どん底の気分で聴いた佐藤優介の新曲には、俺はまだこんなに音楽に興奮することができるのかというほど脳みそを揺さぶられたし、長谷川白紙には人間の測り知れない創造性とポップミュージックの可能性を見せてもらった。そして年末にかけて観たMETAFIVEの配信ライブはやはり震えるほど素晴らしく、スカートがタイトルからして最高のシングルを引っ提げてライブハウスに戻ってきてくれたことは、2022年に向けた大いなる希望だ。結局のところ、自分が愛するものは自分で守るしかない。これからも音楽から受け取った大きなものを、私なりのたどたどしい言葉で記録していきたい。(ドリーミー刑事)
山田稔明
・Lana Del Rey「Arcadia」
・King Of Convenience「Rocky Trail」
・fuvk「retainer」
2021年はとても奇妙な年だった。2020年で非日常を思い知ったはずだったのに、さらに捻じくれて裏返っていく世界に辟易し途方に暮れ、そして気がついたら新しい季節に放り出されて2022年を迎えた。外出自粛がデフォルトになり自宅で音楽に接する時間が増え、つねになにかしらレコードがターンテーブルで回る日々の中で、僕が2022年に好んで聴いたのは、言うなれば「Tranquil=静けさ」を帯びた歌たちだった。Lana Del Reyの『Chemtrails Over The Country Club』は昨年の個人的ベストレコード、しかし秋に出た続作『Blue Banisters』に収録された、静かな祈りのような「Arcadia」を最優秀楽曲として推したい。King Of Convenienceの奇跡の新作からの先行曲「Rocky Trail」は空気をかき乱すことのない静謐なポップソングで胸が踊った。オースティンのベッドルームポップシンガー、 fuvk(発音の仕方をだれか教えて)の「retainer」は体温低めだけれど情熱的な輪舞曲のようで、ヘッドホンで耳をふさいで何度も繰り返し聴いた。2022年が昨年よりも素晴らしい年になるように心から祈る。良い音楽にもたくさん出会えますように。もうそろそろみんなでワイワイ騒いだり踊ったりしたい。(山田稔明)
油納将志
・Yola「Dancing Away In Tears」
・Sofia Kourtesis「Going out」
・Emma Noble「We Gonna Live Forever」
・Little Simz「Woman」
・Cleo Sol「23」
2020年と同様に自宅での作業が中心となった2021年。午前中はNTS、午後はBBCの6 MusicかRadio 1を流しながら、というのが日常で、いつしか番組が変わるタイミングでだいたい何時頃だと把握するようになりました。聴いていて気になった曲はShazamして、自動的にSpotifyのマイ Shazam トラックに加えるようにしています。選んだ5曲のうちのYolaもお気に入りの番組を聴いていて知りました。ブリストル郊外出身で、マッシヴ・アタックやケミカル・ブラザーズのバッキング・ヴォーカルを経た後にブラック・キーズのダン・オーバックに見い出され、彼のレーベル「EASY EYE SOUND」と契約。ここで挙げた「Dancing Away In Tears」はグラミー賞のベスト・ニュー・アーティストにノミネートされた19年発表のデビュー作に続く2作目に収録されたソウル・チューンで、このアルバムもグラミー・ノミネート作です。最初に聴いたときは70年代の曲かと思ったほどのレイドバック感で、ダンが気に入るのもすぐにわかりました。ペルー出身で現在はベルリンを拠点にしているSofia Kourtesisも最初に流れてきて即反応したダンス・トラック。2022年もそんな風に自分にとってラジオが大きな位置を占めそうです。(油納将志)
Yo Kurokawa
・Hope Tala「Tiptoeing」
・問題聰部「Song About Soul(feat.金其禾)」
・?te(壞特)「虧欠」
1983年に初めて黒人女性作家としてピューリッツァー賞を受賞したアリス・ウォーカーの『カラーパープル』は「神さま、あたしは十四歳です」という1文から始まる。主人公・セリーの過酷な人生を通して語られる、「女性の自由はいかにしてなるか?」という問い。晴れやかなその結末が2021年において未だ有効なのは、セリーから否応なく尊厳を奪った人種や性別による差別、貧困、暴力が、今も我々をとり巻く世界とそう変わりないから、というだけではない。彼女を救ったのがヘテロセクシャル以外の愛であり、そして自分を肯定する「仕事」だったから。この小説を読んでいた時によく聴いたのが、同性の恋人の存在をオープンにしているHope Tala「Tiptoeing」だったことに不思議な巡りあわせを感じた。彼女がMVのアウトフィットで見せる少女的フェミニティも大好きだが、それは2021年私を最も興奮させたH&Mと英ファッションデザイナー、Simone Rochaのコラボレーションとも重なる。人種も性別も年齢も関係なく、レースやフリル、リボン、パールが施された洋服を自由に楽しむ人々に、私は強くエンパワーメントされた。「黒人女性作家として初」なんて説明が効用を持たない世界が待ち遠しい。
2021年はソウルの系譜に連なる台湾アーティスト……The Crane、雲端司機、Everydaze、YELLOWらの新曲に心踊らせた。特に林以樂や9m88に続く女性ソウルシンガーの活躍も目覚ましく、問題聰部「Song About Soul(feat.金其禾)」や?te(壞特)「虧欠」での彼女たちの深く濃い歌声に胸を熱くした。2022年こそは現地でのライヴを楽しめる日が来ることを願うばかり。(Yo Kurokawa)

BEST TRACKS OF THE MONTH特別編 -TURNスタッフ/ライター陣が2020年を振り返る-
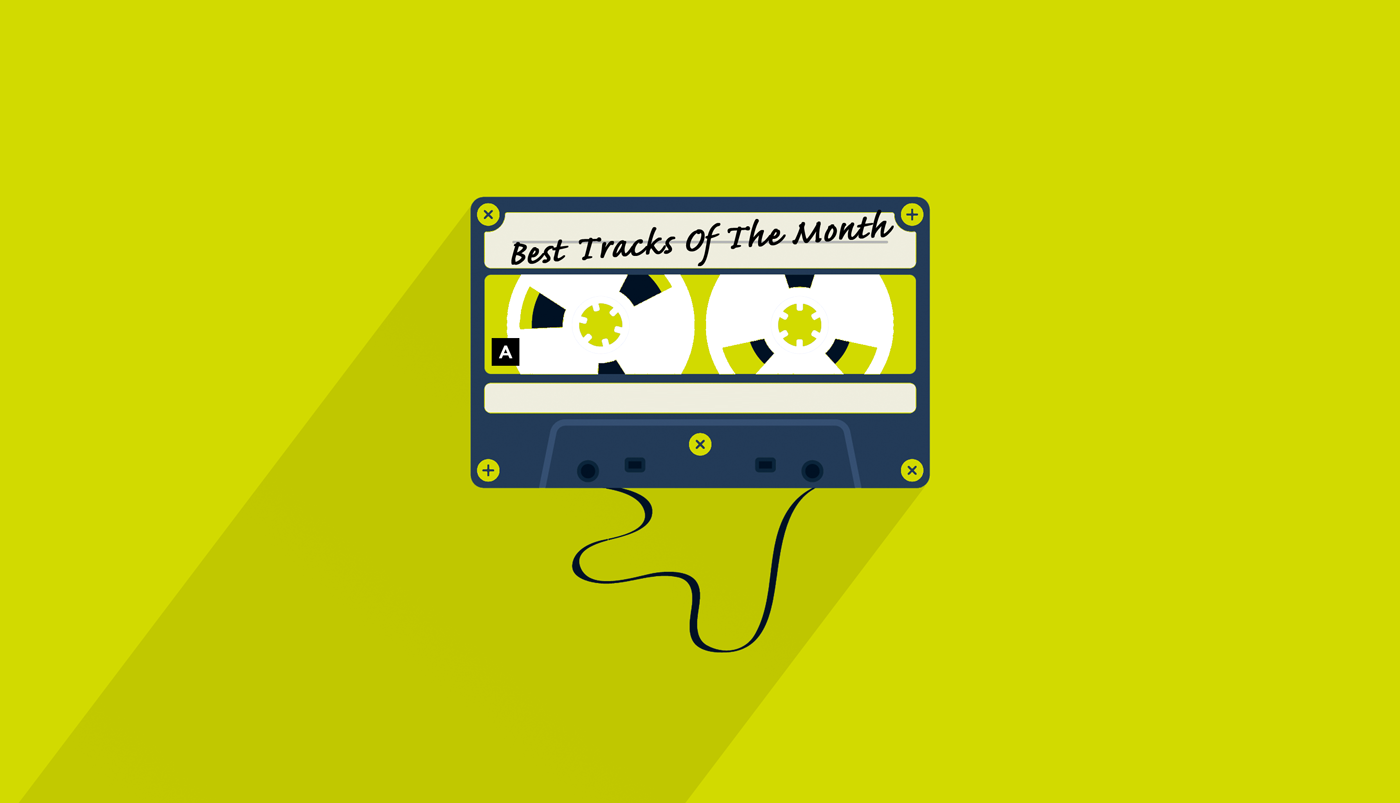
BEST TRACKS OF THE MONTH特別編 -TURNスタッフ/ライター陣が2019年を振り返る-

THE 25 BEST ALBUMS OF 2021

THE 25 BEST ALBUMS OF 2020
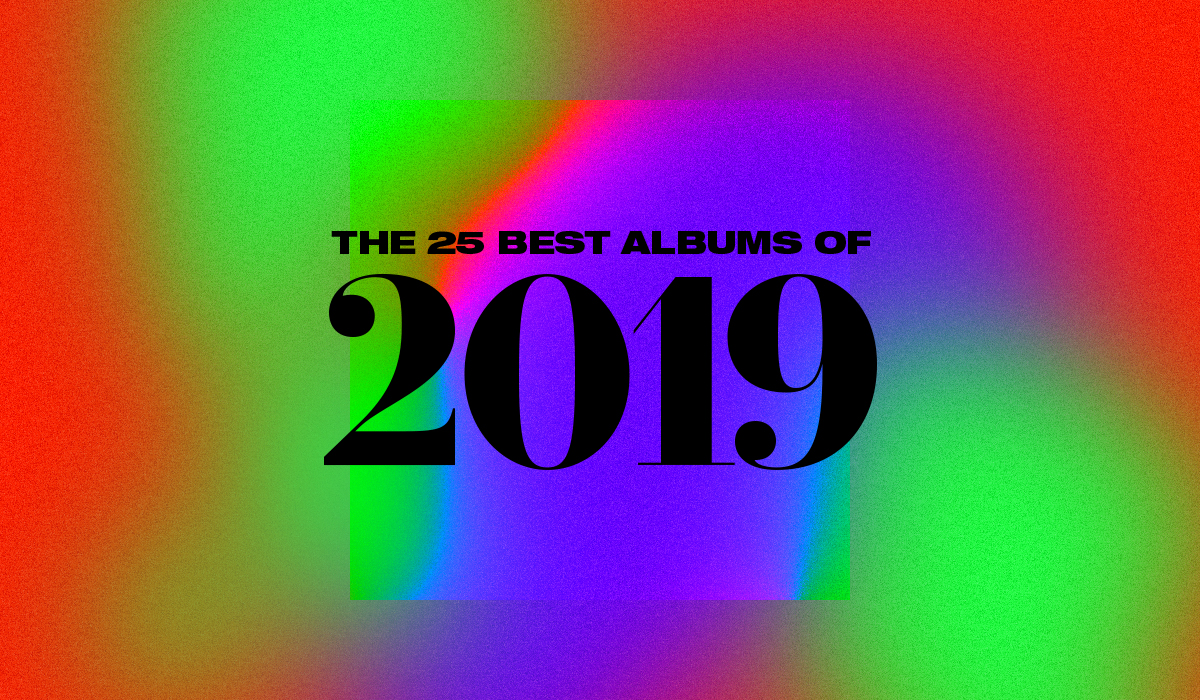
THE 25 BEST ALBUMS OF 2019

THE 25 BEST ALBUMS OF 2018
Text By Sho OkudaHitoshi AbeYo KurokawaHaruka SatoToshiaki YamadaShoya TakahashiYuta SatoDreamy DekaShino OkamuraMasashi YunoNami IgusaDaiki TakakuKoki KatoTetsuya SakamotoYasuyuki Ono
