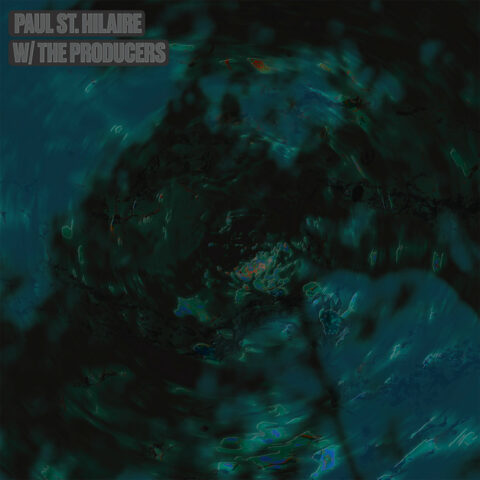ダブ・テクノの発展にシンガーはどう貢献するのか
ポール・セント・ヒレアーの最新作『w/ The Producers』について綴る前に、同作をリリースしたレーベル=《Kynant》について少しだけ触れておこう。《Kynant》は、イギリス系ナイジェリア人でラジオ番組制作者/音楽ライター/DJのリチャード・アキンべヒン(Richard Akingbehin)が2015年にベルリンに設立したレーベル。これまでに、TM404やテレンス・ディクソン、マイク・パーカーといったどこか不穏で蠱惑的なテクノを武器とするプロデューサーの作品をリリースしてきた。そんな《Kynant》は、その方向性が定まってきたように思えた2021年にサブ・レーベル=《Kynant EX》をスタートさせる。ダンスフロアに少なからず意識が置かれていた《Kynant》に対し、《Kynant EX》はダンスフロアにフォーカスせず、我々を内省に誘うような奇妙な揺らぎを持つサウンドを主眼としていた。それはある種の不確かさを排除しない音楽とも言えるが、そんなベクトルを持つ《Kynant EX》がその3番めの作品として2023年にリリースしたのが、ポール・セント・ヒレアーの『Tikiman Vol.1』。ヒレアーのおよそ17年ぶりとなるソロ・アルバムだった。
もちろんその17年の間、ヒレアーは止まるころなく貪欲に動いていた。モーリッツ・フォン・オズワルドとマーク・エルネストゥスによる《Basic Channel》以降のダブ・テクノに新たな解釈を加えるデッドビートやラウダーといったプロデューサーとタッグを組み、その神秘的でソウルフルな歌声を披露し続けていたのだ。特に、ダンスホールやIDM、ミニマル・テクノのエッセンスを加えたデッドビートのダブ・テクノの脈動にヒレアーの優しくも激しい歌声が交錯する『The Infinity Dub Sessions』(2014年)はその一つの到達点と言っていいだろう(今年リリースされた『Rooms of Kairos Sessions』ももちろん必聴だ)。そういったコラボレーション作品では、ヒレアーの出発点の一つであるリズム&サウンドの作品と同様に、ヒレアーはプロダクションというよりも歌声に力点を置いていたように感じる。それゆえ、ヒレアーのプロダクション能力はどこか推し量り難いところがあるように思えるだろう。だが、彼は2001年に《Basic Channel》傘下に自身のレーベル、《False Tuned》を作り、2枚のソロ・アルバム『Unspecified』(2003年)、『Adsom』(2006年)をリリースしていたことを思い出してほしい。そこではルーツ・レゲエに比重が置かれていたが、リズム&サウンド譲りのミニマル・ダブからステッパーズ、ダンスホール、R&Bまでを往還するサウンドは彼のプロダクション・センスの高さを明瞭に証明するものだ。そして、『Tikiman Vol.1』ではその非凡な才能を甦生させるかのように、ジャズやラヴァーズ、ハウス、アンビエントの意匠を纏ったサイケデリック・ダブを展開。ヒレアーの歌声だけではなく、その精緻で奔放なプロダクション能力にも注目した《Kynant》のリチャード・アキンべヒンの慧眼はもっと称えられても良いと思う。
そんなヒレアーの新作『w/ The Producers』だが、『Tikiman Vol.1』とは違い、彼の歌声が再びサウンドの中心に置かれている。そして、そこには彼の歌声をさらに引き立たせるために10組のプロデューサーが集結した。ダブステップ/ベース・ミュージックの重鎮、マーラが無重力感のあるヘヴィなビートを刻む「Like It’s Always Been」では、ヒレアーはマーラが作り出すダブ空間にそっと忍び込み、囁くように歌い上げながらその音響空間を拡張させる。気鋭のプロデューサー、プリオリは「Send Them On」でリズム&サウンドを想起させる霞がかったミニマル・ダブを繰り出すが、ヒレアーはそこにさりげなくメランコリーを加える。さらに、跡部進一による硬質で流麗なダブ・テクノ「Time To Wake Up」では幽霊のように声を漂わせながら時間感覚を捻じ曲げ、現代のデジタル・ダンスホールの革新者、イクイノックスのガヴスボーグが展開する不穏なアンビエント・ダンスホール「Confidential」では、抑制的な声色でその不気味さを加速させる。どんなビートでもヒレアーはそこに余白を見つけ、その余白を損なわないように歌い、楽曲のムードをゆっくりと変化させていくのだ。
本作のコンセプトは、プレス・リリースでも触れられているように、曲それぞれに異なるシンガーを配置したリズム&サウンド『w/ The Artists』(2003年)のコンセプトを転回させたものだと言えるが、こうやって聴き進めていくと、本作には、近年その地平を広げつつあるダブ・テクノの発展においてポール・セント・ヒレアーというシンガーが果たしてきた役割を再考するという観点、さらには、これからのダブ・テクノにどのようにシンガーが交わっていけるのかを想像するという観点が内包されているように感じる。ヒレアーのシンガーとしての底力とサウンドをまとめ上げる編集力が強く刻み込まれた本作は、今後のダブ・テクノ、ひいてはダブとエレクトロニック・ミュージックが緩やかに交錯する場所において、一つの参照点となるのではないだろうか。(坂本哲哉)