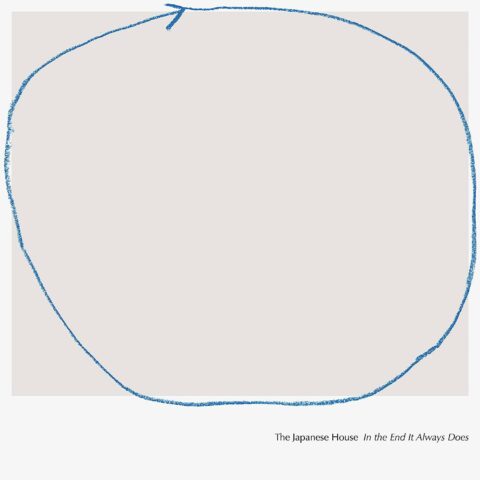去りゆく誰かとの回顧録
The Japanese Houseことアンバー・ベインによる4年ぶりのセカンド・アルバム『In the End it Always Does』はベインの回想録だ。イギリス・バッキンガムシャー出身のシンガー・ソングライターは幼少から音楽家の父のもと、音楽を学んできた。2012年に《Dirty Hit》と契約すると、自身がクィアであることを率直に作品へ込めてきた人である。本作はケント州マーゲートに引っ越したときのこと、三人婚と解消に至るまで……そうした恋の始まりと終わりが綴られているからだろうか、切なくも温かさが漂っている。
本作にはThe 1975のマシュー・ヒーリーとジョージ・ダニエル、ボン・イヴェールのジャスティン・ヴァーノンらが前作『Good at Falling』(2019年)に続いて参加。新たにMUNAのケイティ・ギャヴィン、チャーリーXCXもスタジオに遊びに来ては手伝ってくれたそう。なかでも、プロデューサーのクロエ・クレイマーとの出会いは特別だった。初めてのクィア・アーティスト同士による共作(MUNAのケイティ・ギャヴィンもクィアで「Morning Pages」で共作している)であり、すべての歌詞で“彼女”と書く意味を理解してくれる。多彩なジェンダーとの連携から生まれた信頼関係は、これまでになくリラックスしたヴォーカルや楽曲に反映されていると思う。前作とEP『Chewing Cotton Wool』(2020年)まではエフェクト加工を凝らした、ざらついた質感のヴォーカル処理が目立ったが、本作のリラックスしたなだらかな歌い回しはベイン本来の物憂げな声質の良さをも際立たせる結果となった。
加えて、透き通る電子音や生楽器の音色が響いていく。例えば、アルバムの中で最も古い曲だという「Sad to Breath」。ピアノやギターのフレーズをアップビートに幾層にも織り交ぜているが、澄明な音色や乾いたパーカッションを用いることで、軽快な心地良さをもたらしている。
一方で、海辺の街マーゲートで恋人と過ごした日々を回想する「Sunshine Baby」。この曲でベインは長い付き合いの友人でもある、The 1975のマシュー・ヒーリーとコラボレーションしている。普段からお互いにデモを送りあう親しい二人の影響を感じるのは、ヴァースのコード進行がThe 1975の「Somebody Else」と共通するところだ。さらに<きっと誰かが僕を救ってくれる>という歌詞は、ぐるりと円を描いた本作のアートワークが示す、巡る人間関係の儚さ、そして未来への期待をも意図しているようだ。
愛する人との出会いと別れ、そこで味わう喜びや葛藤を俯瞰してみる。本作『In the end it always does』から伝わってくる楽観性は、時間をかけて得るものなのかもしれない。時間が失恋を癒すように。実際に2年間もの間、全く曲が書けなくなりソファで小さくなっていたとベインは語る。その間も、アイデアだけは止まらなかったというが、いや止められなかったのだろう。アイデアは恋した記憶であり、過去の愛情を繋げたのが『In the End it Always Does』だ。<私は恋に落ちるのが得意で、恋から落ちても生き延びることができる。落ちるのは得意なんだ>。何度躓いても、自身の恋愛経験を飾らずに伝える。それがThe Japanese Houseの音楽の特色であり、“今”のベインが唄う想いなのだろうから。(吉澤奈々)