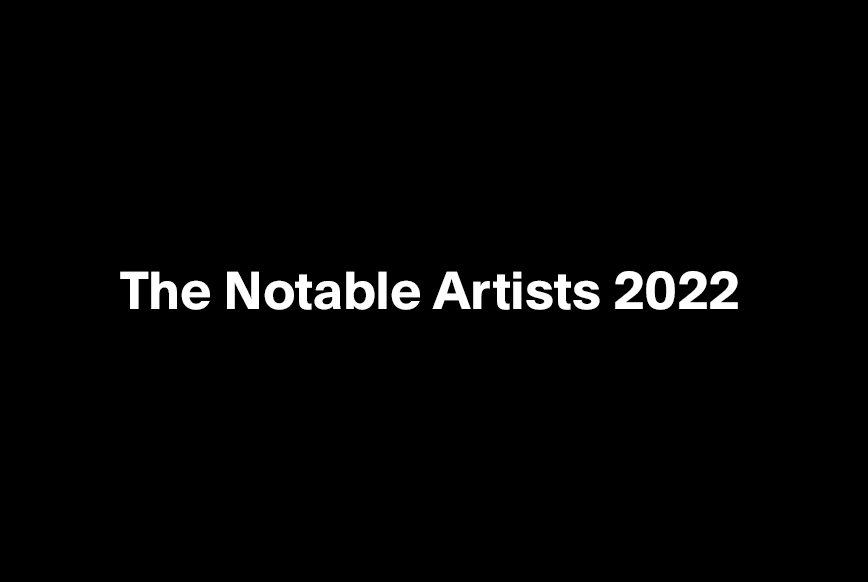《The Notable Artist of 2022》
#9
Will Yip
“アジア系アメリカ人”が生み出すアメリカにおけるロックの一側面
2010年代後半以降アメリカにおけるインディー・ロックの動向を眺めていると、アジアにルーツを持つミュージシャンが数々の良作をリリースしていることに気づくことは難しくない。もちろんそれまでに活躍してきたアジア系アメリカ人のミュージシャンたちを忘却することなどできようもないが、例えばミツキ『Puberty 2』(2016年)を筆頭に、ササミ『SASAMI』(2019年)、ジェイ・サム『Anak Ko』(2019年)、ジャパニーズ・ブレックファスト『Jubilee』(2021年)……とその作品たちを眺めてみると確かに毎年のようにそのミュージシャンの知名度を引き上げ、批評的成功もおさめる強度の高い作品が生み出され続けていることが分かる。そしてそれら作品の多くに特徴的なことは自らのエスニック・マイノリティとしての経験や、ルーツへのまなざしが刻印されているということでもある。そのような近年のインディー・ロックを巡る潮流にあって中国にルーツを持つ音楽プロデューサー、ウィル・イップの存在を忘れてはならないだろう。
ウィル・イップは70年代に貧困から逃げ出すべく着の身着のままで香港を経由しアメリカへと移り住んだ中国人の両親のもと、マンハッタンで生まれフィラデルフィアで育った。ローリン・ヒルと進行を深め彼女の作品ライヴ・ツアーにも参加するなどセッション・ドラマーとして活動する一方で、ザ・ワンダー・イヤーズ、タイトル・ファイト、タイガーズ・ジョー、モダン・ベースボール、ピアノ・ビカム・ザ・ティースといった2010年代にアンダーグラウンドで意欲作を次々と生みだしていた所謂“第四波エモ”シーンの主要バンドたちの作品においてプロデュースやエンジニアリング、ミックスを次々と手がけ、シーンの最重要人物としてキャリアを積み重ねていった。携わったバンドの中には昨年『Glow On』にて一挙に世界的ブレイクを果たしたターンスタイルの名もある。現在はフィラデルフィア周辺を拠点としながら現在は自身が管理する名スタジオ《Studio 4》にて録音した作品をリリースするレーベル《Memory Music》をインディー・レーベル《Run For Cover》の傘下で運営するとともに、2017年には《Atlantic》と提携し《Black Cement Records》を立ち上げるなど現行エモ、インディー・ロックにおいてメジャー、インディーを問わず縦横無尽に駆け巡り数多くの作品を生み出し続ける彼はいまやアメリカにおいてロック・ミュージックに携わるアジア系アメリカ人を代表する一人といってよい。
そのような彼に《Pitchfork》は昨年4月に短いインタビューを行っている。コロナ禍におけるアジア人ヘイトの拡大を契機に彼が立ち上げたアジア系アメリカ人・太平洋諸島系アメリカ人コミュニティ基金のためのチャリティ・ラッフルに関する話題を端緒としたそのインタビューは『Rock Producer Will Yip on the Promise—and Limits—of Asian American Representation in Music』、つまり『ロック・プロデューサー、ウィル・イップの期待(と限界)――音楽におけるアジア系アメリカ人の表現』と題されていた。そこで彼は上述したミツキやササミの活躍や韓国にルーツを持つヤー・ヤー・ヤーズのカレン・Oにも言及しつつこのように語った。
ロックンロールの近現代史を眺めてみれば主として遡ってみても白人が大きな割合を占めていましたよね。私はここにこそ表現の重要性があるように感じているのです。いや、私はそこから逃げていたんですよね。若い頃は、音楽業界のなかで自分の居場所を見つけるためにも、白人のように扱われたいと思っていました。でも、ここ数年は、それが私の責任だとは思っていませんが、誰もが自分のやりたいようにやってよいのだし、私は声を上げることに抵抗がなくなっているのです
ここで語られているのはもちろん白人によるロックンロールを排除せよだとか、アジアン・アメリカンだからこそ鳴らせる音が“本質的に”存在しているだとかという話ではもちろんない。ウィル・イップはここで特定のコミュニティにおけるマジョリティの仕草や慣習を擬態することは表現へと制約をもたらしてしまうこと、それを“当たり前”だと認識すること自体に楔をいれようとしている。それはきっとアジア人的なサウンドやメイキングを誇張して表現することでもなく“アジア人”として自らを現時点ではアイデンティファイしている自らがその人種的な経験や歴史を再帰的に考え、理解し、そこで生まれる葛藤とともにどのような音楽表現を模索していくのかということでもあるだろう。そしてそれは人種というカテゴリーを飛び越えて(音楽)表現を行う誰しもが直面することでもある。その意味でザ・ナショナルのライヴ会場で自分自身がたった一人のブラックであると感じたという経験から、インディー・ロックに対するブラックの関与を再考することを制作の端緒としたデビューEPを作り上げ、今やUSインディー期待の新星と目されるバーティーズ・ストレンジをウィル・イップが《Memory Music》へ迎え入れたことも必然であったのだろう。2年の活動休止を経てミツキが新作『Laurel Hell』を先ごろリリースし、まもなくササミの新作『Squeeze』も届き、6月にはアジア、ラテンにルーツをもつメンバーからなるザ・リンダ・リンダズのデビュー・アルバム『Growing Up』が控える2022年。ウィル・イップの制作活動を注視していくことはアメリカのロック・ミュージックのエッジをなぞることに他ならないのだと思う。(尾野泰幸)
Photo by Jared Pollin
Text By The Notable Artist of 2022Yasuyuki Ono
【The Notable Artist of 2022】
画像をクリックすると一覧ページに飛べます