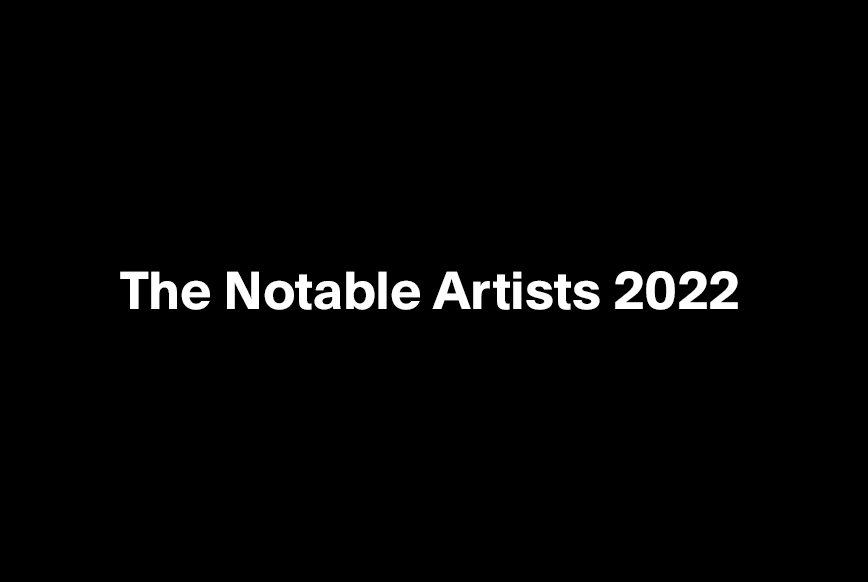《The Notable Artist of 2022》
#2
Library Tapes
ミニマリズムと親密さ ── Library Tapesがパンデミックで手にした“音風景”
近ごろ、AIサービス「Dream」が、ユーザの入力したキーワードをもとに自動生成した抽象画をよく目にする。ときどき、それと同じことを音楽でもできたらと夢想してみる。頭の中のイメージをそのまま音に変換してくれる魔法のAIの代わりに、もしもピアノがその役割を担うことができたら、そこに鳴るのはこんな音楽かもしれない。スウェーデンの作曲家、Library Tapesことデヴィッド・ウェングレンの、「夕暮れ」「夜の空」「秋」などと名づけられたディスコグラフィーを聞いていると、ふとそんなことを思う。
そもそもLibrary Tapesは2004年に2人組として始動し、2作のリリースののちデヴィッドのソロに。活動開始と同時期にピアノを始めた彼は、テクニカルなプレイヤーというよりはプロデューサー型の音楽家だ。音の微妙なズレやアンビエント/ドローン的なサウンドメイクが、繊細な感情の機微を描く彼の持ち味である。映画などの劇伴仕事でも知られLibrary Tapesとはレーベル《1631 Recordings》の同胞でもある小瀬村晶や、Bicepやスワンズの作品にも参加したチェリスト、Julia Kentらとコラボレートも行いながら、確実にファンベースを築いてきた。
彼はパンデミック下の2020年以降、月に1、2曲のペースでシングルの連続リリースを始める(そして2021年後半には週1リリースに加速!)。以前の作品に顕著だったリヴァーブを増幅させた音空間は後退し、打鍵時のカタカタというノイズや木の板が軋む音まで拾った親密なサウンドに。そしてほとんどの曲において、左手は単音を8分のリズムで弾くことに終始している。ロングトーンやリズムのバリエーションは減っているし、曲の展開もほぼなくなり、ただ右手で弾く短いモチーフが繰り返される。はじめにAIを引き合いに出したが、小節を等分して、単音の連なりで和音を形成するピアノからは、エイフェックス・ツインがMIDIから出力された曲をピアノに自動演奏させた「Avril 14th」を想起する。でも人間味がなく単調かというとそうではない。鍵盤のアタックや環境音の入り方の違いが生み出す細かなニュアンスの、機械での再現性は高く望めない。曲の形式や作曲のプロセスはほとんど同じにもかかわらず、曲ごとに微妙に異なる表情はタイトルに結びついて、絵画のように情景を紡いでいく。
ミニマリズム的に音数と曲展開を減少させた背景には小瀬村晶からの影響も感じるが、それ以上にパンデミックとの関係も探りたくなる。人や場所を訪ねることができなくても、部屋でピアノを弾いて創作ができる。2年を費やした大作ではなく、週に一度の小品を作るのであれば、表現は直感的で抽象的なものになる。深い残響音に陶酔を求めるのではなく、より自分や楽器に近い位置にマイクを置くことは、「個」と向き合う時代の必然だ。
Library Tapesの絵日記さながらの月数曲のリリースは、数曲のシングルをコンパイルした何度目かのEP『Dusk』を2021年12月中旬にリリース後、パタリと止んでいる。細かなリリースを除けば、彼の現状最後のアルバムは2020年夏の『The Quiet City』だが、これはほぼ全曲にゲストを招いたコラボレート作品の趣に近い。これほど精力的な活動のわりに、しばらく完全なソロ・アルバムはリリースしていない。徐々に社会が明るさを取り戻しつつある季節において、地道な活動の集大成的なアルバムの制作を予感してしまう。また同じく2021年12月、デヴィッドの変名と思われるWind Wavesという名義で、Library Tapesの楽曲のニューエイジ風のカヴァーと新曲の2曲がリリースされた。活動の節目となる傑作を放つか、さらなる音楽的野心をもってアナザー・サイドを切り開くか。外界へ通じるドアは次々に開きつつある2022年、Library Tapesのさらなる活躍に期待したい。(髙橋翔哉)
Text By Shoya TakahashiThe Notable Artist of 2022
【The Notable Artist of 2022】
画像をクリックすると一覧ページに飛べます