ザ・バンド
かつて彼らは望郷の仲間だった
オリジナル・アルバム・ガイド
先ごろ公開されたザ・バンドのドキュメント映画『ザ・バンド かつて僕らは兄弟だった』が好評だ。カナダ出身、現在27歳という若きダニエル・ロアーが監督したこの作品は、確かにザ・バンドの全盛期の活動にフォーカスし、当時の映像アーカイヴ、メンバーや様々な関係者へのインタビューなどで構成された非常にスタンダードなドキュメンタリーではある。もちろん興味深い発言も多いし、何より貴重なフィルムには何度も心を揺さぶられるが、一時期だけとはいえ一つの家に住み、次第に袂を分かっていっても、最後までどこかで信頼し合っていたことが伝わってくる人間ドラマのような側面が強いのが魅力だ。映画は『ロビー・ロバートソン自伝 ザ・バンドの青春』を原案にしたとされているが、カメラを前に素直に話をするロビー・ロバートソンの穏やかで優しい眼差しからはエゴは一切感じられない。
そこで、TURNでは改めてザ・バンドのオリジナル・アルバム・ガイドをお届けする(再結成以降の作品は除く)。1968年から1978年までの10年で9作品。既に映画を観た方にも、足を運ぶ予定の方にも、ザ・バンドのキャリアを辿るその一助になれば幸いだ。
(ディスクガイド原稿/岡田拓郎、岡村詩野、尾野泰幸)
『Music From Big Pink』
1968年 / Capitol
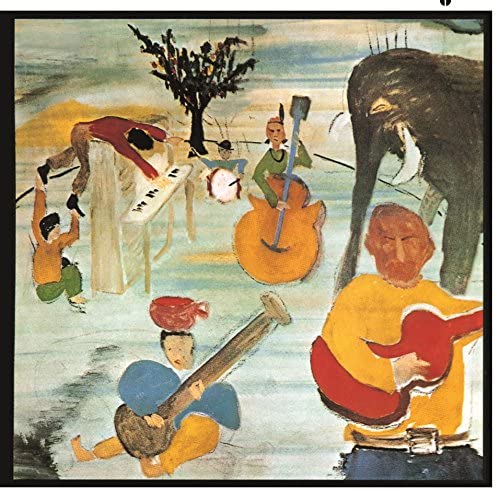
本作についてロビー・ロバートソン曰く「リトル・ウィリー・ジョンのユーモアと、ステイプル・シンガーズ風の歌、スモーキー・ロビンソン・マナーの高音ヴォイスの合体で、歌詞はハンク・ウィリアムスの影響を受けている」とのこと。
20世紀初頭の写真から抜け出してきた亡霊のような風体。以降”暖かみのある音像”の象徴とされる埃っぽさを意図的に狙った木造家屋風録音(プリ・ローファイ?)。教会音楽や40年代以前のアメリカ音楽を思わせるオルガンやホーン・セクションの鳴らし方や奏法は当時のロックやソウルのどのレコードとも全く異なる異質な音。とりあえずで付けられた匿名的バンド名。ジャケットを開けばメンバーとその家族の集合写真。ロックは両親や大人の立て前への抗いであったなら、本作は明確にフラワームーヴメントのまっただ中、かつてブルースやジャズだったはずの過剰に電気増幅されたロックへのロック側による初めての内部告発。リリース当初からある種の懐かしさを纏った音楽であったはずだが、退屈なレコードに退屈する事があっても飽きる事がないように、このレコードの纏う神秘的なノスタルジアはいつの時代に誰が聴いてもきっと同じような感覚を憶えるのではないだろうか。(岡田拓郎)
『The Band』
1969年 / Capitol

てっきり米南部で作られた音だと思っていた本作が、実はカリフォルニアはハリウッド・ヒルズにあるサミー・デイヴィスJr.の豪勢な自宅を借り切って制作したものだと知った時には、愕然と……というよりもまんまとしてやられたことにむしろ清々しい思いがした。今は何かとリアリティと正しい情報が求められるが、ことアートや創作物に関しては、想像力を働かせながら作り上げていく豊かさにまさるものなど実はないのではないか。実際、例えばロビー・ロバートソン作でリヴォン・ヘルムが歌う「The Night They Drove Old Dixie Down」では南北戦争の際に南部軍司令官だったリー将軍が描かれているが、歌詞を書くにあたり、リヴォンはロビーを連れて図書館に行き研究を重ねたという。南北戦争の歴史や地理を彼らはカリフォルニアで想像しながら学んだというのだ。その結果、この曲はザ・バンドの十八番とも言える二分割によるタメ気味のリズムが鮮やかに敷き詰められた代表曲となった。曲の終盤に聞こえてくるガース・ハドソンによるトランペットはまるで騎兵ラッパ「タップス」のようだが、ザ・バンドの特性・個性がそうしたイマジネーションによってもたらされたことは特筆に値するだろう。前作同様ジョン・サイモンがプロデュースしたこの素晴らしきセカンドが本当に南部で制作されていたら、全く違う手応えの作品になっていたかもしれないが、それが果たして本当に歓迎すべきやり方かどうかは全く別問題なのである。カナダで最高位2位を記録、最も商業的成功を収めた1枚。(岡村詩野)
『Stage Fright』
1970年 / Capitol
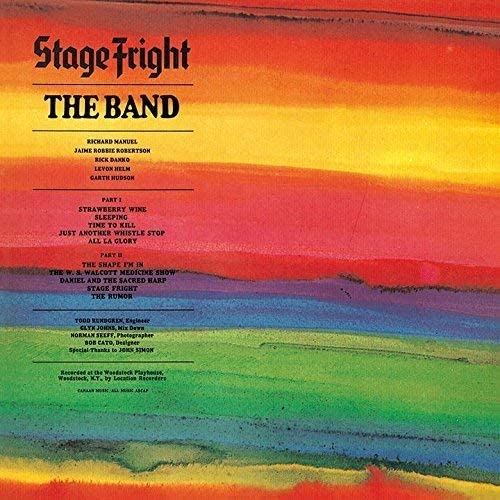
前2作がもたらした急激な名声、毎日同じことを繰り返すツアーへの閉塞的なムードを打開するべく“一発録り”で制作された『Stage Fright(舞台恐怖症)』が、元祖無観客ライブ作品となったのはこんな経緯。当初スタジオに観客を迎えながら前作までとは異なるあまりシリアスではない軽薄で逃避的な”全曲新曲ライブ”を収録する予定であったが、ウッドストック・フェスティバルのようなドンチャン騒ぎを恐れた町の議会はこの計画に強い反発を示しため、急遽ウッドストックのプレイハウスを仮説スタジオに改造し無観客のステージ上で本作の制作が進められた。バンドの行き違いは少しずつ目に見える形となって現れ、エンジニアにはロビー推薦のトッド・ラングレン、レヴォン推薦のグリン・ジョンズの2人が迎えられ異なる質感のトラックが混在する結果となった。
アルバム冒頭、軽やかにドライヴする「Strawberry Wine」や、全2作とは異なる粘り気の少ない乾いた全編のサウンドにはじめは困惑するほどのスタジアム・ロック的”軽薄さ”や”逃避”のムードを制作当初の思惑通り感じ取れるかもしれないが、切迫するパニック感のまま突き進む「Stage Fright」、名声とゴシップそしてその代償を歌う「The Rumor」(皮肉な事に資本主義に対する痛烈なカウンターとして映った彼らも結果として資本主義の闇に呑み込まれ、固く結ばれていた絆もこの後ものの数年でするりと解けてしまう事になる。)など、不安と疲労といった対照的なイメージが浮かび上がる。(岡田拓郎)
『Cahoots』
1971年 / Capitol
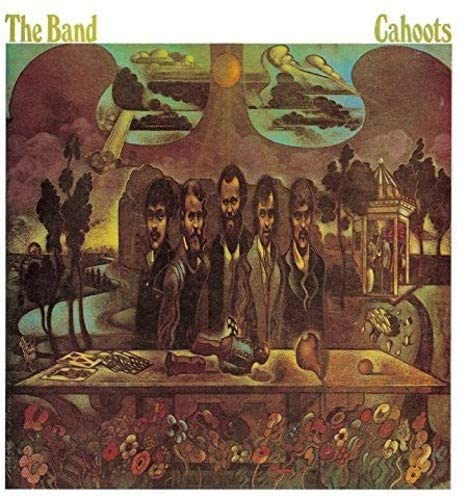
細野晴臣が『Heavenly Music』(2013年)で、本作収録のボブ・ディランによる「When I Paint My Masterpiece」をとりあげたことで、ザ・バンドのディスコグラフィーでもあまり人気のないこの4作目の印象が少し変わった。ディラン自身もセルフカヴァーを発表しているが、細野はあくまでザ・バンドのアレンジ……リヴォン・ヘルムがヴォーカルをとっている本作2曲目をお手本にしている。もちろん細野は2012年に亡くなったリヴォンへの追悼を込めたのだろうが、同時にザ・バンドの親しみやすさ、聴きやすさにフォーカスする結果にもなった。実際に本作は、「When I Paint My Masterpiece」だけでなく多くで自らマンドリンやギターを弾いたリヴォンの朴訥とした歌やプレイが、ほとんどをロビーによって書かれた曲そのものを引き立たせるような一面もある。メンバーで唯一のアメリカ人である彼の持つ素直さ、ポップさはこのアルバムで最も堪能できると言ってもいいかもしれない。彼らを見出したマネージャーのアルバート・グロスマンがニューヨークはウッドストックの自宅敷地内に作ったベアズヴィル・スタジオで録音。散漫との声もあるが、アラン・トゥーサンがホーン・アレンジで参加した「Life Is A Carnival」、ヴァン・モリソンとリチャード・マニュエルとがデュエットした「4% Pantomime」などのトピックもある、今こそ再評価したい中期迷走期の1枚だ。(岡村詩野)
『Rock of Ages』
1972年 / Capitol
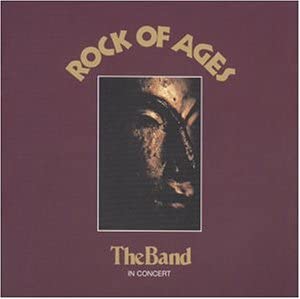
最新リマスタリングで聴くとなおさら音の良さに痺れるが、イントロダクションに続いて始まる「Don’t Do It」(マーヴィン・ゲイ「Baby Don’t You Do It」カヴァー)の最初のベース音が全てと言ってもいいかもしれない。それは、エレクトリックなロック・バンドとしてのダイナミズムと抑揚を見事に伝える最高の“掴み”。ロニー・ホーキンスやボブ・ディランのバックをつとめたキャリアの序盤を経て、堂々大都会で暮れにメイン・コンサートをやれるまでに至った彼らの表現力は、この時点でもう既に最高潮に達している。ザ・バンドのライヴ・アルバムと言えば誰もが最後の『The Last Waltz』(1978年)を挙げるだろうが、本作の方が演奏はエネルギッシュで雄弁だ。1971年12月28日から31日までニューヨークのアカデミー・オブ・ミュージックで行われた4日間の演奏をまとめた2枚組ライヴ・アルバム。実際のコンサートでは、アラン・トゥーサンがアレンジしたホーン・セクションが参加したセッションと、ザ・バンドのメンバーだけによるセッションとに分かれていたが、ここでは曲順含めて再構成されていてライヴ・アルバムとしての大きな流れ(物語)が作られているのがいい。2000年のリイシュー時にボーナス・トラックとしてボブ・ディランが参加した曲もいくつか追加されたが、ディランが登場するや沸き起こる熱狂的な客の反響は少し複雑な気分にもなる。(岡村詩野)

映画劇中で語るロビー・ロバートソン
『Moondog Matinee』
1973年 / Capitol

漲り、張り詰めた創作エネルギーをコントロールするかのように、気楽な雰囲気すら漂うロックンロールやR&Bのオールディーズ・カバーにより構成された作品であり、ザ・バンドの「まなざし」が刻まれたアルバムでもある。白人音楽市場における黒人音楽の可視化の大きな要因をなし「ロックンロール」の伝播に貢献したDJ、アラン・フリードのラジオ番組名を作品名として引用。本作を通じて、ザ・バンドは自身のルーツたるクラレンス・ヘンリーが、ファッツ・ドミノが、プラターズが、そしてサム・クックが歌った曲たちの視線を、カバーを通じて自らの視線と交差させていく。何よりも重要なのは50年代における白人音楽と黒人音楽の混交の象徴たるエルビス・プレスリー「Mistery Train」。本曲は多方からの視線が行き交う本作の結節点としてあるのみならず、「まなざし」のアルバムとしての本作の特徴を明確に示す。(尾野泰幸)
『Northern Lights – Southern Cross』
1975年 / Capitol

いまや兄弟のような彼らの絆がもう既になくなってしまったのを象徴するように、メンバーそれぞれパート別の録音がされた。計算され完璧に適切に配置されたアンサンブルは、かつての“同じ屋根の下”のような暖かみとはかけ離れ、どこかヒヤリとした怖さ……それほどの完成度を感じさせる。時代の移ろいもあるが、ともすればスティーリー・ダンのような。ただそれを、作品の善し悪しに紐付けるのはナンセンスで、個人的にはザ・バンドの名盤と言えば『Music From Big Pink』、この『Northern Lights』を挙げたい。
作詞作曲がいよいよロビー1人になっているのは、このバンドのその後を知る私たちとしては何度見てもいたたまれない気持ちにさせるが、3人のヴォーカルの個性を汲んだ持ち回り、アンサンブルはザ・バンドの最も美しいアルバムの姿を再び取り戻す事となる。「Acadian Driftwood」と「Ring Your Bell」は3人で歌い回す「The Weight」スタイル。寒い夜の駅で断片的な記憶が過る「Hobo Jungle」や、“決して輝かない太陽”、”絶え間ない雨”がイメージされる「It Makes No Difference」で滲ませる深い悲しみを、ロビーが感じていたバンドが辿る旅路の終着地点のうすうすの気づきを重ね合わせてしまうのは野暮かもしれないが、パーソナルな感情を古いアメリカ小説の人物に置き換え演じさせ、それを物語るように別の誰かが歌う感情の傍観者的スタイルが、ここでより深い心の揺さぶりを与えているように感じる。(岡田拓郎)
『Islands』
1977年 / Capitol
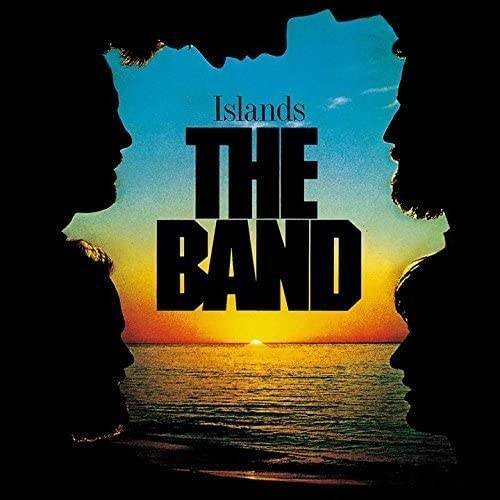
文脈抜きで聴くことのできない作品ではある。《Capitol》との契約上の都合から半ば寄せ集められた曲群によるザ・バンドのオリジナル・メンバーによるスタジオ録音最終作。しかし、あえてその事実を捨象し、いまの視点から聴き直すならば全体の基調となっているレイドバックしたメロウなサウンドと、滑らかなホーン・セクション、薄い膜のようなエレクトリック・ピアノの響きの素晴らしさに驚かざるを得ない。現在でいえばデストロイヤー『Kaputt』(2011年)やホイットニー『Light Upon the Lake』(2016年)、さらにいえばここ日本で湧き出る所謂“タイニー・ポップ”作品群に、上述したサウンドの息吹を垣間見ることも可能だろう。ウェスト・コーストの陽光とサザン・ロックの土の匂いをあの時代に置き去った現在における本作の輝きは、過剰さとは無縁のエヴァーグリーンなバンド・サウンドがまとう「軽さ」にこそある。(尾野泰幸)
『The Last Waltz』
1978年 / Warner
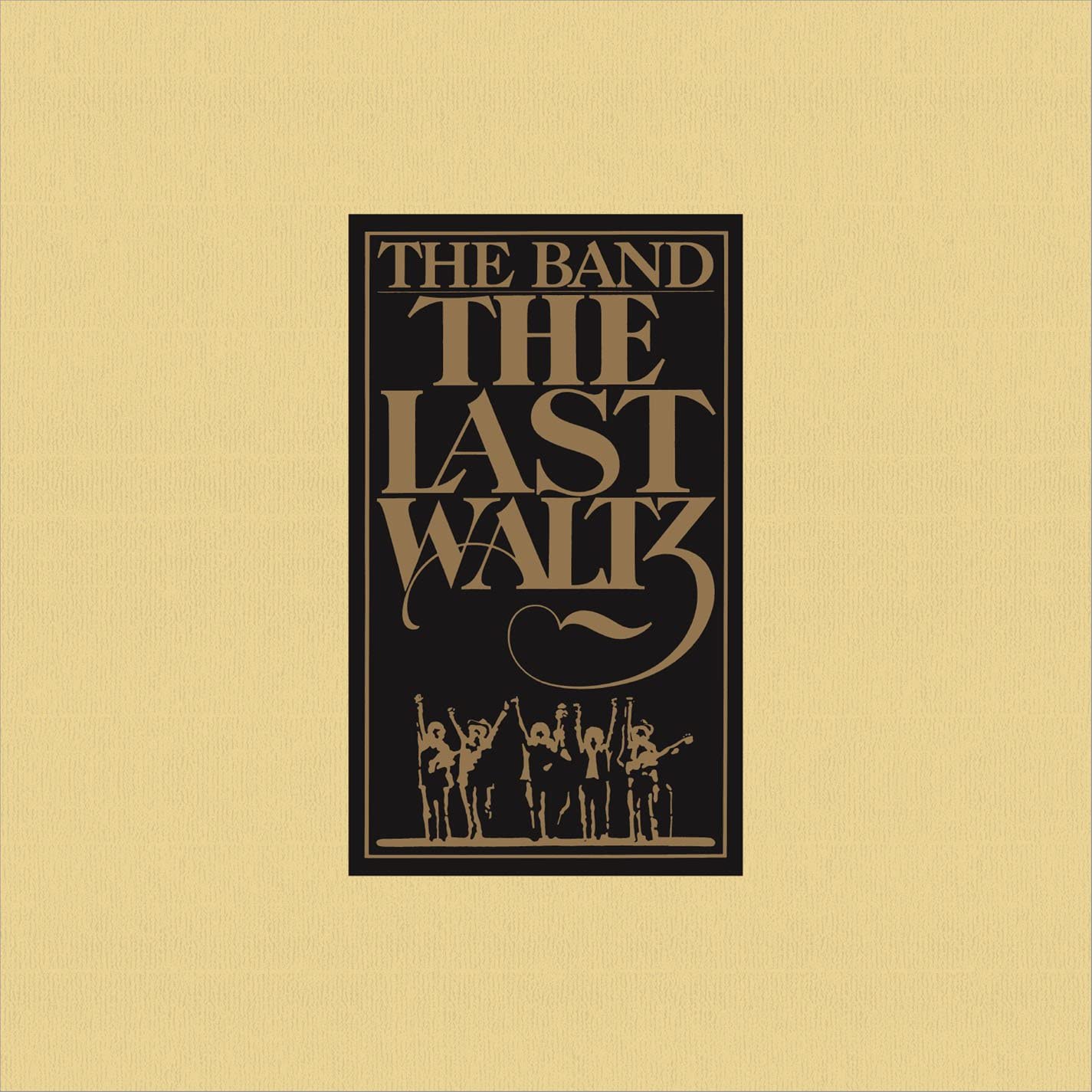
ラスト・コンサートの様子を記録した映画のサウンド・トラック。客演する数多のレジェンドの中でも、彼らの恩人かつ盟友のボブ・ディランによる「Forever Young」での「いつまでも若く」という熱唱と、それにまとわりつくロビー・ロバートソンの叫ぶギターが胸に突き刺さる。だが本作の山場は、グリル・マーカスが古典『Mistery Train』で述べたように、ザ・ステイプルズを迎え、運命に翻弄される男の悲哀を描く「The Weight」、南北戦争後の南軍兵士の悲哀と郷愁を歌う「The Night They Drove Old Dixie Down」の(映画では連続する)2曲。そこに見える、例えばアラバマ・シェイクス『Sound & Color』(2015年)を想起するような、R&B・ブルーズを土台/基調としてきたロック・バンドが鳴らす憂いと希望、多元性の精神の発露にこそ、今、本作を聴く理由がある。(尾野泰幸)

『ザ・バンド かつて僕らは兄弟だった』
角川シネマ有楽町、渋谷WHITE CINE QUINTOほか全国順次公開
配給:彩プロ
出演:ザ・バンド(ロビー・ロバートソン、リック・ダンコ、リヴォン・ヘルム、ガース・ハドソン、リチャード・マニュエル)、マーティン・スコセッシ、ボブ・ディラン、ブルース・スプリングスティーン、エリック・クラプトン、ピーター・ガブリエル、ジョージ・ハリスン、ロニー・ホーキンス、ヴァン・モリソン、タジ・マハール
監督:ダニエル・ロアー
©️Robbie Documentary Productions Inc. 2019
関連記事
【FEATURE】
ボブ・ディラン『Rough And Rowdy Ways』
http://turntokyo.com/features/bob-dylan-rough-and-rowdy-ways/
【FEATURE】
The Young Person’s Guide To Bob Dylan
ボブ・ディランこそ時代の革命家で歴史の継承者だ
http://turntokyo.com/features/features-bobdylan/
【FEATURE】
Another Story Of Bob Dylan
ディランに捧げる断章とマルジナリア
http://turntokyo.com/features/bobdylan-okadatakuro/
