何がすごくて、ユニークなの?
韓国の最重要バンド、シリカ・ゲル(Silica Gel)を4つの視点から紐解く
2022年夏頃以降のシリカ・ゲルの韓国における勢いはまさに向かうところ敵なしだ。シングル「NO PAIN」(2022年)は韓国のロック・ファンにとってのアンセムとなり、2023年8月に発表した「Tik Tak Tok(feat. So!YoON!)」はMVがインディ・バンドでは異例の早さの、公開からわずか9日で再生数100万回突破、受賞者/出演者のほとんどがK-POPアイドルの昨年のMelon Music Awardsでの「Best Music Style」部門の受賞、圧巻のライヴ・パフォーマンスも話題になった。ニュー・アルバム『POWER ANDRE 99』(2023年)を発売前に全曲アルバム収録順で披露した昨年11月の3日間の単独公演(キャパ2,800人)、今年5月に行った3日間の単独公演(キャパ4,000人)、いずれもチケットは発売と同時に即完、いま最もライヴのチケットが取れないバンドである。ちなみに前者のライヴの模様は映画化され、8月より韓国の映画館チェーン《CGV》で公開されることとなっている。シリカ・ゲルはここ数年アクセルを緩めることなく活発な活動を続け、一気にトップ・バンドの一組となった。
Melon Music Awards 2023でのシリカ・ゲルのパフォーマンスそんなシリカ・ゲルの歩みに、昨年夏頃から一部の韓国のメディアやロック・ファンは、「シリカ・ゲルが韓国にバンド(あるいはロック)・ブームを巻き起こす」といった言葉を使うようになった。しかし、私はそうした向きには同意したくない。実際、現在韓国では彼らのようなインディ出自のバンドから、DAY6のようなアイドル、TVのサバイバル番組で人気を得たバンドまで広義の“バンド・ミュージック”が流行中だ。またシリカ・ゲルをきっかけに“バンド・ミュージック”を聴くようになったリスナーも多くいるだろう。ただ、シリカ・ゲルはそもそも典型的なロック・バンドでいることを拒否しようとしているし、その作品も活動スタイルも、特定のシーンやムーヴメントを代表しているとは言いづらいくらいユニークで、多様な側面を持っている。シリカ・ゲルの成功はシーンの変化とイコールではないし、彼らに匹敵するフォロワーの登場を安易に期待することは彼らの独自性、それを探求してきた長く複雑なプロセスを軽く見ていることになると思うのだ。
では、筆者は具体的にシリカ・ゲルのどんなところに独自性を感じ、それが他のバンドには簡単に再現できないものだと思っているのか。その多様な側面を、イベント以外では6年半ぶりとなる単独来日公演を控えたいま、4つに分けて、紐解いていきたい(尚、本稿では便宜上、彼らのキャリアを兵役により活動をストップする2018年初めまでを第一期、兵役から復帰し、活動再開、メンバー構成も変化した2020年の夏以降を第二期とする)。
1.ジャンルの混交、作曲や録音の方式……あらゆる分野でチャレンジングで、実験精神に溢れたバンド
筆者がシリカ・ゲルにずっと夢中でいられるのは、発表する作品、ライヴ・パフォーマンスが毎回新鮮で、次は何を起こしてくれるのか常にワクワクさせてくれるからだ。彼らのキャリアを追いながら確認してみよう。
彼らのサウンドは、デビュー当初から斬新で、スケールの大きいものだった。モダン・サイケデリア、ドリーム・ポップ、ポストロック、エレクトロニカなどを組合せ、曲の途中で展開が変わったり、不規則なリズムを取り入れたりと実験的。若いが故に、初期はやりたいことがとにかく詰め込まれたような楽曲、アルバムが多かったが、そのチャレンジングな精神は聴き手に伝わっていただろうし、只者ではないと認識され、2017年の韓国大衆音楽賞で「今年の新人賞」を受賞、韓国のテレビ局《EBS》が主催する、インディ・シーンの新人アーティストへの登竜門「ハロールーキー大賞」を受賞するなど注目を浴びていた。
第二期に入ると、シングル「Kyo181」(2020年)とその次作「Hibernation」(2021年)でサウンドも一変した。削ぎ落とした音数と、ヒップホップのようにループを重視した制限ある曲構成の中で、ミニマムなサイケデリック・サウンドと、当時影響を受けていたというワンオートリックス・ポイント・ネヴァーを思わせる先鋭的なエレクトロニカ・サウンドをぶつけ合い、オリジナリティと実験性を突き詰めた。またその後のシングル「S G T A P E – 01」(2021年)、「Desert Eagle」(2021年)、「I’MMORTAL」(2022年)も、どれも別々のジャンルのトラックを断片的に組み合わせて完成させたような曲ながら、それぞれ違った色を持っていて、そのアイデアにまたも驚かされた。
一方、2022年の夏にはバンドにとって転機となる「NO PAIN」を発表。キャッチーなメロディやギター・リフ、「僕が作った家で皆一緒に歌おう」というこれまでになく開かれた歌詞のこの曲で、ファン・ベースを一気に拡大した。読者の中にもシリカ・ゲルというとまずこの曲を連想する方も多いだろう。ただこの曲を境に、サウンドはまたも大きく変化を遂げ、音や録音方式についての探求もそれまで以上に深くなっている。
その変化は、ギターの音で表現するなら、以前の彼らが、フェイザー・エフェクトなど空間的な効果でサイケデリックで、抽象的な音を出していたとするなら、「NO PAIN」以降はピッチシフター系のエフェクトを使い、レーザーのように鋭く、輪郭のはっきりした音だ。またシンセサイザーやサンプラーもより積極的に使うようになったし、兼ねてから「ヴォーカルも楽器の一部」というモットーを持っていた彼らは、ヴォーカル・エフェクトも多用するようになり、その音色はカラフルなものから、機械的で不協和音のような複雑な音が強調されるものに変わった。そして、この曲の作曲や録音のプロセスを記録した動画を見てみると、どのギターを、どの厚さの弦を使って、どのエフェクターを通し、どのアンプで出力するか繊細に悩みぬいた様子や、メンバーのアイデアでテープ・レコーダーを採用したエピソードなども垣間見ることができる。「大衆的になった」という声さえ聞かれるこの時期のサウンドの進化のプロセスもそう単純ではなかったのだ。
最新アルバム『POWER ANDRE 99』はそうした「NO PAIN」以降の彼らの探求のゴールのような作品だ。各楽器の音は鮮明に聴こえ、それぞれが合わさりバンド・サウンドとなったときのダイナミズムも圧巻。ヘッドフォンをつけた瞬間、アリーナのような大きな空間でのライヴが目の前に広がるようだ。後日ドラマーのキム・ゴンジェは、新曲を録音するに当たり彼らは使用するアンプやマイクを増やしたり、録音スペースの広さや高さ、曲によって使用するスネアやハイハットのチューニングなどかなり細かく気を遣ったことを話してくれたのだが、当時の彼の言葉からは「ここまでやるのは当たり前」、「やらなきゃいけないことをやっただけ」という強い思いが伝わってきたのをはっきり覚えている。
一つの作品や、一定の時期ごとに、モードを変え、その中でジャンルを混ぜたり、曲構成や、録音方法などで実験的な試みをしてきたシリカ・ゲル。その「変化」を求める姿や、定型に囚われない自由な表現を模索する様は、徹底的だ。大衆が求めていないであろう音であっても、リスクを冒してやりたいとおりにやってみるという勇気も持っている。いつかはギターを一切使わないアルバムや、1分に満たない曲ばかりを集めたアルバムを作るかもしれない。そういう未来の変化についても期待を膨らませられる。
もう一つ重要なのはその実験プロセスだ。ここまで挙げた例からは彼らが、求める完成度や実験性のためには苦労や遠回りも厭わないメンタリティを持っていることがよく分かるし、それが彼らの独創性に繋がっていると気付かされもする。メンバーの中で特に録音や音響への拘りが強いギター・ヴォーカルのキム・チュンチュは、あるインタヴューで自らが「サウンドの黄金期」だと考える60年代や70年代のポップ音楽の録音方式について「ものすごく非効率的なミキシング・コンソールを使ったり、ハードなやり方」だと評しながらも、それが「実際に聴こえる通りのサウンドをよく具現化して」いるので、むしろ「良い音を作るのに楽(なやり方)だ」と語っていて印象的だった。彼らがどれだけの高みを目指しているのか、そのスケールの高さも伺えるだろう。
2.映像、衣装、ゲーム…あらゆるアート形式に拡張するアーティスト集団
シリカ・ゲルの作品は楽曲そのものだけではく、その世界観が拡張されたMV、カヴァー・アート、メンバーの衣装まで、幅広くコンセプトに拘りが感じられる。アルバム『POWER ANDRE 99』と、その時期の一連のカヴァー・アートの関係を例に述べてみよう。
まずサウンドに目を向けみよう。オープニングの「On Black」の混沌を切り裂くような強烈なギター・リフ、「Juxtaposition」の疾走するようなインタールード、「Realize」のレーザー光線のような鋭いギター・リフ、「APEX」の不調をきたした機械から出てくる不協和音のようなリフレインなど、全体がメカニカルな質感の音像で統一されている。そしてそれらは、劇的な曲展開も相まって、メンバーたちもファンだと公言する『新世紀エヴァンゲリオン』、『攻殻機動隊』シリーズ、『AKIRA』のような近未来のディストピア世界を描いたSFアニメを想像させた。
それに対してカヴァー・アートの方はどうか。カリフォルニアを拠点アーティスト、Daylen Seuによって制作された、「Kyo 181」(2020年、『POWER ANDRE 99』には収録されていない)から『Machine Boy』(2023年)、「Tik Tak Tok」(2023年)、そして『POWER ANDRE 99』までの一連のカヴァー・アートを見てみよう。
「Kyo 181」カヴァー・アート 『Machine Boy』カヴァー・アート
『Machine Boy』カヴァー・アート
 「Tik Tak Tok」カヴァー・アート
「Tik Tak Tok」カヴァー・アート
 『POWER ANDRE 99』カヴァー・アート
『POWER ANDRE 99』カヴァー・アート

どれも白と黒を貴重に、機械的かつグロテスクなキャラクターが描かれたコンセプチュアルなものだが、先述のサウンド面の特徴とマッチしていることがわかる。こうしてサウンドとカヴァー・アートのビジュアルを関連させることで、リスナーは楽曲を聴いたときに想像力をより働かせることが出来るだろうし、多面的な鑑賞も可能になる。
そもそもシリカ・ゲルは当初から平凡な「ロック・バンド」ではなかった。後から合流したベースのチェ・ウンヒを除き、バンドは全員、ソウル芸術大学の同じ学科生で、2013年の《平昌ビエンナーレ》の展示に参加するためにVJたちを含めた8人で結成された。バンド演奏とその背景へのVJ演出を同時に行うことが多く、当時の彼らについては「パフォーマンス・チーム」と呼ぶ方が正しいだろう。その《平昌ビエンナーレ》出展のために書かれた曲で構成されたデビューEP『Pure sun』(2015年)は、だからなのか、演奏に溶け込み言葉が聴き取りづらいヴォーカル、静と動を行き来する組曲のようなEPの構成など独特だ。機能的にはポップスというよりはバックラウンド・ミュージック、空間的にはライヴハウスだけでなく、美術館の展示空間のような場所にもマッチしそうである。また同EPのフィジカルCDは、CD盤を実際のシリカゲル・パッケージに封入、カヴァー・アートもメンバーたちが直接プリントしたというし、翌年に発表したデビュー・アルバム『Silica Gel』ではメンバーがスプレーや筆、素手を使って描いた水彩画をカヴァー・アートに使ったり、デビュー当初から楽曲外でも、尋常でないアート全般への関心を形にしていた。
『Pure sun』のCD(写真は筆者の知人より提供) 「sister」(『Pure sun』収録)
『Silica Gel』カヴァー・アート
「sister」(『Pure sun』収録)
『Silica Gel』カヴァー・アート
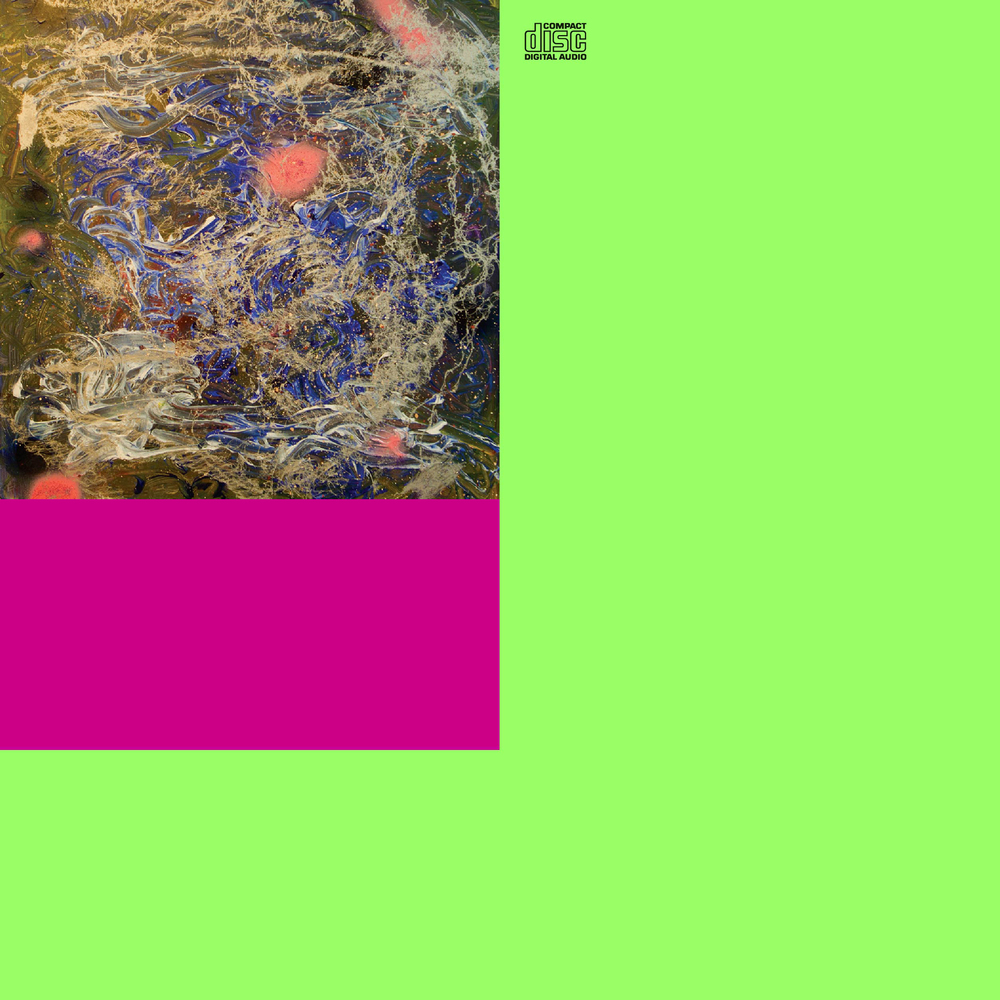
第二期に入り、VJメンバーたちが脱退した後もそのスタイルにブレはない。例えばパンデミックでファンを前にしたライヴが出来なかった2020年にはSo!YoON!、Y2K92をゲストに、オンライン・ライヴ《Syn.THE.Size》を開催。複数の部屋と階段の踊り場をライヴ・スペースにし、スペース毎に異なる色のライティングを用いながら、その模様を反対側の建物からも撮影。オンライン・ストリーミングならではの視覚的な演出を企画した。
オンライン・ライヴ「Syn.THE.Size」その後も、2021年に発表したシングル「Desert Eagle」では、シリカ・ゲルのMVを何度も手掛けている映像監督、MELTMIRRORや、デザイナーのSUPERSALADSTUFF(Haeri Chung)とコラボし、楽曲の世界観を込めたTRPG(テーブルトーク・ロール・プレイング・ゲーム)を製作、販売。また2023年のシングル「Mercurial」はファション・ブランド、SAN SAN GEARと共に企画し、曲のテーマやサウンドに合った衣装も制作した。
「Desert Eagle」のTRPGゲームの解説動画作った楽曲を、目でみる映像に、身につける衣装に、他者と交流し様々な感情を感じられるゲームにと、どんどん他のアートに拡げるシリカ・ゲル。そうすることで、リスナーは多面的な鑑賞や、より自由な解釈をすることも出来る。彼らは音楽、映像、ファッション、ゲームという別々のアートフォームも、その深部では互いリンクし、影響し合っている。そういうマインドを持っているだろうし、その結果が、次の章で述べる幅広い分野のアーティストとの交流や、互いに刺激を受け合うような関係性にも繋がっている。
3.自立した「個人」を尊重し、信じるチームプレイ志向のグループ
・「シリカ・ゲルの音楽を一言で表現するなら、“チームプレイ音楽“だと思う。『攻殻機動隊』に『僕たちは全ての構成員が一つの大義に向かっていく“チームワーク”ではなく、各自が自由に才能を発揮した時に自然に生まれる結果物。“チームワーク”ではなく、“チームプレイ”』という言葉が出てくる」
(https://youtu.be/7_IPHv1txCE?si=RvroLngqchsp3rAj)
・「それぞれが別な機能を持っているモジュールで、その機能を常に開発したり何かを付け加えたりして、全員が集まった時に一つになる」
(https://www.folin.co/video/6732)
これらはヴォーカル・ギターのキム・ハンジュがメンバー個々人とシリカ・ゲルというバンドの関係性について、インタヴューで語った言葉たちだ。この言葉の背景を紐解くために、一度メンバーそれぞれのバックグラウンドや個人活動について触れておこう。
ヴォーカルとギター、鍵盤楽器を担当し、メイン・ソングライターの一人であるキム・ハンジュは大衆音楽以外にも、現代音楽、クラシックなどからも強く影響を受けているらしく、それらはシンセサイザーやサンプラー、ヴォーカルの変声を活用した作曲手法や、「Machineboy空」や「Ondine」のピアノ・ソロ演奏など、シリカ・ゲルでの活動にもはっきりと反映されている。またソロ活動の幅も広く、最近自身が所属するクルー、Bat Apt.のアルバムで初のソロ楽曲を発表しているほか、Kim Doeon(キム・ドオン)、Kim Oki(キム・オキ)、george、Tabber、Blaséなど多様なジャンルのミュージシャンの楽曲へのヴォーカル参加、人気バンド、SE SO NEON(セ・ソ・ニョン)やRMの楽曲などを手掛けたプロデューサー活動、先述のゲーム・クリエイターのクルー、ISVNでの活動、さらに最近ではKim Doeon、CIFIKAと共にトリオを組み、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーの来韓公演のオープニングを務めるなどキリがない。
キム・ハンジュと並びメインのソングライターであり、「Tik Tak Tok feat. So!YoON!」や「Desert Eagle」のソロ演奏でスーパー・ギタリストとしても脚光を浴びているギター・ヴォーカルのキム・チュンチュは、実は普段は韓国インディ・シーンで欠かせない役割を果たしているプロデューサーでもある。プロデューサーとしては、音響に関する深い拘りがあり、フォークやバロック・ポップ、70年代のポップ・ミュージックなど過去の音楽へのリスペクトを込めた、ヴィンテージで温かなタッチが特徴的で、Meaningful Stone(ミーニングフル・ストーン)『A Call from My Dream』、ユン・ジヨン『In My Garden』など彼がフルで手掛けたアルバムは特に必聴だ。そのほかソロ・プロジェクト、Playbookでも1枚のフル・アルバムとEPを発表したり、テレビ番組の音楽監督を担った経験もあったりと、プレイヤーとしてもプロデューサーとしても一流だ。
チームの結成を最初に企てたメンバー、ドラマーのキム・ゴンジェはジャズがバックグラウンドにあり、「Everybody Does」や「APEX」のソロからも分かる通り、手数の多いテクニカルな演奏が印象的だが、彼もまたシリカ・ゲルでのソングライティング、シリカ・ゲル外でもプロデューサーのNthoniusとのデュオ、Shirakami Woodsや、5人組バンド、Apneaのメンバーなど幅広い顔を持っている。
ベーシスト、チェ・ウンヒもまたシリカ・ゲルではソングライティングや「Realize」、「Ryudejakieru」でのMV監督も担っており、バンド外ではサイケデリック・ガレージ・バンド、Wah Wah Wahでギターを担当している。
ここからわかるのはシリカ・ゲルが多様なバックグラウンドを持ち、バンド活動以外でも自らの才能を発揮できる自立したアーティストの集まりであり、それが彼らの多様な音楽性の土台になっているということだ。それが特に象徴的に現れているケースが二通りあるが、一つはすべてのメンバーが作曲した曲が寄せられたEP『SiO2.nH20』(2017年)であり、もう一つがシングル「S G T A P E – 01」と「I’MMORTAL」だ。そして後者はその作曲方法がまさに先述のキム・ハンジュが使った言葉「チームプレイ」そのものである。
まずエレクトロニカ、ロック・サウンドが飛び出しては消えていく24分超えの「S G T A P E – 01」は、作曲のために4日間スタジオでともに寝泊まりしながら作ったという。さらに「I’MMORTAL」ではキム・ハンジュが作曲プロセスについて「ヴァースで繰り返されるテーマは僕が作って、その上の歌メロはウンヒが作ったし、その2つのアイデアが一つのパートの中で組み合わさりました。その次のブリッジはチュンチュが作ったし、それに続けて、コンジェ兄さんのドラムはどう入ってくればいいかと話し合いながら、作ったんです。ポップミュージックのフィールドでは複数人の作曲家たちが一緒に一つの曲を完成させるソングキャンプというものをやるじゃないですか」と語っている通り、シリカ・ゲル流の分業制作が行われている。またこうした作曲方法を取ることで、一度は使えないと思っていたアイデアや、一曲を書くには足りないが、発展性のある断片的なアイデアも、別なメンバーとの協業を経て、面白い作品に生まれ変わっていくのだ。
そして、その試みはシリカ・ゲルのメンバー内だけで完結してはいない。既にカヴァー・アートや衣装の例を述べた通り、シリカ・ゲルの周りには、彼らの多面的な作品を完成させるのに不可欠なコラボレーターたちが多数存在する。まずはレコーディングやライヴでのエンジニアを担っているシン・ジェミン。これまでの全ての作品に関わっているジェミンはキム・ゴンジェ、キム・チュンチュと同じ建物に個人スタジオを持ち、メンバーに近い場所で密にコミュニケーションを取り、シリカ・ゲルの楽曲を最終的にどんな音でリスナーやオーディエンスに届けるかにおいて、欠かせない役割を果たしている。映像ディレクターでは「9」をきっかけに「Kyo 181」、「NO PAIN」、「Mercurial」、「Tik Tak Tok」、「APEX」と多数のMVを手掛けてきたMELTMIRROR、「Desert Eagle」のMV、先述のオンライン・ライヴ「Syn.THE.Size」の演出を手掛けたペク・ユンソクがいる。衣装では「Kyo 181」のMV以降、SAN SAN GEARやHALOMINIUMが度々彼らの衣装を製作しているし、デザイン分野では先日の単独公演「Syn.THE.Size Ⅲ」でもポスター・デザインを行ったsupersaladstuffと頻繁にコラボレーションしている(このうちMELTMIRROR、ぺ・ユンソク、HALOMINIUMのイ・ユミ、SUPERSALADSTUFFらがキム・ハンジュと結成したクルーが先述の「Desert Eagle」のTRPGゲームも制作している「isvn」だ)。重要なのはこれらの協業はほとんどが一回限りではなく、継続的に続いていること。信頼できるパートナーとなって作品を共に完成させているのだ。
さらに付け加えれば、シリカ・ゲルは作品の解釈や拡張性を外部にも委ねる柔軟さを見せている。いくつかのシングルやEPで楽曲のリミックスを周囲のミュージシャンに依頼したり、ファンと共にアルバム『POWER ANDRE 99』から連想、イメージされるワードや世界観を膨らませるブレインストーム・ページを設けたことはその例だ。
シリカ・ゲルの「チームプレイ」は、個の能力や解釈を信じ、委ねてみること、異なるジャンルや立場の他者とも交流し刺激を受け、作品を豊かにしようという、開かれたマインドが基になっている。だからこそ、多様性に溢れた音楽、さまざまなアートフォームに拡張された表現が可能なのだ。《TURN TV》の動画インタヴューインタビュー・シリーズ「THE QUESTIONS✌️」で「タイムマシーンがあったとして、過去の音楽現場に行けるとしたら、どの時代のどんな現場を覗きたいか?」という質問にキム・ハンジュは、20世紀初めから中盤のニューヨークのシーンを答えに挙げ、その理由に「彼らが面白いのが音楽家同士だけでなく、ダンサーや芸術家が一つになってアバンギャルドなシーンを形成しているところ」だと答えていたが、この発言を聞けば、彼が理想とするコミュニティのあり方、コラボレーションに感じる可能性がどんなものかが分かるだろう。
4.すべてを可能にする主体性
ここまで述べてきたシリカ・ゲルの側面に共通していることであり、最後に強調したいのが彼らが持つ「主体性」だ。実験的なサウンドを試みること、音響に拘ることの基にある、自分たちが感じた課題や問題意識。他のアーティストや企業などとのコラボレーションを自ら発案すること、あるいは自ら決定を下すこと。それらも一つの例だ。
また、シリカ・ゲルは地理的、産業的な意味での韓国のバンド、あるいはインディ・シーンへの所属意識が薄いことを度々公言している。あるインタヴューでキム・ハンジュは「韓国でロック・バンドとして活動することにどういう意味を感じているか」という質問に対して、「(自分が)バンドマンだという意識はありません。他のメンバーがどう考えているかはわからないけれど、バンド・シーンに属してバンドとして何らかの意味を克服しなきゃいけないとか、そういうことからは自由になっているし、それが制作するときのアティチュードにも影響を与えていると思います。もし僕がバンドマンとしての意識が徹底している人だとすれば今のシリカ・ゲルのようなバンドをやっていないと思います」と即答していた。
シーンに所属しないということは表現や活動において自由でいることが可能だが、それだけ自らの積極的なブランディングも必要になるし、チャレンジングなことだ。また別のインタヴューで「どうしたらシリカ・ゲルのようになれるか?と聞かれたらどんな言葉を送りたいか?」という質問を受けたメンバーたちは、「誰か助けてくれる人を探すのではなく、誰かの助けになれる人になる方が早いだろうと考えて生きてきました」(キム・ゴンジェ)、「結局僕たちが成長しない限り何もできない。僕たちが自身が大きくなろう、という考えが大きかったです。そういうことが今の状況を作ったと思います」と話している。これは居場所や理想郷は産業の側やシーンが作ってくれるのではなく、自ら信頼できる人と協業することで作り上げるんだという、主体性が込められた発言だ。そうした考えを持ち、自ら一緒に活動できる信頼の出来る仲間との繋がりを拡げてきた彼らだからこそ、流行に左右されることもなく、シーンのインフラやコミュニティが以前より弱体化したとしても、ユニークな個性を持って、安定した活動ができているのだ。
そうして唯一無二になるとことは、ライバルは他のバンドやフォロワーでもなく、シリカ・ゲル自身になることを意味している。実際、ここまで述べてきたシリカ・ゲルが積み上げてきた実力やユニークさは、シリカ・ゲル本人たちにしか超えられない域に来ていると思うのだ。周囲や若いミュージシャンたちは彼らに並ぼう、超えようとは思わないかもしれない。その代わり多大な影響を与えていることは確かなはずだ。(山本大地)
2024年6月26、27日開催の来日公演情報は以下から
6月26日
https://www-shibuya.jp/schedule/017819.php
6月27日
https://www-shibuya.jp/schedule/018008.php
Text By Daichi Yamamoto
