ジャンル、活動拠点、カルチャーやメディアの交差にしなやかに立ち上がる理想の居場所、「Veronica」【パーティーはミラーボール? Vol.1】
パーティーはきっとそこに足りないものがあるから始まる。だとするとパーティーは、コミュニティやシーンと呼ばれるもののいつもは見えていない姿を映し出しているのかも?
足りないものをどのように満たしてきたのか、満たそうとしているのかを知ることは、コミュニティの歩み、ひいてはシーンの変遷と少し先の姿を知ることになるだろう。それに、パーティーの中心にはその街で生活する人たちがいるから、街の普段は見えていない姿を映し出しているとも言えるかもしれない。
本連載では、パーティーの、周囲の環境や状況を映して反射させるその特徴に注目して、ネットレーベル興隆以降の札幌のクラブ・シーンでパーティーを主催する人々に話を訊く。コミュニティやシーン、はたまた札幌という街について、話が重なることで見えてくるなにかがあったらうれしい。
Veronica
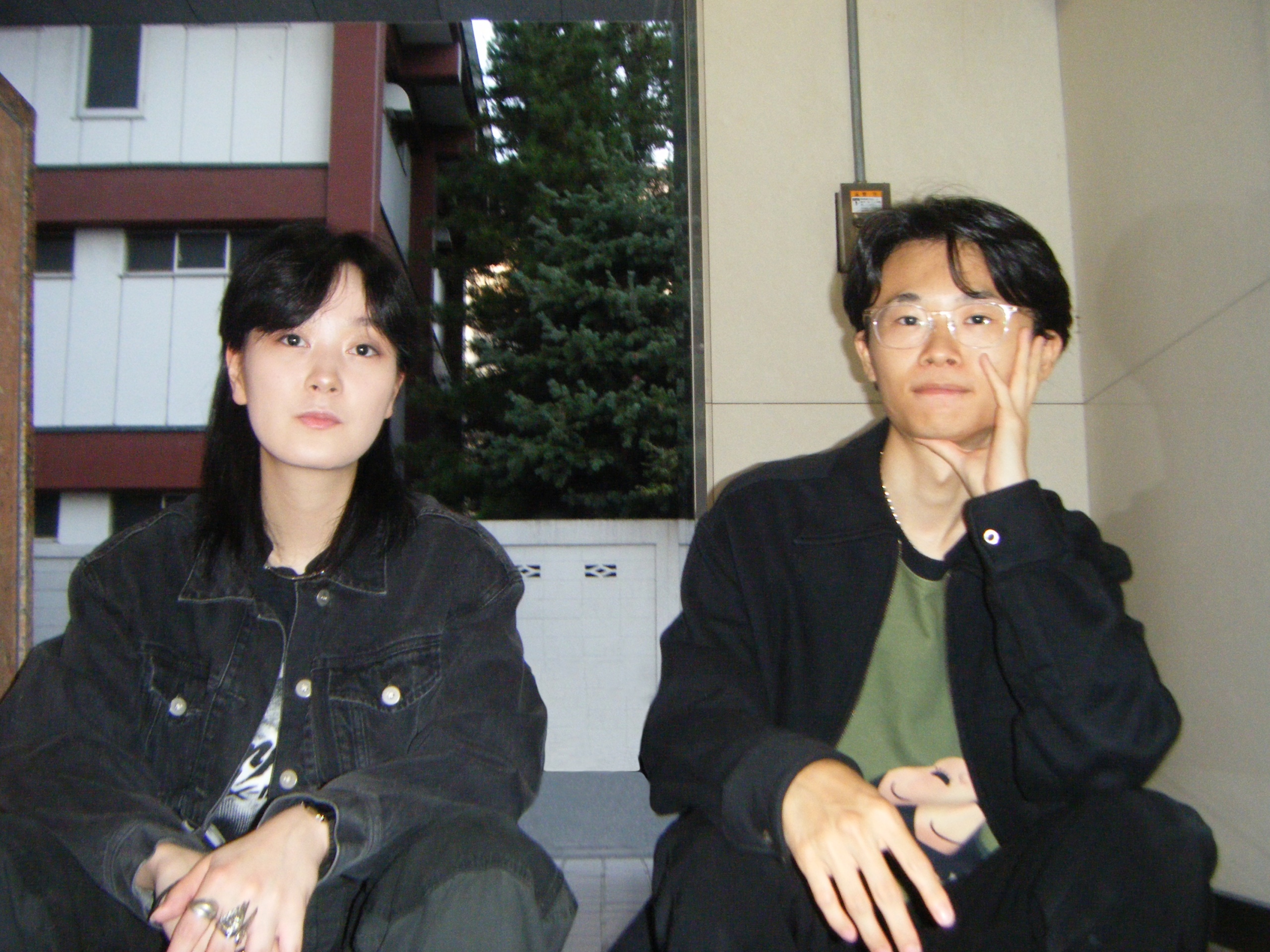
QiA(きあ)とケニアの宴(けにあのうたげ)によるパーティー、DJユニット。
両者は進学を機に札幌へ引っ越し、大学のDTMサークルで出会った。10年代のEDMのリスナーであったことやUKベース・ミュージックへの興味を共通項に持つ。現在、QiAは主にHolyをキーワードに「オリエンタル」という感性を捉え直すような音楽や、アマピアノやゴムなど南アフリカにルーツを持つ音楽を、ケニアの宴は《Shall Not Fade》周辺のクラブ・ユースなベース・ミュージックの質感を探求している。
「Veronica」ではパーティーを始めたきっかけでもあるB2Bがタイムテーブルに必ず組み込まれる。ユニットとしては「O.O.T.C. -Pasocom Music Club FINE LINE Release Party-」などに出演。
SoundCloudやネットレーベルなどインターネットを経由した音楽カルチャーが活況を呈した時代に、新たな札幌の音楽シーンが立ち上がるきっかけをつくったPARKGOLF、BUDDHAHOUSE、Qrionらと、ここ数年で札幌のユース・カルチャーを形づくりつつあるLAUSBUBらの間に位置する世代でもある「Veronica」は、どんなことに目を向けてパーティーをつくっているのか。札幌での活動について話を訊いた。
(インタヴュー・文/佐藤遥 Design/chiyo_midnight Photo/Hitomi Hanajima)
Interview with Veronica
楽しかったB2Bを原体験に自分たちの居場所をつくる
──改めて「Veronica」を結成したきっかけを教えてください。
QiA(以下、Q):コロナの時期にサークル活動の一環として《PLASTIC THEATER》を借りて音を出す日をつくったときに、ケニ宴(ケニアの宴)とB2Bをしたらすごく楽しかったことかな。お客さんが来ないから普段かけられない曲をたくさん流した。ジャンルも決めないでBPMさえ合っていればなんでもいいことにして。
ケニアの宴(以下、K):とにかく自分たちだけが楽しい時間だったよね。
Q:そうだね。こんな曲持ってたの?! みたいな驚きもあって、こういう、うちらが溜めている曲を出せる場所を自分たちでつくろうっていう話になった。
K:その頃、世界中みんながコロナで家から出られないから、《Boiler Room》の他にも、《Keep Hush》とか《HÖR》とかいろんなDJミックスのプラットフォームに注目が集まって、パーティーの配信も一気に増えて、それをたくさん聴いて観ていたことも大きいね。
Q:うん。うちらもこういうパーティーをしたいっていう気持ちで「Veronica」を始めた部分もある。わかりやすい例として、《Boiler Room》を観ていたら《Boiler Room》だってわかる雰囲気と熱気みたいなものがあるじゃん。そういうパーティーは自分が知る限り札幌になかった。だからYouTubeで観た動画のそういう空気を自分たちが体感したかったし、そういう場所を自分たちでつくりたいって思って。
──今まで好きな曲を自由にかけられるタイミングはあまりなかったんですね。
Q:やっぱりパーティーの色に少なからず合わせる必要があるから。そういうのは抜きで、うちらが純粋に好きな曲たちをかけたいと思ってた。当時はゲットーテックとかゴム(Gqom)とかにはまってたんだけど、これで盛り上がったら楽しいだろうなって。
K:出てたパーティーでゲットーテックをかけてもたぶん問題なかったと思うんだけど、そういう消極的で抑えた感じではなくて、自分たちがはまっている曲をメインとしてみんなに楽しんでほしかったんだよね。

──いちばん影響を受けたパーティーはどんなパーティーですか?
Q:ロシアの「Angelwave」っていうパーティーで、DJがジャンルも国も大またぎするミックスをしてるんだよ。たとえば中国のHowie Leeの楽曲みたいに結構エクスペリメンタルなものから、めちゃくちゃ綺麗なトランスまで、距離がありそうな楽曲やジャンルがひとつのミックスというひとつの時間に混在してきれいにまとまっている、その異国感がすごく好き。
──実際には存在していない国のような雰囲気ということですか?
Q:そう。空想上のうちらの国みたいな。「Angelwave」のいろいろなものが混ざっている雰囲気を自分らでも体現したいと思っていた。あとは、コロナでなくなっちゃうクラブも出始めてたし、サークルの活動もちゃんとできなくなっていたので、自分たちの居場所がなくなってしまう不安と守りたい気持ちもあった。だからそういうのを全部ひっくるめて「Veronica」を紹介するときに「異国感」っていう単語をよく使っている。
──なるほど。自分たちの理想の居場所のような意味合いもあるんですね。
憧れ、理想、フラストレーションを包み込む、シルキーでパワーのあるパーティー

──「Veronica」で大事にしていることのひとつは、先ほど言っていたようにパーティーにシグネチャーがあることだと思うのですが、おふたりは異国感のほかに「Veronica」にどんなイメージを持っていますか?
Q:「Veronica」っていう名前を発案したのはケニアだったよね。だけど、聖ヴェロニカのストーリーを読んでこの名前にしたわけではなくて、言葉の響きの神聖さとかハードではないしなやかな雰囲気が自分たちのイメージに近かったから選んだ。
K:繊細な中に力強さがある、シルキーなんだけどパワーもあるイメージ。ヴェロニカっていう女性の名前で語感が強いのもよかったんだよね。
──パーティーを説明するときに「まだ根付いていない音楽」という言葉もよく使っていますね。
K:そうだね。「まだ根付いていない音楽」っていうのは、今までのパーティーではメインにならなかったジャンルのことでもあるし、それだけじゃなくて、すでに広く知られている音楽のうちニュアンスが若干違う曲のことでもあるかも。たとえばガラージはクラブ・カルチャーの歴史の初期からあるジャンルだし、いろんなポップ・ミュージックに使われているからガラージと認識していなくても知らない人はあまりいない音楽だと思う。そこに自分は、おしゃれなイメージとは違う、ダークな感じの楽曲を選んでアプローチしたりしているかな。
──そのアプローチの繊細さやニュアンスの差異が「Veronica」らしさをつくっているように感じます。そういう感覚をゲストの人に伝えることも、パーティーのシグネチャーになる雰囲気をつくって守るために大事そうです。
Q:ゲストとして呼ぶ方にはできるだけ言葉を尽くして「Veronica」のことを説明するし、過去のパーティーの動画を送ったりもする。その人をブッキングした理由もしっかり説明して、とにかく「Veronica」という空間を体現するための一助になってほしいことを伝えるようにしている。

──これまでゲストの人たちにはどんな理由で声をかけたのでしょうか?
K:「Veronica」のゲストは基本1人で、じっくり3人でパーティーをつくっていくことにしているんだけど、初回のDOG NOISEさんはロングセットのDJを観たことがなかったし、自分たちが観たかったから。
Q:そもそもロングセットをする若い人もイベントも札幌にはあまりないからね。そのあと、《PROVO》でtovgoのDJを見たときにすごくシンパシーを感じて、tovgoみたいに同年代でかっこいいDJをしているのに、活動する場所が違うことで自分たちの周りにはあまり知られていない人をピックアップしようって思った。だから2回目はtovgo、3回目はOlgaに声をかけたんだよね。
K:今までかけられなかった音楽をやりたくて「Veronica」を始めたけど、ほかにも同じようなフラストレーションを抱えている人はいるんじゃないかなと思ったんだよ。遊びに行ったパーティーでOlgaさんはゴムをかけていたから、もしかしたら本当はゴムがもうちょっと掘ってやりたいジャンルなんじゃないかなって。
──自分たちのためのパーティーが、自分たちのためだけではないかもしれないと。そして、この間の4回目はフランキー(Frankie $)さんとmizutasssさんでした。
Q:夢叶っちゃう回だったね。フランキーさんは目標だったから。
K:UKGが好きだからフランキーさんのことはヴァイナルでDJやってる東京のUKGのDJとして必然的に知ってて。ミックスの仕方も全然違っていてレベルが違う人だから実際に聴きたいし観てみたいと思ってた。フランキーさんのセットはYouTubeでも聴けないような珍しい音源がほとんどだと思うから、それを北海道で聴かせることができたのはよかったよね。
Q:札幌にUKベースのパーティーはあるけど、あくまでも自分たちが想像するUKのアンダーグラウンドでしかないから、本物のUKベースのDJを札幌で観たいっていう気持ちがあったね。あとは、フランキーさんに影響を受けてDJを始めたmizutasssと一緒に今回のパーティーをつくれたのもうれしかった。
──異国感のイマジナリーな部分が、今回のパーティーを経て少し変わってきそうですね。
札幌の外が拠点の人にとっても、札幌では持て余す人にとっても、活動の場となるカルチャーに

K:フランキーさんに声をかけたのは、初めて道外の人を自分らで呼ぶチャレンジでもあったね。
Q:飛行機のチケットとかホテルの手配とか、初めてだとやっぱり難しかった。
──そうですよね。それでもやっぱり道外のゲストが来てくれることはクラブに行く側からしたらとてもうれしいのですが、DJの立場からはどうですか?
K:やっぱり気づきが多い。ミックスの仕方もかける曲も全然違うし。
Q:そうだね。 道外の人が来たら気合が入るし勉強になる。 それにゲストで来てくれる人たちに札幌のことを知ってもらえるのもうれしいかな。
K:SEKITOVAさんがゲストで来てた昨日(※)の「Sometime, Somewhere」も楽しかったね。
Q:「O.O.T.C.」も楽しかったし、最近、道外からのゲストが多いよね。
K:いい流れだ。
※インタヴューは7/8に行われた。
──でもこの7月みたいな状況は珍しくて、海外のDJやアーティストが日本でツアーするときも海を越えて札幌まで来ることはなかなかないです。少し話が広がりますが、札幌には自分たちが興味を持っているものや新しいものがすぐには入ってこないと思います。そういった点に物足りなさや事足りなさを感じることはありますか?
K:そうだね。音楽でもファッションでも、実際に楽しむという面ではたしかに事足りないかも。スピードでは絶対いちばんになれないし。でも、自分でアンテナを張ってセンスを磨いて、ちゃんと探せばそういう場所や機会はあると思う。まだ見つけられていないものも含めて。
Q:私の感覚だと、逆に札幌は事足りすぎてるかも。田舎の地元にいた頃と比べたら札幌はなんでもできるから何を選べばいいかわからなくなる。
──選択肢が多すぎるということですか?
Q:ノイズが大きい感覚のほうが近いかな。私は何にアンテナを張らないかのほうが大事なんだよね。そうじゃないと、あれもこれもってなって混乱しちゃう。「Veronica」が少ない人数でひとつの空気をつくることを目指しているのにも通じる部分があると思うな。
──なるほど。各々そういった思いを持ちつつ、札幌で実際にパーティーを重ねて気づいたことはありましたか?
K:当初はYouTubeで観るような海外のパーティーは周りにないじゃんと思っていたんだけど、20歳になって《Precious Hall》に行ってみたらみんなで音に向き合うパーティーは札幌にも当たり前にあって、自分が知らないだけだったって気づいた。でもそれと同時に、自分らと同年代の人たちがやっているそういうパーティーは見当たらなくて。 でもさらに「Veronica」を始めていろんな友達ができてきて、今はその考えも違ったかもなって思う。
──同年代で同じような思いを持ってパーティーをしている人がいたということでしょうか?
Q:小樽であった「CAVE」っていうパーティーはすごく楽しかったよ。
K:あとは、思ったよりみんないろんな音楽が好きってことにも気づいた。ヒップホップが好きな友達はダンス・ミュージックにはそこまで興味がないと思っていたんだけど、実は全然そんなことなくて。パーティーに誘ったら、こういうの好きなんだよねって言ってくれる人もいた。だからもっといろんな人を誘って楽しんでもらいたいって思ってきたかな。
──それは「Veronica」の当たり前にジャンルの壁なんてない雰囲気があったからこその出来事かもしれないですね。QiAさんはどうですか?
Q:それこそ小樽に行ったときに《冬虫夏草》のリムくんと話したんだけど、やっぱり札幌至上主義になってしまうところがあると思った。札幌以外にも面白い活動をしている人は絶対にいるのに、場所が離れているから私たちの目に入らないのかもしれないなって。札幌の外に住んでいる人がもう少し来やすい場所があればいいのに。
K:一つ一つの都市が離れてるから。渋谷と新宿みたいな距離じゃなくて、バスや電車で1時間かかる土地だからね。だからパーティーだけじゃなくてレーベルとかコレクティヴ的な動きを「Veronica」ができたら、そういう人たちのための場所になれるかも。もっといろんな「Veronica」があってもいいなって常々思っているし。
Q:ファッションはやりたいよね。
K:そうだね。パーティーにしても、フランキーさんに教えてもらってYouTubeで2002年ぐらいの《clubasia》の動画を見たんだけど、2ステップとかのパーティーでネイルもやってて。そこで服を売っててもいいなと思ったし、いろんなことを混ぜていきたいと思った。音楽があるから服も面白く見れるし、服があるから音楽の説明ができるみたいなこともあると思うから。
Q:音楽もファッションも、いろんな文脈を組み合わせて「Veronica」がつくり上げられている状態が私としても理想かも。
K:だからパーティーの中だけじゃなくて、常に発信できる場所がほしいよね。
Q:そうすることで札幌発のカルチャーのひとつになりたい気持ちもあるし。
K:やっぱり札幌で持て余している人が東京に行っちゃうことが悔しくて。 今まで何人も見てきたし、一緒にDJしてる仲間でこれからもそういう人が出てくるだろうし。でも「Veronica」がもっと大きくなれば札幌にいることを選ぶ理由のひとつになれるかもしれないしね。
Q:そうだね。ケニアは札幌で音楽やっていきたい気持ちが強いの?
K:札幌で音楽やっていきたいっていうか、今は札幌にいたい。仕事とか家賃とか生活のバランスがよくて、なんとかうまくやれてるし。「Veronica」をもっと大きくしていきたいしね。
Q:うん。まずは音楽だね。「Veronica」にインスパイアされて曲をつくってくれる人がいたらすごくうれしいし、ゲストの人が「Veronica」の空間を想像して選んできてくれた曲が「Veronica」とマッチしてるのも見てて本当にあがる。だからレーベルを目指しつつ、最初はミックスの配信をやってみるのがいいかもね。
<了>
Text By Haruka Sato
Design by chiyo_midnightPhoto by Hitomi Hanajima
