またホンデで会おう〜韓国インディ音楽通信〜第5回
2021年韓国インディー・ベスト10
本連載を読んでくださっている皆さん、お久しぶりです。こちら韓国は11月に防疫規制の緩和、いわゆる”ウィズ・コロナ(韓国では”段階的日常回復”と言っています)”に突入しました。ライブの数も増え、これまでは大きくても観客200人規模くらいまでのライブしか出来なかったのが、ようやく数千人規模まで可能になるなど、ようやく変化が見え始め、私も11月以降は週に1本以上のペースでライブに足を運べるようになりました。ただ、身分情報の入ったQRコードあるいは予防接種証明書を見せて入場せねばならず、基本的に着席のライブしかなかったり、クラブは夜12時までしか営業出来なかったりと、制限的ではあります。私が本稿を執筆している12月初旬現在も連日4千人〜5千人の新規感染者が発生している、決して安心出来ない状況ですし、やはりコロナ前の状況まで完全に回復するまではかなり時間がかかりそうです(そして、ライブ・シーンの話をするならば、コロナ以降いくつものライブハウスやクラブが閉店してしまったことも言及せねばなりませんね)。
※注:本稿執筆時以降、韓国国内の感染者数は増加し続け、”ウィズコロナ”は12月18日より一時的に中断、再び営業時間や人員制限などソーシャルディスタンスが強化されるようになりました。
そんな社会的には厳しい状況ですが、今年の韓国インディ・シーンもベテラン・中堅から新人まで多数の優れたアルバムが発表されました。シーン全体には目立ったトレンドのようなものこそないものの、世界的にロック・サウンドが少しずつ元気を取り戻しているのに比例するように今年はインディ・ロックで良いアルバム、シングルが多かった印象。個人的には、来日公演の経験もあるバンド、Say Sue Meや本稿でも紹介するバンド、TRPPなどの人気ドラマOSTへの起用、Silica Gelのメンバーたちが韓国で大人気バラエティ番組をいくつも世に放ったプロデューサーが新たに手掛けるNetflixのバラエティ番組「腹ペコとモジャモジャ」の音楽スタッフで関わるなど、チャートには見えないところで大衆との距離を近づけるオルタナティブ・ロック・バンドたちの活躍にも心踊らされました。
毎回ベスト・アルバム記事をお届けする時に思うことですが、これから紹介する10作を聴けば、きっと韓国インディ・シーンへの関心が高まるでしょう。そう自信を持って言える10枚をセレクトしました。本連載も、来年はより頻繁に且つ多彩な方式で更新し、韓国インディ・シーンの現在をもっと身近にお伝えしたいと思います。(山本大地)

Jeong Cha Sik 정차식(チョン・チャシク) 『Night Driving 야간주행』 (구좌사운드)
チョン・チャシクは1998年に韓国インディ・シーンの第一世代の一組としてデビューしたロック・バンド、Rainy Sunのボーカルであり、ソロでも2011年にはアルバム『The Turbulent Current History』で韓国大衆音楽賞の最優秀ロック・アルバム賞とロック・ソング賞を受賞するなど、長くキャリアを積んで来たアーティスト。本作は、そんな彼が40代になって経験した失恋、それに伴う不眠症やチェジュ島への移住といった経験を題材に作られており、なんと同名の、230ページに及ぶ本も出版されている。<私はいま生命がない / 愛なんて今は虚しい>…アルバム冒頭からその声は震えながら歌うかのように寂しげだ。時にトム・ウェイツのように渋い声でただただ吐き捨てるように歌ったりもするし、「Gracefully」ではボン・イヴェールのようなか細い声も使い分けている。どの曲からも共通しているのは彼の声からひたすらに痛切な悲しさが伝わってくること。冷たいシンセの音や、悲しく踊らせるスロウ・ディスコ(「Shining」)、劇的なムードを演出するパンソリの太鼓(「Went Down」)などアレンジも秀逸。中年シンガーソングライターの快作ブルース・アルバムだ。

Lang Lee 이랑 (イ・ラン) 『オオカミが現れた 늑대가 나타났다』(Your Summer)
来日ツアーを何度も行ったり、10月には折坂悠太のニュー・アルバムに客演するなど日本でも馴染みの深いイ・ランの5年ぶりのアルバム。前作を発表して以降「連帯することで生き抜く力が生まれることを新たに知った」という彼女の視点はこれまで以上に外に開かれている。デモや集会で使われることをイメージして書いたという冒頭のタイトル曲で、彼女は<私たちは役立たずの人たちではないです / あなた達が食べるパンを作る人たちであるだけ>と歌う。それは、どんな形で生きる人の命もどこかしらで必ずあなたの暮らしと繋がっているのだと聴き手に想像力を投げかける、鋭いメッセージだ。一方、2バージョン収録された「患難の世代」では、<大切な私の友達たち / 同時に皆死んでしまおう>と歌いながら、絶望した同胞たちと叫び合う。両曲でフィーチャーされる、性の多様性とフェミニズムを支援する合唱団、オンニ・クワイアのコーラスは市井の人たちの多様な声を掬い上げて、楽曲をより力強くする。
一方、それら大曲の間に収録された肩の力の抜けたトーンの楽曲たちでは、何気無い一日の喜びや疑問、対話をそのまま歌にし、アカペラだったり、ワルツ調のリズムだったり、イ・ランらしい自由な方式で表現する。どうだろう、1曲目でイ・ランと一緒に怒りの声を上げていた僕は8曲目では知らず識らずに笑みを浮かべている。細やかに生きる人の笑顔を照らし、小さな悩みや葛藤にも寄り添うこのアルバムは、“連帯”という言葉の持つ力強さと温かさ両方を感じさせる。

Leesuho 이수호 (イ・スホ) 『Monika』(Balming Tiger)
“オルタナティブK-POPグループ”を標榜するクルー、Balming Tiger所属のプロデューサー兼映像監督(CL、Se So Neon、sogummなどのMV監督を手掛けている)であるマルチ・アーティスト、イ・スホ。音をギザギザに切って壊し、変形させ、無作為に再構築させたかのような彼のビートは、一聴した時から衝撃的だった。3年ぶりのアルバムである本作も彼自身「多くの人が不快に感じる(だろう)」と語る通り、確かに異物感ある音作りだ。ただ、ヒップホップからテクノ、ダンスホール、フットワークまでジャンルが拡大され、個性豊かな声を取り込んだこのアルバムは、実験性とポップ音楽としての強度を両立した非常に訴求力ある作品だと思う。
ゲストの顔ぶれは、イ・スホと同じくBalming Tiger所属のOmega Sapienとsogummをはじめ、ヒップホップ、R&Bからインディ・ロックまで豪華でジャンル横断的。その上、トップバッターのSo!YoON!(Se So Neon)のからラストのチャン・ギハまで、ゲスト達のキャラの濃いヴォーカルを生かしたトラック・メイキングをしている点も素晴らしく、ディレクション能力にも長けている。奇しくも、この韓国のアンダーグラウンドの力を結集した本作は、今年を象徴するアイドル・グループ、aespaがハイパーポップな「Savage」を大ヒットさせたのと同じタイミングで世に放たれた。
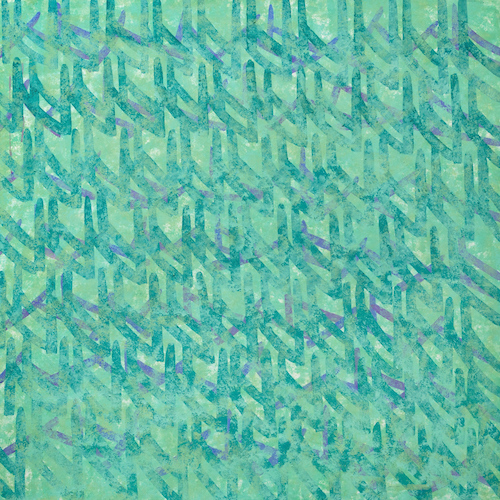
nijuu 니쥬(ニジュー) 『nijuu in the forest』(The state51 Conspiracy)
ソウルとロンドンを拠点に活動するニジューは、2019年、韓国音楽シーンの数々の才能を発掘してきた「ユ・ジェハ音楽競演大会」で入賞、イギリスではBBC Radioを始め多数のメディアで取り上げられるなど注目のシンガーソングライターだ。本作は昨年のデビューEP『nijuu in the sea』に続く『nijuu~』シリーズの2作目。ニジューの歌は童謡のように優しく、子守唄のように平穏を生み出すし、時にスピリチュアルを受けているかのような錯覚を起こさせる、不思議な力を持っている(クリスチャンであることも曲の所々に影響を及ぼしている)。本作のハイライトは、繊細なアコースティック・ギターの弾き語りから、様々な楽器や声が重なり合うカオティックなパートへ展開して行く中盤の「나에게로 Come to me」。<私は水 / 私は森 / 私は花 / 私は陰 / 私は陽の光 / 私は季節 / 私は何にでもなれる>。こう歌う彼女が、自然界のあらゆる存在を超越した姿となって聴き手を包み込む、慰めの歌だ。筆者が足を運んだライブ中も彼女は再三「前よりも強くなった姿を見せたい」と話していた。自らの傷や弱さを隠すことなく正直に表現するニジューだからこそ、こうした歌も力強く届く。

soumbalgwang 소음발광(ソウムパルグァン) 『Happiness, Flower 기쁨, 꽃』(Osoriworks)
ここ数年のイギリスやアイルランドを中心としたポスト・パンクの新しい波は、高熱のエネルギーそのままに海を渡って、韓国の海の玄関口、釜山にも届いた。バンド名は漢字にすると騒音発狂(あるいは発光)。再生ボタンを押すとすぐにノイズまみれのギター、性急なドラミングが聴こえてくる。ブルー・ハーツやNumber Girlも聴いて来たというパンクをひたむきに愛するカン・ドンス(ギター / ヴォーカル)を中心とした4人組が、同郷のSay Sue Meのキム・ビョンギュをプロデューサーに迎えた本作は、Fontaines D.C.、IDLESなど同時代のバンド達から得た刺激を見事に昇華している。シャウト混じりのヴォーカルからは憂鬱や絶望を感じさせる言葉が度々吐き出されるが、最後の力を振り絞るようなラストの「Happiness」はドンスの正直な告白が、聴き手を巻き込んで前に進む力を生み出す名アンセムだ。終盤、同じく同郷・釜山のバンド、Bosudongcooler、 hathaw9y (ハサウェイ)のメンバー達と一緒になって<こうだ、何かしてみたこともないです / 生きようと努力したこともありません>と叫ぶパートは、パンク・ミュージックが持っている「何かを共に叫ぶことが生み出す解放感」を生々しく感じさせる。聴き手を確かに突き動かす快心の一作だ。

TRPP 『TRPP』(Magic Strawberry Sound)
TRPPはバンド、Bye Bye Badmanのギター / ヴォーカルのボンギル、シンガーソングライター、ユン・ジヨン、ギタリストやエンジニアとしてシーンを裏から支えるカン・ウォンウによって結成されたバンドだ。キャリアのある3人のミュージシャンたちの知恵を集めたことで生まれたのは、打ち込みのビートの上でひたすらメンバー全員轟音のシューゲイズ・ギターを鳴らす斬新なスタイル(ライブでも3人が横並びでノイジーにギターを鳴らし続ける姿が爽快!)。そのギター・サウンドだけでも快感を味わわせてくれるが、このバンドがすごいのは、80年代から現在までインディ・ロックの多彩なサウンドをいくつも貪欲に取り込んだこと。夢幻的なヴォーカルが魅力的なスロウな楽曲ではコクトー・ツインズ的なメランコリックなムードが、テンポを速めてみればマッドチェスターのバンド達のダンス・グルーヴが、果てはタイトにギターのリズムを刻む曲では初期ストロークスを思わせるロックンロールまでもが、切れ目なく聴こえてくる。10月末からはNetflixを通して日本でも配信中のTVドラマ「調査官ク・ギョンイ」にも多数の楽曲を提供。インディ・ロック好きたちに夢を見せてくれるようなこのプロジェクトが一作だけの企画バンドで終わらないことを願いたい。

The Volunteers 『The Volunteers』 (Blue Vinyl)
R&Bシンガー、ペク・イェリンをボーカルに、彼女のコラボレーター兼バンド、Bye Bye Badmanのメンバーらによって結成されたバンド、The Volunteersの待望の初アルバム。90年代オルタナ・サウンドのように思い切り歪ませたギターに、パワフルなドラミングやシャウトするイェリンのボーカルが光る序盤の曲から、ラストのメランコリーな「Summer」まで、シンプル且つ無駄がなく、聴き手を一瞬で引き込ませるフックが詰まっている。
オアシスのドキュメンタリーを見てロック・バンドの表現の自由さに魅了されたという彼女の言葉通り、筆者はイェリンの表現の変化にも強く惹かれた。それは、ソロ作の時より衝動的で自信感に溢れて聴こえる歌唱からも、<あなたがすればするほど、私は成長した女性になった気がするの>と歌う「Violet」を始めとした歌詞からも感じられる。彼女はバンドの初ライブとなる10月の《仁川ペンタポート・ロックフェス》で演奏中、フェミニスト運動のスローガンと掛け合わせ「my body my choice, my tattoos, bishes!」と強く叫んだ( 韓国では医師以外によるタトゥー施術が不法とされており、今年合法化を求める動きが強まっていた)。イェリンは正真正銘、芯の通ったロック・スターになったのだ。

Western Kite 『ultraviolet!』 (john choi)
シンガーソングライター、ウエスタン・カイトが韓国とイギリスを行き来しながら制作した約3年半ぶりとなるセカンド・アルバム。9曲25分、ギターがリードするロック・ナンバー「COUCH」、打ち込みビートの「John Choi」や「LARRY」、鍵盤とメロトロンだけの「Inline」など楽曲スタイルはバラバラながら、統一感を抱かせる音作りが秀逸だ。全体的にミドル〜スロウのビートの曲が多く、メロトロンやオルガンの浮遊感ある音色、柔らかく叩かれるドラム、何よりどこか淡白で寂しげなヴォーカル、そのどれもが心地よいグルーヴを作り出している。ジャンルの混淆とオリジナリティを両立した本作はフランク・オーシャンやミゲル、あるいは『Flower Boy』の頃のタイラー・ザ・クリエイターと並べて聴いてもいいだろう。友人でもあるシンガー、g1nger、プロデューサーのWURAMやウ、ドラマーのSHINDRUMといったコラボレーターの起用まで含めて、ウエスタン・カイト自身のプロデュース能力の高さも讃えたい。

Wings of the Isang 이상의 날개 (イサンエナルゲ) 『The Borderline between Hope and Despair 희망과 절망의 경계』 (LOCO Arts & Music)
2枚組、11曲84分の大作アルバムである前作『意識の流れ』で韓国大衆音楽賞、ベスト・モダンロック・アルバム賞を受賞した4人組バンドの5年ぶりのアルバム。ポスト・ロックに括られることが多い彼らだが、筆者がかのジャンルに感じてしまう取っ付きづらさのようなものはこのアルバムからは一切感じない。代わりにただただ圧倒的な音の美しさに浸っていたくなる。まず動と静の使い分けが巧みだ。目を閉じて聴いてみると、轟音のノイズ・ギターの音が止んで静寂が訪れた時、まるで目の前に広大な宇宙の景色が現れたかのよう。その瞬間だけでも、痛みや憂鬱を抱えた心が優しく治癒される。 興味深いのは、ギター / ヴォーカルのムン・ジョンミンが特に影響を受けたミュージシャンとしれ80年代後半のイ・ムンセを中心に数々の歌謡ヒット曲を作曲したイ・ヨンフンを挙げていること。20歳の頃の記憶を懐かしく歌う「Twenty Years Old」のような曲は“ハード化したメランコリックなドリームポップ”ともいうべきサウンドに、彼の優しく無垢なメロディ・センスがこれでもかというほど美しくマッチしている。

Youra 유라 (ユラ) 『GAUSSIAN』 (MUN HWA IN 文化人)
筆者がユラを好きなのは、彼女が常に音楽的な挑戦を追い求めているアーティストに見えるからだ。音楽サバイバル番組出演やドラマOSTの発表、Giriboy、Heizeといった人気アーティストとの共演も幾らかはきっかけになっているだろうが、ラップ / R&B、インディ音楽の両方のリスナーからプロップスを高め続けているのは、サイケデリック・ロックからソウル、ヒップホップまで幅広く吸収してきたユラだけの個性的な音楽性があってこそだと思う。
2作目となるEPである本作も、U-TURN、623といったこれまでにも何度か共作しているプロデューサーらとともに、彼女にとって未知のサウンドを作ろうとした。特にBPM134くらいのやや性急なビートの上でギターとシンセサイザーが交互に跳ねるように響き続ける「 손가락으로 아 긋기만 해도 (ZEBRA)」は<full of fakeness>と囁くユラのボーカルまで含めて、どんなジャンル名でも表現できない奇妙な印象を与える。本作中2曲でギターを演奏しているバンド、Silica Gelのキム・チュンチュにはその後6月に発表した楽曲「Roller Coaster」で全面的なプロデュースを任せ、ギター・ドリヴンな一曲が生まれた。常に次の一手にワクワクさせられる、韓国のオルタナティヴ・ポップの新星に注目だ。
Text By Daichi Yamamoto
連載アーカイブ
【第4回】海辺の田舎町から聴こえてくる懐かしいフォーク!?〜韓国インディ・シーンに登場した新鋭、サゴン
【第3回】Best Korean Indie Albums for The Second Half of 2020
【第2回】朝鮮伝統音楽からジャズ、ファンク、レゲエまで…韓国インディ・シーンのルーツ音楽を更新するバンドたち
【第1回】Best Korean Indie Albums for The First Half of 2020
