対談
三船雅也(ROTH BART BARON)× 尾崎雄貴(BBHF)
「取り繕わない人の音楽がこの先は響いていくのかもしれない」
正直者たちの音楽の根っこにあるもの
ROTH BART BARON(RBB)の三船雅也と、BBHFの尾崎雄貴。それぞれ、5枚目のアルバム『極彩色の祝祭』(2020年10月28日リリース)とセカンド・アルバム『BBHF1 -南下する青年-』(2020年9月2日リリース)を発表したばかりの2組のメインパーソンたちは、聞けばここ1年ほどで交流を深めているのだという。かたや東京でインディペンデントに音楽を探求し続ける中で昨今ビッグ・ネームとも交わるようになってきているROTH BART BARONと、かたや前身バンド=Galileo Galilei時代に一度は東京に出、メジャーのフィールドで注目を浴びながらも故郷・札幌に戻り、今では自らの決断でインディーへと転身したBBHF。2010年代を全く別のフィールドで過ごしてきた両バンドではあるが、不思議なことに、その歩みは、メジャーとインディーという狭間という接合点で今ちょうどクロスし、邂逅を果たしたという事実は、実に興味深いことだ。
いや、メジャー/インディーなんて、正直言ってしまえばどうでもいい括りである。彼らを引き合わせたのは、おそらく、もっと深い、スピリットの部分なのだろう。DIYで音楽を作り、責任をもって作品をパッケージングし、リスナーへまっすぐ届けようとする、真摯さ。互いにUSインディーに共鳴しながらも、それらを自分たちの暮らすこの日本で鳴らすことの難しさを知り、けれども逃げ出したり茶化すことをせずに正面からぶつかっていく、勇敢さ。尾崎自身は「ソングライティングは真逆と言っていいほど違う」と語っているが、2人の対談を通じて見えてきたのは、彼らが、自分たちがルーツとする音楽や、そこから生み出された自分たちの音楽に、ただただ嘘偽りなく正直であるという共通点だ。
最後には、今年の頭に奇跡的なタイミングで来日し、両名とも公演を観に行ったというボン・イヴェールも参加する、テイラー・スウィフトの新譜『Folklore』の話題にまで及んだ対談。彼女を指して、対談中に三船が漏らした「自分の本心がよく見えている、取り繕わない人の音楽が、この先は響いていくのかもしれない」という言葉は、そのまま彼ら2組の鳴らす音楽の根っことも繋がっているように感じられる。コロナ禍の中、東京と札幌というそれぞれの拠点にあるお互いのワークスペースからZoomを繋いで行われた、スピリットで通じ合う2人の対談を、ここにお届けしよう。
(取材進行・文/井草七海、協力/岡村詩野)
──そもそもまず、お二人が出会ったきっかけはどういったものだったんでしょうか?
三船(以下、M):以前に1度ウェブ対談をしたことはあったんですけど、実際に会ったのは、去年の6月にwarbear(尾崎のソロ・プロジェクト)と僕たちとでやった、新代田FEVERでのツーマンライブが初めてです。だから、知り合ってまだ1年くらいなんですよ。
──とはいえ、最近ではお互いに連絡を取り合ったりはしている間柄であると。
尾崎(以下、O):そうですね。自分たちのアルバムができたタイミングで、音源を送らせてもらったり。
M:今年の7月に札幌にライブに行ったんですけど、その時はスケジュールが合わずに会えなくて。でも、コロナの間も「生きてるか?!」とか生存確認したりね(笑)。
 ▲オンラインでの対談風景
▲オンラインでの対談風景
──お互いに直近のアルバムを聴いていらっしゃるかと思うんですが、聴いてみての第一印象はどうでしたか?
M:前回会ったのが、そのwarbearのライヴだったわけですけど、BBHFの今作はそれとはまた全然違う引き出しの作品だなと。音がクリアで透き通ったサウンドでありながら、力強くて立体感があって、いいですよね。やっている本人も楽しそうだなと思いました。
──尾崎さんから見たRBBの新譜はどうですか?
O:今までのRBBのサウンドは、聴き手との間になにかフィルターのようなものがあって、その向こう側に音楽が広がっているような印象を抱いていたんですけど、今回はグッとこちら側に距離を詰めてきたなという感じがして。音が散っていく感じがなくて、トラックそれぞれが意味を持ってぐっと迫ってくるような。と同時に、孤高というか、孤独さも感じました。僕はそういう孤独感のある音楽がすごく好きなので、そこにまず感動しましたね。
M:そうだね、逆に尾崎くんのソロはすごく孤独感がある作品だと思うんだけど、BBHFの今作は孤独じゃない作品に聴こえる。バンド・サウンドだというのもあるんだろうけど、音が広がっていく感じがするというか。
──ロック・バンドでありながらも、アメリカの今のメインストリームの音楽にも近いトラックメイクをされているというという点では、2バンドともある種、音楽性の方向的には似ているようにも思うのですが、かたや孤独感を感じつつ、かたやダイナミックな広がりを感じつつ、という真逆の感想が出てくるのは面白いですね。
O:RBBの今作の制作の様子が映っているトレイラーを見て、僕の思っている以上に多くの人が関わっているんだなというのを知ったんですけど、にもかかわらず、実際にアルバムを聴いた時には“たった1人のひと”が見えたんですよね。ファミリーが周りにたくさんいるというよりは、ただ1人の登場人物が見えるような気がして。それが面白いなと思ったし、そういうたくさんの人が関わる現場から、孤独感のあるサウンドが生まれるのはなぜだろうって。
M:確かに……。昨今、集団でいるっていうのが許されない世界の中で、いろんな人たちがいろんなレベル感で自分と向き合わざるを得ない状況になったのがこの10ヶ月だったと思ってはいるけど、今作は、それを無理やり反映させたというよりは、自然に出ちゃったという感じかもしれない。たくさんの人と関わっているがゆえに浮き彫りになってしまう“個人”というか。
──私は、音づくりという点では昨年リリースの前作(『けものたちの名前』)の方向性を引き継いでいるように聴こえながらも、メロディラインなんかは、『ロットバルトバロンの氷河期』(2014年)の頃に似ているような気もしました。ソングライティングに、より素朴さを感じまして。
M:プロダクションは複雑なんだけど、コアになるソングライティング自体は非常に人間味のあるものになっている、というのは確かにそうかもしれませんね。
──BBHFのアルバムのほうにも、リズムパートにデジタルなサウンドも一緒に使っていたりだとか、生のバンドだからこその制約を抜きにしたプロダクションが見受けられます。バンドという形態の新しいあり方を模索する中で、タフなサウンドが生まれてきたんじゃないかなという風にも思いましたが……。
O:僕自身、インディー・ロックも好きなんですけど、同時にワン・ダイレクションとかもすごく好きで。ジャスティン・ビーバーも大好きだし。そういう、ポップのど真ん中で、ドシッと何かを持っているような音楽も好きなんです。だから、僕らの作品のサウンドも、大きなステージで鳴らすことをイメージしたものにしていますね。
──前身のバンドのGalileo Galileiの時はソニーからリリースされてましたが、今はインディーで活動されているわけですよね。メジャーからインディーへ、という決断を経て今に至るわけですが、作品づくりに関しては、やはり大きな場所で鳴らすイメージがあると。勿論、インディーだから大きなところでライヴができない、というわけではないにせよ、一見すると、相反する決断のようにも感じられますよね。
O:ファンの人たちは「クビになったんじゃないか」と心配してくれるんですけど(笑)、実際は、僕から提案してレーベルから離れることになったんですよ。僕ら自身、10代でデビューしてMステに出るような形で世に出てきたわけですけど、やっぱりどこかイメージを作られていたような感覚があったのも事実で……。だから、僕らの音楽性が方向転換してから、これから進みたい方向とレーベルのプロモーションの方向とがうまく合致しなくなってきていて。それなら、新しいレーベルで、僕らの新しい音楽性を、いいと思ってくれる人たちと一緒にやれたら、と思って今に至っています。
──その音楽性の方向転換には、なにか具体的なきっかけがあったんですか?
O:そうですね……。僕ら自身は、中高生のころにバンドを始めて。その時は邦楽を中心に聴いていて、BUMP OF CHICKENやくるり、the pillowsなんかをカバーしていたんですが、そうしたら、ちょうどそんな高校生くらいの時にデビューしてしまって……。誰しも、大人になるにつれて、より自分に合った音楽性を模索して探っていくと思うんですけど、僕らの場合は、自分たちの音楽性が未完成の状態でデビューしてしまったんですよね。だから、プロになってからどんどん新しい音楽を知っていって、というような流れだったので、成長するにすれて、目指す音楽が変わっていったというか……必然的な変化だったと思います。きっと多くの人がするであろう変化だと思うんですけど、それをみんなが見ている前でしちゃった、っていう感じですね。

──なるほど。そのGalileo Galilei時代も含め、実際に出会う前から、お互いのバンドの音楽は認知していたんじゃないかと思うんですが、初めて知った時の印象はどんなものだったんですか?
M:僕が尾崎くんを知ったのは、『サンレコ』(サウンド&レコーディング・マガジン)で見かけたのが初めてでしたね。で、「すげえ機材持ってる人がいるな」と(笑)。Galileo Galileiはその前からすごく有名だったけど、その、めちゃくちゃ機材を持っていてギークな感じが、生まれは違えど自分に似たようなものを感じる人だなと思っていました。確かに所属レーベルは大きいかもしれないけど、彼らが持っているスピリットはとてもDIYだし、元々インディペンデント心が強いんだろうなというのは最初から感じてて。じゃなきゃ、あれだけ機材を自分たちで集めて責任を持って音楽をパッケージしようっていう風にはならないと思うから。だから、自分たちでハンドメイドした手触り感のあるものを大切にしている人たちの音は絶対にいいだろうなと。
──聴かれてみて、楽曲についてはどう思われました?
M:メインストリームの音楽の中でも、こんなに世界の音楽を勉強している人はいないなっていうのは感じましたね。日本の先の世界を見ていると思ったし、そんなミュージシャンって当時なかなか日本にいなかったし。日本の1億3千万人のことだけしか考えないで音楽やってる人って結構多いけど、そんな中で、アメリカの3億人とか、中国の14億人とかを見ている可能性がある人たちだなっていうのを感じてました。だから、さっき尾崎君が言っていた「大きいところで鳴っているような」っていうのは、わかる気がするな。
O:僕もRBBのことは、実際に会う前から知っていて。僕からすると、RBBは、僕らが行きたかった場所、居たかった場所にいた人という印象でした。だから、海外の好きなアーティストを見るのと同じ目線で、僕はRBBのことを見てました。あと、もし中高生の頃、自分がRBBの音楽を知っていたなら、多分学校に行く時とかに聴いてただろうなって。僕自身、中高の時は不登校ぎみで学校に行くのがすごく嫌で、通学するときは雪の降る中バスに乗ってシガーロスとかを聴いていて……。そんな風に、少しでも現実を忘れるために、自分の孤独感の隣に置いていた音楽になってただろうな、と。
──お互いに音楽を始めた2000年代には、全く違うフィールドにいた同士ではあったけれども、根っこの部分にはシンパシーを感じうる共通点も多そうですね。
O:僕ら、もともと仲の良いバンドって全然いなくて。シーンっていうものにも疎いし、そういうことをあまり考えたくなくて、一度出てきた東京から札幌にまた戻ってきたんですけど、RBBにも、そういうものを感じていました。シーンや界隈を作るっていうより、「自分たちは自分たち」という姿勢で、自分の作るものに集中しているというように、僕には見えていて。かっこいいなって思っていました。
──RBBは、それこそ2010年代の半ばごろには「東京インディーの孤高の存在」なんて言われてましたよね。
M:自分では思ったことないけど(笑)。東京で音楽を始めて不思議に感じたのは、意外と派閥に満ちていたということで。僕らがデビューした頃が2010年代の始まりで、その頃は、森は行きている、スカート、ミツメとかが出てきて、東京のインディーが一つのシーンみたいに言われてた。今でこそ、岡田(拓郎)くんとかは親しいけれども、当時はその中に誰も知り合いがいなくて。
そもそも僕らは、シーンとか関係なく、なんなら日本も外国も関係なくやりたいんだよな、って思いながらずっとDIYでやってきたんだけど、それこそやっと最近になって、くるりと共演したりだとか、去年はアジカンに呼んでもらってGotchとも仲良くなったりし始めて。a flood of circleの佐々木(亮介)くんなんて「シカゴでレコーディングしたいんだけど、どうしたらできるか教えて欲しい」って連絡をくれたところから、交流が始まって。最近になって、ようやくそういう派閥みたいなのがなくなってきたように感じますね。僕らは元々ノーガードでいたんだけども(笑)。
──インディペンデントでずっとやってきたRBBが、少しずつメインストリームとも交わっていくような活動を展開しながら、他方で、一度はメジャーにもいたBBHFがインディペンデントな活動にシフトしながら、音楽的にもよりDIY的なものを作り上げて。その接合点でクロスオーバーしてちょうど2組が出会った、というような道のりはかなり興味深いですね。ちなみに、お互いの共通点でいうと、ソングライティングについてはどうでしょう?
M:バンドでソングライティングをやるメインパーソンなのに、お互い弾き語りをやらないところが同じかな? 「バンドがやりたい!」っていう感じで(笑)。
O:確かに。僕もバンドがやりたいですね、1人ではやりたくないっていう(笑)。
M:二人とも、アウトプットはバンドとしてパッケージされてるものがいいっていう感じだよね。だから、方法論っていうことよりも、思想とかスピリットが似てるのかも。食材の選び方とか、最終的な料理の仕方とかは全然違ったりするけど、ときめくものは一緒っていうか。
O:確かにときめくところは同じかも。にもかかわらず、ソングライティングの捉え方に関しては、真逆と言えるくらい違うと思うんですよね。でも、だからこそ僕はそこに魅力を感じる。僕からすると、三船さんって人は、未知数だし、不可解で、不思議で。違うからこそ、僕はRBBを、アーティストとしてずっと見ていられるんだと思います。
M:似てるのは前提で、違うところにお互い惹かれるのかもしれないね。
──では、違うところって、具体的にどんなところですか?
O:そもそもの人間のあり方の描き方が違うように思います。僕も、歌詞では人間を描くけれど、三船さんの人間の捉え方は、僕にとってはすごく神秘的に見えていて。一方で、僕の場合は、ゲームをやってアニメを見て……っていうような、普通の生活をしてる人を描くし、そこにリアルを求めているところがあって。そこは違うところだなと思いますね。
M:BBHFの今回の作品には、歌詞にちゃんとロールプレイングしている登場人物が出てくるんだよね。ゲームでたとえるなら、ステージがちゃんと構築されていて、その中で生きるキャラのために、世界観をパッケージしてあげている、っていうか。すごく責任感のあるデザインがされている作品だって感じがする。僕はわりと無責任っていうか、そこまでは負わないことが多いかな。メタ的な要素が入ってくるんですよ、僕がゲームを作ると(笑)。僕もゲームもファンタジーも好きで、入口は一緒なのに、出口が違う気がするな。でも、尾崎くんの作る、その完結している世界観には魅力を感じますね。
──なるほど。ちなみに、以前、尾崎さんは『ATOM』(2015年)で初めてRBBを聴いて「仲間だと思った」という風におっしゃっていたかと思うんですが、それはどんなところにですか?
O:音楽的なところですね。というのも、当時、国内を見渡しても、ザ・ナショナルであるとかインターポールであるとか、USのインディー・ロックの、文学的でありながら、バンドらしい泥臭さみたいな部分があるところにシンパシーを感じてやってる人って、なかなかいなくて。でも、RBBには、USインディーのうわべじゃなくて、根っこの部分を鳴らそうとしているのを感じて。だから、「仲間だ!」というよりも、「そういう人たちがいたんだ!」っていう驚きの気持ちが強かったですね。やっぱり、僕自身日本人だから、海外に強く影響を受けたっていう音楽をやろうとすると、どうしても、自分の生活感や人間性から離れていってしまうことがあるなと思っていて、実際それに苦しんだこともあった。でも三船さんの音楽には、それを感じなかったんです。
──ロックはもともとは欧米産とされてきた音楽で、だからこそ、それを日本で鳴らすことがいかに難しいかについては、三船さんも前回のインタビューでもお話ししてくれていたかと思うんですが、実際その『ATOM』の頃はどう思われてたんですか?
M:『ロットバルトバロンの氷河期』を出したら、「日本でこんなスケールのある音を出せるバンドがいるんだ」って日本中の音楽ファンが反応してくれると思ってたんですけど、思ったより反応がなくて(笑)。ただ、今尾崎くんの言ってた生活とのちぐはぐ感みたいなものも、なんとなくわかる。なんだろう……日本でそういうことやろうとすると、みんなふざけちゃうっていうかさ。恥ずかしいのか、なんなのか……。はっぴいえんどもふざけちゃったし、忌野清志郎も「デイドリーム・ビリーバー」をちょっと可愛くしちゃったし。尾崎くんと僕らの似てるところと言ったら、そこをふざけないで真面目にやってるところだと思う。それが被り物だとしても、背中のチャックは絶対見せちゃいけないっていうか。
O:わかります、すごく。僕も、はっぴいえんどだって、ふざけちゃってるよなっていう風に思っていたし。だから三船さんもそういう風に思っていたんだというのは、すごく嬉しいです。本当に、そういう視点で話をする人に僕は今まで会ったことがなかったので。

M:ロック・ミュージックというか、そもそも革新性こそがポップスじゃないですか。そこに挑戦しないで、コピペしてちょっと色だけ変えました、みたいなのはリスペクトがないと思うんですよね。だからRBBは、日本人が当たり前に洋楽 / 邦楽って分けちゃうような既成概念を、一個一個ぶっ壊していく作業をしてきてたわけで。ただもちろん、それは、なにかを論破するみたいな形じゃなくて、音楽として楽しく聴いてもらえればいいと思うし、そのことで変わっていくこともあるんじゃないかなって思ってやってきてます。
O:かっこいいですね、やっぱり。
M:(笑)。でもさ、そういうことに、コロナ禍になってなおさら向き合わなきゃいけなくなった感じがするよね。部屋にこもらなきゃいけなくなって、この自宅の狭い部屋の棚に、本当に埋めるべき音楽ってなんだろうとか、この先続く自分の人生に本当に大事な曲ってなんだろう、とか問われてる気がしていて。だから、そこに対して伝わるものを作りたいなと思ってます。そういうことを探求して、いちいち向き合っていったほうが、結果遠くまで行けるんじゃないかなと。
──ではまさに今、根っこの部分でシンパシーを抱くアーティストや作品って、どんなものなんでしょうか?
M:このコロナの期間は、古いフォークとか、テクノロジーが除外された音楽を結構聴いてました。それこそ、ニール・ヤングとかもう一度聴き返したり。人間の魂そのもののような、ただ声があってギターがあって、というようなものに心惹かれるようになりましたね。以前はバキバキに都会的なものも大好きだったんですけど、今年はなんだかそれが瓦解して、パーソナルなものが響いたというか。
──尾崎さんは、今フェイヴァリットな海外のアーティストっていますか?
O:以前からずっと好きで、今も変わらずフェイヴァリットなのは、ボン・イヴェールですね。今年の来日も東京まで行って。ジャスティン・ヴァーノンという存在そのものが好きなんです。音楽を超えた、憧れを感じるんですよ。音楽としてももちろんとても好きなんですが、人間として……出で立ちから、顔までも(笑)。あと、僕はジャスティンにどこかフェミニンなものを感じるんですよね。そこが魅力的だと思います。
──作品自体は、初期の頃から最近のものまで全部好きですか?
O:『Bon Iver, Bon Iver』(2011年)を最初に聴いたときは、全然好きじゃなかったんですよ。当時の僕は、ですけど。でも、自分の人生の変化の中で少しずつ好きになって行って。作品でいったら、最近のものの方が特に好きかもしれませんね。
──なるほど。BBHFの今作にも、昨今のボン・イヴェールの音づくりの影響をいくらか感じたりもしますしね。そういえば、今回、お二人がお互いの新譜を聴いて、思い起こした他のアーティストのアルバムを3枚考えてきていただいたかと思うんですが、ここでそれぞれ紹介してもらっても良いですか?
O:僕がRBBの新譜を聴いて思い浮かべたのは、まずはアンディ・シャウフの『The Party』(2016年)でした。それから、トクマルシューゴの『Port Entropy』(2010年)、そしてスフィアン・スティーヴンスの『The Ascension』(2020年)ですね。
アンディ・シャウフについては、ホーンのアプローチであるとか、サウンドに近いものを感じて。あとは最初にも言った孤独感というか、いろんな人が制作に携わっているのに、アルバムの中にいる人物が“孤高の人ひとり”という印象があるところですね。トクマルシューゴさんについては、声ですね。三船さんの声の、繊細な糸を編み込んだような感じというか、絹のツヤみたいなものを、日本人なのに感じさせるところが、トクマルさんの声と似ているような気がして。スフィアン・スティーヴンスについては、音のプロダクションというか、レイヤーの奥にいるシンセの存在感に近いものを感じました。
──三船さんが、BBHFの新譜を聴いて思い浮かんだ3枚はどうですか?
M:80年代だと、ハワード・ジョーンズの『Dream Into Action』(1985年)。最近リバイバルしてる80年代のシンセポップな感じがありながらも、でも絶妙な気だるさみたいなのが今のこの世界に近いような……なんかそのヴァイブを今作に感じたというか(笑)。プロダクションの緻密さも、尾崎くんにあってる気がするし。それから、ライ・クーダーの『Ry Cooder』(1970年)ですね。今作の『BBHF1 -南下する青年-』は、少年が南下していくっていう内容だから、サウスの感じがそこにあるかなと。音楽的にマッチしているというよりは、精神的に似ているというところですかね。あと1枚は、テイラー・スウィフトの新譜『Folklore』ですね。尾崎くんの歌にはどこか、“ディーヴァ感”がある気がしてて(笑)。歌い上げてるし、ヴォーカルが力強くて。
──意外な回答でした(笑)。
O:確かに、僕、女性シンガーが好きなんですよね。自分自身は、本当はもっと男らしい声に生まれたかったなというものあるんですけど、だからこそ女性の声にも惹かれるというか。それに、挙げてくれたテイラー・スウィフトの『Folklore』は、個人的にも良く聴いているし、家族でも聴いてますね。あれを聴いて、ミュージシャンがわがままであること、世間が思う「こうであるべき」というイメージに沿うのではなくて、自分の思うままに言いたいことを言う、やりたいことをやるっていう姿勢がすごくいいなと思ったし、アメリカの多くの音楽もこれからそういう風になっていくのかなって。ビッグネームのミュージシャンでも、音楽に対する挑み方が変わってきてるなと。だから、彼女があれをやったことはすごく意味のあることだと思いました。
──三船さんからみた、テイラー・スウィフトの『Folklore』はどうですか?
M:元彼に「私よりも何倍もクールなインディー・ロックでも聴いてなよ」なんて歌ってたテイラーが、自分のほうからインディー・ロックに接近してきたっていう、そのなりふり構わなさに驚きました。でも、政治に対しても、今までずっと黙ってたのに、最近は積極的に発言するようになって。もしかしたら今までのファンがいなくなっちゃうかもしれないのに、勇気を持って一人の人間として世の中にアプローチをし始めていることは、すごくリスペクトできるというか。変わり続けることって、年取ると余計にできなくなるけど、その“変われる強さ”っていうのに勇気をもらったというのはありますよね。あと、インディーロック的なプロダクションがあっても、彼女のメロディーがあれば、結局テイラーになるんだなと(笑)。だから、僕はそこにも彼女の力強さを見た気もします。
──作られたテイラー・スウィフト像を脱ぎ捨てて、徐々に本当にやりたいことに邁進して、言いたいことも言って、というあり方は、どことなく、Galileo GalileiからBBHFへとそのあり方を変えてきた、先ほどの尾崎さんのお話にも似ているような気がしますね。だから、スケールは違うかもしれないけれど、欧米も日本も、もしかすると同じような流れがきているのかも。
M:うん。自分の本心がよく見えている、取り繕わない人の音楽が、この先は響いていくのかもしれない。逆に、嘘をついている音楽は聴かれなくなっていくんじゃないかなって、個人的には思いますね。
<了>
Text By Nami Igusa

BBHF
BBHF1 -南下する青年-
LABEL : Beacon Label
RELEASE DATE : 2020.09.02
購入はこちら
Tower Records / HMV / Amazon / iTunes
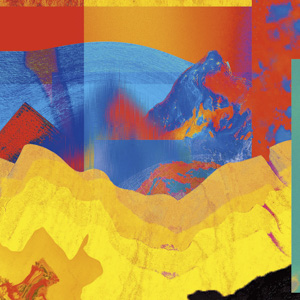
ROTH BART BARON
極彩色の祝祭
LABEL : SPACE SHOWER MUSIC
RELEASE DATE : 2020.10.28
購入はこちら
Tower Records / HMV / Amazon / iTunes
ROTH BART BARON Tour 2020-2021『極彩色の祝祭』
2020年
11月7日(土)広島・クラブクアトロ|主催:広島クラブクアトロ
11月14日(土)静岡・浜松 舘山寺|主催:MINDJIVE
12月5日(土)京都・磔磔
12月12日(土)東京・渋谷 WWW
2021年
1月16日(土)愛知・名古屋 The Bottom Line|協催:jellyfish
1月21日(木)福岡・百年蔵|主催:BEA
1月22日(金)福岡・the Voodoo Lounge|主催:BEA
1月23日(土)熊本・早川倉庫|主催:BEA
2月6日(土)石川・金沢 Art Gummi – Guest Act:noid -|協催:Magical Colors Night
2月7日(日)富山・高岡市生涯学習センター1F リトルウィング|主催:Ishi-G 雑楽工房, Songs 音創会
2月13日(土)大阪・梅田 Shangri-La|主催:SMASH WEST
2月20日(土)北海道・札幌 モエレ沼公園 ガラスのピラミッド|主催:WESS
2月21日(日)北海道・札幌 Sound Lab mole|主催:WESS
2月23日(祝火)宮城・仙台 Rensa|主催:Coolmine

