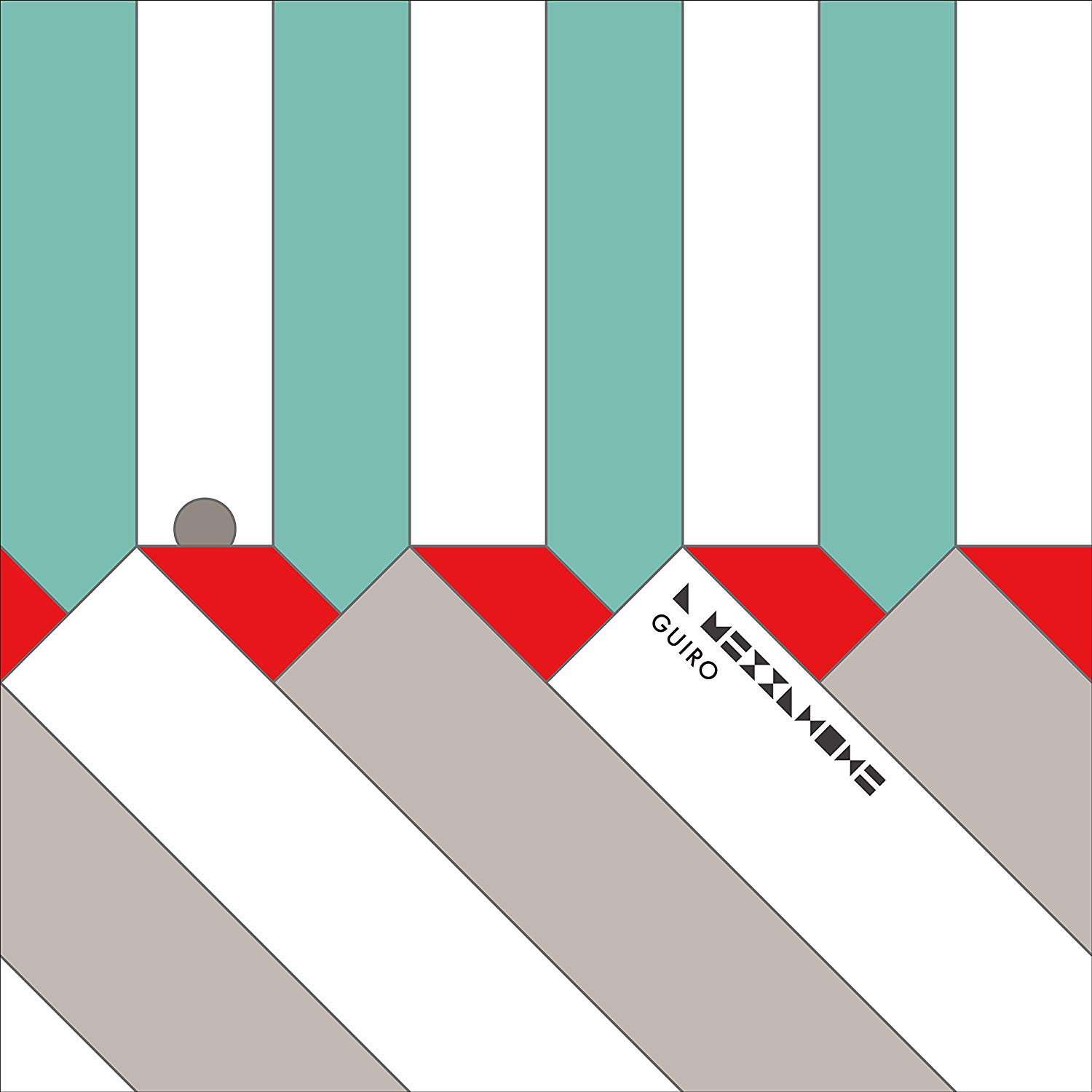「ここでもそっちでもない、そのあいだ。それゆえにすごくいい空間である。『A MEZZANINE (あ・めっざにね)』はそういう作品であってほしい」
名古屋の秘宝・GUIROの絶景たる“美しさ”
GUIROは1997年からヴォーカル・ギターの髙倉一修を中心に愛知・名古屋を拠点に活動するグループで「名古屋の至宝」と称されることもある存在だ。長い活動休止期間を終えた2015年以降は、彼らへのリスペクトを公言するceroとの交流を深めたり、野外フェスへの出演を果たすなど活動が活発化しているものの、彼らがこの20年以上にもおよぶキャリアの中で残してきた音源は、ディスコグラフィーで確認できるものすべてを合わせてもシングル5枚、アルバム1枚。楽曲数にしてわずかに24曲。至宝というより秘宝と言った方がふさわしいかもしれない寡作ぶりだ。
それでも古くからのファンは休止期間も常にその動向に目を凝らし続けていたし、ノンプロモーションの状況にあっても筆者を含む新たなリスナーを誘引し続けてきた。その理由はもちろん、これまでリリースされてきた24曲の楽曲と、見るたびに姿を変化させていくライヴ・パフォーマンスが、唯一無二の驚きと喜びをもたらしてくれるからということに他ならない。
そして、2019年7月に全国流通が開始された約2年半ぶりの5曲入りミニ・アルバム『A MEZZANINE(あ・めっざにね)』(英語ではなくラテン語読み)は、そんな聴き手の過剰な思い入れを、時に華麗に裏切り、時に真正面から受け止めながら、ポップ・ミュージックの新たな彼岸を切り拓いていく傑作だ。GUIROはまたしても、彼ら自身の手でその伝説の先を紡いでしまったのである。
あなたがもしGUIROを知らなかったとしても、美しい音楽を聴きたい、いや、音楽に限らず、映画でも写真でも絵画でも、「美しさ」というものに触れたいという欲望を持つならば、今すぐこの作品を聴いてみてほしい。そこには、どこにも属すことのない、誰も見たことのない5つ(5曲)の絶景が広がっている。
GUIROの現在と、驚きに満ちた新作について、リーダーの髙倉一修に語ってもらった。(取材・文・撮影/ドリーミー刑事)
Interview with Kazunaga Takakura
<『A MEZZANIE(あ・めっざにね)』前夜>
——新作の話に入る前に、GUIROの生み出してきた作品が今なお評価を高め続けてることについて、髙倉さんがどう考えているかを伺いたいと思います。最近でも2004年にリリースした『いそしぎ』(7インチ・シングル『ハッシャバイ』および2007年発表の『Album』に収録)をあの小西康陽氏が年間フェイヴァリットに選び、ラジオ番組でプレイしていました。
髙倉一修(以下、T):本当に不思議としか…。小西さんは僕が高校生の頃にデビューされて、ピチカート・ファイヴも最初の12インチから買って聴いていました。当時からミュージシャンとしての活動に留まらず音楽にまつわる執筆もなさっていて、そこから未知の音楽を沢山教わったという人は少なくないと思うし、僕もその一人でした。『いそしぎ』という曲は96年というGUIROを始める前のエアポケットのような時期にできた曲なんですが、そもそも自作曲にスタンダードのような既存曲のタイトルを拝借するという手法は小西さんの影響です。そのご当人が時を経て自分の書いた曲を発見して下さったんですから…嬉しさ以上に驚きが大きいです。『ABBAU』というシングル(2016年)のB面に収録した「旅をするために」というランバート・ヘンドリックス&ロスのカバーの原曲も小西さんから教えてもらったようなもので。先日お会いした際に7インチをお渡しできて、そのこともお伝えしました。
——他の過去作と同様に、『いそしぎ』は曲もアレンジも音像もまったく古くならない音楽です。ボサ・ノヴァの香りを漂わせつつ、フォーキーな手触りもあって、ジャンルでは割り切れない魅力があります。
T:もしかすると時が経って聴こえ方が変わったという部分もあるのかもしれないですね。作った当時はそういう風には聴こえてなかったかもしれない。僕がリバーブを好まないとか、凝った録音ができないという状況も相まって、どこか宅録的で生々しい録音になった。そこが、フォーク的な手触りを生んだことが、当時より今の時代に合うようになったのかもしれない。
——私は遅ればせながら3年くらい前に初めてGUIROの『Album』(2007年)を聴きましたが、東西、新旧を問わずあらゆる種類の音楽を飲み込みつつ、その痕跡をすべて消し去るような優美で強烈なオリジナリティに衝撃を受けました。しかもさりげなくユーモアを漂わせる余裕すら感じさせる。まさに折衷的なポップスの高みにある作品だと思います。
T:そう言って頂けると報われる思いがしますね。リリースした12年前はSNSもないし、みんなにどんな風に受け取られているかがダイレクトに伝わってこなかったので。
『Album』収録「山猫」ライブ映像(2016年4月3日)
——さて、本作の話に移りたいのですが、今作のリリースに先立つ2018年末にGUIROを髙倉さんのソロプロジェクトから、ベースの厚海義朗さん(cero、東郷清丸、坂口恭平等)とギターの牧野容也さん(小鳥美術館、Hei Tanaka等)を加えたの三人のバンドという体制に変更しました。その理由を教えて頂けますか?
T:再始動からの数年で浮上してきた課題に、運営的な問題と、音楽的飛躍をどう手に入れていくかということがありました。演奏陣は馴染みの面々なのでバンドのように見えていたかもしれませんが、実際はすべて僕からの発信でしか動かないのでマネジメント的な部分の負担が大きくて。このままでは長続きしないと感じていました。楽曲面でも、『ABBAU』で現在進行形をひとつ示せたと思うのですが、ライヴ演奏全般では今日的なタイム感覚の共有が難しいということは表面化していました。昔一緒にやっていた仲間にそれぞれの時間が流れていたんですね。そういう中で資金面のこともあり、音源制作を急がなければなりませんでした。それはフル・アルバムにはならないけれど、今とこれからを示すものでなければと強く思えたことから、体制を見直して録音に臨むことにしたんです。それは厚海君の進化にそぐう人選に踏み切ることでもありました。同時にメンバーとして自発的に運営に関われるかということを厚海君には問い、牧野君からは申し出があり、結果3人でということになりました。
——そうした経緯を経てメンバーとなった厚海さんと牧野さんは、髙倉さんにとってどんな存在ですか?
T:うーん。そうですね…。二人ともいい友人です。真面目だし、助けてくれようという気持ちでいてくれるし、GUIROでやっていることを好きでいてくれるなっていうこともすごく感じるし。今となっては長い付き合い。気心が知れているというところが大きいですね。
——バンドの中ではけっこうディスカッションがあるんですか?
T:リハの現場ではアレンジ面などの話し合いは都度ありますが、音楽の方向性を話し合うようなことはそんなにしてないかな。たまに厚海君とあれ聴いてかっこ良かった、みたいな話はするけど。昔から「こういう音楽が好きだから」っていう趣味の合う人たちが集まってやってる感じではなくて、でも勘どころは共有できてる感じ。許容できる音楽の幅はある意味それぞれ狭くて、でも理解は深いからあまり齟齬がない。あと、僕以外は皆まあまあ楽理的な知識もあるので、厚海君と牧野君の間でなされている会話を僕はポカンと聞いている、なんてこともよくあります。
——ceroや東郷清丸のサポート等で活躍する厚海さんのベースはもちろん、牧野さんのギターも本当にすごいですね。小鳥美術館やHei Tanakaでのプレイも「もうこのままずっと弾いててくれないかな…」と思っちゃうくらいに気持ちがいい。
T:そうですよね。でも長い間アコギで歌のバッキングを中心にやってきた人で、エレキ・ギターを人前で弾く頻度が増えたのはここ数年です。だから彼自身は目下挑戦中っていう気持ちも強いんではないかな。これからますます楽しみなのではと思いますよ。
<新作『A MEZZANINE(あ・めっざにね)』について>
——いよいよ新作『A MEZZANINE(あ・めっざにね)』の楽曲について伺います。まず、もともと5曲のミニアルバムということは決めていたんですか?
T:はい。もともと収録曲は5曲と決めていました。ただ。新曲が上がるかどうかがギリギリまで危ぶまれていた(笑)。
——それが1曲目の「三世紀」ですよね。今作からバンドになったという前情報があっただけに、一曲目が全編で大胆にシンセを使った曲で本当に驚きました。このアイデアは最初からあったんですか?
T:実はあれはデモのつもりで打ち込み始めたもので。
——デモ!? あれが?
T:とりあえず自由な発想で作って、あわよくばバンドに置き換えてレコーディングできれば、という想定でやってたんですけど、とにかく締切ギリギリになってしまったんですね。隅々まで一人でやったもの特有の面白さはあるので、打ち込みに歌が乗ってる状態もありかもという話も途中から出てきてはいました。最悪の場合はこれでいこうとメンバーからも了解をもらって…つまり最悪の形です(笑)。
——スピーカーの前で聴いてると、位相が動くというか何かが蠢いているような感じがします。
T:エレピは揺れてますし、声はパンを振ってるかな。でもそんなに凝ったことはしていないですよ。
——聴き手としてはこれは一体どこから来た音だ?と考えてしまうのですが、全然参照元が見当たらない。かろうじて思い浮かんだのが後期のYMOだったりするんですけど、何か頭の中にあった音楽みたいなものはありますか?
T:あえて参照したものは何もないんです。なるべく無意識的に作りたいので。YMOは中学生の時からずっと聴いて育ってきたので影響は多大ですけど、この曲にどう出てるかはよく分からない。
——クールなアナログ・シンセの音と髙倉さんの声がすごく合っていて、ヴォーカルが始まった瞬間に、シンセの中から髙倉さんが出てきたような驚き、つまり無機的なものと有機的なものの境界が消えてしまうような感覚を覚えました。
T:全部Garage bandでつくっているのでアナログ・シンセとは言えないんですが(笑)アナログ風な…。それでも何かそのような印象が喚起されるなら、試みたことが上手く実を結んでいるということなのかもしれません。この曲は、田代さんから頂いた元詞の中にとてもイマジネイティブな節があって、そこに引き出された楽部を押し広げて曲を形作っていき、できつつある曲に沿うように元詞を解体したり、自分が歌詞を書き足して仕上げていくという、これまでにないやり方でできたものなんですが。何か形而上的というのが相応しいようなイメージを受けたんですね。丸々シンセの音になったのもそれだからだと思うし、フレーズの組み立て、和声的なものもすべてそこに引っ張られて。建築物のようなイメージもあって、中二階のコンセプトはそことも呼応している気がしています。
——この曲はすでにライヴでも演奏されていますが、これからも形を変えていく曲になっていくんでしょうか?
T:バンドで演奏する中で、いい落としどころが見つかっていけば、もう別物になってもいいです。ライヴは楽曲を育てるためのもの、という意識もあるので。
——2曲目が「ノヴァ・エチカ」ですが、「三世紀」から切れ目なく続きます。この繋ぎのアイデアは最初からあったのでしょうか?
T:曲順は想定していたので、たまたまというわけではないんですが。「ノヴァ・エチカ」のイントロがあのようになったのは、今年1月のライヴ直前に厚海君がベースをこういう風に弾きたいっていうアイデアを持ってきたからなんですね。僕はそこにシンセでハモりを重ねたいと思っていて録音の段になってやっとフレーズを考え、そのイントロの導入に更にバロック調のフレーズを付けたいと思って、亀田(暁彦)君に弾いてもらいながら2人で音を選びました。「三世紀」の完成が見えた時点で、バッハのシンフォニアを変調したものを介して2曲目に繋げてみることを思いつきました。
——1曲目と2曲目の境目があまりにもスムーズなので、「繋がっていく」というところにも意味を感じてしまったし、ひょっとして5曲を通じたストーリーがあるのかなとも深読みしたくなりました。
T:自分の意識の上ではそういうストーリーや意味は持たせたつもりはないです。でも無意識の方ではわからない。もしかしたらあのバラバラな5曲が何か繋がってるのかもしれないけど、そこは自分では説明しきれないし、できなくてもいいかなと思ってます。受け取ってくれる方に任せます。
——原曲となった「エチカ」は一度聴いたら忘れられない、GUIROの中で一番印象的なメロディを持ついわば代表曲ですが、今回新たなアレンジで収録した理由はなんですか?
T:まず単純にバンドの音から言うと、今のメンツになったことによる格好良さを端的に感じられる曲だと思うんですね。特に厚海君が考えたベースラインに対して光永渉さん(cero、Lantern Parade等)があんまり跳ねすぎない、跳ねるけどちょっとスクエアなくらいで抑える感じという絶妙なリズムを叩いてくれることで、この曲の現在のあり方が見えた気がして。この変化をちゃんと記録しておきたいという気持ちがありました。ドラムが松石ゲルさん(長年にわたりGUIROのドラムを担ってきた。レコーディング・エンジニアとしてトリプルファイヤー等も手がける)から光永さんに変わったきっかけになった曲でもあるし。なんとかやり切りたいって気持ちがありましたね。
——そのきっかけとはなんですか?
T:厚海君がやりたいと思ったリズムにならなかったということですね。努力はしてみたんだけど。そこで、それまでのメンバーでやれる形で落ち着かせるのか、またはやりたいリズムをやれる体制に変えるのかということを考えた時に、もしゲルさんがメンバーだったとしたら前者だけど、そうではない。僕らがGUIROとしてこの先も何かしら作品を提示し続けていく演奏者であるならば、やりたい形っていうものをつくらなければと決断しての新体制、結果的に交代ということになったんですね
——あのリズムにそういうものが凝縮されているんですね…。
T:そしてこの曲を取り上げたもう一つの理由は、やっぱり、みんなが好きでいてくれている曲ってこともあります。実は僕の中では、何回ももうこの曲はもうやらないって思ってきたんです。2000年くらいに書いた曲で、もう相当の時間が流れているし…。
——いや私も大好きです。
T:ね。いまだにそうおっしゃってくれる方がいる(笑)。活動を長く休んでいる間(08年~15年)も、この曲のことを口にして下さる方が圧倒的に多いんですね。で、もう諦めたんです。
——やらないことを?
T:そう。やめることを諦めまして(笑)。だからもう自分の中で別の意味が生まれています。しかも今のメンツだったら新たな感じでやれるかもしれないってのもあったので。ただ、ネックとしては、このリズムでは自分がなかなか歌いこなせないという…。
——そうなんですか?この新しい節回しがとても色っぽい感じがしました。
T:いや、ここまで持っていけて本当に良かったな、という感じです。録音の終盤までは本当に何とも言えない状態で。僕、つくった当時よりもキーがなぜか上がってるんですよ。上がった分、ハイトーンの落ち着かせどころが見つからなくて。でもその解決策として、コーラスというアイデアがあって。上の主旋律だけじゃなくて、下の部分も自分で重ねられたらおもしろいかもしれない。しかも、カッチリしすぎない思いつき的なニュアンスのあるコーラスがやれたら…と思って、最終的にこういう形になりました。
——あの少しくぐもった感じのコーラスが醸し出す、オブスキュアな雰囲気は本当に魅惑的です。あとこの曲の歌詞には現代に対する警告みたいなものを含んでいるように思えて、そこにも2019年にやる意味があるのかな、と思っていました。
T:あだち(麗三郎)君がとことん録音に付き合ってくれなければあのコーラスはできませんでした。本当に思いつきで重ねていったので。とても感謝してます。あと歌詞に関して、僕自身はあまり「時代に物申す」というような意思を持ってやらないようにしているところがあったけど、東日本大震災を経てから意味合いがちょっと変わってきたりもして…。でもやっぱりそこは受け取る側のストーリーでいいかな。もう自分の手を離れているという気がします。今となっては。
——歌はみんなのもの、という感じがありますか?
T:もしそうなるなら、それが一番いいんじゃないかな。
——そして3曲目が「祝福の歌」。これは厚海さんの作詞作曲ですが、いつ頃書かれたものですか?
T:2013年くらいにはできていたと聞いています。厚海君のソロ・ライブではずっと歌っていたらしいです。
——GUIROでやり始めたのは最近?
T:2017年に合宿的なものをやって、その時に彼が出してきたんですよね。その時のアレンジがベースになってます。
——これ、本当にいい曲ですよね、しみじみと。
T:そう!いい曲なんです。この曲があることでこのアルバムがとても良いものに感じられるというか。ホーンもパーッとした華やかさがあって。
——素直にいい曲だなぁって思うメロディで。あのちょっと強面の厚海さんがこんな曲を書くのか、というギャップが…。
T:ほんとに優しくてナイスガイですね。この曲から想像してもらったそのままの人とも言える。
——名古屋を中心に活躍している浅野紘子さんのフルートは歌に彩りを加えていますし、あだち麗三郎さんのサックスも心がすっとするような雄大さがあります。このホーンのアレンジはどなたがやられたのでしょうか?
T:ホーンのアレンジはその合宿の時にあだち君が中心になって考えたようです。その時のプリプロの録音が元になっていますが、最終的に厚海君が多少ノートの変更をした部分があるかな。あと、プリプロでは高音パートをあだち君がソプラノ・サックスで吹いていたんですが、録音にあたりフルートに変えたいとなり、それなら紘子さんにやって貰いたいねということでお願いしました。僕はこの曲はリズムパターンやコーラスを考えたのですが、それ以外はほとんどノータッチです。
——そして歌詞もとても大らかな世界観があります。
T:ベーシストとしての彼は野性的な魅力があるんだけど、そういう部分とは対照的に彼自身が作る曲はリリカルで、詞もストレートな美しさがあります。
——他の人が書いた曲を歌うのは好きですか?
T:どんどん歌ってみたいんですけど、あんまり機会がないんです。
——ちなみに牧野さんは曲を持ってこられたりはしますか?
T:6月にこの三人だけでライヴをやったんですけど、その時に彼の曲を初めて演奏しました。彼は10年くらいはずっと作曲をしていなかったそうで、それ以来ぶりの曲を持ってきてくれました。それがまたGUIROにおいては新鮮な作風で。だからこれからどんどん作るようになればいいなって思ってます。
——4曲目の「銀河」はたしか古い曲ですよね。
T:すごく古いです。95年だから、まだ20代の頃の曲ですね。
——でもレコーディングするのは今回が初めてですよね。どうしてこのタイミングで?
T:それもね、やっぱり曲がないからね(笑)。
——(笑)じゃあ逆に今までレコーディングしなかった理由はあるんですか?
T:これはGUIROでやるために作った曲じゃないので。あとは、若い時に作ったから、歌詞がちょっとこっぱずかしいっていうのもあって。
——ロマンティックなダンディズムを感じさせる、すごくいい歌詞だと思います。
T:そう思ってもらえるなら、その頃の自分に教えてあげたい(笑)。
——コーラス含めて総勢11人のメンバーによる後半の気品を漂わせながら押し寄せてくるグルーヴが印象的です。メイン・ヴォーカルの大場ともよさんの声に、落ち着いているけど華がある。まさに銀河のような、朽ちない感じがするんですよね。
T:思っていた以上のハマり役でした。彼女は自分の曲はもう少し低めの落ち着いたキーで歌うんですけど、ライヴで人の曲を高めで歌っているのを聴いたらそれもまた素敵だったんですね。知り合って2、3年くらいになるんですけど、ふと頼んでみようかな、と思ってお願いしました。にしても銀河は相当高くて、結構無理をさせてしまったけどがんばってくれて。
——GUIROは過去の作品においても、西本さゆりさん(ett等)のヴォーカル・コーラスをフィーチャーした曲が多いですよね?デュエットする「声」に求めているものはありますか?
T:昔から、僕自身はヴォーカリストとしてのアイデンティティがさほど強く持てなくて、GUIRO以前のバンドにおいてもツインボーカル的な曲だったり、コーラスの役割が大きい曲だったり、自分が作る曲は必ずしも自分で歌うのだと思っていないところがあったんですね。例えば『目覚めた鳥』などは最初からさゆりさんに歌ってもらうために作ったものでしたし、「山猫」のように二声のコーラスの絡みが大事な役割を担う曲もありました。
一緒に歌うとき、その方の声に求めているものがあるにはあると思います。自分もなかなかできているかどうか…というところではあるけれど、声に真ん丸な形を与えて、よいものが届くように発したいと思うんですね。できればそれを共有できるような方と声を合わせたい気がします。言葉で確認したりはしないんですが。
——また、このミニ・アルバム全体や最近のライブでも、亀田暁彦さんによるシンセサイザーが重要な役割を果たしている印象です。この曲でもスペーシーな広がりと風通しのよいユーモアをもたらしてくれている気がします。
T:亀田君はちょっと珍しいタイプの音楽家で、キーボーディストというよりはシンセシスト。電子音楽や現代音楽への造詣も深く、音作りと作曲が不可分な音楽を自身で作っている人です(https://phallusor.bandcamp.com/)。だからこちらに音色のイメージが具体的にある部分は音を出してもらいながら協議したりもしますが、彼が好きで出している音色の方がシャープで格好良いので、特にライヴでは信頼してお任せしています。フレーズに関してはそれなりに指定もあるので、そこは柔軟に対応して貰ってますね。
"「ノヴァ・エチカ」を収録することが決まった時点でエチカってラテン語が基になっているので、曲のサブタイトルにラテン語をはめていくのはどうだろうと思いついたんです。"

——そして最後が「東天紅」です。これはライヴでは演奏されていますが、比較的新しい曲ですよね?
T:そうです。「三世紀」の次に新しい曲です。とは言え、もう3年近く前になりますね。
——ライヴの後半でこの曲を聴くとすごくホッとするような気持ちになります。航海が終わって帰ってきた船を受け止めてくれる港のような。
T:これはもう歌詞に導かれた感じの曲ですね。
——田代万里子さんによる歌詞が先に詞があったということですか?
T:そうです。もう10年くらい前に頂いた歌詞です。彼女は三重でモノポリーズというバンドをやっていて、歌詞がすごくいいなって思っていたので、何か書いてくれませんか?ということをチラッとお願いしたら、ホイっという感じでくれたんです。で、それに曲をつけてみようと頑張ったんだけどつけられず、10年くらい置き去りになってしまって。でもいつかは、とはずっと思い続けていたので、彼女がソロ作品を出した時のレコ発ライヴに出てほしいと誘われた時に、今がそのタイミングかもしれない!とトライしてみたら、割とスッとできたんです。
——それはちょっとといい話ですね…。すごく包み込むような大きさが、歌詞にも曲にもあります。
T:ありがとうございます。作った本人が言うのもあれですが、聴いてるだけで何だか夢の中の光景のようなものが浮かぶんですよ。歌詞をよくよく読めばまあそんな内容ではあるんですが。あと、自分としてはちょっとノベルティソング的な感じがあります。アルバムだったら収録されないかもしれないというか。
——いわゆるシングルのB面的な?
T:そう。GUIROの他の曲と相容れないようなところもあって、ちょっとこぼれてしまう感じ。だけど、作曲者として「こういうことができた」という喜びがあるような、今まで絶対できなかったことができている部分もあるんです。
——髙倉さんの趣味的な色も濃いけれども、演奏やアレンジがかっこいい。西尾賢さん(ソボブキetc.)のピアノやスティール・ギターもエキゾチックだし、戦前・昭和の大衆音楽の香りもあって。
T:西尾さんのピアノには和の心じゃないんだけど、何というか間とか奥ゆかしさを感じてしまうんですね。そういうものが当たり前に備わっていたような昔の日本の音楽が西尾さんも僕も好きだっていうところもあって。スティール・ギターは、まあマヒナスターズ好きだからね。しかし西尾さん、この曲のために買って1週間で弾けるようになっちゃったんですよ。しかもテイクワンOK!(笑)。この国ならではのメロディの感じが忘れ去られてほしくないって思いもあるし、でもそういうものをただやるだけではなくて、そこに何か曲としての新鮮さや新しい試みを入れたいと思っていて、それができたなって感じがします。
——その新しい試みとは、具体的にはどのような部分ですか?
T:試みと言ってしまいましたが偶然にできただけでした(笑)。この曲、転調だらけなんですね。サビの♪いつもあなたの~からのコード進行もその前の進行から転調していると思うんですが、メロディの乗り方がちょっと変わってるんです。で、その変わってる感じが急にこれ夢の中なんだと気づかせてくれるような効果を生んでるなと自分では感じていて。分かる方に説明してもらいたい。それと、♪その地図によれば~道は違い、の“道は”のところに当ててるコードははじめて見つけたもので、これはいつかのむかしに連れて行ってくれる切符のような役目を果たしてくれています。あくまで自分にとってですが。で全体に明るいトーンの曲なんだけど、あの世との境目のような感じもする。
——あの世とこの世の境目!そこがこんな世界だったらいいなと思います。
T:このミニ・アルバムを聴いてくれた方からは、最初の曲(「三世紀」)とこの最後の曲(「東天紅」)が妙に繋がっていると言われることが多いんですよ。ちょっと意外でもあるけど、個人的には嬉しいんです。一番最近に書いた2曲だし。
<アルバム全体を通じて>
——5曲すべてについてお話しを聞かせてもらいました。髙倉さんの中で、この作品がどういう意味を持ったらうれしいなって思うところはありますか?
T:うーん。だって5曲しか入ってないからねぇ…(笑)。フル・アルバムでもないし。でもフル・アルバムじゃない割には力が入ってますね。
——いや、めちゃめちゃ濃いですよ。
T:完成形が見えない状況でギリギリまでやってて、こういう感じになったって感じなんですよ。自分でもこの作品がどんな意味を持つのか、説明がつかないな…。
——ちなみに《A MEZZANINE》つまり《中二階》というタイトルの意味を改めて伺いたいのですが、ただ単にアルバムでもシングルでもない、その間って意味だけじゃないですよね?
T:もちろんそういう意味もあるし、ファースト・アルバムとセカンド・アルバムの間という意味とも取れるんですけどね。そもそもこのバラバラな寄せ集めの5曲を一括りにできる言葉は無いものかということで浮かんできたものです。でも自分にとって中二階ってすごくいいイメージの場所なんです。京都にある民芸運動の中心人物である河井寛次郎の記念館に行った時、その建物の中に妙な高さの部分があって、そこがとても魅力的に見えたことがあったんです。ここでもそっちでもない、そのあいだ。それ故にすごくいい空間である。このミニ・アルバムもそういう作品であってほしいな、という願いを込めました。
——なるほど。
T:そして、「ノヴァ・エチカ」を収録することが決まった時点でエチカってラテン語が基になっているので、曲のサブタイトルにラテン語をはめていくのはどうだろうと思いついたんです。「銀河」は直訳するとGalaxyなんですが、歌詞の内容から考えて「天の川」を意味する「Via Lactea」と意訳しました。「祝福の歌」もちょっとキリスト教的なニュアンスがあって面白い(副題は「Canticum benedictionis」)。それに従って中二階は何というのかということで調べたらば…『A MEZZANINE(あ・めっざにね)』だった。
——髙倉さんがラテン語そのものに惹かれる理由はあるのでしょうか?
T:ブラジル音楽が好きだったということがあります。そしてブラジルやヨーロッパを含めた広い地域のベースになる言葉なのでたぶん親しみを感じるのかな。でもラテン語自体は既に公用語ではないという、妙に浮いているところがおもしろいなって。
——でも、そのラテン語や《A MEZZANINE=中二階》というイメージは、GUIROと通じるところがある気がします。ポップスとしての親しみやすさもあるけど、どこか聖的でアート・コンシャスなものがあるし、普通のバンドかと言えば違うし、でも散発的なプロジェクトというわけでもでない。
T:なるほど。でもその辺は狙ってどうこうできるものではないし、この先どうなるかわからないですけどね。どうなるのかなぁ。
——今は空っぽですか?この作品で出し切った?
T:いや、常に空っぽですよ。次できるのかなって。
——そういう状態って不安な気持ちですか?
T:何十年もこれでやってるから。そこはもうね。やらないともう後がないって部分もあるし。
——いや、いつまでも待ってますよ。
<了>
◾️GUIRO OFFICIAL SITE
http://guiro-som.com/