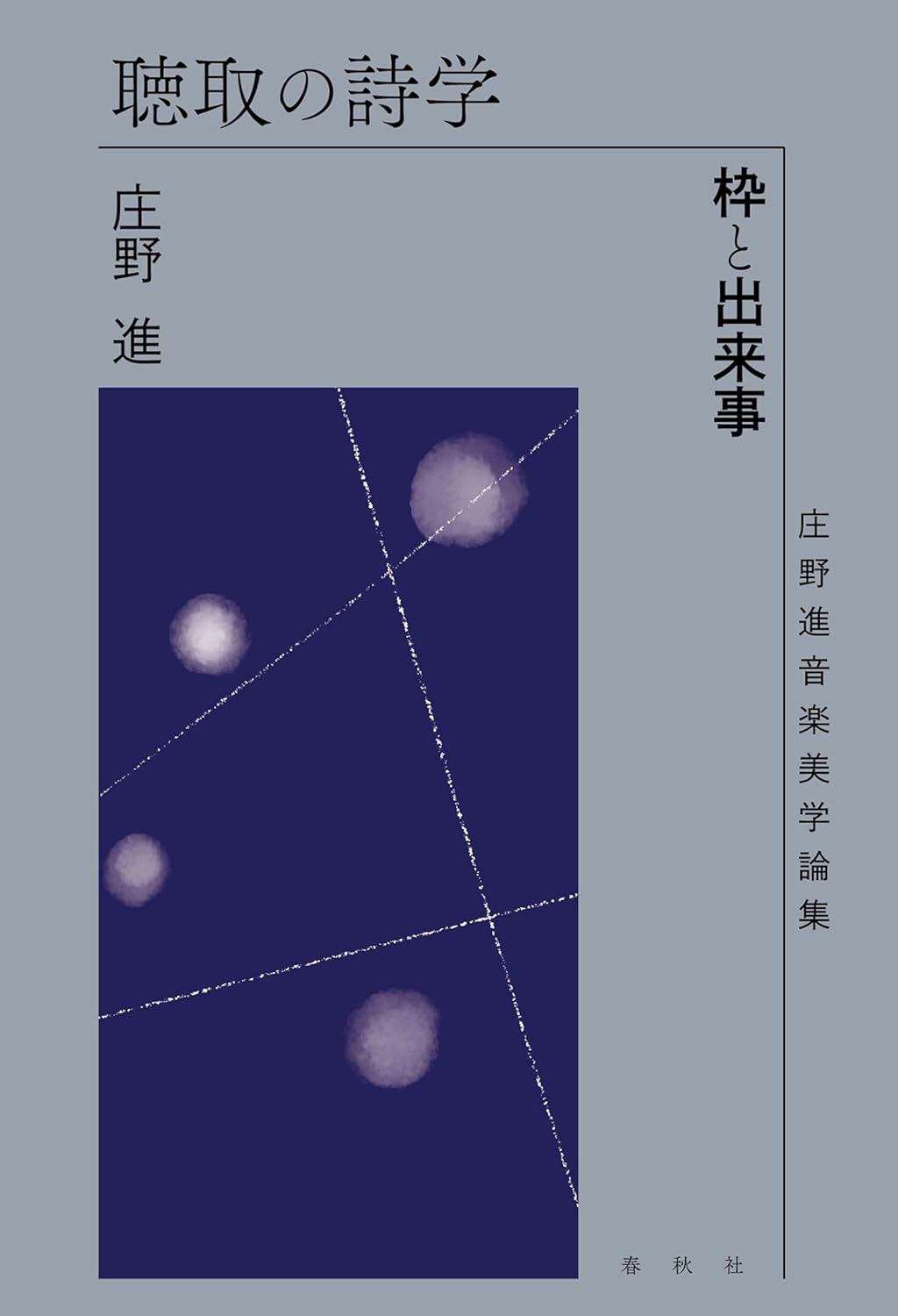【From My Bookshelf】
『聴取の詩学: 枠と出来事 庄野進音楽美学論集』
庄野進(著)
ジョン・ケージの部屋から環境音楽まで。「聴取の詩学」という思考
聴取の詩学の構想
2023年に亡くなった音楽美学者・庄野進(国立音楽大学名誉教授)による『聴取の詩学: 枠と出来事 庄野進音楽美学論集』は、タイトルだけでまず立ち止まらされる。「聴取の詩学」。これは、耳で受けとるという、あまりにも当たり前すぎて逆に説明しづらい行為に、あえて詩学ということばを与えることで、その行為そのものをもう一度組み立て直そうとする態度を示している。単に「どう聴くべきか」というマナーの話ではない。音がつくられ、空間に投げ出され、誰かの耳に届く。その一連の出来事の生成と受容を、能動的な思考の場として扱うためのことばが「聴取の詩学」なのだと、読んでいて理解させられた。
本書は1991年に刊行された原書『聴取の詩学』を土台に、大幅な増補を施した論集である。もともとの『聴取の詩学』では、庄野の主要な思索の軸となったジョン・ケージ、そしてケージと接続される形で論じられるフルクサス運動、スティーヴ・ライヒやフィリップ・グラスらのミニマル・ミュージック、さらにはモートン・フェルドマンといったいわゆる記譜音楽/演奏音楽の境界をゆるませていった作曲家・美術家たちが大きく扱われている。そこでは、音楽を「作品」として閉じるのではなく、聴取という行為そのものが作品の生成にどこまで関与しうるのか、という問いが一貫している。
ケージとその周辺
とくに印象的なのは、フェルドマンに割かれた章で、抽象表現主義の画家たちの作品、たとえばマーク・ロスコ「No. 16 {Green, White, Yellow, on Yellow}」(1951年)やフィリップ・ガストン「To B.W.T.」(1952年)とフェルドマンの音楽を並置しながら、「表面」をめぐる感覚経験を音楽/絵画の両側からほどいていく「第六章 M・フェルドマン──表面の音楽」だ。フェルドマンを単に図形譜といった実績で語るのではなく、抽象絵画の肌理と同じ次元で音を扱おうとした芸術家として浮かび上がらせる書きぶりは新鮮だ。私はこの本を読みながら、でてくる音楽や上演作品や絵画の作品名を逐一ウェブ検索し、鑑賞しつつ読み進めたのだが、そうやって読むと、テキストそのものが展覧会めぐりと試聴の中間にある散策記のように立ち上がる。読むのに時間は数倍かかってしまうが、その遅さこそが本の贅沢さでもある。
庄野がとくにこだわっている概念として、本書のサブタイトルにもなっている「枠と出来事」という言い回しがある。これはケージを論じる際にもっとも鮮明になる。ケージといえば「4分33秒」や無響室体験のエピソードが真っ先に参照されがちだが、庄野はそこだけでは止まらない。1960年代末から70年代にかけての、Chaep Imitation」(1969年)や「Etudes Australes」(1974〜1975年)と同時期に、ことば、版画、グラフィック、イヴェントなど音楽の外側のメディアへ活動領域をぐっと拡げていたケージに、じっと視線を注ぐ。
「音楽実践においていわば自在の境地に達したケージが、今度は美術の可能性を追求し始めたともいえるし、偶然性の音楽において前面に現われた「枠と出来事」という発想の延長上で、視覚的な出来事や文学的な出来事を見たり、読んだりすること、つまり聴取のみならずあらゆる感覚の詩学の可能性を探求し始めたとも考えることができよう。」(P162-163、第七章 J・ケージへ)
たとえば、ある原文から文字の断片だけを縦に拾い上げることで、読む順路そのものを作品化してしまうメゾスティックス(「マルセル・デュシャンに関する、あるいは関しない36のアクロスティックス」〈1970年〉)や、行き先や停車駅をあらかじめ指定した列車そのものを媒介として聴取体験を組織する〈汽車──失われた沈黙を求めて〉(1978年)のようなイヴェントを、庄野は音楽作品と地続きのものとして扱う。そこでは「どこからどこまでが作品なのか?」「どこからが素材で、どこからが出来事なのか?」という問いが根本にある。ケージの活動空間そのものを、つまり「枠」をどう切りとるかによって、我々が「出来事」と呼びたくなるものが立ち上がる。庄野は、ケージが自宅の壁を何度も塗り重ねた塗膜をあえて剥ぎ取り、色や質感の層を露出させ、それ自体を楽しむといった日常的な遊びにも同じ原理を見る。観葉植物や拾ってきた石、机の上の鉛筆までもが、すでに「作品」でありうる。そのどこに枠線を引くのか、そしてその枠の内側で何が出来事として認識されるのか。庄野はそれを「枠と出来事」と呼び、そこにケージの実践の本質を見ている。
環境音楽と感覚の倫理
増補版ではこの見方がさらに広がり、いわゆる「環境音楽」についての章「環境への音楽──環境音楽の定義と価値」(1986年)でも活きてくる。庄野が文章を書いている1980年代半ばには、いま私たちがアンビエントと呼ぶような音響だけでなく、BGMとしての音楽、野外パフォーマンス、環境設計と一体化したサウンドスケープなど、非常に幅広い領域が「環境音楽」という言葉でひとまとめに語られつつあったそうだ。庄野はその雑多さをごまかさず、むしろ丁寧にほどいていく。
彼はまず、実際の空間で演奏される音楽行為そのもの(演奏会場で鳴る音)を「環境の中の音楽」と呼ぶ。つぎに、特定の機能を果たすために音が設計され、BGMのように場そのものを組み替えるものを「環境としての音楽」と位置づける。そして、ブライアン・イーノのアンビエント・ミュージックやフィールド・レコーディングのように、人為的につくった音と、そこにすでにある環境音とが交わることで初めて成立するタイプを「環境への音楽」として区別する。つまり「環境音楽」という一語のなかで、どこに枠を引いて、どの出来事を作品としてカウントするのかで、まったく異なる実践が含まれていることを明らかにしていく。
「重要なことは、作品の形式を構成する限りで、このような作品外の環境的な音が取り入れられる、あるいは再構成されるということの背後に、自然よりも芸術の方に価値があるという観方が前提としてあるという点である。これは、無形態な自然を克服するという、西洋文化に伝統的な自然支配の思想に基づいていると考えられよう。」(P274、環境への音楽)
このとき庄野が鋭いのは、自然の音や都市の雑音が作品に取り込まれるとき、それは単に「自然そのものが尊いから聴こう」という態度ではない、と指摘するところだ。むしろそこには、西洋芸術の長い系譜にある「自然を素材として扱い、形を与えることで価値に変える」という思考が横たわっていることに彼は言及する。14世紀イタリアのカッチャにおける街の喧騒の描写や、16世紀フランスのシャンソンにおける鳥の鳴きまねなど、伝統的な音楽ですでに行われていた環境の取り込みまで遡って検証しながら、庄野は問いを拡張する。環境音はいつ、どのように「素材」になり、どこから自律した表現主体としてふるまい始めるのか。その見きわめの仕方こそが、聴取の倫理や政治性に関わるのだ。
庄野進とケージの対話:音楽の外に存在する音について
ケージへのインタビュー(1985年、1990年)を中心にまとめられた増補部分「II ケージとの対話」では、その問題意識が生のかたちであらわれる。ケージはつぎのように語っている。
「私は未だ受取っていないのですが、最近科学的実験が行なわれ、沈黙のようなものは存在しないということが明らかになってきましたーいつも音があるのです。即ち、UCLAの博士がその実験を行ない、今言ったことを証明する論文を私に送ってくれることになっているのです。しかし私の書いた本〔註:『サイレンス』〕の中では私もいつも音があるということを書いています。人間は目を閉じて何も見ないことができますが、耳を閉じることはできないのです。」(P188、ニューヨークの森の中で)
ケージは、世界にはつねに音が満ちており、完全な沈黙というものは存在しない、という自分の基本的な立場をあらためて語っている。人間は耳を閉じて視覚を遮断することはできるが、聴覚を閉じることはできない。だからこそ、音を排除すべきノイズとして扱うのではなく、そこにある音をどう楽しむか、どう関係を結び直すかが問題なのだ、という方向へ対話は進んでいく。これは、環境音の人体への悪影響を測定しようとする科学的アプローチや、公害的な「騒音」をいかにコントロールするかという行政的な文脈への素朴な期待とは、すこしずれる。ケージは、なぜある持続音は快く感じられ、あるいは別の音は不快に感じられるのかという、感覚の質そのものに興味がある。庄野はこの答えを、単なるエピソード以上のものとして受け取っているように見える。聴取する主体はつねに環境のなかにいて、そしてその主体が「これは音楽だ」「これはそうではない」と引く枠線こそが、出来事を作品化していくのだと。
こうして見ると、「聴取の詩学」というタイトルは、けっして抽象的なレトリックではない。むしろ本書全体を貫く実務的なキーワードに近い。ケージの部屋の壁の塗膜、フェルドマンの音の表面、ロスコの画面の揺らぎ、BGMとして設計された空間音響、イーノのアンビエント、街の雑踏、鳥の声。それらは全て、同じ地平に並べて良いものとして扱われる。ただしその同じ地平は、鑑賞の態度をぬるく均していく相対主義ではない。むしろ逆だ。どの音/どの現象を「出来事」と呼び、それをどんな「枠」によって切り出すのか。その選択こそが、聴取行為の詩学だと言われているのである。
私は読みながら、その「枠を引く」という身ぶりを、YouTubeのゲーム実況動画をバックグラウンドで流しっぱなしにするときの自分の聴き方や、コンビニで聞こえる音声広告のイントネーションの妙にふと注意が向く瞬間に、少し引き寄せて考えてしまう。私たちは日常的に、もうすでに小さな「枠と出来事」を発生させているのではないか、と。庄野のテキストは、それを難しい用語で遠ざけるのではなく、むしろ手元の感覚へ呼び戻す装置として機能する。
※本文中の書籍からの引用箇所は、おおまかにチャンス・オペレーション(偶然性の手法)によって選択されています。(髙橋翔哉)
Text By Shoya Takahashi