Beirut Original Album Guide ~サンタフェから世界へ……チャンス・ザ・ラッパーも魅了するBeirutの音楽旅
『Gulag Orkestar』(2006年)

エミール・クストリッツァ監督の諸作品や、そのクストリッツァもメンバーのノー・スモーキング・オーケストラのアルバムと並べて聴くと確かに気づく。ジプシー・ブラスやバルカン音楽の哀感溢れる情熱に魅せられてこのファーストを制作したのだろうということが。だが、一方でシナトラもかくや…のヴォーカル・ミュージックとさえ呼べる震えるようなしなやかな歌声が、聴き手のそうした明確なルーツ特定の目線を煙に巻く。君は誰なんだ。ここはどこなんだ。彼の名前はザック・コンドン。ここはニューメキシコ州アルバカーキ。でも、300年前、ここはヨーロッパからの入植の地だったはず。そんな時空と地域を超えたロマンティックな批評性がこのアルバムを今なお輝かせる。昨年来日したA Hawk And A Hacksawのジェレミー・バーンズ(もちろんニュートラル・ミルク・ホテル!)とヘザー・トロストも参加。(岡村詩野)
『The Flying Club Cup』(2007年)

ノスタルジックなメロディー・ラインを軸とし、オーウェン・パレットによるストリングス・アレンジが作品に奥行きと端麗な色彩を加えている。前作でバルカン音楽へ向けられた視線は西方へ。ザック・コンドンがパリ滞在を経てたどり着いたのは、20世紀初頭のパリ上空を飛ぶ気球の物語という作品コンセプト、シャンソンへのアプローチだった。本作は「ロック」というクリシェに嵌らず、いま・ここにはない彼方の音楽と繋がりながら生まれ出るグローバルな大衆音楽の可能性を示す。実際、チャンス・ザ・ラッパーは本作の「Nantes」を自身の「Long Time」でサンプリング。ストリーミング・サービスによりポップの世界地図がゆらぐ今こそ聴かれるべき作品だと思う。(尾野泰幸)
『The Rip Tide』(2011年)
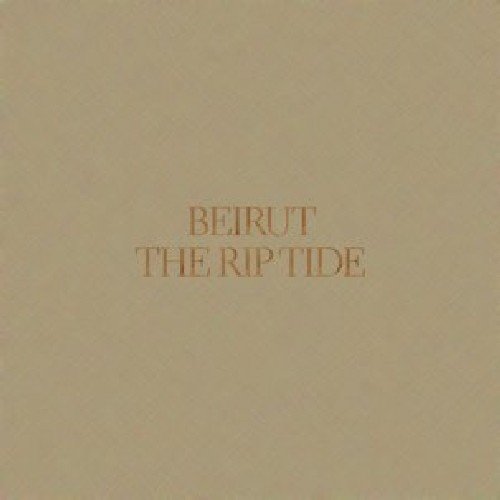
世界を旅するベイルートが選んだのはアメリカ。2010年、パティ・スミスが「ニューヨーク市は私達の街ではない、街を探さないと」と発言。様々なアーティストが州内北部や州外に移動していた国内の動きに呼応するように故郷=「Santa Fe」はじめ「East Harlem」と母国を見つめながら海を目指した本作。USポップミュージックを感じる歌主体の楽曲群、けれどオーセンティック過ぎないのはギターを持たずウクレレやトランペットを演奏する彼らしさがそのままだから。現在の居住地ベルリンへと続く旅の根源を振り返る重要作。(加藤孔紀)
『No No No』(2015年)

ザック・コンドン自身の病や、妻との離別が大因となったであろう内省的で、悲哀に満ちたリリックが胸に迫る。だが、それとは対象的にあっけらかんと鳴り響くポップなサウンドが素晴らしい。前作同様に特定地域への(音楽的)焦点化は行われず、シンプルで普遍的なチェンバー・ポップが展開する。本作に明瞭なポップさを与えているリズミカルなピアノや、ギター・サウンドの前景化など、より身体的で動的なサウンド・プロダクションと併走して、思考は深く、深く脳裏の底へと沈み込んでいく。陰と陽。静と動。ベイルートというプロジェクトの二つの顔を示す一枚。(尾野泰幸)
『Gallipoli』(2019年)

ベイルートの、そしてザック・コンドンのルネサンスーーそんな賛辞を贈りたい。『Gallipoli』から押し寄せるのは、音楽を創ることの悦び、音を奏でることの悦びだ。端正に整った歌モノとしても聴けた直近作『No No No』(2015年)などに比べると、ラフな構成の楽曲が多い今作。演奏も、均質には整えられていない。だが、あくまで自然体のままの演奏で形づくられた楽曲たちは、本当に伸び伸びと楽しげなのだ。それは、定型化された現代のポップやロックの枠組みから解き放たれているということ。ドラム・セクションの刻む拍も比較的自由でオン・グリッドではないし、また弦楽器が支配的でなく、これまで以上に金管楽器中心の構成となっていることからも、それが伺えるだろう。
ただの懐古趣味ではない。むしろその逆で、今作でとりわけ驚かされるのはその特異なサウンド・プロダクションだ。恐ろしくデッドな音色のドラム・セクションをはじめとした生々しい密室感と、ホーンの突き抜けるような華やかさが共存、ラフな手触りは残したまま、くっきりとした今風の輪郭にまとめあげられている。どうしてこんな音に仕上がるのか、ちょっとびっくりするくらいだ。
東欧~地中海音楽に根差しそれらを時代をも超えて敬愛してきたザックだが、それは決してコロニアリズムではない。南イタリアの中世の城塞都市で目にした市民の行進がモチーフの表題曲には、旧い街に息づく人間の営みへの驚嘆が、ダイレクトに、そして素直にあらわれている。現代的に過度に整えられていない演奏と構成で描いたその古きよき光景に、自身の驚きと興奮を先鋭的なサウンドでもって注ぎ込んでいるのだ。我々が忘れていた何かがふいに意味を持ち、それに再び色を与えるーーその瞬間の鮮やかな体感が、この『Gallipoli』そのものなのだ。まさにそれはちょうど、ザックが今作のために、かつて使っていた古いファルフィッサのオルガンを蘇らせたような具合に。(井草七海)
■Beirut Official Site
https://www.beirutband.com/
■ビートインク内アーティスト情報
https://www.beatink.com/artists/detail.php?artist_id=1450
