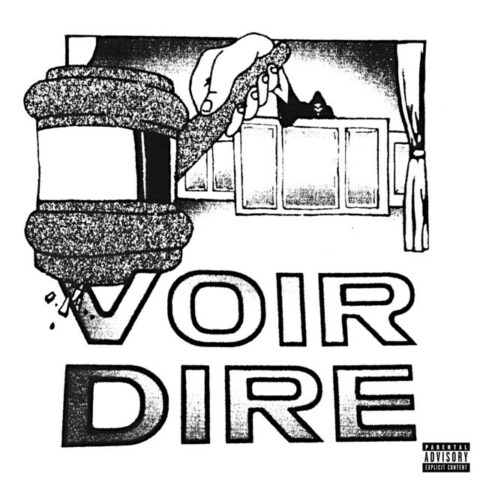安らかさを獲得するために、散りばめられる真実の断片
真実とは模倣不可能なものであり、虚偽とは変形不可能なものである。
──ロベール・ブレッソン『シネマトグラフ覚書―映画監督のノート』より
アール・スウェットシャツは“真実”が自分自身の中にしかないことを知っている。恐らくはそうなのだろう。耳障りなノイズ。身軽なスネア。喋り声。2010年のミックステープ『Earl』に遡ってみても、そこで鳴る音は、触れそうなくらい生々しさを湛えている。
2018年、アールは『Some Rap Songs』で自らの父の死を、あたかも永続的に続いていくようなビートとラップの洪水にて悼んだ。24分間。断絶することなく、もっと言うのであればその境目をできるだけ曖昧にするように垂れ流されるビートと、途切れることのない、まるで喋り続けているようなラップ。『Some Rap Songs』は、背景に重く沈み込むようなものを抱えながら、驚くべき聞きやすさ、いや、聞かせてしまうような催眠術にも似た魔力を持った作品だった。それは『Doris』(2013年)にも見られた鬱や喪失、父親という存在に対する複雑な思いがより濃厚に感じられるからでも、単にタイトであるからというだけでもない。その境目のなさ、流動的的な様が、彼の感情の渦中に放り込まれるように、あまりに生々しく、時に美しくもあるからこそ危険なのである。流れる音と言葉は次々に現れて、鮮烈に私たちの脳裏にこびり付いては、消えていく。
あるいは聴き始めればもう戻ってこられないのである。その後戻りのできなさが切なさを生むし、病みつきにもなる。改めて言うのであれば、やはりこれは彼のディスコグラフィの中でも特別な作品なのだろう。多くの人が認めるように、以前以降を分けるような作品でもあるし、“死”に対する意識を、一連の流れの中で提示した、あるいはそういう風に魅せた作品としてJ・ディラ『Donuts』(2006年)とマック・ミラー『Circles』(2020年)の間に並べてもいいかもしれない。
ともかくそういう音楽だったのだ。まるで渦中に放り出されるかのごとき生々しさ。身軽さと深刻さの同居。少なくとも私にとって、これが明らかな魅力だった。
恐らくそれは、アール・スウェットシャツのラップが、時にタイトに言葉をスピットしていくことも深く関係している。彼から放り出される言葉は多くの場合において抽象的だが、その意味をじっくり考えさせる間もなく、全てをタイトに済ませていた。止まってなどくれない。
しかしだからこそ暇な時にジャンクに聞きたくもなるし、意味を追求し何度も繰り返し聴いてみたくもなる。彼の音楽の手軽さと上質な噛みごたえは中毒性があるし、クラブでも部屋でも路上でも、いつどんな時でも彼の音楽を流すという選択肢を私の中に与えるような…要は頭から離れづらいのである。
どこにでもついてくるような音楽。アール・スウェットシャツの作品をそう感じている身としては、昨年のアルバム『SICK!』の洗練は、いささか私を冷静にさせた。『SICK!』は『Some Rap Songs』以降のタイトさと制止不能な感覚を湛えながらも、今まで以上にクリアな質感と緩急を提示していた。ざらついたフィルムの画は鮮明になり、粒子の数も減った。1曲目「Old Friend」で降った雨が、続く「2010」のリリックの描写に引き継がれていたりもして、芸や演出も細かく抜かりがない。パンデミック以降のアウトプットとしての『SICK!』は弾けていてアイロニカルでありながらも、これまで以上に統制されたものが確かにあった。一方で、まるで、思わず口から出てきてしまうわけではないが出すとスッキリする嘔吐物のように、真実らしいものを、自分自身から出しているアールの姿は健在といえる。
それが一貫されている限り、馴染み深いアルケミスト(The Alchemist)とのコラボレーションで送る新作『VOIR DIRE』が退屈なレコードになることなどないだろう。“真実を語る”という直球のようなタイトルは、アール・スウェットシャツの新作に相応しい。
因みにこれは言っておいた方がいいと思うが、この作品には二つのバージョンがある。一つは《Gala Music》というウェブサイトで8月に配信、もう一つは10月に各音楽ストリーミングサービスで配信されている。約2ヶ月遅れて配信になった後者は、前者収録の「All the Small Things」「My Brother, the Wind」「Geb」の代わりに、「Heat Check」、そしてヴィンス・ステイプルスが参加した「Mancala」「The Caliphate」が収録された。実際、録音時期も様々に異なるアルケミストとの曲が集められたミックステープ的作品という側面が強いだろう。
ここでは、主に後者のことについて話そうと思うが、そこでまず注目したいのは、ヴィンス・ステイプルスとの蜜月だ。先述のミックステープ『Earl』からラップを交わしてきた両者は、この10年以上の間にも、お互いの作品に頻繁に登場してきた。本作におけるヴィンスのラップは、まさしく彼らしいレトリックに溢れているが、それはアールとのやり取りの中での文脈も強い。「Mancala」では、子供時代の家庭環境を回想するアールと、ロングビーチのストリートの記憶を回想するヴィンスの姿が窺え、互いの昔話(目にしてきたもの)を語り合っているような関係性が見える。また、「The Caliphate」のアールのヴァースにおける鮮烈な血の描写は、『Doris』収録の「Burgundy」が血の色を意味していたことを思い出す。アールとヴィンスのやりとりには具体的な痛みが常にある。アールの憂鬱に内省的な表現は変わらず確認できるが、そういった楽曲に視覚的な痛みの描写を浮かび上がらせるのが、ヴィンスの存在なのである。
その中で、今回のアルケミストの仕事はというと、『SICK!』と比べるとシンプルかもしれないが、多様な音を入れながら洗練され、十分に私たちを引き込む。大仰なストリングス、ジャジーなピアノの音色。「Vin Skully」におけるRalph Graham「Stay on the Good Side」のサンプルループ。魅力的な細部に溢れるが、全体を見た時に各曲のムードの差は浮き沈みを表現しているのだろうか。まるで、“底なし沼でも浮かんでいられる方法”(Vin Skully)を探すアールに寄り添うように。
これは特に「Sirius Blac」や「Dead Zone」に顕著だが、本作におけるアールのラップは特徴的だった弾力性や瞬発性よりも、低い声で言葉を紡ぐしなやかな感触が強く、どこか落ち着いている。どうやら過去に向き合うアールは安定を、安らかさを渇望しているようだ。その様子は、様々な意味で“渦中”の作品であった『Some Rap Songs』から数年経った今では、当然のことのようにも思える。最終曲「Free the Ruler」のタイトルが2021年に他界したドレイコ・ザ・ルーラーのことを表しているように、今まで同様“死”に関する言及にも溢れてもいるが、アルケミストのサウンドに腰を落ち着かせ、今まで以上に冷静に、過去と向き合っている気もするのだ。
絶え間なく流れる言葉の中で、彼が描いてきたものは自分の目の前のこと、内側のこと。それは他の誰でもない、自分の中にだけ存在するもの。唯一無二の彼が辿り着こうとする安らかさは、今までの彼と、今の彼と、そしてこれからの彼に耳を傾けなければ見つからない。だからそこで聞こえる、その声の変化も、サウンドの抑揚も、話し声も、過去のメロディーも、全てがこの『VOIR DIRE』に集められた真実の断片なのである。(市川タツキ)
関連記事
【REVIEW】
MIKE『Burning Desire』
http://turntokyo.com/reviews/burning-desire-mike/
【REVIEW】
Navy Blue『Ways of Knowing』
http://turntokyo.com/reviews/ways-of-knowing-navy-blue/
【REVIEW】
Slauson Malone 1『Excelsior』
http://turntokyo.com/reviews/excelsior-slauson-malone-1/