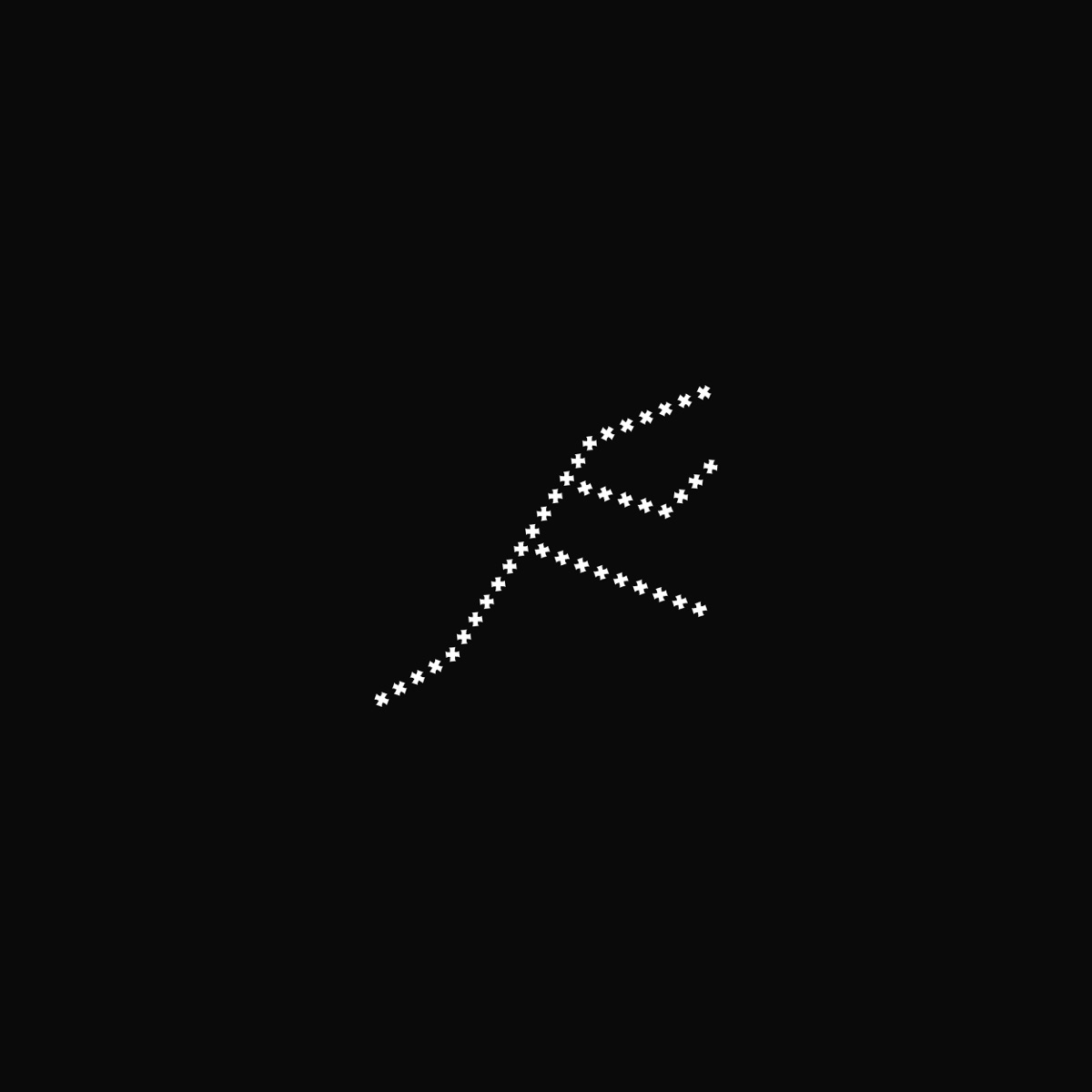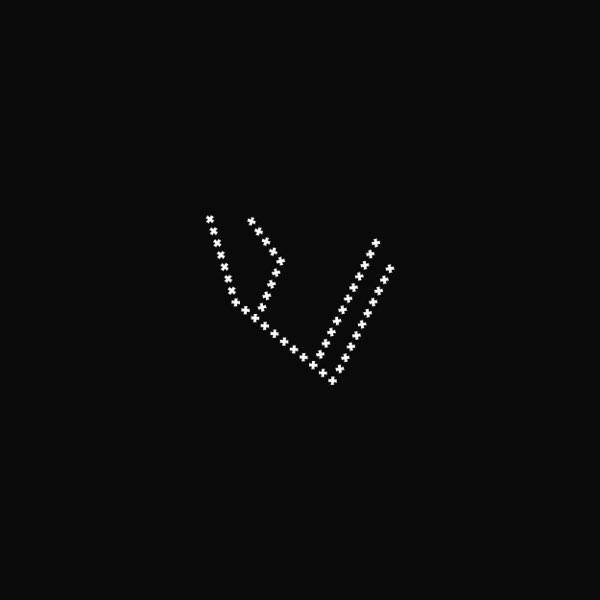ニコラス・ジャー『Piedras 1 & 2』
チリ現代史を巡る悼みと抵抗のアヴァンポップ
近年ではザ・スマイルやPJハーヴェイのミュージック・ビデオを手がけていることでも知られるチリのアーティスト・デュオであるクリストバル・レオン&ホアキン・コシーニャの短編『名前のノート』(2023年)は、チリのピノチェト独裁政権下で行方不明になった子どもたちの記憶を巡る作品だ(日本では彼らの長編第2作『ハイパーボリア人』と2025年2月に同時上映される)。そこでは、政治の横暴によって犠牲になった者たちの名前が読みあげられ、物悲しいタッチの手描きのアニメーションが被害者たちの癒えない悲しみに寄り添おうとする。あるいはチリの映画監督パブロ・ララインによる『伯爵』(2023年)は、アウグスト・ピノチェトが吸血鬼として250年生き永らえている設定のダーク・コメディであった。昨年は1973年の軍事クーデターから50年という節目の年であったため、こうしたモチーフが目立っていたということもあるが、チリのアーティストたちはチリ現代史をどのようにアートに反映させるかという挑戦をいまも続けている。そして、ニコラス・ジャーによる4年ぶりのソロ・アルバムである本作も、そうした動きに連動するものである。
ピノチェトによるクーデターの際にチリを脱出してニューヨークに移住した両親を持つニコラス・ジャーが、チリの虐殺をモチーフにしたのはセカンド・アルバム『Sirens』(2016年)収録の「Three Sides of Nazareth」でのことだった。それはジャーにとって音楽的な飛躍を助長する主題だったと感じられるし、政治的な作品を多く手がけてきたアーティストである父アルフレッドの軌跡をパーソナルにたどることでもあっただろう。彼のチリのルーツに対するアイデンティティは、つねに政治や歴史と切り離せないものだった。
『Piedras』はチリのサンティアゴにある人権博物館でのコンサートのために「Piedras」を書いたことに端を発したプロジェクトで、『Archivos de Radio Piedras』というラジオ劇やインスタレーションに発展したものを音楽作品としてまとめたものだ。もともとは1973年から1990年にかけておこなわれた人権侵害の犠牲者を悼むものであったが、ラジオ劇としてはサリナス・ハスブンという架空の作家兼ミュージシャンの失踪を追うものになっているという(ここがピノチェト政権下で起きた事件と重なる)。その劇は遠くない未来のチリでインターネット遮断攻撃がおこなわれたという設定になっており、そのため通信にはDIYラジオが用いられる。そこで流れるのがこの音楽だ。つまり、ある種のSF作品であり、そこではディストピアめいたチリ社会が夢想されている。
ゆえに本作では、未来的な音楽が志向される。これまでもDJ、アンビエント作家、実験的なエレクトロニック・ミュージシャン、サイケ・ポップ・プロジェクト(ダークサイド)の片割れと多面的な要素を見せてきたジャーだが、ここでは未知の音楽を創造するためにさらにエクレクティックなサウンドに挑戦し、『1』ではレゲトンなどのラテン・ポップ、フォルクローレ、インディー・ロック、ノイズ、IDMが入り乱れた歌ものが多く収録され、『2』では瞑想的なダーク・アンビエントから始まり、アップテンポのビートの連打で終わっていく。ただそこで興味深いのは、未来の音楽だからといってそれが必ずしも新しいわけではなく、過去の音楽の残骸や反響音が混ざり合っていることだ。スクラップされたものとしてのポップ・ミュージック。荒廃した近未来で漂っているかもしれない音楽──それは、散らかっていて、不定形で、悲しい。この物悲しさは、チリの歴史の狭間に消えていった人びとを悼むことからもたらされている。また、チリに多く住んでいるパレスチナ難民とその子孫の苦しみにも光が当てられ、現在ガザで起きていることとも接続される。
ファースト・アルバム『Space Is Only Noise』(2011年)がリリースされたとき、前衛を標榜する両親からはレフトフィールドなものを目指せと言われる、というようなことを冗談交じりに語っていたのが自分の印象に残っているが、逆に言えばジャー本人にはポップに対する意志がつねにあるということだと思う。そうした傾向が『Piedras』にも表れており、そのため大衆音楽の断片がジャーの折衷主義のもとで繋ぎ合わされているのだ。ここには60~70年代に浮上しピノチェト政権で弾圧された音楽運動であるヌエバ・カンシオンや、チリの舞踏音楽クエカからの影響もあるというが、つまり音楽も政治運動も大衆的なものであるはずだ、という想いがジャーにはあるのではないか。『1』に多く現れる歌はもちろん、『2』のアンビエントにもメロディックなところがあり、ジャーのソングに対する意識の高さも感じられる。チリのおける弾圧や植民地主義をコンセプトにした本作が、ポップの実験として成立していること自体がジャーの音楽家としての個性であり、志であるだろう。アルバムでもっとも温かい響きを持ったポップ・ソング「Song of hope」のタイトルは皮肉でもなんでもない。圧政のなかにあっても人びとは社会運動を起こしてきたし、そこに大衆音楽は連動してきたのだから。(木津毅)
Text By Tsuyoshi Kizu