未来のヒットが聴こえる
〜ジャック・アントノフ〜
テイラーも信頼する人気プロデューサー
ジャック・アントノフ。1984年3月31日ニュージャージー州ベルゲンフィールド生まれ。これまでにグラミー賞を5回受賞している当代きっての人気プロデューサー/ミュージシャンだ。テイラー・スウィフトとの仕事で一気に知名度をあげ、ロード、ラナ・デル・レイ、クレイロら女性アーティストを中心に数多くをプロデュースする手腕は今や知らぬものはいないほど。一方で、彼の音楽家としての出発点は自らバンドを率いていた90年代後半まで遡る。1998年、高校2年の時に幼馴染みたちとOutlineを結成。2002年には自らがリード・ヴォーカルを務めるSteel Trainへ。これら初期キャリアのバンドでもそれぞれ積極的に活動していたが、彼の名前がより知られるきっかけとなったのは2008年に結成したFun.でのブレイクだった。2012年にリリースされたセカンド・アルバム『Some Nights』と、ジャネール・モネイをフィーチュアしたシングル「We Are Young」が大ヒット。だが、その栄誉もつかのま、今度は2014年にソロ・プロジェクトであるブリーチャーズをスタートさせている。この7月にはブルース・スプリングスティーン、ラナ・デル・レイをそれぞれフィーチュアした曲も収録するニュー・アルバム『Take The Sadness Out Of Saturday Night』をリリースした。売れっ子プロデューサーとしての実績を重ねていく傍ら、彼は自身の創作活動の足取りも決して止めていない。しかも、その“両輪”がともに商業的成功を収めている、数少ない例と言っていいだろう。
ユダヤ人であること、高校3年の時に妹を脳腫瘍で亡くしていること、ドラッグに手を出し統合失調症を引き起こしそうになったこと……彼には過去いくつかの重要なトラウマがあり、それを自身で告白してきているし、実際にブリーチャーズの新作にはそんな自身の苦い記憶や体験を反映させた曲もある。そうして個人の心の痛みと戦う他方、プロデュース・ワークにおいてルーツ・ミュージックへの真摯なアプローチにもトライするようになった。音楽ビジネスのど真ん中でトップランナーとして走り続けるジャック・アントノフ。今回はプロデューサーとして制作に携わった/もしくは自身がメンバーとして関わるバンドの主要作品で彼の仕事を辿ってみたい。
(ディスクガイド原稿/井草七海、岩渕亜衣、上野功平、岡村詩野、尾野泰幸、加藤孔紀、かなふぁん/kiss the gambler、木津毅、高久大輝、山田稔明)
Fun.『Some Nights』
2012年 / Fueled by Ramen
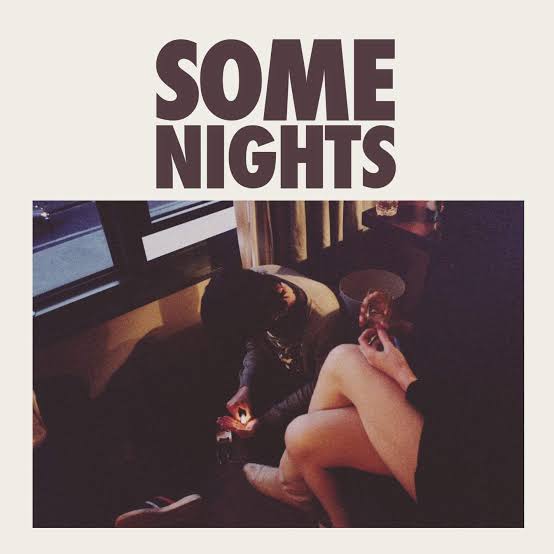
2012年、夏。周囲の人と上手く関わることができない私は「この世の終わり」といった顔をして毎日を生きていた。このままでは学校に行けなくなってしまう。そう考えた私は、一人カナダの大叔母の家を目指して、旅に出た。数日後、大草原へのドライブに連れ出してくれた大叔母は「私も大学時代のことは思い出したくないね」と言って、カーステレオから、発表されたばかりのこのFun.のセカンド・アルバム『Some Nights』を爆音で流し始めた。その瞬間、私の人生は音を立てて光の方へ進み出した。
ジャネール・モネイをフィーチュアしたヒット曲(全米1位)「We Are Young」を含む本作は、ジェフ・バスカーをプロデューサーに迎えて9ヶ月という短期間で制作。ヴォーカルのネイト・ルイスが考案した歌詞とメロディに対して、アンドリュー・ドストとジャック・アントノフがコードや楽器のアレンジを加えていった。メロウなピアノと雄大なヴォーカルが印象的な「intro」から一転、表題曲「Some Nights」は、メンバー全員の重厚なコーラスと、大地を駆け抜けるような躍動感あるドラムが特徴的だ。この楽曲でアントノフは、ギターの他、ドラムのアレンジも担当しており、サイモン&ガーファンクルの「Cecillia」からも引用している。「厳しい状況下でも最後には光が見える」という詞の内容は、英語が聞き取れなかった私にも十分に伝わってきた。
18歳の時に妹を癌で失い、悲しみから一時は麻薬に溺れたアントノフだが、Fun.での活動をきっかけに立ち直り、今では周知の通り、テイラー・スウィフトを始めとする才能豊かなアーティストたちと音楽制作に励んでいる。そんな彼の数奇な人生を描いたような『Some Nights』に救われた人は、きっと私だけではなく数え知れないだろう。(かなふぁん/kiss the gambler)
Lorde『Melodrama』
2017年 / Universal

ジャック・アントノフにとっては初めて全体をプロデュースしたアルバムで、ロードにとっては世界的ヒットとなったデビュー作『Pure Heroine』(2013年)を経ての4年ぶりの作品。けれど、そんな2人は新たな挑戦への緊張感というより、直向きに創作に向き合うことでこの瑞々しくも作家性をはっきりと記す作品を完成させることができたように思う。メロドラマという散々演じられてきた主題であるにも関わらず、彼女によって書かれた詩の数々は、破局による自身の悲哀の感情を様々な視点から何度も何度も振り返り、自らの新たな面を発見することで作品を鮮やかに彩った。一方、アントノフは、本作でプロデューサーとしての自身の存在を発見したという。前作で印象的だったダンサブルで重厚なビートにのって歌う彼女の姿を残しながら、本作では2曲のピアノ・バラードを筆頭にピアノの音が色濃く印象を残す。歌とピアノ中心のSSW然としたアレンジに彼女の自問自答を写すように、けれど一歩間違えればシリアスになりすぎるバラードを、ダンサブルな曲と隣り合わせにしても自然に、共作としても関わりながらポップに響かせた。そうやって、2013年と2017年の彼女を地続きにさせながら本作の中でバランスよく表現することに尽力したことが彼の功績だろう。「『Melodrama』に関わらなければ、今の僕はなかった」と今年のインタビューで語るように、彼が関わったテイラー・スウィフトやクレイロの近作も、それぞれの心情や作風の変化を感じさせながら、けれどこれまでの彼女たちの姿も確かに残す作品だった。(加藤孔紀)
St. Vincent『Masseduction』
2017年 / Loma Vista

2017年、真夏の真夜中にセイント・ヴィンセントの来日公演を観た。ステージで独りシアトリカルにギターをかき鳴らし歌うアニー・クラーク、先鋭的でアヴァンな才女という先入観が確信に変わると同時に、MCや立ち居振る舞いがとても可憐だと感じた。熱烈なアンコールに応えるかたちで演奏されたのがリリース前の新曲「Los Angels」と「New York」。特にギターを弾かずに歌う「New York」は“あなたがいないNYなんてNYじゃない”と始まる、かつてなく感傷的かつ感情的なラブソングで、初めて聴いたそのメロディが頭から離れないまま朝を迎えたことを憶えている。その2ヶ月後にリリースされた本作はジャック・アントノフとの共同プロデュース(収録曲中5曲が共作)。グラマラスなインダストリアルビートと彼女のギタープレイは原色のアートワーク同様にこのアルバム全編を通して特徴的に響くのだけれど、ジャック・アントノフ主導で書かれたと推測される「Happy Birthday, Johnny」、そして前述の「New York」におけるアニー・クラークの歌が垣間見せる人間味と人肌の温度がとても印象的なコントラストとなっている。彼女はアントノフのことを「究極のチアリーダーで冷笑的なところがひとつもない」と評したが、エキセントリックな仮面の下の彼女の素顔を引き出したのがアントノフ持ち前のポップネスだとするならば、二人の化学反応はうまく作用したと言えるだろう。(山田稔明)
Lana Del Rey『Norman Fucking Rockwell!』
2019年 / Polydor
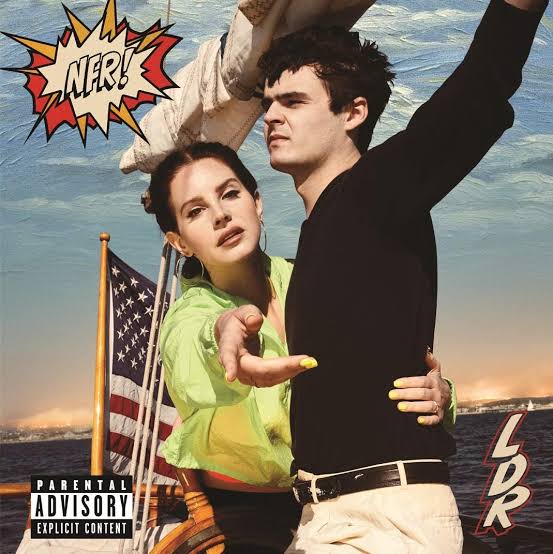
かねてから「虐待的なパートナーとの関係を描写している」と批判されることも少なくなかったラナ・デル・レイ。相手から離れたくても離れられない、自虐的で自嘲めいた愛。それをどう評価するかは一旦措くにせよ、ともかく、その対象となる相手を転換してみせたのが今作だ。相手の名前は……アメリカ。ノーマン・ロックウェルが描いたような(主に白人の)中産階級の牧歌的な生活の裏に差別や暴力が覆い隠されている、グロテスクな白人中心社会としてのアメリカ。しかしそれは自分から決して引き剥がすことができない、故郷(ふるさと)としてのアメリカでもある。「California」で、アメリカから離れていく人々を見送りながら「帰ってきたら寄ってよ」と声をかける彼女はたぶん、いくら憎んでも愛しても、“アメリカ”から離れられない自分自身を知っているのだ。 今作、そして似たテーマ性を持つ直近作でラナがジャック・アントノフと組んだのは、こうした母国へのアンビバレンツな感情を、郷愁を誘うようなアメリカーナ風のソングライティングでもって表現するためだろう。ピアノとアコースティック・ギターの音色に、ヴィンテージ・ライクなエレキ・ギターがささやかに色を足す程度の楽曲であっても、アントノフらしい楽器の生の鳴りを引き立たせたサウンド・メイクによって、複雑に揺れる心がドラマティックに描き出されているのも流石。そしてそこにはやはり、白人としてアメリカに暮らす自身へのシニカルな目線と嘆息が見え隠れするのである。(井草七海)
Kevin Abstract『Arizona Baby』
2019年 / Question Everything

ジャック・アントノフががっつり関わったおそらく唯一のラップ・アルバムであろう、ブロックハンプトンのリーダーであるケヴィン・アブストラクトによるソロ名義3作目。ラナ・デル・レイ「Venice Bitch」に感銘を受けたケヴィンがアントノフに声をかけたことを端緒としており、作品の大半がそれまでにグループのいくつかの楽曲でプロデューサーを務めていたRomil Hemnaniとの共同プロデュースという形をとっている。ゆえにアルバムの冒頭「Big Wheels」やラスト「Boyer」などに顕著なブロックハンプトンらしい混沌とした実験的アプローチと、アントノフによる生楽器主体のサウンド・プロダクションがひとつの作品の中でせめぎ合っていることは必然といっていいだろう。ところどころピッチシフトされたヴォーカルや暖かなブラスが牽引するアップビート、シリアスに過去を振り返るリリックなどがいびつな調和をみせる「Joyride」が本作のハイライトだ。
数々の“女性”アーティストを手がけてきたアントノフと、ラップという赤裸々な表現方法に投影されるゲイであるケヴィンの持つクィアネスがどこか呼応し合っているかのような、繊細さと大胆さを兼ね備えた1枚。「ヘッドライトは夜明けを指している」(「Baby Boy」)と切実に響く歌声も聴き逃せない。なお、8曲目「Crumble」ではアントノフもヴォーカルを担当している。(高久大輝)
Taylor Swift『Lover』
2019年 / Universal

いまや女性アーティストのオーガニックな内面を引き出すことにかけて随一のプロデューサーであるジャック・アントノフだが、彼の実績の始まりであり大きな転機となったのは何と言ってもテイラー・スウィフトとの共作だろう。2014年のアルバム『Red』でジャックがテイラーの単独作品に初めて参加した以降、常にジャックは彼女の表現活動の一番の理解者として傍にいた。テイラーは作品を人生のチャプターとして位置付け、常に自身の感情をむき出しで投影させているが、彼女の世界的ポップ・アイコンとしての自我の確立と一人の女性として奔放に幸せを追求することの両立を音楽面から支えたのは何よりジャックの存在であるだろう。この2019年のアルバム『Lover』は、フェミニズムやLGBTQについてテイラーが自身の社会的影響力を自覚し使命感を持って発信した重要なスタンス表明の作品であり、ジャックがプロデュースした「Cruel Summer」ではセイント・ヴィンセントを迎え情熱的なアンセムでアルバムのヒットをしっかりと牽引した。一方でテイラーの星座の射手座をタイトルに冠した「The Archer」ではジャックの静かに寄り添うミニマムなシンセの音色が“私のヒーローはみんな独りで死んでいく”“ずっと自分の姿が嫌いだった”というダークでパーソナルなテイラーの逡巡の吐露を誘い、彼女を癒す。どの尺度においても魅力を引き出す柔軟性こそ、テイラーとの相性の良さでありジャックの手腕なのだ。(岩渕亜衣)
The Chicks『Gaslighter』
2020年 / Columbia
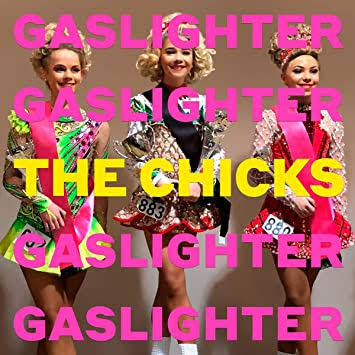
2000年代のポップで起きたことを知る者にとってとりわけ、テイラー・スウィフトの『Lover』にディクシー・チックス改めザ・チックスが参加したのは感動的な出来事だったに違いない。保守的なリスナーが多いカントリー・シーンで共和党を批判することはご法度だとスウィフトは周りに言われたというが、それは前例があったからだ。イラク戦争とブッシュ政権を批判したディクシー・チックスはかつて、シーンから「干された」。だからこそ、それでも政治的な発言を勇敢におこなったスウィフトは、シーンの尊敬する大先輩とともに「声」を出すことが必要だった。わたしたちは恐れない(恐れなかった)、と。
その異なる世代のアーティストを音の面で繋いだのがジャック・アントノフだ。じつに14年ぶりとなる本作において、彼が担ったのは何よりも彼女たちの復帰作を「いまのポップの音」にする役割だろう。といっても奇を衒ったことはあまりしていない。ディクシー・チックスが元来持っていたダイナミックなメロディ展開を生かす形で様々な楽器を配し、立体的なプロダクションを施しつつも、最終的には生音主体のカントリー・ポップであることを最大限尊重している。ブリーチャーズの新作を聴くにつけ、彼がいま広範のアメリカ大衆音楽を包摂しようとしていることが窺えるが、本作での経験もかなり影響していると思われる。アントノフは現在、カントリーの再発掘とモダナイズという昨今のポップ・シーンにおける重要課題に参加するひとりでもあるのだ。(木津毅)
Carly Rae Jepsen『Dedicated Side B』
2020年 / Schoolboy / Interscope

ジャックとカーリーの付き合いは2012年の「Sweetie」(『Kiss』収録)まで遡るが、エル・ファニング主演の映画『ティーン・スピリット』のためにオリジナル曲「Wildflowers」を2人で書き下ろしたことは、よっぽど創作意欲が“燃える”出来事だったのだろう。劇中でもフィーチャーされた(かつ、カーリーが敬愛する)ロビンの名曲「Dancing On My Own」を手がけたスウェーデンのパトリック・バーガーを迎えた瞬間から『Dedicated』は優勝確定のアルバムだったわけで、なるほど、ABBA発ジョルジオ・モロダー経由ロビン着のように眩いサウンドは、ブリーチャーズの力強いシンセ・ポップとよく馴染む。表サイド(ジャケは背中)の『Dedicated』ではダフト・パンク風のロボ声と70年代フレーバーをまぶした「Want You in My Room」の参加だけに留まったジャックだが、こちらのサイドB(ジャケは正面)では決意表明みたいなオープナー「This Love Isn’t Crazy」を共作し、ブリーチャーズ名義で「Comeback」にも友情出演。5曲目でペンを執ったデヴ・ハインズを差し置いて、“何を感じてるのかわからない。でも、信じてる”と息の合ったデュエットを披露している。そうそう、ポンタス・ウィンバーグ(マイク・スノウ)、ヌーニー・バオ(アヴィーチー他)、そしてサイドBのみに招かれたマーカス・クルネガルド(チャーリーXCX他)といった、裏方のスウェディッシュ人脈もいい仕事をしてます。(上野功平)
Bleachers『Take the Sadness Out of Saturday Night』
2021年 / RCA

ジャック・アントノフ自身が10代に経験した妹の病死、9・11の衝撃とイラク戦争での親類の死といった出来事を背景とし、その経験をデペッシュ・モード、ヤズーなどの80年代のシンセ・ポップ、ニュー・ウェイヴや、ブルース・スプリングスティーンから影響を受けたアンセミックなプロダクションによるハートランド・ロックに乗せて物語ったデビュー作『Strange Desire』(2014年)の時点から、ジャック・アントノフのソロ名義たるブリーチャーズは自身の心に忘れがたく刻まれた痛みや原風景を表現しようとしてきた。アメフトなどで利用される移動式観覧席にちなむブリーチャーズというプロジェクト名自体が、アントノフにとって自身が生活した“郊外”を想起させる言葉だというように。その意味で自身と同郷であるブルース・スプリングスティーンをフィーチュアし、印象的なリフのシンセサイザーを用いシックにまとめあげた「Chinatown」の完成がアントノフにとって特別な出来事であっただろうことは想像に難くない。本作におけるボスの影響はホーンが颯爽と響き渡る「How Dare You Want More」や、大袈裟なくらいのコーラスとケバついたシンセサイザーのポップ・ロック「Stop Makin This Hurt」からも見て取ることができる。郊外生活に潜む自身の心痛ましい記憶を前を向くために語り続けるというアントノフがブリーチャーズという名のもとで試みた挑戦は、そのルーツとなるボスとの邂逅を経てなお続くだろう。(尾野泰幸)
Clairo『Sling』
2021年 / Repblic / Fader

ロスタムがプロデュースしたファーストと、ジャック・アントノフが手がけたこのセカンド。どちらがクレイロの良さを引き出せているのか評価や好みが分かれるかもしれないし、結論を言うとどちらもアルバムとしてすごくいい。ただ、本作の奥ゆかしくも豊かな情緒を伝える多様なアレンジは、YouTubeでの楽曲配信で話題となり、近年はムラ・マサ、チャーリーXCXの作品で客演したり、クロードとユニットを組んだり……と、Z世代を代表するベッドルーム・ポップ・シンガー・ソングライターとしての見え方とはまた異なる表情を伝えている。それは、60年代のソフト・ロックやA&Mサウンドのような、聴きやすく耳にも優しい、でもハーモニーやアレンジは見事なまでに構築されたポップスの歌い手としての顔。実際に、バンド・サウンドも覗かせるが、基本はピアノやアコースティック・ギターなどの生楽器がメインの、繊細で不安定さも覗かせる本人のシンガーとしての表現力に賭けたかのような仕上がりだ。けれど、コロナ以降の世界を反映させたような他者との違和感・齟齬を伝える歌詞ながら、決して極端にシリアスには聞こえないのが本作の良さ。気軽に誰でも聴けるサンシャイン〜AMポップ感、ストリングスがさりげなく敷き詰められた優美なバロック・ポップ調などのアレンジが、言葉の力で聴き手を収斂させるような現代の窮屈な状況を開放させている。ポップスのポップスたるいい意味での気安さが現代に欠けていることをアントノフはわかっているのかもしれない。(岡村詩野)
関連記事
【FEATURE】
セイント・ヴィンセント
屈強かつしなやかな史上最強パフォーマーへの軌跡〜オリジナル・アルバム・ガイド
http://turntokyo.com/features/st-vincent-discguide/
Text By Toshiaki YamadaAi IwabuchiKanafun(kiss the gambler)Tsuyoshi KizuShino OkamuraNami IgusaDaiki TakakuKoki KatoYasuyuki OnoKohei Ueno
