「頭から電流が走って、その場で何かが起こってしまうような感覚を重視している」
新作『Eraser, Pencil』で見せたPot-pourriの超跳躍
Pot-pourri=ポプリの語源は、もともと直訳で“腐った鍋”から発展し“ごった煮”を意味するようになったフランス語。一般的には、乾燥させた花びらやハーブにオイルやスパイスをまぶして香りを楽しむもの、というイメージが強いが、実は音楽用語でもあり、よく知られた旋律やその断片をつなぎ合せた接続曲のことを指す。その事実を知ってしまえば、このPot-pourriがごった煮……とまでは言わないが、音作りの面でも感覚的にもハイブリッドで領域を横断、低音を強調させつつ丹念に作り込む場面もあれば、思い切ってヴォルテージをあげていく場面もあるなど多様なアスペクトを持ったバンドであることの意味がわかるのではないかと思う。少なくとも筆者は、滝沢朋恵、浮乃、PSP Socialも参加したニュー・アルバム『Eraser, Pencil』を聴いて、この過剰な面白さを持つポップをどのように言葉で表現すればいいだろうか? とジレンマに塗れて地団駄を踏んでは胸が熱くなった。なぜなら、ここにはトータスやナイン・インチ・ネイルズ、あるいはART-SCHOOLやTHE NOVEMBERSといった日本のエモーショナルなアクトとコミットできる瞬間もあれば、プリファブ・スプラウトやトーク・トークなどとのシンクロニシティもあるからだ。
尤も、Pot-pourriは単純に音数が多いだけの情報量満載のポップスを聴かせるバンドではない。作詞作曲とアレンジを担当するヴォーカル/アコースティック・ギターのSawawoのソロ・プロジェクトのような形でスタートするも、プログラミング、シンセサイザー、ギター・エフェクト、ドラム・マシン、そしてミックスまでを担当し音を大局で捉えることができるRyo Nagaiが加わり、ベースのShibasaki、ドラムのTaroとともにバンド編成であることが強調されるようになってからは、雑種たる異種格闘的な刺激の嵐の上で音たる音が精緻に合成されるようになった。その異形だがメランコリックでもあるポップ・アマルガムとしてのPot-pourriの現在地点を探るべく、SawawoとRyo Nagaiに話を聞いた。(インタヴュー・文/岡村詩野)
2024年8月24日に東京・落合《soup》にて行われたワンマン・ライヴ「変わらないもの、変わっていくもの」から「Dressed in Black」 撮影・編集: ホシノダイスケ Mix: Ryo Nagai
Interview with Sawawo, Ryo Nagai
──最初はSawawoさんを中心とするユニットという見え方でしたが、今となってはバンドという感覚が結構強くあるようですね。
Sawawo(以下、S):はい。最初動き出したときは確かに僕一人で宅録でやっていて。バンドというよりも、プロジェクトとして始まって、メンバーを集めていろいろ試行錯誤してっていう感じでした。
──Ryo Nagaiさんが加入されたのは正確にはいつ頃ですか。
Ryo Nagai(以下、N):2017年の……いつだったかな。
S:お声がけしたのが春ぐらいで、正式に加入してもらったのが7月でした。それより前から付き合いはあったんです。知り合った当時僕ら2人とも高校生で、音楽ファンであり、なおかつバンドもやってる、みたいなところで繋がって。その中で、音楽に対する造詣というか視点が面白いなと思っていて。Pot-pourriを始めたはいいけれど、バンドとしてメンバー・チェンジも激しくてタイミングが難しく、彼(Nagai)を誘える機会を探しあぐねていたんです。
──2017年の夏に正式加入という形であれば、ファースト・アルバム(『Classic』)の時点では既にメンバーとしてしっかり制作に関わっていたわけですね。
S:はい、Nagaiくんが入って2年は経過している形でリリースを迎えているので。いわゆる音源制作、それもしかもちゃんとしたフル・アルバムのリリース制作のタイミングだったんです。それもあってバンドっぽい感覚が強まってきました。それまでは音源は僕一人で作ってたので、他のメンバーとも一緒に作業するような発想があんまりなかったんです。でも、一方でライヴではメンバーに任せすぎちゃっていて……なのでその頃はぐちゃぐちゃな状態になっていたりしました。でも、Nagaiくんが入ってくれて、そのあたりのバランス感覚もどんどんどんどん良くなっていって、メンバーに任せられる裁量も増えました。
N:Sawawoさんが言ってたバランスっていうのもあるし、確かにバンド感も変わってきたと思います。ファーストのときには、今自分のすることみたいなのをかなりかっちり決めて、ただ関わるみたいな感じだったんですけど、セカンド以降は自分でこれはいいとかこれはよくないとかを言えるようになってきました。
──Nagaiさんは非常にマルチなプレイヤーでありクリエイターでプログラミングを含めた多様な楽器演奏を見渡せるポジションにいると思うのですが、最初加入するにあたってはメインはどのような役割だったのでしょうか。
N:いや、最初はもう僕は楽器を弾きたくなかったんですよ(笑)。全然自分は演奏がうまくなくて、その音そのものに興味があるタイプなんです。バンドの雰囲気を見て、アコースティック・ギター、ベース、ドラム、ヴォーカルとパートが4つある中で、シンセはそこには必要ないかな……と思ったりするような、そういう感覚ですかね。で、それなら録音し終わったものにエフェクトをかけようかな、みたいな発想です。そこから、アコースティック・ギターとスネアドラムにエフェクトをかける作業をライヴでやっていました。つまりエフェクト担当です。
──既にある音に対して後からそれを変えていくポジションにいたNagaiさんが、どのような形で実際に演奏そのものに変わっていくようになったのですか。
N:セカンド・アルバム(『Diary』)のミックスをSawawoさんにお願いされた時に、結構いろいろ試したんです。シンセやドラム・マシンを入れてみるようなアイデアとか。そのとき、いろんな音を扱える感じになってきたって自覚があったのかな……バンドの求めているサウンド……Pot-pourriの歌がもっと良くなるかとかがわかってきたというか。でも、そのあたりのタイミングでバンド全体でパラダイムシフトが起きた感じはしますね。歌ものというか歌を生かすため、あるいは歌っていうのがまず大前提にある楽曲を関わって一緒に作ってるんだっていうような感覚が強まると、その関わり方の間口が広がっていくんですよ。そもそも他に自分のやりたいことをやってる人がいないっていうのに気づいたのもあります。
S:そうですね。そう考えたら、今度のアルバムの前に、セカンドで完全に体制が変わったことがまず大きかったと思います。実際にセカンド制作以降、このバンド史上で一番重点的にちゃんと同じメンバーでライヴをやるようになって。何回も何回もセカンドの曲を演奏していくっていう中で、歌っている自分の意識も変わってくる、みたいな感覚はあったかと思います。
N:それはありましたね。ライヴで同じ曲を何回も繰り返してやっていくうちに、なんというか……グルーヴみたいなのがちゃんと出てくるっていうのを実感して。バンドっぽさ、バンド感もその頃繰り返しライヴをしていたことから生まれたのかもしれないです。レコーディングや音作りの現場ではやっぱちょっと得られないものじゃないですか。それを繰り返しているうちに、ライヴ音源を出したいとか、録音したものを生の感じで残したいって気持ちも湧いてきたし、どうやったらそのグルーヴを起こせるかとか、そういうのはすごい考えたりしたかもしれないです。
Sawawo(手前)
──(『Eraser, Pencil』収録の)「Dressed in Black」という曲は、まさにそうした意識改革と作業の具体化によってゴリっとした質感が表出されたのでしょうか。
S:そうですね。その前の「Y」ってシングル曲でも、最初に一発目のドラムの録音を使おうっていう感じになっていました。一番最初のフレッシュな感じを残したかったし、曲のヴァイブスはちょっと伝わるんじゃないかって思って。そういうのはライヴをやってくうちに気づいたことかもしれないです。「Dressed in Black」は(新作に向けての)かなり初期の段階で全体像が見えた曲でした。
──バンドとしての自覚が芽生える中で、具体的にイメージしていたバンドはいましたか。
N:僕はナイン・インチ・ネイルズのようにパフォーマンスを作り込んでいるバンドですね。あとは、マーク・スチュワート(ザ・ポップ・グループ)のやってきたこととか……ブリストル周辺のポスト・パンク寄りのもの……特にマークのソロ・ワークみたいなのを想定しています。今一番やりたいことというか。
S:僕はバンド感、ライヴ感っていうのにうまくハマるイメージのバンドは浮かばないんですけど、スポンティニアスというかその場で生まれてくるような感じというか、その場のハコの空気感が反映されるような演奏に惹かれますね。いい意味でブレが大きい演奏をするようなイメージというか。毎回毎回違うものを提示できるような。一番特徴的に現れるのがNagaiくんのエフェクターのパートだと思うんですけど、それ以外の部分でも演奏に即興性の現れるようなことができればと思っています。ただ、だからってフリージャズをやるとか、そういう感じじゃなくて、頭から電流が走って、その場で何かが起こってしまうような感覚を重視しています。
N:身体での表現もライヴで意識するようになってきましたね。僕が入ってすぐの頃のPot-pourriって、演劇的なイメージというか、劇を見てるような雰囲気があって。正直、それがちょっととっつきにくかったところもあったと思うんです。それがどんどん変わっていって……でも、身体表現自体はメンバー全員の意識の中に今もしっかりあるのかもしれないと思いますね。
──確かにPot-pourriの作品は単にバンド感のあるものというより、どんどんフィジカルになっていっていると思います。音も弾性の強いものになっていますし、Sawawoさんのヴォーカルもエナジェティックになっています。その一方で、楽曲のポップさはどの曲にもある。というより、むしろそのポップさはバンド感と比例しているように感じるんです。
N:ポップ……うん、本当にそれはあるかな。「Dressed in Black」を作ってる最中は、まるでステロイドで増強したザ・キュアーみたいだなって思ったりしました(笑)。筋肉ムキムキにしちゃったザ・キュアーみたいな感じかもしれないって思ったり。作ってバランスを見ていくうちに、一番いいラインみたいなのは今はそこだなって感じたんですよね。Sawawoさんはどう感じていました?
S:いや、そう思います。実際、今回のアルバムを作り始める最初の段階で、割とポップなものにしようみたいな気持ちは結構ありました。2枚目まで作ってみて、いい評判に繋がったと思っていたんですけど、自分の中のポップさというか、ポップなものもすごい好きな自分がいて、それをもっとうまく伝えられるんじゃないかな、そういう面をちょっと出したいなって思っていたところは確かにありました。
──そのポップさを引き出すにあたって、具体的にやってみたことはありますか。
S:はい。例えば、曲もまずすごく簡単な状態で……ギターでジャカジャカ弾いたようなものをメンバーに渡したんです。全然わけわかんないと思うんですけど、できました! どうぞ! みたいな感じで。最初からあんまり難しく考え込まずに、口をついて出てくるようなポップな感じがあるといいなって思って。「Dressed in Black」も、最初前半まで作って、中間以降は様子見ながら、でもなんかちょっと違うなってことになって、スタジオでいろいろジャムってみたら出てきた展開があって……って感じでした。Nagaiくんがリズムトラックを全部差し替えた曲もありました。
N:「Setting Sun」ですね。
S:あと「X」も。
N:もうメロディー以外の他のものは全部変えたと思います。僕も自分で曲を作ったりしてたから、自分だったらこうするな、とか思って、それをSawawoさんに伝えたりして……お互いにコンセンサスが取れるようになってきました。あと、もともとポップだけど、どこかいびつなところがあるっていうのがSawawoさんのソングライティングだと思っていて。そこを生かして、それに合う音を選ぶと、自然とそういうポップなものになっていくように思います。やろうと思えば、一般的なJ-POPのようにツルンとしたストリングスを入れて感動的にして……みたいなこともできると思うんですけど、そうじゃない、このバンドの最適解を見つける……というような作業だったかなと。
S:自分としては自分の曲の特徴みたいなものはそこまで意識してなかったかもしれないです。昔は、それまであまりやっていなかったこともやってみよう、増やしていこうってことも考えていたんですけど、今回は結構自然に出ちゃったって感じがしますね。これまでやってきたことが既に血肉になっていたということなのかもしれないです。
Ryo Nagai(奥)
──私は今作を聴いて、まさに“過剰ポップ”の極みのような面白さがあると思ったんです。もしかすると音数自体はそれほど多くないのかもしれないですけれど、音の抜き差しが結構ハードに聞こえさせるような作品になっているなと。
N:なるほど。今回はいい感じにベーシック・トラックを作ってから、メンバーにも投げて、それを壊したり、めちゃくちゃに歪ませちゃったり、削ったりとか、1回全部抜いてみるとか。増やすというより欠落させてみる、とにかく一度ハズしてみるようなことはしたんです。そこで何か必要になってくるものをどんどん見極めて。本当に必要な音を欲しい時は入れるって感じで……そのおっしゃる過剰さって(ナイン・インチ・ネイルズの)『The Downward Spiral』みたいな過剰さだったとしたら、すごくよくわかるというか。確かに変なサンプル入っているし、「Y」とか「Dressed in Black」では録ったギターの音に生演奏的にエフェクトを一回全部かけてみて、それをまた削るっていうような細かい作業をやったんです。しかも録音する場所を重要視して。パソコンとMIDIコントローラーを持って上野公園に行って録ってみたり、川沿いでやってみるとか……。そうやって一発録りしたものを載せて消していくみたいなこともやったんです。それで何か独特のムード、その場の空気感みたいなものが生まれてきて……うん、そういう作業が過剰に聞こえるようになっているのかなって気もします。
──実際は過剰じゃないけど、過剰に聞こえてしまう。生の録音物の良さと、それをあとから作業していくことの面白さのコントラストがカギになっているのかもしれないですね。
N:ああ、そうですね。その面白さに気づいたのって……そういえば前作(『Diary』)のマスタリングのときにROVOの益子(樹)さんがブルースが好きだって話をされてて。マディ・ウォーターズのアルバムとか聴かせてもらったりとかしたんです。生の演奏をそのまま録って、それをどう生かしていくのか? みたいなのにちょっと意識が芽生えたところはあるかもしれないです。あと、エンジニア的な作業でいくと、もともと(トータスの)ジョン・マッケンタイアの録音が好きっていうのもありますけど、彼の音の、どこかに空気感が残ってる感じがする仕上がりってなんだろう? って思ったら、結局録音スタジオだったり、機材とかだったり、演奏者の雰囲気だったりっていうのが大きいですよね。あとは、『攻殻機動隊』の「ゴースト」みたいな、音を規定する「魂」のようなものがあるかもしれないと思ったりして……。それで言うと、実は「Dressed in Black」はアルバム・ミックスでコーラスを差し替えたんです。シングルのときはコーラスを重ねていってたんですけど、やっぱり(差し替え時のスタジオでの)全員で一回曲を通していっせいに歌おうってことになって。そうしたら雰囲気が自分たちの中で良くなっていって。録音物として残るかもしれない、それが伝わるのかもしれないって思ったところもあるかもしれないです。
──ミックスによって全然違う作品になりますよね。
N:そうなんですよね。ミックスでこんなに違うんだ! って気づかせてくれたのは、高校時代ずっと大好きで聴いていたART-SCHOOLの影響もあるかもしれないです。エンジニアごとにもう全然雰囲気が変わるってことも、ART-SCHOOLの作品で実感できたところもあります。「あと10秒で」のアルバム・ミックスとシングル・ミックスがこんなに違うんだ! って当時は驚きました。
S:もしかすると、今回のアルバムで僕がやったこととNagaiくんがやったことって結構対照的なのかもしれないです。僕の方で何か録音したり、録ってもらおうとした部分は、前回よりも割と環境を統一してやったところがあって。ヴォーカル録りも、いい歌、いいパフォーマンスを残したかったんで、リラックスできる自室、もしくは、録音を担当してくれた友人の田村悠二くん(Lanes)の家で録らせてもらったりしたんですよ。それが効果的に作品に反映されたと思います。今、思ったんですけど、情報が多いとか過剰な音楽って、楽譜自体が複雑な場合、それは情報が多いってことになるんですけど、その楽譜をそのまま演奏しません、あるいは、うまく演奏できませんっていう情報の増やし方もあるのかなって気がしてて。例えばペイヴメントは僕にはすごく情報が多い音楽に聞こえるんですよ。Pot-pourriも、もしかするとそういう側面で過剰って聞こえるのかなって気がしています。
<了>

Text By Shino Okamura

Pot-pourri 3rd Album 『Eraser, Pencil』 Release Party
◾️2025年3月30日(日) 東京・新大久保 EARTHDOM
開場17:30 開演18:00
チケットはこちらから :
https://tiget.net/events/378233
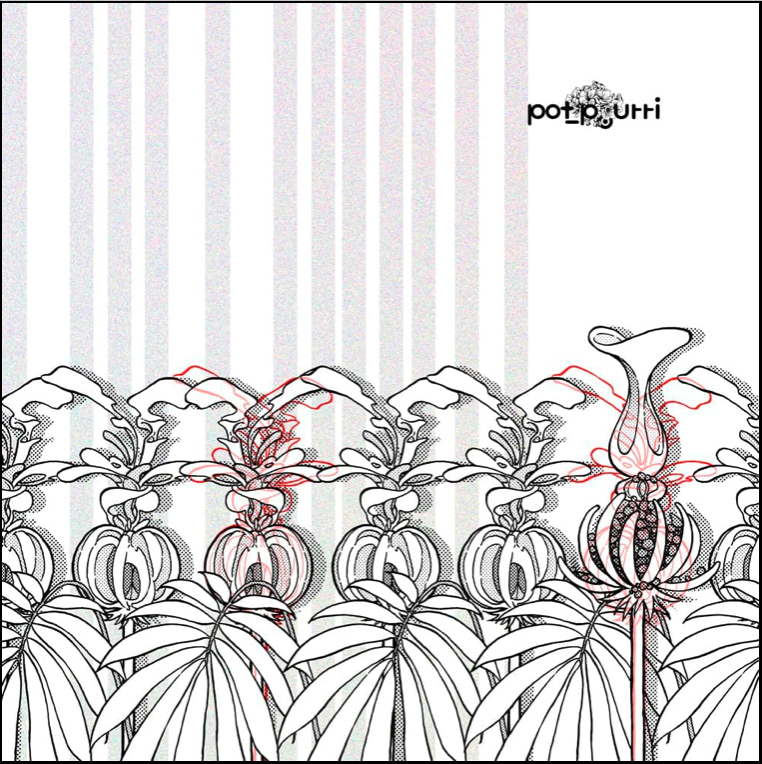
Pot-pourri
『Eraser, Pencil』
RELEASE DATE : 2025.02.05
LABEL : UNKNOWNMIX / HEADZ
CDのご購入は以下から
HEADZ公式オンラインショップ
関連記事
【REVIEW】
Pot-pourri
『Diary』
https://turntokyo.com/reviews/pot-pourri-diary/
