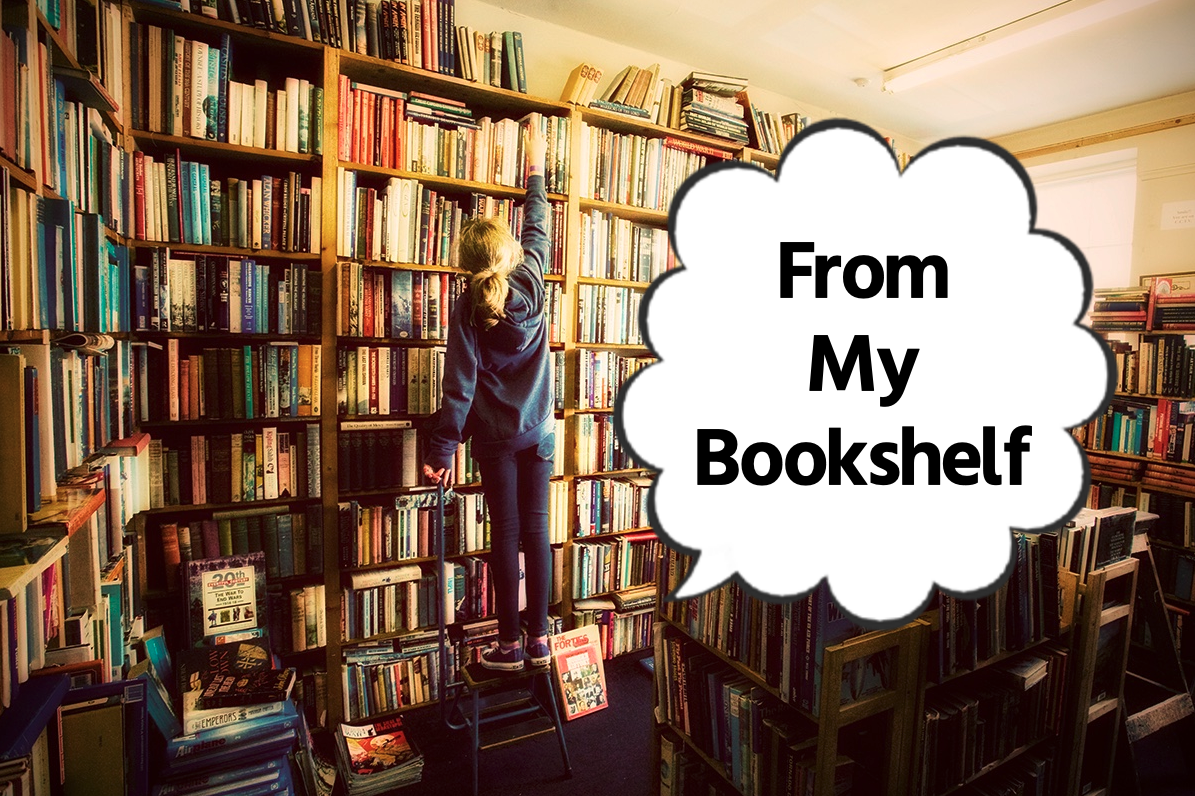【From My Bookshelf】
Vol. 44
『ピアノへの旅』
坂本龍一(著)
知るを訪ねる本
ピアノには全く縁のない人生であり続けている。幼稚園に入る前に習い始めた楽器はヴァイオリンで、高校になってからはベースやギターを弾き、吹奏楽部ではクラリネットを選んだ。バンジョーやマンドリンを試したこともある。でも、なぜだろう、ピアノはもとより鍵盤類には手を出さなかった。小さい頃、周囲はピアノやエレクトーン教室に通っているコばかりだったからウンザリしたというのもあったし、高校の選択授業で音楽をとったら強制的にピアノをやらされる羽目になり、「他の楽器ではなぜダメなのか」と聞いたら「ピアノでやることが決まっているからピアノもしくはそれに相当する鍵盤楽器を買ってください」などと言われて腹が立った、というのもあるような気がするが、ともあれ、ピアノとは一定の距離をとって今に至っている。むろん、ピアノが嫌いというわけではない。ただ、本書で坂本龍一自らが話している「ピアノの音はどうしても粒々になってしまう──自然にすーっと伸びていくものじゃなくて、バラバラの粒々が並んでいくので、うまく並べようとか、きれいに並べようとか、座標の上で操作したくなる」(91ページ)楽器としての特性がゆえに、10代の頃は魅力を感じなかっただけかもしれないのだが。
坂本龍一は生涯を通じてピアノのジェネラルな印象を変えた(もしくは変えようとした)ミュージシャンの一人である。少なくともピアノをメインとする演奏、ピアノで鳴らされた楽曲においては、演奏そのものより、鳴らされた音に対する意識的な操作性、あるいは、偶発的な変幻性によってどのように聞こえるのか、響くのか、印象をもたらすのか、を常に視野に入れていた音楽家であり作曲家だった。あらゆるピアニスト、あらゆるピアノ主体の作曲家は、そこに挑み続けていると言った方がいいかもしれないが、それでも、ひたすら練習を重ねる体育会系的なレッスンを否定するがごとく、「まず、自分をピアニストだと思ったことは一度もないんですよ。ピアノの練習が大っ嫌い(中略)いつもいかに練習しないで弾くかっていうことばっかり考えている子どもでした」(19ページ)「ピアニストになろうなんて思ったこともない」(20ページ)と言い切る坂本が、それでも死ぬ直前までピアノの前に座り、鍵盤に手を置き、鳴らした音を収録して作品とする作業をしていたということに、人としてのチャームと業を感じないではいられない。練習は大嫌いでも、ピアニストという職業には興味がなくても、彼はどうしようもなくピアノが好きだった。「音がどうしても粒々になってしまって、きれいに並べようとしたくなる」楽器としての特性がゆえに、きっと坂本はピアノがたまらなく好きだったのだろう。私は、いかにして粒々の連続であるはずのピアノの音を持続するように解釈するか、永続させるように操作するか、に苦心とカタルシスを感じて(?)作り上げた坂本の(とりわけ晩年の)スタジオ・レコーディング作品が好きだが、それは聴くたびにピアノの記憶を塗り替えられていく実感があるからなのかもしれないと思っている。
本書は2021年7月に刊行された『コモンズ: スコラvol.18 ピアノへの旅』の本文構成を変え、装丁も新たにしたものだが、坂本が国立音楽大学楽器学資料館を訪ねた際の写真、最初期の鍵盤楽器の話のなどもそのまま掲載されている。基本的には旧版と大きな違いはない。鍵盤楽器の歴史や音の鳴る仕組みも理解できる、初心者にも大変優しい本だし、何より伊東信宏、上尾信也各氏との対話がメインなので、テーマは専門的ながらも坂本の話し言葉が好きな私のようなファンには、坂本のいつになく丁寧でたおやかな話し振りが味わえる本でもある。とりわけ、伊東と上尾に教えを受けるような「第2部 ピアノの起源を探る」は、ピアノ(とその話)の前では素直になる坂本の“知るを学ぶ姿”が表出されていて、坂本関連の書籍の中でも1、2位を争うほどになかなか清々しい。
中では、2部の対談の終盤で、エアコンや蛍光灯の音……昔はなかった生活ノイズのせいで、歴史の長いクラヴィコードの音が聞こえにくくなっている、という話をしている箇所が興味深い。坂本は、「座標軸の中の点になっていくんですよ、19世紀から20世紀にかけてどんどん。そして、大量の点としての音をほとんど統計的に操作するクセナキスや、1つひとつの音を雨粒のようなものと捉えて大量に使って「音の雲」のようなものを示そうとしたリゲティまで行き着くわけです」(182ページ)と話し、自身が生涯を通じて取り組んできた鍵盤の音の粒と持続性の関係を、実際に古いクラヴィコードに触れた感触から改めて整理している。私は坂本の、特に『アウト・オブ・ノイズ』(2009年)以降……とりわけ『async』と最後の『12』がたまらなく好きだが、それはもちろん、予定や計画なんて意味をなさない一人旅のような、ふっと立ち止まったところで音が鳴っているかのようなあれらの作品を一聴するとさりげない作品の一側面が、創作という意思の範囲を超えているように聞こえるからなのだが、しかしながらそれは、その背後に決して偶発だけではない、時代と科学によって立証されるものが当然あるからだ。それが何なのかを教えてくれるのが本書でもある。
ところで、今、東京都現代美術館で開催されている《坂本龍一|音を観る 時を聴く》が大盛況で入場してもなかなかゆっくり観られないという。筆者もなんとか行こうと思っているが、日付指定のオンラインチケット制になり、なかなか調整が難しくなってしまった。美術館なんてフラリと足を運ぶ、近くまで来たから立ち寄ってみる……なんて感じで気まぐれに観たいものじゃないのか、とも思うが、まあ、展覧会に限らず、映画もライヴも、なかなかそうはいかない時代になった。欲しいなと思っていたミュージアム・ショップでの『B-2 unit』のTシャツも速攻で完売しちゃったらしい。残念だ。もし、どうしても期間内に行けなかったら……いや、行けたとしても、本書に出てくる国立音楽大学の楽器学資料館には必ず足を運んでみようと思っている。こちらは入館料無料、誰でも予約不要でいつでも見学できるそうだ。“坂本龍一が遺したもの”は、実はいたるところにある。何も作品や映画、展覧会だけが全てではないのである。(岡村詩野)
Text By Shino Okamura

『ピアノへの旅』
著者 : 坂本龍一
出版社 : アルテスパブリッシング
発売日 : 2024.12.28
購入はこちら
関連記事
【FEATURE】
わたしのこの一冊〜
大切なことはすべて音楽書が教えてくれた
http://turntokyo.com/features/the-best-book-of-mine/