【From My Bookshelf】
Vol.1
『奇妙なものとぞっとするもの──小説・映画・音楽、文化論集』
否定性の先にあるポテンシャルをすくいあげよ
1990年代に少年時代を過ごした私は、例によってホラーやオカルトが大好きで、それは現在の趣味嗜好から人格形成までにかなり影響を与えていると思う。
私が通っていた幼稚園には小さな体育館のような建物があって、舞台の上の上手と下手には体育館らしく分厚い緞帳が何枚かぶら下がっていた。また、舞台の背後には仕切りがあって、うしろを通りぬけられるようになっていた。窓がほとんどなく昼間でも薄暗い体育館は、休憩時間などには立ち入る者がおらず、すこし不気味だった。だが、私や友人たちにとっては格好の遊び場で、というのも、がらんとした何もないフロアに対して舞台上は遊びのための仕掛けに満ちていたからだった。
舞台のおもしろさは、襞のような緞帳と背後を通り抜けられるようになっている仕掛けが空間を複層化していることだった。そこで肝試しをしたり、ミステリアスな設定を起点にした探偵ごっこをしたりと、既存のものをうまく利用した発想は、つまらない大人になった今の自分のイマジネーションよりもずっと豊かだったと感じる。
ある時、舞台のうしろ側を駆けていたら、暗闇の中できらっと光る小さなものを見つけた。拾い上げてみると、それは、そんなところに落ちているはずがない明治時代以前の硬貨だった。わくわくしたのと同時に、ちょっとぞっとしたことをよく覚えている。
幼稚園の先生にその硬貨について聞いても、なんなのかはよくわからないと言う。今となってはその硬貨がいつの時代のものだったのかすらわからないが、その時に幼い私が確信したのは、薄暗い体育館の舞台は過去やどこか別の世界に通じているんだ、ということだった。
マーク・フィッシャーの『奇妙なものとぞっとするもの』を読んでいて、30年近く前のそんなエピソードをふと思いだした。
『奇妙なものとぞっとするもの──小説・映画・音楽、文化論集』は、2017年1月13日に自ら命を絶ったマーク・フィッシャーの生前最後の著書で、イギリスでは2016年12月15日に刊行されている。最近、晩年の講義録『ポスト資本主義の欲望』が邦訳されたことも話題だが、仲山ひふみによる紹介で詳しく書かれていることもあり、思想家や批評家としてのフィッシャーの説明はここでは措く。
この本でフィッシャーは、小説、映画、音楽などの作品を彼の視点から読みときながら、「奇妙なもの」と「ぞっとするもの」を論じていく。両者は、概念というのか、恐怖に近い感情それ自体というのか、あるいは感情を呼び起こすものというのか(「情動だが、同時に様態でもある」、「存在の様態とさえいえるかもしれない」と説明されている)、とにかくえも言われぬものである。
本の方法や構成は、同じく五井健太郎の訳で《ele-king books》から2019年に刊行された『わが人生の幽霊たち――うつ病、憑在論、失われた未来』に通じており、言ってみれば、ひとつのテーマに貫かれた作品論が束ねられた集成になっている(『わが人生の幽霊たち』については以前、書評を書いたので、そちらを参照してほしい)。
ジャック・デリダ由来の憑在論という概念自体が多少複雑であるうえ、論じられている作品が日本の読者にはなじみが薄いものが多く、ページ数も膨大だった『わが人生の幽霊たち』に対して、『奇妙なものとぞっとするもの』は比較的読みやすく、身近に感じられる。なにしろ、奇妙なものとぞっとするものの定義が明快だし、いずれも一般的な感覚や生活の実感を通して理解しやすい。日々、生活においても、作品を鑑賞していても、「奇妙だ」、「ぞっとする」と感じることは誰にだってあるだろう。
フィッシャーの定義によると、奇妙なもの(the weird)とは、「何にも属していないもの」で、「慣れ親しんだものにたいして、(中略)それを超えたところにあるものをもたら」す、「同じところに属していない二つ以上のものを結合する」ものである。べつの言いかたをすると、それは「何かが間違っている」という動揺や異様さの感覚を伴うため、既存の枠組みや世界理解を揺さぶってみせる。そして、そういった「真の外在性」こそが、決定的な特質なのだという。
奇妙なものについて論じるために、フィッシャーはまずH・P・ラヴクロフトの作品を読みこんでいく。ラヴクロフト作品において奇妙なものは「恐怖ではなく魅惑」であり、否定性が「むしろそれを純化していく喜びの様態である」といい、かなり倒錯性を感じさせる。
ほかにH・G・ウェルズ、ティム・パワーズ、ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー、フィリップ・K・ディック、デイヴィッド・リンチといった作家によるホラーやSFの小説、映画を読みこんでいくのだが、珍しく音楽の例として挙げられているザ・フォールの項に注目したい。
ここでフィッシャーは、「グロテスク」という言葉の由来や原義に立ち返ることから始め、「反感と同様笑いを引き起こす」という「奇妙なものの特殊な例の一つ」である「グロテスクなもの」、そしてそれと奇妙なものとの「合流を示すこれ以上ない例として」ザ・フォールの作品を考えている。
といっても、演奏やプロダクションについて言及されてはいるものの、後半で中心的な検討材料になっているのはマーク・E・スミスのリリックだ。ラヴクラフト的な怪奇でグロテスクな「混合物」としての例でまず挙げられるのが、まさに『Grotesque (After The Gramme)』という題が与えられたアルバムの中の「The N.W.R.A.」である。フィッシャーがたびたび強調しているのは歌詞の登場人物の労働者ロマン・トータルの身体が「触手だらけ」であることで、それは「有機的な全体性とは相容れないもの」なのだという。
「The N.W.R.A.」に代表されるザ・フォールの表現の核心とは、フィッシャーにとって、「労働者階級出身であると同時に実験的で、大衆的であると同時にモダニスト的」、そして「存在しえないものであり存在してはならないもの」という特徴である。言い換えれば、先に引いた「混合物」や「有機的な全体性とは相容れないもの」である、ということだろう。つまりは「今、ここ」の現実の外になにかがあること(外在性)、あるいは世界の内に裂けめのようにして存在する外部との関係性が、中心的なテーマであり、フィッシャーがザ・フォールの音楽に見いだす可能性なのである。
もう一方のぞっとするもの(the eerie)は、「何にも属していないものの現前」、「不在の失敗や現前の失敗によって構成されている」のだという。
序文にわかりやすい例がある。「部分的に人間がいなくなった風景」という描写だ。これは、ネット・ミームであるリミナル・スペースのことを想起すると理解しやすい。詳細はこの本からの引用もある木澤佐登志の論考「【コラム】Liminal Spaceとは何か」に譲るが、リミナル・スペースは「何かがあるはずのところに無が現前している」現前の失敗の好例であると言える。人間、あるいは人間性や人間味、社会性や言語が、あるべきところにない静寂の空間──それが、リミナル・スペースが人をぞっとさせる特徴である。
ぞっとするものについての論でおもしろいのは、評論の対象に作品だけでなく、こういった現実の空間や土地さえもが含まれているところで、サフォーク州のフェリックストーのコンテナ港とサットン・フーの船葬場、ワックスハムの村がぞっとするものの例に挙げられているのが印象的だ。それらの無機的な、だが確実に人工物であるものに埋め尽くされた空間は、「不在によって支配されている」。
ぞっとするものについて重要なのは、行為主体(エージェント)/行為主体性(エージェンシー)についての問いであると、フィッシャーは強調する。これはちょっとややこしいのだが、「代理人」や「媒介するもの」、「作用因子」といった多義的な意味を持つ“agent”ないし“agency”は、つまり、なにか物を動かす作用をはたらいたり、ある行為を遂行したりする主体を指す言葉である。自由意志との関連も深い哲学的な概念だが、とにかく、行為をおこなう主体が存在しているのか、どんな主体がいて、それがなにをやっているのかがよくわからない、それがぞっとするのだ、というふうに解釈していいだろう。
そこでフィッシャーが指摘しているのが、その最たるものとしての資本の存在である。大きな影響力と支配力を及ぼし、人や物を動かす絶大な力を発揮する不可視の資本は、そうであるがゆえに人をぞっとさせる。その点で、フィッシャーのぞっとするものについての論は、疎外論のひとつとして読むこともできるだろう。
『奇妙なものとぞっとするもの』を読んでいて強く感じたのは、フィッシャーの外部への指向/志向性だ。それを目の当たりにすると、やはり『資本主義リアリズム』で描出された出口なきハイパー資本主義社会からのイグジットを模索していたのだろうと、容易に予想できる。それは、五井のあとがきにもあるとおりだ。
目の前にある行き詰まった現実世界の中に、あるいは外に、他なるもの、外在するものを見いだそうとすること。あるいは、「有機的な全体性とは相容れない」奇妙なものにベットしてみること。フィッシャーは亡くなってしまったが、彼がここで論じたことは、日常的な感覚で理解しやすいこともあって、残された私たちにとって政治的な、社会的な、システム的なオルタナティヴを考えるヒントに満ちている。奇妙なもの、ぞっとするものの否定性の先にあるポテンシャルをすくいあげよ、とフィッシャーは言っているかのようだ。
また、これは牽強付会であるものの、ひとつ言っておきたいのは、『奇妙なものとぞっとするもの』の論は、私が敬愛する映画監督、黒沢清の作家論にかなり応用できそうだということ。
黒沢のシグネチャーのひとつに、揺れるカーテンや半透明のヴェールという小道具の多用がある。これについて黒沢は、カットを割ることなく「一つの情景があって、カーテンの向こう側にまた何かがあるという状態を作ることができる小道具」(『黒沢清の映画術』)だと明言している。ヴェールやカーテンの先(外)を予期させ、空間を複層化したうえで結合、混合した様を見せるその演出は、まさにぞっとするものの一例だろう。
あるいは、黒沢映画でカーテンを揺らしている行為主体は、いったいなんなのだろうか。風なのか、それとも……? 物が勝手に落ちたり倒れたりして音を立てる、というホラーにありがちな演出をより不気味にしたものも黒沢作品には多いのだが、それも行為主体性への問いをはらんだものにほかならない。そして、脱政治的、非政治的で美的なものであることが批判、指摘されがちな黒沢作品には、その点において政治性が潜性している、と言うことができる。
ここで最初のエピソードに戻ってみると、だれもいない幼稚園の体育館のフロアはリミナル・スペースのようでもあり、複層化した舞台上の空間は黒沢映画の空間のようでもあった。
あの硬貨の落とし主は、行為主体は、なんだったのだろうか? (天野龍太郎)
Text By Ryutaro Amano
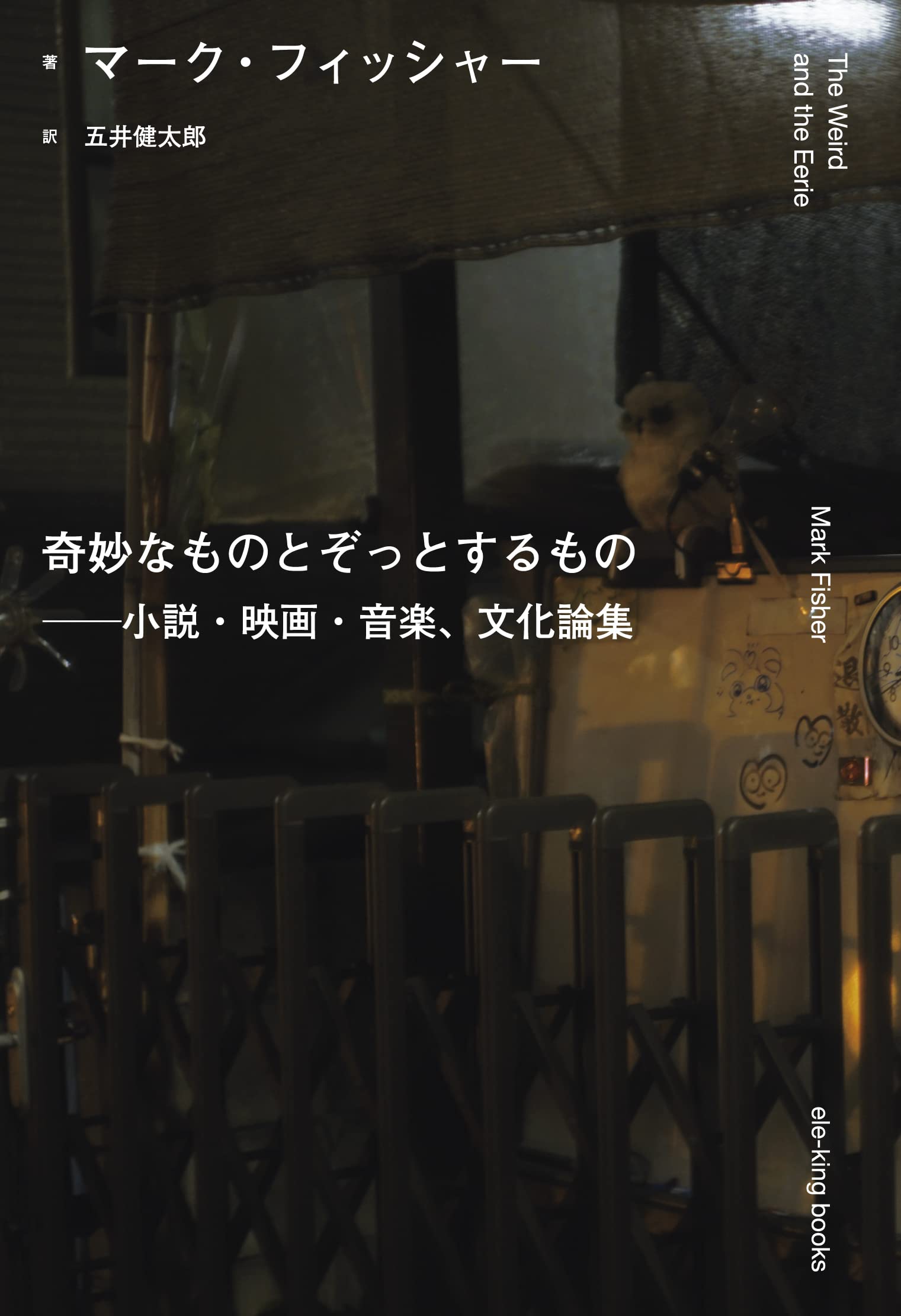
『奇妙なものとぞっとするもの──小説・映画・音楽、文化論集』
著者: マーク・フィッシャー
翻訳:五井健太郎
出版社:P-Vine / ele-king books
発売日:2022年12月02日
購入はこちら
書評リレー連載【From My Bookshelf】
過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)
関連記事
【FEATURE】
わたしのこの一冊〜
大切なことはすべて音楽書が教えてくれた
http://turntokyo.com/features/the-best-book-of-mine/

