スタジオの空気を封じ込める魔法
ダン・キャリー 主要作品ディスク・ガイド
~UKの“いま”を生み出す人気プロデューサー~
2019年ごろ、フォンテインズD.C.やブラック・ミディなどを手がけるロンドン/ダブリン、インディー・シーンのキーマンとして各メディアでも名前を頻繁に目にするようになったプロデューサー、ダン・キャリー。それ以前にも2014年には、ケイ・テンペストとニック・マルヴェイのプロデュース作品をマーキュリー・プライズのノミネートに送り込むなど、着実にキャリアを前進させていた。だが近年の彼の仕事ぶりとその刺激的な作品の数々には特に驚かされる。
1969年、ロンドン北部イズリントン生まれ、現在はロンドン南部ストリーサム在住のダン・キャリー。彼は90年代半ば、複数のユニットでトリップ・ホップ〜ビッグ・ビート系のミュージシャンとして活動をスタートしている。近年のインディー・ロック系の作品群のイメージからすると意外に思えるところもあるが、彼の手がけたバンド・サウンドにおけるドラムやベースの撮り音への拘りには、そうしたエレクトロニック/ダンス的なバックグラウンドが透けて見えるかもしれない。
彼のプロデューサーとしての貢献は、すでにこの《TURN》でも、先頃発表された第65回グラミー賞で2部門を受賞したウェット・レッグ、ハニーグレイズといったアーティストへのインタヴューによって明かされている部分もある。メンバーの関係性への介入の巧さ、ライヴを中心とした生々しい空気感を記録するレコーディング・メソッドは、まさにインディー・ミュージシャンたちの音楽と相性がいい。そうした部分は、2013年に設立し現在ではUKのインディー登竜門の一つとなっているレーベル《Speedy Wunderground》と、そこでの自分のスタジオを使ったレコーディングでの経験値によって還元されたものなのだろう。
本記事はそんなダン・キャリーのディスク・ガイドとして、彼の00年代からのプロデュース・ワークの変遷と進化を、じつに25枚の作品とともに俯瞰してみる。ちょっと意外に思える過去のコラボレートや、彼が紡いできた世代とジャンルを越えた繋がり、そこから立ち上がる一つのコミュニティーとしてのUKシーンの現在とそれから。楽しみながら、彼の軌跡を振り返ってみてほしい。ちなみに、3月3日リリース予定のスロータイのサード・アルバム『UGLY』もダン・キャリーがプロデュースすることが発表されている。 (編集部)
(ディスク・ガイド原稿/相澤宏子、阿部仁知、岡村詩野、小倉健一、尾野泰幸、風間一慶、木津毅、駒井憲嗣、吸い雲、高久大輝、髙橋翔哉、tt、hiwatt、油納将志、吉澤奈々)
Emilíana Torrini『Me and Armini』
2008年 / Rough Trade

ダン・キャリーがエミリアナ・トリーニを手がけたのはこれが最初ではない。この前に『Fisheman’s Woman』(2005年)という、タイトルから思わずマイク・スコットのウォーターボーイズを思い出してしまうような作品をプロデュースし、ギター、ベースなどでもバックアップしている(そのアルバムでビル・キャラハンの曲をカヴァーしているから、というわけではないが、舌足らずな愛らしいヴォーカルも相まってジョアンナ・ニューサムを思い出した人も当時多かっただろう)。だが、プロデューサーとしてまだ駆け出しの時分にこうしたフォーキーなアーティストに関わったからこそ、キャリーはこの後シーアやリリー・アレンなどの人気アーティストの楽曲も手がけていくが、たとえダンス・ミックスの作業でも、ダイナミックな音作りでも繊細なアコースティック楽器の音を埋没させない硬軟つけた仕事をするようになったのかもしれない。エミリアナにとってダンと組んだ2作目となる本作では、同郷の大先輩であるビョークを思わせる4曲目や9曲目のようなユニークな節回しの曲も増えているし、バンド・サウンドを大胆に取り入れた曲も存在感を放っているが、一方で3曲目や10曲目などかつてカヴァーもしたサンディ・デニーもかくや……と思える素朴というより優美な曲が情緒的な息吹を存分に伝える。妊娠を理由に断ったビョークの代わりに歌った映画『ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔』のエンディング曲(2002年)が話題を集めたが、77年アイスランドはコーパヴォグル出身、コツコツとカヴァー曲を歌ってきたこのシンガー・ソングライターの幅広い表現力を引き出したのはキャリーだと思うのだ。(岡村詩野)
Franz Ferdinand『Tonight: Franz Ferdinand』
2009年 / Domino, Sony

2009年頃のUKインディーは過渡期であった。ニュー・レイヴ・シーンも終焉間近で、活動休止や解散を宣言するバンドもちらほら。そんな中、00年代を牽引したアークティック・モンキーズとフランツ・フェルディナンドという《Domino》が誇る二巨頭は、アダルト、セクシー、ダーク、マッドといった形容が似合うサウンドの作品をリリースした。両作共に未だ賛否が分かれているが、この変化がその後のUKインディーの指針になったと言える。
フランツ・フェルディナンドの『Tonight』は、「踊れる」というバンドの哲学は残しつつ、絶妙なレイヤーの変化を遂げた。それには、この作品で名を知らしめたプロデューサー、ダン・キャリーが大きく貢献している。当時はその作家性を知る由も無かったが、後に手掛けた作品を聴いていく中で、この作品がキャリーの趣味性が最も色濃い物だったと断言できる。
彼が手掛けた作品は、いずれも暗いトーンで、ささくれ立ち、脆いながらもマッドネスを内に秘めた印象だ。それはレゲエやダブが傍にあった彼のオリジンも一つの要因である。『Tonight』には、スプリング・リヴァーブのじめっとした残響や、マッドなサイレンなどのダブマナーと言える要素が印象的に多用されている。
ダブへの欲求が発展し過ぎた結果、このアルバムのダブ・ヴァージョンである『Blood』がバンドとキャリーの共作でリリースされたが、見過ごされがちな逸品であるし、よりダン・キャリーの作家性に触れることができる。彼を語る上では確実に避けて通ることのできない一作(二作)である。(hiwatt)
Miles Kane『Colour of the Trap』
2011年 / Columbia

特に日本のインディ・ロック・リスナーの間ではラスト・シャドウ・パペッツとしての印象が強いであろうマイルズ・ケインだが、ザ・リトル・フレイムス、ラスカルズといった正統なロックンロール・バンドを渡り歩いてきたキャリアの持ち主でもある。そんなマイルズのソロ・デビュー作『Colour Of the Trap』は60年代のソウル・ミュージックやサイケデリック・ロックへの憧憬をストレートに表現したアルバムと言える。ともすればレトロ一辺倒になりかねない方向性ではあるものの、絶妙にモダンなプロダクションに仕上がっているのは、本特集の主役であるダン・キャリーと、当時はゴリラズなどでその手腕を発揮していたダン・ジ・オートメーターという2人のプロデューサーの貢献も大きいのだろう。
また、本作はラスト・シャドウ・パペッツの2枚のアルバムの狭間で制作された作品の1つであり、随所にそのエッセンスが散りばめられている。例えば、「Counting Down The Days」のキャッチーなメロディの中に潜むマカロニ・ウエスタン的な展開は『The Age Of The Understatement』の名残りがあり、何より「Telepathy」を始めとするサイケデリック・ガレージ・サウンドは、後の『Everything You’ve Come To Expect』に連なるものである(その点では次作『Don’t Forget Who You Are』は王道ロック・サウンドに回帰した感があり、どちらかと言えばラスト・シャドウ・パペッツ要素は希薄だ)。本作は偉大なる盟友アレックス・ターナーの影に隠れながらも、バンドのサウンドを形にするうえでの重要なパートナーであるマイルズの非凡な才能を再確認できる、そんなアルバムと言えるのかもしれない。(tt)
Oh Land『Oh Land』
2011年 / Epic, Fake Diamond

コペンハーゲン出身のSSW=オーランドが、USデビューを迎える転機作でもあった『Oh Land』。2作目のセルフタイトル・アルバムは、プロデューサーにダン・キャリーをはじめ、ビヨンセやデペッシュ・モードを手がけたデイヴ・マクラッケンらを迎えて制作された。故郷のデンマークで音楽活動をしていたオーランド自らブッキングして《SXSW》に出演。そこから2年の準備期間を費やして完成したのが本作である。全編を通して彼女の愛くるしい歌声とシンセを活かした、優美なエレクトロ・ポップという印象を受ける。さらに、キャリーの手掛けた5曲はどれも毒っ気があり先鋭なサウンドが活かされているようだ。いきなり冒頭の「Perfection」から、乾いたスネアの音色とヴォーカルがはっきり分離したサウンドが際立つ。ドンシャリと表現しても不思議ではない強弱の調子は、異様な緊張を醸し出していた。ビートのBPMもそれほど早くないし、うねりの効いたサイドチェインも入ってこない。それでも、煌びやかな中音域を際立たせ、歌声のレイヤーを重ねることで奥行きのあるダンス・ポップに仕上がっている。さらに、シンセポップ調の「Voodoo」もキャッチーだが、反復を繰り返すシンセのフレーズはウェット・レッグを彷彿とさせる中毒性がある。ダン・キャリーの手腕による、ひねりの効いたエッジーな音使いによって、妖艶な影を本作に落としたと言えるだろう。(吉澤奈々)
Chairlift『Something』
2012年 / Kanine, Young

ブラッド・オレンジやチャーリーXCXさらにはビヨンセの作品にも参加するなど、ソロ・アーティストとして確たる地位を築くキャロライン・ポラチェックがキャリア初期に組んでいたバンド、チェアリフト。2008年のデビュー・アルバム『Does You Inspire You』は楽曲がiPodのCMに使用されたことでも話題となり、本作はそれに続くセカンド・アルバム。
表向きは一見当たり障りのない80s風ポップスの体であるが、その実アルバムのクレジットに目を向けると、今やBeckのグラミー獲得アルバムも手がけるコールM.G.N率いるThe Samps、Violenceのフロントマンで現在はプロデューサーとしても活躍するJorge Elbrecht、元ザ・ペインズ・オブ・ビーイング・ピュア・アット・ハートのメンバー、現アイス・クワイアのカート・フェルドマンといった面々が参加、そしてプロデュースにはダン・キャリーという玄人センスが露呈したカルチャー盤。
本作収録の「I Belong In Your Arms」には日本盤CDのボーナスディスクと7インチにしか収録されていない日本語ヴァージョンが存在するのですが、そのMV含め人によってはギャグになりかねないラインを成立させる姿はまさに「アーティスト」と呼ぶにふさわしい。(小倉健一)
Mystery Jets『Radlands』
2012年 / Rough Trade

テムズ川に浮かぶ小さな島「イール・パイ・アイランド」を拠点として生まれたミステリー・ジェッツ。かつて一世を風靡したロンドンの音楽シーンの一つ、テムズ・ビートの代表格バンドだった。実に懐かしいシーンだ。2010年代からはこうしたシーンの盛り上がりも寂しいものとなり、そもそもイギリス国内でもインディ・バンドの存在感が薄れていった時代だった。
そんな時期に、アメリカはテキサス・オースティンでレコーディングが行われたミステリー・ジェッツの4thアルバム『Radlands』。特徴ははっきりしているが、掴みどころが難しい作品である。
初のアメリカでのレコーディングというのも納得の、フォークやカントリーの要素が散りばめられ、骨太でアンセム的な音を目指したような作品だ。これまでは、サイケとシンセポップとプログレがとっ散らかったような、ちょっと不思議でミステリアスで、ドリーミーな、心踊るような楽しさがある…そんな感じが他に類を見ない大きな魅力のひとつであったが、この作品は非常にタイトにまとまった作品である。
その中でも「Someone Purer」はいつものミステリー・ジェッツのポップさが活かされており、サビでは大合唱を起こせるような軽快で明快なメロディが印象的だが、曲の最後には不穏な余韻が残る。こういった要素の組み合わせは非常に彼ららしいと感じた。全体としては、らしさを失わずに新しい方向に向かうことの難しさを痛感させられた作品であった。(相澤宏子)
TOY『TOY』
2012年 / Heavenly

前身であるジョー・リーン&ザ・ジン・ジャン・ジョンのレコーディングにおける仕事を記憶していたバンドが、キャリーにデビュー作のプロデュースを依頼。ガレージ・ロック・リバイバルの徒花的イメージだった彼らが、ノイ!―もっと端的に言うと「Hallogallo」―の影響下にあるアンサンブルへと変貌を遂げたのは、信頼関係を築いた上でアーティストが無意識のところで持っていた指向を引き出すキャリーの手腕によるところが少なくないだろう。現場ではスタジオにスモーク・マシーンとレーザーが持ち込まれたそうだが、テイクとオーバーダビングを限りなく削いだうえで、そうした演出でバンドのモチベーションを上げていくキャリーのアティチュードが結実している。「Dead & Gone」にあるドロップや、「Colours Running Out」のヒプノティックなベースラインといったトレードマークのほかに、いささか大仰なバラッド「My Heart Skip A Beat」に顕著なように、甘い憂いのある80sなポップセンスが顔をのぞかせるのは、クラウトロックから影響を受けた他のアーティストとは一線を画す点として記しておきたい。今彼らのディスコグラフィを俯瞰してみて、その時々で実験性を加えながらも、美しく統制されたノイズと音のレイヤーが生むバランスはほぼ崩れていないのは驚くべきことだし、いかにこのファースト・アルバムが彼らに重要だったかを物語っている。(駒井憲嗣)
Bat for Lashes『The Haunted Man』
2012年 / Parlophone, EMI, Capitol

ナターシャ・カーンによるバット・フォー・ラッシーズの3作目で、ダン・キャリーは11曲中7曲に参加。カーンにとっては絶賛されたセカンド作『Two Suns』(2009年)のネクストにあたる正念場であったため、かなりの気合が感じられる一作だ。ビョークやケイト・ブッシュと比較されてきた少しダークで妖艶なエレクトロ・ポップを拡張するために、彼女が選んだのは多くのゲスト・ミュージシャンを呼びこむことだった。TV・オン・ザ・レディオのデイヴ・シーテック、ポーティスヘッドのエイドリアン・アトリー、ロブ・エリス、そしてベック・ハンセン。そのようにしてサウンドの幅を広げるなかで、全体像をまとめる役割を担ったのがキャリーだったのだろう。前作に引き続きプロデュースはカーンとデヴィッド・コステンがメインになっているが、クレジットを見るとキャリーは(コステンも担当している)プログラミングのほかにギターやピアノ・パーカッション、ベース・プログラミング、シンセも扱っている。実際、キャリーの参加トラックを聴くとその空間的なサウンド・プロダクションもさることながら、音色の多彩さに舌を巻く。あくまでカーンによるアトモスフェリックなタッチを尊重しつつ、音の使い分けと配置をきめ細かくおこなったキャリーは本作の洗練のキーパーソンだったにちがいない。とりわけアルバム後半の、より入り組んだムードに分け入っていくようなニュアンスに富んだサウンドは、聴き手を心地よく耽溺させるバット・フォー・ラッシーズの歌世界に対する深い理解が感じられる。(木津毅)
Steve Mason『Monkey Minds in the Devil’s Time』
2013年 / Double Six

近年のダン・キャリーの仕事を思い浮かべると、たとえばフォンテインズD.C.「Jackie Down The Line」におけるスネアの音抜けやライドの伸びやかな響き、スクイッド「Pamphlets」におけるライドの粒立ちなど、ドラム、特に皮モノ・金モノの録り音が印象に残る。そうした中・高域の音が、アコギと小気味よく混ざる感じ。これが、わたしが彼に対して持っているイメージだ。しかし、この人って最初はもうちょっとエレクトロ寄りというか、ダンス畑から出てきた人ではなかったかしら…と思ったとき、転換点として意外にもこの作品あたりがキーになったりするのではないか。
スティーヴ・メイソンはベータ・バンドなどで知られる音楽家で、本作はそのセカンド・ソロ・アルバム。フォーク~ダブ~ジャズを横断する意欲的な作品で、サウンドはフォー・リズムに管弦が絡む生楽器主体のものだ。録音は良く、特に「Lie Awake」や「A Lot Of Love」での演奏者の姿が見えるようなウェット気味なドラムは素晴らしい。そして、そこでは先述した伸びやかなライドが印象深く鳴っている。もともとキャリーの持ち味だったエレクトロ要素は「Lonely」の電子ドラムなどに見られるものの、それよりはるかに生楽器の響きが印象に残る作品だ。
同時期、ダンは自スタジオでの短時間でシンプルな録音を掲げて《Speedy Wunderground》を設立しているので、ここにはそうした関心も表われているのではないだろうか。そして、そのレーベル第1弾リリースはまさにこのスティーヴ・メイソンが歌う「I Go Out」だったりする。そうやって考えていくと、現在の彼の仕事に繋がる作品として聴き返す価値があるのでは?と思えてくる、隠れた名作である。(吸い雲)
Nick Mulvey『First Mind』
2014年 / Fiction

ニック・マルヴェイといえば、キューバのハバナで音楽と芸術を学び、帰国後も学院で民族音楽学を専攻した熱心な研究者の一面をもつ。そんなマルヴェイはUKジャズに新風を吹き込んだ、ポルティコ・カルテットの初期メンバーでもあった。ポスト・ロックから現代音楽まで網羅するポルティコ・カルテットを脱退してから、初のソロ・アルバムとなったのが今作。
『First Mind』(2014年)はフォークとエレクトロニカの境目なく、ボーダーレスに楽器が鳴り響いている。プロデューサーにダン・キャリーを選んだのは、こうした積極的な折衷への共鳴にあるのかもしれない。そう感じるのは「Cucurucu」のポエトリー・リーディング調に語り始めるマルヴェイの歌声に、ベース、ストリングス、コーラスなど多彩なサウンドが重なり、フォークからポップに変化していくさま。こうした、遊び心のある楽器の配置はキャリーならではと言える。さらに「Fever To The Form」ではギターのカッティングをクリアにして輪郭を浮き立たせる。反復するフレーズが徐々に層を増していく流れは、ポルティコ・カルテットに通じる即興性を感じ取れるはず。ソロになって作風が変わったという声もあるようだが、トラディショナルに重きを置く一面や、自由度の高い奏法においては同じである。そうしたジャンルや楽器の枠を飛び越えて繋げる仕事ぶりはダン・キャリーの得意技でもあり、いまも重要な役目をもっている。(吉澤奈々)
SEXWITCH『SEXWITCH』
2015年 / Echo
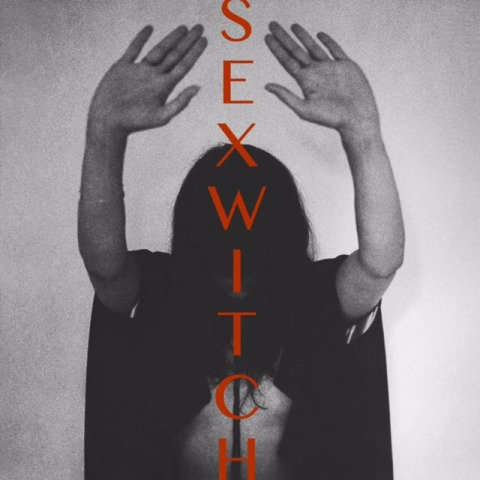
ダン・キャリーとバット・フォー・ラッシーズのナターシャ・カーンがコンセプト設定からアレンジに至るまでを共同で制作し、バックにTOYを従えたプロジェクト=SEXWITCH。バット・フォー・ラッシーズの作品に何度も現れる2つのテーマをストレートに掲げたこの挑発的な集団は、西洋の外側に散らばる「サイケ」で「ウィアード」なレコードを発掘し、それらを英訳した上でクラウトロックに乗せて再び現代に召喚する。モロッコにタイ、イランなどディグの対象は広範に及んだ。
『Tago Mago』期のカンにも通じる呪術的な反復の美学を、ナターシャ・カーンはより禍々しく増幅させる。それはオリジナルに潜んでいた霊性を引っ張り出す儀式のようでもあり、単なるカヴァーに止まらない啓示を私たちに与えてくれる。特にハンマービートの反復性が土着的な恐怖感と合流する現象は、一種の新発見とも呼べるものではないだろうか。
とりわけ啓示的なのは本作のラスト。唯一欧米圏からのカヴァーとなった米アシッド・フォーク界のカルトスター、スキップ・スペンスの「War In Peace」だ。ベックやマッドハニーも取り上げた一曲だが、彼らは限りなくオリジナルに近いダウナーなテンションで接近を図る。だからこそオリジナルに備わる朴訥とした抒情性を実感できるし、その上で数多のジャンルとの結節も予感させられる。正に魔女然とした、神秘的な試みと言えよう。(風間一慶)
Teleman『Brilliant Sanity』
2016年 / Moshi Moshi

Telemanの2作目『Brilliant Sanity』はダン・キャリーの意向により、シンセ・サウンドに軸をおいて制作されたという。元スウェードのギタリスト、バーナード・バトラーがプロデュースを手掛けた前作『Breakfast』(2014年)は、ギターのリフやリズムを活かしたミニマルな印象があった。今作はキャリーがミキシングに携わったこともあり、ぐっとメロディアスでコード進行を意識した楽曲が多く感じられる。なにより、シンセを大きく取り入れたことで、3ピースであるTelemanの演奏をよりバンド・サウンドへと比重を置くものになったのだ。
冒頭の「Dusseldorf」はタイトなドラムの演奏、ソリッドなギターソロとUKインディー・ロックの特徴はありながらも、80年代風のシンセや女性ヴォーカルが入ることで、キャッチーな作風になっている。とくにアルバム・タイトル曲の「Brilliant Sanity」で楽曲の流れがメランコリーなシンセポップへと一変するのが印象的。マイナー調のシンセ・フレーズを、フランジャーの動きなど抑揚とひねりのある音色をつけて進む様は、今作のシンセ・サウンドを特徴づけている。フランツ・フェルディナンドやベル・アンド・セバスチャンのサポート・アクトをはじめ、《Moshi Moshi》の出身である、Teleman。UKインディー・ロックを熟知するキャリーがプロデュースを手掛けた本作は、サウンドの通り密度を増している。(吉澤奈々)
Pumarosa『The Witch』
2017年 / Fiction

ロンドンを拠点に活動する5人組バンドのデビュー・アルバム。ザ・キュアーで知られるユニバーサルミュージック傘下のフィクションからリリースされた。
2009年に発表されたフランツ・フェルディナンドの3作目『Tonight』で抜擢され、日本でもその名が知られるようになったダン・キャリーだが、その後はロック・バンドのプロデュース仕事が増えていき、TOYやチェアリフト、テレグラムなどのサイケデリックなテイストを持つバンドを多く手がけるようになる。並行するように、バット・フォー・ラッシーズやオール・ウィー・アーといったシンセポップのアーティストもプロデュースしており、ダンはどちらの音の方向性にも長けた存在として重宝されたことが伺える。このピューマローザはシンセとサックス担当のメンバーを含む編成で、ドリーム・ポップを基軸にシンセポップやポストパンクの要素も取り込んだサウンドが特徴であり、ダンがプロデュースしたのはまさに正解と言える。
全10曲中、6分超えが4曲、残りも4分超えと長めの曲で全体が構成されており、静かな導入から徐々に盛り上がっていくパターンの曲調が多いのはインプロで演奏しながら曲を形作っていくプロセスを採用しているのだろう。ともすればまとまりに欠けるアプローチになってしまいがちだが、そのまとめ役としてダンが手腕を振るったことが伺える。09年発表の2作目ではセイント・ヴィンセントやエンジェル・オルセンらを手がけるジョン・コングルトンがプロデュースを担当。こちらはちょっとまとまり過ぎている感があるが、デビュー作で展開した世界をさらに押し拡げた力作となっている。(油納将志)
black midi『Schlagenheim』
2019年 / Rough Trade

サウス・ロンドンにて4人組としてスタートしたロック・バンド、ブラック・ミディ。当時は、メンバー全員が20、21歳であるとか、ブリット・スクール出身であるとか、チャーチに従事していたとか、数時間におよぶジャムから作曲しているとか、情報のノイズも多いしどこか高尚で難解な作品として語られるきらいがあったような。しかしその後の2作を経験している現在の私たちにとっては、本作はひじょうに初期衝動と遊び心とエネルギーのほとばしるデビュー作らしいアルバムとして振り返られるべき。上述のとおり長いセッションののちに、それを素材としてツギハギするという創作プロセスによるチグハグな手ざわりは、メンバーの関係性や空気感を残しながらも、コンポーザーとしての感性を同時ににおわせる。そしてそこには、「バンドの関係性にズカズカ踏み入るのではなくスタジオの空気を重要視する」ことに長けたプロデューサー、ダン・キャリーの手腕によるところもかなりあるはず。そんな中で最初期に生まれた楽曲のひとつ、「bmbmbm」で胸に迫るように削り続けるギターと、ヴォーカルの“purpose”の破裂する発声と、引き伸ばされた口角と、どもりチグハグになる言葉は、彼らのコラージュ的な編集センスと重なり、本作のクラウトロック~ノー・ウェイヴ的側面を強調している。その後のメンバーの脱退、ジャズとプログとヴォードヴィルへの超接近。ひとときの静寂、そして膨張の前ぶれ……。これが彼らの、はじめで最後のポストパンク・レコード。(髙橋翔哉)
Warmduscher『Tainted Lunch』
2019年 / The Leaf Label

ならず者のバンドマンが演奏を始めた途端に礼儀正しく縮こまり、オーソドックスなサウンドを鳴らして肩透かしを食う、なんてことは少なからずあるが、Warmduscherに限っては安心だ。そう高を括っていた人々にとって本作の冒頭──リヴィングレジェンド、イギー・ポップによる独白──は、意表を突くものだっただろうか。あるいは、アルバムの中盤、6曲目「Burner」の明らかに浮いたGファンク的サウンドとクール・キースのラップを聴いて、彼らがセルアウトしたと感じただろうか。多くのリスナーにとって、その答えはノーのはずだ。WarmduscherはたしかにUKの薄汚れたインディー・バンドだが、Warmduscherの作品を愛聴する人々は、型にはまったアルバムなんて求めちゃいないし、でも同時に音楽以下のゴミを聴きたいんでもない。Warmduscherの連中は、それを良く理解しているようだった。アルバムを、できれば何周か聴いてみるといい。サウンドはヴァリエーションに富んでいるというよりカオスと呼んだ方が正確で、でもどうしてか耳に馴染めば馴染むほどに良く聴こえてはこないか。つまりリスナーは、彼らが音楽を“クソ真面目”に、やりたい放題やっているのが聴きたいのだ。そして、後ろにはダン・キャリー。これほど納得できることも珍しいだろう。
ちなみにWarmduscherの作品のほとんどをキャリーが手掛けているが、『At The Hotspot』(2022年)のプロデュースはキャリーがコロナに感染したためホット・チップのジョー・ゴッダードとアル・ドイルが担当している。(高久大輝)
La Roux『Supervision』
2020年 / Supercolour

ラ・ルーことエリー・ジャクソンといえば、デビュー時のエキセントリックなヘアスタイルに象徴されるような(画像検索してみてください)、よくデザインされていてスタイリッシュなシンセ・ポップーーそれもヤズーやユーリズミックスの血を引くような――で颯爽とポップ・シーンに現れた存在。そのイメージはいまでも強く、その後は比較的寡作のなかでゆるやかにサウンドを広げてきた彼女だが、この3作目ではシンセ・ポップの土台はそのままにゆるいファンクやディスコの感覚を大きく導入している。連想される固有名詞はナイル・ロジャーズ、ジョージ・マイケル、そしてマイケル・ジャクソン。ダン・キャリーはそして、ジャクソンとともに本作のプロダクションとミキシングを手がけ、シンセやベースも弾いている。キャリーはすでにブラック・ミディやスクイッドのデビュー作を担当したことで“いまのロックの音”を作れるプロデューサーとして話題になっていたタイミングなので、このようなある種ティピカルなジャンルのアーティストも同時にこなせることをここで証明している。そしてまた、ラ・ルーの初期のサウンドよりもシンセにせよ生音にせよ感触はずいぶんまろやかになっていて、デザイン性の高さに心地よい穏やかさを加えることにも成功していると言えるだろう。ダン・キャリーはある意味でジャンル・ミックスの時代を代表するプロデューサーのひとりだが、それは特定のジャンルに対する深い理解や鋭い感性を持ち合わせているからこそなのだ……ということを、本作は端的に示している。(木津毅)
Fontaines D.C.『A Hero’s Death』
2020年 / Partisan
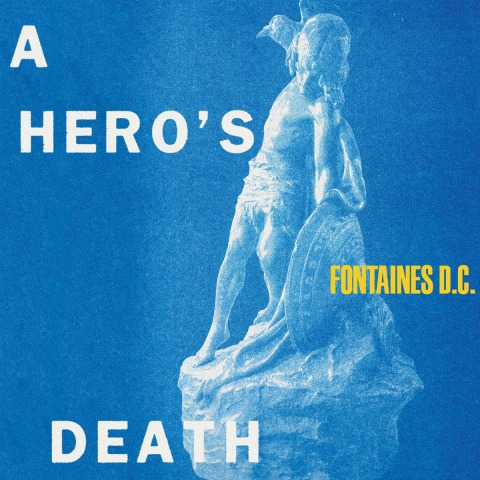
2010年代後半の“ロック”における最大級のムーヴメントを形成したサウス・ロンドン周辺と比肩する注目を浴びたアイルランド・ダブリンを出自とし、同エリアにおけるロック・バンドの展開に対する注目度を引き上げる存在ともなった五人組による二作目。ダブリンという都市に堆積する人々の物語と記憶を土台に、錆びたナイフを振り回すような衝動的なポストパンク・サウンドと暗闇のなかで時に叫び、時に静かに独り言つような表情豊かなヴォーカルを刻印した一作目『Dogrel』は《The Guardian》をして、アークティック・モンキーズの一作目にも匹敵する鮮やかな特徴を持ち、メインストリームのインディー・ロック・バンドの基準をリセットする程の出来栄えだと評された。二作目たる本作ではそれらのタイトでメリハリの利いたサウンド的特徴を踏襲しつつも、まどろみのなかで方向感覚を喪失させるようなサイケデリック・サウンドに、相対的にスローなアシッド・フォーク的楽曲も展開され、バンドの奥行きと表現力を感じることができる。
本作は上述したサウス・ロンドンとダブリン周辺で活躍している数多くのバンドの作品に携わり、シーンの結節点となっているダン・キャリーのプロデュースのもと、彼の自宅でレコーディングされている。いくつかのインタヴューでシーンのまとめ役としてのダンの存在感と、プロデュース/レコーディング・ワークに対する信頼感が複数のメンバーから語られているが、一作目の成功とそれにともなう大規模ツアーにより疲弊し、自らの足元を物理的にも精神的にも見失いかけていたバンドにおける制作的な下支えとしてダンの存在が、きっと本作にも不可欠だったはず。(尾野泰幸)
Goat Girl『On All Fours』
2021年 / Rough Trade

シェイムやブラック・ミディらを輩出し、2010年代後半からのUKシーンを語る上で外せない磁場となったサウス・ロンドンのウインドミルより登場したゴート・ガール。本作は2018年のデビュー・アルバムに続くセカンド・アルバムで、前作に引き続きダンがプロデュースを担当している。
19曲40分、2分前後の楽曲を中心にデビュー・アルバム然とした勢いに満ちた前作から一転、本作ではメランコリックなムードが全体を覆い、明らかに雰囲気を異にしている。ダンス・ビートやシンセサイザーの導入など注目すべきポイントはいくつかあるが、特に耳を惹かれるのはバンドのリズムに対するアプローチだ。
前作リリース後にベーシストのNaimaが脱退(彼女は昨年《Sub Pop》よりソロ・アルバムをリリース。ゴート・ガールのメンバーも参加しており、レコーディングはダンが担当した)、新たにHollyが加入したことを契機に本作の制作が始まったそうだが、彼女のプレイが楽曲に新たな彩りを加え、メランコリックな中にも躍動感と推進力をもたらしている。
彼女たちの政治・社会問題に対して意識的な姿勢にはザ・クラッシュの面影を見ることもできるが、それは音楽の面においても同様だ。前作が『White Riot(白い暴動)』だとしたら、本作はさながら『Sandinista!(サンディニスタ!)』といっても決して過大評価にはならないだろう。バンドの持つ雑食性、溢れ出るアイディアを、あくまでゴート・ガール流のポップスとしてまとめあげたダンの手腕も見事。(小倉健一)
Squid『Bright Green Field』
2021年 / Warp

先行き不透明な社会の閉塞感を描き出しながらも、自由なフィーリングに満ち溢れている本作。近年のダン・キャリー・ワークスに特徴的なことでもあるが、彼はありのままのバンド像に寄り添う。まるで最初からそこにいないかのように、あるいは「第6のメンバー」と語るほどに分かち難く親密な、共犯者としてそこにいるように。そこはかとなく感じられるどこか神経質なインテリジェンスや、リズムセクションがじわじわとグルーヴを刻んでいくスタイルはダンのシグネチャーの一つだが、まるでどちら由来の性質かわからないくらい、両者は不可分に結びついているように感じられる。
近年彼がプロデュースした一連の作品はギターロックの復権だとかジャンル間のクロスオーヴァーと結びつけて語られがちではあるが、多分ややこしいこと抜きにダン・キャリーはスクイッドと遊びたいだけだろう。精妙なアンビエンスから弦が唸るポストパンク、秩序の中に肉感が宿るクラウトロックの要素など、様々な緩と急を気ままに行き来しながら、ふとジャズのエレガンスも立ち現れて…。だがジャンルの分類など野暮と思えるような、軽やかでしなやかな遊び心が本作からは感じられるのだ。
整然としているように見えるけど何か軋んでいて、どんどん“遊び”がなくなっていく日常の中で、混沌の中に陶酔を見出す彼らの表現はますます妙なリアリティを持っているように思えてならない。でもそれはこのディストピアを生きる希望なのだと、本作は物語っている。(阿部仁知)
Kae Tempest『The Line Is a Curve』
2022年 / American

スポークン・ワード・パフォーマー、詩人、小説家、劇作家として知られるケイ・テンペスト。アルバムからのファースト・シングル「More Pressure」を聴いたとき、そのアップリフティングなビートや、いくつもの単語を並置し対比させた上でポエトリーというよりフロウ重視でラップしていく手つき、それらの軽やかなフィーリングが心地よかった。前作『The Book of Traps and Lessons』ではポエトリー色の強さやゲストを招かない自作詩集の要素の強さから、ストイックな印象が漂っていたのとは対照的である。本作では、ビートにはエレクトロポップやミニマル・ウェイヴを取り込んでいて、キャリア初期からプロデュースしてきたダン・キャリーが元々エレクトロニックに根差した作り手であったことを思い出させる。また、オープンなレコードを目指した本作は、リアン・ラ・ハヴァス、フォンテインズD.C.のグリアン・チャッテンなど、従来のアルバムと異なり積極的にゲストを招いていることが本作の風通しの良さを生んでいる。このことがサウス・ロンドンという土地の身近さを改めて感じさせるほか、ケイは、ドライ・クリーニングやフォンテインズD.C.といった近年のUK/アイルランドのスポークン・ワード、しゃべり呟くヴォーカルの潮流の先駆者という角度でも評価され、時代とシーンを象徴する存在となったのである。(髙橋翔哉)
Wet Leg『Wet Leg』
2022年 / Domino

ワイト島出身のリアン・ティーズデールとヘスター・チェンバースによるインディ・ロック・デュオによるこのデビュー作は、様々なメディアからの賞賛と共にシーンへと受け入れられた。ここにあるのは近年のダン・キャリーによる仕事の中でもかなりストレートな部類とも言えそうな、驚くほどポップなメロディーと疾駆するバンド・サウンド。つまり、彼女らの音楽は目立った新しさを持ったものではなく、むしろロックの殿堂に名を連ねる偉大なバンドたちの後ろ姿を喚び起させるものだ。この音は、あるいはそれが歓迎される状況は、懐古趣味によってなるものだろうか。それとも長きにわたるインディ・ロック劣勢というチャート上での盛衰により敷衍されたイメージが呼び込んだバックラッシュだろうか。否。そういった懐疑的な印象を持つに至ったのならば、ぜひ歌詞を読みながら、彼女たちの歌声に耳を澄ませてみて欲しい。綴られているのは喜怒哀楽と狂気をコントロールするような、あえてそのコントロールを手放すかのような、言うなれば一周回った歌詞であり、聴こえてくるのは過剰に憂いもせず、嘆くこともしない、揶揄いのニュアンスが僅かに混じった、エモーションとは少し距離を置く歌声である。それらが情報や物語に溢れ、逆に平坦にすら感じるこの世界に生きる人々を熱狂させるのは必然なのではないだろうか。そういったニュアンスを直球で伝えることを選んだキャリーの感度の高さにもまた、驚かされてしまう。ティーズデールは言う。「彼はほんと“魔法使い”なんだよね」。(高久大輝)
Honeyglaze『Honeyglaze』
2022年 / Speedy Wunderground

ヴォーカルのAnouska Sokolowのソロ・プロジェクトに始まりバンド編成となった3人組。ドラマーとして合流したYuri Shibuichiのインタビューによると、最初はYuriのベッドルーム・スタジオでアイデアを持ち寄っていたものの、ダン・キャリーと出会ってからはサウス・ロンドンにあるキャリーの練習スタジオを自由に使わせてもらい、セッションを重ねて一気にライヴ・バンドっぽいタフネスを備えていくようになったのだという。バンドがバンドっぽい演奏をするようなるプロセスをほぼ初期段階から時間をかけてサポート、という意味ではこのファーストだけが彼の仕事ではないと言えるのだろう。「アーティストが安心できる環境を作るのがすごくうまい」というのはYuriの発言だが、まだディレクションが定まっていない若手に選択肢を自由に与えていく大らかな姿勢が彼らを育て上げることとなった。その結果、歌詞を手がけるフィリピン系女性のAnouska、メロディ作りや演奏、アレンジに腐心するYuriとベースのティム・カーティス……というこのトライアングルは素直な歌を聞かせるオーセンティックなギター・バンドというスタイルに着地することとなり、ジャズやポスト・ロック系が躍動するアグレッシヴな現代のサウス・ロンドンでは少々異質な存在になったとも言える。とはいえ、間合いをうまくビートの中に取り入れたドラムや、主張し過ぎない滑らかなベースライン、それになにより柔らかな質感の歌と自らの歌と共鳴させたような繊細なギター・フレーズは、意外にも多彩な曲調を引き出しており、初期からある程度ジャズ、ブラジル音楽、AORなどの要素を持っていたエヴリシング・バット・ザ・ガールを少し思い出させるのだった。(岡村詩野)
Sinead O’Brien『Time Bend and Break The Bower』
2022年 / Chess Club Records

《The Windmill》で開催されたスポークン・ワード・ナイトでのパフォーマンスが契機となり音楽活動を本格的に開始し、ゴート・ガールのホーリーの口利きで《Speedy Wunderground》と契約。2019年にシングル「Taking On Time」をリリースという経緯からも、サウス・ロンドンのシーンに位置づけられがちだったが、このアルバムはそうした彼女のパブリック・イメージをかなぐり捨てるものだ。謎めいたリリックとソリッドなポストパンク的バンド・アンサンブルの衝突が軸になっているものの、本作ではかなり大胆に様々なプロダクションが導入されている。とりわけ「Holy Country」ではノスタルジックなアコースティック・ギターの導入から突如エレクトロクラッシュ的シンセサイザーが飛び込み、さらにラフなエレクトリック・ギターのリフが挿入され、全体としてはラスト・シャドウ・パペッツを思わせるチェンバー・ポップ的ムードさえ漂うなか、祖国アイルランドの壮大なストーリーが3分半のなかで展開。オブライエンの持つオーラと言葉の力、そしてプロダクションが拮抗するスリルに満ちている。近年もDeep Tanをはじめとした新しいアーティストが、キャリーのもとバンドの生々しいグルーヴをみるみるうちにビルドアップさせていっており、アーティストの最もピュアな部分を引き出し、作品にしていくことに彼の真骨頂があることが手に取るように分かる。(駒井憲嗣)
Foals『Life Is Yours』
2022年 / Warner, ADA

実はこの作品は最初に聴いた時はピンと来なかった。フォールズはダンサブルでありながらも憂鬱な、時に攻撃的なサウンドが独特の雰囲気を出しており、それが良さだと思っていたからだ。ギター・サウンドよりもシンセのリフが目立つ今時なダンス・ポップ・アルバムは、彼ららしさが打ち消されるような気さえしていた。
だが、今夏のフジロック・フェスティバルでこの作品の曲の演奏を観た時(筆者はコロナに罹ったため配信で鑑賞)自分の考えは間違っていたと感じた。彼らは何よりもライブで映えるバンドである。音源の再現とリアルでしか表現できない熱量のフュージョンによって、曲調が暗かろうが明るかろうが、一様に彼らはフロアを沸かせ、オーディエンスを高揚させることができる。それは特徴的なリズム、ビート、メロディ、力強く感情を込めたヴォーカルが合わさってこそのものだ。そこに何ら変わりはなかった。
曲調がこれまでと比べてポップで明るいのは、作品にその時々の感情が色濃く反映される非常に刹那的な感覚を持ったバンドの特徴をよく表しているとも言える。パンデミック下という非常に閉塞的な状況の中で彼らが求めたのは、音楽を作る喜びから生まれるポジティヴな感情、鬱屈とした雰囲気から脱するための高揚感を得るための表現だった。「人生はあなたのもの/選択はあなた自身のもの/あなたの人生が待っている」これは、明るい未来に向かうための作品である。(相澤宏子)
The Lounge Society『Tired of Liberty』
2022年 / Speedy Wunderground

2020年にダン・キャリーのプロデュースでデビュー・シングル「Generation Game」を《Speedy Wunderground》からリリースした4人組、ザ・ラウンジ・ソサエティ。当時、彼らは16歳から17歳で、レコーディングに参加するには学校の許可が必要で、ロンドンで宿泊するホテルにチェックインするときは大人が付き添ったそうだ。そのシングルはレーベル史上最速で売れた7インチとなったが、5分30秒の中にパンクやインディー・ポップ、プログレ、クレズマーなどが凝縮されており、ダンは彼ら10代特有のフラストレーションやニヒリズムを減衰させることなく、うまくまとめてみせた。きっとメンバーたちはダンを魔術師を見るように目を見張ったことだろう。
それから2年。同じく《Speedy Wunderground》から発表された本デビュー・アルバムは、マンチェスターとリーズの間にある人口4,500人の小さな街で生まれ育った4人が、ダンがプロデュースしてきた南ロンドンのバンドたちを仰ぎ見て制作されたというところにも意義を見い出せる。遠く離れたブリクストンのウィンドミルでカオスな演奏を繰り広げるバンドたちの影響が下の世代や地方にも及び始め、彼らの第二世代としてこうして登場し始めたのだ。初期アークティック・モンキーズのような性急なガレージ・ロックとジョセフKのようなアート・パンクが衝突する、青さほとばしる1枚。ダンも微笑ましく彼らの演奏を見ていたはずだ。(油納将志)
Text By Hitoshi AbeKenji KomaiShoya TakahashiNana YoshizawaIkkei KazamaKenichi OguraSuimokuhiwattttTsuyoshi KizuShino OkamuraMasashi YunoDaiki TakakuYasuyuki OnoHiroko Aizawa
関連記事
【FEATURE】
「繰り返さないこと」── スクイッドの音楽が高い実験性と爆発的なエネルギーを共存させる理由
http://turntokyo.com/features/squid/
【INTERVIEW】
「ただずっとライヴで経験を積んで人と繋がっていった」
ハニーグレイズのYuri Shibuichiが語るサウス・ロンドン、そしてダン・キャリー
http://turntokyo.com/features/honeyglaze-yuri-shibuichi-interview/
【INTERVIEW】
「本当に美しい音楽を作りたいなら自分たちはダン・キャリーを選ぶだろう」
Wet Legが語る思いもよらなかったアルバム制作とピュアなインディ・ポップ魂
http://turntokyo.com/features/wet-leg-interview/
