カリブー/ダフニ
ディスク・ガイド
〜ダン・スナイスの眩いサウンド・デザイン史〜
ポスト・ボーズ・オブ・カナダ的なIDMとしてスタートし、サイケデリック・ロック、クラウトロック、そしてUKハウスへと定着していく……。時代と地域とを越えた旅路と、その後現在の拠点でもあるロンドンのクラブ・シーンや“友人”たちとの共振。カリブー、そしてよりダンス・ミュージックに主軸をおいた別名義ダフニとして活動している、1978年、カナダはオンタリオ州ダンダス生まれの音楽家、ダン・スナイスの音楽をひとことで言い表すのは非常に難しい。
カリブーまたはダフニのSpotifyアーティスト・ページで公開されている1000曲以上24時間超えのプレイリストを、あなたは目にしたことがあるだろうか。そこへ雑多に収められたジャンルも時代もばらばらの楽曲群は、DJとしての感覚を垣間見せているというのは確かにそうだが、彼自身が同時にとても良きリスナーであることが感じ取れる。
自身のゆたかなリスナー体験を結晶化させたような作品たちを、どのように聴くのか。またどの作品から聴いたのか。それによってあなたが、音楽においてリズム、メロディー、それともサウンドのテクスチャなのか、どのような部分に注意を払っているのかがわかってしまうかもしれない。実際に彼のディスコグラフィーを何から聴いたかによって、彼の音楽に対するイメージとか思い入れも百人百様の広がりがあるように思う。
これはダフニ名義としての新作『Cherry』のリリースを機に、ダン・スナイスの音楽がもつ不定形で奥深い魅力、その正体にあらためて迫るためのディスク・ガイドである。本記事ではカリブーの前身であるマニトバや、ダフニ名義の作品ももちろん網羅しているため、楽しみながらあなただけのダン・スナイス像を描きだしてみてほしい。(編集部)
(ディスク・ガイド原稿/岡村詩野、加藤孔紀、木津毅、駒井憲嗣、佐藤遥、高久大輝、髙橋翔哉、吉澤奈々)
Manitoba『Start Breaking My Heart』
2001年 / The Leaf Label

90年代のオウテカやエイフェックス・ツイン、ボーズ・オブ・カナダを通過したサウンドであり、2000年代に台頭したエレクトロニカ、例えばレイ・ハラカミとの近似性が感じられる。けれど、今、本作を再生すると、とりわけハープやトランペットなどの管楽器、そしてエレクトリック・ピアノなどの(おそらくはサンプリングされた)フレーズやハーモニーが際立って聞こえてくる。電子音楽とスピリチュアル・ジャズを交差させていて、ともすればフライング・ロータスの『Cosmogramma』(2010年)やMoor Mother『Jazz Codes』(2022年)に先駆けた作品のようにすら思える。この実験の痕跡は、特に「Paul’s Birthday」で顕著だ。果敢にジャンルを横断したサウンドの大半は、PCとAcid v1.0やSound Forgeといったソフト・ウェアで制作されたという。そして、そこに投影されたのは、彼の目から見た風景。日常を切り取ったようなアートワーク、そして自身の出身地「Dundas, Ontario」や特定の知人について言及するような「Jame’s Second Haircut」などが曲名になっている。まるで半径50メートルほどを描いたこの自作自演には歌こそないものの、2010年代のベッドルーム・ポップが自室から描写した親密さへと繋がるものも感じるのだ。訴訟によって名前を変更する前の、マニトバ名義でのプライベートで実験的なファースト・アルバム。(加藤孔紀)
Manitoba『Up in Flames』
2003年 / The Leaf Label, Domino

突如サイケデリックなポップへと向かい驚きを持って受け止められた今作についてダン・スナイスは、イサカなど当時掘っていた60~70年代のレコードがレファレンスであると明かしている。めくるめく白昼夢のようなムードゆえ、マイ・ブラディ・バレンタインやマーキュリー・レヴが引き合いに出されてきたが、『Cherry』の多幸感を堪能した耳であらためて聴くと、彼のサンプリングに対する野心がしっかりと刻まれていることを再確認する。映画『Fantastic Planet』(1973年)からの引用がファンタジックなムードを花開かせる「Every Time She Turns ‘Round It’s Her Birthday」、テキサス産サイケ・バンド、バブル・パピーの曲をまるごと使いし柔らかな木漏れ日と陶酔を描き出す「Skunks」と、“しょぼい”PCとビギナー向けのシーケンサー・ソフト、Acid v1.0を用い、いかに秀逸なループを作れるか、ブレイクビーツの可能性を追求していたことが伺える。一方、その頃のステージでは、ちょうどコーネリアスがそうしていたように、ステージに投影する映像にクリックのトラックを加え、再生するDVDに合わせてサンプリングを楽器に変換し演奏するスタイルでアニマル・コレクティヴらと対バンしていたというのも、スナイスのクリエイティビティが環境そしてテクノロジーと密接に関わっていることが伺い知れる逸話だ。(駒井憲嗣)
Caribou『The Milk of Human Kindness』
2005年 / The Leaf Label, Domino

前作であり至高のサイケデリック絵巻『Up in Flames』のあたたかくもセンチメンタルなサウンドを、さらにリズムに重点をおく形で推し進めたのがこの『The Milk of Human Kindness』。特に60、70年代のクラウトロック〜サイケデリック・ロックを中心としたモータリックなビートの影響が印象的である。「A Final Warning」のノイ!や「Brahminy Kite」のシルヴァー・アップルス、ほかにも初期クラフトワークなど、ここまで具体的なリファレンスがサウンドから連想できる作品も少ないのでは。しかしただノスタルジックな作品というわけではなく、あくまでステレオラブを通過した2000年代ならではの参照であるように伺える。「Hello Hammerheads」のように当時コリーンやハンネ・ヒュッケルバーグもかかえていた《The Leaf Label》的なフォークと結合したような楽曲が多数収められているのが興味深い。また“Leaf”つながりでいえば「Leaf House」が収録された『Sung Tongs』期のアニマル・コレクティヴとの共振もみてとれる。初期はなにかと作品ごとの方向転換がいちじるしいダン・スナイスだが、案外それぞれの時代に応じた適応と、良きリスナーとしての感性をぞんぶんに発揮しているだけなのかもしれない。(髙橋翔哉)
Caribou『Andorra』
2007年 / City Slang, Merge

倍音を重層させ、サイケデリックな反響の空間を拡げる『Andorra』。《The Leaf Label》から《City Slang》にレーベル移籍後となる本作では「60年代の音楽を作り出したかった」とダン・スナイスが語っているようにソフト〜サイケデリック・ロックの影響を強く反映している。だが、はじめて自らのヴォーカルを全曲に取り入れる試みにより、緻密なメロディーの振動とピッチの配置を実現したのだろう。カナダの音楽賞ポラリス・ミュージック・プライズを受賞したパーソナルな作品でありつつ、実験音楽とも呼べる快作だ。
緩やかなヴォーカルのビブラートとシンバル音が交錯する「Melody Day」から、初期のアニマル・コレクティヴを連想させる毒っけのあるサイケ・ポップ「Desiree」など、フォーキーで目の眩むような明るい音色が特徴。しかし、後半の「Sundialing」からラストの「Niobe」にかけて、歌声は小さくなりドラムと電子音のビートが厚みを加速していく。それまでの、ぼやけていたノイズはクリアになり近づけてくるようだ。その偶発的な様は、まるで夢から現実に戻る視覚と聴覚の意識に近いようにも思えた。『Andorra』は、旋律線の絡み合う構築を、一歩引いたところから俯瞰して見渡すような視覚的錯覚に陥る。と同時に、一瞬の儚いメランコリーと隣り合わせの、音楽は時間芸術ということを思い出させてくれるだろう。(吉澤奈々)
Caribou『Swim』
2010年 / City Slang, Merge

IDMからクラウトロック、サイケ・ポップと来て、ダンス・ミュージックへ。初~中期のダン・スナイスの変遷はじつに大胆だったが、なかでも本作は明確にターニング・ポイントでありエポック・メイキングだった。よりダンス・ミュージックを意識したダフニ名義があるとはいえ、マニトバやカリブーでこれまでやって来たことを踏まえつつハウス、ミニマル・テクノからの影響を露にし、アーティスト・イメージすら大胆に更新したのだ。なんでも当時ブリアルやピアソン・サウンドの登場に刺激を受けたとのことだが、時代を動かしていたベース・ミュージックに引っ張られることなく、どこかストイックかつ実験主義的にダンス・サウンドに取り組んでいる。同年リリースでもっとも近い作品はフォー・テットの『There Is Love in You』だろう。あるいは、『Swim』とのタイトルからひとに真っ先に想起させたのはアーサー・ラッセルの「Let’s Go Swimming」で、要は音響の工夫こそが聴きどころのアルバムだったのである。水中で遊んでいるときのように、音が揺れ、回っている。
オープニングの大名曲「Odessa」に始まりめくるめくダンス・サウンドが展開されるなか、組曲的な「Hannibal」に顕著だがオーケストラル・ポップのアプローチが入っているのも面白い。構築的な楽曲の上でスナイスの線の細い歌声が乗るミスマッチ感もあり、結果としてクラブ・ミュージックとインディの中間を射抜き、ダンスフロアの汗とベッドルームの夢を備えた作品に仕上がっている。その両方の輝きを生み出せるのがダン・スナイスという音楽家だ。(木津毅)
Daphni『Jiaolong』
2012年 / Merge
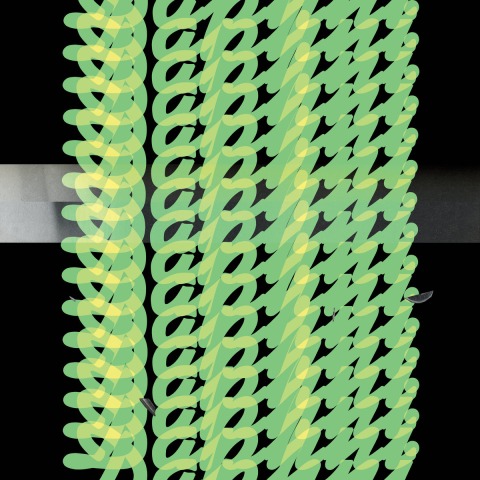
2000年代末からフローティング・ポインツやジョイ・オービソンなどが登場しポスト・ダブステップの興隆によってエキサイティングな場所へと様変わりしたロンドンのクラブ・シーン、その場に居合わせていなくとも当時の熱量をそのままパッケージングしたと思えるほどのエネルギーとリアリティがこの作品には詰まっている。クラブ・シーンから受けた影響が初めて落とし込まれたのは『Swim』であったがそれだけに収まらず、DJを活発に行いながらダフニとして12インチで作品を発表し、それらと新曲を合わせてハウスを軸にまとめたのが本作だ。「Ne Noya」や「Jiao」のシンセにはライヴ感があり「Springs」にはインプロっぽさがあるが、その聴こえ方の通りモジュラーシンセを即興的に演奏し、会場へ移動する前の短時間でつくられている楽曲が多いという。「Ne Noya」のほかにも「Paris」からはグローバルな音楽が再発見というかたちでリイシューされたり楽曲に取り入れられたりした当時の空気がよくわかる。「Aroha」と「Long」にはカリブーらしいメロディアスな部分もあり、興味を惹かれる方へ向かいながら柔軟に活動を続けることを大いに楽しんでいたことが伝わってくるだろう。コラボの相手はツアーで共演した人や親友を選ぶことからもわかる、彼のいい意味で狙わない自然体の活動ゆえのアルバムと言えるだろう。(佐藤遥)
Caribou『Our Love』
2014年 / City Slang, Merge

ダン・スナイスのキャリアのうち、もっとも親密でもっともロマンチック。彼はカリブーの活動で「できるだけ自分の人生を捉えようとしている」と話していて、本作では、『Swim』の反響をきっかけに自分の興味関心だけではなく他者も意識した寛大なレコードをつくろうと思ったこと、そして、子どもが誕生したことが大きく関係しているようだ。これらを結んだ焦点に「愛」が立ち上がるのには合点がいくだろう。
たとえば、ゆったりと展開するハーモニーやプツっと途切れるボーカルサンプルが印象的な、好意のすれ違いを歌う「Silver」、静かにリズムを刻むコンガやきらめくオブリガート、徐々に厚くなるシンセとともに関係の修復について歌う「Back Home」、どちらも恋人についての曲と受け取ることもできるが、パートナーや友人、家族などについての曲でもある。各人のさまざまな関係で生じる愛と音のレイヤーを重ね合わせ、立体的な像(=Our Love)が結ばれていく。愛についてのロマンチックな曲というと、いささか単純な綺麗事だと思ってしまわなくもないが、こうしてかたちづくられた像はそう言わせない複雑さも、ひねくれた見解を包み込む寛容さも持ち合わせている。ほぼアルバム全編にわたってあたたかみのある音や声で甘くて切ないメロディーとハーモニーをつむぐ姿勢を崩さなかったからこその結実。とすると、彼の音楽の魅力はその実直さにあるのかもしれない。(佐藤遥)
Daphni『Joli Mai』
2017年 / Jiaolong(Self-released)

このアルバムと連動して語らねばならない作品が本作の僅か3ヶ月ほど前にリリースされている。《Fabric》のミックス・シリーズとして同年7月21日に発表された『Fabriclive 93』。ダフニのオリジナル未発表曲23曲に新曲4曲……それもダフニによるニュー・エディットによるもので、要は自身の曲だけで構成された立派なオリジナル・アルバムの一つとしてカウントしてもいい内容だ。そのミックスCDのために作ったトラックをほぼフル尺で収録しているのが本作。つまり『Fabriclive 93』のキネティックかつ催眠的なタッチが底辺で確実に継続しているため、たとえば「Life’s What You Make It」のようにメランコリックなメロディの曲はとりわけ地続きであるように聞こえるだろう。一方で『Fabriclive 93』にも収録されていた「Face To Face」や先行曲「Hey Drum」「The Truth」のように機能的なエレクトロに着地させた曲が要所要所で作品に強度を与えているのも聴きどころ。マニトバ時代からダン・スナイスの作品は直線的・狭窄的なシャープネスと、流線的・広角的な柔らかさが共存することが多く、その共存がもたらす時空の歪みはしばしばトランシーでサイケデリックな聴後感となって我々リスナーにフロアライクな音楽以上の想像力を求めてきた。今思えばそれこそがメロディアスなポップ・ミュージック……ひいてはシューゲイザーやドリーム・ポップの一端を遺伝子に持つ側面と、ダブステップやミニマル・テクノにも足を伸ばそうとする側面とに引っ張られ合っても、なお美しくあろうとするこの人の立脚点なのだろうと思う。(岡村詩野)
Daphni『Sizzling EP』
2019年 / Jiaolong(Self-released)
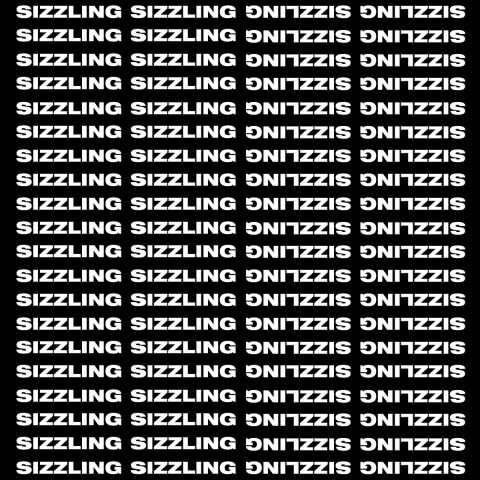
ダン・スナイスのキャリアを振り返るうえで見過ごしてはならない作品がこの『Sizzling EP』である。無名のファンク・グループParadiseの楽曲を大々的にサンプリングしたエレクトロディスコな表題曲をはじめ、カリブー『Swim』以降のUKハウス路線と比較してきわめて異色といえるEP。表題曲のジャスティスを彷彿とさせるつんのめったディスコ・ビート、「If」の蹴りつけ叩きつけるようなキックとピアノなど、以前の作品にみられたドリーミーな“陶酔感”からは想像もつかないほどマッシヴで暴力的な作品である。音が耳に近くて、そしてやかましい。リズムのズレを強調したグルーヴは、汗のたぎる引きつったダンスに身体を誘う。小節を8分で刻む歪んだベースが印象強い「Romeo」の、リップス・インク「Funky Town」と電気グルーヴ「Shangri-La」(と元ネタのシルヴェッティ「Spring Rain」)をあわせたようなストリングスのメロディーは、キャッチーさをとおり越したその大味さにとても笑える。これらの極端さはEPならではの自由な実験と、自身が積み上げてきたスタイルと期待からの解放である。しかしここで手に入れた大胆なサンプリング感覚などはその後の『Suddenly』、『Cherry』でも活かされており、本作が単なる“寄り道”でないことを裏づけている。(髙橋翔哉)
Caribou『Suddenly』
2020年 / City Slang, Merge

意味を置き去りした荒々しいラップのサンプルが「Sunny’s Time」から聞こえたときの驚きを今でもはっきり覚えている。しかし、それだけではない。この『Suddenly』には、ジャジーなハウスが突如切り替わる「Lime」や、ギター・フレーズが蛇行する「Like I Loved You」など、様々なアイデアが所狭しと詰め込まれている。さらに驚くべきは、明らかに不自然な展開や不協和音、細部まで作り込まれた豊かなシンセの響きまで、もっと言うとハウス、ディスコ、フォークなど多様なジャンルをダン・スナイスは滑らかに繋いでいるということだ。全体に優しさの膜が張っているかのような心地よさ。世界的なパンデミックとほぼ同時期にリリースされたことはおそらく偶然ではあるが、必然にすら感じる“癒し”を内包したサウンド。制作面では参加した友人のKieran Hebden、つまりフォー・テットの力添えも大きいのであろうが、本作に受けるそういった印象は直接的にはダン自身の柔らかなファルセット・ヴォーカルに支えられたものだろう。それに本作では声を楽器のように扱う一方で、具体的な歌詞も目立つ。中でも意味深いのは2014年に急逝してしまった、サウンド・エンジニアとしてダンと共に働いたトランス女性、Julia Brightly(ちなみにCaribou名義の前作にはその名を冠した曲がある)へと捧げられた「Magpie」だ。ジェンダーに関する問題に対しての世界の変容を振り返り、それでもまだ変わらなければならないと歌うダンはやはり優しく、そして強い。(高久大輝)
Daphni『Cherry』
2022年 / Jiaolong(Self-released)

ダフニのアルバムとしては5年ぶりとなる本作。光の粒のグリッチ・ノイズが不規則に飛び交う「Cherry」やピッチの微妙に上がったジャズ・ピアノが流麗に揺れすすむ「Cloudy」など、ここにおさめられた楽曲には“繊細”とか“静謐”という表現がよく似合う。こういったテクスチャや音の位相と配置を強く意識させるサウンド・デザインは、カリブー名義の前作『Suddenly』から引き継がれたものでもある。ひとつの楽曲に多くのアイディアがこれでもかと詰めこまれた『Suddenly』はその転換の違和感に快楽性を見いだしていたが、対照的に『Cherry』は楽曲ごとにひとつのアイディアを深く掘りさげ展開することで、直感や発想のよろこびを聴き手に共有する。いずれの楽曲も非常にシンプルで、かつこれまでのダフニ名義の作品にくらべてメロディーやエモーションがそぎ落とされたように感じるのも、アイディアそのものへの快楽が先行しているためだろう。
ちなみにダフニの3枚のアルバムは5年周期で、律儀にもすべて10月初旬に発表されている。偶然なのか、それとも10年前からの大いなる計画の一部なのか。「Cherry」でビートのたった1秒の静止が無限の渇望を生みだすように、「Always There」でサックス・ソロが時間をかけて電子の群れに呑まれていくように。ダン・スナイスはダンス・ミュージックやDJが時間芸術であることを証明する。個人の瞑想と想像力は思いもよらない可能性の広がりを秘めていることをほのめかしながら。(髙橋翔哉)
Text By Haruka SatoKenji KomaiShoya TakahashiNana YoshizawaTsuyoshi KizuShino OkamuraDaiki TakakuKoki Kato
