「自由なソングライティングと凝ったアレンジ、その良いバランスを見つけ出したいと思っている」
グリズリー・ベアのダニエル・ロッセン
積み上げた創造性の成果を語る
ダニエル・ロッセンはグリズリー・ベアの“頭脳”と呼ばれることが多い。CANTなどでソロ活動をしたり、《Terrible Records》を運営しプロデューサーとしても活躍するクリス・テイラー、2年前にFools名義でミックステープのようなソロ・ワーク作を出したりリミックスも手がけるクリストファー・ベア、そして何と言っても、現在はバンドと少し距離を置いているものの(完全な脱退ではないそうだ)グリズリー・ベアを最初にソロ・ユニットとしてスタートさせたエド・ドロスト……と個性派揃い、曲者揃いのメンバーの中にあって、今年40歳を迎えるダニエルは確かにこれまで実直にグリズリー・ベアに向き合ってきた……そんな印象がある。
『All The King’s Men』や『The Hustler』といった作品で知られる映画監督、ロバート・ロッセンの孫という血筋を持つダニエルは、もちろん、大学生の頃からデパートメント・オブ・イーグルスとして活動してきたキャリアの持ち主だ。しかし、セカンド・アルバム『Yellow House』(2006年)でグリズリー・ベアに加入してからというもの、1人の音楽家として作品ごとに次々と磨きをかけていくようになっていった。それはヴォーカリストとしてであり、ギタリストとしてであり、ソングライターとしてであり……全米8位を獲得した3作目『Veckatimest』(2009年)を起点とするグリズリー・ベアのブレイクを支える一方で、彼自身がメンバーの誰より寡黙にミュージシャンシップを高めていっていたと言ってもいいかもしれない。ソロなど課外活動をする必要がないほどにダニエルはグリズリー・ベアであってきた……ゆえに“頭脳”と呼ばれるようになったのだろう。
それだけに、そんなダニエル・ロッセンが、これまでEPなどはあっても初のソロ・アルバムをリリースすると聞いた時は、ようやく機が熟したのだろうと素直に嬉しくなった。自身「唯一自信を持って演奏できる楽器」というギターを筆頭に、数々の楽器をこなす彼は、“頭脳”である一方で“肉体”でもある。ここに届けられたファースト・ソロ『You Belong There』でもチェロやコントラバスなども含め実に多くの楽器を自ら操っていて、グリズリー・ベアの一員として実直に寡黙に音楽家としてのスキルアップに向き合ってきた彼のその“成果”が感じられたりもするだろう。
そして、ソングライティングや歌い手としての層の厚み、表現力のほどは、ティム・バックリィ、ビル・フリーゼル、クラウス・ノミ、ギャビン・ブライヤーズ、フランシス・レイ、エンニオ・モリコーネ、スペインのカタルーニャ地方の民謡、米南部のゴスペル、MPB時代のカエターノ・ヴェローゾ、サンダーキャットやクリス・デイヴら現代のアブストラクトなジャズ……様々なアーティストやエレメンツが浮かんでくるほど。けれど、本作はそれでもどうしようもなく美しいヴォーカル・アルバムだ。頭脳・肉体を鍛えてきた経験が、決して大仰に背伸びすることなく、歌、旋律、演奏にナチュラルに結実している。ノア・ジョージソンやピーター・ラーキンがミックスで参加しているほか、グリズリー・ベアの盟友であるクリストファー・ベア、ディアフーフのジョン・ディーテリヒ、アンバー・ワイマン、そして、驚くことにニュートラル・ミルク・ホテル/ア・ホーク・アンド・ア・ハックソーのジェレミー・バーンズの名前もクレジットにはあるが、彼らはみな、現在はサンタフェに暮らすダニエルの周辺に自然に集まった仲間たちだ。
クレジットに刻まれた「I love you Amelia I love you Alice」。この2人は彼の妻と娘の名前だという(このページの写真も妻のアメリアが撮影)。これはそういうアルバムなのだ。
(インタビュー・文/岡村詩野 通訳/原口美穂)
Interview with Daniel Rossen
──今、あなたはブルックリン界隈を離れ、サンタフェに拠点を移しているそうですね。
Daniel Rossen(以下、D):そうなんだ。2013年に僕のパートナーと一緒にブルックリンを出て、しばらくはNYのアップステートに住んでいた。すごく田舎で、周りに何もないところ。その後、彼女の出身がサンタフェなんだけど、彼女の家族もそこにいるってことでサンタフェに引っ越してきたんだ。すごく綺麗なところで、僕も前から気に入っていたし。ブルックリンを出た理由は、あの時はなんかニューヨークに住むことに疲れてしまっていたんだよね。レストランにいったりするのも飽きてしまって。同じことの繰り返しみたいなのもよくないなと思ってさ。それで、どこかで違う生活をしてみることにしたんだ。一度出ると、もう戻れないよ(笑)。
──2012年に最初のEP『Silent Hour/Golden Mile』が届いてからこのファースト・アルバムを心待ちにしていました。あのEPのリリース後、すぐにでもソロ・アルバムが届くのかな?と思っていたら、先にグリズリー・ベアのアルバム『Painted Ruins』が届きました。この順番の流れ、いきさつなどをおしえてもらえますか? ソロ・アルバムの作業に入っていた中、グリズリー・ベアの新作作業が始まってしまった、などなど、どういう順序の流れがあったのでしょうか? また、2018年にはレコード・ストア・デイに12インチ・シングル『Deerslayer』をリリースしていますよね。
D:EPを制作していた時は、同時にグリズリーの『Shields』(2012年)も制作していたんだ。だから、あの二つの作品のマテリアルは同じところから来ている。そして、あの作品がリリースされた後は、数年間ちょっとレコーディングから離れていたんだ。2017年に『Painted Ruins』がリリースされたけど、僕は正直あのアルバムにはそこまで関わっていない。その数年間は、なぜかあまり音楽活動に対してそこまで意欲がわかなくて。今振り返ると、何年か無駄にしてしまったかなと少し後悔もしている。田舎に住んでいて、外の世界で何が起こっているのかをあまり理解てきていなかったんだよね(笑)。時間の感覚がなくなるというか。2014年から2018の間は……ぼーっとしていた。まあ、それはそれでよかったんだけど。でも娘が生まれたことで、また違ったモチベーションが出て来たんだ。自分の人生の一部を表現したくなった、って感じかな。音楽から少し離れてかなり時間が経っていたし。『Deerslayer』は、どのレコードにも収録したいと思わなかったから、あの曲単体でリリースすることにしたんだ。B面は、僕の昔のバンド、Department of Eaglesのバンドメイトの曲。あの12インチは、シンプルにスタジオで楽しい時間を過ごしたくて、それが形になったものだね。真剣に曲を作りたかったというよりは、何かナイスなことをしたくて出来上がった作品なんだ。
──EP『Silent Hour/Golden Mile』はグリズリー・ベアの『Shields』と同じ年にリリースされていたので、最初はどうしてもグリズリー・ベアとの接続性を感じていました。ですが、それ以前から独学でドラムやチェロ、コントラバスを習ったりもしていたそうで、あなたが一人で全ての演奏や創作作業の工程をこなすような流れができていたのだろうと思います。こうしたソロ・ワークへの流れは、そもそもあなたにとってどういうモティヴェイションがきっかけとなったものなのでしょうか?
D:アルバムができるまでに時間はかかったけど、曲はずっと書いていたんだ。今は3歳の娘もいるから、子育てとの両立もあってね。ソロ・ワークへのモチベーションは常にあったんだけど、時間がなかっただけ。で、最近になってバンドの他のメンバーもそれぞれ他のプロジェクトの活動で忙しくなっていたし、ソロ活動に時間をかけれるようになって、アルバムを完成させることが出来たんだ。一人で全ての演奏をやっているのは、それしか方法がなかったから(笑)自分ができることをやっていくうちに、自然に方向性が定まっていった感じだね。
──チェロやコントラバスはもちろん、今作にも使用されている管楽器も含めクラシック音楽の分野の楽器類への改めてのアプローチが一つのきっかけになっているようにも感じます。
D:ああ、そうだね。でも、ギターだけは昔習っていたけど、あとは殆ど独学。今回は少しゲスト・プレイヤーにも参加してもらってはいるけど、木管楽器やストリングは自分で演奏してる。チェロは演奏し始めて結構経つんだけど、未だにマスターできてる感じはしないね(笑)。自分でもまだちゃんと弾けてるかはわからない。だから、本当は他のミュージシャンに頼むことも出来たんだけど、パンデミックでそれができなかった。だから、自分で演奏しなければいけなくてさ。自分で手に取れる楽器を使って、出来ることをやってみた結果がこのアルバムなんだ。
──あなた自身はもともとクラシック音楽やジャズのマナー、演奏技法や作曲方法などを学んでいたそうですし、グリズリー・ベアにそうした要素を持ち込んでいたのはまさしくあなただったわけですが、それでも改めて様々な楽器演奏に向き合うことで、どういったことに気づいたり、発見があったりしましたか?
D:木管楽器を手にしたのはかなり久しぶりだったから、今回は学ぶべきことがたくさんあったと思う。あとは新しく安いアップライトベースを買ったから、運弓法も今回新たに勉強した。ニュー・アルバムの制作のためにそれらを学んことで、前よりはスキルアップしたんじゃないかと自分では感じているよ。アルバム制作は、管弦楽編成の知識を広げるのにすごく良い機会だったと思う。
──今、そもそもあなたはどのくらいの種類の楽器演奏ができるのでしょうか? 今回のアルバムでもギターはもちろん、チェロ、ピアノ、アップライトベース、シンセなどを自ら演奏していますね? あなたのプレイヤーとしての圧倒的な技術をみせつけるギター以外だと、どの楽器が最も得意だったり、表現しやすかったりしますか?
D:いやあ、自信を持って演奏できるのはたった一つ、ギターだけ(笑)。でも一応演奏できるのは、ピアノ、ベース、今回のレコードでは叩いていないけどドラム、チェロ、アップライトベース、木管楽器、クラリネット。でもそれらを演奏出来ますと公言するのは気が引ける。音楽セオリーも含め、全てが独学だからね。ギター以外に得意だと思う楽器は…ないな(笑)。今回殆どを自分で演奏したのも、状況的に仕方なかったからだし。次回は是非とも他のプレイヤーたちに参加してもらいたいと思ってる。ちゃんと自分のプレイに自信が持てているミュージシャンたちにね(笑)。僕はアレンジ担当、とういうことで(笑)。
──これからトライしたい楽器はありますか?
D:どうかな……。今回も、トライしたかったというよりは、自分が持っている楽器を集めて使ったんだ。だから、高校の吹奏楽部が使う楽器、みたいなセレクションだった。オールドスクールなアコースティックの楽器。でもそれはそれでナイスだったと思う。
──2020年以降はコロナと昨今のオミクロン……ロックダウンやパンデミックへの対応などで作業もいろいろと滞りがちだったかと思いますが、コロナの影響は具体的にどのように受けたと言えますか? また、今回のあなたのソロ作品の方向性、ヴィジョンにそれらの影響はあったのでしょうか?
D:アルバムを制作するにあたって、今回はたまたまスペースとモチベーションとマテリアルが同時にあった。それは多分コロナの影響ではなく、偶然だったと思うんだよね。でも、レコードの作り方にはもちろんコロナは影響したと思う。自分自身で殆ど作業しないといけなかったのは、パンデミックが理由だったから。方向性やヴィジョンに関しては、わからない。でも、もしかしたら影響したのかもしれないね。一つ言えるのは、今回アルバムを作ってみて、余計に他のミュージシャンとコラボレーションがしたいという思いが強くなったこと。次回作品を作る時は、今回とは違う内容にしたいと思ってるんだ。でもまあ、それを計画するのも簡単ではないし、どうなるかわからないけど。
──アルバムのほとんどはサンタフェのあなたの自宅で録音されたとのことですが、その自宅の録音環境、機材やしつらえなど、どのようなものなのかおしえてもらえますか?
D:元々は建築事務所だった場所を改築して出来たスタジオなんだ(笑)。だから未だに本棚とかファイルなんかが残ってるし、色々なものが詰め込まれてすごく散らかってる(笑)。僕の奥さんはアーティストなんだけど、彼女の作品やそれ用の箱なんかも置いてあるし、そこに僕のピアノやドラムキット、ベース、その他楽器も置いてあってさ。とにかくゴチャゴチャ。僕はその環境で作業してるんだ(笑)。使っている機材は本当に普通のもので、小さなレコーディングのセッティングがあるだけ。特別でも希少な機材でも全くない。スペースを占領しているのは主に楽器だね。機材に関しては、すごくミニマルなんだ。
──LAの《Valentine Studio》でマイケル・ハリスと追加で録音したようですが、具体的に《Valentine》で収録したのはどういう部分だったのでしょうか?
D:全てのドラム。クリス・ベアと僕は同じ都市に住んでいないから、彼のパートを全部《Valentine》でレコーディングしたんだ。その後は、ヴォーカルをレコーディングした。それから、少しだけど他のミュージシャンにバスーン(ファゴット)を演奏してもらって、それも録音した。彼女の名前はクレジットにはのってないけど。主にレコーディングしたのはドラムとボーカルだね。
──基本はあなた自身のプロデュースですが、ノア・ジョージソンやピーター・ラーキンがミックスで参加しているほか、グリズリー・ベアの盟友であるクリス・ベア、ディアフーフのジョン・ディーテリヒ、アンバー・ワイマン、そして、驚くことにニュートラル・ミルク・ホテル/ア・ホーク・アンド・ア・ハックソーのジェレミー・バーンズも演奏で参加しています。あなたが一人で全てを作ることも可能だった中、こうした仲間たちに声をかけたのは、それぞれのゲストに対し、どういうイメージがあったからなのでしょうか?
D:本当はもっと他のゲストに参加して欲しかったんだけど、さっきも話したように、状況的に一人で作業するしかなかったんだ。でもやはり他の人に協力してもらったのは、”これで十分”というのが自分で判断するのがすごく難しかったから(笑)。ノアにはレコード全体をミックスしてもらう予定だったんだけど、スケジュールとか色々あってピーターにもミックスをお願いした。ピーターはサンタフェに住んでいるからね。ミュージシャンに関しては、クリス・ベアはもちろんバンド・メイトだし、ジョン・ディーテリヒは友人なんだ。ジョンは制作当時ニューメキシコに住んでいたからお願いした。彼はタイトル・トラックでエレキを演奏してくれていて、曲の形を定めるのを手伝ってくれたよ。ジェレミー・バーンズも友人でニューメキシコにいるし、リスペクトしているからお願いした。彼は一曲でハンマー・ダルシマーを演奏してくれている。アンバー・ワイマンはマイク・ハリスが紹介してくれたんだけど、彼女も素晴らしいミュージシャンで、スタジオにきていくつか既に書かれていたパートを演奏してくれたんだ。

──「You Belong There」というタイトルが意味する世界、あなたがこの作品にこめた思いを非常に抽象的な表現ながらそこに感じることができます。このタイトル曲の歌詞を含め、今作であなたがリリックに与えた意志、思想などはどういうものだったのでしょうか?
D:曲の「You Belong There」の内容は距離について。その曲だけでなく、アルバム全体で自分が置かれている立場や場所、そこからの移動や転移について書かれていると思う。自分が属する場所から離れることの難しさとか。タイトル曲の「You Belong There」は僕が10代の時に弾いたピアノの音源をベースに作られたもので、それをずっと前に引きずりだしてきて、そこから作業を始めたんだ。そこから更に何年も放って置いたんだけど、数年前にまたそこにスコアを乗せ、ジョン・ディーテリヒのギターを乗せて完成した。あの曲は長い時間をかけて出来上がった作品だから、様々な側面を持っている。即興っぽくもあり、同時に沢山手をかけて作られた作品でもあり、17歳から40歳までの自分が詰まったトラックで、僕にとってはある意味すごく意味のあるトラックなんだ。なんか、自分のいる場所、宿命が映し出されているような感覚があるんだよね。このアルバムはコンセプト・レコードではないけど、“You Belong There”をそのままアルバム・タイトルにしたのは、アルバム全体で場所や宿命、一つのから抜け出せなくなる状態、一つの場所に属している状況が表現されているような気がしたから。このアルバムでは、僕がニューヨーク州の田舎で過ごした時間や自分の故郷、その場所との繋がり、そこから離れた経験。今は戻れないその場所と今の自分の置かれた状況が照らし合わされているんだ。
──「Shadow in the Fame」もとても示唆的な歌詞ですね。人類の消滅、衰退を連想させる内容で、資本主義社会の崩壊を前提としたリリックのようにも読めます。これはあなたがブルックリンを離れたり、一人で様々な楽器を演奏するようになったりしたことと関係があると言えますか? こうした思想の背後にあるあなたの考えを聞かせてください。
D:この曲もある特定のこと一つだけに関して歌われたものではないけれど、この曲は、僕の娘が生まれる直前に書かれた作品。直接そのことについて書かれているわけではないけれど、その時に思いついたメロディと歌詞が「Shadow in the Fame」になったんだ。誰かのことを愛することはわかっているけどその誰かのことをまだ知らない不安というか、そのフィーリングは僕にとってはある意味恐怖でもあった。あと40歳になるところだったから、体力的にもなんか心配で(笑)。でもその曲は、娘が赤ん坊の時に歌詞はなしでコード進行を彼女にむけて演奏していたんだ。子守唄と超ヘヴィーな曲の中間、みたいな(笑)。誰かと繋がりその人を愛することへの不安は、この曲で表現されていることの一つだと思う。
──2020年にあなたは大統領選挙投票者登録のためのライブストリーム・コンサート『Vote Ready』を開催していますね、私もアーカイヴを観ましたが、こうした行動と今回のアルバムのリリックの方向性にも合流ポイントがあるように思えます。『Vote Ready』を企画した後、何か心境面で変化はありましたか?
D:ああ、あのパフォーマンスで演奏した曲がアルバムに収録されているし、あの場で曲をパフォーマンス出来たことで、曲の形を固めることは出来たから、それは良かったと思う。アルバムというよりは、あの曲を完成させるのに良い影響を与えた、という方が的確かな。
──そうしたリリックにおける明確なテーマがある一方で、サウンド面は、美しく力強く、混沌としてはいるものの情熱的で人間の強さのようなものを様々な音のアングルから伝えようとしているように感じます。曲ごとの音のイメージ、アレンジ、リズムやテンポ、使用楽器などはどのように決めていったのでしょうか?
D:覚えてないなあ(苦笑)。頭にあったのは、ロック・レコードは作りたくない、ということだけだった。まあ、周りにエレクトロ系の楽器がなかったというのもあったけど、それだけじゃなく、アコースティックの方向で進めていきたいというのは考えていたんだ。オールドファッションのアレンジ、オールドファッションの楽器を取り入れつつ、自分にとっては新しいことを何かやってみる、というのが最初の目標だったかな。結果的にそれとは少し違うものになったかな、とは思うけど。ジャズやクラシックのアレンジメントを学んだというバックグラウンドもあったから、それを今回のレコードでもう少し広げてみたかったんだ。
──ストリングスや管楽器の使い方も絶妙ですが、あなたのギタリストとしての矜持と、それらオーケストラルなアレンジとかしっかりシンクロしていて、独自の仕上がりになっています。アレンジ、演奏面で、参考にした作品、アーティストなどがいたらおしえてください。
D:アルバムを聴けばその影響が一聴瞭然だと思うけど、アルバムを作っていた時は、ブラジリアン・ミュージックを沢山聴いていたんだ。特にバーデン・パウエルのレコードとエグベルト・ジスモンチの『水とワイン』。『水とワイン』はものすごく美しく、そして奇妙なレコードで、アルバムを作り始めた時は何度も聴いていたね。Spotifyでは聴けないんだけどYouTubeでは聴ける(笑)。良い音楽でSpotifyにないものってたくさんあるんだよね(笑)。
──あなたが今作でやろうとした方向性は、ポップ・ミュージックのフォルムを解体、再構築する作業であり、一方でそれぞれに歴史を刻んできた様々なジャンルの美学たるマナーを継承する作業であるようにも思えます。自由な表現を目指すかたわら定型を守ることとの間で何か逡巡したりすることはなかったでしょうか?
D:今回は自由をかなり感じていたんだ。何かを期待されているわけでもなかったし、自分が作りたいものを作りたいように作れたと思う。アレンジをしっかり考えたりするのは好きだけど、僕は同時になるだけ自然の流れで曲作りを進めることも心がけているんだ。自由なソングライティングと凝ったアレンジ、その良いバランスを見つけ出したいし、それが僕にとっては興味深いんだよね。もうそれは何年も試みていることで、だんだん最良のバランスに近づいてきたと思う。構成にこだわりながらもディテールにあまりこだわりすぎず、聴こえるがままに曲をなるだけ早くレコーディングするというのは難しい。今回はレコーディングにおいてマイクのセッティングを含め全てを自分でやらないといけなかったから、そのバランスを保つのは大変だったよ(笑)。
──そして、本作を一本貫いているのは、やはりあなたのエモーショナルで崇高、でもヒューマンなタッチのヴォーカルかと思います。グリズリー・ベアなどこれまでの場でのヴォーカル・パフォーマンスと、今回のソロにおける歌の表現、どのあたりの具体的な成熟が現れていると思いますか? ヴォーカリストとして、あなたがお手本にしている、大きな影響を受けているのはどういう人なのでしょうか?
D:あまり自分自身をヴォーカリストと思ったことがないんだよ。でも、年を重ねるうちに声が変わってきたかなとは思う。あと、今回のレコードではこれまでよりもいくつかの部分では繊細に、ソフトに歌うように意識した部分はあったかも。前みたいに叫び続けてない(笑)。自分の中では、未だにメロディの書き方に自信が持てていないんだよね。このアルバムは、それを練習する良い練習だったと思う。
──ちなみに、ギタリストとしてはあなたのお手本はどなたになりますか?
D:思いつかないけど、今挙げるとすればバーデン・パウエルかな。でも正直、僕はあまり楽器としてギターが好きではない(笑)。ギターは好きな楽器というより、自分が知っている楽器という感じなんだ。でもギターで好きなのは、やっぱり昔のクラシックな作品かな。レッドベリーとか、昔ながらのブルースが好き。あとはすごくテクニカルなギターだね。それこそバーデン・パウエルはその一人。ジャンゴ・ラインハルトも好きだな。彼は素晴らしい。
──さて、どうしてもこれは聞かねばなりません。グリズリー・ベアの次のアクションはどのような感じになっていますか? 実は私は2年ほど前、まだコロナ前に京都でエド・ドロストにバッタリ会いました。その時はまだ彼がセラピストになるためにバンドを離れることが発表される前でした。彼が復帰することはもうないのでしょうか。
D:いや、エドは完全にバンドを離れたわけではないんだよ。心理療法を学ぶために学校に通わなければいけなかったから、少し音楽活動から離れなければいけなかっただけ。そんな彼の意思を僕はリスペクトしているし、他の事がしたくなるのもよくわかるって感じ。新作については今はまだ考え中なんだ。グリズリー・ベアは15年も続いているし、メンバー誰もが自分の時間を取っていた時期があると思う。それが今はエドの番というわけだよ(笑)。
<了>
Text By Shino Okamura
Photo By Amelia Bauer
Interpretation By Miho Haraguchi
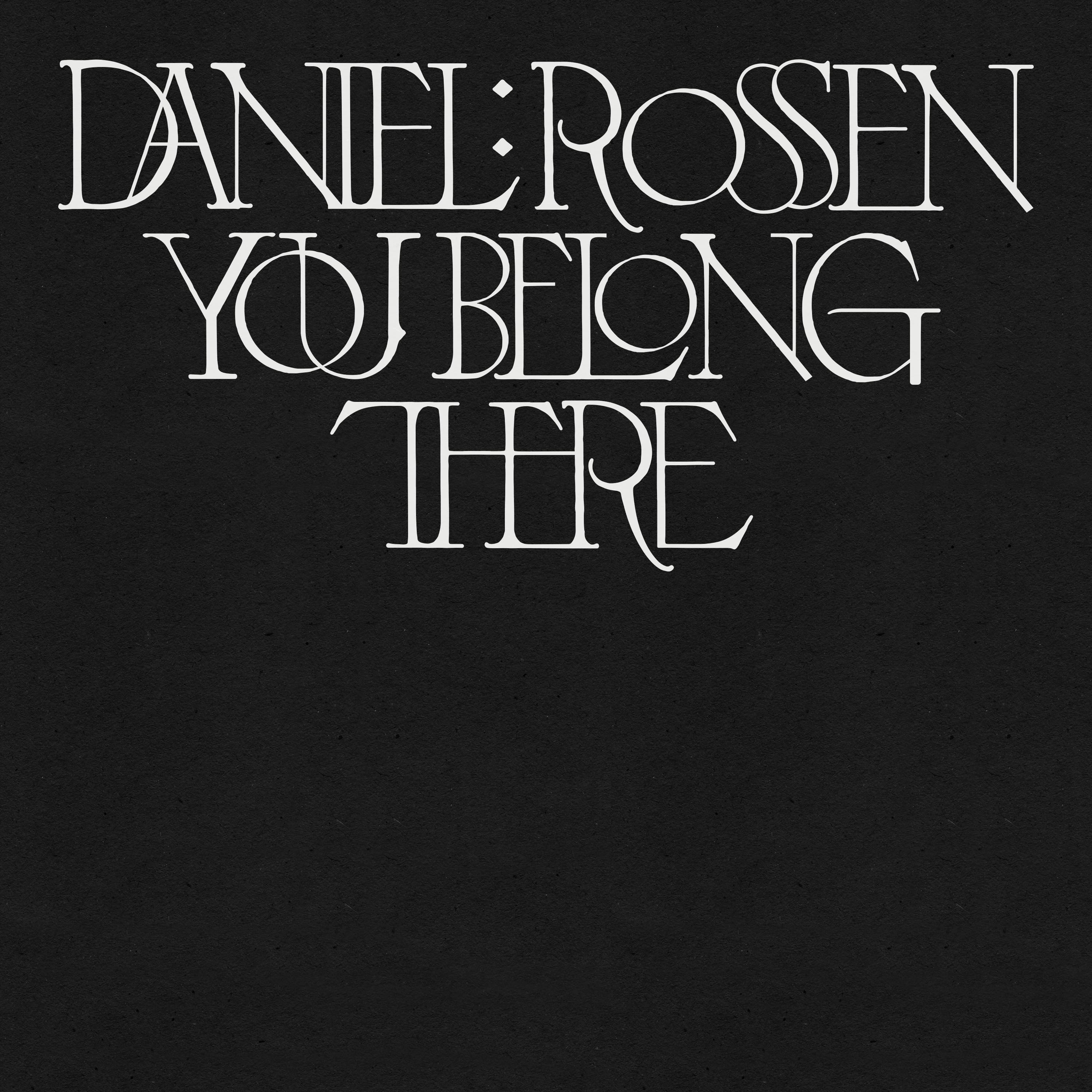
Daniel Rossen
You Belong There
LABEL : 4AD / Beatink
RELEASE DATE : 2022.04.08
購入はこちら
Tower Records / HMV / Amazon / iTunes
