疾走する男の気骨たる記録
ブルース・スプリングスティーン
アルバム・ガイド
2012年3月15日にブルース・スプリングスティーンは《SXSW》にて催された基調講演にて、ロック、フォーク、カントリー、ソウル、パンク、エレクトロニカ、など様々な形態の音楽に言及し、自らのキャリアを振り返りながらこう語った。
音楽活動に正しさや純粋さは関係ない。ひたすら音楽を演るしかない。おれたちが生きているのは、もはや真実がすべてという世界ではない。現代社会の真実とは鏡張りの部屋のように多面的だ。才能の輝きが色あせてきたら、頼りになるのはなにかというだけのことだ。(中略)結局は自分の音楽が最終的に求めている意欲と目的に頼ることになる。(※1)
第二のボブ・ディランというマーケティング的側面を背景に制作されたシンガーソングライター然としたファースト・アルバム『Greetings from Asbury Park, N.J.』(1973年)。パンク前夜の衝動性とアメリカという国家に対峙する文学性とコンシャスネスを刻印し、現在に至るまでのロック・ミュージシャンとしての“ボス”像を形成した『Born to Run』(1975年)。時代とともに急速に姿を変えるアメリカのなかで生きる人々の姿をミニマルかつアコースティックなサウンドで描いた『Nebraska』(1982年)や『The Ghost of Tom Joad』(1995年)。シンセサイザーとスネア・ドラムを重用し、80年代のロック・サウンドの範型を形成した『Born in the U.S.A.』(1984年)。ピート・シーガーのレパートリーなどカヴァーした『We Shall Overcome: The Seeger Sessions』(2006年)。2023年現在のソロ最新作である『Only the Strong Survive』(2022年)は60~70年代のソウル・ミュージックを中心とするカヴァー集であるといったように、従来(特に日本国内で)イメージされる“ロック・ミュージシャン”としてのブルース・スプリングスティーン像といったものは、上述した発言にも見られる通り、実は彼の多様な音楽性の一部を切り取ったものでしかない。
加え、国内の音楽批評や言説、特にオールド・ロックを対象としたメディア以外において、ブルース・スプリングスティーンの名前が言及されることはあまり多くないように思える。言及されるとしても各年代のディスク・ガイドにて『Born to Run』や『The River』、『Born in the U.S.A.』が登場し、“ロック”というジャンル名の元に収束することで、彼の音楽的な視野の広さと懐の深さを見逃してしまう。ゆえに、今回《TURN》ではブルース・スプリングスティーンのディスクガイドを通じて彼のキャリアを振り返ることを試みる。それは彼の音楽性のみならず、現在に至るまで多くの(若手)ミュージシャンとコラボレーションや客演が絶えず舞い込み、リスペクトが損なわれることなく蓄積されているブルース・スプリングスティーンという人間が生み出す音楽がなぜアメリカを中心として求心力を失っていないのかをとらえなおすことにも繋がるだろう。
このディスク・ガイドのなかで、これからブルース・スプリングスティーンを初めて聴くという人に、しばらく聴いていないという人に、ずっと聴いてきたという人に何らかの新たなブルースとの出会いがあればと願う。(編集部)
Top photo by Joel Bernstein
※1 Burger, Jeff ed., SPRINGSTEEN ON SPRINGSTEEN: Interviews, Speeches, and Encounters,Chicago : Chicago Review Press.(安達眞弓訳,2013,『都会で聖者になるのはたいへんだーーブルース・スプリングスティーン インタビュー集1973~2012』スペースシャワーブックス,p.630。)
(ディスク・ガイド原稿/天野龍太郎、井草七海、岡村詩野、尾野泰幸、木津毅、キドウシンペイ、柴崎祐二、高久大輝、髙橋翔哉、山田稔明、吉澤奈々)
Text By Ryutaro AmanoToshiaki YamadaShoya TakahashiNana YoshizawaTsuyoshi KizuShino OkamuraYuji ShibasakiNami IgusaDaiki TakakuYasuyuki OnoSinpei Kido
『Greetings from Asbury Park, N.J.』
1973年 / Columbia
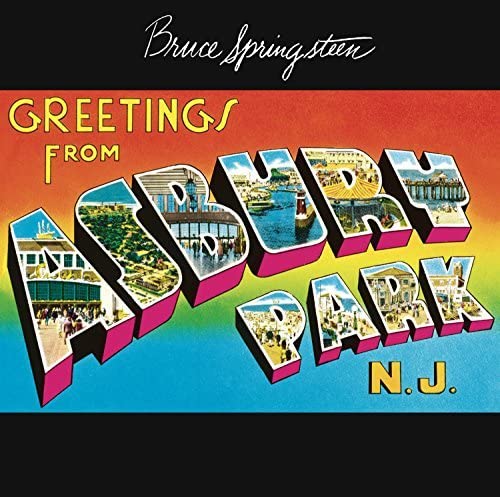
想像と現実の乖離。これまでの自分と、現在の自分との乖離。自己のなかの意識と、外部からの視線と評価との乖離。期待を裏切られたことによる不安と恐怖は、人間を逃避の衝動に向かわせる。車や地下鉄といったモチーフ、恋や放蕩の節操のなさ、ギターの刻みの多さや前のめりなドラミング。すべてに通底する“速い”イメージから、その衝動性とか不安に結びつけるのは強引? それ以外にも、基本的に不安と衝動、そしてその反動と余波としての虚勢とに形作られたレコードではある。「Growin’ Up」、「It’s Hard to Be a Saint in the City」のやたら大胆で自信家の10代の主人公にしてもそう。「Blinded by the Light」、「Spirit in the Night」で語られる不良の叙事詩(実体験も含まれている)や、不思議で不穏なイメージの断片にしてもそう。ただ自己と外部との乖離がもたらすのはそうしたあやうさだけではない。ストリップ・バーでのライヴで観客に歌を聴いてもらえないことに苛立った経験が、ボブ・ディランにも喩えられる詩的な文学性を生み出したこと。ソングライティングの“いろは”も知らずに書かれたちぐはぐな楽曲展開が、のちに「よく練られた構成」と評されたこと。未来は彼を「聖者」にした。だけど孤独な23歳の不良青年はそうとも知らず、劣等感と自信を同時に胸に詰めストリートを闊歩していた。(髙橋翔哉)
『The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle』
1973年 / Columbia

ライヴ・バンドとしての充実と、レコーディング・アーティストとしてのアイデンティティ確立の葛藤。本作では、そのギャップを埋めようと徐々に「Eストリート・バンドだけのサウンドとは何か」という模索を深め、実践へと昇華されつつあるのがわかる。後の諸作に比べると、ひとまずあらゆる要素に挑戦しようとする気概がある分やや総花的ともいえるが、同時にそれがゆえ本作でしか聴くことのできない様々なきらめきが捉えられている。
冒頭の「Eストリート・シャッフル」は、R&B的なホーン・リフを交えたパーティー・ナンバーで、特にリズム面からはソウル・ミュージックの香りが匂い立つ。これは、初期Eストリート・バンドを支えたデヴィッド・サンシャスのクラヴィネットとヴィニ・ロペスのドラムスの「ファンキー」さの賜物だろう。私はDJとして、一時期よくこの曲をレア・グルーヴ曲とミックスしてかけていたのだが、フロアの誰もが「あのブルース・スプリングスティーン」であることを特に意識せず心地よさそうに体を揺らしていた様子を記憶している。
その他、甘辛いフォーク曲「4th of July, Asbury Park (Sandy) (邦題:7月4日のアズベリー・パーク)」、ボブ・ディラン風の「Incident on 57th Street(邦題:57番通りの出来事)」、Eストリート・ロックンロール最初の成功形である「Rosalita (Come Out Tonight)」、クラシック音楽から拝借したピアノ・フレーズの交じる壮大な「New York City Serenade」など、このアルバムならではのバラエティは実に楽しく、儚く、美しい。「ウォール・オブ・サウンド」へと突入する以前、さっぱり風味の録音/ミックスも今となれば好ましく聴ける。(柴崎祐二)
『Born to Run』
1975年 / Columbia

「ロイ・オービソンが孤独な者たちのために歌っている/ああ、それは俺のことだ/そして俺はお前だけが欲しい」——オープニングの「Thunder Road」でスプリングスティーンはそう歌う。感傷的なハーモニカを振り払うように、弾む足取りと連動する鍵盤。あまり上手くはないが、情熱だけは持て余した男の歌……「さあ俺の手を取ってくれ/今夜車に乗って、約束の地へ向かうんだ」。スプリングスティーンはつねにアメリカの夢とそれにまつわる希望と失意を描く作家だが、前作までに多く見られたニュージャージーの記名性をやや離れることで、そのことにはっきりと自覚的になったのがこのアルバムだ。1975年、アメリカで生きる若者たちはベトナム戦争の後遺症に苦しみ、行き場をなくしていた。だからこそかれは、目的地を持たぬまま疾走する己の姿をそのままロックンロールで鳴らそうとしたのだ。ボブ・ディランのような詩、フィル・スペクターのようなサウンド、デュアン・エディのようなギター、ロイ・オービソンのような歌を目指したというあまりにも有名なエピソードは、当時のスプリングスティーンが同胞たる若者たちを鼓舞する音を思い描いていたことを象徴している。だから本作には、あらゆる瞬間に生命力が漲っており……表題曲「Born to Run」の中盤、クラレンス・クレモンスがサックスを気持ちよく歌わせればアンサンブルはさらなる高みを目指してぶつかり合う。夢に破れた者たちが溢れかえる街を見据えながら、そこからどこかへ旅立とうとする衝動が躍動する本作は、その後のスプリングスティーンの走る道を決定づけることとなった。(木津毅)

『Darkness on the Edge of Town』
1978年 / Columbia

前作の成功はむしろスプリングスティーンに法的な争いなどの厄介ごとを招く結果となったが、本作はそうしたゴタゴタのせいで制作開始が予定よりも遅れることで英国パンクの勃興からダイレクトな影響を受けることになった。そのときかれが必要としたのは『Born to Run』で高く評価されたウォール・オブ・サウンドではなく、シンプルでプリミティヴな怒りのエネルギーだったのだ。いっぽうで、ジョン・スタインベックの古典のジョン・フォードによる映画化『怒りの葡萄』(1940年)、同じくフォードの『捜索者』(1956年)、エリア・カザンの『エデンの東』(1955年)といったアメリカのクラシカルな映画を参照し、同時にそれまで距離を感じていたというカントリー音楽の価値を発見することで、アメリカの内部でくすぶっている人びとの悲しみをより精緻に描き出すことになる。父と息子の葛藤をアメリカに続く呪縛として語る「Adam Raised a Cain」、労働者の悲哀を叙情的に歌う「Factory」、そしてアメリカの夢に破れた者がそれでも生きる理由を探そうとする様を体現する「The Promised Land」……。ひょっとすると「街」という以上にアメリカ自体の暗闇を見つめようとしたこのアルバムは、より研磨した音とともに『The River』や『Nebraska』にテーマを受け継ぐこととなり、そしてまた、のちにハートランド・ロックと呼ばれるものの魂を呼び起こしたのだった。(木津毅)
『The River』
1980年 / Columbia
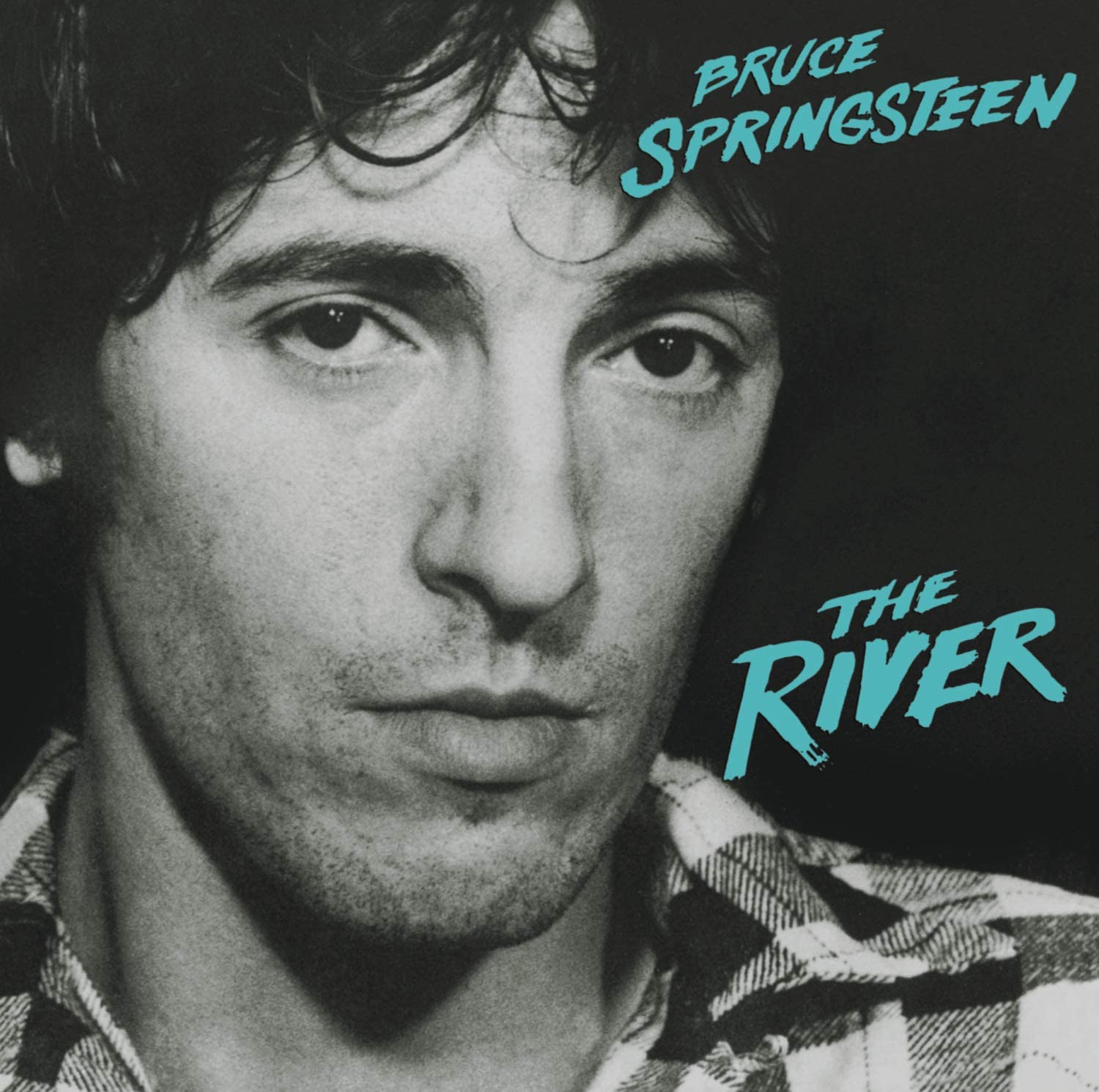
最高のコンディションにあるEストリート・バンドが叩きつける、問答無用のバーバンド・ロックンロール。ザ・バーズなどのフォーク・ロックをポップかつ鋭くアップデートしたような「The Ties That Bind」や「Two Hearts」をはじめ、同時代のパワー・ポップやパンク・ロックとの共振度も並でない。フィル・スペクター風のヒット曲「Hungry Heart」は、元々はラモーンズのために描き下ろしたものだ。
他方、重くゴシカルなフォーク調の楽曲群もあまりに素晴らしい。若くして結婚妊娠を経験し経済的な苦難を味わったという妹の半生を元に書かれた表題曲は、タフな社会状況のルポルタージュであることを超えて、古典的なバラッドにも比肩する根源的なナラティブの力と崇高な詩情を訴えかける。
けたたましくクルマを走らせ、気の置けない仲間と杯を交わし土曜の夜にハメを外す。そしてまたにじり寄る不安が取り囲む日常へと帰っていく。この2枚組レコードの中にあるのは、自由への渇望と、それへの諦め、同時に諦められない心、そしてあらゆる「普通の人々」の生に忍び寄ってくるざらついた無情と、成熟への誘いだ。この残酷ながらも美しい二面性。ブルース・スプリングスティーンの音楽には、開放と抑圧の両方がお互いをじっと見据えるように同居している。分裂と統合。だから、それらの二面性がもっとも美しい形で併存するこのアルバムは、彼の代表作であると同時に現代の神話であり、また苛烈なほど自然主義的で切迫した「物語」でもある。(柴崎祐二)
『Nebraska』
1982年 / Columbia

本作は1957年から1958年にかけてネブラスカで11人を殺害したチャールズ・スタークウェザー事件との関連のみならず、フラナリー・オコナーの小説、そして今の視点からいくとワイズ・ブラッドの最新作との繋がりで語るべきアルバムだろう。逮捕後に死刑となったスタークウェザーの目線から歌詞を書いたとされるタイトル曲には「They declared me unfit to live(彼らは僕を生きるに値しないと宣告した)」という一節がある。一方でアルバムの最後には「Reason To Believe(邦題:生きる理由)」という曲も収められている。「生きるに値しない」とは何か。スプリングスティーンはスタークウェザーのような人物が現れるに至った社会背景に胸を痛めながら、「生きる価値」など誰にも決めることができない、まして神は無力と訴えているように思えてならない。彼をそんな思いに至らしめたきっかけの一つが、反宗教とも読めるオコナーの小説との出会い…中でも『賢い血』であったことは既に多数指摘されているが、『賢い血』の原題が“Wise Blood”であることを思うに、あらゆる人間に等しく死の危険が及んだパンデミック状況下に生まれ、最後の審判をテーマにしたようなワイズ・ブラッドの『And In The Darkness, Hearts Aglow』(2022年)に、このテーゼが引き継がれているように思えてしまう。自室で一人で録音した音源に、多少のオーバーダブを加えて完成させた本作は、のどかなアメリカの田舎に潜む人間社会の闇を炙り出した大傑作だ。と同時に、ここに横たわるのは、地球上のすべての人間が常に向き合うべき生命の尊厳であることを忘れてはならない。(岡村詩野)
『Born in the U.S.A.』
1984年 / Columbia
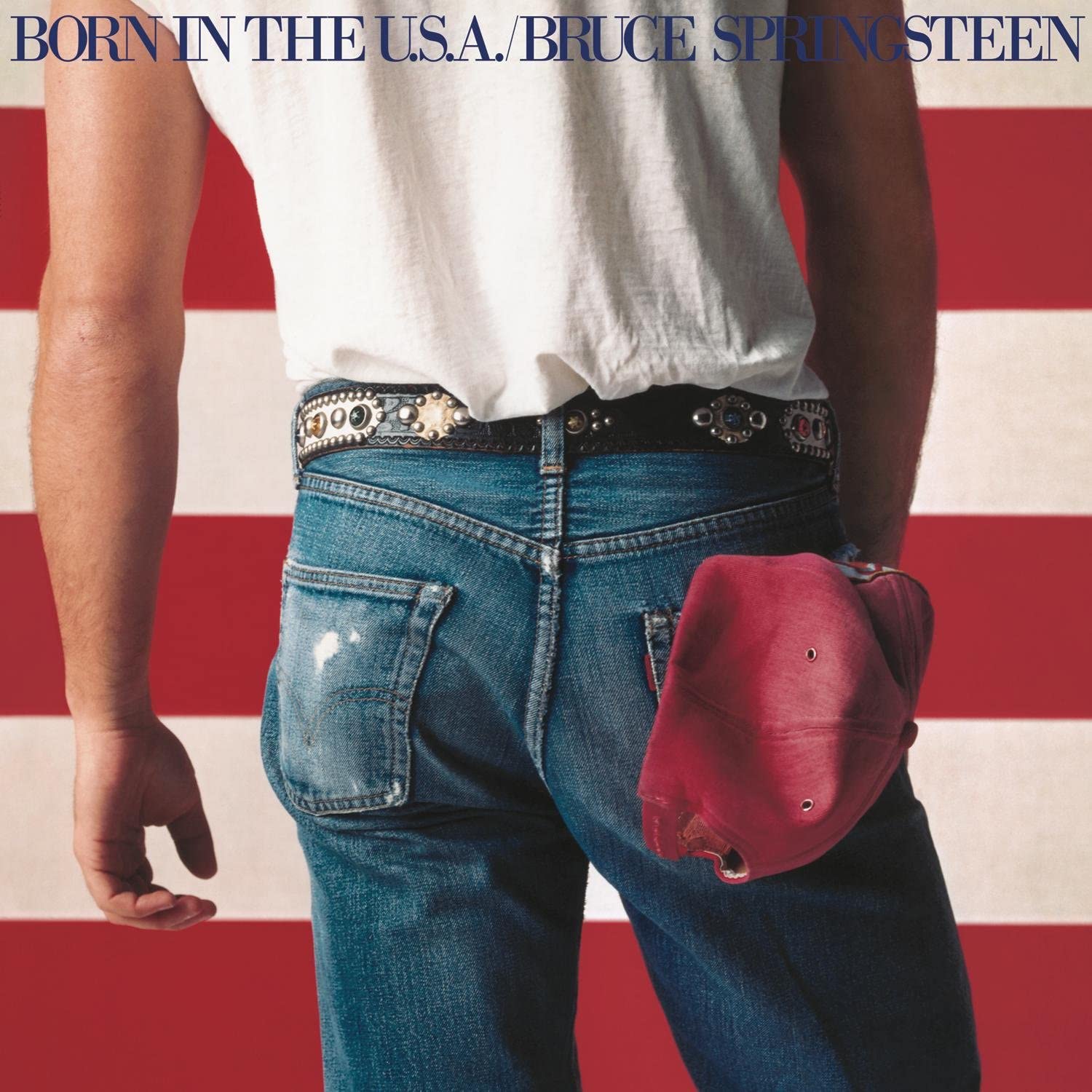
ベトナム戦争帰還兵の疎外と苦悩を刻印した表題曲「Born in the U.S.A.」が時の共和党レーガン政権により愛国的楽曲として受容されたという本作にまとわりつくエピソードはあまりにも有名。しかしそのような本作に内包されたポリティカル、コンシャスな精神性に注目するのと同じくらい、いやそれ以上にサウンドに注目が集まるべき作品だと思う。眩く楽し気に、仄暗く物憂げに鳴り響くシンセサイザー。サウンド・バランスを大きめに傾けたスネア・ドラム。快活に力強く弾むボーカル。震え泣くサックス。そこから放たれるサウンドの輝きとエネルギーに耳を傾けてほしい。現在に至るまで全世界で3,000万枚以上のセールスをあげ、海をも越え本作以降における80年代ロック・サウンドの範型を生み出した稀代のモンスター・アルバムは誰しもが憧れ、恋焦がれるようなクールでダンサブルなサウンドなしには生まれなかっただろうから。ベトナム戦争帰還兵の難局、工場労働者の失業と貧困、寂れた地方都市の生活、米国資本主義の拡大とともにそこから零れ落ちていった人びとの姿を、あらゆるところから迸るポップなサウンドとともにブルースは歌い上げていく。ブルースが本作である種の混沌の中で生み出したロック・ミュージックは多くの誤解≒解釈を生み、受け入れ、乗り越え、世界中の人々を虜にした。名盤とはきっとそういうものだ。(尾野泰幸)
『Tunnel of Love』
1987年 / Columbia

世界を熱狂させた『Born in the U.S.A.』、そしてEストリート・バンドとのステージでの輝きを封じ込めた“LP5枚組ライブ盤”『THE ”LIVE” 1975-1985』の異例の大ヒットを経て放たれた『Tunnel of Love』は、予想を覆すような内省的な作品になった。ノースリーブのGジャンにバンダナを巻いてシャウトする姿はそこにはなく、小綺麗なスーツにループタイでかしこまったボスが佇む。自宅スタジオで録音されたという点で1982年作『Nebraska』との共通点もあるけれど、モデルで女優のジュリアン・フィリップスとの電撃結婚と破局、泥沼の離婚調停というプライベートな問題が色濃く影響して、さもすると彼の長いキャリアのなかで最も赤裸々な感情が表出した作品ではないかと感じる。どれだけ名声や財産を手に入れても、自分の愛を誇示しようとも、愛する者の心が掴めない葛藤。覗き込んだ瞳の中に人間の二面性を見つけてため息を吐き、途方に暮れる。収められた12篇の歌たちはすべて愛にまつわる告白だ。ドイツの思想家フロムは愛とは孤独な人間が孤独を癒そうとする営みであり、より幸福に生きるための最高の技術であると定義した。その後パティ・シャルファとの揺るぎない愛を獲得する前の、当時30代なかばだったスプリングスティーンが彷徨った光の見えない“愛のトンネル”のなかで翻弄される姿は、切なくやるせなく、しかし、どうしようもなくロマンティックだ。発売当時中2だった僕は背伸びをして「愛ってやつは…」とわかったふりをして聴いていたけれど、35年経って大人になった今、もっとずっと心に響くようになった1枚。(山田稔明)

『Human Touch』
1992年 / Columbia

人のぬくもり、明るい側面に視点を向けたポップ・ロック色の強い作品が『Human Touch』だろう。1988年にEストリート・バンドが解散してからのリリースとなって、従来のEストリート・バンドが持つR&Rのダイナミズムやホーンセクションによる力強い躍動は感じられない。このことからも本作はファンの間で人気が分かれることになるが、新たにアーティストやバックヴォーカリストを迎えた制作は、AOR調の楽曲やシンセを用いたアレンジとよく調和している。プライベートで父親となった影響もあるのだろう、スプリングスティーンの楽観的なヴォーカルは一段と朗らかに響き、楽曲の充実度と相まっている。むしろもっと評価していい作品ではないだろうか。
イントロから目の開くようなピアノが耀く「Roll of the Dice」、高らかなメロディーが印象的な「All Or Nothin’ At All」、憂愁を含んだギターが癒しを誘う「Man’s Job」と時期が違えばシングル・カットされても不思議ではない楽曲。なによりベースのランディ・ジャクソンとドラムのジェフ・ポーカロが生み出すジャズの影響や、淡々とストイックにグルーヴを生み出すリズムセクションは重要な役割を担っている。ボス曰く、本作におけるファンからの評価については「90年代にポジティブな曲を書くことは成功しなかった」と語っているが、それでもアルバムを通して楽曲のバリエーションの豊かさや率直な表現は健在である。(吉澤奈々)
『Lucky Town』
1992年 / Columbia

長年共に音を鳴らしてきたEストリート・バンドを休息や他のミュージシャンとの活動への興味といった理由から無期限の活動停止とし、ニューヨークを離れ拠点をロサンゼルスへと移動。そしてブルースが父親となった時期に、三週間という短期間で制作された4年ぶり10枚目のスタジオ・アルバム。半ば音楽活動を再開させるという仕事上の義務感も手伝い作り上げた同時リリースの9枚目『Human Touch』と比べ、子どもの誕生をきっかけに自らの生きた証を発見するというリリックが印象的な「Living Proof」の制作をきっかけに一気に書き上げた本作は“自分自身の内面や居場所を再発見すること”というテーマに沿ったまとまりのある一作に仕上がっている。涙を誘うギター・ソロが印象的なハートランド・ロック「Better Days」、ハーモニカが軽やかに駆け回る「Local Hero」、湾岸戦争へと言及した「Souls of the Departed」など佳曲ぞろいだがブルースのディスコグラフィの中では地味な作品ではある。本作を最後に『Tunnel Of Love』以降続いていた私小説的な作品風景から次作ではよりコンシャスな方向性へと舵を切ることになるが、本作が生まれ出た時期を『Born in the U.S.A.』でのワールドワイドな成功以降の自己や周囲に対する再帰的な反省の時代ととらえれば、それは必要な通り道だっただろうと思う。(尾野泰幸)
『The Ghost of Tom JoadLucky Town』
1995年 / Columbia

ジョン・スタインベック『怒りの葡萄』の主人公、トム・ジョードをシンボリックな対象として取り上げ、アメリカの内省をストーリーテリングによって深く掘り下げた傑作アルバム。全編アコースティック・ギターを中心とした小編成。ボスの静かに語りかけるような歌声とハーモニカに加え、蜃気楼のごとく、うっすら立ち上がっては消えるペダル・スティール、ヴァイオリンが優しく歌を包み込むが、全体的にはダークなトーンに貫かれている。大恐慌後の1930年代、農業という人間の営みになくてはならい仕事に就きながら、やがてゆき場をなくし転げ落ちる普通の家族を描いた『怒りの葡萄』。それは資本メカニズムが膨張した本作発表の95年の背景と当然重なる。
本作は、“新たな下層階級史”という副題で、アメリカ社会の暗部を綴った、デール・マハリッジ著『あてどない旅』(1985年)に、大きくインスパイアされたと本人が語っているように、南西部を舞台に過酷な労働と不当な賃金、階級格差、差別といった扱いに苦しみ、残された数少ない選択肢(時に犯罪も)から生きる術を懸命に探し続ける多くの人の物語だ。そこには、生きる幸せを求め続けただけの人々の願いを、残酷に切り裂くアメリカ社会・経済の暴力性と矛盾が、溜まった澱のように無言で重くのしかかる。笑ってしまうほどに、今の時代を反映したテーマだが、特定のイデオロギーの代弁者となることを拒み、象徴となることへの距離を置き、物語を通じて生活者の姿を浮き彫りにすることに徹しているからこそ、本作の力強さがいつもでも失われないのだろう。(キドウシンペイ)

『The Rising』
2002年 / Columbia
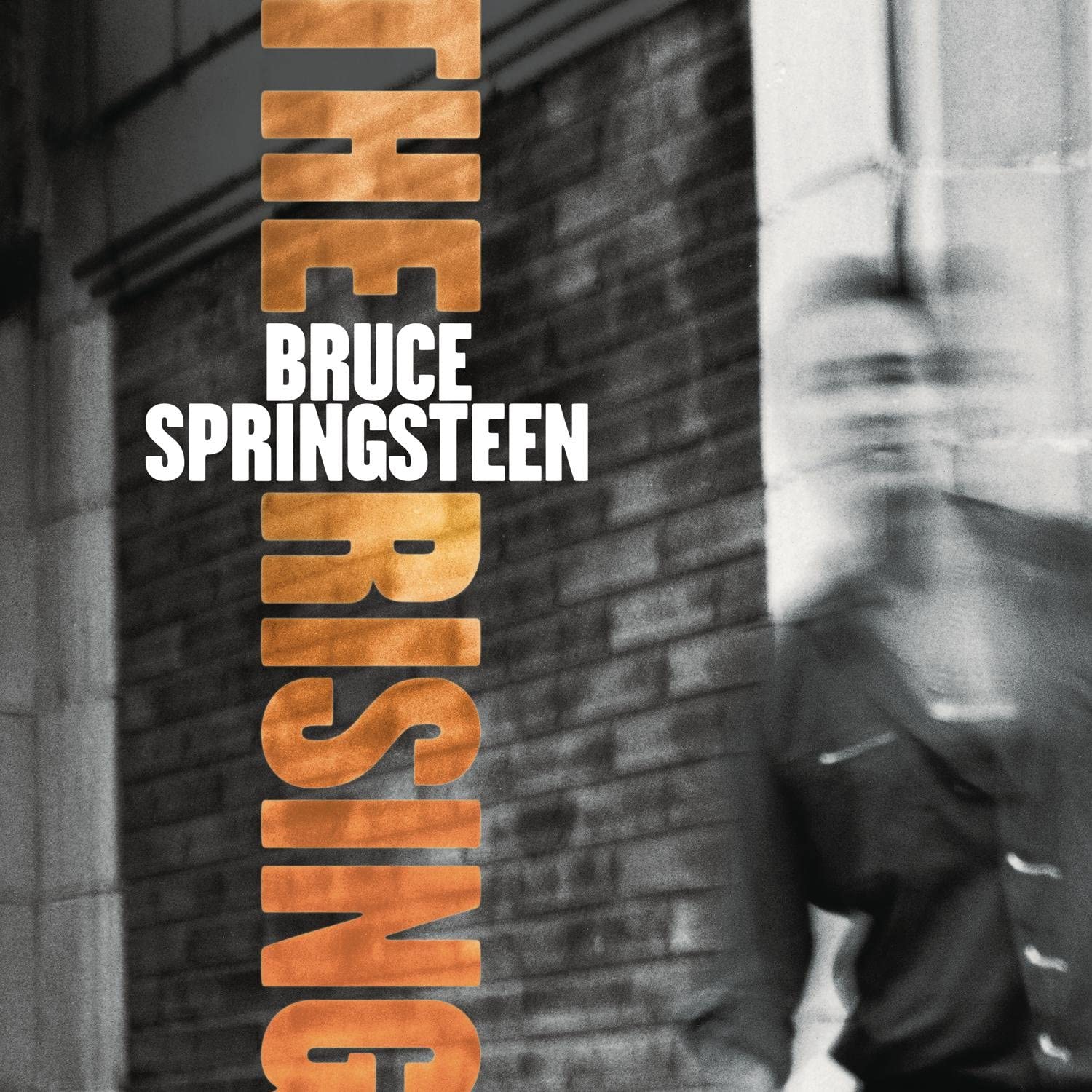
2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロの衝撃と、そこから生まれた数多の人の複雑な感情のもつれあいを背景に、事件に巻き込まれた人びとへの哀悼、事件へと向き合いそこから再起を図るためのレジリエンス、そして対立に陥ることのない人類の融和を表現しようと作り上げた12枚目。『Born in the U.S.A.』(1984年)以来、18年ぶりに一体となって作品を作り上げたE・ストリート・バンドが鳴らす、パワフルで太い芯の通ったハートランド・ロック・サウンドと全面を通じて展開するストリングスによる壮大な構成が印象に残るが、「Waitin’ On a Sunny Day」で鳴るクラレンス・クレモンズの宙に舞い上がるように高らかなサックスの咆哮が何よりも感動的。
プロデューサーにはパール・ジャムやレイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのプロデュース・ワークでグランジ以降のロックのメイン・ストリームを支えたブレンダン・オブライエンを招聘。厚みを増したオルタナティブ・ロック以降のロック・サウンドへと目くばせしつつ、サウンドのモダナイズにも挑戦した。
ほとんどの収録楽曲はもちろん9.11以降に書かれたものだが、同事件の10日後に出演したチャリティーTV番組で歌い上げた「My City of Ruins」は90年代に荒廃の一途を辿った自らの地元であるアズベリー・パークの光景を歌ったもので事件以前に書かれた楽曲だったというエピソードは、一つの歌に仮託される想いや感情をリスナーとともに常に構築し続けようとするブルースの姿勢を示しているようで、それこそが彼の歌が歌い継がれる理由でもあるのだと思う。実際にタイトル楽曲の「The Rising」は後にバラク・オバマの大統領選キャンペーンテーマソングとして使用され、「My City Ruins」は2011年ニュージーランド・クライストチャーチ大地震の復興のアンセムとなるなど、ブルースが本作で示した未来への希望と融和の精神性は時と場所を越え今も世界のどこかで誰かの心を照らしている。(尾野泰幸)
『Devils & Dust』
2005年 / Columbia

80年代の『Nebraska』、90年代の『The Ghost of Tom Joad』に続く、2000年代のアコースティック・アルバム。有機的なオーケストレーションやエレクトロニクスを交えるプロダクションは硬軟自在だが、やはり生楽器の録音の素晴らしさにリリースから18年経ったいま聴いてもため息が出る。プロデューサーはボス本人に加え、90年代のロック・シーンで重要な働きをしたブレンダン・オブライエン(『The Rising』と『Magic』も手がける)。もう一人は『Nebraska』のマスタリングを担ったというチャック・プロトキンで、「All the Way Home」と「Long Time Comin’」のみを担当。収録曲には過去に作曲されたものも多いというが、それはさておき、「Black Cowboys」というあまり目立たない曲に注目してほしい。ソウル・コーラスを背負ったシンプルなフォークで、シングル・マザーの家庭で育った貧しい黒人の少年レイニー・ウィリアムズの物語が描かれる。死と血に塗れたストリートには出ないで、あなたは私の誇りだから、と母は子に言う。しかし、母はギャングの男に付け入られ、ドラッグ中毒に(80年代にアフリカン・アメリカンのコミュニティで猛威を振るったクラック・コカインだろうか)。レイニーは母と家を捨て、街へ出る──という歌だ。他にも、群れの中の馬の視点から歌う暗喩的な「Silver Palomino」、売春についての「Reno」など、キャリア屈指の味わい深いストーリーテリングで魅せる。そして、何はともあれ、イラク戦争の兵士の視点から歌うタイトル・ソングである。2005年は、ジョージ・W・ブッシュ政権の第2期が始まった年だった。前作に続いて全米1位を獲得、グラミーの受賞もし、何度目かの絶頂期だったディケイドを控えめに代表する隠れた傑作だ。(天野龍太郎)
『We Shall Overcome: The Seeger Sessions』
2006年 / Columbia

70年代のある時期のスプリングスティーンに対して“ストリート・ロッカー”という呼称が適切だったように、90年代終盤から2000年代以降にかけての彼はアメリカのルーツ音楽を社会とコミットするための武器とする“運動家”としての横顔が強く滲み出ている。公民権運動の象徴たるフォーク・シンガー=ピート・シーガーの曲を中心に伝統的なフォーク、カントリー、ブルーグラスなどのトラッドや、そこに独自の歌詞を加えたものなどを、スージー・タイレルや妻でもあるパティ・スキャルファも含めた多数のメンバーとのセッションで完成させた本作は、アメリカン・ルーツ音楽は差別解放、人権獲得のために今こそ必要とするスプリングスティーンの信念が現れた重要作だ。伏線となっているのは、98年にリリースされたシーガーのトリビュート・アルバム『Where Have All the Flowers Gone: The Songs Of Pete Seeger』への参加だろうが、ここではその際にカヴァーした「We Shall Overcome」よりはるかにリラックスして仲間たちと唱和する様子が伝わってくる。皆で手を取り合い、共に歩んでいこうとするリベラルな姿勢によりシフトしていることが興味深く、作者不詳の伝承曲を多くピックアップしていることにもスプリングスティーンの名もなき人々への寄り添いを感じることができるだろう。“ストリート・ロッカー”時代と“運動家”としての顔に一切の齟齬や矛盾がないのは、アメリカのボスとなってもなお彼が常に市井の目線を忘れていないからなのだ。(岡村詩野)
『Magic』
2007年 / Columbia

『The Rising』(2002年)以来のEストリート・バンドと組んだ作品で、同作と同様にプロデューサーはブレンダン・オブライエン。次のスタジオ・アルバム『Working on a Dream』と並べて三部作として、ブルース・スプリングスティーンとEストリート・バンド、ブレンダン・オブライエンのタッグによる2000年代を聴くことができるだろう。冒頭「Radio Nowhere」から響く威勢のいいロック・サウンドも一つの特徴だが、かといって大味なわけではなく、スロウでストリングスなどを程よく活用した「Devil’s Arcade」など、サウンドの濃淡を楽しめる。表題曲「Magic」は「真実であれば何でも嘘と思わせることができ、嘘であれば何でも真実と思わせることのできる時代」、つまりポスト・トゥルースの時代を生きることについて歌っており(それはもちろん比喩的な歌詞に落とし込まれている)、いち早く時代に押し寄せる不穏な気配を察知して行動していたボスには驚くばかり。9.11以後のアメリカの変化を歌った「Long Walk Home」はジェントリフィケーションと紐づけることもできそうだ。アルバムのリリースから2週間後に追加となった、長年アシスタントとして共に歩んできたTerry Magovernへと宛てられた追悼曲「Terry’s Song」はまっすぐに涙を誘う。(高久大輝)
『Working on a Dream』
2009年 / Columbia

Eストリート・バンドの優れたアコーディオン/キーボード奏者、ダニー・フェデリチこと“Phantom”Danが2008年4月に亡くなり、惜しくも最後に参加したアルバムとなった。どこか「Born To Run」や『The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle』(1973年)を思い起こさせるのもそのはずで「Wild Billy’s Circus Story」の続編であり、追悼曲となったのが12曲目「The Last Carnival」だ。“サン・ダウン、サン・ダウン/テントはすべて撤去される/どこへ行ったの、私のハンサムなビリー?”……創立メンバーであり盟友を亡くした悲痛さと愛を差し出す歌声が、ラストに向かい静かに消えていく。
それまでの楽曲が前作『Magic』からの流れを引き継ぐ、気迫のこもったサウンドだから尚のことハッキリとした対比に驚いてしまう。約8分間に渡る壮大なオープニング曲「Outlaw Pete」からピアノとギターソロが爽快なR&Rナンバー「My Lucky Day」の流れは感情を昂らせる。ボスのエネルギーに満ちた歌声と流麗なストリングスが印象的だ。プロデュースとミキシングにブレンダン・オブライエンを迎えて、4度目のタッグを組んだことも創作活動がスムーズに運んだ故だろう。『The Rising』『Magic』に続く三部作の旅を終え、新たなポップ・ロックの集大成となった。(吉澤奈々)
『Wrecking Ball』
2012年 / Columbia
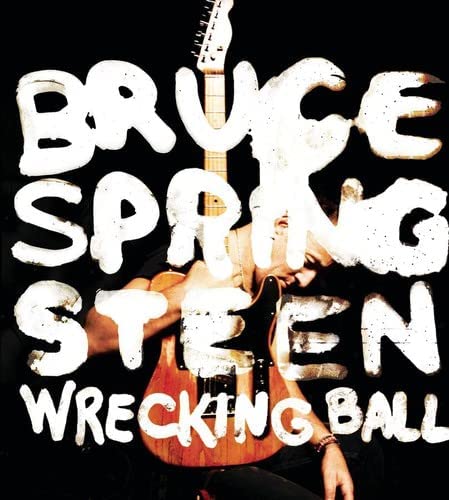
ボスがアメリカの大統領になったらいいのに。これまで誰に言うでもなく何度もそう独りごちてきた。彼が支持したオバマが大統領になったときは本当に嬉しくて「未来が変わる?」とさえ思ったけれどそんな簡単なことじゃなくて、いつだって次から次に暗雲が立ち込めるのが世の常。リーマンショック以降の世界経済危機、日本では東日本大震災で時代のフェーズが変わった。そんなタイミングでリリースされた『Wrecking Ball』、再生ボタンを押すと力強く鳴り響く太鼓の音、混沌の時代に結束を呼びかけるアンセム「We Take Care of Our Own」は21世紀版「Born in the U.S.A.」か。サビのリフレインにあわせて僕らは拳を振り上げるけれど、そのフレーズは「Born in the U.S.A.」同様に意味深で抽象的だ。この作品で初めてタッグを組んで以降、最新作『Only the Strong Survive』まで共同プロデューサーとなるロン・アニエロが担ったのはEストリート・バンドの幻影を包括しつつも、それをさらに進化・深化させたモダンなサウンド。密度の濃い音像のなかにザラッとしたリズムループが新鮮に響く。民俗音楽研究家アラン・ロマックスが蒐集した古い音源を大胆にサンプリングし、フォスターからカーティス・メイフィールドまでが意図的に引用されて浮かび上がるのはアメリカの光と影。急逝したクラレンス・クレモンズの咆哮が唸る「Land of Hope and Dreams」でクライマックスに。土埃のなかに「怒りの葡萄」のトム・ジョード、ウディ・ガスリー、そしてピート・シーガーの魂が漂っている。ボスが大統領になったら? いやいや、命ある限りアメリカの心を歌ってもらわないと困るのだ、スプリングスティーンには。(山田稔明)
『High Hopes』
2014年 / Columbia

本人いわく「過去10年の未発表曲のうちのベスト」をスタジオ録音したもので、要は21世紀のある時期のかれのコンピレーション的な趣を持った作品だ。その分まとまりには欠けるところはあるが、Eストリート・バンドとともにトム・モレロが多くの曲でハードかつ暑苦しいギターを弾いていることもあり、老齢に差しかかったスプリングスティーンがなおも熱い想いを滾らせていたことがよく伝わってくる。「ある時期」とはつまり9・11を利用したイラク戦争があり、ブッシュ政権があり、リーマンショックを契機とした金融危機があったアメリカのことで、そうした時代にこそ庶民の側にどうやって立つのか向き合ったにちがいない。その葛藤を断片的に記録しているのだ。90年代に一度リリースしたティム・スコット・マコンネルの「High Hopes」の再録から始まる本作は、そのように20世紀にスプリングスティーンがたどって来た道のりを今世紀に重ね合わせることで、変わらず市井の人びとを鼓舞することを宣言しているのだろう……生きている限り望みはある、と。いやそれだけでなく、たとえばクラレンス・クレモンズへの哀悼がそこここにふと立ち現れるように、もうこの世から去ってしまった人びとを讃えることも忘れていない。白眉はベトナム戦争で犠牲になった音楽仲間に捧げられたバラッド「The Wall」。このシンプルで優しい歌のトーンはスーサイドのカヴァー「Dream Baby Dream」へと引き継がれ、アンダーグラウンドの伝説が庶民のためのロック音楽と接続されることで、あまりにも両義的な「夢」が立ち上がる。夢に破れ、それでも夢を描く人びとのためにスプリングスティーンは歌い続けるのである。(木津毅)

『Western Stars』
2019年 / Columbia

本作の全曲ライヴを収録した映画の冒頭でボスは語る──個人とコミュニティの間で葛藤するのがアメリカ人である、と。政治的にはリベラルでありながら古き良きアメリカを愛する白人の老年男性、というボス自身の複雑な二面性とともに、本作の核心をついた言葉だ。重要な1曲をあげるなら個人的に推したいのは「Stones」。“朝起きたら、口いっぱいに石が詰まっていた/そして言われた、それはお前がついてきた嘘だと”、“お前のしてきたことを見ろ”という歌詞は表面的には恋人や家族関係の難しさを歌っているようで、その実コインの裏表のように、白人男性としての彼のアメリカ社会に対する罪と贖罪の意識を吐露しているようでもあるのが秀逸だ。
70年代のウエストコースト・サウンドを全面的に取り入れ、表題曲では西部劇をモチーフに。だが漲るフロンティア精神は遥か昔、まるで自らを時代遅れと評するかのように落ちぶれた西部劇俳優の主人公に自身を投影。大所帯のオーケストラも今作の目玉だが(若干アレンジが常套なのは否めないものの)西部の荒野を思わせるその壮大さや、バカラックのような優美さが、むしろ彼の孤独を際立たせてしまうのが哀しくも胸を打つ。無論、彼の古き(白人の)アメリカへの愛着は恣意的にも感じるが、少なくともボスにはその自覚があり、折り合いをつけられない苦悩こそが彼の哲学なのだと濃厚に理解できるからこそ、今作は傑作と呼ばれるのだろう。当時彼と同世代の白人大統領であったトランプを積極的に批判していたのも自然な流れ。(井草七海)
『Letter to You』
2020年 / Columbia
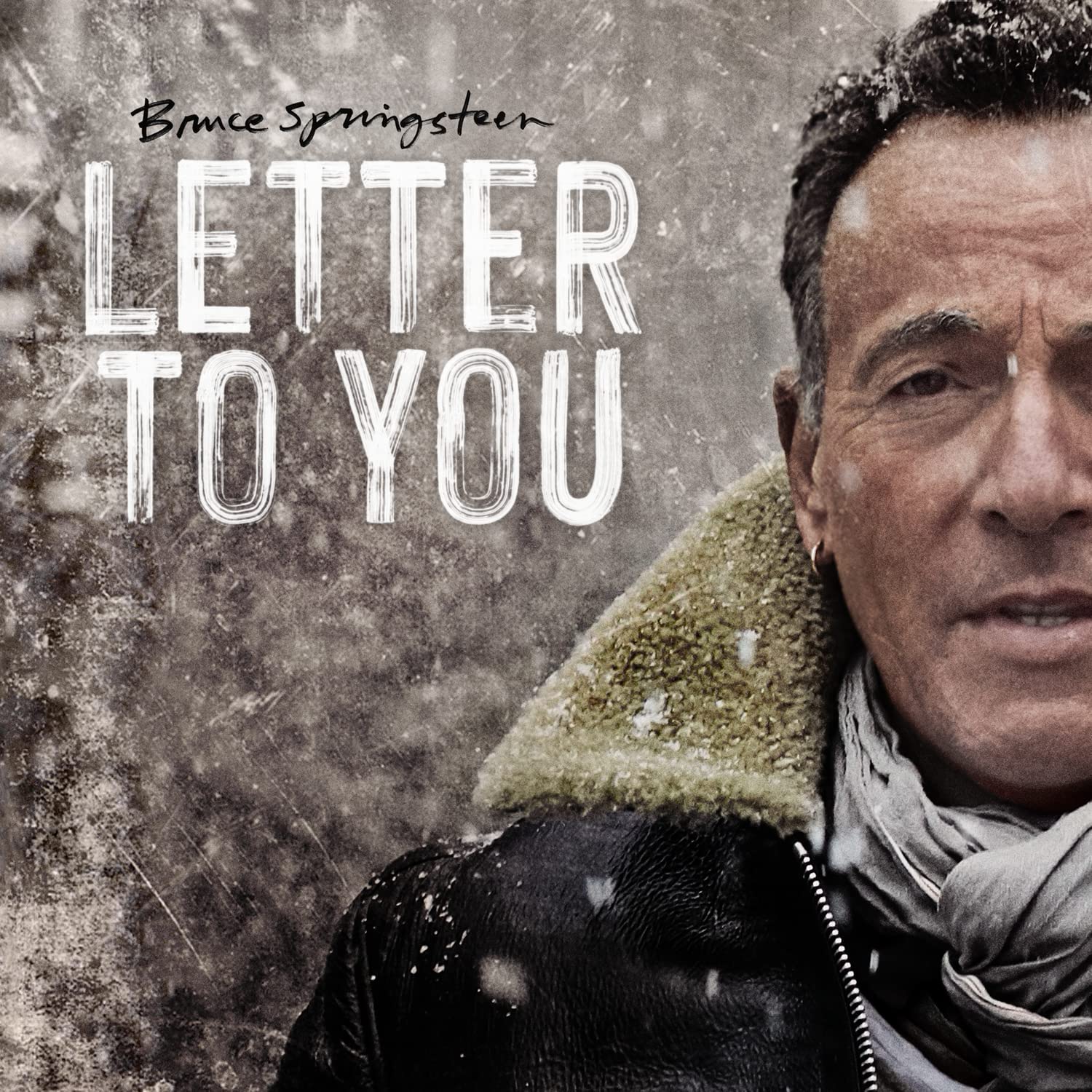
かつて、ロックンロールという一つの文化においては、「老い」とか「改悛」といった事柄や心情は、積極的に無視するべき、もっといえば軽蔑すべき存在と考えられていた。この「常識」をいまもなお信望し続ける人がいるとしたら、まさにそういったテーマを抱いたこのアルバム=ブルース・スプリングスティーンによる現時点での最新オリジナル・アルバム『Letter To You』は、実に怪しからん一枚ということになるだろう。
しかし、考えてみればブルースはそのキャリアのスタート時点から、未来への希望や成長への期待とともに、過去や喪失と向き合いそれを慈しむことで訪れる豊穣や、「現在」のために湧き出るエネルギーを歌っていた、「懐古的な」ロックンローラーでもあった。
多くの友人を亡くし、自身のキャリアを振りかける様々なプロジェクトを続ける中で、ブルースはついに、もっとも前向きな形で過去と向き合おうとする。久々に集結したEストリート・バンドとともに、たった4日間のライヴ・セッションで録音された本作には、成熟を経てなお歩みを止めようとしない彼ら自身の姿が「今、ここ」の実感とともに刻まれている。「If I Was the Priest」、「Janey Needs a Shooter」、「Song for Orphans」は、かつて彼がレコード・デビュー前に書いていた曲の約50年越しの新録だ。その鮮烈な音の響きわたるところで、過去は現在と接続され、現在を癒やし、現在を照らし出す。(柴崎祐二)
『Only the Strong Survive』
2022年 / Columbia

『We Shall Overcome: The Seeger Sessions』(2006年)と対にして聴きたい目下のソロ名義最新作にしてカヴァー集。Eストリート・バンドとの久々のツアーを前に少し声を温めておきたかった、とでも言うかのように、おそらく彼ならソラで歌えるであろう60〜70年代のソウル・ミュージックを楽しげに歌っているのが微笑ましくていい。選曲も、フォー・トップス、テンプテーションズ、シュープリームスといったモータウン〜ノーザン・ソウル系の曲がメインになっているが、《Stax》のウィリアム・ベル作の曲が2曲、フランキー・ヴァリやウォーカー・ブラザーズで知られる「The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore(邦題:太陽はもう輝かない)」、さらに例外的に1985年のコモドアーズのヒット曲「Nightshift」なども含まれていて、今歌いたい曲を気軽に選んだかのよう。現在87歳のサム・ムーアとのデュエット2曲はさながらサム&デイヴ再現のようだ。とはいえ、スプリングスティーンがジョン・ハモンドに見出されてデビューする前にリズム&ブルーズの影響を強く受けたバンドをやっていたことはファンの間で知られているし、エルヴィス・プレスリーに憧れていたことも有名だが、ここでは無理にソウルフルに歌おうとしていないことが却って良い結果となっている。それどころか、何を歌っても喉を震わせるあのスプリングスティーン節であり、Eストリート・ホーンズが参加していることもあってか、このまま続けてオリジナル曲へとメドレーになっても違和感がないというアレンジ。みんなで歌える邪気のないこうしたアルバムをポンと作れてしまうのも彼がアメリカのボスであり続ける理由なのだろう。ジャケットをよく見ると小さく“Vol.1”の文字もある。2もふと肩慣らししたい時に作ってほしい。(岡村詩野)
